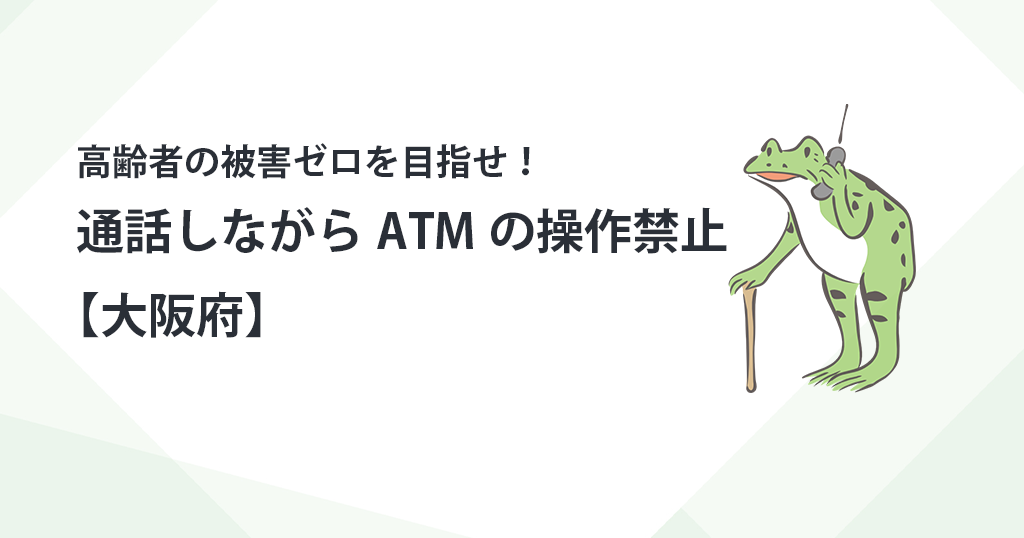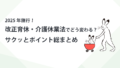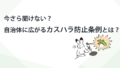大阪府「通話しながらATM操作禁止」の背景と特殊詐欺の現状
大阪府では、近年深刻化している「特殊詐欺」(振り込め詐欺・還付金詐欺など)を防ぐために、ATM操作時のルールを厳しくする条例が可決・施行されました。これが「通話しながらのATM操作禁止」というものです。ニュースの見出しなどで「高齢者がスマートフォンなどで通話しながらATMの操作をしてはいけない」と報じられています。この背景には、大阪府内での特殊詐欺被害が毎年のように増加しており、被害にあう人の多くが65歳以上の高齢者であるという現実があります。
詐欺の代表的な手口の1つとして、「還付金詐欺」が挙げられます。これは、「医療費が戻ります」「保険料が返金されます」などと役所職員や保険組合などを名乗り、高齢者に「ATMで手続きすれば簡単にお金が返ってきます」と言葉巧みに誘導するやり方です。電話の相手を信じ込んでしまい、スマホ越しに指示されるままATMを操作した結果、気づかぬうちに詐欺グループの口座へ振り込みを行ってしまうことが大きな問題になっています。
なぜ「通話しながら」なのか?
犯人は、電話を通して具体的な操作を1ステップずつ説明します。「今、カードを入れてください」「ここで暗証番号を押してください」「『送金』を選んでください」といった具合です。そのため、被害者が手続きに気づく間もなく、実際にお金を振り込んでしまうのです。本来、ATMは「お金を引き出す」「口座に入金する」など、自分や家族が普段使う用途で使用するはずですが、詐欺犯は「高額なお金が戻りますよ」「今日を逃すと返金できなくなります」といった焦らせる言葉を使うことで、相手を混乱させ、ATMの操作を続けさせます。
条例による禁止の意味
条例のポイントは「高齢者を守ること」にあります。もちろん、通話しながらATMを操作したとしても、そのすべてが詐欺被害になるわけではありません。ただ、特殊詐欺の大半が電話で指示を受けながらATM操作をする手口であることが多いため、大阪府としては“通話しながらの操作は危険だ”という意識を県民や高齢者に強く持ってもらい、また、金融機関やコンビニの店員なども「通話しているお客さんがいたら声をかける」という具体的な対策が取りやすい環境を作ろうとしています。
もっとも、この条例には罰則がありません。違反してしまったとしても「逮捕」などはなく、あくまでも「禁止行為」として明記することで、関係者みんなの注意喚起を狙うものです。「法的拘束力でガチガチに縛る」というよりは、「社会全体で注意しましょう」「積極的に声かけしましょう」という姿勢を示す施策といえます。
大阪以外の自治体・警察の動き
実はこのような通話禁止の取り組みは、大阪に限らずほかの地域でも「ATMを利用している高齢者に声をかけましょう」という呼びかけが警察を中心に行われています。兵庫県警察が令和5年8月に公表したPDFファイル【特殊詐欺水際阻止協力の店(家)ニュース】によれば、令和5年上半期の還付金詐欺被害は181件、被害額は1億9000万円に上り、前年と比べて被害が大幅に増えているとのことです。ポスターや店内アナウンスなどで広報していても、なかなか減らないのが実情であり、より強い対策(禁止や義務付け)を求める声が強まってきました。
しかし、ATMを設置している金融機関やコンビニ側には「従業員の負担が増えるのでは」「本当に店員がすべてをチェックできるのか」という不安があります。条例の施行によって、店側は「通話しながら操作をするお客さんがいたら声をかける義務」を負うことになるからです。ただ、こうした面倒を「それならATMを店に置かなければいいや」と考えるお店が出てくると、お客さんの利便性にも影響します。こうした点も今後の議論の課題になっていくでしょう。
条例の仕組みと具体例〜ATM前の通話をどう止める?〜
「通話しながらATM操作禁止」という条例がどのように運用されるのか、また実際にどのようなシーンが想定されるかについて、具体的なエピソードを交えて紹介していきましょう。
具体的な条文イメージ
大阪府の条例案(他地域でも同様の条例が続く可能性あり)をまとめると、
- 65歳以上の高齢者がATMを利用するとき、スマートフォンや携帯電話などで通話しながら操作を行ってはならない。
- 銀行やコンビニなど、ATMを設置している事業者は、店内に「通話しながらのATM操作は禁止」というポスターや看板を掲示し、利用者に周知する義務がある。
- 事業者や従業員は、明らかに通話中である高齢者がATMを操作しようとしている場合、声をかけて操作を中止させるよう努める。万一、不審であれば警察へ通報すること。
- 罰則はないが、高齢者がこの禁止事項に違反した場合も、注意喚起の対象となりうる。
こうしたルールにより、たとえばコンビニで働く店員さんが「お客さんが通話しながらATMを操作している!」と気づけば、すぐに声かけして止めることになるわけです。
想定されるATMでのやり取り
- ケース1:コンビニATM編
高齢女性がお菓子と飲み物を買いながらATMでお金を下ろそうとしている。レジで並んでいたときから、スマホをずっと耳に当てて会話している様子。店員さんが「あれ?ATMのところまで電話しながら行ってる…」と思い、慌てて「すみません、通話しながらの操作は禁止なんですよ。何かお困りですか?」と声をかける。するとお客さんは「えっ、役所から電話が来ていて手続きを今すぐしないと還付金がもらえないって…」。怪しいと思った店員さんは警察に連絡。結果的に詐欺被害を未然に防ぐことができた。 - ケース2:銀行ATM編
平日の昼間。高齢男性が銀行ロビーに入り、案内スタッフに「あ、ちょっとATMで振り込むんで」とだけ言い、スマホで通話をしながら操作を始める。通常、銀行の職員は声をかけやすい環境だが、あまりに混んでいると対応に追われて気づくのが遅れる可能性もある。条例が施行されれば、「ATM前で通話はできない」というルールがはっきりするので、職員が「申し訳ありませんが、条例で禁止されています。お電話は一度切っていただけますか?」と行動しやすくなる。
なぜ罰則がないのか
多くの条例には、罰金などのペナルティが設定されるケースもあります。しかし、本件の条例に罰則を設けると、「通話しながら操作」自体が犯罪になってしまい、たとえば本当に緊急通話中だった高齢者まで処罰の対象となりかねないという懸念があります。また、詐欺を防ぐはずが、逆に一般の利用者から「そこまでしなくても…」という反発を受ける可能性も高いでしょう。そこで、あくまでも「抑止力」としての条例としての側面が強調されているのです。禁止行為として明確に定義することで、「電話をしながら操作するのは危ない」「自分も止めないといけないし、周囲も止めるべき」と社会全体で合意を作っていく狙いといえます。
施行後の課題
条例によって、金融機関やコンビニの従業員への負担増をどうカバーするかが大きな論点です。接客で忙しいコンビニでは、通話しながらATMに向かう全員をチェックするのは大変ですし、不審に思って声をかけたら逆ギレされるかもしれません。また、耳が遠いお年寄りに大声で説明しようとすると、周りのお客さんも見ていて気まずい雰囲気になるかもしれません。しかし、それでも「詐欺に遭うのを防げるなら…」と店側も協力しようとしています。今後は行政や警察からの支援(マニュアル作成、研修、ポスター配布など)がどの程度整備されるかがカギとなるでしょう。
詐欺被害にあう高齢者の実態と心理~なぜ引っかかる?~
「通話しながらATM操作禁止」の条例が導入されるほど、高齢者の詐欺被害は深刻な状況です。では、どうして高齢者はこうした詐欺にあいやすいのでしょうか。本章では、詐欺の具体例や高齢者の心理状況を探りながら、対策のヒントを探っていきます。
高齢者の詐欺被害が多い理由
- 社会経験が豊富でも詐欺知識が不足
高齢者は人生経験が長く、賢い方が多いのですが、反面、インターネットやスマホを使いこなしていないケースも少なくありません。詐欺の方法は日々進化しており、「ATMでお金が戻ってくる」というウソ話にも、“そういう制度があるのかな”と信じてしまう可能性があります。 - 家族・友人に相談しづらい
一人暮らしや夫婦だけの世帯が増えており、高齢者が身近に相談できる相手を失っているケースも。詐欺グループはそんな弱みを知っていて、「家族には内緒にしてくださいね」などと言って孤立を狙います。 - 電話を止めづらい
高齢者は電話で相手の話を途中で遮ることに抵抗を感じる人が多いといわれます。特に「お役所の人」「警察の人」を装われると、断ることが失礼だと考えてしまいがちです。結果として長電話に巻き込まれ、指示通りに行動してしまいます。
よくある詐欺パターンとシナリオ
- 還付金詐欺
「○○区役所ですが、医療費の払い戻しがあり、お客様の口座に振り込めます。ただ、今日中にATMで手続きをしないと期限が切れます。誰にも言わず、今からATMへ行ってください」と言われ、被害者は急いで銀行やコンビニのATMへ向かう。電話口で指示されるボタンを押すと、自分の口座から詐欺グループの口座へお金が振り込まれる。 - オレオレ詐欺(親族詐欺)
「もしもし、おれだけど。交通事故を起こしちゃって、示談金がすぐに必要なんだ。お願いだから、今すぐ振り込んでくれないか」など、息子や孫を名乗るパターン。家族を助けたいという思いから、すぐにお金を振り込んでしまう。 - 架空料金請求
「携帯料金が滞納されています。このままだと裁判になります。支払いはATMからできますよ」などと脅され、コンビニATMなどで振り込みをさせられる。最近は偽のハガキやメールを送りつけて不安をあおる手口も増加中。
認知症や判断力の問題
さらに深刻なのが、認知症や軽度認知障害(MCI)の方が被害に遭うケースです。本人は騙されていることに気づかないまま、何度も詐欺グループにお金を送ってしまう例もあります。家族が定期的に口座をチェックしたり、金融機関に「一定額以上の振り込みは不可」設定をお願いしたりするなど、周囲のサポートが非常に大切です。条例があっても、本人がきちんと理解していなければ通話しながらATMを操作してしまうかもしれません。
電話を止めることの意義
「通話しながらのATM操作禁止」は、高齢者の心理面に直接働きかけるものではありませんが、いざATMに行こうとする段階で第三者の目が入ることで、本人に「これってもしかして怪しいかも」と気づいてもらうチャンスを与えます。
- 周囲からの声かけ
コンビニ店員や銀行職員が積極的に「あれ?この人、電話しながら操作してる」と気づく。その一言で「まさか自分が…」と我に返ることがあります。 - 詐欺グループの計画を乱す
犯人は電話しながら操作させる前提でシナリオを組んでいます。途中で通話が切られる、あるいは誰かに見られると計画が破綻し、被害が発生しにくくなるのです。
まとめ
高齢者の方は「ATMでお金が戻ってくる」「期限が今日までだ」といった話を切羽詰まって聞くと、「すぐにやらなくては」と思いがちです。そうした心のすき間を突いてくるのが詐欺グループの手口です。条例は、その“最後のライン”となるATM操作時に通話を禁じることで、詐欺をブロックしようという狙いがあります。これは決して完璧な対策ではありませんが、一度でも「詐欺を疑うチャンス」が増えるだけで、多くの人の貴重な財産を守れる可能性が高まるのです。
今後の課題と高齢者を守るためのアクション~「条例だけで終わらない」社会づくり~
最後に、現行の「通話しながらATM操作禁止」条例や、特殊詐欺対策のさらなる課題・展望について考察します。また、高齢者の被害を防ぐために私たちがどのような行動をとれるのか、具体的なアクションを提案します。
条例の限界
条例の最大の特徴は「強制力・罰則がない」ことです。そのため、もし誰も見ていない場所で高齢者が通話しながらATMを操作してしまえば、結局は被害を防ぎきれない可能性があります。さらに、高齢者を狙う詐欺は電話だけでなく、SNSやメール、訪問販売など多様化しつつあり、これらすべてに対処するためには「ATMでの通話禁止」だけで十分とは言えません。
また、金融機関やコンビニなどの現場スタッフに声かけの負担がかかり、トラブルに発展するリスクもゼロではありません。「私のプライバシーに踏み込むな」「店員の仕事じゃないだろう」と怒る利用者がいるかもしれません。社会全体で「声をかけ合う文化」を育てていく必要があります。
さらなる有効策は?
- ATMのシステム改良
技術的には、「通話しながらATMの操作を感知したら、一時的に利用を停止する」などの仕組みも検討されています。たとえば、ATMの内蔵カメラや周辺の音声検出装置などを活用し、利用者が電話中であることを検知する技術が将来的には出てくるかもしれません。ただし、プライバシーの問題やコスト面など、まだハードルは高いといえます。 - 1日の振り込み上限額設定
すでに銀行などで実施しているように、高齢者の口座については「ATMから振り込める額を1日に数万円程度に制限する」ことが考えられます。大金を詐欺被害としてすぐに失わないよう、段階的に安全策を講じるやり方です。 - 地域コミュニティの強化
一番効果的なのは、やはり人間同士のつながりです。高齢者同士が「私、こんな電話がかかってきたんだけど…」と日頃から話し合うことで、“怪しい電話”をみんなで共有できます。自治会や老人クラブなどで定期的に情報交換会を行い、怪しいパターンを学ぶ機会をつくるとよいでしょう。
家族・周囲ができる対策
- 定期的な声掛け
「最近、還付金詐欺が増えているらしいよ。ATMに行くときは絶対に誰かに確認してからにしようね」と、家族や近所の知人にあらかじめ声をかけておく。 - 着信拒否や留守番電話の活用
詐欺の多くは固定電話にもかかってきます。留守番電話を設定しておき、知らない番号には直接出ないようにすると被害を予防しやすくなります。 - 銀行・郵便局などへの相談
「実家の父が振り込め詐欺に遭うかもしれないので、大きな額の振り込みがあった場合は連絡をください」と金融機関に相談しておくことも有効です。すべての銀行が必ず対応できるとは限りませんが、一度相談する価値はあります。
私たちにできること
- 「変だな?」と思ったら遠慮せず声をかける
スーパーやコンビニで、高齢の方が電話片手にATMへ向かっているのを見かけたら、そっと「大丈夫ですか?」とひと言かけるだけでも被害防止に役立ちます。もちろん、過度に干渉するのはよくありませんが、いまや「特殊詐欺は身近で起こるもの」という意識をもって行動したいところです。 - 学校教育や地域イベントでの周知
中学生や高校生が家に帰って、おじいちゃん・おばあちゃんに「ATMで電話しちゃだめだって習ったよ」と伝えるだけでも、相当の効果があります。若い世代が「詐欺をやめさせる主役」になれるよう、学校の授業や地域行事で情報を共有する機会がもっと増えるといいでしょう。
まとめ
「通話しながらATM操作禁止」は、被害をゼロにはできないまでも、確実に詐欺を食い止めるための有力な一歩です。兵庫県警察が公開した資料【特殊詐欺水際阻止協力の店(家)ニュース】でも、還付金詐欺が急増している実態が示されていますが、その一方で、店員や銀行員が声をかけて被害を防いだ例も多数報告されています。条例が“きっかけ”となり、社会全体が高齢者詐欺を深刻な問題と認識していくなら、今後さらに様々な対策の導入が検討されるでしょう。私たち一人ひとりも、周囲への思いやりや「おかしいと感じたら声をかける」という意識を忘れないようにすることが重要です。
最後に、繰り返しになりますが「今日は還付金がもらえる最後のチャンス」「誰にも言わずに振り込んでほしい」などと焦らせる電話には絶対に応じないようにしましょう。ATMの前で電話が鳴っても、一度切って冷静に考える習慣をつける。これだけでも、私たちや大切な家族を詐欺の被害から救う大きな手段になるはずです。
高齢者を狙う悪質な詐欺をなくすため、まずは私たちが知識を持ち、周囲にも声をかけ合う文化を広げていきましょう。