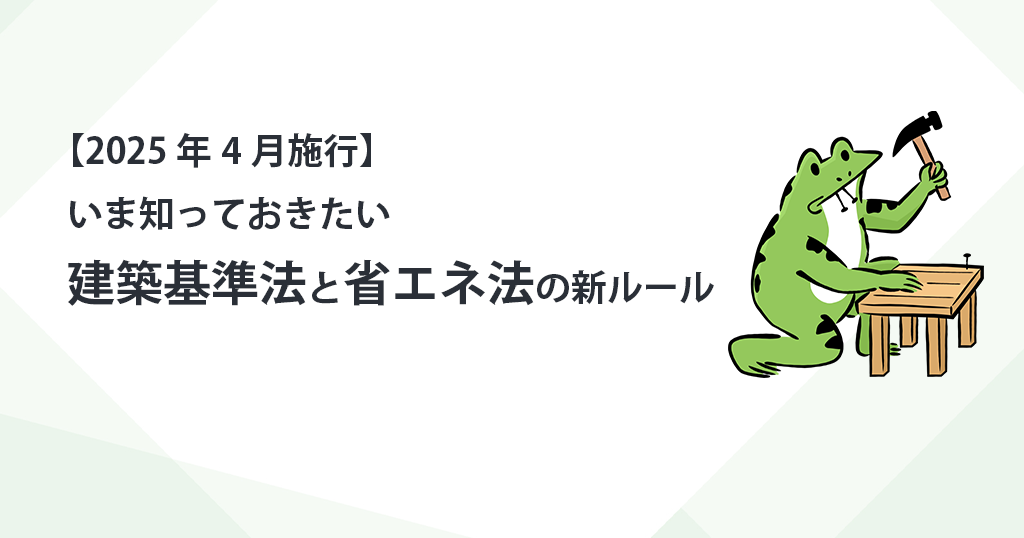背景と改正の目的
2020年に日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2030年度には温室効果ガスを2013年度比で46%削減するという目標を掲げました。これに伴い、建築分野でも省エネ化・脱炭素化への取り組みが強く求められるようになりました。建築物は日本国内の最終エネルギー消費の約3割を占めるとされ、ここでの削減がカーボンニュートラル実現の大きな鍵となります。
そこで焦点となるのが、住宅・オフィスビルなどへの省エネ基準適合義務の拡大や木造化促進です。建築物省エネ法(正式名称:「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」)は、2016年の制度開始後、段階的に改正を重ね、2017年には一部の中大規模建築物(2,000平方メートル超の非住宅)へ省エネ基準適合義務を導入し、2021年には300平方メートル超の非住宅へ対象を広げました。しかし、多くの住宅や小規模建物は義務化の対象外であったため、全体の省エネ性能底上げには物足りなさが指摘されてきました。
さらに、法改正の背景には気候危機への対応だけでなく「省エネ住宅や木造建築物の普及は地域活性化や災害対策にも寄与する」という観点があります。近年、異常気象や原油価格の高騰による光熱費問題が顕在化しており、断熱性能の高い省エネ建築は居住者の快適性向上だけでなく、経済面・防災面でも効果が期待されます。加えて、日本は世界的に見て木材資源が豊富かつ森林面積が広く、木材を適正に活用しつつ森林整備を進めれば、CO₂吸収源の確保と林業活性化を図れるという長所もあります。
以上を踏まえて、今回の改正で目指されるのは「より強い省エネ基準への適合義務付け」と「木造建築物への多様な設計を可能にする構造規制・防火規制の合理化」です。すなわち、建築物省エネ法においては「2025年4月以降すべての新築建築物で省エネ基準適合を義務化する」方向が定められています。また、改正建築基準法では、「4号特例」の見直しや「階高の高い木造建築物への構造規制の合理化」などが盛り込まれ、これにより木造建築の活用幅が拡大する見込みです。
さらに、既存ストック(中古建築物)にも大きな影響が及ぶことが特徴です。現行基準に合わない建物、いわゆる「既存不適格建築物」を省エネ改修して長寿命化を図ろうとするとき、今回の改正では高さ制限や接道義務などの規定を緩和する措置が用意されました。この狙いは「既存建築物の省エネリフォームを円滑化」し、ストックの再生を促進することにあります。省エネ性能向上と同時に建物の長寿命化を進めれば、廃材削減やCO₂排出抑制につながり、SDGsの達成にも寄与するためです。
このように、建築基準法・建築物省エネ法の改正の背景には「脱炭素社会の実現」「エネルギー価格高騰対策」「既存ストックの性能向上」など多面的な要素があります。まさに今後は、「新築時に省エネ基準をクリアするだけでなく、既存建築物をいかに省エネリフォームし、木造化を含めた建物の特性を最適に活かすか」が大きなテーマとなるのです。
建築物省エネ法改正のポイント
省エネ基準適合義務化の対象拡大
従来の建築物省エネ法では「延床面積300平方メートル以上の非住宅建築物」までが適合義務の範囲でした。しかし2025年4月施行の改正では、「すべての新築建築物」に省エネ基準への適合義務が課されます。つまり、300平方メートル未満の小規模住宅や店舗など、これまでは説明義務のみに留まっていた建物も含め、設計段階で省エネ基準を満たさなければならなくなります。
- 住宅トップランナー制度の拡充
これまでは、建売戸建て住宅・注文戸建て住宅・賃貸アパートを一定戸数以上供給する事業者が対象でしたが、改正では「分譲マンション」も対象に加わります。そのため、分譲マンション事業者もトップランナー基準を意識した設計を行う必要が出てきます。 - 増改築への対応
大規模な増改築では、改築部分だけでなく建物全体に現行基準を遡及させるケースがありましたが、改正後は「増改築を行う部分のみ」適合義務を課すかたちに変更されます。ただし増改築範囲によっては全体改修を求められる場合もあるため、計画段階で要注意です。
適合性判定手続きの合理化
適合義務の拡大に伴い、建築確認の審査対象物件が大幅に増加すると見込まれます。そのため、審査・申請の手続きをできるだけ円滑に行う仕組みが整備されます。具体的には、建築主事による建築確認審査のなかで省エネ性能の確認が組み込まれる流れとなり、仕様基準を用いるなど審査が比較的容易な場合には「省エネ適合性判定(省エネ適判)」を省略できる制度が導入されます。
- 仕様基準適合なら省エネ適判不要
たとえば「UA値(外皮性能)1.0以下」「一次エネルギー消費量BEI値1.0以下」などの計算を行わず、一定の仕様基準に従って設計・施工をすれば、適合判定が省略できるケースが設けられる予定です。
建築士の説明努力義務
小規模建築物に対しては、建築主の省エネ性能向上をサポートするために、建築士が「省エネ性能や再エネ設備のメリット」を建築主に説明する努力義務が新たに明記されます。省エネ性や再エネ導入の必要性を知らない施主に対して専門家がアドバイスすることで、実際の建物計画に省エネ・再エネ技術を組み込むよう促すわけです。
表示制度の推進
改正法では、建物を売買・賃貸する際の省エネ性能表示を推進し、事業者が適切な表示を行うよう「国土交通大臣による告示・勧告・公表・命令」が可能になります。これにより、物件広告などに省エネ性能ラベル(BELSや住宅性能評価など)を示す流れが一層強化される見通しです。
建築物再エネ利用促進区域制度
市町村が指定する「再エネ利用促進区域」において、新築時に太陽光発電・太陽熱利用などの再エネ設備を導入しやすいよう、建築士による建築主への説明義務や、形態規制(高さ制限や容積率など)の特例許可が設けられます。これにより、地元自治体主導で再エネ普及を後押ししていく枠組みが用意されることになります。
建築基準法改正のポイントと木造化促進
「4号特例」の見直し
これまで木造2階建て以下・延べ面積500平方メートル以下の建築物は、建築確認で構造耐力などの一部審査が省略できる「4号特例」の対象でした。しかし2025年4月施行の改正により、木造2階建て住宅などの一部が特例対象外となり、「新2号建築物」「新3号建築物」という区分に整理されます。
- 新2号建築物:従来の4号建築物のうち延べ面積200平方メートル超の木造2階建て建築物などが該当。建築確認手続における構造・省エネ審査が必要になります。
- 新3号建築物:延べ面積200平方メートル以下の平屋建築物などが該当。旧来の4号特例と同様の一部審査省略が認められます。
4号特例が縮小される結果、木造住宅であっても「2階建て・延べ面積200平方メートル超」であれば、構造耐力規定や省エネ規定などをしっかり建築確認審査でチェックする必要が生じます。これは、小規模とはいえ「木造住宅の安全性・省エネ性能を確実に担保しよう」という方針のあらわれです。
階高の高い木造建築物の構造規制の合理化
従来、高さ13メートル又は軒高9メートルを超える木造建築物は、高度な構造計算が求められ、一級建築士しか設計・工事監理ができませんでした。今改正ではこの基準が「高さ16メートル」に拡大され、二級建築士でも設計可能な範囲が広がります。これにより、より階高を高くした木造3階建て住宅などを二級建築士が扱いやすくなり、木造建築物の選択の幅が拡大します。
さらに、延べ面積300平方メートル超の木造建築物に対しては構造計算が必要になるなど、スパンの大きい大空間建築物を安全に設計するためのルールが整理されました。結果として「小規模~中規模の木造建築」が増加傾向にあり、高耐震性や省エネ性能を備えた木造建物が普及していく見込みです。
防火規制の合理化
- 大規模建築物の木造化促進
延べ面積3000平方メートル超の建築物を木造とする場合、現行では「耐火構造」にするか、3000平方メートルごとに耐火構造体で区画する必要があります。改正後は「燃えしろ設計法」などを取り入れた新たな構造方法を認めることで、木材の「あらわし」を可能にしながら大規模建築物の延焼リスクを抑える設計ができます。 - 部分的な木造化
耐火構造が求められる大規模建築物でも、壁や床で防火区画した範囲内であれば木造構造にできるよう規定が緩和されます。たとえば大規模ビルの上階やメゾネット住戸など、一部を木造化して魅力を高めることが容易になるわけです。 - 低層部の木造化
高層部と低層部を壁などで区画すれば「防火上別棟」として取り扱い、低層部分を木造化できるようになりました。結果、高層ビルの下層階だけ木造化し、残りは耐火構造という設計も可能になります。
既存不適格建築物への対応
既存不適格建築物(建築当時は適法だったが、その後の法改正で一部が不適格となった建物)を大規模修繕やリノベーションする際、防火・避難規定や集団規定が一律に遡及適用されて大掛かりな改修が必要になるケースがありました。今回の改正では、防火規定・集団規定(接道義務や道路内建築制限など)の一部において「省エネ改修等の工事を行う場合は現行基準を求めない」という緩和措置が導入されます。これにより、築年数の古いビルやマンションを断熱改修するときの手続き・コストが抑えられ、既存ストックの活用が促進されることが期待されます。
影響・対応策と今後の展望
建設・不動産業界への影響
- 設計・施工体制の再整備
2025年以降は、小規模住宅でも省エネ基準適合審査が必須となるため、設計段階での計算や書類作成、審査手数料などが増加します。中小工務店や設計事務所、施工会社は、省エネ性能の知識や構造計算のスキルを改めて習得し、人員体制・社内マニュアル整備を行う必要があります。
また、4号特例縮小によって木造2階建て等の住宅でも構造・省エネ審査が行われるケースが増え、確認申請にかかる期間が長引く恐れがあります。建設工程のスケジュール管理がこれまで以上に重要になるでしょう。 - コストの上昇と住宅価格への影響
断熱材、サッシ、高効率設備など省エネに必要な材料・機器の導入により、建築コストは上昇が避けられません。しかし長期的には、光熱費の削減効果や住宅の付加価値向上が見込めるため、エンドユーザーに対しては「省エネ住宅のライフサイクルコストのメリット」を丁寧に説明する必要があります。
既存建築物オーナー・管理者への影響
既存ストックを省エネ化するための改修にあたっては、「既存不適格規定」が大きな壁でした。改正では、形態規制(高さ・容積率・建蔽率など)や接道義務の緩和措置が設けられ、一定範囲の改修なら遡及適用を免れる可能性があります。これはリノベーションやコンバージョン(用途変更)を活性化し得る材料となるでしょう。
- 住宅金融支援機構のローン
既存住宅の省エネ改修向けの低利融資制度(グリーンリフォームローン)が創設されることも追い風です。改修のための初期費用負担を軽減できるため、オーナーや管理者にとっては導入しやすい環境が整いつつあります。
消費者・居住者へのメリット
- 快適性・健康性の向上
断熱性能が高い住まいは、夏の猛暑日でも冷房効率が良く、冬場の暖房による温度ムラが減ります。結露やヒートショックのリスク軽減も期待でき、結果として健康面のメリットが大きいです。 - 光熱費削減
一次エネルギー消費量を削減できる設備や断熱材を採用すれば、長期的に光熱費を節約できる点は消費者にとって魅力です。加えて、再エネ設備(太陽光パネル等)を導入すればさらに電力自給率が高まり、災害時のレジリエンスやCO₂削減が可能になります。
今後の展望:ZEH・ZEB化のさらなる推進
改正法施行後も、「2030年に新築住宅でZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準」「2050年に建物ストック平均でZEH・ZEB水準」といったさらなる高断熱・高効率化のロードマップが想定されています。
- 誘導基準・トップランナー基準の引き上げ
国交省は、改正後の動向を見据えて数年おきに基準を引き上げる可能性を示唆しています。建設業界や住宅市場は「さらに厳しい省エネ目標へ段階的に対応する」必要があるでしょう。 - 情報発信と周知
建築士・施工事業者・不動産事業者のみならず、ユーザー(施主・購入者)も「省エネ性能表示」を目にする機会が増える見込みです。表示制度の普及によって省エネ性能が数値・ラベルで比較されるようになり、住宅選び・ビル選びにおいて省エネ性能が大きな決定要因となっていくでしょう。
参考文献・関連資料
まとめ
2025年に施行される建築基準法・建築物省エネ法の改正は、日本の住宅・建築分野における省エネ・脱炭素化を一段と加速させる重要な転機となるでしょう。小規模住宅も含めた省エネ基準適合義務の拡大、木造建築物の構造・防火規制の合理化、既存不適格建築物への緩和策など、多方面で大きな変化が起こります。これらの改正を上手に活かすことは、環境負荷低減だけでなく建築の魅力向上や住生活の質向上、さらにはエネルギーコスト削減といったメリットをもたらします。
ただし、施行までの準備期間は限られており、特に中小工務店や設計・施工の事業者は新基準への対応を早期に進める必要があります。具体的には、以下のようなステップが考えられます。
- 社内教育・研修の実施:省エネ計算や断熱技術、木造構造規定などに対する社員向け研修を行い、適合審査への対応力を高める。
- 業務フローの見直し:設計段階で省エネ性能を確認・数値化する仕組みを用意し、確認申請書類の作成をスムーズに行えるようにする。
- 設備・材料の確保:高断熱の建材や高効率設備など、取り扱い製品のラインナップを見直し、施主への提案を強化。
- リフォーム提案の拡充:既存住宅やビルへの省エネリフォームに伴う規制緩和措置を活用した新たなビジネスチャンスを見出す。
一方で、住宅購入者や建物オーナーにとっては、改正法への対応によるコスト増が懸念されるものの、長期的な光熱費削減や資産価値の向上を考慮すれば、プラスに転じる見込みが高いです。特に「住宅金融支援機構のグリーンリフォームローン」などの制度や、自治体の補助金を上手に活用することで、導入時の費用を抑えながら快適かつ環境配慮型の建築物を手に入れるチャンスが生まれています。
今後は、さらなるZEH・ZEB化に向けて省エネ基準の引き上げが検討される可能性が高く、「省エネ+再エネ」を組み合わせた総合的な設計が求められていくでしょう。消費者意識も高まる中、建築関連事業者は「環境性能をいかにわかりやすく可視化して、経済的メリットとして訴求するか」が鍵となります。ぜひ本稿を参考に、最新動向を踏まえた設計・施工・改修プランの検討を進めてみてください。
新法施行までの残された期間を有効に使い、各事業者・所有者がしっかりと準備を整えることで、より安全かつ快適、環境にも優しい建物ストックを社会に提供していくことが期待されます。