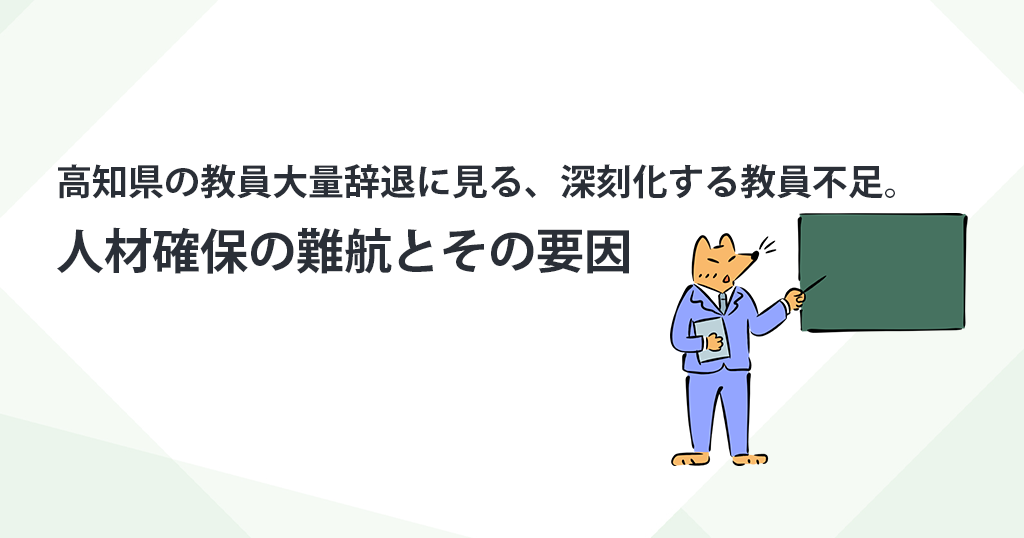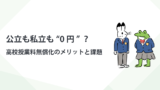高知県の教員大量辞退の報道を受け、深刻化する教員不足に関して、多くの自治体が「潜在的な教員免許保有者の掘り起こし」や「大学3年時点での囲い込み」などを進める一方、なかなか成果に結びつかず、最終的に多くの辞退を招いてしまう状況が全国で見られており、今回は日本の教員不足の現状と要因に関してまとめます。
日本の教員不足の現状と背景
日本では近年、「教員不足」が深刻な課題として注目を集めています。文部科学省の調査によると、2021年(令和3年)度の始業日時点で、全国で2,558人もの教員が不足していたと報告されました。さらに学校種別にみると、小学校や中学校での不足が特に目立ち、4月時点で必要な人数を満たせないまま始業式を迎えざるを得ないケースが全国的に発生しています。こうした教員不足の問題は、一見すると「数が足りない」という単純な話に思えますが、その背景には複雑な要因がいくつも絡み合っています。
例えば、少子化が進んでいる一方で、特別支援学級の数は増加の一途をたどっています。特別支援学級は1つの学級に配置される児童・生徒数が比較的少ないため、より多くの教員が必要となります。2022年度の時点で、特別支援学級は全国で7万6千学級を超え(小中学校のみの合計)、2010年代より大幅に増えています。さらに、小学校では「35人学級」の推進や高学年の教科担任制などが導入され、従来よりも多くの教員配置が求められるようになってきています。こうした制度改革自体は教育の質向上を目指した重要な取り組みですが、教員数の増加を伴うため、各自治体が適切に教員を確保できないと「人手不足」を招きかねません。
また、大量退職と大量採用が重なっていることも見逃せない要素の一つです。いわゆる「団塊世代」の教員が一斉に退職したことで、各自治体が正規採用を大幅に増やしてきました。これにより、長く非正規の臨時講師や非常勤講師として働きながら正規採用を目指していた既卒者層が、ここ数年で一気に正規教員として採用されました。その結果、代替要員としての非正規教員を探してもなかなか見つからず、産育休や病気休職などの穴を埋める代替教員が決定的に不足する構造的な問題が浮き彫りになっています。
他にも、若手教員を中心に産休・育休を取得する割合が増えていることも大きな要因の一つです。最近は20代や30代の教員が増えたことで、子育て世代として育児休業を取得するケースが増加しています。もちろん、これは社会全体として好ましい傾向ですが、現場ではその代替要員が確保できない場合、学級担任を他の教員が兼務せざるを得ず、業務が集中してさらに残業が増える、といった悪循環が起きがちです。
こうした状況から、文部科学省は2022年(令和4年)度の教員採用試験の倍率を調べたところ、全校種の総計で3.4倍と過去最低を記録したと報告しています。特に小学校は2.3倍という低水準で、合格しても辞退する人が増えている自治体も少なくありません。これは、複数の自治体や民間企業の併願が増えたこと、さらには「教員の仕事の大変さ」に対するイメージが若者の間で広まっていることも大きく影響しているとみられています。
このように、教員不足は「数」の問題にとどまらず、「仕事の忙しさや負担の大きさ」「採用制度の現状」「特別支援学級や少人数学級の拡充」など、さまざまな要素が複合的に絡んでいます。そのため、対策には単に「採用枠を増やす」だけでなく、学校現場の働き方改革やICT活用、人材バンクの活用や制度改革など、多方向からのアプローチが必要です。次のセクションでは、これらの原因をもう少し詳細にひもときながら、どのような対策が模索されているかを見ていきましょう。
教員不足が生じる主な要因とその深層
日本の教員不足は一時的な現象ではなく、背景に複数の構造的な要因が存在しています。ここでは、その要因をいくつかの視点から整理し、中学生でもわかるように具体的な例とともに紹介します。
特別支援学級の拡充による教員需要の増加
近年、「特別な支援が必要な児童・生徒」を対象とする特別支援学級の数が急激に増えています。2022年度時点で全国の特別支援学級数は7万6千を超え、小中学校では2010年代と比べて倍増に近い伸びを示している地域もあります。特別支援学級では教員1人あたりの受け持ち人数が通常学級より少なく設定されているため、少人数でも子どもたちにきめ細かい支援を行える反面、より多くの教員配置が求められます。
産休・育休の増加と代替要員の不足
20代・30代の若手教員が増えていることは、教育現場に新しい発想をもたらす一方で、育児休業を取る教員が増える傾向にもつながっています。文部科学省の報告によれば、産休・育休取得者は平成24年度には1万5千人台でしたが、令和4年度には2万3千人超と大きく増加。以前はこうした産休や育休の代替として非正規の臨時講師を確保することができていました。しかし、大量退職・大量採用の流れで、免許を持ちながら非正規で待機していた層が一気に正規採用され、その結果「臨時講師のなり手」が枯渇しているのです。
働き方やイメージの問題
教員の業務は「授業」だけでなく、部活動や保護者対応、事務作業、校務分掌などが重なり合い、とても忙しい現状があります。いわゆる「ブラック部活」の問題や、「モンスターペアレント」に代表される保護者対応などが注目されることで、教師という仕事のイメージが悪化している側面も指摘されてきました。また、民間企業の就職活動が早期化し、4年生の夏頃には内定を得る学生が増える中、教員採用試験の結果が出るのは10月前後と遅いため、途中で進路変更して民間企業に流れてしまう事例もあります。
地域格差や地方公務員定数の削減
少子化で生徒数自体は減っているものの、地方自治体による公務員削減の流れが強まった時期に、教員の定数も削減対象となった地域があります。例えば、地方公務員全体の人件費を圧縮する計画が先行してしまい、正規採用を抑制してきた結果として「非正規中心の教員配置」を続けてきた自治体では、前述のような産休代替や病休代替に対応しきれなくなるケースが顕在化しています。その一方で、特別支援学級や少人数学級の取り組みを積極的に進めている自治体ほど、新たに必要となる教員数が増え、慢性的な不足に陥る可能性があります。
構造的な「大量退職・大量採用」と教員採用試験の倍率低下
団塊世代の大量退職によって、数万人規模の新規採用がここ10年ほど続きました。その結果として、かつては「狭き門」と言われた教員採用試験の倍率が大きく下がっています。令和4年度の試験では全校種で3.4倍、小学校は2.3倍と、いずれも過去最低を記録しました。さらに、合格してもほかの自治体や民間企業を選ぶ「辞退」が相次ぎ、採用計画の見直しや追加募集を余儀なくされている自治体もあります(※高知県では合格者の7割以上が辞退してしまい、急遽2次募集を行う事態が報じられました)。
こうした要因を総合すると、教員不足は一時的に解決する問題ではなく、教育現場の業務量削減や処遇の改善、採用制度の見直しなど、長期的かつ多方面からの改革が求められます。次のセクションでは、文部科学省や各都道府県・政令指定都市教育委員会が実施している具体的な対策を取り上げながら、その成果や課題を見ていきましょう。
文部科学省・各自治体の具体的対策
文部科学省の動き
文部科学省は「教員不足の解消に向けた各教育委員会における取組事例」をまとめ、教員不足の要因と改善策を各自治体で情報共有するよう促しています。この資料によれば、令和5年度補正予算(約5億円)と令和6年度当初予算案(同じく約5億円)を用い、次のような施策を実施・検討しています。
- 大学・民間企業等と連携した教師人材の確保推進事業
- 教員になろうとする人を大学入学の段階から支援する「地域教員希望枠」を設け、大学と教育委員会が連携して質の高い教師を育成・確保する。
- 民間企業やNPOなどと共同で「多様な社会人が学校現場に参画できるルート」を開拓する。いわば人材バンク的なシステムを整備し、臨時講師や非常勤スタッフとしてのマッチングも視野に入れる。
- ペーパーティーチャー(教員免許状を取得後、現場経験がない人)向け研修の推進
- 都道府県や指定都市の教育委員会が主体となり、免許取得後に長らく教壇に立っていない人を対象とした講習会やセミナーを実施し、再び学校現場へ参入してもらうきっかけを作る。
- 採用試験の早期化や複数回実施
- 教員採用試験が民間企業の就職活動より遅い時期に行われるため、学生が内定辞退をせざるを得なくなっている構造的な問題を解消するため、一部自治体では6月から試験を行うほか、追加募集を積極的に行うようになっています。
- 産休・育休代替の先行配置を支援
- 年度初めから産休や育休に入る見込みのある教員の代替要員を、年度当初から確保するための特別な加配定数を認める支援策を講じています。臨時講師を早めに確保しやすくし、学級担任の「空白期間」をなくそうという狙いです。
参考資料
教師不足の解消に向けた各教育委員会における取組事例(文部科学省)
各自治体における特色ある取り組み
文部科学省の資料からは、いくつかの自治体が独自の工夫を凝らしている事例が紹介されています。
- 埼玉県:「ペーパーティーチャーセミナー」
免許を持っていながら現場経験がない人やブランクがある人を対象に、短期集中的に必要な研修を行うセミナーを開催。参加者にはそのまま講師登録をしてもらい、実際に代替要員として任用されるケースも増えているとのことです。 - 大阪府:「教員スタートアッププログラム」
学校勤務の実践的なノウハウを学ぶ機会を提供し、履修後は臨時講師として採用される流れを作っています。テレビドラマとのコラボレーションで大々的にPRを行うなど、受験者の裾野拡大を図る取り組みも話題になっています。 - 神戸市:「教員スタートプログラム」
現代の教育課題や学習指導の基礎を、学校現場や講義形式でセットで学べるプログラムを提供。参加後にそのまま非常勤講師や臨時講師として働くことを目指す仕組みです。 - 福岡県:NPO法人Teach For Japan(TFJ)との連携
社会人経験者向けのパネルディスカッションをオンラインで開催。企業や民間で働く人たちに向けて、教職のやりがいや社会的意義を伝え、採用試験を受けるきっかけづくりを行っています。 - 鹿児島県:「かごしまの先生スタートプログラム」
鹿児島大学の「学校教育キャッチアップ講座」を県教委が全額負担して受講可能にし、そのまま研修を経て臨時講師や正規教員を目指してもらうシステムを整備。大型商業施設でのPRイベントなども実施しています。
オンライン化やICT活用の進展
コロナ禍を経て、オンラインを活用した説明会や研修が増えたことも特徴です。例えば「ペーパーティーチャーセミナー」や「スタートアッププログラム」などでは、Zoom等を使った講義や相談会が実施され、遠隔地からでも気軽に参加できるようになりました。これにより、これまで地域の制約があった人材も参加しやすくなっています。
これらの事例から、教員不足対策には「免許を持っているが現場を離れていた人」や「民間企業など別のキャリアを持つ人」の掘り起こしに注力している姿勢が見えます。しかし、それだけでは追いつかないほどの需要増が続いていることも事実です。次のセクションでは、これからの展望や残された課題について考えていきます。
今後の展望
教員不足の問題は、日本の学校教育の質や子どもたちの未来に直結する重大な課題です。一部の専門家からは「数年後には少子化で生徒数が減り、自然と解消に向かうのではないか」という見方もありますが、文部科学省や多くの自治体は、この見通しを楽観的すぎると捉えています。なぜなら、特別支援学級や少人数教育の必要性が高まる一方で、依然として産休・育休の増加やメンタルヘルスに起因する病休者の増加が止まっていないからです。
一方で、働き方改革や待遇改善などを強化することで、教員のなり手を増やす努力も進められています。具体的には、以下のようなポイントが焦点となるでしょう。
- 長時間労働の是正と部活動改革
部活動指導の地域移行やスクールサポートスタッフの活用などにより、教員の働き方を抜本的に見直す動きが加速しています。特に「休日の部活動移行」などが進めば、週末の顧問業務から解放される教員が増え、離職や敬遠する動きが抑えられる可能性があります。 - ICTの活用による事務効率化
授業準備や評価、学級経営に関する記録など、紙ベースの業務を削減し、デジタル化を推進することで、教員の負担を軽減する取り組みが広がりつつあります。これは自治体や学校ごとの環境整備が鍵になりますが、標準化や支援金の拡充が期待されています。 - 多様なキャリアと教職をつなぐルートの整備
企業やNPOで経験を積んだ人が教員として参入する際のハードルを下げるため、特別免許状の制度を拡充したり、大学での実習免除や複数回の採用試験を取り入れたりといった改革が進行中です。多様な社会人経験をもつ教員が増えることで、学校の教育内容にもプラスの効果が期待できます。 - メンタルヘルスと若手教員のサポート
病休・休職の大部分を占めると言われる精神疾患への対策としては、専門家によるサポートや職場内の協力体制が重要視されています。若手教員が孤立しないような研修体制やメンター制度、管理職や同僚によるきめ細かいケアが不可欠です。
以上のように、教員不足の解消には多面的なアプローチが必要です。文部科学省も各地の教育委員会も、採用枠の拡充だけでなく、「学校を働きやすい職場へ変える」という改革を同時に進めようとしています。そうすることで、現在の現場を支える教員が疲弊せずに働き続けられる環境を整え、新しい人材が「魅力的な職業」として教職を選ぶように誘導することが狙いです。
しかし、こうした改革には予算や人員の確保、社会的な理解が欠かせません。たとえば、国が定める教員定数に対して0.3%が不足しているという数字だけを見ても、「ほんのわずか」と思う人がいるかもしれません。ところが、実際の学校現場で1人でも教員が不足すれば、学級担任の代わりがいないクラスが出るなど、子どもたちの学びに直接影響が及びます。また、自治体によっては教員の追加募集や早期試験を導入しても効果が限定的で、応募者が集まらず2次、3次と何度も募集を繰り返している例も見られます。
最終的には、「新卒者が教職を志願したい」「既卒・社会人がキャリアチェンジしやすい」「現職教員が長く健康に働ける」環境を、国・自治体・学校・大学・民間企業などが一丸となって作り上げることが鍵となるでしょう。中学生のみなさんが大人になる頃には、教育現場がもっと柔軟で、先生方が働きやすい環境になっていることを願いつつ、現時点ではまだまだ取り組むべき課題が山積しているのが現実です。
まとめ
- 教員不足 は少子化にもかかわらず、特別支援学級数の増加や産休・育休の拡大などにより、深刻化している。
- 原因 は、大量退職・大量採用で採用試験の倍率が低下し、臨時講師のなり手が減ったこと、長時間労働や厳しい職場環境などのイメージ悪化、地方公務員定数の削減など多岐にわたる。
- 対策 としては、文部科学省や各自治体がペーパーティーチャーセミナー、スタートアッププログラム、マッチングシステム構築、採用試験の早期化など様々な施策を展開中。
- 今後 は、働き方改革やキャリアチェンジしやすい制度づくり、ICTを使った効率化やメンタルヘルス対策など、多方面から環境を整えることが必須となる。
以上を踏まえ、教員不足問題は単なる「人数」の話ではなく、学校教育の将来を支える人材がどのように集まり、どう成長できるかという「教育の根幹」に関わる重要なテーマだと言えます。われわれ一人ひとりがこの現状を理解し、魅力ある教育現場を一緒に作っていく意識を持つことが大切です。