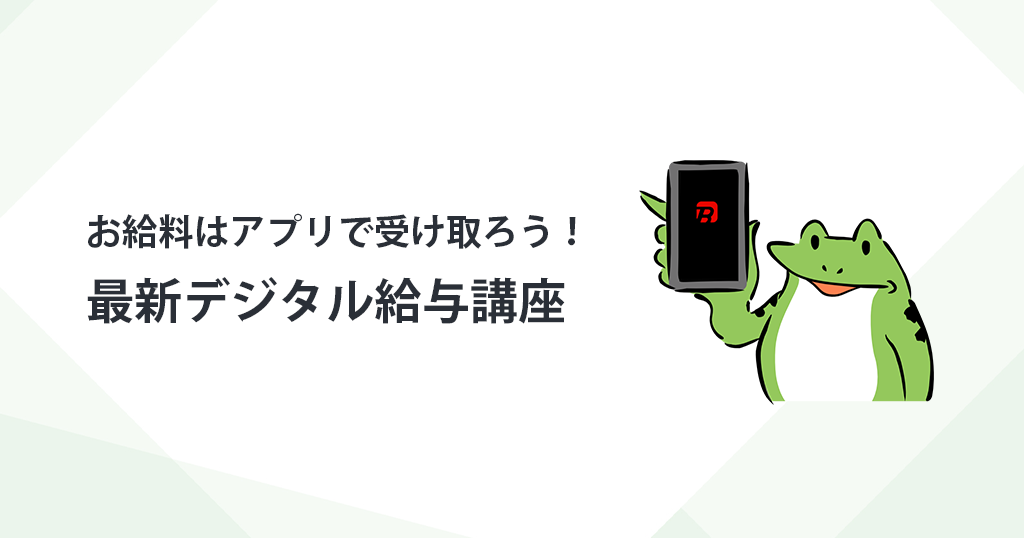デジタル給与とは?
デジタル給与(賃金のデジタル払い)とは?
「デジタル給与」とは、これまで一般的だった現金手渡しや銀行口座振り込み以外に、「資金移動業者」と呼ばれる銀行以外の送金サービス事業者の口座へ給与を振り込み、それを従業員が電子マネー等で受け取る仕組みのことです。たとえば、スマートフォンアプリの○○Payや電子マネーサービスの口座が利用されます。
通常、賃金は「通貨で、直接、全額、毎月1回以上、一定の期日までに支払う」ことが法律(労働基準法第24条)で定められています。しかし、キャッシュレス化や外国人労働者の増加など、社会の変化に対応するために、2023年4月より「厚生労働大臣が指定した資金移動業者口座への振込」も例外的に認められるようになりました。この仕組みが「賃金のデジタル払い」です。
どうして今、デジタル給与が注目されているの?
- キャッシュレス決済の普及
新型コロナウイルスの流行をきっかけに、接触を減らす決済手段としてQRコード決済や電子マネーなどが急速に普及しました。 - 外国人労働者の増加
銀行口座の開設が難しい外国人労働者が増加している背景から、より柔軟な給与支払い方法が求められています。 - 政府方針と規制改革
日本政府はキャッシュレス化推進の一環として、「銀行以外の方法で賃金を支払う道」を拡げる取り組みを進めています。
デジタル給与は全員必ずやらなければならないの?
いいえ、デジタル給与は「従業員が希望する場合のみ」利用できます。企業側にも導入の義務はなく、労働者本人にも強制はできません。もし導入する場合は、会社側と従業員代表が話し合って労使協定を締結し、その上で利用する従業員個別の同意書(賃金をデジタルで受け取ることへの同意)を交わします。
厚生労働省からの通達のポイント
- 現金化できないポイントや仮想通貨での支払いは認められない
- デジタル給与はあくまで「銀行振込や現金手渡し以外にも選べる手段」の一つ
- 従業員が希望しない限り、現状の受け取り方法を変更する必要はない
- 口座残高の上限や、破綻時の保証制度などのルールが定められている
参考資料
労働者・雇用主さまへ 賃金のデジタル払いが可能になります!(厚生労働省)
まとめ
デジタル給与は、社会のキャッシュレス化や働き方の多様化に応える新しい制度です。銀行口座を通した振り込みと併用することも可能で、実際に使うかどうかは従業員の希望や、会社の運用方針に左右されます。次章では、デジタル給与が誕生した経緯や制度の基本ルールについて、さらに詳しく見ていきましょう。
デジタル給与創設の経緯と制度概要
これまでの賃金支払いルール
日本の法律(労働基準法)は、本来「賃金は現金(通貨)で支払う」ことが大原則でした。しかし、社会情勢の変化を踏まえて、銀行振込も従業員本人の同意があれば認められるようになったのです。そして近年、さらなるキャッシュレス化や外国人労働者の増加などを背景に、銀行以外の口座に対しても賃金支払いを可能にしようとする声が高まりました。
制度が生まれた理由
- キャッシュレス推進政策:経済産業省が中心となり、2025年までにキャッシュレス決済比率を大幅に高める目標を掲げています。
- 多様な働き方との相性:副業・兼業をしている人、派遣社員、外国人労働者など、銀行口座以外での受け取りを望む層が増えています。
- リスク分散:最近は、銀行口座の維持が難しいケース(在留期間の短い外国人など)や、給与を複数のサービスに分散して受け取りたいというニーズが一定数確認されています。
厚生労働大臣による指定制度
デジタル給与を実現するためには、「資金移動業者」と呼ばれる非銀行系の送金サービス業者が厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。指定を受けるためには、下記のような要件を満たさなければなりません。
- 破綻した場合の補償制度を備えていること
- 従業員の口座残高を上限100万円等、ルールで管理できること
- 不正送金などが起こった際の対応や情報セキュリティ対策がしっかりしていること
こうした厳しい条件をクリアしたうえで「指定資金移動業者」となるため、企業側は安心して利用できる仕組みが整えられています。
現在の指定資金移動業者
2025年4月時点では、「PayPay株式会社」「株式会社リクルートMUFGビジネス」「楽天Edy株式会社」「auペイメント株式会社」の4社が指定を受けています。また、今後も他の事業者が参入する可能性があり、それによって利用できるサービスの選択肢が増えることが期待されています。
まとめ
デジタル給与は、働く人の利便性を高めるだけでなく、企業や社会全体のキャッシュレス化を推進するうえでも大きな一歩です。次章では、どのような企業や従業員がこの制度を使うと便利なのか、また導入による具体的なメリットを紹介します。
指定資金移動業者とは?~実際のサービス内容と選び方~
指定資金移動業者って?
デジタル給与を担う「指定資金移動業者」は、銀行以外で送金サービスを提供している会社のうち、厚生労働省と財務局(金融庁など)の審査をパスした事業者を指します。これらの業者は、給与という重要なお金を扱うため、利用者の資金を守る仕組み(破綻時の保証など)や不正送金への対策を講じています。
主な指定資金移動業者とサービス特徴
- PayPay株式会社
給与の一部または全部を「PayPay」アプリ残高として受け取る。上限は20万円。超過分は登録してある銀行口座へ自動で移されるなど、利便性が高い。 - 株式会社リクルートMUFGビジネス
「COIN+」という名称で給与をデジタルで受け取れるサービスを提供。三菱UFJ銀行との連携により保証体制も確立。 - 楽天Edy株式会社
「楽天ペイ給与受取」として給与を受け取り、楽天グループのサービスや街のお店、ネットショッピングで幅広く活用できる。 - auペイメント株式会社
「au PAY 給与受取」としてサービス開始。給与をスマホアプリの残高として受け取り、買い物や各種支払いに利用できる。
指定業者を選ぶ際のポイント
- 利用しやすさ:従業員が普段から使っている決済アプリやポイントサービスがあるか
- チャージや送金の手数料:給与の一部または超過分を銀行口座へ移動する際の手数料負担はどうか
- サービス上限や保証制度:口座残高上限はいくらか、破綻保証はどのようになっているか
- 会社・従業員のニーズ:利便性の面(よく使う店舗やサービスで支払い可能か)、外国人労働者が多いか、など個別事情
4. PDF資料¹との関連
MHLW(厚生労働省)が公開しているリーフレットでも、「資金移動業者をきちんと選びましょう」「賃金の一部を希望すればデジタルで、残りは銀行振込でもOK」といったわかりやすいイラストで解説があります。特に重要なのは“破綻時の保証”で、給与を預けた資金移動業者が万一倒産しても、指定の保険会社や保証機関によって全額が補償される仕組みです。
まとめ
資金移動業者の多様化によって、デジタル給与の使い勝手がさらに広がっています。どのサービスを選ぶかは会社・従業員それぞれのニーズ次第ですが、特に多くの人が使っているアプリや、ポイント還元などの特典があるかどうかが注目ポイントになりそうです。次章では、デジタル給与のメリットを掘り下げます。
デジタル給与のメリット~企業・従業員双方の視点~
企業側のメリット
- コスト削減の可能性
従業員数が多い会社では、毎月の給与振込手数料がばかになりません。資金移動業者への振込手数料は、銀行よりも安く設定されることが多く、場合によっては大幅なコストカットが期待できます。 - 企業イメージの向上
デジタル化や新しい働き方に対応できる企業であるとアピールできるため、採用面や従業員満足度(エンゲージメント)向上などにもつながります。 - 外国人労働者への対応
銀行口座を作るハードルが高い短期在留の外国人社員でも、スマホアプリの口座を用意するだけで給与をスムーズに受け取れるようになります。
従業員(受取側)のメリット
- キャッシュレス決済がスムーズに
給与を受け取ってから改めてチャージする手間が減り、買い物や請求支払いがすぐに可能になります。 - 必要な分だけ銀行口座に移せる
給与の一部のみをデジタルで受け取って、残りは銀行口座振込にするなど、柔軟な管理が可能です。また、スマホアプリ上から必要なときだけ口座に戻せる(初回は無料など)場合もあり、生活スタイルに合わせて使えます。 - ポイントやキャンペーンの活用
デジタル払い対応の電子マネーでは独自のキャンペーンやポイント還元があることが多く、結果的に手元のお金が増えたり、便利なクーポンを使えたりするメリットがあります。
具体例
例えば、従業員が「毎月3万円だけはQRコード決済サービスにデジタル給与としてチャージし、残りは従来通り銀行口座に振り込まれる」と設定すると、日常のコンビニ決済やショッピングサイト、公共料金の支払いなどが簡単になり、手数料や時間の節約にもつながります。
まとめ
デジタル給与は、企業にとってコスト面や柔軟な人材受け入れを可能にする手段であり、従業員にとってはキャッシュレス生活をより便利にする手段です。しかし、メリットばかりではありません。次章ではデメリットやリスク面をしっかり把握していきましょう。
デジタル給与のデメリット・リスク~注意点を押さえよう~
企業側のデメリット・リスク
- 二重管理の手間
全従業員がデジタル給与を使うわけではないため、「銀行振込組」と「デジタル払い組」の2種類の振込データを作らなければならないケースがあります。管理や確認作業が増えてしまう恐れがあるため、給与システムや人事部門の負担を考慮しなければなりません。 - 手数料の扱い
銀行振込の場合、従業員1人あたりにいくらかの振込手数料がかかるのと同様に、資金移動業者への振込手数料も発生します。契約形態によっては銀行より安くなる可能性がある一方、複雑な料金プランや追加コストがかかることもあり、事前のシミュレーションが重要です。 - システムとの連携コスト
自社の給与計算システムがデジタル給与に対応していない場合、新たにシステム改修や外部サービスとのAPI連携が必要となるかもしれません。
従業員(受取側)のデメリット・リスク
- 希望の資金移動業者が選べない可能性
会社側と労使協定で決めた指定資金移動業者しか利用できない場合があるため、自分が愛用しているキャッシュレスアプリを指定できないケースも考えられます。 - 残高上限がある
資金移動業者の口座には法律上の上限があり、現在は多くの場合100万円が目安です(PayPayは20万円、楽天Edy・auペイメントは10万円など、事業者により異なる)。多額のボーナスや高額給与を一度に受け取りたいときには、結局銀行口座への自動送金が必要です。 - セキュリティ上の注意
スマホのアプリを紛失したりパスワードを盗まれたりした場合、不正送金のリスクがあります。万が一被害が発生しても、補償内容はケースによって異なるので注意が必要です。
破綻リスクと補償制度
万が一、指定資金移動業者が破綻した場合はどうなるのか。厚生労働省の仕組みとして、あらかじめ保険会社などの保証機関が定められていて、給与として受け取った分の残高は6営業日以内に全額弁済されることが約束されています。ただし、規約をよく確認しておくことが大切です。
まとめ
デジタル給与には便利な面がたくさんありますが、会社や従業員がそれぞれ管理をどう行うか、手数料の負担はどうなるか、セキュリティ対策は十分かなど、事前に検討すべき項目が多くあります。最後の章では、実際に導入する場合の流れと最新動向を紹介します。
導入手順とこれからの展望~実際に使うには?~
企業が導入するための手順
- 社内検討・従業員アンケート
デジタル給与を導入する目的や想定メリット・デメリットを整理し、従業員に対して「どのサービスなら使いたいか」「どのくらい希望者がいるか」を確認します。 - 指定資金移動業者の決定
厚生労働省サイトで公表されている指定事業者リストを参照し、手数料やサービス内容を比較検討のうえ、選定します。 - 労使協定の締結・就業規則の改定
事業場の労働組合や従業員代表と協議し、指定資金移動業者を明記した労使協定を締結。必要に応じて就業規則や給与規定を改定し、労働基準監督署へ届け出ます。 - 従業員への周知と同意書の取得
デジタル給与を希望する社員に、利用手順・注意点・口座情報登録などを説明し、同意書(または申込書)をもらいます。 - システム設定・運用開始
自社給与システムで振込先を登録し、テスト実施後、本番運用へ。初回は少額での振込など、慎重に実施する企業も多いでしょう。
最新動向(2024年~2025年)
- 2024年8月以降、PayPay社を皮切りに複数の事業者が指定を受けはじめ、同年11月から「PayPay給与受取」の対象がさらに広がるなど、じわじわと利用企業が増えつつあります。
- 2025年3月には「楽天ペイ給与受取」も本格スタート予定で、選択肢が増えることで普及のペースが上がるか注目されています。
- なお、デジタル給与が解禁されたといっても、すぐに全社的に導入する企業はまだ多くありません。試験導入や、一部従業員のみ・給与の一部のみを対象にするケースが増えると見込まれています。
今後の展望
- サービスの多様化:指定資金移動業者の増加に伴い、よりお得なキャンペーンや管理ツールが登場し、デジタル給与の普及が進む可能性があります。
- 周辺サービスとの連携:家計簿アプリや財務管理システムなどと自動連携する取り組みが増えれば、給与受け取りから家計管理までシームレスに行えるようになるかもしれません。
- 企業の柔軟な対応がカギ:完全デジタル給与に切り替える企業はまだ少数ですが、一部適用や複数支給方法を併用するなど、企業が柔軟な対応を進めることで、従業員満足度向上と企業イメージのアップにつながるでしょう。
Q&A形式でおさらい
- Q:デジタル給与って使いたくないときも強制?
→ いいえ、希望しない人は銀行口座で受け取り続けられます。 - Q:残高を現金化するのに手数料は?
→ 月1回まで無料としている事業者も多いですが、2回目以降や振込先の銀行によっては手数料がかかる場合があります。 - Q:資金移動業者が倒産したら給与はどうなるの?
→ 破綻時には指定の保険会社などから6営業日以内に全額が弁済されると法律で定められています。
まとめ
デジタル給与はまだ導入したばかりの企業が多くなく、「これから」の制度といえます。けれども利便性が高いため、徐々に普及が進むでしょう。自分や自社が導入するなら、メリット・デメリットをよく比較検討し、ルールや手数料をしっかり確認しながら、安全に活用してください。
参考リンク
- 厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
- 『賃金のデジタル払いが可能になります』リーフレット(厚生労働省)
- 各指定資金移動業者の公式サイト
「デジタル給与」は、これからの働き方やキャッシュレス社会を考えるうえでも大変重要なキーワードとなっています。ぜひ、周囲と情報を共有しながら検討を進めてみてください。