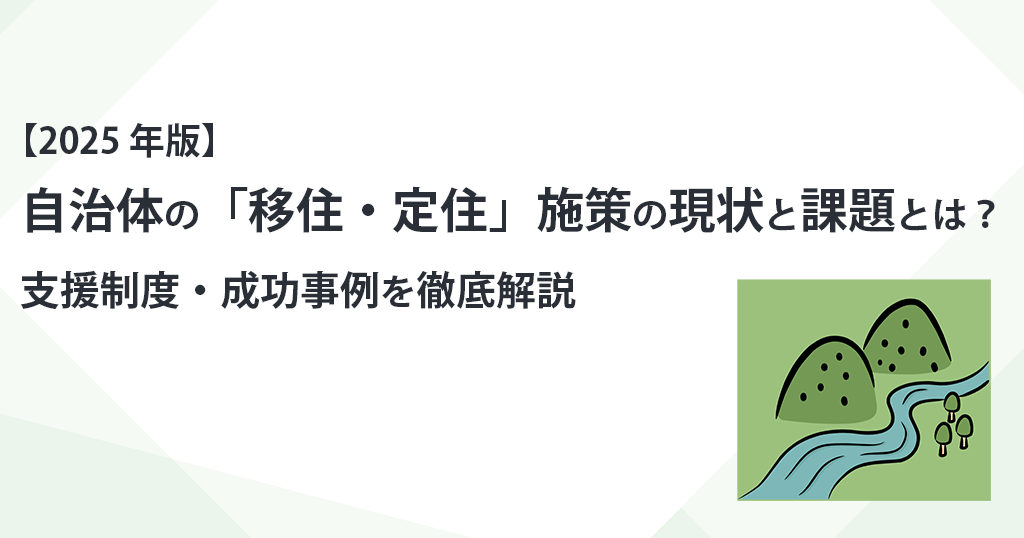注目される「移住・定住」施策の背景と理由
人口減少と少子高齢化の進行
総務省の国勢調査や内閣官房・内閣府の「地方創生ポータルサイト」(※2)でも明らかなように、日本全体の人口減少と少子高齢化が進行しており、特に地方では深刻です。若年層が進学や就職を機に大都市圏に流出し、地方には高齢者が集中的に残る「人口の偏り」が生じています。このままでは集落の維持すら危ぶまれるという自治体も少なくなく、「移住・定住」を通じて地域に新しい人材を呼び込みたいというのが大きな背景です。
例:秋田県にかほ市のケース
秋田県は全国でも特に少子高齢化が進んでいる地域。にかほ市では、若い世代が子育てしながら安心して暮らせるよう、保育料の無償化や医療費助成を拡充。また、移住前に1ヶ月〜1年間滞在できる「移住体験住宅」制度を整え、都市部の人が四季を通じて秋田での生活を試せる仕組みを整えたところ、滞在後そのまま定住に移行する事例が増加し、一定の成果を上げています。
東京圏への一極集中のリスク
東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)への過度な人口集中は、首都直下型地震など災害リスクや高い生活コスト、通勤ストレスなど多数の問題をはらんでいます。一方、新型コロナウイルス感染症の流行を機にテレワーク・リモートワークが普及し、「必ずしも都心にいなくても仕事を続けられる」という働き方が広まりました。これにより、大都市にこだわらず、自然環境や子育て環境の整った地方を検討する層が急増したのです。
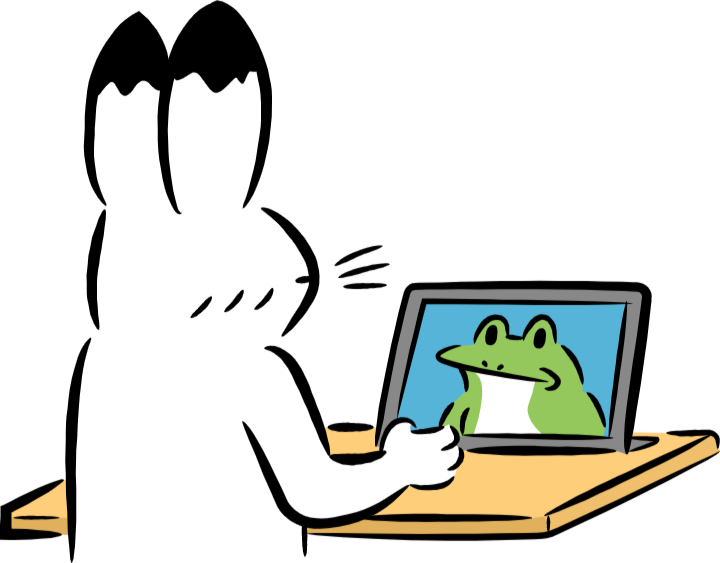
例:高知県室戸市のケース
室戸市(※1の自治体調査報告にも掲載)は、遠隔地でのテレワーク導入が相次ぐ中、「無料職業紹介所ジョブ住室戸」の開設や移住相談員を配置し、住まいと仕事の両輪でサポートを強化。支援を充実させた結果、令和3年度の移住者は過去最高を記録し、特に30〜40代の子育て世代が増加しました。
国の地方創生政策と財政的後押し
政府は「地方創生」の一環で、移住・定住を支援する交付金や補助金を多数用意しています。有名な例として「地方創生移住支援金(最大100万円〜300万円)」「地方創生起業支援事業」「特定地域づくり事業協同組合制度」などが挙げられます。さらに、2021年度からはリモートワーク移住にも補助が適用されるなど要件が緩和され、多くの自治体がこれら国の制度を活用しながら独自の上乗せ補助をセットにして移住者を呼び込み始めています。
働き方の多様化とワーケーション・二拠点居住
近年、「ワーケーション」や「デュアルライフ(二拠点居住)」が注目されています。自治体によっては、週末移住やシーズン限定での長期滞在を受け入れる施設や、ワーケーション受け入れ企業・宿泊施設をリスト化することで、潜在的な移住希望者との接点を増やしています。実際に現地滞在を経て、最終的に定住に至る例も報告されています。
例:長野県松本市のケース
観光要素の強い松本市は、ワーケーションや観光型テレワークを誘致し、滞在中に地元企業との交流会をセッティング。移住前に具体的な求人情報を得られることで、「観光目的で来たけれど、実は地元企業で働ける」と気づき、そのまま移住を決断するケースが増えています。
自治体の移住・定住施策の現状
情報発信と移住相談体制の整備
(1) 空き家バンク
全国的に導入が進む「空き家バンク」は、地方で増加する空き家を有効活用する仕組み。自治体ごとにウェブサイトやポータルサイトに物件情報を掲載し、移住希望者と持ち主をマッチングします。しかし、所有者との調整や物件の改修費用がネックになる場合も多いです。そのため自治体の多くは「空き家改修補助」や「家財道具撤去費用の助成」などをセットにして利用を促しています。
成功事例:岡山県和気町
和気町は「空き家活用事業補助金」を設け、物件改修費や引越費用などを総合的に助成。空き家の登録数を増やすため、町職員が空き家所有者宅を訪問して協力を得るアプローチを実施したところ、登録物件数が2倍以上に増え、成約件数も大幅にアップしています。
(2) 移住専門窓口・移住コーディネーター
役場内に「移住定住推進室」を立ち上げたり、NPO法人などの中間支援組織に窓口業務を委託する動きも盛んです。移住希望者へのワンストップ対応や現地案内、地域住民とのマッチングなどを専門スタッフがきめ細かく行うことで、移住後のミスマッチを減らす狙いがあります。
住宅支援策の多様化
(1) 新築・購入への補助
各自治体が「定住促進」の一環で、最大100万~200万円の購入補助を用意する例が多くみられます。また子育て世帯の場合、加算支給が行われるなど、政策的に若い世代を呼び込みたい意図が明確に表れています。
成功事例:宮城県七ヶ宿町「地域担い手づくり支援住宅」
この町では、新築の戸建て住宅を最長20年間借り上げ、家賃を払い続ければ土地・建物ともに最終的に無償譲渡されるという大胆な支援策を実施。地区住民が移住者を受け入れるためのコミュニケーションの場を設けたところ、子育て世代の移住が相次ぎ、一部地区では小学校の児童数増加に成功しました。
(2) 家賃助成・引越費補助
移住希望者が最初に住む賃貸物件の家賃を何年か補助したり、引っ越し費用を助成する制度は、多くの自治体で導入が進んでいます。なかには「2年間家賃半額」という大胆な例や、「交通費補助」をセットにする自治体もあり、引越しの初期コストを大幅に抑えられる点で人気です。
子育て・教育支援の強化
(1) 保育・医療費無償化の拡張
若い世代の移住を重視する自治体ほど、保育園や幼稚園の保育料、給食費、医療費の無料化が充実。たとえば北海道上士幌町や石川県かほく市は「子ども医療費無料」や「認定こども園の保育料無料」を掲げ、子ども1人当たり100万円の住宅取得補助など大胆な仕組みが注目を集めています。
(2) 山村留学・地域みらい留学
小中高生が一定期間だけ地方の学校で学ぶ制度や、高校段階で都市から地方に留学する「地域みらい留学」が広がりつつあります。これにより、子ども自身や保護者が「地方の暮らしや教育環境」を実際に体験し、後に家族ごと移住するケースが増えたという報告も。自治体としては、体験プログラムに加え、移住後の奨学金返還支援や学校外学習サポートを強化している事例が見られます。
就労・起業支援の取り組み
(1) 無料職業紹介所や独自求人サイト
都市部の求職者と地元企業を結びつけるために、自治体が職業紹介所を開設したり、独自の求人サイトを運営する例が増えています。青森県八戸市では「無料職業紹介所」のほか、UIJターン就職希望者向けに移住支援金の上乗せを行い、実績を伸ばしています。
(2) 起業・スタートアップ支援
移住を機に起業を考える人向けに、コワーキングスペースの無料利用や家賃補助、創業資金の助成を行う自治体も見られます。島根県海士町のように、「移住者向け創業塾」と「ふるさと納税を活用した資金調達」を組み合わせて支援する事例も注目され、若い起業家が次々と島へ渡り、観光や水産加工など新たなビジネスを展開しています。
移住・定住施策が抱える主な課題
周知不足とターゲット設定の難しさ
(1) 広報・PRの限界
せっかく手厚い移住支援を用意していても、全国的に情報量が膨大なため、各自治体の施策が埋もれてしまう問題があります。また、観光PRとの区別が曖昧だと「観光には行ってみたいが、移住まではイメージできない」というギャップが発生します。より具体的な移住者インタビューや、移住後の仕事・暮らし事例を届ける工夫が必要です。
課題事例:Webサイトへのアクセスが伸び悩む
多くの自治体が「移住ポータルサイト」「SNSアカウント」を立ち上げているものの、検索上位に表示されず、都市部在住者の目に留まりにくい。検索エンジン最適化(SEO)やSNS広告などマーケティング手法を活用しきれていない自治体が多いとの指摘があります。
移住後のコミュニティ受け入れ
(1) 地域住民との摩擦
「移住者ばかり優遇されて、既存住民が損している」という不満や、「よそ者が入ってきても地域行事に非協力的」といった相互不信が課題となるケースも。移住担当課やNPOが橋渡し役となり、移住者と地元住民を交流させる懇親会やイベントを開催して関係性を深める取り組みが不可欠です。
成功事例:新潟県佐渡市「さど暮らしサポーター」
佐渡市では、移住者のサポートを担う「さど暮らしサポーター」という制度を設け、移住希望者や転入者が日常的に相談できる先輩移住者を登録。これにより移住者同士のコミュニティ形成も進み、地元住民との接点を作る機会も増えた結果、定着率が向上しています。
仕事・収入面の安定不足
地方には「雇用先が少ない」「賃金水準が低い」などの問題も残ります。一次産業以外の選択肢が乏しい地域もあり、転職しづらいという課題が顕著です。また、テレワークで稼ぐ人を歓迎する自治体が増えつつも、通信環境の整備や職種によっては難しい場面もあります。
課題事例:新規就農の壁
就農希望者は増えている一方で、「長期研修期間と初期投資」「営農技術習得の難しさ」を乗り越えられず、途中で断念して都会へ戻るケースがある。自治体が就農支援金を用意しても、指導体制や経営ノウハウサポートが十分でない場合、定着は難しいのが実情です。
財源・人材不足と施策の継続性
移住施策を充実させるためには、空き家バンクの運営や改修補助、新たな産業振興など多数の業務が発生しますが、人口の少ない自治体ほど財源不足・人手不足が深刻です。外部資金(企業版ふるさと納税など)を活用する動きもあるものの、受け入れのノウハウが追いついていないケースも。また、国の交付金に頼り切りだと期限切れ後に事業が終了し、移住希望者が継続的に支援を受けられなくなるリスクがあります。
関係人口をどう定住につなげるか
ワーケーションや二拠点居住をきっかけに「ゆるやかに地域と関わる層=関係人口」が増えている一方、そこからさらに「定住」へステップアップするための仕掛けが不足しがち。季節イベントや地元のコミュニティ活動に関わってもらい、滞在頻度を上げることで定住を後押しする取り組みが求められますが、成功事例はまだ限定的です。
各自治体の成功事例と今後の展望
最後に、各地で実績を上げている成功事例を紹介しながら、今後の移住・定住施策がどう発展していくかを考察します。
成功事例ピックアップ
- 北海道上士幌町:子育て支援を軸に転入増
- こども園の保育料無料化・医療費高校生まで完全無償化など手厚い子育て支援を実施。ふるさと納税を活用した財源確保に成功し、移住者支援を継続的に行える環境を整えた。
- 生活体験住宅(お試し移住)の稼働率は常に高く、実際に1ヶ月〜1年程度の体験を経たファミリー層が移住・定住に至るケースが増加。2023年は転入超過人数が目標の3倍を上回ったと報告されている。
- 島根県海士町:関係人口から起業・定住へ
- 「ないものはない」のキャッチフレーズで挑戦を歓迎するブランドイメージを作り、教育(高校魅力化)や起業支援(ふるさと納税を活用)に注力。単なる“観光”や“短期滞在”から長期的にかかわる関係人口を増やし、実際に定住・起業に至る若者が増えている。
- 「大人の島留学」など滞在型プログラムで実際の島暮らしを経験できるようにし、気に入った人が島に家を借りる・建てる流れを整備したことで若年層の移住促進につながった。
- 石川県かほく市:住環境・子育て環境の魅力を徹底PR
- 金沢市中心部から車で20分という地の利を活かし、「住むならかほく」とアピール。市独自の子育て施策(保育料一部無償化、出産祝い金、給食費支援など)を強化し、企業誘致も同時に推進。結果として転入が転出を上回る好循環を実現。
- YoutubeやInstagramで「妻の機嫌がいい編」というPR動画を制作し、“家族が暮らしやすい町”をユーモラスに発信して話題化に成功。移住フェアでもパンフレット配布だけでなく映像を見せて興味を引く手法が高く評価されている。
今後の展望と取り組みの方向性
- デジタル技術の活用
オンライン相談・VR内見・移住フェアのバーチャル開催など、コロナ以降高まったデジタルニーズに対応し、若年層にアピールする動きが拡大する見通し。自治体DX推進とのシナジーも期待されます。 - 企業誘致×起業支援の連携強化
地域に安定した雇用や活気ある経済がないと、移住希望者の不安は拭えません。IT・製造業など幅広い産業を誘致し、移住者が仕事を得やすい環境づくりを加速させる自治体が増えています。また、スタートアップエコシステム構築やインキュベーション施設の整備で、外部人材が起業しやすい土壌を整える動きも注目されます。 - 住民自治やコミュニティ形成への配慮
移住者向けの補助金や制度だけでなく、既存住民を含めたコミュニティ運営をどう円滑にするかが次の課題です。移住者が地域に溶け込みやすいよう、自治会への加入促進策や「移住・定住応援団」といった草の根組織を育成する事例が増えるでしょう。 - 若者・子育て世帯への特化と多世代の移住
子育て世帯の移住は地域の将来に直結するため、引き続き優遇策が拡充される見込みです。一方、近年はシニア世代やリタイア後のセカンドライフとしての地方移住も根強い人気があり、幅広い世代をバランスよく受け入れる仕組みも必要となっています。 - 関係人口からの定住ステップアップ支援
ワーケーションや週末移住を契機に、最終的には住民票を移してもらう流れをどう作るかが鍵になります。具体的には「家賃助成」「二拠点居住者向け税制優遇」「農業・DIY体験プログラム」などをセット化し、関わりを深める施策がさらに充実していくと考えられます。
おわりに
自治体における移住・定住施策は、人口減少や高齢化、東京圏への過度な集中といった日本社会が抱える問題への重要な解決策として注目されています。実際に、各地の成功事例を見ると、(1)情報発信と相談体制の充実、(2)住まい・仕事・子育て環境の手厚いサポート、(3)地元住民との共生・コミュニティデザイン が鍵を握っていることが分かります。
一方で、財源や人材の不足、施策の継続性・周知不足など多様な課題も浮き彫りです。今後はデジタル活用や関係人口の段階的な定住促進など、従来の枠を超えた新たなアプローチが求められるでしょう。移住検討者は、国や自治体が提供する制度を賢く活用しつつ、自分に合った地域やライフスタイルを模索し、安心して新天地に根付けるよう情報収集をすすめることが大切です。
参考・引用元
- (※1)一般社団法人自治体DX推進協議会「自治体における移住・定住施策の現状と課題」(2025年3月5日 公開)
- (※2)内閣官房・内閣府「地方創生ポータルサイト」
- (※3)JOIN(一般社団法人移住・交流推進機構)関連資料
- 総務省「『地方への人の流れの創出』に向けた効果的移住定住推進施策 事例集」
- 各自治体公式サイトにおける事例(北海道上士幌町、石川県かほく市、島根県海士町、宮城県七ヶ宿町、新潟県佐渡市 等)
本記事が、移住・定住施策について詳しく知りたい方や、実際に地方への移住を検討される方への一助となれば幸いです。