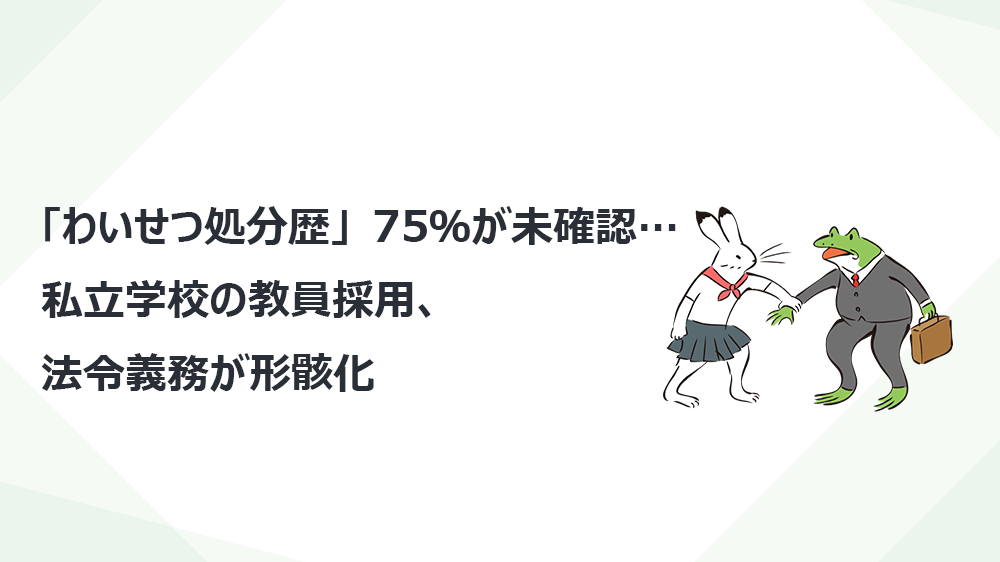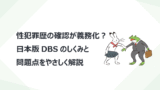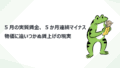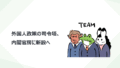2023年度から本格運用が始まった「教員わいせつ処分歴データベース」。これは、過去に児童・生徒に対してわいせつ行為などで懲戒処分を受けた教員が、再び教育現場に戻ることを防ぐための仕組みだ。
ところが、文部科学省が2024年に実施した調査で、全国の私立幼稚園・小中高校を運営する学校法人のうち、約75%にあたる5480法人が、このDBを教員採用時に確認していなかったことが明らかになった。
これは、教員による児童生徒性暴力防止法に違反する行為である。法律ではDBでのチェックを明確に義務付けているにもかかわらず、その運用が現場で徹底されていないという現実が浮かび上がった。
利用状況の内訳
以下の表は、私立学校法人によるDB利用状況の概要を示している。
| 区分 | 法人数 | 割合 |
|---|---|---|
| DBを登録していない | 3,062法人 | 約42% |
| DBを登録したが活用していない | 2,418法人 | 約33% |
| DBを活用している | 約1,780法人 | 約25% |
| 合計(回答数) | 7,258法人 | 100% |
出典:文部科学省 私立学校法人への調査(2023年度)
私学のうち4分の3がDBを使っていないという事実は、制度設計と周知、運用の間に大きな断絶があることを示している。特に「義務だと知らなかった」「教員免許の有効性を確認するシステムと誤認していた」など、制度の理解不足が原因として挙げられている。
なぜ見逃されていたのか?
実際にDBを活用しなかった学校法人の主な理由には、次のようなものがあった。
- 「義務化されていることを知らなかった」
- 「免許更新制度の確認DBと勘違いしていた」
- 「手続きや照会の方法がわかりづらい」
- 「採用時に照会するタイミングを逃した」
特に注目すべきは、「知らなかった」という理由が多数を占めている点だ。つまり、法律が存在しても、現場が把握していなければ意味がないのである。
公立学校との対比
公立学校では、すべての教育委員会がDBの利用登録を済ませているとされている。ただし、文部科学省は「すべての採用の場面でDBが活用されているかは把握していない」としており、形式的な登録にとどまっている可能性もある。
なぜ確認されていないのか?
私立学校法人の75%が、教員の採用時に国の「わいせつ処分歴データベース(DB)」を確認していなかったという事実は、単なる手続きミスでは片づけられない。これは子どもたちの安全を守る制度が、法的義務であるにもかかわらず形骸化している証左ともいえる。
「義務であることを知らなかった」
文部科学省の調査によると、DBを利用していない法人の多くが「チェックが義務であることをそもそも知らなかった」と回答している。この認識不足は、以下の2点が原因とされる。
- 法改正に対する現場周知の不足
- 通知文書や説明会の不徹底
たとえば、文科省は2024年3月に各都道府県や政令市に対して、私学にDBの活用徹底を求める通知を出しているが、その後も対応が進まなかった学校法人が多い。教育現場では「人手が足りず通知まで目が届かなかった」「毎年の制度変更に追いつけない」という声も少なくない。
「別の制度と勘違い」
DBを「教員免許の有効性確認システム」と勘違いしていたという学校法人も多かった。たしかに、教員に関する制度は複雑で、似た名称の仕組みも多い。
以下に、混同されがちな制度の違いをまとめておく。
| 制度名 | 内容 | 管轄 |
|---|---|---|
| 教員免許状更新講習制度(※2022年廃止) | 免許の有効性を保つための講習 | 文科省 |
| 教員免許状有効性確認システム | 教員免許が有効かどうかを確認 | 文科省 |
| 教員わいせつ処分歴DB | わいせつ処分歴の有無を照会 | 文科省 |
| 日本版DBS(2026年導入予定) | 子どもと接する職業全般の性犯罪歴照会 | こども家庭庁/法務省 |
このように、「免許確認」と「わいせつ歴照会」は制度の目的も対象も異なる。混同は防げたはずであり、教育現場の情報リテラシー向上が課題といえる。
文科省の対応と課題
文部科学省は以下のような対応を取っている。
- 2024年3月:都道府県・政令市を通じて私学への通知を発出
- 活用促進のための周知パンフレットを配布
- 対象法人のヒアリング調査の実施
しかし、調査結果を見るかぎり、通知を受けたにもかかわらず「DBを知らなかった」という法人が一定数存在することから、通知だけでは不十分であることが分かる。文科省にはより強制力のある対策や、未確認法人の公表といった「次の一手」が求められている。
データベースは何を目的とするか?
児童生徒への性暴力やわいせつ行為を防ぐために整備された「教員わいせつ処分歴データベース」は、2021年5月に成立した「教員による児童生徒性暴力等防止法」(正式名称:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律)に基づいて行われている。
この法律の主な目的は、児童生徒にわいせつ行為などで懲戒処分された教員が、別の学校で再び子どもと関わることを未然に防ぐことにある。具体的には以下のような仕組みだ。
主なポイント
- 対象者:懲戒免職・失効処分となった元教員
- DB登録情報:氏名・生年月日・処分内容・処分日など
- 利用者:公立=教育委員会、私立=学校法人
- 利用目的:教員採用時に当該人物の照会
このデータベースは「内部利用のみ」を前提としており、一般には公開されていない。つまり、子どもを守るために、採用を決める側が“裏で”確認するための制度である。
DB確認の義務化とその背景
法整備の背景には、過去にわいせつ行為で処分を受けた教員が他県や別の学校に再就職し、再び性加害に及んだ事例が複数あったことがある。こうした再発を防ぐために、2021年の法改正では次のような措置が盛り込まれた。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| データベースの設置 | わいせつ処分歴の一元管理 |
| 採用前のDB照会の義務化 | 公私問わず、採用前に確認必須 |
| 教員免許再交付の厳格化 | 再取得の審査を厳格に実施 |
つまり、単なる「再犯防止」だけでなく、「教職への信頼性の担保」という教育現場全体の健全化を目的として制度が整えられた。
日本版DBSの導入
この教員向けの制度に加えて、政府は2026年末から「日本版DBS(Disclosure and Barring System)」の導入を予定している。これは、学校以外の子どもに接する業種(学童保育、習い事教室、こども食堂など)でも性犯罪歴を照会できる制度で、こども家庭庁と法務省が主導する。
| 名称 | 日本版DBS |
|---|---|
| 開始予定 | 2026年末 |
| 対象 | 学校以外の子ども接触職業(例:学童、塾など) |
| 管轄 | こども家庭庁・法務省 |
| 照会方法 | 雇用主が照会し、性犯罪歴の有無を確認 |
これは英国のDBS制度を参考にしており、対象業種は今後拡大していく可能性もある。
つまり、教員DBは「今の職場」で子どもを守る第一の防波堤であり、日本版DBSは「学校以外」も含めた第二の防波堤となる。制度は着々と整いつつあるが、最大の課題はやはり“実際に活用されているかどうか”である。
わいせつ行為の現実──数字が示す深刻さ
文部科学省が2023年度に実施した教員の懲戒処分等に関する調査結果(2024年6月公表)を見ると、児童・生徒への性暴力の実態は深刻で、決して一部の例外ではないことがわかる。数字が示す現場の現実は、DB活用の必要性を強く裏付けている。
懲戒処分を受けた教員の実態
調査によると、性犯罪・性暴力などにより懲戒処分を受けた教員は、令和5年度だけで320人に上った。そのうち、児童生徒への性暴力(以下、児童生徒性暴力等)に該当するのは157人で、全体の約5割に相当する…。
被処分者の年齢別構成(全体320人中)
| 年代 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20代 | 105人 | 32.8% |
| 30代 | 86人 | 26.9% |
| 40代 | 51人 | 15.9% |
| 50代以上 | 78人 | 24.4% |
20〜30代の若年層が半数以上を占めており、将来のある若い教員が重大な非行に及ぶケースが多い。
学校種別での発生状況
| 学校種 | 被処分者数 | 在職者に対する割合 |
|---|---|---|
| 中学校 | 111人 | 0.05% |
| 高等学校 | 100人 | 0.06% |
| 小学校 | 85人 | 0.02% |
| 特別支援学校 | 22人 | 0.02% |
中学・高校での発生が顕著で、思春期の生徒と日常的に接する環境がリスク要因となっていると考えられる。
加害教員が対象とした相手の内訳を見ると、特に深刻な傾向が読み取れる。
| 被害者の属性 | 割合 |
|---|---|
| 自校の児童・生徒(18歳未満含む) | 54.1% |
| 他校の児童・生徒 | 8.8% |
| 教職員(自校・他校) | 16.5% |
| その他・未分類 | 13.4% |
つまり、半数以上が「自分が日常的に教えている子どもたち」に対して行為に及んでいたのである…。これは単なる“教員の不祥事”ではなく、教育という信頼関係に基づく場を悪用した“裏切り”である。
わいせつ行為は発覚しにくい犯罪とされるが、今回の調査では以下のようなルートで判明していた。
| 発覚の要因 | 割合 |
|---|---|
| 教職員等への相談 | 40.7% |
| 警察からの連絡 | 19.7% |
| 被害者自身の申告 | 14.6% |
| その他 | 23.6% |
つまり、子ども本人や保護者が声を上げて初めて明るみに出るケースが多い。それでも氷山の一角にすぎない可能性がある。
数は多くないが、絶対に見逃してはならない
令和5年度に児童生徒への性暴力で処分された教員は157人。日本全国の教員数と比べれば、割合としては0.02〜0.03%にすぎない。
しかし、たった一人でもその行為が重大であり、影響は計り知れない。しかも、その人物が別の学校に再就職し、再犯に及んでしまうような状況があってはならない。
この数字こそが、採用時にDBを照会することの必要性を如実に物語っている。
発覚のきっかけと捜査の現状
教員による児童生徒への性暴力は、しばしば「密室で起こる」「発覚しにくい」犯罪と言われている。だからこそ、その発覚のきっかけや、その後の捜査対応には大きな注目が集まる。文部科学省の2023年度調査は、子どもたちがどのように助けを求め、学校や社会がどう対応してきたかを映し出している。
発覚のきっかけは子どもや保護者からの相談が最多
児童生徒性暴力の157件について、発覚の要因を分類した結果が以下の表だ。
| 発覚の要因 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 教職員等への相談(ア~ウ合算) | 64件 | 40.7% |
| 警察からの連絡 | 31件 | 19.7% |
| 加害者本人からの申告 | 14件 | 8.9% |
| 教職員の現場目撃 | 2件 | 1.3% |
| 学校アンケートで判明 | 0件 | 0.0% |
| その他 | 37件 | 23.6% |
教職員への相談が最も多いという結果は、子どもや保護者が学校内の信頼できる大人に助けを求めている証拠でもある。ただし、アンケートなどの「学校主導の能動的発見」が0件というのは注目すべき課題だ。これは予防のためのシステムが機能していないことを意味する。
発覚した事件のうち、実際に刑事手続きが取られたケースはどのくらいあるのか。調査では以下のような結果が出ている。
| 捜査対応の有無 | 件数(157件中) | 割合 |
|---|---|---|
| 捜査機関が把握・告発された | 87件 | 55.4% |
| 告発されなかった理由がある | 70件 | 44.6% |
告発されなかったケースの内訳は以下のとおりである。
- 犯罪に当たらないと判断:37件
- 被害者や保護者が告発を望まず:11件
- その他の事情:22件
つまり、約4割以上が刑事事件になっていない。これは被害者や保護者の心情への配慮や、証拠の不十分さ、教員との関係性など複雑な事情が背景にあると考えられる。
多くの専門家が指摘するのは、「子どもたちが声を上げられない」構造的な問題だ。特に教員という立場にある大人に対して、児童や生徒が不快感や恐怖を言葉にして訴えることは簡単ではない。さらに、家庭や学校が「問題にしたくない」という空気を作り出してしまうと、加害者はその“沈黙”に甘えて再犯に及ぶ。
以下は、告発されなかった一部の典型的な背景である。
- 「被害者が萎縮して親に話せなかった」
- 「保護者が“騒ぎを大きくしたくない”と希望」
- 「証拠がなく立証が困難と判断された」
これは、制度的には“告発されていない”が、実態としては“見過ごされた”とも言える。
事件と処分の間にある“空白期間”
調査とは別に、過去の報道では「事件発生から懲戒処分までに長期間が空いた」「処分後も再就職先で再犯した」などのケースも報告されている。
この“空白期間”をどう埋めるかが、今後の制度運用にとって鍵となる。
- 採用前のDB照会は義務
- しかし「どの時点で」「どこまでの情報を」チェックすべきか、基準の明確化が求められる
専門家の見解と今後の課題
児童・生徒への性加害を未然に防ぐために整備されたデータベース制度。しかし実際には、私学の多くがその存在すら知らず、現場での運用もままならない。こうした実態に対して、法制度や教育行政に詳しい専門家からは厳しい指摘が相次いでいる。
「義務を知らない」は通らない
淑徳大学の坂田仰教授(教育制度論)は、次のようにコメントしている。
「私立学校に法令順守を指導できる人材が、自治体には不足している。国は、DB確認を怠った学校法人の名前を公表するなど、対応を促す強い仕組みを作るべきだ」
この見解は、「知らなかった」「勘違いしていた」といった説明では、児童生徒の安全を守れないという強い警鐘だ。教員採用という教育の根幹をなす場面において、最低限の法令確認が行われない状況は、組織の責任といえる。
一方、学校現場からは以下のような課題も挙げられている。
- 「制度が複雑で、どこに問い合わせていいか分からない」
- 「採用業務を事務員1人が担っており、照会まで手が回らない」
- 「個人情報を扱うので、確認に慎重にならざるを得ない」
これらは制度運用における「現場負担」の声であり、制度と現場との間にある“理解のズレ”を浮き彫りにしている。
今後の課題
制度を形骸化させないためには、以下のような施策が今後求められる。
1. 学校法人に対する義務周知と研修の強化
都道府県や政令市を通じた文科省の「通知」だけでは不十分である。オンライン研修や実務マニュアルの配布など、より踏み込んだサポートが必要だ。
2. 利用状況の公開と第三者監査の導入
どの学校法人がDBを活用しているか、年次報告として国が一覧で公開する仕組みを整えるべきだ。社会的プレッシャーが制度遵守を後押しする。
3. 「日本版DBS」との制度接続の検討
2026年に予定されている「日本版DBS」は、学校外の子ども関連職に広がる性犯罪歴確認制度。教員DBと連携し、より包括的な「子どもを守る枠組み」として整備することが期待される。
子どもを守るために必要なのは「制度」ではなく「姿勢」
防犯アドバイザーの京師美佳氏は、今回の調査結果に対してこうコメントしている。
「義務だからやるのではなく、まずは子どもたちを守るという気持ちで必ず実行してほしい。犯罪を犯した教員が現場に戻ることは絶対にあってはならない」
これは制度を「こなす」意識ではなく、制度の「目的」を理解して実行する姿勢の重要性を語っている。まさに、形式的な手続きでは子どもを守れないという現実に、我々は向き合う必要がある。
制度はある、しかし使われなければ意味がない
文部科学省が整備した「教員わいせつ処分歴データベース(DB)」は、わいせつ行為で懲戒免職・失効処分となった教員の再就職を防ぐための、きわめて重要な制度である。
しかし、実際には私立学校法人の4分の3がこの制度を採用時に活用しておらず、「知らなかった」「別の制度と勘違いした」などの理由で、運用がなされていない現状がある。これは明確な法令違反であり、制度が正しく運用されなければ、いくら整備されていても子どもたちは守られない。
法律は「盾」になっていない
制度は整った。ルールもある。けれども、それを「使うべき人」が使っていなければ、子どもにとっては何の意味もない。
これは、鍵のかかった扉があっても、鍵を使わずに開け放っているのと同じだ。教員採用という重要な局面において、「確認を怠った」という言い訳が通用するはずがない。
数字が示す現実──“一部の例外”では済まない
- わいせつなどで懲戒処分された教員は令和5年度に320人
- そのうち児童生徒への性暴力が157人(約半数)
- 被害者の半数以上が「自校の生徒」
- 発覚の40%超が、児童や保護者からの“直接の訴え”
つまり、現実に教員による性加害は発生しており、その防止にはDB照会が欠かせない。
制度はあくまでツールである。大切なのは、それを運用する大人たちの姿勢と責任感だ。学校法人や教育委員会が「子どもたちを加害から守る」という本質的な目的を忘れず、形式的な対応にとどまらない「実行」を選ぶことが求められる。
日本版DBSに向けて
2026年から始まる「日本版DBS」では、教員に限らず、塾や学童保育、こども食堂など、子どもに接する多くの職種が性犯罪歴の確認対象になる予定だ。これは、子どもを守る視点が学校内から社会全体へと広がっていくことを意味している。
その第一歩として、いま目の前にある制度──教員DB──を、まずは100%活用すること。それが社会全体に「本気で守る姿勢」を示す最も明確なメッセージとなるだろう。
守るべきは制度ではなく、子どもの未来
教員DBは、制度としてはすでに完成している。あとは、使うだけだ。
子どもの声を信じ、声なき不安に気づき、そして守ること。
それが、教育に携わるすべての人に求められる最低限の姿勢である。