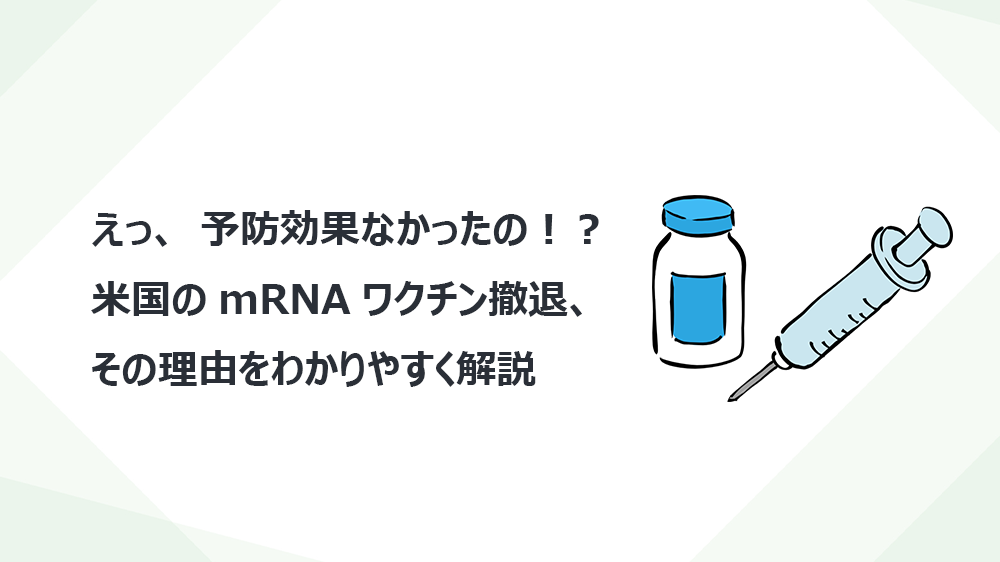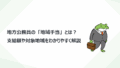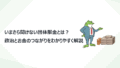新型コロナ対策の“切り札”として脚光を浴びたmRNAワクチン。しかし、2025年8月、米国政府が「予防効果が限定的」との判断から、約500億円規模にのぼるmRNAワクチン関連事業の支援を段階的に終了すると発表しました。この突然の方針転換の背景には、どんな事情があるのでしょうか?
この記事では、「なぜ米国がmRNAワクチンから撤退するのか?」という疑問に対して、わかりやすく解説します。
mRNAワクチンとは?いまさら聞けない基礎知識
mRNAワクチンとは、ウイルスの「設計図」を一部だけ取り出して、それを体内に送り込むことで免疫をつけるタイプのワクチンです。新型コロナウイルス(COVID-19)の流行で世界中に知られるようになりましたが、まだしくみをよく知らない人も多いかもしれません。
まず、「mRNA」とは「メッセンジャーRNA(リボ核酸)」の略で、細胞がタンパク質を作るための“命令書”のようなものです。mRNAワクチンでは、このmRNAを人工的に合成して注射することで、体内の細胞が一時的にウイルスの「スパイクタンパク質(無害な部分)」を作ります。すると体はそれを異物だと認識して、「抗体」や「免疫記憶」を作り、実際のウイルスが体に入ってきたときに素早く攻撃できるよう備えるのです。
この仕組みには、いくつかの大きなメリットがあります。
- ウイルスそのものを使わないため、安全性が高いとされる
- 設計から量産までが早く、新たな変異にも柔軟に対応できる
- これまで難しかったウイルスにも応用が期待されている(がん・エイズなど)
新型コロナが広がるなかで、米ファイザー社と独ビオンテック社が共同開発したmRNAワクチン、さらに米モデルナ社のワクチンが世界中で使用され、多くの命を救ったとされています。日本でも多くの人がこれらのワクチンを接種しました。
ただし、万能というわけではありません。変異株への対応が追いつかないことや、時間とともに効果が弱まること、冷凍保存が必要な点など、課題も少なくありません。今回の「撤退」発表には、こうした技術的な限界が関係している可能性もあるのです。
米国が進めてきたmRNAワクチン投資のこれまで
アメリカは新型コロナウイルスが世界的に流行しはじめた2020年当初から、mRNAワクチンの開発を国家戦略の中心に据えてきました。その中心的役割を担ったのが、米保健福祉省(HHS)傘下の機関「BARDA(生物医学先端研究開発局)」です。
BARDAは、公衆衛生上の緊急事態に対応するための医薬品やワクチンの開発を支援する機関で、新型コロナ対策としてワクチン開発企業に数十億ドル(日本円で数千億円規模)の資金を投じました。その象徴が「オペレーション・ワープスピード」と呼ばれる政策です。
これは、ワクチン開発を最速で進めるために政府が製薬会社に資金援助を行い、開発・製造・流通の各段階を通常よりも大幅に短縮して進めるというもの。mRNA技術を使ったファイザーやモデルナは、この支援によって短期間でワクチンを実用化し、世界中での接種が実現しました。
新型コロナだけでなく、アメリカ政府はその後もmRNA技術を活用した次世代ワクチンへの投資を進めていました。たとえば鳥インフルエンザ(H5N1)に備えるmRNAワクチンの研究にも巨額の予算を投入。2024年にはモデルナに対して約5億9,000万ドル(約870億円)規模の契約を結び、新たな感染症への備えを加速させていたのです。
このように、mRNAワクチンは「パンデミック対策の柱」として、米国の公衆衛生政策の中核を占めていました。それだけに、今回の「突然の方針転換」は多くの人々にとって驚きだったと言えます。
なぜ「予防効果なし」と判断されたのか?
2025年8月、米国保健福祉省(HHS)は、mRNAワクチン関連の契約22件を段階的に終了する方針を発表しました。これは、ワクチン開発を支援する政府機関BARDAを通じて実施されてきた、総額約5億ドル(約780億円)規模のプロジェクトを取りやめるという、非常に大きな政策転換です。
この決定の背景には、「予防効果が限定的である」という評価があります。とくに、HHSの長官であり、大統領候補としても注目されているロバート・F・ケネディ・ジュニア氏は、mRNAワクチンに対してかねてより慎重な立場を取っていました。
ケネディ長官は、mRNAワクチンについて「COVID-19のような上気道感染症に対して、期待されたほどの感染予防効果が得られていない」と明言しました。実際、新型コロナにおけるmRNAワクチンは、重症化や死亡のリスクを大きく下げることには成功したものの、ウイルスそのものの感染拡大を完全に防ぐことはできませんでした。
特に、オミクロン株以降の変異株に対しては、ワクチンを打っていても感染する「ブレイクスルー感染」が頻発しました。これにより、mRNAワクチンの感染予防力に対する信頼は一部で揺らぎ始めていたのです。
また、米国ではワクチン接種率の伸び悩みも課題となっており、追加接種(ブースター)の需要が大きく減少しています。巨額の公的資金を投じているにもかかわらず、国民の関心が薄れているという現状も、政府としては再考の理由のひとつとなりました。
さらに、冷蔵・冷凍保存など流通の手間や、変異株に合わせた頻繁な改良の必要性といった技術面の限界も無視できません。
こうした要素が積み重なり、米政府は「mRNAワクチンは上気道感染症に対する予防策としては限定的」との結論に至ったと考えられます。そしてその結果、投資の継続を見送る決定が下されたのです。
具体的に何が中止されたの?
今回、米国保健福祉省(HHS)が発表したmRNAワクチン関連の「契約終了」には、非常に具体的な内容があります。対象となったのは、BARDA(生物医学先端研究開発局)を通じて締結された22件のプロジェクト契約。その総額は約5億ドル(日本円でおよそ780億円)にのぼります。
中止の対象となった企業には、世界的に知られる大手製薬会社が含まれています。
- モデルナ(Moderna)
- ファイザー(Pfizer)
- サノフィ・パスツール(Sanofi Pasteur)
- CSLセキルス(CSL Seqirus)
- グリットストーン・バイオ(Gritstone Bio) など
たとえば、モデルナはH5N1型の鳥インフルエンザに備えるmRNAワクチンの開発契約を米政府と結んでおり、2024年には約5.9億ドルの資金提供が行われていました。しかし、今回の方針転換により、研究資金の交付契約そのものが無効とされ、将来の購入に関する取り決めも白紙に戻されることとなりました。
これにより、多くの企業が進めていた「次世代ワクチン」の研究計画が一時停止、または中断を余儀なくされることになります。なかには、すでに実験段階まで進んでいたプロジェクトも含まれており、製薬業界へのインパクトは大きいと見られています。
一方で、HHSはすべてのmRNAプロジェクトを完全に打ち切るわけではなく、すでに終了間近の研究や、特定の成果が見込まれるプロジェクトについては「例外的に」継続を認める方針も示しています。
つまり、今回の決定は「全面的な技術否定」ではなく、「政府主導での資金投入は止める」という方向転換です。これは今後、企業の側にとっては、政府支援のない自力開発を迫られるという大きな意味を持つことになります。
専門家はどう見ている?
米国政府が突如としてmRNAワクチン開発支援を中止すると発表した今回の決定に対し、医療・科学分野の専門家からはさまざまな反応が寄せられています。なかには、この動きを「科学的ではなく、政治的判断だ」とする声も少なくありません。
たとえば、米ジョンズ・ホプキンス大学のウイルス学教授、アンドリュー・ペコズ氏は「mRNA技術は今なお進化の途中であり、今回のような一律の資金打ち切りは、今後のパンデミック対策能力を削ぐことになりかねない」と警鐘を鳴らしています。
また、BARDAの元局長であるリック・ブライト氏も、「この決定は、国家のバイオセキュリティにとって深刻な戦略的誤りだ」と強く批判。ワクチン開発における多様性と柔軟性を維持することの重要性を訴えました。
さらに、ミネソタ大学感染症研究センターのマイケル・オスターホルム教授は、「mRNAは、迅速に対応が求められる感染症対策において極めて有効な技術だ。予防効果の議論だけで見切るべきではない」と述べています。
このように、専門家の多くは今回の方針転換に対して懐疑的であり、特に「mRNAワクチンは重症化を防ぐうえでは有効だった」という事実を軽視すべきではないとの声が強く上がっています。
一方で、「現時点での感染症対策としてはmRNAに過度に依存すべきではない」「新たなプラットフォームにも目を向けるべき」といった慎重派の意見もあります。これまでの投資が成果を十分に出せていないという点では、政府の見直しも一定の理解を得ている面もあります。
つまり、今回の決定は賛否が大きく分かれるものであり、「科学の視点」と「政策判断」とのズレが今後の焦点になっていくでしょう。
mRNAの未来はどうなる?
米国政府が公的資金によるmRNAワクチン開発支援を打ち切ると発表したことは、大きな衝撃を与えましたが、だからといってmRNA技術そのものの終わりを意味するわけではありません。むしろ、これからが「mRNAの本当の勝負どころ」とも言えます。
まず、医療の世界では、mRNA技術は新型コロナ以外にもさまざまな疾患への応用が期待されています。たとえば、がんワクチンや難病、個別化医療(患者ごとに最適な治療を施す方法)などです。実際、モデルナやバイオンテックなどは、新型コロナワクチンで得たノウハウを活かして、がん免疫療法のmRNAワクチン開発に注力しています。
また、米国以外の国々では、mRNAワクチンや治療薬への研究投資は依然として続いています。たとえばEU(欧州連合)や中国、韓国などでは、国策としてmRNA製造拠点の整備や研究支援が進められています。つまり、「米国が手を引いたからといって、世界全体が後退するわけではない」のです。
一方で、mRNA技術の課題も依然として存在します。たとえば、
- 長期的な安全性や副反応への評価が完全に定まっていない
- 冷凍・冷蔵保存など流通インフラへの依存度が高い
- 感染予防より重症化予防に強みがあり、用途が限定されやすい
こうした制約があるなか、今後の研究・開発は「どの分野にどう活かすか」の選択と集中が必要になってきます。
今回の米国の動きは、「コロナ対策としてのmRNA」に一つの区切りをつけただけであり、技術としてのmRNA自体はまだ多くの可能性を秘めています。今後は、政府主導の大量投資ではなく、民間や国際的な連携によって、より応用的かつ持続可能な形で研究が進むとみられています。
つまり、「撤退=終わり」ではなく、「新たなステージへの転換」と捉えるべきなのかもしれません。
撤退は「終わり」ではなく「転換」かも
今回の米国政府によるmRNAワクチンへの支援中止は、多くの人にとって衝撃的なニュースでした。「予防効果が十分でなかった」との理由で、巨額の投資がストップされ、主要製薬会社との契約が次々に終了へ向かう——こうした動きは、新型コロナ禍を経て私たちが信じてきた「科学の進歩」への信頼にも、少なからぬ影響を与えたかもしれません。
しかし、この「撤退」は、決してmRNAワクチンそのものの失敗を意味するものではありません。
mRNAワクチンは、短期間での開発が可能で、重症化予防には大きな効果を発揮しました。確かに、上気道感染症のように感染自体を完全に防ぐという点では限界もありましたが、それでも多くの命を救ったのは事実です。
また、がん治療や次世代ワクチンなど、より広い医療分野でのmRNA技術の応用は、今まさに本格化しようとしています。米国が「COVID用の大量生産体制」から一歩引いたとしても、技術としてのmRNAは生きているのです。
重要なのは、「撤退」という言葉の印象に振り回されず、その背景にある判断や将来の展望を冷静に見ることです。感染症対策における技術選択は、政治・経済・医療のバランスの中で決まるものであり、常に最先端であるとは限りません。
今回の決定は、「終わり」ではなく「分岐点」と言えるでしょう。mRNAという革新技術が、コロナ対策という“非常時の役割”から、次の“日常医療”へのステージへ進もうとしている。その転換期に、私たちが何を学び、どう備えるのかが、今後の医療と社会に問われています。
参考情報
米厚生省、mRNAワクチン開発を段階的に終了へ(ロイター通信)
米国、mRNAワクチンへの投資中止 ケネディ長官「予防効果なし」(日本経済新聞)
Trump Administration to Wind Down mRNA Vaccine Development(TIME)
RFK Jr. announces end to some mRNA contracts, including for flu, covid(ワシントンポスト)