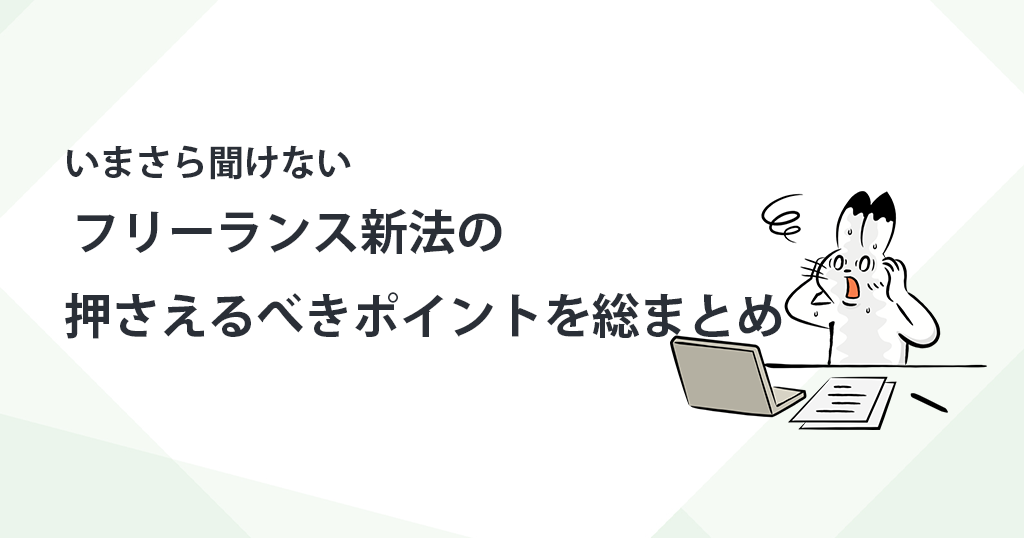背景と目的
近年、日本では会社に雇われる働き方だけではなく、自分のスキルを生かして個人事業主として働く「フリーランス」と呼ばれる働き方が注目されています。インターネットやSNSの発展、リモートワークの普及により、場所を選ばずに仕事を受けられる時代になったことが理由の一つです。また、副業ブームもあり、会社員が副業として業務委託契約(フリーランス的な働き方)をする事例も増えています。
ところが、フリーランスは個人であるがゆえに、会社組織と取引をするときに報酬が遅れてしまったり、契約の途中で急に仕事を打ち切られたり、また一方的にハラスメントを受けたりするなど、弱い立場に置かれがちです。もともと雇用関係を前提とする労働基準法などは、「労働者」と法的にみなされる人を保護するもの。しかし「事業者同士」の取引形態になっているフリーランスには適用されにくい面があり、不都合が生じていました。
こうした問題は、第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」で多くの相談として蓄積されてきました。相談内容の約3割近くが報酬に関するトラブルで、なかには交通事故時の罰金名目で報酬から控除されてしまう事例や、契約書自体が存在しないため紛争になっても証拠がないといった深刻なケースも多数報告されています。
フリーランス新法とは
こうした背景を受け、2023年4月28日に成立し、同年5月12日に公布された新しい法律が「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、いわゆる「フリーランス新法」です。この法律は「フリーランス」が安心して働ける環境を整えるために、主に以下2つの目的を掲げています。
- フリーランス(特定受託事業者)と発注事業者(特定業務委託事業者や業務委託事業者)の間の取引の適正化
- 具体的には、契約条件の書面・メール等による明示(取引条件の明確化)
- 報酬支払期日の設定義務、禁止行為(受領拒否・買いたたきなど)の明確化
- フリーランスの就業環境の整備
- ハラスメント防止
- 育児や介護と仕事を両立するための配慮
- 中途解除の場合の予告義務
施行は2024年11月1日からです。施行と同時に、この法律の運用にあわせて政令や省令、ガイドラインが公表される予定であり、具体的な細かいルールもそこに盛り込まれます。

法律名に「フリーランス」と書いていないのはなぜ?
法律の正式名称を見ると「フリーランス」という言葉が含まれていません。これは法律上の対象を正確に示すために、「特定受託事業者」「特定業務委託事業者」といった用語を使っているからです。
- 特定受託事業者:従業員を使用しない個人や、代表者以外に役員や従業員がいない法人(=実質、一人で事業をしている)
- 特定業務委託事業者:フリーランスに仕事を委託する事業者で、従業員を使用している個人・法人
フリーランスという表現はガイドラインなどの文書でも使われていますが、実際には「従業員の有無」を基準とした定義がかなり詳細に定められています。
フリーランス新法の対象範囲・適用取引
「業務委託」の定義
フリーランス新法で対象になるのは、事業者間(BtoB)の「業務委託」です。具体的には以下のように定義されています。
- 物品の製造または加工を行う委託
- プログラムやデザイン、文章など情報成果物の作成を行う委託
- 役務の提供を行う委託
ポイントは、売買や貸借、また一般消費者(BtoC)との取引は対象外という点です。中学生向けの例えでいえば、自分が絵を描いたり音楽を作ったりして、それを企業に納品してお金をもらう形が「業務委託」。一方で、友達同士で「プリントをコピーしてあげるからジュースおごって」というのは業務委託とはみなされません。
特定受託事業者
法律でいう「フリーランス」は「特定受託事業者」と呼ばれ、次の要件を満たす事業者です。
- 業務委託の相手方である事業者(受注者側)
- 従業員を使用しない(個人または代表者のみの法人)
さらに短時間アルバイトや、2週間だけ手伝ってもらうといった一時的雇用の場合は、従業員を使用しているとみなされないなど、細かい例外があります。詳しい基準は今後の政令・省令で明らかになる見込みです。
特定業務委託事業者と業務委託事業者
いっぽう、仕事を発注する側の事業者は、以下のように分かれます。
- 特定業務委託事業者:フリーランスに仕事を依頼し、かつ従業員を使用する事業者(比較的大きな企業など)
- 業務委託事業者:フリーランスに仕事を依頼する事業者だが、従業員を使用していない(つまり、フリーランス同士で外注する)
注意すべきなのは、法律による規制の内容(取引条件の明示義務や禁止行為など)によっては、特定業務委託事業者にだけ課されるものがあったり、業務委託事業者にも共通して課されるものがあったりする点です。
まとめ
フリーランス新法の対象がとても幅広い、という点は重要です。資本金や業種で絞るのではなく、あくまで「1人でやっている受注者」と「それに仕事を頼む発注者」の関係全般に及ぶ可能性があります。契約名称が「請負」「準委任」「業務委託」などバラバラであっても、実際の実態が物品の製造・作成や役務の提供であれば、新法の適用対象になり得ます。また、すべてのケースで法律が必ずしも適用されるわけではなく、例えば政令で定める期間以上の契約に限定される規定もある(後述)という点にも留意が必要です。
取引の適正化に関する主なポイント
取引条件の明示義務(法3条)
最も基本かつ重要なルールの一つが「契約条件を書面またはメールなどで明示しなければならない」というものです。とくに口頭だけで仕事を受けてしまうと、後から「約束した金額と違う」「納期があいまい」「業務内容がいつの間にか変わった」などの争いが起こりがちです。
明示すべき項目
具体的には、業務内容(給付の内容)、報酬の額、支払期日などが必須ですが、それ以外に「その他必要な項目」が政令で定められる予定です。下請法(下請代金支払遅延等防止法)でいう書面の交付義務に近い仕組みになる見込みです。ただし、フリーランス新法では、フリーランス同士の取引でも適用されるという特徴があります。
→ citeturn0file1
書面や電磁的記録の具体例
書面交付だけでなく、メールやPDF、クラウドサービス上のテキスト、SNSのメッセージ送信などを利用して「条件を明示する」ことでもOKになると想定されています。ただしLINEやSlackの場合、あとから削除されるリスクもあるため、スクリーンショットの保存など証拠を残す工夫が必要という指摘もあります。
報酬支払期日の設定と支払遅延の防止(法4条)
特定業務委託事業者がフリーランスへ仕事を発注する際、成果物を受け取ったら受領日から60日以内に期日を設定し、そしてその期日内にできる限り早くお金を支払う必要があります。再委託のケース(発注者からさらに下請けを出すような構造)では別ルールもあり、具体的には上位から支払いを受けた日から30日以内に支払うことが求められます。
なぜ60日以内なのか
企業がサプライヤーに支払うさいの下請法のルールとの整合性を考慮しつつ、フリーランスが必要以上に待たされないようにするためです。実際に「予算が足りなくなったら後回しにされる」「報酬サイトが長すぎて生活が苦しい」といったトラブルが多発しており、その改善策としてこの法律で60日以内の期日設定を義務化しています。
禁止行為(法5条)
フリーランスの立場を守るため、特定業務委託事業者から特定受託事業者に対して、以下の行為は禁止されます。ただし、ここは政令で定める一定期間以上の業務委託のみを対象とします。
- 正当な理由なく成果物を受け取らない(受領拒否)
- 正当な理由なく報酬を減額する
- 正当な理由なく返品を行う
- 通常より極端に低い報酬を不当に定める(いわゆる買いたたき)
- 正当な理由なく、発注事業者指定の商品や役務を買わせたり使わせたりする(購入・利用強制)
- フリーランス側に無償で追加の作業をさせるなどの「不当な経済上の利益の提供要請」
- 正当な理由なく、フリーランスにやり直しや変更を求める
一方的に契約を打ち切る行為(受領拒否等)は、とくに運送などの業務で報酬を得られないまま実費を負担させられてしまうトラブルを防ぐ狙いがあります。買いたたきは別名「不当に安く報酬を設定する行為」であり、下請法でも禁止されています。
まとめ
ここまでのポイントを踏まえると、フリーランス新法では「契約内容を明確にし、報酬は60日以内に設定し、かつ禁止行為があれば処分もあり得る」という規定になっています。ただし、すべてが無条件で当てはまるわけではなく、従業員を使う発注者かどうか、契約期間が政令で定める日数以上かどうかなど、細かい条件がある点に注意が必要です。
就業環境の整備に関するポイント
募集情報の的確表示義務(法12条)
クラウドソーシングサイトやSNSなどを使って不特定多数に「フリーランス募集」をかけるとき、発注者側は以下の2点を守らなければならなくなります。
- 虚偽の表示や誤解を招く表示をしない
- 募集情報を正確かつ最新の内容に保つ
「月収50万円確実!」「実績ゼロでも高額報酬!」といった誇大な募集広告を出して、実際はまったく条件が違う、といったケースがこれまで散見されていました。こうした募集段階での「釣り広告」を防ぐことで、フリーランスが誤った情報に振り回されることを防止します。
妊娠・出産・育児・介護との両立配慮(法13条)
特定業務委託事業者が一定期間以上の継続的な業務委託を行う場合、フリーランスから妊娠・出産・育児・介護などの申し出があれば、これらに配慮しなければなりません。たとえば「納期を若干延ばせないか」「打ち合わせの時間帯を夜にずらせないか」などです。短期間・単発の契約には努力義務として課されます。
フリーランス協会の調査によると、女性フリーランスの中には産後1カ月以内で復帰せざるを得ない人もおり、こうした育児や介護との両立に苦しむ事例が多々あります。新法によって、事前にちゃんと申し出れば柔軟な対応をしないといけないことになるのは大きな進歩です。
ハラスメント対策(法14条)
これまで会社員には「セクハラ」「マタハラ」「パワハラ」を防ぐ制度がある程度整備されてきましたが、フリーランスには必ずしも該当しませんでした。新法では、特定業務委託事業者に以下の措置が義務付けられます。
- ハラスメントを行わない方針を明確化し、社内周知・啓発すること
- フリーランスからハラスメントの相談があったときに、適切に対応する体制を整備すること
- 実際にハラスメントが起きた場合は、事後的に迅速な解決策を取ること
さらに、フリーランスがハラスメントを相談したことを理由に、契約不更新や報酬の減額などの不利益な扱いをするのも禁止されています。
中途解除時の予告義務(法16条)
一定期間(政令で定める期間)以上の継続的業務委託の場合、フリーランスにとってその発注者への依存度が高いとみなされます。このとき発注事業者が急に契約を打ち切ると、フリーランスは次の仕事を探す余裕がなく大変困ってしまいます。そこで、契約を中途解除する際や契約更新をしないときには、少なくとも30日前にフリーランスへ予告する義務が新法で定められました。
ただし、災害などやむを得ない事由があるときは30日前の予告をしなくてもいいという例外があります。フリーランス側に契約違反や大きな落ち度がある場合は解除を即時行使できる可能性があるため、詳細は今後のガイドラインに注目が集まっています。
違反した場合の仕組みと罰則
フリーランス側からの申出
フリーランス新法に違反する行為があった場合、フリーランスは公的機関に対して「こんな違反がありました」と申し出ることができます。
- 取引適正化のルール(契約書面交付、報酬支払い、禁止行為など)に違反したと思われる場合 → 公正取引委員会もしくは中小企業庁
- 就業環境整備(ハラスメント防止、育児介護の配慮、中途解除予告義務など)に違反したと思われる場合 → 厚生労働省
相手の発注事業者が「公的機関に申し出たから、お前にもう仕事はやらないぞ」と不利益を与えることも禁止されており、従わない場合には行政処分の対象になります。
公的機関が行う対応
申し出を受けた行政機関は、報告徴収や立入検査を行うことができます。その結果、違反が認められるとまず「勧告」がなされ、発注事業者が勧告に従わない場合は「命令」が出される可能性があります。これを無視すると、50万円以下の罰金などのペナルティや、企業名が公表されるおそれがあります。
なお、フリーランスに対するハラスメント対策は命令の対象外であり、同時に「自発的な改善努力を促す」という形が想定されています。いずれにしても、企業イメージや社会的信用を失うリスクを考えれば、簡単に違反をしてよいものではありません。
罰則の概要
- 命令違反、不報告・虚偽報告、検査拒否など → 50万円以下の罰金
- ハラスメントの防止に関する不報告や虚偽報告 → 20万円以下の過料
- 両罰規定があり、法違反を行った個人だけでなく雇用主や法人そのものも処罰対象となり得ます。
フリーランス・トラブル110番との関係
厚生労働省から委託を受けた第二東京弁護士会は、フリーランスの無料電話相談「フリーランス・トラブル110番」を運営しています。報酬不払いなどに悩んだフリーランスは、まずここに相談し、弁護士からアドバイスを受けたり、和解あっせん手続を検討したりできます。この110番は、新法の施行後も大いに活用される見込みです。
フリーランス新法がもたらすメリットと注意点
フリーランス側のメリット
- 契約条件が明確化されることで、後から「言った・言わない」のトラブルが減る。
- 報酬の支払が遅れたり買いたたきされたりしても、公的機関や「フリーランス・トラブル110番」に相談しやすくなる。
- 育児や介護と仕事を両立するための配慮義務、ハラスメント対策が整備される。
発注事業者側のメリット
- ルールが明確になることで、トラブル防止につながる。
- フリーランスとの取引が適正化されることで、企業の社会的信用が高まる。
- ハラスメントや報酬トラブルなどが減るため、優秀なフリーランスを確保しやすくなる。
新法ができると「いちいち契約書を用意しないといけなくて面倒」と感じる発注企業もあるかもしれませんが、結果として「後で裁判になる」「評判が落ちる」というリスクを回避できるメリットがあります。
注意点
- すべての契約に適用されるわけではない
取引内容や契約期間(政令で定める期間以上)などによっては、一部の禁止行為規定が適用されない場合がある。 - 偽装フリーランスとの線引き
実態としては労働者に近いのに「事業者」とされているケースだと、むしろ労働基準法で保護されるべき問題かもしれません。 - 下位法令やガイドライン待ち
法律本文だけでは解釈が曖昧な部分が多く、今後の政令・省令・ガイドラインで細部が決まる。
フリーランス協会や連合などの評価
フリーランス協会はこの法律を歓迎する立場をとっており、特に「取引条件の明示」や「禁止行為の明文化」は大きな前進だと評価しています。ただし、契約期間が短いケースには適用されない行為規制もあることなどから、「すべてのフリーランスが十分に守られるわけではない」という懸念も示されています。また、連合(日本労働組合総連合会)も、労働者性の判断基準との境目や執行体制の強化が今後の課題としています。
今後の展望
施行までのスケジュール
フリーランス新法は2024年11月1日に施行されます。公布の日(2023年5月12日)から1年6カ月以内の範囲で施行日が決まることになっており、それが2024年11月1日です。施行までに政令、省令、ガイドラインが整備され、周知期間が設けられます。
- 政令・省令の策定:具体的な「契約期間の基準」「書面に記載すべきその他の事項」「報酬の支払期日や再委託の場合の扱い」などを定める。
- ガイドラインの公表:業務委託契約で想定される様々な状況(クラウドソーシングや運送、ITエンジニア、デザイン、音楽・映像制作など)に合わせた事例が盛り込まれる可能性。
- 周知期間:企業やフリーランスが対応できるように、セミナーやリーフレットが配られるなどの広報活動が行われる予定。
残る課題
- 労働者性の判断基準:実態としては雇用契約に近いが、名目上はフリーランスにされている「偽装フリーランス」の問題が依然として残る。
- 執行体制の充実:公正取引委員会や厚生労働省など行政機関がどれだけ積極的に調査や指導を行うか。
- 取引期間の線引き:5条、13条、16条のように、政令で定める期間以上かどうかで適用される規定が変わる。具体的に何カ月以上になるのか要注目。
施行後の相談窓口
- 公正取引委員会、中小企業庁:取引条件明示や支払い、禁止行為などのトラブル
- 厚生労働省(都道府県労働局):ハラスメント対策、育児介護配慮、中途解除予告など
- フリーランス・トラブル110番:電話・メール等で無料法律相談、和解あっせん
まとめ
日本という社会の中で、働き方はどんどん変わっています。大企業に就職するだけでなく、自分の得意なことを活かし、一人の力でいろんな会社と取引する「フリーランス」が増えています。新しい働き方だからこそ、これまでの法律では守りきれなかった問題が出てきています。そこで「フリーランス新法」が2024年11月にスタートし、フリーランスが安心して活躍できるように、契約や報酬、ハラスメント防止などのルールを定めたのです。
ただし、新法ができてもまだ「偽装フリーランス」「非常に短い契約期間」「公的機関に相談しづらい雰囲気」など、課題は残っています。重要なのは、フリーランスと発注事業者がそれぞれ法律を学び、きちんと守る努力をすること。困ったときは行政機関や弁護士会など第三者に相談することが大切です。