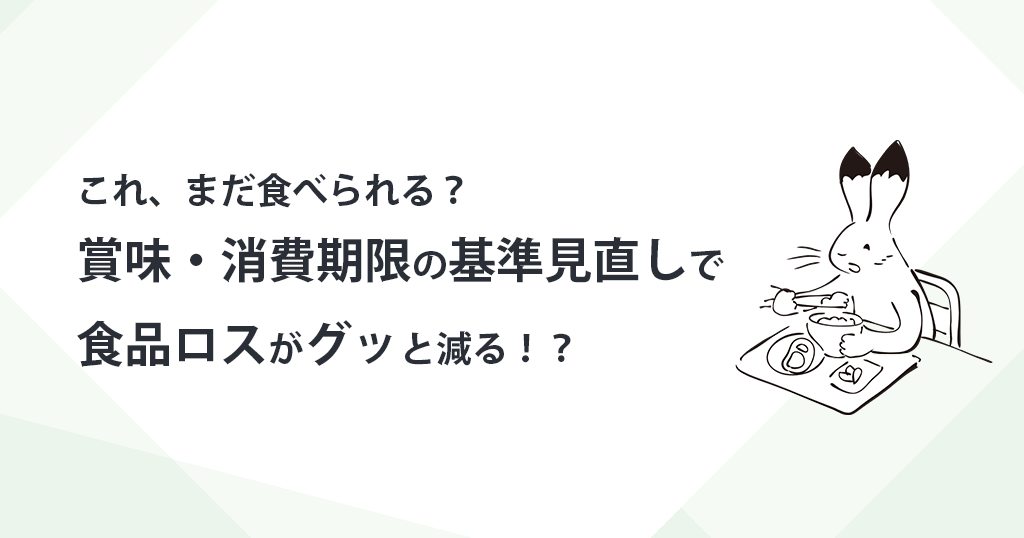「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(消費者庁)が閣議決定されたことにより、今後食品の賞味期限・消費期限の期限延長と表示方法もより分かりやすいものに変更となるようです。これにより食品ロス削減にどうつながるのかを解説していきます。
食品ロス削減の背景と現状
近年、「食品ロス」という言葉をよく耳にするようになりました。食品ロスとは、本来ならば食べられるはずの食品が廃棄されてしまう現象のことです。世界では大量の食料が生産されていますが、そのうち約3分の1にあたる13億トンもの食品が捨てられているという推計もあります。一方で、世界人口は今後も増え続け、栄養不足や飢餓に苦しむ方々はまだまだ多いのが現実です。このギャップは倫理的な問題だけでなく、環境問題や経済的ロス、社会的格差の拡大など、様々な形で私たちの暮らしに影響を及ぼしています。
日本に目を向けると、年間で約472万トンもの食品ロスが発生しており、そのうち約236万トンは家庭から、残りの約236万トンは企業(外食産業・食品製造業・小売業など)から排出されていると推計されています。食品ロスは大きく分けると、「まだ食べられるのに直接捨ててしまった」「食べ残してしまった」「皮や骨などの不可食部分を剥きすぎた(過剰除去)」という三つのケースによって生じます。スーパーやコンビニ、外食産業などでは、賞味期限や消費期限を厳格に管理するあまり、売れ残ったり返品された食品が大量に廃棄されることも少なくありません。
さらに、日本は食料自給率がカロリーベースで38%程度と低く、多くの食料を海外から輸入しています。それにもかかわらず、食べられる食品を大量に捨てているという実態は、家計にも大きな影響を与えています。例えば、消費者庁の推計によると、年間472万トンの食品ロスは約4兆円の経済損失にあたり、温室効果ガス排出量に換算すると約1046万トンCO₂に相当するとも言われています。これは、私たちの買い物や食生活が環境にも家計にも少なからぬ「ムダ」や「損」を生み出しているということです。
一方で、賞味期限が過ぎただけでは安全に食べられる食品が廃棄されたり、消費者が少しでも「傷みそう」「期限が近いかも」と感じた食品をためらわず処分したりするケースもあります。実際、インタビューなどでは「1日や1週間ぐらい過ぎても食べちゃう」という人もいる一方、「ちょっと過ぎたらすぐ捨てる」という人も多く、食品ごとに捉え方が大きく違います。こうした違いは、食品の安全基準や保存技術の進歩が消費者に正しく伝わっていない部分が影響しているかもしれません。
また、街の人々の声をみると、「納豆は数日過ぎても食べるけど、肉や魚は怖い」「調味料は気づいたら2年前のものが出てきた」など、期限への判断が曖昧なまま日々の暮らしを送っているケースも見受けられます。これらの声からわかるように、多くの人が「食品ロスを減らしたい」と思いながらも、具体的に何をすればいいのか、どの程度なら食べても大丈夫なのか、といった基準に迷いがあることが分かります。
そのため、「食品ロス削減推進法」や国によるガイドラインの見直し、新たな期限表示の基準づくりといった施策が進められています。これらは単に「捨てる量を減らそう」というだけでなく、「安心して食べられる期限」を正しく理解し、廃棄を減らすためのルールを見直し、実際の商慣習や賞味期限表示などを改革する狙いがあります。消費者庁が公表している「食品寄附ガイドライン」や「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」もまた、フードバンク活動の拡大や外食時の食べきり・持ち帰りを後押しし、より広範囲で食品ロスを削減するための取り組みなのです。
賞味期限・消費期限の基準見直しと社会的影響
近年、日本政府は「賞味期限」や「消費期限」の設定を見直す動きを強化しています。理由の一つは、食品の製造・保存技術が進歩し、実際にはもっと長く食べられる場合でも、期限を安全側に寄せすぎて設定していたケースがあるからです。たとえば、国や自治体のガイドラインが2005年頃に作成された時代に比べ、真空パックやレトルト技術、冷凍輸送網などが格段に向上し、一定期間以上は十分に品質を保てる食品が増えてきました。
こうした実情を踏まえ、政府は企業に対して「期限をより長めに設定することを検討してほしい」と促すガイドライン改正案を提示しており、2025年3月25日に閣議決定されました。実際、冷凍食品メーカーのニチレイフーズが「今川焼」「たい焼き」の賞味期限を12か月から18か月に延長したり、ファミリーマートがおむすびなど約70品目の消費期限を2時間延長したりなど、すでに動き出している事例もあります。こういった取り組みを進めることで、店舗や家庭でのフードロス削減に貢献できると期待されています。
一方、「消費期限」を過ぎた食品は原則として食べないことが推奨されており、食中毒のリスクを避けるためにも厳しく管理されるべきポイントです。肉や魚などの傷みやすい食品は安全に食べられる期限を守らないと、健康被害の可能性が高まります。そのため、「消費期限」の意味を正しく理解し、過ぎた食品は食べないというルールを徹底することが重要です。
また、新たな期限表示の導入にあたっては、消費者向けに「賞味期限が過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません」と明示したり、「消費期限は○年○月○日までに食べきってください」といったよりわかりやすい表示にすることも検討されています。こうした措置は、期限表示の理解を助け、必要以上に捨ててしまう食品を減らすための仕組みづくりの一環です。
これらの「期限延長」や「表示改革」の取り組みは、消費者の利用行動を変えるだけでなく、企業の商習慣にも影響を与えます。これまで「3分の1ルール」という商慣習により、製造日から賞味期限の3分の1以内に小売店舗に納品しなければならない、といったかなり厳格な仕組みが存在していました。結果として、まだまだおいしく食べられる食品が期限切れ扱いで返品・廃棄されるケースが多かったのです。今後このようなルールを見直し、適正に需要予測を行うことで無理のない量の仕入れをし、期限が近い食品は値引き販売などで売りきるといった工夫が広がれば、国内全体の食品ロスは大きく減少する可能性があります。
さらに、店舗や外食チェーンの廃棄削減は、コストダウンや環境負荷低減にもつながります。廃棄食品を焼却処分する際の費用だけでなく、輸送にかかる燃料や人件費の浪費も削減できるからです。その結果、企業の利益が増えたり、家庭への販売価格も抑えられたりするかもしれません。ただし、期限表示を緩和することで衛生管理が甘くなってしまえば本末転倒です。あくまでも高まった保存技術に見合った“現実的な期限”を設定し、安全と無駄のバランスを見極めなければなりません。
以上のように、期限表示の見直しや商習慣の改革は一朝一夕に進むものではありませんが、これまで「もったいない」と感じながらも捨てていた食品を活かすための大きな一歩です。国や企業がリードすることで、消費者の意識変革にもつながり、社会全体で「必要以上に食べ物を捨てない文化」を育てる契機になるでしょう。そうした文化が根付けば、「消費者が食品ロス削減に取り組む」「企業がそれをサポートする」という好循環が生まれ、やがては世界に誇る食の循環モデルとして発展していくはずです。
具体的な取り組み事例と私たちのアクション
食品ロス削減のためには、国や自治体の制度改革だけでなく、私たち一人ひとりの日常生活や企業の工夫、地域社会の連携が必要です。ここでは、具体的な取り組み事例と、すぐにでも取り入れられるアクションを紹介します。
まず、家庭でできることの代表例が「買いすぎない」「作りすぎない」「食べきる」という3つのステップです。買い物に出かける前に冷蔵庫の中をチェックして、必要な分だけ買うようにすれば無駄なストックを減らせます。特売で大量に買い込むメリットは確かにありますが、消費しきれないほど買って結局捨ててしまっては意味がありません。さらに、調理の際は家族の予定や食べられる量を考慮し、余りそうなら冷凍や乾燥保存できる食材は先に処理しておきましょう。
また、「てまえどり」や「値引き品」の活用も効果的です。スーパーやコンビニでは、期限が近い食品を手前に置いていることが多く、すぐに使う予定があるならそちらを積極的に選ぶことでお店の廃棄を減らせます。「自分が買わなくても誰かが買うだろう」と思うかもしれませんが、実際には店頭で売れ残った商品の多くは捨てられてしまいます。したがって「てまえどり」は、家庭の節約にも社会の食品ロス削減にも貢献する賢い選択なのです。
次に、外食産業の事例としては、「30・10運動」や「mottECO」などが知られています。たとえば宴会で乾杯して最初の30分間は席を立たずに料理を味わい、終了前の10分間でもう一度席に戻って残りを食べきるよう呼びかける「30・10運動」。あるいは、食べきれなかった料理を容器に詰めて持ち帰る行為を積極的に促進する「mottECO」の取り組み。これらは消費者の工夫と飲食店側の協力によってはじめて成り立ちます。厚生労働省や消費者庁がまとめた「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」に従って衛生面の注意点をしっかり理解し、安全な範囲で行うならば、有効な食品ロス削減策といえるでしょう。
また、「フードバンク」という仕組みにも注目です。食品メーカーや小売店、外食チェーンなどで売れ残ってしまったり、包装に傷がついていたりして通常販売が難しいが、中身は問題なく食べられる食品を福祉団体やこども食堂へ寄付する活動です。農林漁業や食品製造・流通現場で規格外となった未利用食品を有効活用する取り組みも進んでいます。このように、まだ食べられるのに捨てられてしまう大量の食品を一つでも多く必要とする方々のもとに届けることができれば、社会のセーフティネットとして大きな役割を果たすだけでなく、ロスを大幅に減らせる可能性が高まります。
フードバンク活動には、「誰が保管や管理をするのか」「品質が保たれるよう、どのように流通させるか」という課題もありますが、「食品寄附ガイドライン(消費者庁)」 を参照することで、安全で持続的な寄付の仕組みを作っている団体が増えています。企業からの寄付だけでなく、家庭でも「フードドライブ」と呼ばれる方法で、未開封の食品を集めて地元のNPOに届ける動きが各地で盛り上がっています。
さらに、デジタル技術を使った「フードシェアリング」サービスも注目です。スマホのアプリなどを使い、閉店間際の飲食店で余った料理や売れ残りそうな食材を割引価格や無料で引き取れる仕組みを作り、廃棄を減らす試みが大都市を中心に普及しつつあります。これにより、お店側は廃棄コストを削減でき、利用者は安価に食品を手に入れられるという利点があります。
要するに、食品ロスを減らすには「家庭」「企業」「地域」が一体となり、それぞれの立場で取り組むことが大切です。私たちは消費者として「買いすぎない・作りすぎない・食べきる」ことを意識し、企業は商習慣を見直したり、サービスや技術を工夫したりする。そして自治体やNPOなどが地域のネットワークを築けば、フードバンクやフードドライブの活動も拡がりやすくなる。こうした多層的な取り組みが、最終的に大きな食品ロス削減へとつながっていくのです。
未来をつくる食品ロス削減の道
ここまで見てきたように、食品ロス問題は家庭から外食産業、企業の製造・販売過程、そして国や自治体の施策まで、社会全体の課題となっています。一方で、日本には「もったいない」の文化や、自然や食材に感謝する「いただきます」「ごちそうさま」の習慣が根づいており、それを現代の仕組みや技術と組み合わせることで、食品ロスを大幅に減らせる可能性が十分にあるのです。
では、私たちが導き出す「答え」とは何か。
一言でいえば、「食べ物を大切にする意識を、システム・文化・人の行動変容の三位一体で支えること」です。具体的には以下の三つのポイントが重要です。
- システムの整備
企業の商慣習の見直しや、賞味期限・消費期限の基準改定、フードバンクやフードシェアリングの仕組み拡充など、ロスを削減するための制度や仕組みを常にアップデートする。これには国や自治体の後押しが不可欠ですが、一方で企業やNPOがイノベーティブなサービスを生み出しやすいような環境づくりも大切です。 - 文化や意識の醸成
「もったいない」「いただきます」「ごちそうさま」といった日本の食文化を原点に、食の大切さを再認識する。宴会や外食での「30・10運動」や家庭での「買いすぎない・作りすぎない・食べきる」「てまえどり」など、誰でも取り組める行動をもっと広めていく。学校教育や地域の啓発活動を活用して、子どもから大人までが楽しく食品ロス削減に参加できる仕掛けを育てます。 - 行動変容の促進
システムと文化が整っても、実際に動くのは人間です。消費者がフードドライブやフードシェアリングに参加したり、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めて需要予測を高度化したり、農林漁業者が規格外品の新たな価値創造に取り組んだりと、個々の行動が重なり合ってこそ食品ロスは削減されます。大規模イベントでの食材調達や地元の祭りなど身近なシーンから変えていくことも有効です。
そして、これらを継続的に回していくためには、国民一人ひとりがこの問題を「我が事」と捉え、「できることから取り組む」という主体的な姿勢が欠かせません。食品ロスの削減は環境面でも経済面でも、そして社会的にもメリットが大きく、まさにSDGsの「持続可能な生産と消費」に直結する取り組みです。例えば、大量の食品廃棄物を処理するコストが減れば、自治体の財政負担も軽くなり、その分を子育てや福祉などの別の分野に回せるかもしれません。家計から見れば、無駄な食費や電気代も削減できる可能性がありますし、世界規模で見れば飢餓や栄養不足に苦しむ人々への支援策とも連携が強まります。
まさに、食品ロス削減への道のりは、未来をつくる道でもあります。従来の「捨てる前提」で組まれた流通や生活習慣を転換し、「食べ切るための工夫」による付加価値を見いだすことで、新たなビジネスチャンスや地域コミュニティの活性化も期待できるのです。今はまだ模索段階の取り組みが数多くありますが、一つひとつの小さな実践が結びつけば、社会全体の大きな変化につながるでしょう。
私たち一人ひとりが日常の中で「ムダを省く意識」を持ち、その意識を社会全体で支えるためのルールづくりや技術革新、教育が欠かせないということです。食品ロス削減は難しい課題のように見えますが、身近な行動から着実に積み重ねていけば、確実に前進します。国や企業を巻き込む動きに発展させるためにも、まずは私たち自身が買い物の仕方や食卓の状況、外食のマナーを少しずつ変えていくことが、長い目で見れば社会を変える大きな力になるのです。
ここで取り上げた数々の事例やガイドライン、そしてそれぞれの立場でできる具体的な対策を知ることが、最初の一歩になります。日々の買い物や食事のシーンでできることを考え、「もったいない」を合言葉に、一緒に食品ロス削減を実践していきましょう。
参考資料
食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(消費者庁)
食品寄附ガイドライン(消費者庁)