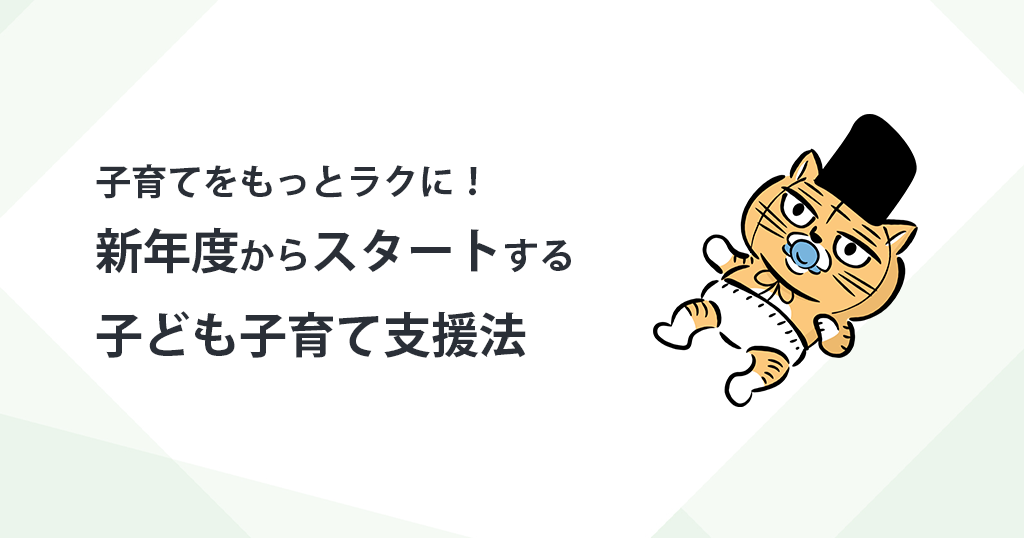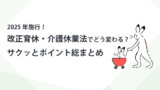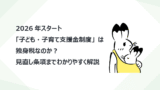2025年に向けた子ども・子育て支援法の流れ
日本では近年、少子化が深刻な社会課題となっています。国の総人口に占める子どもの割合は年々低下し、人口構造そのものへの影響が顕著となるなか、子どもの成長環境や子育て世帯をどう支えるかが極めて重要になっています。これを受け、政府は大規模な政策パッケージとして「こども未来戦略」を打ち出し、「2025年までに子ども・子育て支援施策を抜本強化する」と表明しました。
その中心的役割を担うのが、今回の「子ども子育て支援法」の改正です。実は本法は、2012年(平成24年)に成立してから段階的に施行され、保育の受け皿拡大や無償化などを柱としてきました。しかし依然として、地域や世帯ごとに受けられるサービスや金銭的サポートが不十分という指摘や、妊娠期・産後直後への支援の手薄さなどが課題として残っていました。
そこで2024年に大きな改正が成立し、2025年から新たな施策が順次スタートしていく流れです。この改正により、
- ライフステージを通じた経済的支援の強化
- 児童手当の大幅拡充(所得制限撤廃や高校生年代までの延長など)
- 妊娠期に着目した「妊婦のための支援給付」創設
- 出産・産後期から子育て初期までの切れ目ない伴走型支援
- 全ての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
- こども誰でも通園制度(満3歳未満の子どもにも、スポット的に通える枠を用意)
- 産後ケア事業の充実・強化
- 児童扶養手当の加算額拡充(多子家庭へのさらなる配慮)
- 共働き・共育て(男女ともに仕事と育児の両立)の推進
- 出生直後に男女とも育休を取得した場合の「出生後休業支援給付」
- 時短勤務をした場合の「育児時短就業給付」
- 国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)の育児期間保険料免除
- 子ども・子育て支援特別会計(いわゆる「こども金庫」)の創設
- 児童手当や育児休業給付などの財源を一元管理し、施策の見える化・安定化を図る
- 医療保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」を新たに徴収(令和8年度から段階的に導入)
こうした改正の背景には、「生み育てやすい社会」への切実な要請があります。子育てにまつわる費用負担やキャリア中断の不安を軽減し、「将来への希望を保てる」環境づくりが急務だからです。一方で、施行にあたっては地方自治体の財源確保や企業側の就業規則整備など、多岐にわたる調整が必要とされます。
さらに、2025年4月や10月の段階で施行される制度改正(例えば出生後休業支援給付や育児時短就業給付など)は、別の関連法(育児・介護休業法など)との連動も大きいため、企業と自治体は早めの準備が求められます。一部の制度は「施行日が2025年4月1日」「2025年10月1日」「2026年4月1日」といった複数のタイミングで段階導入される点も要注意です。
ライフステージ別の新たな支援策(児童手当・こども誰でも通園制度など)
まずは、今回の改正の中核といえる「ライフステージを通じた経済的支援の強化」を紐解きます。これは、赤ちゃんがお腹にいる妊娠期から、高校生年代に達するまでの間、段階に応じてさまざまな手厚い施策を行うものです。特に注目されるのが、児童手当の抜本的拡充と妊娠期からの支援強化です。
児童手当の抜本的拡充
- 所得制限の撤廃・高校生年代まで延長
従来は一定以上の所得がある世帯には減額給付(特例給付)となり、中学生までしか受給できませんでした。これが2025年の改正により、所得制限が撤廃され、高校生年代まで支給対象となります。家計に占める教育費の負担が重い世帯には大きなメリットです。 - 第3子以降は月3万円に
多子家庭の経済負担をより軽減するため、第3子以降にかかる児童手当の支給額を月3万円へと引き上げる措置が導入されます。さらに、高校生年代まで継続して受給できるので、従来よりも長い期間、手厚い援助が得られることになります。 - 支給回数を年6回に増加
現行では2月・6月・10月の3回支給でしたが、偶数月ごとに計6回の支給となり、家計管理もしやすくなると見込まれます。
妊娠期からの新たなサポート:妊婦のための支援給付
「妊娠期の負担軽減を図る」という狙いで、新たに**妊婦支援給付(仮称)**が創設されます。概ね10万円相当の経済的支援が想定されており、各自治体の伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)とセットで実施される予定です。たとえば、
- 妊娠初期(認定後)、最初に一律5万円
- その後、妊娠している子どもの人数に応じてさらに5万円ずつ
といった形が想定されており、妊娠届出~出産届出まで切れ目なく支援を受けられます。この制度は「出産をあきらめずに済む環境づくり」を目指すもので、金銭給付だけでなく自治体による訪問や相談も組み合わせる点が大きな特徴です。
こども誰でも通園制度
0~3歳未満の子どもが、スポット的に保育所等に通える仕組みとして新設されるのが「こども誰でも通園制度」です。従来、保育施設を利用するには一定の保育の必要性が認められる(両親とも働いている等)といった要件が厳しく設定されていました。しかし、この制度では「週に数時間だけ」「月に数日だけ」といった柔軟な使い方が想定されます。2024~2025年度にかけて試行を広げ、2026年度から本格的に給付化される予定です。
例としては、在宅ワーク中のお母さんが「少しだけ集中して仕事する時間を確保したい」「子どもに集団生活を少し経験させたい」といったニーズに応えることが可能になります。ただし、利用時間には上限(月10時間程度等)が設けられる見込みで、すべての保育施設が対象になるわけではありません。自治体ごとの整備計画や指定事業所の拡大がカギとなるでしょう。
産後ケア事業・多子家庭支援の拡充
産後ケア事業は、出産後に母子を支援するサービスで、宿泊型・訪問型・デイサービス型など多様な形態があります。今回の改正では、市町村単位だけでなく都道府県や医療機関との連携を強化して「広域的な受け皿づくり」を目指すとされています。市町村の枠を越えて利用できる仕組みを整え、産後の体調やメンタルケアに迅速に対応するのが狙いです。
また、児童扶養手当の第3子以降への加算が手厚くなる変更も予定されています。ひとり親世帯などを中心に、子育ての経済的負担を一層軽減することで、就業・学び直し・再就職など多方面での自立を促す狙いがあります。
共働き・共育てを推進する新制度(出生後休業支援給付・育児時短就業給付・国民年金保険料の免除)
続いて、「共働き・共育て」の推進を目指す新たな施策に注目します。保育の受け皿整備だけではなく、出産直後から男女がともに育児に参加できるよう、就労環境を整えるのが改正の大きなポイントです。
出生後休業支援給付
育児休業給付はすでに存在しますが、さらに**「出生後休業支援給付」**が新設されます。具体的には、子どもが生まれてから8週間以内に父母それぞれが14日以上の育児休業を取得すると、
- 28日を上限に、「休業前賃金の13%相当」が上乗せされる
- 従来の育児休業給付(賃金の67%相当)と合算すると、実質80%(手取りで10割近く)の支給が可能になる
これによって、特に男性の育児休業取得が進むと期待されています。配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合には、この「14日以上取得」の要件が一部緩和される見通しです。
育児時短就業給付
もう一つの目玉が、「育児時短就業給付」です。これは2歳未満の子を養育する雇用保険被保険者が、時短勤務をした場合に「時短勤務中の賃金の10%を追加給付する」という仕組みです。
従来、短時間勤務をすると当然ながらその分の賃金が減少しますが、子育てに必要な時間を確保しながら、「完全休業ではない働き方」を選んだ労働者をサポートするのが狙いです。給付率を高くしすぎるとフルタイム勤務者との不公平が大きくなるため、10%に設定されました。こうした「中間的」な給付制度は、これまでになかった新しいアプローチといえます。
国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置
会社員や公務員と異なり、自営業者やフリーランスは育児休業制度がないため、出産直後の所得減少リスクが大きいとされてきました。そこで創設されるのが、「国民年金第1号被保険者の育児期間保険料免除」です。
- 子が1歳になるまでの間、国民年金保険料を免除
- 免除期間については年金の受給資格期間に含め、基礎年金額も満額保障
この措置により、「出産や育児のために年金保険料が払えず受給額が下がる」という不安を解消します。所得要件は設定されない予定で、就業の有無を問わず該当者が利用できる見通しです。
4. 企業・自治体への影響と対応
こうした新制度は、雇用保険法など他の法律とも密接にリンクしているため、2025年4月や10月施行で一気にスタートします。企業は就業規則や人事制度の改訂が必要になり、自治体も周知や窓口対応、新たな申請手続き整備などが求められます。
たとえば出生後休業支援給付を実際に受けるには、労働者が「14日以上の育児休業を取得」しやすい雇用環境が必須です。制度を知らないまま従業員が産後の休業を取得しなかった場合、給付は受けられません。また、時短勤務給付についても勤務実績の管理や賃金計算の方法が絡むため、企業の給与システム整備も欠かせません。
「共働き・共育て」を社会全体で応援するという大きなビジョンのもと、法整備・制度設計・労務管理がセットになって動いていくわけです。
財源確保と子ども・子育て支援特別会計(こども金庫)の創設
最後に、これらの施策を支える財源面の仕組みについて解説します。子ども関連の支援拡充は費用が膨大になるため、新たな財源確保策として「子ども・子育て支援金制度」が注目されています。これは、現行の保育拠出金や雇用保険料に加え、医療保険料とあわせて徴収する形で導入されるのが特徴です。
なぜ「こども金庫」を設置するのか
従来、児童手当や保育の無償化などに用いられる費用は、年金特別会計の一部や各種助成金・地方負担など複数ルートで賄われてきました。この仕組みは複雑で、国民にとって「どこにどれだけお金が集まり、どの施策に使われているのか」が見えにくかった側面があります。
そこで「こども金庫」=子ども・子育て支援特別会計を創設し、
- 児童手当
- 妊婦のための支援給付
- こども誰でも通園制度
- 育児休業給付関連(出生後休業支援給付など)
といった支出を一元管理することで、透明性と安定性を高める狙いがあるのです。
2. 子ども・子育て支援金制度(医療保険料との連動)
令和8年度(2026年度)から段階的に医療保険の保険料に「子ども・子育て支援金」を上乗せして徴収し、その財源を特別会計に繰り入れる仕組みが導入されます。具体的には、健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険などが被保険者や事業主から追加保険料として集め、国へ納付します。
- 令和8年度に0.6兆円程度、令和9年度に0.8兆円、令和10年度(2028年度)には1兆円規模
- 賃上げや歳出改革による別の軽減効果を相殺し、「国民負担が実質的に増えない」よう計算する
ただし、これは「本当に実質負担ゼロなのか」「将来的に保険料がさらに上がる可能性がないのか」といった懸念があるのも事実です。また、国民健康保険では低所得者の均等割軽減など特別措置を設けるとしており、自治体や保険者間で調整が必要になります。
地方自治体や企業への影響
今回の支援金導入や特別会計の創設によって、地方自治体には、
- 妊婦支援給付やこども誰でも通園制度の窓口
- 介護保険料・国保料などと同様に住民へ周知・徴収方法の説明
- 保育施設を新たに指定・監督し経営情報を開示する手続き
といった事務が増えます。自治体の財政や人材リソースを圧迫する可能性もあり、その対策として、デジタル技術(ICT)の活用や自治体間連携による効率化が求められています。
一方、企業側も、雇用保険法の改正や育児休業関連給付の適用拡充に合わせた就業規則の改訂、給与システムの更新などを進める必要があります。加えて、医療保険料とのセットで「子ども・子育て支援金」を徴収される形となるため、従業員向けの説明や社会保険手続きについても細かな調整が避けられません。
展望と課題
今回の改正は、少子化が深刻化するなかで「最後のチャンス」ともいえる時期に投入された大規模な取り組みです。妊娠・出産から就学前の保育、高校生年代までの児童手当拡充、そして父母がともに育児しやすい制度設計を一体的に進めようとする点は高く評価できます。その一方で、
- 制度が複雑化し、利用者が混乱する可能性
- 自治体・企業の実務負担の増大
- 財源の持続性(本当に賃上げや歳出改革で相殺できるのか)
など、まだ慎重に見守るべき課題も多々あります。特に利用者サイドである保護者は、支援金や給付の申請タイミング・対象年齢・手続き先などを理解しないと、受け取れるはずの給付を逃すおそれがあります。今後、国や自治体がどのように情報を周知し、ユーザーフレンドリーな手続きを実現するかが重要なポイントでしょう。
いずれにせよ、2025年~2026年に向けて、子育て支援制度は大きく舵を切ります。子育て世帯が安心して利用できるよう、社会全体で情報共有・環境整備を進めることが欠かせません。
妊娠期・産後ケアから高校生年代まで切れ目なくサポートを行うための改正と、それに伴う財源確保の仕組みが大きな柱となっています。特に2025年4月・10月施行の施策は企業や自治体への影響も大きいため、早めの情報収集と準備が必要です。