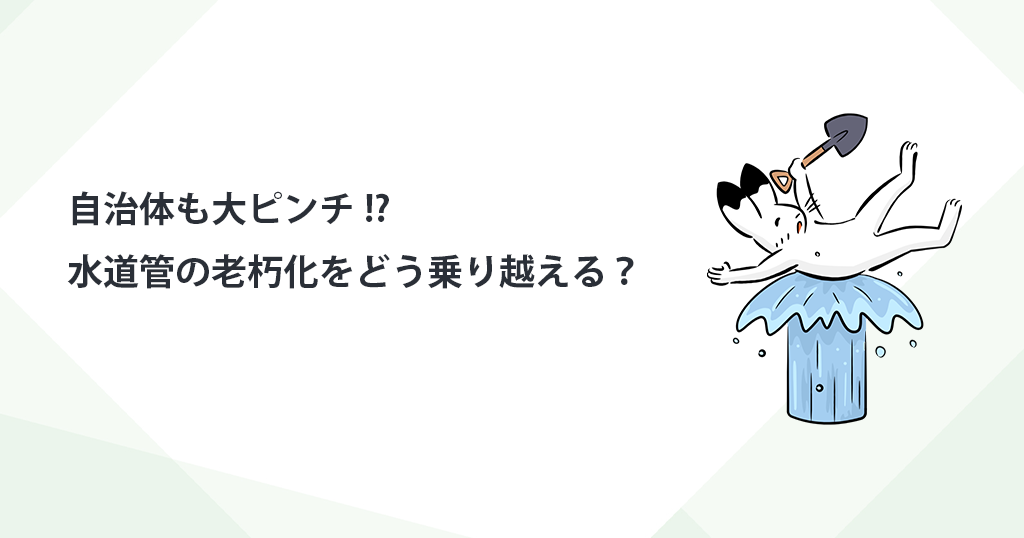2025年1月に埼玉県八潮市でおこった道路陥没事故。老朽化した下水道管の破損が原因とされています。今回は、各自治体がかかえる「水道管老朽化問題」を解説いたします。
水道管老朽化問題とは何か
水道管の老朽化問題とは、読んで字のごとく「水道管が古くなり、維持や管理が難しくなっている」状態を指します。私たちがふだん何気なく使っている水道は、蛇口をひねると当たり前のように水が出ますが、その裏には長い年月を経た管路がたくさん敷設されていることをイメージしてください。
日本の水道管の多くは、高度経済成長期(1960~70年代)に一斉に整備されました。それから半世紀以上が経過した現在、耐用年数(法定耐用年数は40年とされています)を超えて使われ続けている水道管が徐々に増えているのです。実際、厚生労働省などの調査によれば、40年超の管路(老朽管)の割合が年々上昇しており、令和3年度には全体の2割を超えるまでになっています。さらに、更新率(=1年間に更新される管路の延長を全体の延長で割ったもの)も低下の傾向があり、老朽化に追いついていないのが現実です。
こうした老朽化が進むと、何が起こるのでしょうか。大きく分けて3つの影響が考えられます。
- 漏水・断水トラブル
水道管が劣化して穴があいてしまうと、道路に水が噴き出してしまったり、断水が起きたりする危険があります。特に老朽化した管は地震や自然災害のときに破損リスクが高く、水道の復旧に時間がかかる恐れがあります。2021年10月、和歌山市で水管橋が崩落し、市内約6万戸が約1週間断水した事例は記憶に新しいところです。 - 水質低下の懸念
水道水そのものは浄水場でしっかり処理されてから配水されますが、途中の管路が劣化して錆などが混ざれば、家庭に届く水の品質が下がる可能性もあります。日本の水は基本的に安全と言われていますが、だからこそ管路の老朽化には注意が必要です。 - 維持管理コストの増大
老朽化した管路をそのままにしておくと、漏水事故や補修費用がかさんでしまいます。さらに、水道事業者(市町村など)が抱える施設全体を更新しようとすると、莫大な費用が必要となります。ところが、少子高齢化で人口が減り、水道の使用量や料金収入が減少する一方、施設の維持費は増大するため、経営が苦しくなってしまうのです。
こういった問題は昔から潜在的には存在していましたが、最近になって本格的に目に見える形で現れてきました。たとえば、令和元年頃から、漏水事故や水管橋の破損がニュースで取り上げられたり、各地の地方自治体が水道料金の値上げを余儀なくされる動きが報道されたりしています。
厚生労働省や総務省、国土交通省なども、このまま放置すれば今後さらに深刻化するとの危機感から、更新率を上げるための財政支援や、事業の広域連携(小規模な水道事業をまとめるなど)の推進、さらには官民連携(民間の力を活用すること)の仕組みづくりを急いでいます。しかし、実際には小規模自治体ほど経営基盤が弱く、料金改定のハードルも高いのが現状です。よって、根本的な解決は一筋縄ではいきません。
老朽化の原因と広がり(人口減少・経営難・耐震化の遅れ)
「なぜ老朽化が進むまで放置してしまったのか?」という疑問があるかもしれません。ここには、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
高度経済成長期のインフラ整備
先ほど述べたように、1960~70年代の高度経済成長期に、日本全国で大量の水道管がいっせいに敷設されました。設計上の耐用年数が40年前後だとしても、一度に造ったものは、一度に寿命を迎えることになります。これを「更新需要の山が同じタイミングでやってくる」と表現することがあります。結果として、全国の水道管がいっせいに古くなってしまっているわけです。
人口減少と財政難
一方で、日本全体で進む人口減少は、自治体の水道事業収入に直接響きます。人口が多いほど、水道料金収入は増えますが、人口が減れば水の使用量(有収水量)が減り、収益が下がります。これが「収入減」となって経営を圧迫し、結果として思うように更新投資ができなくなってしまうのです。
特に過疎化が進む地域では、住民1人あたりの管路延長が長いわりに収入が少なく、水道料金を値上げしても負担が大きくなるだけで、住民生活に影響を与えかねません。このため、少しずつでも管路の改修が進めばよいほうで、現実には後回しになりがちです。
耐震化の遅れ
日本は地震大国と呼ばれるほど地震が多い国ですが、実は水道管路や水道施設の耐震化はまだ進み切っていません。令和4年度時点で、基幹管路の耐震適合率は全国平均で4割程度という報告もあります。これは大きな地震が起きた際に、断水が長引くリスクがあることを示しています。実際、東日本大震災の際にも水道管の破損が広範囲で見られ、復旧に時間がかかった例があります。
耐震化を行うには、地中に埋設された管を耐震性の高い素材に交換するなど大規模な工事が必要です。工事費のほかにも、道路を掘り返す際の交通規制や住民生活への配慮など、ハードルは少なくありません。
技術者不足と高齢化
水道事業は専門性が高く、管路の維持管理や施設運用には経験とノウハウが必要です。ところが、自治体の職員数はピーク時から3割程度減少しており(特に地方ほど深刻)、さらに技術系職員の高齢化も進んでいます。引退が進む一方で若手が確保できず、知識や技術の継承がスムーズに行われないという懸念があります。
また、事務系との兼務で管理を行っている小さな自治体もあり、一人で何役もこなしている現場では、点検や修繕にまで手が回らないケースもあります。このように、ヒト(人材)の問題も大きい要因です。
不測の事故リスク
老朽化した管路は地中に埋もれているため、実際にどの程度劣化しているのか目視しづらいのも課題です。ある日突然漏水が発生し、道路が陥没するなどの事態も全国各地で報告されています。とりわけ、水道管橋のように橋梁部分に添架された管が壊れると、川を渡す水が止まってしまい、大規模な断水を引き起こすおそれがあります。
さらに、事故が起きるとその修理費のみならず、道路が使用できなくなる、交通渋滞が起きるなど社会的損失も拡大します。「整備するよりも事故対応費のほうが高くついてしまった」とならないよう、早めのメンテナンスが重要なのです。
以上のように、老朽化の問題は、単に「古くなったから交換すればいい」という単純な話ではなく、人口問題や財政問題、技術・人材の問題など、さまざまな要因が重なり合って生じています。次のセクションでは、具体的にどんな解決策が考えられるのかを見ていきましょう。
解決策1──アセットマネジメントの推進・広域連携
老朽化した水道管を計画的に更新し、安全な水を安定的に供給するには、長期的な視点で施設や収支を管理する「アセットマネジメント」が欠かせません。
アセットマネジメントとは?
アセットマネジメントを直訳すると「資産管理」という意味ですが、水道事業の場合は「将来にわたって水道サービスを持続可能にするために、施設の状態や更新費用、財源計画を長期スパンで考え、最適な投資やメンテナンスを行う仕組み」を指します。
具体的には、以下のような流れで進めます:
- 施設台帳やデータの整備
どの地域にどんな素材・口径の管路がいつ敷設され、どれほど劣化しているかなど、台帳(施設情報)を電子化して把握します。 - 点検と評価
現地調査や観測機器、ロボットなどを用いて管路の老朽度をチェックし、漏水リスクや破断リスクを数値化するなど評価を行います。 - 長期の更新計画と費用試算
今後10年~40年程度のスパンで、いつどこを更新し、どれほどの費用が必要になるか試算します。加えて、人口減少や節水率などを見越し、水道料金や財源確保策を検討します。 - 優先順位をつけた改修
限られた予算の中で、どの管路を先に改修すべきかをリスクベースで決定。大地震時の被害が大きい地域や、過去に漏水を繰り返している管路などを重点的に更新するのが一般的です。
厚生労働省はこうしたアセットマネジメントを事業者に推奨しており、「水道施設台帳の作成」や「計画的な更新等」を水道法で義務化(令和元年施行)しました。しかしながら、実際にアセットマネジメントを本格導入している事業者は、全体の7割程度という報告もあります。特に小規模なところでは、職員不足や費用面の問題もあって難しい面があるのが実情です。
広域連携でスケールメリットを得る
もう一つの解決策が「広域連携」です。水道事業は市町村ごとに運営されるのが原則ですが、人口減少が著しい地方部などでは、単独での経営が厳しくなっています。そのため、複数の自治体が一つの水道事業体としてまとまったり、浄水場や配水池などの施設を共同で管理したりする事例が増えてきました。
例えば、香川県広域水道企業団のように、県と市町が一体となって事業を運営することで、施設の統廃合が進み、更新コストの抑制や人材の効率的配置などが期待できます。また、和歌山県内でも、複数の町が水道用水供給事業を共同化して運営を合理化するなどの取り組みが見られます。
都道府県がリーダーシップをとって、関係する市町村や事業体を束ね、広域化や官民連携を促進する仕組みが法整備されたこともあり(平成30年の水道法改正)、今後さらに広域連携が加速することが予想されます。ただ、料金体系の調整や事業統合に伴う住民理解など、解決すべき課題もあるため、一気に広がるわけではないのが現状です。
官民連携(コンセッション方式など)
さらに、官民連携(Public-Private Partnership=PPP)の活用も注目を集めています。公共施設等運営権(いわゆるコンセッション方式)を用いれば、所有権は自治体に残したまま運営の権限を民間に委ねられる仕組みが整備されました。
実際、宮城県では上水道、下水道、工業用水道を一体で官民連携する取り組みが始まっており、大きな注目を集めています。ただ、水道は公衆衛生に直結するため、「民間に任せて大丈夫なのか」「料金はどうなるのか」などの懸念の声もあるのは事実です。民間の技術力・経営ノウハウを活用しつつも、安全・安心を確保するためのルールづくりと情報公開が必要不可欠でしょう。
こうした広域連携や官民連携の動きは、単独の自治体では限界がある財政面・人材面でのサポートを補う上で大切な選択肢です。次は、さらに実務レベルで役立つ「デジタル技術の活用」や「点検技術の進歩」など、次のセクションで具体的に取り上げていきます。
解決策2──デジタル技術と点検・補修の革新
老朽化した管路を見つけ出し、効率的に補修するには、従来の人手による目視点検だけでなく、最新のデジタル技術やロボット技術の活用が欠かせません。最近は国や自治体、民間企業が協力して、さまざまな新技術を開発・実証しています。
ドローンやロボットによる点検
地上からの点検が難しい水管橋や山間部の送水管、あるいはトンネル状の導水路を調べる際、ドローンや水中ロボットが活躍しています。人が立ち入りにくい場所でも、高解像度カメラやセンサーを搭載した無人機が内部を撮影し、ひび割れや漏水箇所を特定するのです。
例えば、北九州市では水道橋の点検にドローンを活用して点検時間を大幅に短縮したり、また一部地域では水中ロボットが老朽化した管の内部をくまなく撮影して劣化状況を評価したりしています。こうした技術革新は、人手不足や安全上の理由からも非常に期待されています。
AIやセンサーによる監視
漏水が起こってから対応するのではなく、事前に劣化の兆候を捉えられればベストですよね。そこで注目されているのがセンサー技術やAI解析です。管路に振動センサーや流量計を設置し、微妙な変化を検知して「ここで漏水の恐れがある」といった予防的な対策を打つ試みが進んでいます。
また、衛星によるリモートセンシング技術(SAR衛星を使った地盤沈下の検知など)を組み合わせることで、大規模に水道管周辺の地盤を監視するプロジェクトもあります。こうしたAIやセンサー技術を活用すれば、人が現場をくまなく歩き回らなくても、異変を早期に見つけられる可能性が高まります。
既設管路のリニューアル工法
老朽管を更新するには、路面を大きく掘り起こして管を取り替える「開削工法」が一般的でしたが、交通や住民生活への影響が大きいというデメリットがあります。そこで、管の内側に樹脂のライニング材を入れて補強する「非開削工法」や、「反転形成工法」「SPR工法」など、道路をほとんど掘らずに管の内部から補修する技術が開発されています。
下水管では「管きょ更生工法」と呼ばれる一連の技術が普及しつつあり、近年は上水道でも簡易的なライニング工法が一部導入されています。こうした工法により、工期短縮やコスト削減が期待できるものの、適用には事前調査や施工ノウハウが必要であり、全ての老朽管に一律に適用できるわけではありません。
データベース活用と情報共有
点検で集めた情報は膨大になりがちです。管路の位置や素材、設置年、破損履歴などを体系的に管理するデータベースがあれば、劣化状況を地図上で可視化し、優先度を決めて補修計画を組むことができます。近年はクラウドを活用して地理情報システム(GIS)と連動した「水道施設管理システム」を導入する自治体が増えています。
また、上水道だけでなく下水道や農業用水、工業用水の分野でも、老朽化の兆候を早期に発見するためのICT(情報通信技術)利用が重要視されています。最終的にはこうした情報を自治体間や関連企業間で共有し、互いのノウハウを学び合うことで、より効率的なメンテナンスができるようになるでしょう。
このように、技術的なイノベーションは、老朽化問題解決の大きな助けとなります。ただし、新技術を導入するにも予算が必要であり、ある程度の専門知識を持った人材も不可欠です。次のセクションでは、そうした人材面の課題と、それを補うための取り組みについて説明します。
人材・財政面の課題と今後への提案
水道管の老朽化問題を解決するには、施設の更新計画やデジタル技術の導入だけでなく、それを運用する「人材」、そして膨大な「資金」が欠かせません。
人材不足と技術継承
地方自治体の水道事業職員は、ピークから3~4割減少したと言われています。特に技術職員の高齢化や退職者の増加により、現場ノウハウが失われつつあります。若い人材を採用しようにも、給与面や職場環境などが十分に魅力的でないと応募が少なく、結果として人材確保が難しいという悪循環に陥るケースがあるのです。
また、水道は電気設備や配管工事、化学的な水質管理など多岐にわたる技術が必要です。専門分野ごとに技術の継承を図るための研修やマニュアル整備、外部のコンサルタント会社との連携など、さまざまな取り組みが求められています。
さらに、水道事業の広域化が進むことで、より大きな組織で専門分野を分担しやすくなる可能性もありますが、一方で職員の配置転換や再教育も必要になるでしょう。
財政負担の平準化
老朽化した水道管を更新するためには巨額の費用がかかりますが、一度に整備しようとすると財政負担が急増してしまう恐れがあります。そこで、計画的なアセットマネジメントに基づいて更新事業を「平準化」し、年度ごとの負担が極端に跳ね上がらないようにすることが重要です。
国や都道府県の補助金・交付金を活用する方法もありますが、税収が限られる中では、水道料金の改定も避けられないケースがあるでしょう。利用者の理解を得るためには、「なぜ料金を上げる必要があるのか」「どのように使われるのか」を丁寧に説明することが大切です。
情報公開と住民参加
水道管の老朽化状況や更新計画を、できる限り住民にわかりやすく公開する取り組みも求められます。水道事業は住民生活に不可欠な公共サービスなので、その運営に関する情報を共有することで、住民の安心感につながりますし、料金改定に際しても理解を得やすくなります。
例えば、「○○年度にどの地区の管路を改修し、費用はこれだけかかる」「耐震化率がどれくらい向上する」といった数値をグラフやイラストなどで示すことが有効です。さらに住民の声を聞きながら、広域連携や官民連携のメリット・デメリットを話し合う場を設けると、地域全体で問題を共有しやすくなります。
持続可能な水道サービスへの道
最後に、老朽化した水道管を取り替えるだけでなく、「これからも地域の水道をどう維持していくか」を考える必要があります。人口が減っていく中で、全く同じ規模のインフラを抱え続けるのは非現実的な場合もあります。施設の集約や多目的化(例:農業用水や工業用水との連携)を進めるなど、新しい発想で再設計する必要性があるのです。
たとえば、水道管と一緒に下水道や電線共同溝などの埋設管をまとめて整備するとコストが削減できるという考え方もあります。あるいは少子高齢化によって使用量が減った水源を、観光資源や防災用に転用する事例も模索されています。
このように、水道管の老朽化問題は技術・財政・人材・制度のあらゆる面にかかわる複合的な課題です。ただし、それは同時に「水道事業をどう未来に引き継ぐか」を考えるチャンスでもあります。今後は、国や自治体、民間企業が協力し合い、広域連携や官民連携を進めながら、持続可能な水道サービスを守っていく道を模索し続けることが求められています。
参考資料
水道事業における適切な資産管理(アセットマネジメント)の推進について(国土交通省)
施設の老朽化対策と適正な維持管理(国土交通省)
水道の現状と水道法の見直しについて(厚生労働省)