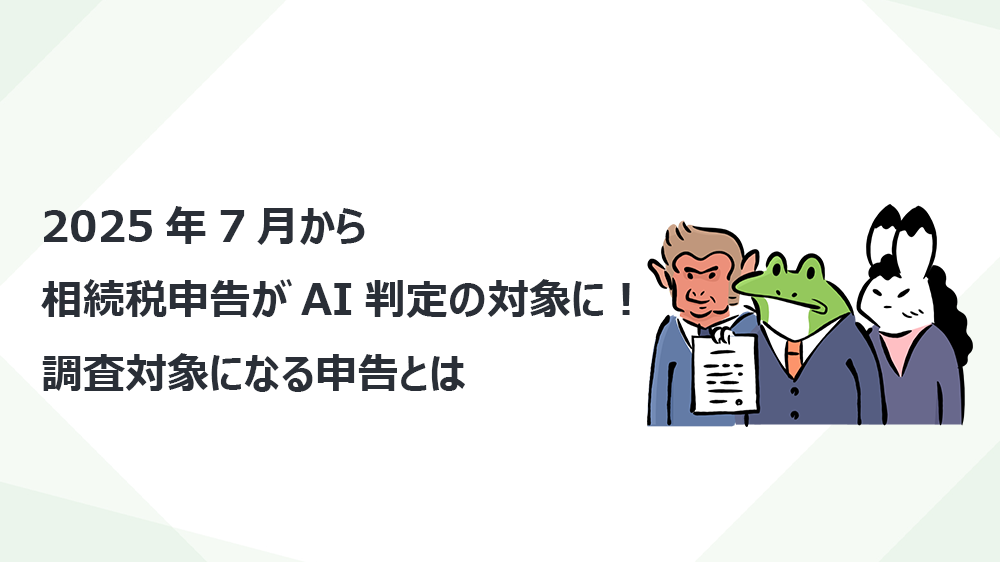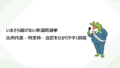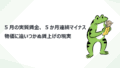2025年7月、ついに国税庁が相続税調査の選定にAI(人工知能)を本格導入します。これにより、2023年以降に提出されたすべての相続税申告書が、自動的にAIによるスクリーニングの対象となります。申告内容に“ミス”や“漏れ”があれば、相続財産の大小に関係なく調査対象となる可能性があるのです。この記事では、AIによる判定がどのように行われるのか、調査対象とされやすい申告の特徴、そして私たちにできる備えについて詳しく解説します。正しく申告したつもりでも、不意打ちのように調査の通知が来る前に――今こそ最新の相続対策を確認しておきましょう。
AIが相続税調査を選ぶ時代に
これまで税務署の職員が人の目で行っていた「相続税調査の対象者選び」を、なんとAI(人工知能)が担うことになったのです。これにより、過去の申告内容を学習したAIが、「この申告は調査が必要そうだ」と判断した人をピックアップしていく仕組みになります。
AIというと、最近では画像生成やチャットツール、自動翻訳など身近になってきましたが、今回のニュースは税金の分野です。相続税という、一生に一度あるかないかの手続きを終えたあとに、「あなたの申告、間違っているかもしれません」と連絡が来る可能性があるとなれば、驚かずにはいられません。
とはいえ、「ちゃんと申告していれば問題ないはず」と思う人も多いでしょう。それはそのとおりです。ですが、相続税の申告には少しだけクセがあります。たとえば…
- 不動産の評価方法が複雑で、税理士によって見解が分かれることがある
- 名義預金や名義株といった“見えにくい財産”があると、正しく申告したつもりでも漏れになる
- 暗号資産や海外資産など、新しい形の財産が増えており、気づかず見落としてしまうこともある
このように「知らずにミスをしてしまう」ことが、相続税ではよく起こります。AIはそうしたミスのパターンを過去のデータから学んでいて、「似たような間違いをしているかも」と判断すると、自動的に“調査候補”として通知するようになります。
つまりこれからの時代、「資産が多いから狙われる」という単純な話ではなく、「内容に疑わしい点があるかどうか」が選定の基準になるのです。しかもAIは、何十万件という膨大な申告書の中から、たった数秒で“おかしな申告”を見つけ出せるほど、スピードも正確さも兼ね備えています。
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月以内に行う必要があります。その期限に向けて手続きや書類集めを進め、ようやく提出が終わったあとに、「1年後に税務署から調査の連絡が来た」というケースも決して珍しくありません。今後は、この調査の入り口にAIが立つことになります。
「自分にはあまり関係なさそう」と思う人もいるかもしれません。ですが、相続税の調査は何も富裕層だけの話ではありません。たとえば…
- 小さな株式口座を子ども名義で持っていた
- 家族の預金口座に自分の資金を移していた
- 評価が難しい田舎の土地がある
など、一般家庭でも“ミス”と見なされるリスクはあります。国税庁としても、調査対象をできるだけ公平に選ぶために、AIを活用するという方向に進んでいるのです。
このように、2025年7月からの相続税調査は「AIが選ぶ」時代へと突入します。正しく申告していれば恐れる必要はありませんが、「正しいつもりでミスをしていた」というのが最も怖いポイントです。これから相続税の申告を考えている方、すでに申告を終えた方、どちらにとっても知っておきたいのが、「AIがどうやって申告を判定するのか」「どんな申告が選ばれやすいのか」「どうすればリスクを下げられるのか」といった情報です。
国税庁がAI導入に踏み切った背景
「税金の調査にAIが使われるなんて、なんだか少し怖い気もする」と感じた方もいるかもしれません。ですが、今回の国税庁によるAI導入は、時代の流れの中で自然な決断ともいえます。ここでは、なぜ国税庁が相続税調査の選定にAIを取り入れようとしているのか、その背景を丁寧に見ていきましょう。
人手不足という現実
国税庁で働く税務職員の数は、ここ10年で約6%も減少しています。これは日本全体の少子高齢化や人員削減の流れの中で、どうしても避けられなかった部分です。ベテラン職員の定年退職も増えており、「経験と勘」で調査対象を選んできた優秀な人材が年々少なくなっているのです。
一方で、相続税の申告件数は増加傾向にあります。背景には、地価の上昇や基礎控除の縮小といった制度改正があります。かつては「資産家だけの税金」と思われていた相続税ですが、最近では一般的な家庭でも課税される可能性が十分にある状況です。
つまり、「人が減っているのに仕事は増えている」――国税庁が抱えるこのギャップを埋めるために、AIの力を借りるというのはごく自然な流れだったといえるでしょう。
相続税ならではの“申告一発勝負”
相続税は、所得税や法人税と違って「毎年提出するもの」ではありません。被相続人が亡くなったタイミングで、一度だけ申告を行う「一過性の税金」です。つまり、「おかしいな?」と思っても、税務署が調査に入るタイミングを逃せば、二度とチェックできないのです。
しかも、調査には人手と時間がかかります。相続税の申告後、調査に至るまでには通常1年ほどの時間がかかるとされており、その間に「申告ミスを見逃してしまう」というリスクが現実に存在しています。
国税庁としては、この“調査の空白”をなくすことが課題でした。そこで登場するのがAI。申告書が提出された時点で、過去のデータをもとに「これは調査すべき申告かどうか」を自動的に判断できる仕組みが整えば、調査のタイミングを逃すリスクも大幅に減らせます。
実はAIの導入は初めてじゃない
相続税分野でのAI導入は今回が初めてのように見えるかもしれませんが、実はすでに他の税目で先行導入されています。
国税庁は2018年からAIの実証実験を開始し、2021年には法人税・消費税の分野でAIが本格的に稼働を始めました。これらの分野では、例えば「売上と仕入れのバランスが極端」「一部の月だけ利益が急に落ちている」といった“不自然な動き”をAIが見つけ出し、調査対象として絞り込む仕組みが活用されています。
この成功事例をふまえ、「相続税にも応用しよう」というのが今回の方針です。実際、2023年からは相続税申告書のデータをAIが学習しており、2025年7月にはそのデータを活かしてスクリーニング(選別)が本格スタートします。
データで選ぶ“公平な調査”の実現へ
AIを使う理由は効率化だけではありません。もうひとつ大きな狙いは、「調査の公平性」です。
これまでの税務調査では、どうしても「資産規模が大きい人=調査対象になりやすい」という傾向がありました。これは職員が限られた時間の中で、効率よく税収を確保するために避けがたい事情でしたが、逆に言えば「資産が少ない人は見逃される」という不公平にもつながっていたのです。
AIは過去の不正事例や申告ミスのパターンを分析して、「金額の大小に関係なく、ミスの可能性が高い申告」を抽出することができます。つまり、富裕層に限らず、誰にでも等しく調査の目が届くようになるわけです。
このことは「怖い」と感じる人もいれば、「正直者が損をしない世の中になる」と歓迎する人もいるでしょう。
このように、国税庁がAIを導入する背景には、単なる技術の進化だけではなく、社会構造の変化や公平性の追求といった、さまざまな要素が関係しています。では、このAIは具体的にどのように申告内容を見て、どんな基準で「調査が必要」と判断するのでしょうか?
AIがどうやって“怪しい申告”を見つけるのか?
2025年7月から、国税庁は相続税の申告に対してAI(人工知能)によるチェックを本格的に導入します。このAIは、私たちが提出した相続税申告書をスキャンして「調査すべきかどうか」を判定しますが、一体どのような仕組みで“怪しい申告”を見つけるのでしょうか?
ここでは、AIがどこを見ているのか、そして何をもとに判断しているのかを、なるべくわかりやすく解説していきます。
すべての申告がAIのスクリーニング対象に
まず知っておきたいのは、2023年以降の相続税申告書はすべて、AIによるスクリーニングの対象になるという点です。スクリーニングとは、「たくさんある中から、気になるものを絞り込む作業」のこと。つまり、AIがすべての申告書をチェックし、その中から「これは調査が必要かも」と思う申告を自動的に選び出すのです。
相続税の申告は、年間およそ16万件ほどあります。AIはすでに数十万件分の過去の申告データを学習済みで、「どんな申告にミスが多いか」「どんな書類が怪しいか」といったパターンを把握しています。
AIは“申告内容”をスコアで評価する
AIによるチェックの特徴のひとつが、リスクスコアによる評価です。これは、提出された相続税申告書に対して、0.0〜1.0の間でスコアを付け、「この申告はどのくらい“怪しい”か」を数値化する仕組みです。
- スコアが高い(例:0.9)→ 調査の可能性が高くなる
- スコアが低い(例:0.1)→ 調査される可能性は低い
このように、数値で判断するため、調査先を選ぶスピードが一気に早くなり、かつ公平性も高まると言われています。
どんな申告がスコアを高くされやすい?
では、どんな相続税申告がAIに「調査が必要」と思われやすいのでしょうか?以下のようなケースが、リスクスコアが高くなりやすいとされています。
名義預金や名義株があるケース
たとえば「主婦で収入がないはずの奥さんの口座に多額の預金がある」といったケースでは、「これは実は亡くなった人の財産では?」と疑われる可能性があります。
財産評価が相場と大きくずれている
土地の評価額が近隣の土地と比べて明らかに安いなど、不自然な評価がされていると「過少申告(少なく見せる)しているのでは?」とAIが反応します。
特例の使い方に違和感がある
配偶者控除や小規模宅地の特例などの適用条件に、微妙なズレがあると「誤解や過信による誤適用」の可能性があると判断されます。
暗号資産・海外資産の記載がない
AIは「あるはずの財産が書かれていない」という情報にも敏感です。最近では、仮想通貨や海外口座も調査対象になっています。
活躍するのは「RIN(リン)」というAIツール
国税庁が実際に導入しているAIシステムは、「RIN(相続税選定支援ツール)」と呼ばれています。このRINは、申告書の内容だけでなく、国税庁がもともと持っている情報――たとえば保険金の支払調書、金地金の売買記録、財産債務調書など――も一緒に分析します。
RINは、申告書の内容がどれだけ“過去の不正申告パターン”に近いかを調べ、申告ごとにA〜Dのランクを付けます。
- Aランク:調査が最も必要とされる高リスク
- Dランク:リスクが低く、調査対象にならない可能性が高い
このように、経験豊富な調査官の“目利き”をデータ化し、申告内容と照らし合わせて判断するのが、RINの大きな特徴です。
AIだからこそ見逃さない“わずかな異常値”
AIの強みは、「人間では気づかないような細かなズレ」にも敏感であることです。
たとえば…
- 同じ地域の人たちと比べて、保険金の金額だけが異常に多い
- 一部の財産が不自然に評価されている
- 昨年と比べて財産の推移が急激すぎる
こうした“異常値”は、調査官が過去の経験で感じ取る「違和感」でしたが、AIならその感覚をデータで再現できます。
調査対象は「誰でもなり得る」時代へ
これまで相続税の調査といえば「資産家が狙われるもの」というイメージがありました。しかし、AI導入により、調査の基準が「資産額」ではなく「ミスや不自然さの有無」に変わってきています。
つまり、金額が小さくても、申告にミスがあれば調査対象になり得るということ。逆に、財産が多くても正確に申告されていれば、調査される可能性は低くなるのです。
2025年7月以降、私たちの申告はAIによってスコア化され、自動的に“調査の要否”が判断されるようになります。こう聞くと少し怖い気もしますが、正しく申告できていれば心配することはありません。
AI時代の相続税申告、納税者に求められる「備え」
AI(人工知能)が相続税申告を自動でスクリーニングする時代が、2025年7月から本格的に始まります。これまでは人間の調査官が時間をかけて行っていた「怪しい申告」の見極めが、AIによって一瞬で判定されるようになるのです。
これによって、「人間の目をすり抜けたから大丈夫だった」という時代は終わります。これからの相続税申告には、より一層“正確さ”と“透明性”が求められます。
では、私たちはこのAI時代にどう備えればよいのでしょうか?ここでは、相続税申告でトラブルや調査を避けるための実践的な対策を紹介します。
「正しい申告をすれば安心」は本当。でも落とし穴も
まず大前提として、正しく申告していればAIに選ばれることは基本的にありません。リスクスコアが低くなり、調査の対象外とされるからです。
しかし、多くの人が思い違いしてしまうのが、「自分は正しく申告したつもり」でも、実は見落としや誤りがあったケースです。
たとえば、以下のような「ありがちなミス」があります:
- 評価の仕方を間違えていた(特に土地や非上場株式)
- 名義預金があるのに、その意味を理解せずに申告していない
- 生命保険や退職金など、税法上の扱いが異なる資産の申告漏れ
- 小規模宅地等の特例を使えると勘違いしていた
- 海外資産や暗号資産の申告を忘れていた
これらは、どれも意図的ではなく、「知らなかった」「見落とした」「判断が分かれる」といった理由で起こりがちなものです。しかし、AIはそれを“リスクが高い申告”と判断し、調査の対象にしてくる可能性が高くなります。
相続税に強い税理士に相談することが最大の防御
相続税の申告は、他の税金(たとえば所得税や消費税)と比べても、はるかに複雑です。申告書の書き方も、財産の評価方法も、特例の適用条件も、専門的な知識が必要です。
そのため、「とりあえず近所の税理士さんにお願いした」というだけでは不十分な場合もあります。特に次のような財産が含まれている場合は、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
- 複数の土地(評価に差が出やすい)
- 上場・非上場株式(名義と実質の区別が難しい)
- 暗号資産(取引履歴や評価額の確認が複雑)
- 海外の銀行口座や不動産(資料の取得と評価に時間がかかる)
「税理士=どの分野でも対応できる」わけではありません。相続税申告に慣れている税理士ほど、評価方法や特例に強く、AIに“怪しまれない”申告書を作ってくれます。
財産の棚卸しと書類整理は早めに
AIは過去のデータをもとに、財産の種類や金額、提出された書類を細かく分析します。そのため、申告する側の準備不足がミスや漏れに直結します。
以下のような準備は、なるべく早めに行っておくことをおすすめします。
- すべての財産をリストアップする(預金、不動産、株式、保険、車など)
- 名義が違う財産も確認(家族名義の預金や株など)
- 過去の贈与記録を整理(贈与税の申告書や通帳履歴)
- 証明資料をそろえる(残高証明書、不動産登記簿、契約書など)
資料が足りなかったり不備があると、AIは「不明点が多い=リスクが高い」と判断する可能性があるため、抜け漏れのないよう丁寧に確認しておきましょう。
特例や控除は“使えるかどうか”を慎重に判断
相続税にはさまざまな特例や控除制度があります。たとえば「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」「障害者控除」などがありますが、条件を誤って使ってしまうと、逆に“過少申告”と判断されてしまいます。
特例の適用条件は、実はとても細かく、「実際に住んでいたか」「どれくらいの期間だったか」「被相続人との関係はどうだったか」などを厳密に確認する必要があります。
この点も、経験のある専門家と一緒に判断するのが確実です。自分では大丈夫だと思っていても、国税庁やAIの視点では「条件を満たしていない」とされる可能性があります。
書類提出後も安心しきらないことが大切
相続税の申告は、一度提出すれば終わりではありません。申告から約1年後、突然税務署から調査の連絡が来ることがあります。特に、これからはAIが「怪しい」と思った申告に絞って選ぶため、その可能性はより高くなります。
逆に言えば、提出したあとの過ごし方も含めて「備え」が必要な時代です。
- 提出後も、申告書や関連書類はきちんと保存しておく
- 調査連絡が来たら慌てず、提出した税理士や専門家に相談する
- 万が一ミスがあっても、意図的でなければ事情を説明することが重要
AIが申告書を自動で判定する時代は、ある意味では「正直者が評価される時代」ともいえます。ですが、申告内容の正確さを担保するには、知識と準備、そしてプロのサポートが欠かせません。
相続代行サービスの役割と安心感
相続税の申告にAI(人工知能)が本格導入される時代。正しく申告していれば基本的に問題ないとはいえ、専門知識が求められる場面も多く、初めての方にとってはやはり不安がつきまとうものです。そんな時に、強い味方になってくれるのが「相続手続き代行サービス」です。
ここでは、相続代行サービスがどのような役割を果たし、どんな人におすすめなのか、そしてAI時代にどのような安心を与えてくれるのかについて、わかりやすくご紹介します。
相続は「手続きの山」――すべてを一人でこなすのは大変
相続というと、「相続税を払えば終わり」と思いがちですが、実際はその前後に多くの手続きが発生します。
たとえば、こんな作業があります:
- 戸籍・住民票などの書類を集める
- 銀行口座の凍結解除・残高証明の取得
- 不動産の名義変更手続き
- 車の名義変更
- 株式や投資信託の相続手続き
- 相続人全員の同意を得るための遺産分割協議
- 相続税の申告・納付
どれも1つ1つが煩雑で、役所や金融機関、法務局など複数の窓口を回らなければなりません。しかも、慣れない専門用語が多く、期限も限られているため、途中で手続きが止まってしまうこともよくあります。
相続代行サービスは「全部まとめてお任せ」できる心強い存在
相続代行サービスとは、こうした相続に関するさまざまな手続きを、1つの窓口で一括して対応してくれるサービスです。
たとえば、「遺産相続手続まごころ代行センター」のような全国対応型のサービスでは、以下のようなサポートが受けられます:
| サポート内容 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍や住民票の収集 | 被相続人や相続人の戸籍を代わりに集める |
| 銀行・証券会社とのやり取り | 口座の凍結解除、残高証明取得などを代行 |
| 不動産・自動車の名義変更 | 登記や陸運局への申請もすべてお任せ |
| 相続税申告のサポート | 相続税に強い税理士との連携で対応 |
| 相続人間の話し合い支援 | 中立的な立場でのファシリテーションも可能 |
手続きが複雑化する一方で、忙しいご遺族の時間と労力を軽減し、正確に進めることができるのが最大の魅力です。
AI時代の相続に必要なのは「正確さ」と「専門家の視点」
AIが相続税申告をチェックする時代では、「うっかりミス」や「見落とし」が重く見られ、調査対象になりやすくなっています。
そのため、「とりあえず自分でやってみる」よりも、「最初から専門家と一緒にやる」ほうが結果的にリスクを下げられます。
特に相続代行サービスの良いところは、税理士・司法書士・行政書士などの各専門家と連携して対応してくれる点です。個人では見落としやすい財産や、評価方法の難しい土地なども、プロの目でしっかり確認してもらえるため、AIに“怪しまれない”申告を実現できます。
実際の相談者の声:「まごころ」で不安が安心に変わった
実際に相続代行サービスを利用された方の声をご紹介します:
「親が亡くなったあと、何から始めればよいのか分からず途方に暮れていましたが、まごころ代行センターに電話したら、すぐに状況を整理してくれて、必要な書類の手配や役所への連絡まで全部代行してくれました。相続税の申告もミスのないよう、税理士さんが丁寧に対応してくださり、安心できました」(50代女性・東京都)
「兄弟間で遺産分割がうまく進まず困っていましたが、センターの方が中立の立場で話をまとめてくれたおかげで、感情的にならずに協議を進めることができました」(40代男性・大阪府)
こうしたサポートがあることで、ご家族は気持ちの整理に集中できるとともに、後々のトラブルや調査の不安からも解放されます。
「自分はまだ先の話」と思っている方にもおすすめ
相続はいつ起きるかわかりません。親や配偶者の急な病気や事故など、突然の出来事で始まるケースが多く、準備ができていないことが大半です。
ですから、「まだうちは関係ない」と思っている方でも、事前にどんな手続きがあるのかを知っておくこと、そして信頼できる相談先を知っておくことは、いざという時の安心につながります。
相続代行サービスの多くは相談無料ですので、気になることがある方は、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
AIの導入により、相続税の調査対象は公平かつ効率的に選ばれるようになりますが、それでも「人の目」「人のサポート」は欠かせません。
相続という大切な局面で、間違いのない申告とスムーズな手続きを進めるためには、専門家と一緒に、確実に、丁寧に取り組むことが最大の備えです。
相続代行サービスは、そのすべてをまるごと支えてくれる存在です。2025年のAI本格導入に備え、ぜひ一度「相続のプロ」に相談してみてはいかがでしょうか?
参考資料
税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(国税庁)