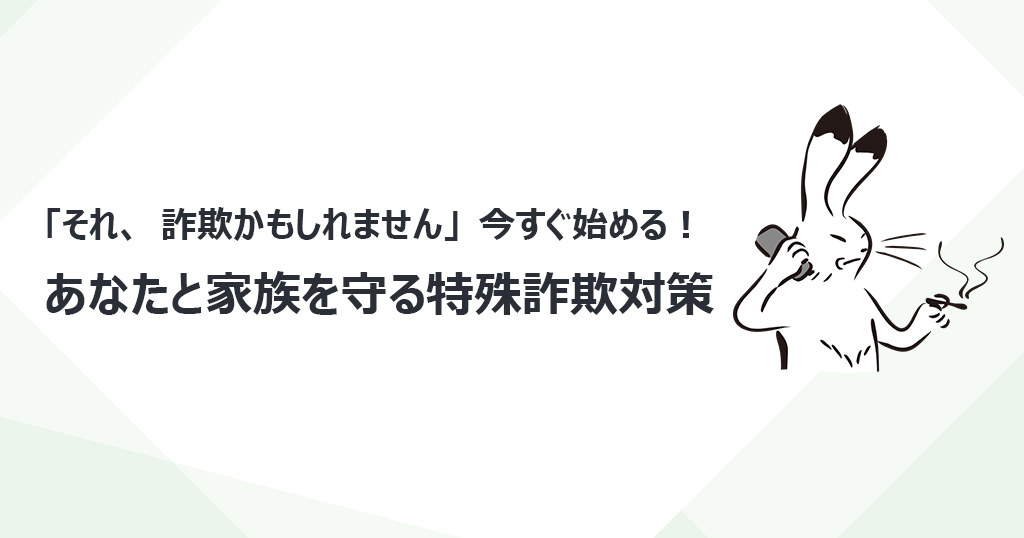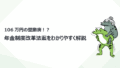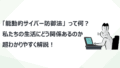「まさか自分が…」
これは、特殊詐欺の被害にあった多くの人が口にする言葉です。
特殊詐欺(とくしゅさぎ)は、犯人が直接あなたに会うことなく、電話やSNSなどを使って、うまく言葉で信用させ、お金をだまし取る犯罪です。
特に70代~の方々は、携帯電話やインターネットに不慣れなことが多く、詐欺グループから“狙いやすい”と見なされているのが現実です。
しかし、知っていれば防げるのがこの犯罪の特徴でもあります。この記事では、「どんな手口があるのか」「なぜ騙されるのか」「どう防ぐべきか」を一つひとつ丁寧に解説します。
特殊詐欺の特徴とは?
特殊詐欺は、犯人が顔を見せず、電話・メール・SNSなどを通じて騙すという特徴があります。
犯人は、さもそれらしく振る舞い、あなたの不安や信頼を利用してきます。
警察官、銀行員、息子、孫、弁護士、税務署職員など、肩書や立場を偽ってくるのが常套手段です。
その上で、被害者が自らATMを操作したり、キャッシュカードを渡してしまったりするように仕向けてきます。
ここで忘れてはいけないのは、「自分の意思で動いた」と錯覚させる巧妙な誘導があること。
つまり、ただ脅すのではなく、信じさせ、協力させることが彼らの手口なのです。
代表的な詐欺の種類とその手口
ここで、実際に多く報告されている代表的な手口を表でご紹介します。
名前を聞いたことがあるものでも、細かい特徴を知らないと簡単に騙されてしまう恐れがあります。
| 詐欺の種類 | 主な手口の内容 |
|---|---|
| オレオレ詐欺 | 息子・孫になりすまし、「事故を起こした」「会社のお金を使い込んだ」などと伝えて現金を要求する。 |
| 預貯金詐欺 | 銀行員や警察官を装い、「口座が不正に使われた」「カードを交換する」と言ってキャッシュカードを受け取りに来る。 |
| キャッシュカード詐欺盗 | 犯人が家を訪れ、カードを封筒に入れさせ、暗証番号とともにすり替えて盗む。 |
| 架空料金請求詐欺 | 「未納料金がある」とSMSやはがきを送り、電子マネーなどで支払わせる。 |
| 還付金詐欺 | 「医療費・年金の払い戻しがある」と言ってATMでの手続きを指示し、口座間送金でお金を騙し取る。 |
| SNS型投資詐欺 | SNSや広告を通じて「必ず儲かる」と勧誘し、ネットバンキングで高額な資金を振り込ませる。 |
| SNS型ロマンス詐欺 | 恋愛感情を利用して信頼させ、「結婚費用」や「病気の治療費」などの理由で金銭を要求する。 |
なぜ騙されるのか?人の心理をつく巧妙なテクニック
「自分は騙されない」と思っている方も多いと思います。
しかし、実際の詐欺事件では、“警戒していたはずの人”が被害に遭っているケースが多いのです。
その理由は、犯人が次のような心理テクニックを使ってくるからです。
犯人の主な戦術リスト
- 焦らせる:今すぐに振り込まないと取り返しがつかないと煽る
- 秘密にさせる:「内緒にして」と言って、家族や友人に相談させない
- 立場を偽る:息子や孫、警察官など、信じざるを得ない存在になりすます
- 一部だけ本当の情報を使う:本名、住所、家族構成などを言い当て、信頼を得る
- 感情に訴える:「お願い」「助けて」など、人情に訴えて冷静さを奪う
つまり、騙されるのではなく、“信じさせられる”のが本質なのです。
そして、それは年齢や性格に関係なく、誰にでも起こりうることなのです。
特殊詐欺に騙されないための基本行動3カ条
では、こうした巧妙な詐欺にどう立ち向かえばよいのでしょうか?
基本となる3つのポイントを押さえることで、被害は確実に防げます。
電話でお金の話が出たら、必ず一度切る!
たとえ「家族」や「役所」「警察」だとしても、電話で突然お金の話が出たら必ずいったん電話を切る。
そして、自分から本人に連絡して確認するか、家族に相談するのが最も安全です。
留守番電話・番号表示を必ず使う
- 非通知の電話は受けない設定にする
- 留守番電話を常にオンにして、メッセージを確認してからかけ直す
- 防犯機能付きの電話機を使う
これらを実行するだけで、犯人と直接話すリスクを大きく減らすことができます。
不安を感じたら、すぐに相談する
以下の公的機関は、ちょっとした不安でも親切に対応してくれます。
| 相談先 | 電話番号 |
|---|---|
| 警察相談専用窓口 | #9110 |
| 消費者ホットライン | 188 |
| 金融商品詐欺・未公開株相談 | 0120-344-999 |
迷ったら、「相談してみる」だけでも立派な防御策です。
「自分は大丈夫」が一番危険
特殊詐欺は、あなたの財布だけでなく、あなたの信頼・愛情・時間までも奪っていく卑劣な犯罪です。
しかし、事前に情報を知っていれば、被害をほぼ完全に防ぐことができる数少ない犯罪でもあります。
- 「電話でお金の話」は即切る
- 「一人で判断しない」で相談する
- 「知らない番号とは話さない」環境を作る
この3つを心がけるだけで、あなたも、そしてあなたの家族も、詐欺から守られる可能性は大きく上がります。
特殊詐欺の手口と具体的な対策
詐欺は“手口”を知るだけで防げる!
私たちは、「振り込め詐欺」や「オレオレ詐欺」という言葉を聞いたことがあります。
でも、その中身を正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか?
特殊詐欺の被害に遭う人の多くは、「そんなの知ってたつもりだったのに…」と口にします。
その理由は、手口がどんどん進化しているからです。昔のような単純な詐欺ではなく、今は巧妙でリアルな演出がされているため、気づかないうちに騙されてしまいます。
ここでは、最新の詐欺の手口と、その対策をセットで紹介します。
「知ってる」と「実際に防げる」は違います。読むことで、あなたの身を守る力がぐっと上がります。
代表的な詐欺手口6選とその対策
以下に、被害が多く報告されている6つの手口を詳しく紹介します。
それぞれに「対策」も記載していますので、実際に自分がその場にいたらどうするか?と想像しながら読んでみてください。
オレオレ詐欺(なりすまし詐欺)
手口の流れ
- 息子・孫などを名乗る人物から電話
- 「事故を起こした」「会社のお金を使ってしまった」といった内容でお金を要求
- 被害者が心配になり、指示どおり現金を用意して渡してしまう
使われる言い回しの例
- 「風邪をひいて声が変なんだ…」
- 「今日中に振り込まないと逮捕されるかも…」
- 「会社の人が取りに行くから現金を渡して」
対策ポイント
- 本人を名乗る電話が来たら、一度電話を切って、自分からいつもの番号にかけ直す
- 「合言葉」を家族で決めておき、本人確認に使う
- 電話の内容を録音できる防犯機能付き電話機を使う
還付金詐欺(お金が戻るふりをする詐欺)
手口の流れ
- 自治体職員や税務署職員を名乗る
- 「医療費の返還がある」「年金の還付がある」と連絡してくる
- ATMで手続きをさせ、逆に犯人の口座に送金させる
よくあるセリフ
- 「封筒を送りましたが、ご確認いただけていないようで…」
- 「還付には今日中の手続きが必要です」
- 「携帯を持ってATMへ行ってください」
対策ポイント
- ATMで“お金が戻る”ことは絶対にありません!
- 行政機関がATM操作を案内することも絶対にありません
- 「お金が戻る話」は一度切って家族か市役所に確認
架空料金請求詐欺(未納通知型)
手口の流れ
- SMSやハガキで「サイト利用料が未納」などと送られる
- 架空の法務省・裁判所名義で支払いを要求
- 電話をかけると「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」と言われる
対策ポイント
- SMSやハガキに書かれた番号には絶対にかけ直さない
- 本物の行政機関がコンビニでの支払いを求めることは絶対にない
- 不安なら警察や消費生活センターにすぐ相談
キャッシュカード詐欺盗(すり替え型)
手口の流れ
- 警察や銀行協会の名を語り「不正利用されている」と電話
- 「キャッシュカードを確認に行く」と訪問
- 本物のカードと偽カードをすり替えて盗み出す
対策ポイント
- 警察・銀行がキャッシュカードを取りに来ることは絶対にない
- 暗証番号を聞かれた時点で100%詐欺
- 「封筒に入れてください」「割印をください」は要注意!
SNS型投資詐欺(ネットで稼げる話は詐欺の入り口)
手口の流れ
- SNSで「無料の投資セミナー」「著名人の投資法」として接触
- LINEなどでグループに招かれ、儲け話が繰り返される
- 投資アプリを通じて振込をさせ、被害額は数百万円以上になることも
対策ポイント
- 「必ず儲かる」「あなただけに紹介」は詐欺の常套句
- 金融庁のサイトで業者名が掲載されているか必ず確認
- 個人名義の口座への送金は危険信号!
SNS型ロマンス詐欺(恋心を利用する詐欺)
手口の流れ
- マッチングアプリやSNSで知り合い、親しみを演出
- 「病気で手術費が必要」「投資で一緒に増やそう」と話を持ちかける
- 被害者の口座から何度も送金させる
対策ポイント
- 一度も会ったことのない人にお金の話をされたら要注意
- SNSで知り合ってLINEにすぐ移行する場合は警戒すべき
- 相談せずにお金を送る前に、必ず誰かに話す!
共通の防止策:「話さない」「相談する」「記録を残す」
全ての詐欺に共通する最大の防止策は、「犯人と会話しないこと」です。
通話録音・番号表示・非通知拒否などの機能を使い、そもそも会話を始めない仕組みを整えることが重要です。
また、「これは詐欺かもしれない…」と少しでも感じたら、恥ずかしがらずに家族に相談することが、自分を守る一番の方法になります。
「想定外」を「想定内」に変える
特殊詐欺の怖さは、「予想できないやり方で騙してくること」です。
しかし、あらかじめ手口を知っていれば、その“想定外”も“想定内”に変えることができます。
あなた自身のために、そしてあなたの家族や友人のために――
今日紹介した内容を周囲に伝えるだけでも、大切な人を守る第一歩になります。
特殊詐欺を防ぐには?
詐欺は“準備”で防げる時代です
特殊詐欺の手口は年々巧妙になっていますが、実はその対策も日々進化しています。
これまで紹介してきた通り、詐欺犯はあなたに「電話させる」「ATMを操作させる」「カードを渡させる」ことでお金を奪います。
でも裏を返せば――
「電話に出なければ、会話が始まらない」
「ATMに行かなければ、送金されない」
「カードを渡さなければ、お金は引き出されない」
つまり、行動の前にブロックする方法があれば、被害は防げるのです。
このセクションでは、そのための防犯対策や相談窓口、制度などを詳しく紹介します。
まずはこれ!今日からできる基本の防犯対策5選
特殊詐欺に対して最も効果があるのは、「犯人と話をしない環境を整える」ことです。
以下に、誰でもすぐに始められる基本的な対策を5つご紹介します。
留守番電話を常時オンにする
詐欺犯は録音を嫌がるため、電話が留守番設定になっているとすぐに切る傾向があります。
高齢者世帯では、普段から留守番電話を「常時オン」に設定しておくだけで、会話のリスクを大きく減らせます。
番号表示・非通知拒否サービスを利用する
固定電話には、相手の番号を表示させる「ナンバーディスプレイ」機能があります。
これに加え、「非通知拒否サービス」を使うことで、番号が表示されない相手からの着信をブロックできます。
| サービス内容 | 効果 |
|---|---|
| ナンバーディスプレイ | 誰からかかってきたかを電話に表示。怪しい番号を避けられる。 |
| 非通知拒否サービス | 非通知でかかってきた電話は自動でシャットアウト。 |
どの電話会社でも申し込み可能で、月額数百円で利用できるケースが多く、詐欺対策としてはコストパフォーマンス抜群です。
防犯機能付き電話機を導入する
最近では、「防犯アナウンス機能」や「自動通話録音機能」を備えた電話機が多く販売されています。
主な機能例:
- 着信前に「この通話は録音されます」と自動音声で警告
- 通話内容を自動で録音して、あとから家族と確認できる
- 着信履歴の保存・番号ブロック機能付き
これにより、犯人は電話をかけてもリスクを感じ、すぐに通話を切る傾向があります。
合言葉を家族で決めておく
オレオレ詐欺は「声が違うけど風邪をひいた」などと言い訳して、騙そうとします。
そこで有効なのが、家族だけに通じる“合言葉”を事前に決めておくことです。
例:
- 「ペットの名前は何?」
- 「初めて一緒に行った旅行先は?」
- 「父の日にもらったプレゼントは?」
合言葉を知らない相手なら、その時点で詐欺と分かります。
国際電話の利用を停止する
最近では、海外からの電話番号を使った詐欺も増えています。
普段、海外と電話をしないのであれば、国際電話の発着信自体を停止してしまうのが安心です。
これは電話会社に申し込むことで簡単に設定できます。
不安なとき、誰に相談すればいいの?
「これって詐欺かもしれない…」
そんな時に、頼れる公的な窓口も充実しています。
少しでも不安を感じたら、ためらわずに以下に連絡を取りましょう。
| 相談窓口 | 内容 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 警察相談専用ダイヤル | 詐欺の疑いがあるときに警察が助言してくれる全国共通番号 | #9110 |
| 消費者ホットライン | 消費生活に関する相談全般(詐欺・契約トラブルなど) | 188 |
| 未公開株通報窓口 | 株・金融商品関連の詐欺に関する専用窓口(日本証券業協会) | 0120-344-999 |
| 金融庁 | 投資や暗号資産などの被害報告先 | https://www.fsa.go.jp/ |
| 消費者庁 | 特殊詐欺対策、注意喚起ページを常時更新 | https://www.caa.go.jp/ |
ポイントは、「相談しても無駄」と思わないこと。
どんなに些細な疑いでも、実は他にも同じ被害が出ている“予兆”かもしれません。
迷ったら、これを確認しよう
「電話でお金の話が出たけど、本当に詐欺なのかな?」
そう迷ったときに、以下の5項目のいずれかに当てはまったら、即アウトです。
| チェック項目 | 危険度 |
|---|---|
| 電話で「今日中に振り込め」と言われた | 非常に高い |
| 家族を名乗る人が「番号が変わった」と言ってきた | 高い |
| 公的機関を名乗り「ATMで手続き」と案内された | 高い |
| 「内緒にして」と言われた | 非常に高い |
| コンビニで電子マネーを買わせようとされた | 非常に高い |
この表を家の電話のそばや冷蔵庫に貼っておくだけでも、判断力が高まります。
被害ゼロの鍵は「話さない仕組み」と「相談する習慣」
特殊詐欺は、あなたが「話し始める前」に止められます。
そして、「これって大丈夫かな?」と少しでも疑問に思ったときに、すぐに相談できる“癖”をつけることが最大の防御策になります。
- 留守番電話・番号表示・非通知拒否で“話さない仕組み”を
- 防犯機能付き電話や迷惑電話防止機器の導入を
- 相談先を「冷蔵庫・電話機の近く」にメモしておく
- 家族と「騙されないための合言葉」を持つ
- 電話が来たら“焦らず、いったん切る”勇気を持つ
この5つを守れば、あなたの家も、あなたの家族も、特殊詐欺の魔の手から遠ざけられるはずです。
実際の被害事例とその後
「うちは大丈夫」と思っていた家庭に起こったこと
特殊詐欺の怖さは、その被害が身近な場所・ありふれた家庭で突然起きてしまうことにあります。
ここでは、実際に報告された複数のケースをもとに、どのように被害が始まり、どんな結果になったのかを紹介します。
事例から学ぶことで、「自分だったらどうするか?」を考えるきっかけになるはずです。
ケース①:オレオレ詐欺(東京都・70代女性)
概要
ある日、女性のもとに「息子」を名乗る人物から電話がかかってきました。
「風邪をひいて声が変だけど…」と言い、「会社の金を使い込んでしまって、今日中に返さないとクビになる」と助けを求めてきました。
彼女は焦りながらも、「家には大金はない」と言いましたが、犯人は「上司が取りに行くから、できるだけ用意して」と迫ってきます。
不安になった女性は言われるがままに、自宅に訪れた“息子の上司”に現金100万円を手渡してしまいました。
結果とその後
後日、実の息子と連絡が取れて詐欺だと判明。しかし、犯人の足取りはつかめず、お金は戻ってきませんでした。
女性は「自分が騙されるなんて…」というショックでしばらく外出もできない状態に。
現在は、家族で合言葉を決め、防犯電話機を導入しています。
教訓
- 声が違っても「本人かも」と思い込んでしまう
- 電話だけで判断せず、必ず本人に折り返し連絡をする習慣を!
ケース②:還付金詐欺(茨城県・65歳男性)
概要
市役所の職員を名乗る男から「医療費の還付金があります。今日が期限です」と電話が来ました。
「携帯を持ってATMに行ってください。手続きの方法を電話で説明します」と言われ、ATMを操作するよう指示されます。
操作の指示通りに進めた結果、実際には犯人の口座に3回に分けて送金してしまい、合計約60万円の被害となりました。
結果とその後
家に戻って妻に話したところ、「そんなことはおかしい!」と通報。
しかし既にお金は引き出されており、返金は困難。
「手続きがわからない自分に優しくしてくれた人が、まさか犯人だったとは」と男性は悔しさを滲ませました。
教訓
- ATMで還付金がもらえることは絶対にない
- 公的機関がATM操作を指示することも絶対にない
- 迷ったら、一旦帰ってから誰かに相談すること
ケース③:SNS型ロマンス詐欺(大阪府・50代女性)
概要
SNSで知り合った“海外駐在中の男性”と毎日やり取りを重ね、次第に恋愛感情を抱くようになった女性。
ある日、「帰国したいけど手続きにお金がかかる」「一緒に住むために投資が必要」と頼まれ、合計300万円以上を送金。
その後も「送金すれば出金できる」と言われ続け、さらに150万円を振り込んだ直後、連絡が取れなくなりました。
結果とその後
家族が気づいて被害届を出しましたが、相手の身元もわからず、捜査は難航。
彼女は精神的ショックで1年近く人間不信に。
現在はカウンセリングを受けながら、自助グループに参加しています。
教訓
- 一度も会ったことのない相手に「お金」の話をされたら詐欺を疑うこと
- どんなに親しくなった相手でも、「恋愛」+「送金」は警戒を
「騙された」と言えない人が多い
多くの被害者は、「恥ずかしい」「自分のせいだ」と思い込み、周囲に言えなくなってしまいます。
でも、詐欺に遭ったことはあなたのせいではありません。
それよりも、早く相談し、同じような被害者が出ないようにすることが重要です。
被害を打ち明けることで得られるもの
- 再発防止:犯人の手口が警察に伝わり、他の被害を防げる
- 支援制度の活用:カウンセリングや支援団体によるサポートが受けられる
- 心の回復:周囲と共有することで、「自分だけじゃない」と感じられる
相談先・支援先一覧(再掲)
| 区分 | 窓口名・団体名 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|---|
| 警察 | 警察相談専用ダイヤル | 詐欺通報・相談 | #9110 |
| 消費者庁 | 消費者ホットライン | 消費生活全般の相談 | 188 |
| 心の支援 | 全国犯罪被害者支援ネットワーク | 被害者と家族へのカウンセリング | https://www.nnvs.org |
| 弁護士会 | 法テラス | 法的手続き・損害回復の相談 | 0570-078374 |
家族や地域の“声かけ”が命を救う
実際、多くの被害が未然に防がれているのは家族や銀行員、地域の人の「気づき」や「声かけ」です。
- 銀行員が「大金を振り込もうとしている高齢者」を止めた
- ご近所さんが「何度も宅配を受け取っている様子」に不審を感じた
- 子どもが「おばあちゃんの電話の様子」を変だと気づいた
こうした周囲の“ひとこと”で、被害が防がれている例は多数あります。
見て見ぬふりをせず、優しく声をかけることが、詐欺防止の鍵です。
「もしも被害に遭ったら」こそが大事
詐欺に遭ってしまったあと、一番大切なのは「これからどう立ち直るか」です。
お金の損失だけでなく、心のダメージや信頼の喪失は計り知れません。
だからこそ、自分を責めず、誰かに相談し、適切な支援を受けることが何よりも大切です。
また、こうした実例を周囲の人と共有することで、「自分も気をつけよう」「おじいちゃん・おばあちゃんに教えてあげよう」といった意識が広がります。
次の被害者を生まないために――。
それは、いまこの記事を読んでいるあなたの一言から始められるかもしれません。
これからの特殊詐欺対策
「防ぐ」のは、あなたひとりの責任ではない
ここまでのセクションで、特殊詐欺の手口や実例、防犯対策、相談窓口を紹介してきました。
お分かりいただけたように、詐欺犯は“人の感情”に付け込んで、巧みに信頼を得ながらお金を奪います。
つまり、被害を防ぐには情報や仕組みだけではなく、人と人との“つながり”や“見守り”も不可欠なのです。
この最終章では、家庭、地域、社会全体で詐欺を防ぐために、私たちが「今から」「無理なく」「続けられる」行動を提案します。
家庭でできる!日常の防犯習慣
特殊詐欺の多くは、家庭の電話から始まります。
つまり、「家の中でできる備え」こそが最も効果的です。以下の5つの習慣を家族で共有しましょう。
| 防犯習慣 | 目的 |
|---|---|
| 電話機に「非通知拒否・録音機能」を設定する | 詐欺犯との会話を事前にシャットアウト |
| 留守番電話を常時オンにする | 犯人が直接会話を始めにくくする |
| 合言葉を決めておく | なりすまし詐欺を見抜く |
| 通話内容をメモする | 後で家族や警察に説明できるようにする |
| 電話でお金の話が出たら一度切る | 落ち着いて考える時間を確保する |
さらに、冷蔵庫や電話の近くに「詐欺チェックリスト」や「相談窓口の番号」を貼っておくと、パニック時でも落ち着いて対応できます。
地域でできる!見守りと声かけ
特殊詐欺は家庭内で完結するケースが多いため、ご近所や町内会での見守り活動が極めて重要です。
一見「余計なお世話」と思えることでも、声をかけるだけで詐欺被害を防げることがあります。
地域でできる防犯アクション
- 高齢者宅に不審な電話がかかってきていないか、さりげなく確認する
- 銀行や郵便局で高齢者が大金を引き出そうとしていたら、職員が声をかける
- 自治会や町内会で、定期的に「詐欺対策勉強会」を開催する
- 防犯ポスターや注意喚起チラシを回覧板で共有する
- 見守りボランティアや地域包括支援センターと連携する
こうした取り組みは、「うちは大丈夫」と思っている人にも警戒心を持たせる効果があります。
特に一人暮らしや高齢世帯の多い地域では、ご近所同士の声かけが命綱になります。
社会としてできること:行政・企業の取り組み
国や自治体、企業でも特殊詐欺対策は進んでいます。
私たち一人ひとりが、こうした取り組みを知って活用し、広めていくことが大切です。
| 組織・機関名 | 主な取り組み内容 |
|---|---|
| 警察庁・都道府県警察 | SOS47プロジェクト/電話録音機の無料貸与/地域巡回・講演 |
| 金融機関(銀行・ゆうちょ) | ATMでの高額出金時に声かけ/不審な送金操作を検知して警察通報 |
| 電話会社 | 特殊詐欺対策サービス(番号表示、非通知拒否など)/迷惑電話フィルター機能の普及 |
| 消費者庁 | 啓発ポスター・テレビCMの配信/被害事例の公表と注意喚起 |
| 法テラス/犯罪被害者支援団体 | 精神的ショックに対するカウンセリングや法律相談の提供 |
おすすめサイト
あなたにもできる、周囲を守る3つの行動
ここまで読んでくださったあなたに、ぜひお願いしたいことがあります。
それは、「知識を周りに渡すこと」です。
周囲を守る3つの具体行動
- 家族や親しい人と情報を共有する
→ この記事の内容を話題にするだけでも効果的です。 - 詐欺の話題を“恥ずかしくない”雰囲気にする
→ 「実はうちにも変な電話があってさ」と日常会話で話せる空気をつくる。 - 防犯グッズや相談先を教えてあげる
→ 高齢の親や知人に防犯電話の使い方や、#9110などの相談先を紹介する。
「私には関係ない」と思わず、誰かの命と生活を守るために、今すぐ行動してみませんか?
詐欺を“防ぐ社会”をみんなでつくろう
特殊詐欺は、個人の注意だけでは限界があります。
でも、家庭・地域・社会が連携して行動すれば、被害を「ゼロ」に近づけることは可能です。
- あなたの家庭が「詐欺に強い家庭」になる
- 地域が「声をかけ合える安心のまち」になる
- 社会が「詐欺を許さない空気」に変わる
その第一歩は、「自分は大丈夫」ではなく、「自分が誰かを守る」意識を持つことです。
この記事が、あなたとあなたの大切な人を守る力となれば幸いです。
| 相談窓口 | 内容 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 警察相談専用ダイヤル | 詐欺の疑いがあるときに警察が助言してくれる全国共通番号 | #9110 |
| 消費者ホットライン | 消費生活に関する相談全般(詐欺・契約トラブルなど) | 188 |
| 未公開株通報窓口 | 株・金融商品関連の詐欺に関する専用窓口(日本証券業協会) | 0120-344-999 |
| 金融庁 | 投資や暗号資産などの被害報告先 | https://www.fsa.go.jp/ |
| 消費者庁 | 特殊詐欺対策、注意喚起ページを常時更新 | https://www.caa.go.jp/ |
参考情報
特殊詐欺対策ページ(警察庁)