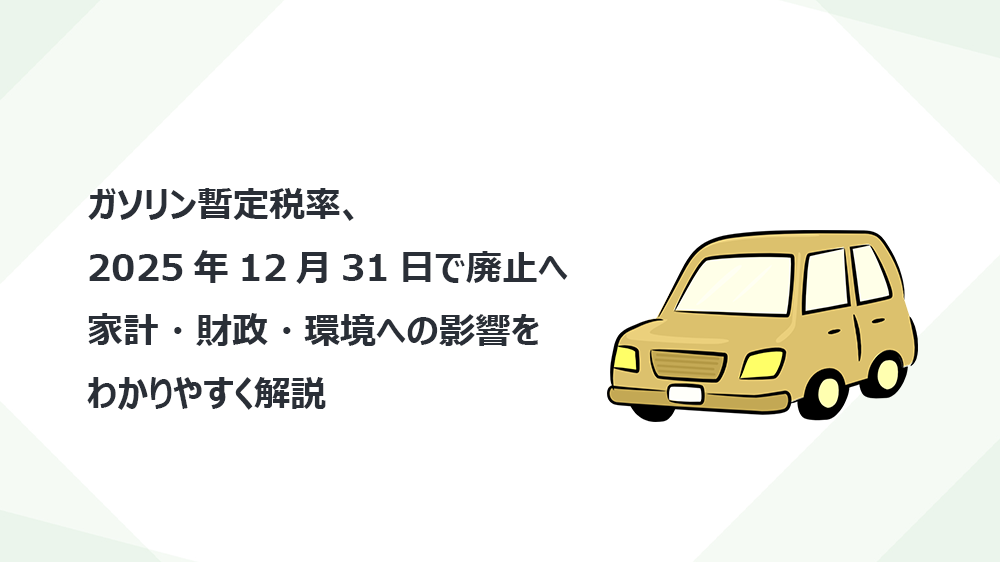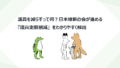ついに「ガソリン暫定税率」廃止決定
2025年10月下旬、政府はついに「ガソリン暫定税率」を2025年12月31日で廃止する方針を正式に打ち出しました。
長年にわたって議論されながらも続いてきたこの税制が、ようやく終わりを迎えることになります。
そもそもガソリン価格には、原油価格だけでなく「税金」が大きく関わっています。
その中でも特に注目されてきたのが「暫定税率」と呼ばれる上乗せ分。
一時的に導入されたはずのこの仕組みは、実は約50年もの間続いてきたのです。
この暫定税率が廃止されることで、ガソリン代は2026年から下がる見通しです。
「少しでも家計がラクになるかも」と感じる人も多いでしょう。
しかし同時に、「国や自治体の財政に穴があく」「環境政策に逆行する」といった懸念の声も上がっています。
今回は、
- 暫定税率がどんな仕組みなのか
- なぜ廃止が決まったのか
- 廃止後、わたしたちの暮らしにどんな影響があるのか
を、生活者の目線でわかりやすく解説していきます。
暫定税率とは?仕組みと導入の経緯
「ガソリン暫定税率」という言葉はよく耳にするものの、「実際に何のこと?」と感じる人も多いでしょう。
簡単に言うと、ガソリン税に上乗せされている“特別な税金”のことです。
私たちがガソリンスタンドで1リットル=170円などの価格で給油するとき、そのうちの約半分が税金で構成されています。
具体的には「揮発油税」や「地方道路税」といった税金が含まれており、その一部に「暫定税率分」と呼ばれる上乗せ分があります。
つまり、ガソリンの価格には、「本来の税金+上乗せされた税金」が含まれているのです。
この暫定税率が導入されたのは、1970年代の高度経済成長期。
当時、日本では車の保有台数が急増し、道路整備が追いつかない状況でした。
政府は「道路を整備するための特別な財源が必要だ」として、期間限定で税金を上乗せすることを決めたのです。
「暫定」と名づけられたのも、「道路が整えば不要になるはず」という前提からでした。
しかしその後も、道路整備や維持費、さらには財政難などを理由に延長が繰り返され、結果的に半世紀近く“暫定”が続くことになりました。
「一時的なはずが、いつの間にか恒久化した税」といえるでしょう。
ちなみに、ガソリン1リットルあたりの税金の内訳を見てみると以下のようになります。
| 区分 | 税額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 揮発油税 | 約28.7円 | 本来の税率 |
| 暫定税率分(上乗せ) | 約24.3円 | 今回廃止予定 |
| 地方道路税など | 約5.2円 | 地方向け財源 |
| 消費税(10%) | 約15円前後 | 税金にも課税 |
合計すると、ガソリン1リットルあたり約70円前後が税金として含まれています。
つまり、もし暫定税率分(約25円)が廃止されれば、理論上1リットルあたり25円ほど値下がる可能性があるのです。
なぜ今、廃止が決まったのか
半世紀にわたって続いてきた「暫定税率」。
それが、なぜ今になって廃止されることになったのか?
この背景には、ここ数年の「物価高」と「国民の負担感の高まり」が深く関係しています。
まず大きな要因は、ガソリン価格の高止まりです。
2022年以降、原油価格の上昇や円安の影響で、全国平均のガソリン価格は一時1リットル=180円を超えました。
政府は補助金(いわゆる「激変緩和措置」)で価格を抑えてきましたが、家計への負担感は依然として強いまま。
この状況で「税金を下げて直接的に価格を引き下げるべきだ」という声が強まったのです。
次に、政治的な流れも大きな後押しとなりました。
2025年は政権にとって重要な節目の年であり、「生活支援」「減税」「景気回復」がキーワードになっています。
ガソリン税は誰もが日常的に支払う“わかりやすい税”であるため、廃止は「国民に直接届く減税策」として注目を集めました。
また、政府・与党内でも「暫定」と言いながら恒久化してきたこの仕組みに対し、
「もはや制度としての整合性が取れない」という批判が根強くありました。
特に日本維新の会や立憲民主党など、野党側は長年「暫定税率の見直し」を訴えてきた経緯があります。
こうした政治的圧力も、今回の決定を後押しした形です。
さらに、エネルギー政策の転換期という点も見逃せません。
政府は今後、EV(電気自動車)やハイブリッド車の普及を進めていく方針を打ち出しており、
「ガソリン依存からの脱却」が国の大きな目標となっています。
その流れの中で、ガソリン税を見直すのは「時代の変化に合わせた税制改革」とも言えるのです。
こうして、
- 家計の支援
- 政治的なアピール
- 税制の整理整頓
- 脱炭素時代への転換
これら4つの要因が重なり、2025年12月31日での廃止という大きな決断につながりました。
2025年12月31日で終了、2026年から新税制へ
政府が発表した方針によると、ガソリンの暫定税率は2025年12月31日をもって正式に廃止されます。
つまり、2026年1月1日以降に給油するときには、この“上乗せ分”が消えることになります。
とはいえ、ガソリンスタンドでの価格が年明けからいきなり25円安くなるとは限りません。
税率変更に伴う調整には少し時間がかかるため、実際に値下がりを実感できるのは2026年初頭〜春頃になる可能性が高いと見られています。
では、暫定税率の廃止によってどれくらいガソリン価格が変わるのでしょうか?
現在、ガソリン税のうち暫定分は1リットルあたり約24〜25円。
この分がなくなることで、理論上は1リットルあたり25円前後の値下げが見込まれます。
つまり、50リットル給油すれば約1,200円前後の節約になる計算です。
毎月車に乗る人にとっては、年間数万円規模の家計改善効果が期待できるでしょう。
ただし、ここで注意すべきなのが「新たな税制の導入が検討されている」という点です。
政府は今回の廃止にあわせて、道路整備や環境対策の財源を確保するための新しい課税方式を議論しています。
候補として挙がっているのは、
- 「走行距離課税」(走った距離に応じて課税)
- 「炭素税」(CO₂排出量に応じて課税)
などです。
これらの新税は、ガソリンに直接課税するのではなく、「環境への負担」に応じて公平に徴収する仕組みを目指しています。
そのため、暫定税率廃止後も完全な“減税効果”が長く続くとは限らないという見方も出ています。
政府関係者によると、2026年度の税制改正では「新しいエネルギー課税体系」が本格的に議論される予定で、
2027年以降に新制度へ移行する可能性もあるとのことです。
まとめると、流れは次のようになります。
| 時期 | 主な動き | ガソリン価格の見通し |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 暫定税率が正式に廃止 | 現行価格が維持 |
| 2026年1月以降 | 暫定分の撤廃を反映 | 約25円程度の値下がり見込み |
| 2026年中 | 新税制(環境税など)を検討 | 徐々に再課税の可能性あり |
| 2027年以降 | 新しい課税制度が施行 | 税率が再調整される見通し |
つまり、2026年は一時的にガソリンが安くなる“節目の年”になる可能性があります。
ただし、その後は「環境」「財政」「公平性」をめぐって、再び税制が変化していくことも考えられます。
家計・企業・地方財政の視点で
ガソリン暫定税率の廃止によって、「やっとガソリン代が下がる!」と期待している人は多いでしょう。
実際、この政策は家計にとっては大きなプラスの効果をもたらす可能性があります。
しかし同時に、企業や自治体、そして国の財政には少なからぬ影響も生じます。
ここでは、そのメリットとリスクを3つの視点から整理してみましょう。
家計への影響:毎月の給油コストが軽くなる
ガソリン価格が1リットルあたり約25円下がると、車を日常的に使う家庭では年間数万円の節約効果が見込まれます。
たとえば、週に1回50リットル給油する家庭の場合、
25円 × 50リットル × 4回 = 月あたり約5,000円の負担減。
年間にすれば約6万円の節約になります。
物価上昇や電気代の高騰などで家計が圧迫されているなか、この減税は確実に家計の支えになるでしょう。
また、車通勤が多い地方在住の人ほど恩恵が大きくなると予想されます。
企業への影響:物流コストが減り、価格転嫁の抑制にも
物流や運輸、建設、農業など、燃料を多く使う業界にとっても今回の廃止は大きな朗報です。
軽油やガソリン代が下がることで、輸送コストの圧縮につながり、結果的に物価上昇の抑制効果も期待されます。
たとえば、トラック1台が年間で使用する燃料は数万リットルにも及ぶため、1リットルあたり25円の値下げは数十万円単位の経費削減になります。
その分を企業が価格に反映すれば、商品の値上げを抑える効果も出てくるかもしれません。
ただし、これも短期的な効果にとどまる可能性があります。
新しい環境税や炭素課税が導入されれば、再び燃料価格が上昇する可能性もあるため、企業は燃費効率化やEV導入など、長期的なコスト対策を進める必要があります。
地方自治体・国の財政への影響:年間2兆円の税収減に
一方で懸念されているのが、税収の大幅減少です。
ガソリンの暫定税率による税収は、国と地方を合わせて年間約2兆円規模。
その多くは道路の整備や維持管理、災害時の復旧などに充てられています。
この財源が失われることで、
- 地方の道路補修やインフラ整備が遅れる
- 災害時の対応予算が不足する
- 財政赤字がさらに拡大する
といった懸念も指摘されています。
政府は、これらの影響を最小限に抑えるために「新しい税源の確保策」を検討中です。
たとえば、電動車の普及が進む中で「EVにも何らかの課税を行うべきでは」という議論も出ています。
ただし、こうした制度設計には時間がかかるため、2026年は財政面の“つなぎの年”になると見られます。
三者の関係をまとめると
| 視点 | メリット | 懸念点 |
|---|---|---|
| 家計 | ガソリン代が下がり生活費が軽減 | 新税導入で再値上げの可能性 |
| 企業 | 燃料コスト削減・物価安定効果 | 長期的な税制再編で再コスト増 |
| 国・自治体 | なし(税収減が痛手) | 道路維持・財政再建への影響 |
このように、暫定税率廃止は短期的には“うれしいニュース”ですが、
長期的には「税収減をどう補うか」「環境政策とどう両立するか」という新たな課題が浮かび上がります。
環境政策とのバランス
ガソリン暫定税率の廃止は、家計にとってありがたいニュースである一方、環境政策との整合性という点では、少し複雑な問題を抱えています。
ガソリン価格が下がれば、どうしても車の利用が増え、結果としてCO₂(温室効果ガス)の排出が増える可能性があるからです。
政府はこれまで、「脱炭素社会」「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げてきました。
それなのにガソリン税を下げるのは、いわば環境政策と逆行する動きにも見えます。
実際、環境団体や専門家の中には「短期的な家計支援に偏りすぎている」と懸念する声も少なくありません。
では、政府はこの矛盾をどう解消しようとしているのでしょうか?
その鍵を握るのが、“新しい課税の仕組み”です。
炭素税(カーボンプライシング)への移行構想
政府は、暫定税率の廃止に合わせて炭素税(カーボンプライシング)の導入を検討しています。
これは、ガソリンそのものではなく、「CO₂排出量」に応じて課税する仕組みです。
排出量の多い企業や燃料に対して多くの税を課し、環境にやさしい選択を促す狙いがあります。
つまり、「走れば走るほど税金を払う」という発想から、「汚すほど税金を払う」という形へと転換していくわけです。
この考え方は、ヨーロッパではすでに主流になっており、環境保護と経済活動を両立させる新しい税体系として注目されています。
EVやハイブリッド車の普及を後押し
また、ガソリン価格が下がることで「ガソリン車が再び売れるのでは」との懸念もありますが、
政府は一方でEV(電気自動車)やハイブリッド車への補助金を強化する方針を示しています。
つまり、
- ガソリン車には税の優遇をやめる
- EVや環境対応車には支援を手厚くする
という“バランス型の政策”をとることで、
「ガソリン税を下げても脱炭素は進める」という姿勢を示しているのです。
海外との比較:環境税で価格を上げる国も
日本とは対照的に、ヨーロッパ各国ではむしろ燃料税を引き上げている国が多いのも現実です。
たとえばフランスやドイツでは、炭素税や環境負担金の導入で、ガソリン価格が日本よりも高い水準で推移しています。
これは「環境負荷を価格に反映させる」という考え方が社会に浸透しているためです。
その点、日本はまだ“移行期”にあります。
暫定税率の廃止は、短期的にはガソリン代を下げる施策ですが、長期的には「環境を軸とした新税制」へのステップとも言えるのです。
環境と家計、どちらを優先するか
結局のところ、この問題は「環境と生活のどちらを優先するか」という問いに行きつきます。
一時的にガソリンが安くなれば家計は助かりますが、長期的には地球温暖化対策に逆風が吹く可能性もあります。
政府は、家計支援と環境対策の両立を掲げていますが、どちらの効果を重視するかで政策の方向性が変わります。
今後の議論では、「負担の公平性」と「環境への配慮」をどう両立させるかが、大きなテーマになっていくでしょう。
各政党の反応と今後の議論
2025年12月31日でのガソリン暫定税率廃止方針は、政府・与野党の間でも大きな議論を呼んでいます。
「家計支援につながる」と歓迎する声がある一方で、「財源をどう確保するのか」「環境政策との整合性は?」という懸念も根強く、政党によって立場は分かれています。
自民党:財政との両立を重視、段階的な移行を検討
与党・自民党は、今回の廃止を「生活支援策の一環」として一定の理解を示しています。
ただし、同時に税収減による財政への影響を強く懸念しており、「一気にすべてをなくすのではなく、段階的に廃止していくべき」との声も上がっています。
特に道路整備やインフラ維持に使われている税収が大きいため、地方からは「廃止するなら代わりの財源を用意してほしい」という要望が相次いでいます。
政府・自民党は、2026年度以降の税制改正で「新しいエネルギー課税」を導入する方針を明確にしており、
「減税による景気刺激」と「財源の再構築」を両立させる形を模索しています。
公明党:環境税への転換に前向き
連立与党の公明党は、「生活支援」と「環境対策」のバランスを重視しています。
同党は以前から、ガソリン税の見直しについて「環境負荷に応じた新しい税制を導入すべき」と主張しており、
暫定税率廃止を炭素税導入のきっかけと捉えています。
また、公明党はEV普及や再生可能エネルギーへの投資促進も政策の柱に掲げており、
「ガソリン税を下げて終わりではなく、その先に持続可能な交通社会をつくるべきだ」という姿勢を取っています。
日本維新の会:早期廃止を高く評価
日本維新の会は、暫定税率の廃止に最も積極的な政党の一つです。
以前から「暫定の名に値しない」「国民負担を軽減すべき」として、
“即時廃止”を掲げてきました。
今回の政府決定に対しても「遅すぎるが方向性は正しい」と評価するコメントを発表。
同時に、「減税の効果を一時的なものにせず、行政コストの削減とセットで恒久的に家計を支援すべき」との立場を取っています。
立憲民主党:家計支援を評価しつつ財政再建に懸念
立憲民主党も、物価高対策としての廃止は「国民の負担軽減になる」と評価しています。
一方で、年間2兆円にのぼる税収減については「無計画な減税は将来世代へのツケ回しになる」と指摘。
そのため、廃止後の税収の使い道と新たな財源の確保策を明確にするよう求める姿勢を見せています。
国民民主党:段階的な減税と環境負担税を提案
国民民主党は、ガソリン価格の安定を重視しつつ、
暫定税率を「段階的に引き下げる」案を以前から主張してきました。
また、環境政策の観点からも、炭素税や走行距離課税の導入に理解を示しています。
つまり、「家計支援も環境もどちらも守る現実的なアプローチ」を取る政党と言えるでしょう。
今後の焦点:新税制と地方財源の再構築
各党が一致しているのは、「家計支援が必要」という点。
ただし、「その財源をどこから捻出するか」については意見が割れています。
政府は2026年度の税制改正に向けて、
- 環境税や炭素課税などの新制度設計
- 地方への財源移譲の見直し
- EV時代に対応したインフラ維持の仕組み
といった具体策を検討する予定です。
今後は、“減税の次の一手”が政治の焦点となっていくでしょう。
暫定税率廃止で“安くなる未来”は一時的かもしれない
長い間「いつまで暫定なの?」と疑問視されてきたガソリン暫定税率が、ついに2025年12月31日で廃止されます。
2026年からはガソリン価格が1リットルあたり20円台下がる見通しで、家計にとっては明るいニュースです。
しかし、その喜びは“永遠に続く”とは言い切れません。
家計は助かるが、財政は厳しく
一時的な値下がりによって、車通勤や買い物など日常の出費は確かに軽くなります。
家計の節約効果は年間で数万円規模にもなるでしょう。
ですが、その裏で国や地方自治体が得ていた年間約2兆円の税収が消えることになります。
この財源は道路の補修や橋の維持、災害対応などにも使われていたため、
「廃止すれば終わり」というわけではなく、次の財源をどうするかという課題がすぐに浮上します。
政府はすでに環境税や炭素課税などの導入を検討しており、
結果的に「別の形で税金がかかる」可能性は十分にあります。
環境と経済のはざまで
もう一つ忘れてはいけないのが、環境への影響です。
ガソリンが安くなれば、車の利用は増え、CO₂排出量も上がる可能性があります。
政府はこの点を補うために、電気自動車(EV)の普及支援や再生エネルギー投資を同時に進めようとしていますが、
これらの施策がどれほど早く実を結ぶかは未知数です。
つまり、今回の廃止は「環境負荷を増やさずに家計を支える」ためのバランスの試みとも言えます。
単なる減税ではなく、エネルギー政策の転換点として見ることが重要でしょう。
2026年は“過渡期”、新しい税制への始まり
2026年は、ガソリン価格が下がる一方で、次の税制の設計が本格化する「過渡期」になります。
2027年以降は、環境負担に応じた新たな課税(炭素税など)が段階的に導入される可能性もあります。
このように、今回の暫定税率廃止は“終わり”ではなく、エネルギー課税の新しい時代の始まりと捉えるべきかもしれません。