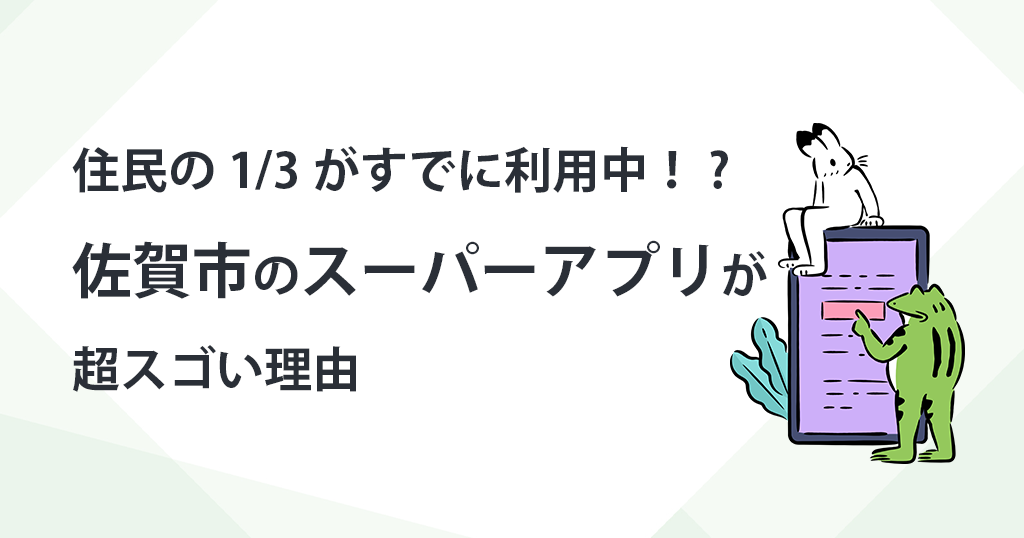佐賀市スーパーアプリ誕生の背景と狙い
佐賀市が公式にリリースした「佐賀市スーパーアプリ」は、いま自治体が進めるDX(デジタルトランスフォーメーション)を象徴するような取り組みとして、全国的にも大きな注目を集めています。そもそも「スーパーアプリ」とは、1つのアプリのなかに複数の機能やサービスをまとめて提供する仕組みのことをいいます。たとえば、民間の有名アプリでも、メッセージ機能の他に決済機能やタクシー予約などさまざまな機能を入れ子にしているケースがありますよね。「佐賀市公式スーパーアプリ」はまさしく自治体版のこうした構成になっており、市民が利用する行政サービスを一括してスマホに収めてしまおうというわけです。
一見すると「行政サービスのアプリ版」で終わりかと思われがちですが、佐賀市公式スーパーアプリには大きく分けて3つの意義があります。まず1つ目が、“誰一人取り残さない”行政サービスの提供です。従来は行政手続きや市の情報を取得する際、ウェブサイトを探したり窓口に行ったりと、多くのステップが必要でした。特に高齢者や子育て中の方、あるいは多忙な働く世代には、手間と時間のかかる作業です。そこで、すべてをワンストップ化したスーパーアプリを整備することで「わかりやすく・すぐ探せる・間違えない」利用環境を整え、より多くの市民が気軽に行政に触れられるようにしようとしています。
2つ目が、住民・地域・企業・行政が一体となって新しい地域価値を創り上げる「共創」の取り組みを強化することです。市の公式アプリというと、普通は“行政の一方通行的な情報発信”で終わりがちです。ところが、佐賀市スーパーアプリには、地域の人たちが投稿できる掲示板や、地元企業が参加できるミニアプリの枠組み、さらにはマイナンバーカードを活用した「デジタル市民証」など、多方面の連携を見すえて機能が設計されています。これは市や行政サービスを利用する市民だけでなく、地元のNPOや企業など、多くのステークホルダーが入り込みやすいプラットフォームになることを狙っています。
3つ目の意義は、行政データや民間データをフル活用する“本物のDX”を推進することです。佐賀市では庁内のデータを標準化・オープン化し、住民情報や各種事業のデータを将来的に連携させることで、災害対応やEBPM(Evidence-based Policy Making:証拠に基づく政策立案)などにも役立てようとしています。単なる電子化にとどまらず、データ分析による未来志向の施策立案にも生かす基盤づくりを進めているのです。
このような背景には、もちろん全国的に進む人口減少や財政難、そして行政手続きの効率化ニーズが存在します。佐賀市はこれら社会問題を解決する手段の1つとして、スーパーアプリという革新的な仕組みに挑戦し、他自治体と連携しながら全国的に波及させることを視野に入れているのが大きな特徴です。市長の積極的なリーダーシップと若手職員による横断組織を設置し、地元企業や大学、NPOとのコンソーシアムを結成することで、従来の縦割り行政の壁を取り払い、スピード感のある開発が実現しました。
こうした取り組みの成果として、「日本DX大賞2024」で優秀賞を受賞するなど、その先駆性や今後の発展性が大いに評価されています。さらに、2023年6月の本格稼働から早い段階でダウンロード数が飛躍的に増加した点も、佐賀市民をはじめ多くの人が関心を寄せている証拠と言えるでしょう。以上のように、「佐賀市公式スーパーアプリ」は単なる自治体のサービス集約アプリではなく、「地域社会を変革するDXプラットフォーム」として位置づけられているのです。中学生のみなさんが将来、このような先進的な取り組みにかかわる仕事につくとき、今回の佐賀市の挑戦はきっと良い参考になるはずです。

スーパーアプリの機能と特徴
「スーパーアプリ」と聞くと、スマートフォン上で大きなアプリが動いているイメージを抱くかもしれません。実際には、アプリの中にさらに多くの“ミニアプリ”が詰まっている構成になっており、利用者は必要に応じてミニアプリを使い分けます。これはいわば“デジタルの商店街”とでも言うべきもの。1つの入口をくぐると、多数の専門店(ミニアプリ)がズラッと並んでいて、好きな店に入れるという仕組みです。
佐賀市公式スーパーアプリに搭載されている機能は多岐にわたります。たとえば「ごみカレンダー」では、地区ごとに異なる燃えるごみ・資源ごみなどの収集日を表示し、しかも前日に通知を送る機能があるので、つい出し忘れをしてしまいがちな人にはうれしいサービスとなっています。また、「電子申請」機能を使えば、従来であれば書類を書いて、役所に行って提出し、職員とやり取りしなければならなかったものが、オンライン上で済ませられます。外出が難しいときやちょっと忙しいときなどは大助かりです。
さらに、図書館カードや市民証といった“紙の証明書類”もデジタル化され、アプリ内で提示できるようになりました。これにより、図書館に行くときも「カードを忘れちゃった!」という問題が減り、スマホさえあればスイスイと本を借りられるわけです。加えて、防災情報や災害時の避難所チェックイン機能など“もしものとき”に役立つ仕組みも充実しており、台風や大雨のときにリアルタイムで市からの通知を受け取ることができます。こうした防災面でのメリットは特に高齢者や車の移動が難しい方などにとって安心材料になりますよね。
「ミニアプリが互いに連携する」というのも、このスーパーアプリの特徴です。たとえば、ごみカレンダーが単独で動くだけではなく、地域の掲示板機能とつながって「○○地区では明日、燃えるごみの出し方について講習会をやります」といったお知らせがタイムリーに届く仕組みを作ることも可能です。アプリが単なる自治体情報の羅列ではなく、まちづくりの情報共有の場として発展していくことが期待されています。
さらに、「マーケティング」の要素も取り入れられる予定です。住民がどのようなサービスをどのタイミングで使っているのかをデータとして集約し、市民の困りごとを行政が先にキャッチできるようになるわけです。たとえば、図書館貸出の統計が上がれば、どの年代がどんな本を好むのか把握できるかもしれません。ごみカレンダーの利用状況がわかれば、ごみ減量のキャンペーンを効果的に実施するヒントになるでしょう。こうしたデータを使ったまちづくりの最前線が「佐賀市公式スーパーアプリ」には詰まっているのです。
スマホは日々の生活の中で“当たり前”のツールとなっているかもしれません。このスーパーアプリは、その“当たり前”に行政サービスを載せてしまおう、という発想です。市の大切な制度や情報って、正直なところ文字が多くて難解なイメージがあり、「なんだか敷居が高いなあ」と思うこともあるでしょう。しかし、こうした機能をアプリ一つで利用できるようになるなら、子どもから大人、高齢者まで誰でも使いやすくなります。「とりあえずこのアプリを入れておけば、佐賀市の情報は大体OK」となるわけです。
このように、佐賀市公式スーパーアプリの魅力は一言で言えば「ワンストップサービス+連携による拡張性」です。これが災害対応や観光促進など多方面で機能しはじめると、住民同士のコミュニケーション活性化だけでなく、地域経済の活性化にも貢献するでしょう。そしてこのモデルを他自治体へと展開していくことで、日本全体の行政サービスが“スマホで完結”するようになる未来が見え始めているのです。
実際の操作方法と利用シーン―ミニアプリの並べ替えや市民証きせかえ
さて、佐賀市公式スーパーアプリの話題は分かったとして、「実際にどうやって使うの?」と疑問を抱く方もいるでしょう。ここでは具体的な操作例と、どんなシーンで役立つかをご紹介します。中学生のみなさんにとっては、実際にスマホを操作しながら学ぶとイメージがつきやすいと思います。
まず、アプリをダウンロードしたら、ホーム画面に「ミニアプリ」と呼ばれるアイコンが複数並んでいるのを確認できます。たとえば「ごみカレンダー」「れんらくん(学校出欠連絡)」「天気予報」「災害・防犯情報」「観光情報」「イベントに参加しよう!」など、生活や学習に便利そうなミニアプリがそろっています。この並び順は自分の好みに合わせてカスタマイズ可能です。使う頻度の高いものをホームの上段に配置すれば、素早くアクセスできるメリットがあります。具体的には「ミニアプリ一覧」→「編集」というボタンをタップして、ホーム画面に表示・非表示させたいミニアプリを選択し、ドラッグ&ドロップで位置を変えます。最後に「保存」をタップすると完了です。
参考資料
ミニアプリの並べ替え(佐賀市)
さらに、ホーム画面上部にあるカード状の表示領域には「ごみカレンダー」「天気予報」「図書館利用カード」「デジタル市民証」などが左右にスライドして切り替わります。たとえば、図書館へ行く時はスッとスマホを取り出して、カード表示を切り替えてバーコードを見せるだけで本が借りられます。切り替えの仕方もスワイプ操作で直感的にできるのが便利です。
参考資料
デジタルカードの入れ替え(佐賀市)
そして、この「デジタル市民証」という機能が今後、さらに活用の幅を広げそうだと期待されています。現在は、イベントや避難所でチェックインする際にスマホの画面を読み取ってもらうことで、スムーズに本人確認ができる仕組みになっていますが、将来的には地域ポイントとの連動や、商店街での割引特典など、さまざまなかたちで「スマホひとつで生活できる」を実現するための基盤になるかもしれません。
また「デジタル市民証」の背景画像は、佐賀市にゆかりのある写真(バルーンフェスタやひまわり畑など)にきせかえられます。手順としては、市民証画面で歯車マークをタップし、「市民証のきせかえ」メニューからお好みの画像を選ぶだけ。13種類もの選択肢が用意されています。見た目も自分好みにアレンジすると、アプリを開く楽しみがちょっと増しますよね。
参考資料
佐賀市民証(デジタル市民証)の画像きせかえ(佐賀市)
具体的な利用シーンとしては、たとえば朝起きたら天気予報をチェックし、ゴミ出し日かどうか確認して、もしゴミ出し日なら「忘れずに捨てるぞ」と心の準備ができます。学校や職場に向かう途中、タブレットやスマホから地域のイベント情報をチェックして、放課後に参加してみようと計画を立てる。図書館で本を借りるときは画面を見せるだけ。もし雨が降りそうなら、災害情報のプッシュ通知で注意喚起を受けられる――といった具合です。何気ない日常のワンシーンを少しずつ便利に、効率的にしてくれるのが、このスーパーアプリの魅力なのです。
また、市民がアプリを自発的に使い、意見を投げかけられる「ご意見フォーム」も備わっているため、「こんな機能があったら便利だよね」「ここがちょっと使いづらい」といったフィードバックを市民自らが気軽に届けられます。運営側も年4回以上のペースで柔軟にバージョンアップを実施しているので、この先もどんどん進化していく予定です。まさに「みんなで創るアプリ」というわけですね。
このように、実際の操作方法はスマホに慣れた人ならすぐにわかるシンプルさでありながら、ミニアプリやカードの配置をカスタマイズし、デジタル市民証を活用することで、自分だけの“便利な役所窓口”を作れるところが最大のポイントです。ここにさらに新機能が追加されれば、住民生活はますます便利になり、佐賀市が掲げる「日本一便利なまち」へと近づいていくでしょう。
導入効果と今後の展望―住民・行政双方のメリット
佐賀市公式スーパーアプリのメリットは、市民目線と行政運営目線の双方から語ることができます。まず市民目線では、わざわざ行政サイトを検索したり役所へ足を運ばなくても、スマホひとつで手続きが進められるようになるため、時間と手間を大きく削減できます。たとえば、子育て世代が毎回役所に行く負担は相当なものですが、アプリ経由で申請や問い合わせが可能になれば、育児と手続きを同時進行せずに済むわけです。また、ごみ出しの通知や防災情報のリアルタイム配信は、誰にとってもありがたい機能といえるでしょう。高齢者の中にも「スマホは持っているが、使いこなせない」という方が多いのも事実ですが、今後は地域のIT講座などでスーパーアプリを活用することで、スマホの基本操作と同時に行政サービスの使い方も学べる機会が増えるかもしれません。
一方、行政運営の側から見ると、オンライン化によって窓口業務が効率化し、紙書類を減らせるメリットがあります。職員の業務負荷が下がることで、より住民に寄り添った相談対応や新しい施策づくりに力を注ぐ余裕が生まれる可能性があります。また、デジタル市民証や各種手続きデータが蓄積されれば、住民のニーズをより正確に把握し、将来的には「住民一人ひとりに合わせたきめ細かな行政サービス」を実現できるかもしれません。たとえば、子育て世帯には保育サービスや子ども向けイベント情報を自動的にプッシュ通知するなど、個別対応がさらにしやすくなるでしょう。
DX推進という観点でも、スーパーアプリの存在は大きいです。従来は各部署ごとにデータベースやシステムがバラバラで、住民が問い合わせるたびに手続きが重複する事態が起きていました。しかしスーパーアプリ上でIDやデータを統一すれば、一度登録した情報を繰り返し活用できるため、自治体内の業務効率化のみならず、将来的には民間サービスとも連携しやすくなります。たとえば、地元商店街のクーポン配信をアプリから行ったり、観光客向けの電子チケットを販売したりと、行政と地域経済の結びつきを強めることが可能になるでしょう。
また、「日本一便利なまち」を目指すという大きなビジョンを掲げる佐賀市は、このアプリを佐賀市だけで終わらせるつもりはないようです。すでに九州のほかの自治体でも同種の公式スーパーアプリを導入する動きがあり、佐賀市のプラットフォームを共同利用する形でコストを抑えつつ、高機能アプリを手に入れる仕組みが進んでいます。これにより、小規模自治体でもDXを加速させやすくなるわけです。もし全国の自治体に同様のアプリが広がれば、「引っ越ししたけど、スーパーアプリが同じだから使い方が共通で安心」といった利便性も期待できます。
さらには、2024年度には生成AIを活用した観光ルート提案や健康メニュー提案機能の実装が目指されています。従来のAIは特定のタスクに特化したものでしたが、生成AIなら「ユーザー個々のニーズや条件に合わせて、よりパーソナライズされた回答や提案をしてくれる」可能性があり、観光客が多い佐賀市の文化・自然・グルメ情報を混ぜ合わせて、驚きのプランを提示することも夢ではありません。そうなれば、行政アプリの枠を超えたエンターテインメント的な魅力が加わり、より幅広い層の利用を促すことができるでしょう。
今後の課題としては、高齢者やデジタルが苦手な層へのサポート強化だけでなく、デジタルデバイドを埋める取り組みが欠かせません。また、個人情報保護やセキュリティ対策も重要であり、住民が安心して使える環境をどれだけ整えられるかがカギになります。しかし佐賀市の取り組みは、こうした課題の解決策として「市民参加型の開発体制」を敷き、ご意見フォームからの要望を優先的にアプリ改善に取り込むなど、常にアップデートを重ねている点に強みがあるのです。まさに「動きます、佐賀市」という言葉が象徴するように、改良を続けていく姿勢が頼もしいところといえます。
住民参加と今後の可能性―日本のDXを前へ進める佐賀市スーパーアプリ
最後に、佐賀市スーパーアプリの本質的な意義と、そこから広がる未来について考察してみましょう。先に述べたように、このアプリは単なる行政手続きのデジタル化ではなく、「みんなで創るアプリ」という点に価値があります。行政と住民が一緒にアイデアを出し合い、新機能を追加し、課題を解決していくプラットフォームとして機能しているのです。
例えば、市民から寄せられた意見として「もっと子育て関連の情報をまとめてほしい」「公共交通と連動して、バスの時刻表や乗り換え案内と連携してほしい」などがあれば、それをもとに新しいミニアプリが開発されたり、既存の機能が改善されたりします。こうしたアップデートを継続することで、本当に市民の声に寄り添った仕組みになっていくわけです。従来の行政サービスは、どうしても“一般化された制度”を市民が受け取るスタイルでしたが、スーパーアプリでは市民が提案者の立場になり得るというのが新鮮です。
また、行政サイドからみても、アプリを通じて多様なデータを収集し分析することで、新たな政策立案の材料を得られる期待があります。たとえば、「市内のどのエリアでどんなイベントが人気なのか」「どの年代がどういう申請を多くしているのか」をリアルタイムで把握することが可能です。これによって、その地域や年代に合った施策を打ち出せるため、的確な予算配分やサポートがしやすくなるでしょう。こうした“エビデンスに基づく政策立案”は、日本全体の自治体が抱える課題でもあり、佐賀市の事例は重要な先行モデルとなり得ます。
さらに、共同利用やシステム共有という考え方は、他自治体にも波及可能なスキームです。佐賀市が構築したシステムをベースに、別の市町村が独自のミニアプリやデザインを追加して“自分たちの公式スーパーアプリ”を作れば、大幅なコスト削減と開発スピードの向上が見込まれます。これは日本全体の行政DXの底上げにつながり、国が掲げるデジタル田園都市国家構想とも親和性が高いアプローチです。「自治体公式スーパーアプリ」が当たり前になれば、引っ越し先でも仕組みがほぼ同じというメリットが生まれ、全国的にデジタル行政の標準化が進む可能性があります。
また、今後は生成AIの実装により、“利用者一人ひとりが必要としている情報やサービスを見極めて適切に提供する”次世代のパーソナライズが実現するかもしれません。子ども向けには学習支援アプリ、高齢者向けには健康増進や医療連携機能といったように、AIがユーザーの状況を予測してベストな提案をしてくれる未来が想定されます。AIと聞くと少し難しく感じる人もいるかもしれませんが、スーパーアプリのUI(ユーザーインターフェース)さえわかりやすく設計されていれば、利用者は特別な知識がなくてもごく自然にその恩恵を受けられます。
佐賀市公式スーパーアプリは、現時点でも約3分の1の市民が利用しているとされ(今後も増加が見込まれます)、デジタル市民証の登録者数では50代以上が半数を占めるなど、ITに苦手意識を持つ層まで取り込めている点が注目されます。市民同士が教え合う文化が生まれ、イベントや講座を通じてデジタルリテラシーを底上げする動きも出てきているようです。こうした“共に学び、共に創る”土台があるからこそ、スーパーアプリという壮大な挑戦が定着し、さらなる発展を期待できるのでしょう。
結局のところ、この佐賀市の挑戦は「アプリを導入すれば何でも解決」という単純な話ではなく、行政・住民・地域・企業が一緒にDXを進める“共創”を生む仕掛けづくりにあります。市が“何かしてあげる”ではなく、みんなが“当事者”となり、最終的に「住みやすいまち」を形作っていく。それこそが「佐賀市公式スーパーアプリ」が日本のDXを前へ前へと進める大きな原動力になるのです。