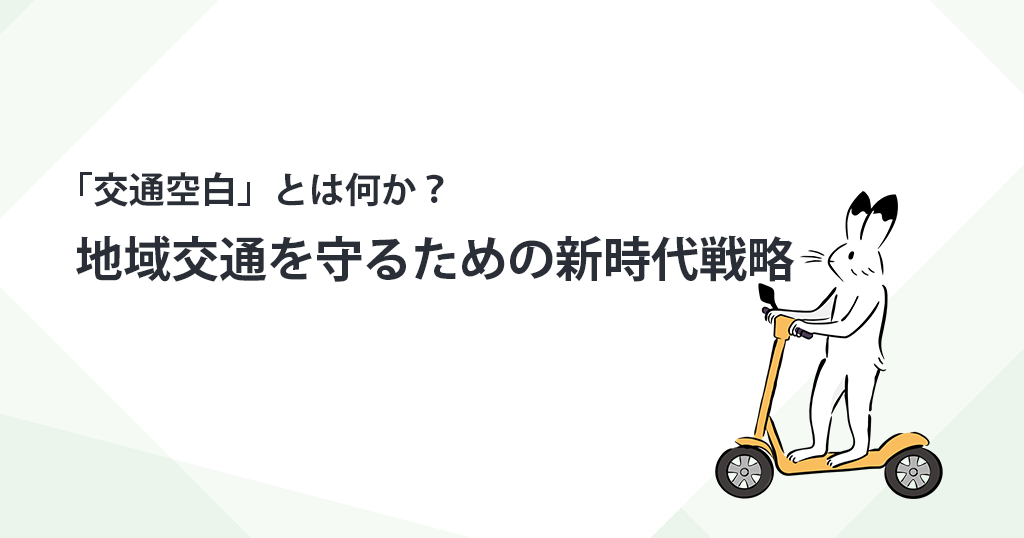交通空白とは何か
「交通空白」という言葉の意味
「交通空白」とは、地域の住民や観光客など、移動手段を必要とする人々が十分に公共交通やタクシーなどを利用できない状態を指す言葉です。国土交通省は、バス停や駅が近くになく、タクシーを30分以内に呼ぶことが難しい地域や、運行本数が極端に少なく移動手段として使い勝手が悪い地域を「交通空白」と位置づけています。
このような状況は、たとえば「自分の家からバス停や駅まで何キロも離れている」「タクシーが呼べると言っても、30分以上も待たなければならない」などのケースが典型的です。地域住民のみならず、旅行者や観光客にとっても、移動が難しい場所といえます。
交通空白が広がる背景
日本では少子高齢化や過疎化が進む地域が増え、従来のバス路線や鉄道路線が廃止・減便に追い込まれるケースが相次いでいます。さらに、コロナ禍による観光需要の激減でタクシーやバス事業者の経営が悪化し、働き手(運転手)不足が深刻になったことも、「交通空白」の一因となっています。
一方で都市部ではインバウンド(外国人観光客)の需要が回復し、高速鉄道や空港がある地点は観光客でにぎわうのに、その先の移動手段が確保できないために旅行者が少ないまま…という地域も少なくありません。こうした“繁忙部と過疎部”の差が、さらに「交通空白」の深刻化を招いているともいえます。
交通空白がもたらす問題
交通空白が起こると、地域の住民や高齢者、運転免許を返納した方などが買い物や通院に困るだけでなく、観光客にとっても「そこへ行きたいけれど、足がないから諦める」という状況が生じ、地域経済の活性化を妨げる要因にもなります。
また、大きな工場を誘致して一時的に人口が増えたとしても、公共交通やタクシーの供給が追いついていないと深刻な交通渋滞が起きるなど、地域全体のくらしを支えるインフラが整わないまま拡大してしまい、結局はその地域に定着しにくいという問題にも繋がります。
交通空白をめぐる最近の動き
こうした問題を受けて、国土交通省は「交通空白」解消を目指すために令和6年7月17日に「交通空白」解消本部を立ち上げて本格的な対策を開始しました。特に、タクシー事業者やNPO法人、自治体が自家用車や一般ドライバーを活用して有償運送を行う「公共ライドシェア」や「日本版ライドシェア」と呼ばれる仕組みを普及させるべく動いています。これは、乗合タクシーやAIオンデマンドバスなどの仕組みと組み合わせて使うことで、「公共交通が機能しにくい過疎部・観光地の足を補う新しい交通システム」として注目されています。
交通空白という言葉は、一見専門的に聞こえますが、実は私たちの身近な地域社会や観光地において起きている深刻な課題のひとつです。人口減少・高齢化が進み、コロナ禍でバスやタクシーの運転手不足が顕在化したことで、地域の住民の「生活の足」、旅行者の「観光の足」が確保できなくなる現象が各地で進んでいます。
この課題への本格的な取り組みとして、ライドシェアや乗合タクシーなど多様な交通手段の仕組みを導入しようという動きが国や自治体の間で活発化しており、まさに今、大きく状況が変わろうとしているところです。
交通空白の具体的な背景と事例
人口減少・高齢化と交通の縮退
交通空白の主な原因の一つとして挙げられるのが、人口減少と高齢化に伴うバスや鉄道など公共交通サービスの縮退です。地域の人口が減れば、乗客が少なくなり、路線の運行経費をまかなえなくなります。その結果、バスや鉄道の便数が削減され、さらに住民が車に頼るようになると、利用者の減少に拍車がかかり、最終的には路線廃止に至る悪循環が生まれます。
また高齢者が多く暮らす地域では、自家用車を利用できない住民が増えるため、公共交通に頼りたいのにその公共交通がなくなってしまうという深刻な事態となります。
コロナ禍による観光客の変動と需給の不一致
近年、コロナ禍からの回復で観光業は徐々に盛り上がりつつありますが、訪日外国人は東京や大阪、名古屋など大都市圏への滞在が多いという偏りが見られます。一方で地方の観光地は訪れる人が依然として少ない場合があり、その少ない需要に合わせて地元タクシーやバスの供給体制が縮小されたままのところもあります。
ところが、いざ大型イベントや観光シーズンが来ると、一時的に観光客が増えて「タクシーやバスが捕まらない」という逆の現象が起きます。これもまた需給のミスマッチで、「観光の足」が確保できない一因となっています。
産業構造の変化と交通渋滞
交通空白の問題は「車がない」「路線がない」というだけでなく、「車がありすぎる」ことも問題になる場合があります。具体的には、たとえば工場誘致によって急速に人口や車の台数が増えた地域で、従来は自家用車がないと暮らせなかったため公共交通が整備されておらず、多くの人が車で移動するしか選択肢がない状態です。
その結果として通勤時間帯に大渋滞が発生し、バスなどがあっても遅延が常態化するため、利用者がさらに減ってしまう。その結果、公共交通が縮小するという別の悪循環が起きるのです。
具体的な地域事例
- 熊本県の半導体工場周辺: 台湾の大手企業が工場を新設し、従業員向けの住環境が整備されつつある一方で、もともと公共交通の便が悪く通勤ラッシュの渋滞が深刻化しているという話があります。このケースでは、新たにバスの増便やライドシェアの導入を検討するだけでなく、通勤ラッシュのタイミングを分散させる働き方改革も大きなテーマとなっています。
- 小松市の夜間帯の交通: 石川県小松市では、新幹線駅や空港があるものの、夜間に移動手段が不足していたため、公共ライドシェアを導入して木曜から土曜にかけて夕方から深夜まで運行できるようにした事例があります。地域住民や観光客だけでなく、地震で被災した方の移動手段確保にも役立っています。
人口減少・高齢化、観光需要の偏在、産業構造の変化…こうした要因が複雑に絡み合った結果として生じる「交通空白」は、一度生じると利用者数がますます減り、事業者も撤退せざるを得ないという深刻なサイクルを生み出します。すでに少なくなってしまった交通資源を回復させるには、多様なアプローチが必要です。自治体や交通事業者だけでなく、地域の住民が主体的に関わるライドシェアや、産業界が協力して「貨客混載」を行うなど、新しい形の公共交通の模索がいま急務となっています。
国土交通省の「交通空白」解消本部とライドシェア施策
国土交通省「交通空白」解消本部の概要
国土交通省は2024年7月頃から、人口減少や高齢化、観光需要の偏りによって生じる「交通空白」の解消に向けた特別な体制として「交通空白」解消本部を立ち上げました。大臣を本部長とし、副大臣や各局長、地方運輸局の長などが参加する形で、バスやタクシー、鉄道、さらには観光庁など幅広い分野の幹部が集まり、全国的な解消を目指しています。
この本部では「日本版ライドシェア」「公共ライドシェア」の普及、そして主要駅や空港といった「交通結節点」から観光地などへのアクセスを強化することを柱に、各自治体への伴走支援を実施しています。
「公共ライドシェア」とは
「公共ライドシェア」は、過疎地や高齢化が進む地域など、一般的なバス路線の維持が困難な地域を対象に、市町村やNPO法人などが主体となって、自家用車で人を有償運送する仕組みです。乗合タクシーの一種ですが、二種免許を持たない一般ドライバーが自治体の管理のもとで安全対策を講じながら運行できるという特徴があります。
- 熊本県水上村の例では、路線バスが通っていない地区と公立病院を結ぶ送迎を、村が運営する形で週2回ほど実施しています。運賃は500円に抑え、地元住民には経済的負担を軽く、かつ安定的に通院をサポートする形を実現しました。
- 石川県小松市では、夜間帯の公共ライドシェアを導入し、観光客や住民の「夕方以降の足」を確保するとともに、能登半島地震での被災者支援にも役立てています。
「日本版ライドシェア」とは
「日本版ライドシェア」は、タクシー事業者が管理するもと、一般ドライバー(自家用車等)を活用して有償運送を行う仕組みです。
これは、需要が少ない地域や、イベント開催時など一時的にタクシーが不足する場面に合わせて、タクシー事業者が補完的に車両を増やすことで、ドライバー不足や車両不足に対応することを目指しています。例えば鳥取県で開催されたイベントでは、「とっとライドシェア」という枠組みを活用し、タクシー配車アプリや電話連絡によって利用者の需要に応える試みが実施されました。
ライドシェアにおける課題と期待
ライドシェアは、特に過疎地やイベント時などに強みを発揮すると期待されていますが、導入時には以下のような課題もあります。
- 安全管理: 二種免許が不要なため、タクシー事業者の管理や自治体の監督をどうしっかり行うか。
- 利用者の認知: 新しい仕組みなので、高齢者や観光客が「どう使えばいいのか」を知らない場合が多い。
- 運賃設定: 既存のタクシーとの価格競合や運転手の収入確保、制度上の運賃規定など。
これらを解決するために、国土交通省や自治体、そして交通事業者が協力して「安全運行のルールづくり」や「使いやすい配車アプリの導入支援」、運賃のダイナミックプライシングの導入など多様な対策を講じようとしています。
国土交通省が掲げる「交通空白」解消本部の大きな狙いは、全国約600の自治体でライドシェアが導入されていない現状を打破し、すべての地域でタクシーやライドシェアが利用できるようにすることにあります。さらに、主要駅や空港など約700箇所の「交通結節点」で二次交通が確保され、観光客やビジネス客がスムーズに各地へ移動できる状態を目指しているのです。
この動きが本格化したのは2024年以降ですが、今後3年間を「集中対策期間」と位置づけて全国的に解消を進める計画があり、多様なライドシェア事業のバリエーションが同時多発的に広がる見込みです。新たな運賃制度やIT技術を活用した配車システムなども次々と試されようとしており、“次世代の地域交通”がどのように定着していくのか注目が集まっています。
観光の足・働き手不足への対応策
観光地でタクシーがつかまらない問題
地方の観光地では、宿泊施設や観光スポットが点在しているにもかかわらず、駅からバス路線がない、あるいはタクシー会社が十分に車両を用意できないため、観光客が「せっかく来たのに移動ができない」という事態が生じています。特に、鉄道駅や空港から目的地までの「二次交通」が不足していて、多くの観光客がタクシーを探すのに苦労する場面が多いと指摘されています。
主要駅・空港からの「二次交通」強化
こうした問題を解決すべく、国土交通省は「主要交通結節点でタクシー等を確保する」という目標を立て、駅や空港周辺でライドシェアを普及させる取り組みを進めています。加えて、観光客が駅に到着したタイミングを把握してタクシーを自動手配するシステムや、航空便の到着時刻に合わせたシャトルバス運行など、デジタル技術を使った多様な工夫が試みられています。
具体例として「改札ピッでタクシー手配(群馬県高崎市)」のような施策があり、新幹線などの乗車券予約システムとタクシー配車システムを連動させ、列車が到着するとほぼ同時にタクシーを手配できる仕組みづくりが進められています。
働き手不足への多角的アプローチ
「交通空白」解消には運転手不足の解消も欠かせません。観光地だけでなく、地方のバス会社やタクシー会社は深刻な運転手不足に悩んでいます。そこで、既存のプロドライバーだけでなく、
- 一般ドライバーを活用: 日本版ライドシェアや公共ライドシェアで「ドライバー登録」を促進し、空き時間に旅客運送を担ってもらう。
- 貨客混載: ライドシェアドライバーが旅客輸送の合間に荷物配達を行うことで、運転手の稼働を上げると同時に運転手側の収入源も確保。
- 鉄道事業者など異業種との連携: 駅員がライドシェアのドライバーとして出向し、オフピークや観光繁忙期にドライバーとして運行を助ける。
など、多角的な仕組みを組み合わせようという試みが進んでいます。
夜間需要・イベント需要への対応
また観光客の悩みとして多いのが「夜遅い時間に公共交通やタクシーがなくて困る」「イベント会場周辺でピーク時に車が足りなくなる」といったケースです。
- 夜間対応:石川県小松市の公共ライドシェア事例のように、木~土曜の17時~24時の時間帯に運行することで居酒屋利用客や観光客の移動を確保したり、災害時の対応に活かしたりする。
- イベント対応:鳥取県が実施した「とっとライドシェア」のように、短期的にドライバーを確保し、配車アプリと連動してピーク需要に応える。
こうした事例は実際の効果も徐々に出始めており、全国展開が期待されています。
観光需要の喚起、地方の活性化のためには、主要駅や空港などの交通結節点からスムーズに観光地へ移動できる体制が不可欠です。その一方で、少子高齢化やコロナ禍などにより地方で働き手不足が加速するなか、「観光の足」を確保するには多角的な工夫が求められています。日本版ライドシェアのドライバーは、観光ピーク時やイベント時にタクシーの車両不足を補う存在となり、公共ライドシェアは日常の生活の足を支える存在として地域住民や観光客の移動を支えます。
こうした取り組みはまだ広がり始めたばかりですが、「夜間帯」や「イベント需要」「貨客混載」といったキーワードで具体的な事例が増え始めているのは大きな進歩と言えるでしょう。今後は運転手の待遇や安全対策、利用者への周知などさらに洗練された仕組みづくりが求められます。
今後の展望とまとめ
これからの3年間が勝負
国土交通省は、令和7年度から9年度までの3年間を「交通空白解消・集中対策期間」と定め、全国の自治体や交通事業者、関係企業と手を取り合い、一つ一つの「交通空白」を解消していく方針を示しています。具体的には、次のようなアクションが予定されます。
- 伴走支援:公共ライドシェアや日本版ライドシェアが未導入の自治体に対し、導入に必要なノウハウ、補助制度などの情報を提供する。
- 主要駅や空港の二次交通対策:観光客やビジネス客が速やかに目的地へ移動できるようなタクシー、シャトルバス、ライドシェアを整備する。
- 新しい運賃・料金制度の導入:ダイナミックプライシングや変動料金制の是非を検討し、供給不足・需要過多となる時間帯を調整。
- システム連携の標準化:異なる配車アプリやバス会社システムの標準仕様を策定し、共同配車や相乗りをスムーズに行う。
デジタル技術とMaaSの可能性
近年、スマートフォンのアプリやAIを使ったオンデマンド交通サービス、運行管理システムなどデジタル技術が大きく進歩しています。いわゆる「MaaS(Mobility as a Service)」と呼ばれる概念では、列車やバス、タクシー、ライドシェアなどの複数の交通手段を一つのプラットフォームで予約・決済し、シームレスに移動できる世界を目指します。
- 改札連動型のタクシー予約:新幹線の予約情報と連動してタクシーを待機させ、降車後すぐに移動できる仕組み。
- 相乗りタクシーのリアルタイムマッチング:ピーク時に既存車両を効率的に使うため、その場で同方向の利用客をマッチングして相乗りを成立させる。
- オープンソースの送迎管理システム:宿泊施設や介護施設が共同で送迎車両を運行管理し、空き車両を地域住民に提供するシステム。
これらの取り組みは、働き手不足や地域の人口減少が続くなかで、地域交通をより効率的に、かつ利用者に優しい形へと再構築する可能性を秘めています。
地域の自発的な取り組みの重要性
国や都道府県が制度や補助を用意しても、最後に「交通空白」を埋めるのは各自治体や地域の住民、事業者の意欲的な行動です。ライドシェア導入を検討する際には、地元での合意形成や運転手の募集、利用者の周知など手間ひまがかかります。しかし、それを乗り越えた先には、
- 高齢者でも安心して暮らせる地域社会
- 観光客が気軽に足を伸ばせる観光地
- 商業施設や宿泊施設などを含めた地域経済の底上げ
といった多大な効果が期待できます。地域が自発的に動き、行政が後押しする形が今後ますます重要となるでしょう。
課題を超えて「地域を守る・活性化する」道へ
交通空白の解消は、一朝一夕でできるものではありません。しかし、小規模自治体が公共ライドシェアを導入して高齢者の通院を支えたり、大規模イベントに合わせて日本版ライドシェアを活用したりする事例が着実に増えています。さらに、鉄道事業者や観光施設、物流企業など、異業種が協力することで「一石二鳥」あるいは「三鳥」の効果を得られる動きも出てきました。
- 鉄道会社社員がライドシェアドライバーを兼任する取り組みでは、駅での業務と運転手を兼務し、観光客や住民の足を確保しながら従業員の働き方改革にもつなげようとしています。
- 貨客混載では、旅客輸送の“空き時間”に荷物を運ぶことで、宅配ドライバー不足を解消しつつライドシェアドライバーの収入を補い、運転手不足の抑止にもつながります。
「交通空白」は、日本が抱える人口減少、高齢化、地域経済の停滞などの複合的要因によって起こる深刻な問題です。しかし、国や自治体、民間企業が協力し、ライドシェアや相乗りタクシー、AIデマンドバスなど新しい仕組みを積極的に取り入れていくことで、解決へ向けた道筋が見えてきています。
特に国土交通省が立ち上げた「交通空白」解消本部が中心となり、「公共ライドシェア」「日本版ライドシェア」をキーワードに数多くの実証実験や制度改正を進めている今こそが、地域交通を再生させる大きなチャンスです。ここまで見てきたように、成功事例が増えれば増えるほど全国へ展開する動きも加速していきます。
要するに、答えは「多様なプレーヤーが連携して、新しい交通手段を導入・普及させること」がカギだという点です。 新しい発想やデジタル技術を組み合わせ、さらに安全管理や地元合意形成といった足元の課題を一つずつ解決していけば、「交通空白」の解消は十分に可能です。それはすなわち、地域住民の暮らしやすさを高め、地域を元気にするだけでなく、日本全体の活力を下支えすることにもつながります。
「交通空白」問題は、私たちの暮らしやすさや観光地の魅力を左右する、とても大切なテーマです。国土交通省や自治体、事業者、そして地域住民が一体となった取り組みが各地で少しずつ成果をあげているいま、まさに日本全体が次のステップを踏み出そうとしている段階だと言えるでしょう。