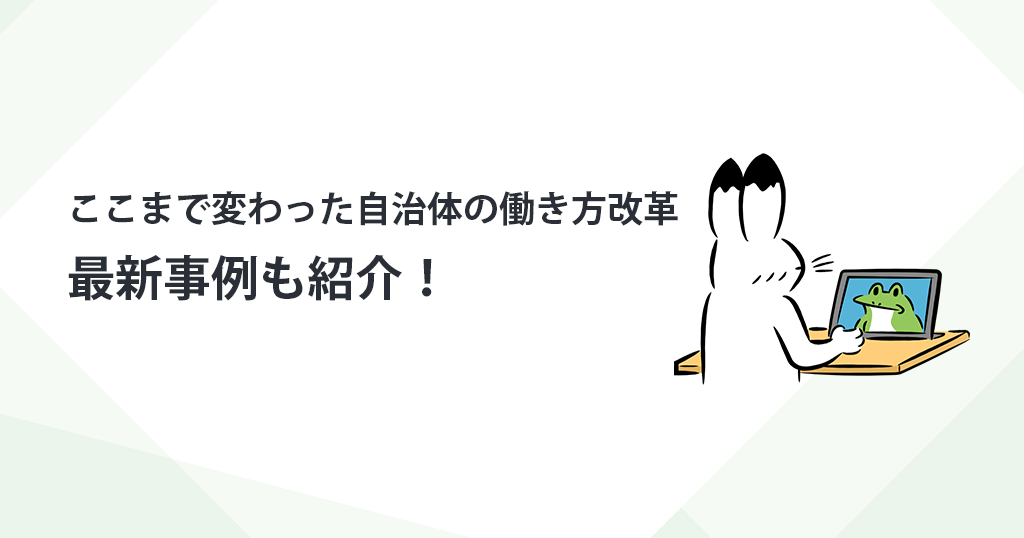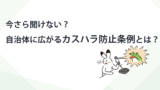働き方改革の背景と基本的な考え方
働き方改革とは、「すべての働く人が、その状況に応じて多様な働き方を選び、能力を最大限に発揮できる社会をつくるための取り組み」と言われています。少子高齢化や人口減少が進む日本では、働き手となる人が減る一方で、企業や役所がこなす仕事はますます複雑化・多様化しており、人材を効率的かつ活用しやすくしていく必要があります。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、自宅やサテライトオフィスなど、職場以外で働く「リモートワーク・テレワーク」を活用する企業や自治体が増えるなど、社会全体で働く場所や働く時間に関する意識が大きく変化しました。
日本政府は、この状況を放置すれば生産年齢人口がさらに減り、経済力も地域の活力も弱まってしまうと考え、「働き方改革関連法」を整備し、企業にも残業時間の上限規制や年次有給休暇の取得促進など、さまざまなルールの適用を始めています。一方で、地方自治体(都道府県や市区町村)にも、人口減少や高齢化、業務の複雑化・高度化といった課題がのしかかり、限られた人数の職員で住民サービスの質を維持・向上しなくてはいけません。
このような背景において、働き方改革は大きく以下の2つのポイントに着目して進められています。
- 労働時間の削減や柔軟化
長時間労働を是正し、健康を守るために、国レベルでも残業時間の上限規制や年休取得義務化などを進めています。地方自治体でも同様の取り組みが求められており、「月の残業時間は45時間以内」「年720時間以内」を守ろうとする動きが進んでいます。さらに、テレワーク制度やフレックスタイムなど、職員が自分の生活に合わせて働く時間と場所を柔軟に選べるような制度を試行する自治体も増え始めています。ただし、住民窓口や緊急時対応など、職場に行く必要がある業務が大半を占める場合は、完全なテレワークが難しい、フレックス制が機能しにくいといった課題も残ります。 - 多様な人材の活躍推進
育児や介護など家庭の事情に応じた柔軟な働き方を導入することによって、男女問わず長く働ける職場環境を整える狙いがあります。特に、女性活躍推進の観点からは、出産や育児をきっかけに退職やキャリアダウンを余儀なくされないように、在宅勤務や時短勤務、フレックスタイム制などを駆使し、管理職に占める女性割合を高めようとする地方公共団体が見られます。また、障害のある方や高齢者が活躍できるように、職場に必要な設備を整える「合理的配慮」を行ったり、職務を細分化したり、ICTを活用して働きやすさを確保する動きが徐々に広がっています。
これらの改革は、単に労働条件を変えるだけでなく、「業務そのものの見直し」や「サービスを維持しながら職員の負担を減らす工夫」が不可欠とされています。たとえば、「業務フローをデジタル化し、紙書類を減らす」「会議の回数を最小限に抑える」「内部向けの報告や資料作成をシンプルにする」といった細かな改善が、働き方改革の成果につながりやすいとされています。
一方、実際に自治体で働く職員の中には、「災害対応や突発的な住民要望に追われ、残業削減が進まない」「限られた人数でのテレワークは、かえって職場の負担を増やす」「正規職員と非正規職員の間に待遇や職務範囲に差があり、働き方改革の恩恵が偏っている」などの声が上がっています。そのため、各自治体は、自団体の規模や業務内容、地域特性などに合わせて、働き方改革をさらに発展させる工夫が求められている状況です。
こうして見ると、働き方改革は「単に残業が減らせるかどうか」という問題だけではなく、「人材不足を補いながら組織としての生産性をどう上げるか」「職員が能力を十分発揮し、やりがいを感じる職場づくりをどう実現するか」といった点にも連動していることが分かります。次の章では、具体的な施策例や現状の成果・課題などを踏まえながら、今後どのように働き方改革を進めていけばよいのかを考えてみましょう。
働き方改革の具体策と展望
前章で述べたように、働き方改革には「労働時間の削減・柔軟化」と「多様な人材の活躍推進」の2つの視点があり、自治体職員の方々もさまざまな工夫を進めています。ここでは、具体的な施策やその成果・課題、そして今後に向けた結論・見通しを整理してみましょう。
業務プロセスの改善とデジタル活用
働き方改革を成功させる上でカギとなるのが「業務プロセスの見直し・効率化」です。自治体の仕事は、地方議会への報告や内部調整、各種書類の承認手続き、住民への通知書作成など、事務作業が多岐にわたります。これらを削減・簡略化するために、デジタル技術を活用する動きが進んでおり、以下のような取り組みがみられます。
- 電子決裁・ペーパーレス化
書類を紙で回覧する習慣を見直し、電子決裁システムを導入することで、承認・決裁にかかる時間と労力を減らす。 - RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入
定型的・繰り返しの入力業務などをソフトウェアのロボットに任せ、人間の職員はより創造的な業務に集中する。 - オンライン会議・テレカンファレンスの活用
離れた庁舎や在宅勤務中の職員ともリアルタイムにやり取りでき、移動時間を削減するだけでなく、会議のスピードアップが期待できる。
こうしたデジタル技術の導入にはセキュリティや個人情報保護の問題、さらには情報端末の整備、職員全体のITリテラシー向上といった課題もあるため、何も準備せずに一気に進むわけではありません。しかし、自治体が抱える大きな事務量を考えると、このデジタル化は働き方改革の要になるといえます。
テレワークやフレックスタイム制の導入
もう一つの柱が「柔軟な働き方」です。特に、育児や介護を担う職員、あるいは通勤に時間がかかる職員などにとって、在宅勤務や時差出勤・フレックスタイムは大きなメリットが期待できます。実際、感染症拡大の影響で、在宅で公務をこなす実験を行った地方自治体もありました。具体的には以下の点がポイントです。
- 在宅勤務(テレワーク)の拡大
業務に必要なネットワークや機器を整備し、コールセンター職員や企画業務の担当者が在宅で資料作成・会議参加をできる環境を整備。とはいえ、窓口対応や防災業務など、現場でなければ対応できない仕事とのバランス調整が大きな課題です。 - フレックス制・早出遅出勤務
ラッシュアワーを避けて出勤したり、子どもの送り迎えに合わせて始業・終業時刻を調整できる制度。自治体でも導入が進むものの、法制度上、フレックスはまだ限定的であることが多いです。
これらの施策は「業務効率が上がる」「職員のWLBが改善する」などのメリットがある反面、「業務の他律性や住民応対の必要性が強い」「全体的な連絡・調整が難しくなる」「労務管理(誰が何時間働いたか)に手間がかかる」といった課題が挙げられます。
結論・今後の展望
働き方改革は、単に残業時間を減らすだけの取り組みではありません。行政運営の仕組みを見直し、職員が必要な業務に集中できる体制を整えながら、住民サービスの質を高めていくための大きな改革です。テレワークやフレックスタイムなどの柔軟な勤務制度を取り入れる場合でも、特に「繁忙期と閑散期が明確に分かれる職種であるかどうか」「災害や突発案件に即応する仕組みをどう確保するか」を十分に検討し、実施することが大切です。
また、職員一人ひとりのキャリア形成や人材育成の観点からは、「女性活躍推進」「障害者雇用」「育児・介護との両立支援」を含めて考える必要があります。時間制約のある職員を受け入れて活躍してもらうためには、業務プロセスや評価・昇進の方法、周囲の協力体制など、組織としての柔軟さが求められます。
今後、AIやRPAなどの技術がさらに進化し、定型的な作業の多くを機械に任せられるようになると、自治体職員は人間にしかできない仕事――つまり企画立案や住民対応、交渉・調整などに重点的に時間を割くことができます。そのためにも「働き方改革」によって、単なる時間の短縮だけでなく、職員が創造的な働き方をするための下地を整えることが不可欠です。
まとめとして、働き方改革を通じて「自治体職員それぞれが自らの状況に応じて働きやすい方法を選びながらも、行政サービスのレベルを高めていく」という状況が理想です。こうした改革には時間がかかるうえ、全庁的な意識改革や法制度の整備など課題は少なくありませんが、長期的には地域住民の安心と信頼を支える重要な取り組みとして、今後ますます加速することが期待されます。
自治体の事例紹介
ここでは、地方自治体が具体的にどのような働き方改革を進めているかをいくつかピックアップして紹介します。いずれも先進的・特徴的な例ですが、規模や業務内容、地域特性に合わせて取り組んでいるため、どの自治体でもそのまま真似できるわけではありません。それでもヒントになる実践が多くあります。
福岡県北九州市:女性活躍推進と短期ジョブローテーション
北九州市では、平成20年ごろから本格的に女性職員の活躍推進に取り組むため、人材育成・女性活躍推進の専任部署を設置しました。具体的には、係長クラスの女性職員が企画・財政部門など多様な業務を経験できるように2年間隔で部署異動させる「短期ジョブローテーション」を導入。業務を早期に習得し、キャリア意識を高められるようサポートしてきた結果、女性管理職比率はおよそ10年で倍増(約6%→14%超)しました。
ただし、所属長にとっては2年で人員が変わる負担もあり、全庁的な「女性育成が重要」という意識づくりを継続することで、短期ローテーションのデメリットを上回る成果を上げています。
神奈川県川崎市:本部制による全庁的な働き方改革推進
政令指定都市の川崎市は、平成29年に「働き方・仕事の進め方改革推進プログラム」を策定し、市長をトップとする「働き方・仕事の進め方改革推進本部」と、各局に設置された部局本部が連携して全庁的に取り組んでいます。月2回、推進担当者が集まる定例会議を開き、残業時間の削減や会議ルールの見直しなど具体的なアイデアを共有・実行。また、職員アンケートによる実態把握や、時間外勤務の多い部署への重点フォローなど、地道なPDCAを徹底することで徐々に残業削減と業務効率化を進めているのが特徴です。
三重県:労使協働の「ワーク・ライフ・マネジメント」
三重県では、職員と管理者(使用者側)が共に話し合い、残業時間の削減や業務改善を進める「ワーク・ライフ・マネジメント」を推進しています。各所属は、自分たちの業務や時間外勤務が増えるタイミングを洗い出し、改善策をまとめた「職場アクションシート」を作成。年度の途中で2回以上検証しては改善を重ねる仕組みを確立しました。特に、原因となる業務を細分化し、誰でも担当できるよう工夫することで特定の人に負担が集中しないようにし、実際に部署ごとの残業時間が減っているという報告もあります。
京都府木津川市:女性の採用拡大と多様な採用試験制度
比較的小規模な木津川市では、採用面接の試験官が男性に偏っていることが課題となり、女性職員を増やす目的で「採用試験官に女性を積極的に登用」し始めました。また、人物重視の試験「チャレンジ枠」を設けたところ、応募者が幅広い地域から集まり、採用者に占める女性割合が大きく上昇。民間の新卒採用に近いスタイルでアピールしたところ、自治体で働く意欲と素質のある人材を確保できた成功例といえます。
東京都調布市:メンター制度でキャリア支援
女性の昇任に対する意識を高め、育児などで悩みを抱えやすい職員をサポートするため、調布市は「庁内メンター制度」を導入しています。管理職経験や育児・介護経験のある職員が「メンター」として、若手や育児中の職員を個別にサポートし、キャリアアップに向けた相談に乗る仕組みです。先輩の体験談を参考にできるだけでなく、上司以外に気軽にアドバイスを求められる存在がいることで、職場の風通しも良くなり、離職率の低下に寄与しているといわれています。
大阪府寝屋川市:独自に提案した「1年単位の変形労働時間制」
寝屋川市は、小規模自治体ならではの課題(繁忙期と閑散期の差が激しい、業務量と職員数のバランス)に着目し、「1年単位の変形労働時間制を地方公務員にも導入できるよう法改正を行ってほしい」と提案しました。これは、繁忙期に労働時間を増やして閑散期に休日を集中取得できる仕組みで、事務量の平準化や時間外勤務削減を狙いとしています。ただし、突発的な住民要望や災害対応など、公務の特性に照らして慎重な検討も必要との指摘もあり、国レベルで議論が進められている段階です。
以上、地方自治体の実践事例をいくつか紹介しました。自治体ごとに規模や課題が違い、働き方改革の方法は多彩です。しかし、共通しているのは「職員が生き生きと働き、住民サービスを高める」という本質的な目標です。デジタル活用、フレックスタイムやテレワーク、女性活躍推進、メンター制度といった具体策を効果的に組み合わせ、各自治体の特性を活かしながら働き方改革を進めることが、これからの自治体運営に大きな意義を持つでしょう。