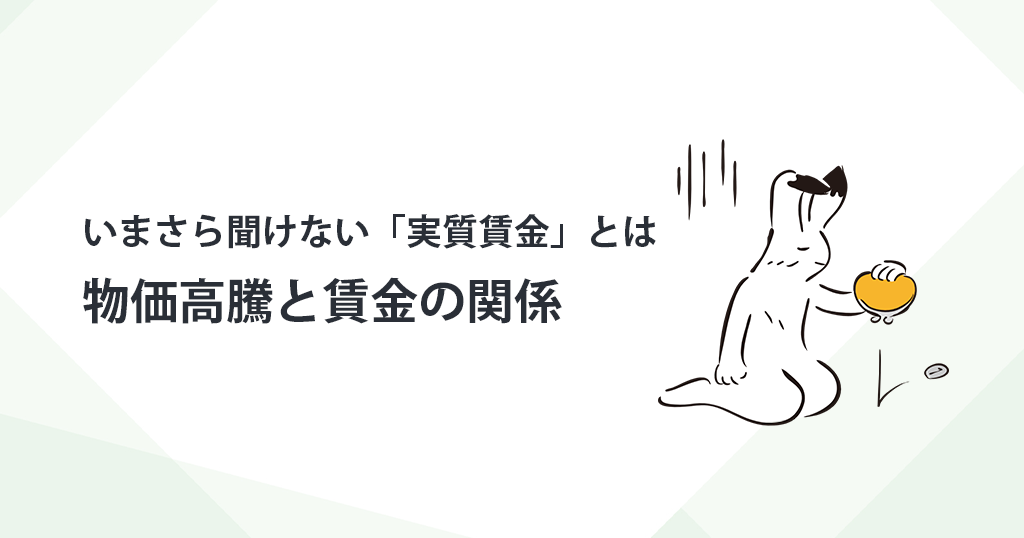実質賃金の基本的な考え方と重要性
実質賃金とは、簡単にいうと「物価の変動を考慮したうえで、お給料が実際どのくらいのモノやサービスを買えるか」を示す指標です。
私たちが普段「給与明細」や「求人情報」で目にするお給料は、名目賃金(額面賃金)と呼ばれています。名目賃金という言葉はあまり馴染みがないかもしれませんが、「会社やアルバイト先から支払われる実際の金額」が名目賃金です。たとえば手取りではなく、税金や社会保険料を引かれる前の「総支給額」を指すことが多いです。
しかし、私たちの生活の実感として大切なのは、「同じ給料でも物価が上がっていたら生活は苦しくなる」という事実です。つまり、名目賃金がどんなに上がっても、物価がさらに高く上昇してしまうと、実質的には「たくさん稼いでいる」ことにならないケースが出てきます。この「名目賃金の変化率」と「物価上昇率」を比べるのが、実質賃金を見るうえで最も重要なポイントです。
実質賃金を用いる意義
- 生活実感に近い
実質賃金は、「いまの給料でどれだけ物が買えるか」という、私たちの実際の暮らしに直結する数値です。名目賃金が増えても物価がもっと高くなれば、実生活では「買えるものの量」が減り苦しくなります。 - 政策判断の基準になる
国や政府が経済政策を検討するとき、単に名目の給与だけを見ても、国民の生活水準を正確に把握できません。例えば、物価が急騰しているのに、賃金の伸びが追いついていない状況では、生活支援策や賃上げ誘導策などが必要になるわけです。 - インフレ・デフレの影響を把握しやすい
物価は上がったり下がったりしますが、これを「インフレ」や「デフレ」といいます。インフレが大きく進むと、名目賃金がわずかに増えただけでは生活が苦しくなるおそれがあります。逆にデフレのときは、名目賃金があまり伸びなくても物価が下がるぶん、実質賃金が上がることもあります。こうした経済状況の把握にも、実質賃金という指標が欠かせません。
実質賃金の計算方法の概要
一般的には、名目賃金(たとえば平均給与)を物価指数で割って算出します。物価指数としては総務省が公表する「消費者物価指数(CPI)」がよく使われます。さらにもう一歩踏み込むと、
実質賃金 = 名目賃金 ÷ 物価指数 × 100(指数表現の場合)
といった形になります。また、賃金の変化率を見たいときは「名目賃金の伸び率 – 物価の上昇率」でざっくりと確認できることもあります。
実質賃金と景気の関係
企業が利益をあげやすく、労働者の給与を上げる余裕がある「好景気」では名目賃金も増えやすくなり、もし物価の上昇が緩やかであれば実質賃金もプラスになりやすくなります。しかし、物価が急に上昇したり(インフレ)、賃金を上げるほど企業に余裕がなかったりすると、実質賃金は伸び悩んでしまうのです。
実質賃金が継続して下がり続けると、消費が冷え込み、さらに経済が落ち込む恐れもあるため、政策面でも重要視される指標となっています。
こうした理由から、実質賃金はニュースなどでも頻繁に取り上げられます。とくに物価が上がっているときには、「賃金の伸び率が物価上昇を上回っているのか、下回っているのか」に注目が集まるのです。
名目賃金の伸びと物価高騰の関係
前のセクションで実質賃金が「名目賃金から物価変動の影響を除いたもの」と説明しました。ここでは、実質賃金を考えるうえで欠かせない名目賃金と物価高騰(インフレ)の関係をより詳しく見ていきましょう。
名目賃金の意義と伸び方
- 実際に支給される金額としての意味
名目賃金は、私たちが実際に「給与明細で確認する金額」にほぼ等しい概念です。企業側が人件費として計上するコストであり、労働者にとっては「働いた見返りに受け取る報酬」です。 - 伸び率は企業の業績や景気に左右される
名目賃金が上がる要因として、企業の収益が増え、労働者の賃金に配分できる余力ができることが挙げられます。好景気で売上が伸びれば、ボーナスが増えたり、ベースアップ(ベア)が行われたりしやすくなります。 - 最低賃金や春闘の影響
日本では毎年「春闘(しゅんとう)」と呼ばれる労使交渉によって、賃金引き上げのベースラインが議論されます。さらに近年は最低賃金の引き上げも注目されており、非正規雇用を中心に名目賃金が上昇する動きが見られます。
物価高騰(インフレ)の仕組み
物価が上がる理由はさまざまですが、大きく分けると以下のようなケースが考えられます。
- 需要が増える
人々が商品やサービスをたくさん買うようになると、それに伴って価格が上がります。たとえば大人気のゲーム機が品薄になると値段が上がるのと同じ原理です。 - 原材料費や輸入コストの上昇
ガソリンや小麦など、輸入に頼っている原材料の価格が世界的に上がると、企業はコスト増を販売価格に転嫁せざるを得なくなり、結果として商品価格が上がることがあります。また円安が進むと、海外からの輸入品を買うのにより多くの円が必要になるため、これも国内の物価上昇につながります。 - 金融政策や世界情勢の影響
日本銀行が金利を低く保ってお金を流通させる政策をとると、世の中に出回るお金の量が増えやすくなり、インフレ圧力がかかりやすくなることもあります。世界的には紛争や災害などで物流が停滞し、一時的に需給バランスが崩れて物価が急騰するケースもあります。
名目賃金の伸び vs. 物価の上昇
実質賃金を左右する大きな鍵は、名目賃金の伸び率が物価上昇率を上回るかどうかです。もし名目賃金の伸びが物価上昇よりも大きければ、実質賃金はプラスになるため、生活水準は上がると言えます。逆に、物価上昇のほうが大きい場合は、実質的に生活が苦しくなる可能性が高いです。
例として、
- 名目賃金が3%上昇
- 物価が4%上昇
という状況なら、実質賃金はおおむね-1%ほどになってしまいます。物価が1%高くなったぶん、お給料の上げ幅が追いつかず、トータルでは「買えるモノが減る」イメージです。
家計や消費への影響
家計にとっては、「名目賃金が増えたからお金持ちになった!」と単純に喜べないのが難しいところです。スーパーの食品コーナーを見て、「あれ、卵が以前より高い」「パンも値段が上がった」と感じていれば、たとえ給料が増えたとしても、出ていくお金のほうが多ければ生活は苦しくなるわけです。
また、実質賃金が下がり続けると、生活必需品の支払いが優先され、外食やレジャーなどの消費が抑えられ、最終的には企業の売上低下や景気の後退につながるおそれもあります。そうなると、さらに企業が人件費を抑制して賃金を上げにくくなるという悪循環が起こり得ます。
賃金と物価を同時に見る重要性
名目賃金を見ても「ちゃんと上がっているじゃないか」と思うかもしれません。しかし、物価の変動を必ずセットで考えることが、景気分析や家計管理のうえで欠かせないのです。ニュースで「インフレ率○%」「物価上昇○%」などと報じられたときには、自分の給料がどの程度増えたかを同時に確認し、実質的な影響を考えるのがおすすめです。
厚生労働省の毎月勤労統計から見る実質賃金の動向
ここでは、実質賃金が具体的にどのように推移しているのか、厚生労働省が公表している「毎月勤労統計調査」を例にとりながら解説します。
毎月勤労統計調査とは?
厚生労働省が実施する公的統計のひとつで、賃金や労働時間、雇用の動向を把握する目的で行われています。規模の大きい事業所(30人以上)と中小事業所(5人以上30人未満)の両方を対象にしており、サンプル(標本)を入れ替えながら継続的に調査しています。
- 公表内容の例
- 現金給与総額:基本給や残業代、賞与(ボーナス)などを合わせた1人あたり平均の給与
- 所定内給与:いわゆる基本給の部分
- 実質賃金:上記の給与額を消費者物価指数で補正した値
この「毎月勤労統計調査」によって、月ごとの名目賃金の動きと、それに対する物価調整後(実質賃金)の伸び率が公表されています。
2025年2月の実質賃金は前年比-1.2%(2カ月連続マイナス)
具体的な数値として、厚生労働省が2025年4月7日に発表した速報によると、2025年2月の実質賃金(従業員5人以上の事業所ベース)は前年同月比-1.2%でした。これは2カ月連続のマイナスとなります。
一方で、名目賃金を示す1人あたりの現金給与総額は28万9,562円で、伸び率は+3.1%です。数字だけ見ると「賃金が増えている!」と感じますが、同じ期間の物価上昇率(コメや生鮮食品、ガソリンなどの値上がり)がおよそ4.3%だったため、名目賃金の伸びを上回る物価上昇により、実質賃金はマイナス幅を維持しているわけです。
なぜ実質賃金が2カ月連続マイナスなのか
- 物価上昇が続いている
2025年前半にかけて、コメや野菜、さらにはエネルギー関連の価格も上昇基調にあります。特に政府によるガソリン価格の高騰を抑える措置が縮小されたことで、消費者の負担が増えやすい状況が継続しています。 - 基本給(所定内給与)の伸びが鈍い
2025年2月時点で、所定内給与の伸び率は1.6%と報じられています。名目全体としては3.1%伸びていても、残業代やボーナスなど特別な支払いが影響している部分もあり、ベースとなる基本給があまり上がっていない点がポイントです。 - パート労働者の増加
全体の3割を占めるパートタイム労働者の比率が高まると、全体の平均給与が押し下げられやすくなります。さらに、パート労働者は物価高の影響を比較的受けやすく、実質賃金がマイナスに振れやすいとも言えます。
今後の見通し
春闘の結果などで名目賃金の引き上げが期待される一方、インフレ(物価高騰)の動向によっては、実質賃金がプラスに転じるかどうかは不透明です。厚生労働省は「賃上げの動きは続いている」とコメントしていますが、足もとの物価上昇が賃金の伸びを上回り続けるかぎり、実質賃金マイナスがしばらく継続する可能性もあります。
また、2月の段階で「コメや生鮮食品の値上がり」「ガソリン補助縮小」などによる物価押し上げが大きく影響したように、世界的な資源価格や為替相場が落ち着かないかぎり、日本国内の物価も安定しにくいと考えられます。賃金が伸びても、物価がさらに急上昇すれば、実質賃金のマイナス傾向からなかなか抜け出せないという状況が続くかもしれません。
サンプル入替えによる月次比較への注意点
実は、毎月勤労統計調査では1月に調査対象の事業所を部分的に入れ替える作業(サンプル入替え)が行われています(大企業が抜けたり入ったりするため、平均給与が一定でない可能性がある)。ただし、ここ数年は特別調査も含めてなるべく月次比較がスムーズになるよう調整されているため、大きな断層は出にくくなっています。ただし短期的な数値変化を見る際は、このサンプル変更の影響も一応頭に入れておく必要があります。
実質賃金の今後の課題とまとめ
最後に、実質賃金が下がると私たちの生活にどのような影響があり、また名目賃金と物価高騰の動きを踏まえてどんな対応が求められるかを整理します。
実質賃金の下落がもたらすリスク
- 家計の負担増
食品や光熱費、ガソリンなどの日常生活で必須となる支出が増える一方で、給与の実質価値が下がると、家計が圧迫されやすくなります。貯蓄や教育費、レジャーに回せるお金が減ってしまうのは大きな痛手です。 - 消費の冷え込み
家計が節約志向になると、外食を控えたり旅行を諦めたりする人が増えます。企業からすると売上が伸び悩み、人件費を抑えようとする動きが広がりかねません。これがまた実質賃金の伸びを阻む悪循環につながります。 - 企業業績や雇用への影響
物価が上昇してもそのぶん売価に転嫁できない企業や、コスト増を吸収できない中小企業では、賃金の引き上げが難しくなる場合があります。最悪の場合、リストラや倒産という形で雇用にも悪影響が及ぶ可能性が出てきます。
名目賃金を上げる取り組みとその課題
企業の賃上げ努力
- 生産性の向上
企業が製品・サービスの付加価値を高め、業績をしっかり伸ばすことで賃上げの原資を確保できます。とくにIT投資や業務効率化、人材教育への投資が不可欠と言われています。 - 利益配分の見直し
売上や利益を拡大したとしても、内部留保だけでなく、労働者への賃金還元を適切に行う意識が企業に求められます。長期的に見ると、従業員のモチベーション向上や人材流出防止にも役立つでしょう。
政府・行政の政策サポート
- 最低賃金の引き上げ
非正規雇用の割合が大きい日本では、最低賃金の上昇が大多数の労働者の名目賃金上昇に直結します。ただし、急激に上げると中小企業が耐えられず、逆に雇用が失われるリスクもあるため、慎重なバランスが必要です。 - 税制優遇や助成金による賃上げ支援
賃上げを実施した企業に対して、法人税の優遇などを行う施策もあります。こうしたサポートを効果的に設計することで、企業の賃上げを後押しする仕組みが整備されつつあります。
働き方・雇用形態の見直し
- 同一労働同一賃金
パートやアルバイト、派遣など非正規で働く人と、正規雇用者の格差を不合理に大きくしないようにする動きが進んでいます。同じ仕事内容であれば賃金もなるべく近づけようという考え方です。 - 多様な働き方の推進
テレワークやフレックス勤務など、多様な働き方を導入する企業が増えれば、育児や介護と両立しやすくなり、就業者も増加します。結果的に人手不足が緩和され、労働市場全体が安定する可能性もあります。
物価高騰への対応
- 補助金や給付金の活用
政府がエネルギー価格の高騰を一部抑える補助金を出しているように、家計が急激な負担増にならないよう対策が講じられることがあります。ただし、根本的な解決策ではなく、財政負担もあるので長期的には限界があるでしょう。 - 家計管理の見直し
個々の消費者としては、値上がりする商品をなるべく抑えたり、買い物の工夫をしたりと、支出を見直すことがまず手軽にできる対策です。とはいえ、収入があまり増えないまま物価だけが上がると厳しいのは変わりません。 - 世界情勢の安定
原油価格や農産物の国際価格など、日本単独の努力ではどうにもならない要素も多々あります。戦争や紛争が長引くと物流が滞り、インフレがさらに進む恐れもあるため、国際社会全体での協調が望まれます。
まとめと展望
- 賃金がどれだけ上がっても物価高がそれ以上に上がれば、実質賃金は下がる。これが私たちの暮らしを左右する根本的なメカニズムです。
- 最近の毎月勤労統計では、名目賃金自体はプラスになっているものの、物価上昇に追い付かず実質賃金が連続マイナスという状況になっています。
- 政府や企業が賃上げを推進したとしても、国際的なインフレ要因や資源価格の乱高下が続くかぎり、生活実感として改善を感じにくい時期が続くかもしれません。
- しかし、長期的に見れば、生産性の向上や働き方改革、最低賃金の漸進的な引き上げなどに取り組むことで、実質賃金のプラス化や国民生活の底上げが期待できます。
実質賃金は単なる数字ではなく、私たち一人ひとりの生活水準を映す鏡です。ニュースなどで取り上げられるときは「物価と賃金のどちらがどのくらい上がったのか?」をセットで確認し、どれだけの購買力を維持できているかを意識してみましょう。そうすることで、家計の見通しや将来への備えを考えるうえでも役立つはずです。
名目賃金の伸びと物価高騰の関係を踏まえ、政府や企業、そして私たち個人それぞれがどのように対応すべきかを考えるきっかけになれば幸いです。