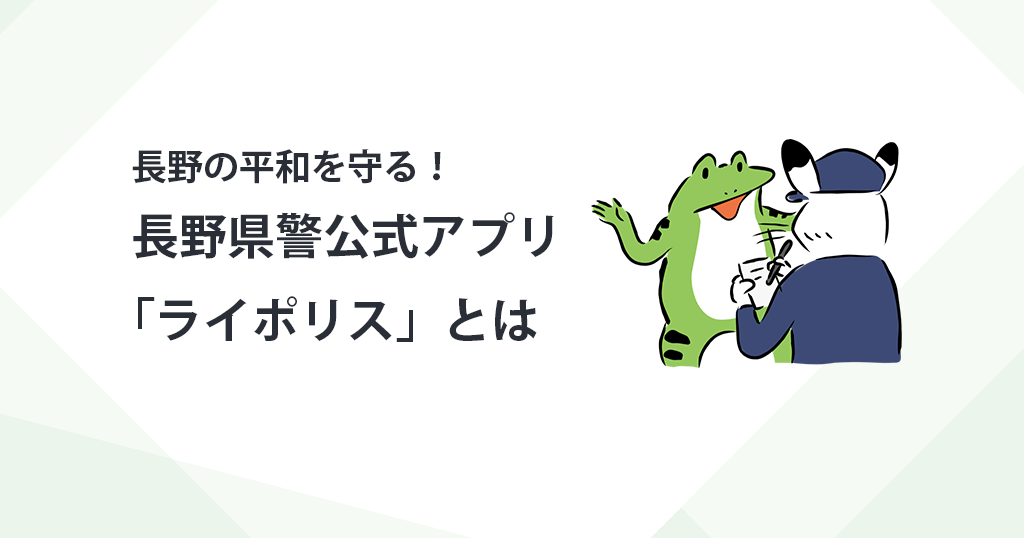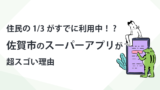ライポリスとは
長野県警察が2025年2月3日から本格運用を始めた公式アプリ「ライポリス」は、県内に住む人たちの安全・安心を守ることを目的とした総合防犯アプリです。新聞記事や長野県警公式ホームページなどによれば、最近増加している電話でお金をだまし取る「特殊詐欺」や、不審者情報、交通事故情報、さらには自然豊かな長野県ならではの「クマなどの動物情報」まで、さまざまな情報を地図(マップ)上で確認できるよう設計されています。
私たちはスマートフォンを日常的に使っているため、防犯や災害、交通ルールなどに関する情報にリアルタイムでアクセスできることが当たり前になりつつあります。しかし、防犯情報や事件・事故の情報は、市町村からのメール配信サービスや地域の回覧板などに限定され、いざという時に素早く知ることが難しい場合もありました。そこで、長野県警察は県民の声を踏まえ、より多くの人が気軽に活用できるスマートフォン用アプリとして「ライポリス」を立ち上げたのです。
このアプリの最大の目的は「犯罪の起きにくい環境づくり」と「県民の自主防犯意識の向上」にあります。単に事件や事故の発生件数を伝えるだけでなく、ユーザー自身が「今、どこで、どんな危険がありそうか」を把握できるようにして、防犯行動を取るきっかけを提供するというわけです。さらに「防犯ブザー機能」や「クマよけ鈴」など、利用者の身の安全を守るための機能が追加されており、警察が持つ防犯ノウハウをアプリに凝縮させている点が特徴といえます。
具体的には、長野県警察ホームページにも掲載されているように、利用者がスマホのGPS機能をオンにすることで、事件や事故情報を地図でチェックしながらパトロールしたり、危険を感じたときにはすぐに音やメッセージで周囲に助けを求めたりできるようになっています。もともと「ライポくん安心メール」というメール配信サービスを提供していましたが、2025年3月末で運用を終了し、その役割を「ライポリス」に統合する形を取っています。これにより、防犯に関わる情報が一元化され、より直感的に閲覧しやすくなりました。
また本アプリを活用することで、子どもや高齢者の方が遭遇しやすい詐欺や声かけ、痴漢といった被害を最小限に食い止めることも期待できます。なぜなら、これまでのメール配信サービスでは文章だけの情報提供が主流で、いつ、どこで発生したかをイメージしにくかったのが難点でした。「ライポリス」では地図を用いるため、地理的イメージと危険への注意喚起が結び付きやすく、利用者が日頃から「ここはちょっと気をつけた方がいい」といった感覚を持つきっかけになります。警察が一方的に情報を発信するのではなく、利用者が積極的に防犯に協力できる相互作用が「ライポリス」の強みです。
ライポリスの主な機能
「ライポリス」の魅力は、何といっても多彩な機能がそろっている点にあります。ここでは主な機能を細かく見ていきましょう。長野県警察ホームページや関連資料を見ると、主に以下のような機能が明記されています。また「利用規約」にも、それぞれの機能使用における注意点や免責事項が示されていますので、実際に使うときは併せて確認することがおすすめです。
安全・安心マップ機能
- 地図表示
県内で起きた犯罪や不審者、電話でお金詐欺、交通事故、クマ・動物出没などの情報が地図上にアイコンで表示されます。「どこで、なにが」起きているかを視覚的につかむことができるため、自分が住んでいる地域や通学路、職場の周辺状況をすぐにチェックできます。 - マイエリアの設定
ユーザーが「マイエリア」と呼ばれる警察署単位の地域を最大3か所まで設定できる仕組みになっており、自宅や学校、勤務先などに合わせて設定しておけば、そこに関連する情報がプッシュ通知で届くようになります。たとえば学校近くで不審者情報があった場合は、すぐにスマホに通知が来るので、注意喚起しやすくなるわけです。
防犯ブザー・クマよけ鈴機能
- 防犯ブザー
アプリ上にある「防犯ブザー」ボタンを押すと、大きな警告音が鳴り響き、周囲に異常を知らせます。また、音を出さずに位置情報だけを家族などに送信するモードもあるため、もし危険を感じたときに声が出せなくても、静かに助けを求めることが可能です。 - クマよけ鈴
長野県は自然豊かで、熊やイノシシ、猿などが出没しやすい地域も多数あります。この機能を使えば、熊などの野生動物に自分の存在を知らせる鈴の音をアプリで流すことができます。山道を歩くときなどに手軽に使えるため、登山客や散歩好きの方にもありがたい機能です。
痴漢対策機能
- メッセージ画面表示
「痴漢されています、声をかけてくれませんか?」など、周囲に助けを求めるためのメッセージを画面に大きく表示する機能です。実際に声を出しづらい状況でも、スマホ画面に文字を表示することで、周囲の人に助けてもらうきっかけを作ります。これにより、被害にあった人が1人で抱え込まずに済むように工夫されています。 - 110番通報のショートカット
痴漢などの犯罪被害に遭いそう、あるいは遭っている可能性がある場合は、素早く通報できるようにアプリ画面にショートカットが用意されています。ただし、通報前後の状況を安全に保つためにも、周囲の人に協力を求めたり、可能なら移動できる場所を確保するなどの対策もあわせて行うことが大切です。
見守りパトロール支援機能
- 重点エリアの可視化
マップ上で犯罪や不審者情報の多いエリアを重点地区として示し、そこをパトロールするよう促す仕組みになっています。地域の防犯ボランティアや学校関係者、保護者などが、危険が多い場所をチェックしながらパトロール活動をするのに役立ちます。 - ポイントを貯める「ミッション」
パトロールやアプリを開くだけでもポイントが貯まる仕様があり、一定量を貯めると「階級」が上がるなど、ゲーム感覚で楽しく継続できる工夫がされています。楽しみながら日常的にアプリを開くことで、防犯意識を常に高められる点がポイントです。
ココ通知(位置情報送信)機能
- 家族間の位置共有
アプリをインストールしている家族や友人を「メンバー登録」しておくと、ワンタップで現在位置とメッセージを送信できます。万が一のトラブルや災害時に素早く位置情報を伝えられるため、安心感が得られます。ただし、相手が同じアプリを入れていないと、メンバーとして登録できない点には注意が必要です。 - プライバシーへの配慮
自分の位置情報が常に相手に知られてしまうわけではなく、「送信ボタン」を押したタイミングだけ通知される仕様です。必要なときのみ位置情報が届くように設計されており、「勝手に位置情報を追跡されるのは嫌だ」という懸念にも対応しています。
これらの機能は、防犯・安全対策を意識して生活する上で非常に便利です。しかし、本アプリはあくまで「自分たち自身の注意を補助するツール」であり、利用規約でも「本アプリが安全を完全に保証するものではない」ことが明言されています。特に外を歩く際は周囲の様子に気を配り、自動車や自転車を運転する際はアプリ操作より交通ルールを優先しなければなりません。便利だからこそ、正しく使ってこそ意味がある点を理解する必要があります。
ライポリスを使う意義と注意点
ライポリスが提供する多彩な機能は、県民の日常生活を安全に過ごすための強力なサポート役です。しかし、「アプリを入れただけ」で犯罪や事故から完全に守られるわけではありません。ここでは、ライポリスを使う上で特に知っておきたい意義と注意点を取り上げます。
自主防犯意識の高まり
防犯アプリを入れるメリットの一つは、自分自身の防犯意識を高められることです。通知やマップを日々チェックすることで、「このあたりでは最近不審者が目撃されている」「この近くで交通事故があった」などを把握できます。そうすると自然に、「ちょっと気をつけよう」「夜は大通りを使って帰ろう」という意識が働きます。学生でも、通学路を自分で確かめながら安全ルートを考えるきっかけになるでしょう。
さらに「見守りパトロール支援機能」を活用すれば、地域のボランティア活動や学校・PTAなどが協力し合い、頻繁に不審者情報が出るエリアを重点的に巡回することができます。こうした活動を通じて「自分たちで街を守る」という姿勢が養われ、結果として犯罪が起きにくい地域づくりへとつながります。
情報の即時性と確実性
以前は、郵送やチラシ、町内放送、あるいは回覧板などで情報が伝達されていました。しかし、こうした方法は時間がかかったり、届く範囲が限られたりしてしまいます。一方、スマートフォンのプッシュ通知は瞬時に届くうえ、多くの人が常に身近にスマホを持っているため、より確実に情報を受け取れます。
ただし、通信回線やサーバーの混雑状況によっては、通知が遅延することもゼロではありません。利用規約でも明記されているように、アプリが一時停止したり、配信に遅れが生じたりする場合があります。したがって、プッシュ通知が来ないからといって「何も起こっていない」と決めつけるのではなく、定期的にアプリを自分で開いて地図情報を確認することが望ましいです。
プライバシーとアプリの利用方法
GPS機能や位置情報の取り扱いは、便利な反面、個人のプライバシーに配慮が必要です。「ライポリス」では、利用者が任意で位置情報を送る仕様であり、常に位置情報を追跡されるわけではありません。送信先も、あらかじめメンバー登録している家族や友人だけに限定されます。子どもや高齢者が使う場合でも、位置情報が勝手に外部へ漏れる危険性は低いよう設計されています。
とはいえ、スマホを持っていない人やガラケーを使っている人など、利用できない人もまだまだ存在します。家族全員が同じアプリを使える環境を整えておくと、いざという時にスムーズに助け合うことができます。反対に、メンバー登録をしないままでは「ココ通知」機能などの恩恵を受けられないので、家族や友人と相談して事前に環境を整えておくと安心です。
正しい使い方とルール順守
防犯ブザーや痴漢対策機能を活用する時は、周囲の状況を十分に確かめましょう。外を歩きながらアプリの操作に気を取られると、交通事故に巻き込まれる危険が高まります。特に自転車や自動車を運転中の「ながらスマホ」は法律で禁止されています。防犯意識が高まったつもりで、かえって交通ルールを疎かにしてしまっては、本末転倒です。
さらに、アプリの防犯機能を過信しすぎるのも注意が必要です。万が一、身の危険を感じる状況に遭遇した場合、まずは周囲に大声で助けを求めたり、安全な場所へ逃げたりすることが最優先となります。防犯ブザーはあくまで補助的な道具であり、「ブザーさえあれば安心」というわけではありません。また、痴漢やストーカー被害など緊急性の高いケースでは、迷わず110番通報を行い、警察に助けを求めることが大事です。
長期的な視点での活用
アプリの新しさに注目が集まりがちですが、犯罪や事故の発生状況は日々変化します。「ライポリス」を導入しただけで状況が劇的に改善するわけではなく、住民一人ひとりがアプリを活用し続け、地域や学校、職場などで情報を共有し、危険に対する意識を高め合うことが重要です。継続的に情報をチェックすることで、トラブルに巻き込まれる可能性を下げることに繋がります。
また、このアプリは今後もアップデートによって機能追加や改良が行われる可能性があります。新機能が追加されたときには、積極的に利用してみてください。地域全体でアプリを活用し、適切なフィードバックを行うことで、より安全・安心な長野県づくりが進むと期待されています。
ライポリスの名称の由来
最後に、このアプリの大きな特徴である「ライポリス」という名前の由来や、長野県警察のシンボルマスコット「ライポくん」、そしてアプリのさらなる発展の可能性について詳しく触れます。
「ライポリス」の名前の由来
長野県警察には、県鳥である雷鳥(ライチョウ)をモチーフにしたシンボルマスコット「ライポくん」が存在します。「ライポくん安心メール」というサービスを以前から提供していましたが、2025年3月末をもって役割を終了し、「ライポリス」に統合しました。
「ライポリス」は、「ライポくん」と「ポリス(警察)」を組み合わせた造語です。さらに、「ポ」には「ピープル(人々)」や「ピース(平和)」を表す「P」の意味も含まれ、「県民の平和を守る警察」という願いが込められています。実際、長野県は山々に囲まれ自然が豊かな地域ですが、だからこそ自然災害や野生動物との遭遇など、都会とは違ったリスクも存在します。「ライポリス」という名称は、県民の安全・安心を広い視野で見守るという姿勢をわかりやすく表しています。
シンボルマスコット「ライポくん」の役割
「ライポくん」は警察を象徴するキャラクターであり、防犯に関するポスターやイベントなどでも積極的にアピールされています。そのかわいらしく親しみやすい見た目から、中学生や小学生、さらには幼児まで幅広い世代に受け入れられやすく、「警察=怖いところ」というイメージを和らげる大きな役割を担っています。
県民が警察に興味を持ち、防犯活動に参加するきっかけづくりにもなっており、「ライポリス」アプリのデザインやアイコンにも「ライポくん」が登場します。一部では、相棒の「ライピィちゃん」というキャラクターも存在し、SNSや公式チラシで二人が登場することもあります。こうしたキャラクター戦略によって、堅苦しいイメージになりがちな防犯情報を、もっと身近に感じられる工夫がされているのです。
アプリの今後の展望
現在の「ライポリス」には、「地図表示」「防犯ブザー」「痴漢対策」「クマよけ鈴」「見守りパトロール」「ココ通知」など多彩な機能が搭載されています。しかし、長野県警察が公開している利用規約にもあるように、アプリの内容や機能は今後の運用状況や利用者の声に応じて、予告なく変更される可能性があります。また、県内だけではなく、他の道府県警察で類似のアプリやメール配信サービスが展開されることで、さらなる防犯ネットワークの広がりが期待されています。
実際、地域の防犯は警察だけで完結するものではありません。学校や家庭、自治会、企業など、地域社会全体が情報共有と意識づけを行うことがカギとなります。ライポリスの「見守りパトロール支援」機能は、まさにこうした協働を促す仕組みの一つです。将来的には、より詳細なエリア通知や、AIを活用した犯罪予測などが導入される可能性もあり、技術の進歩とともに防犯対策がさらに進化していくでしょう。
アプリ活用への呼びかけ
「ライポリス」は長野県警察の公式防犯アプリとして、犯罪や事故の情報を地図で直感的に把握できるだけでなく、多様な防犯ツールを提供し、県民の自主的な防犯活動を支える存在となっています。その名前には「雷鳥」や「警察」、そして「平和・人々のための取り組み」といった意味が盛り込まれ、シンボルマスコット「ライポくん」とともに、親しみやすく防犯意識を高める工夫が凝らされています。
中学生や高校生など若い世代にとっては、防犯だけでなく「自分を守る力」を身につけるきっかけにもなるでしょう。大人たちにとっても、高齢の家族や子どもを見守る手段として役立ちます。すでに多くの機能が備わっているとはいえ、アプリを使っているだけで完全に安心というわけではありません。利用者一人ひとりが防犯意識をもち、危ない場所には近づかない、怪しいメールや電話には応じない、といった心構えが必須です。
これからの時代、IT技術やスマホアプリは防犯・安全対策の柱の一つになっていくでしょう。「ライポリス」を活用しながら、周囲の大人や友人同士で情報を共有し、日常に潜む犯罪や事故のリスクを少しでも減らしていけると素晴らしいですね。長野県警察の取り組みが、全国各地での防犯アプリの充実にもつながり、だれもが安心して暮らせる社会を目指していく動きがますます広がることを期待したいと思います。
以上が、長野県警察が提供する安全・安心アプリ「ライポリス」についての解説記事になります。各種情報は公式ホームページや配布資料()、利用規約()にも詳しく書かれていますので、導入の際にはぜひ一度目を通してみてください。アプリを正しく使いこなし、日常生活をより安全で安心なものにしていきましょう。
ios・Android共通QRコード