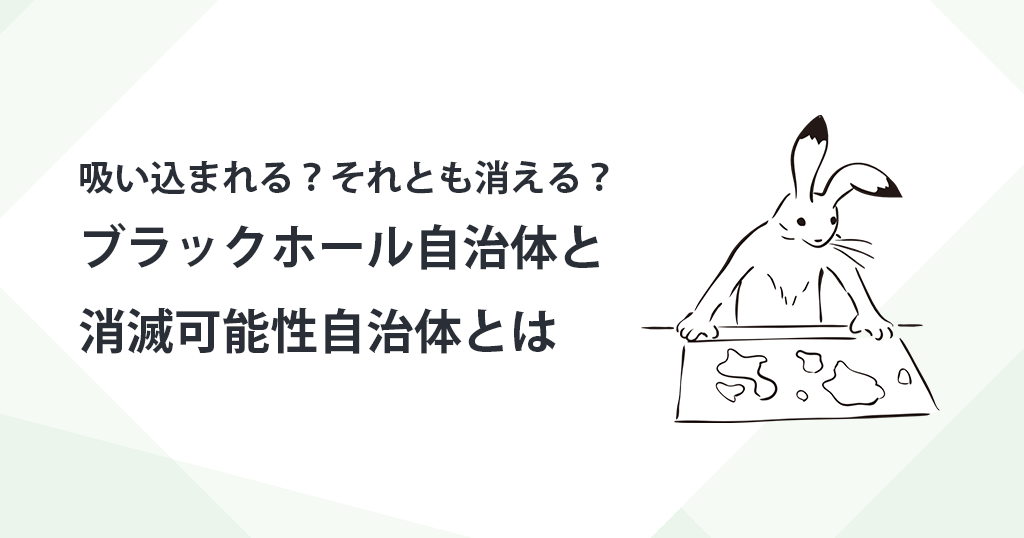地域創生や自治体関連の情報をあつめているとたびたび出てくる「ブラックホール型自治体」と「消滅可能性自治体」。該当地域に住んでいる人からすると、住んでいる地域が消滅してしまうのではないかと不安になる方もいるかもしれません。
今回はそんな「ブラックホール型自治体」と「消滅可能性自治体」についてまとめました。
ブラックホール自治体とは?
ブラックホール自治体のイメージ
「ブラックホール自治体」とは、もともと民間の有識者グループである人口戦略会議が「地方自治体『持続可能性』分析レポート」(2024年4月)を発表した際に使った表現のひとつです。このレポートは、人口問題、とくに20歳から39歳までの若い女性人口(若年女性人口)の将来見通しに着目して、30年後に人口がどのように変化するかを全国の自治体単位で推計しました。
その中で、「ブラックホール型自治体」は、周囲から多くの若年女性が流入してきて出生率が非常に低い 特徴をあわせ持つため、「人をのみこむように吸い寄せるけれど子どもが生まれない」というイメージから「ブラックホール」と呼ばれたのです。
レポートでは「移動仮定(=ある程度今の人口移動が続くという仮定)」でみた場合には減少率が少ない(=若者が集まってくる)一方、「封鎖人口(=転入・転出がゼロになると仮定した場合の人口)」でみると出生率の低さから大幅に人口が減る──この両面のギャップが極端に大きい自治体を「ブラックホール型」と定義しています。
たとえば東京都の一部地域や、大阪市・京都市、さらにいくつかの都市部(渋谷区、文京区など)がこうしたタイプに該当するとされました。テレビや新聞でも「東京はブラックホールだ」という表現が紹介されることで、都市部が若者をのみこみつつ少子化を助長しているという印象を与えています。
「東京がブラックホール」と呼ばれる仕組み
少し専門的に見てみると、「東京圏は出生率が低いから、人口全体が最終的に減りやすい」といわれています。さらに、東京都をはじめとする大都市圏には毎年地方から20代の若者、特に若年女性が大量に移り住む(転入)流れが続いています。そうするとどうなるかというと、
- 都市部は20代や30代前半の未婚女性が多い
- 合計特殊出生率で見ると、未婚女性が多いほど分母が膨らみ、出生率が低くなりやすい
- 他方、出身地である地方側は、若い女性が都市に移ってしまうので、子どもを産む世代(20〜39歳女性)が減ってしまう
- 結果、地方は高齢化と人口流出が進み、都市部は見かけの出生率が下がったまま…
というしくみです。すなわち、都市部(例えば東京)が若者を吸い寄せる(一方で子どもをあまり産まない)状態をブラックホールになぞらえているのです。
ただ、これを正しく理解するためには、合計特殊出生率という指標に潜む特徴も知っておく必要があります。合計特殊出生率は「15〜49歳の女性人口に対して、1人の女性が一生のうちに産む子どもの数」を理論的に示したものです。しかし、そこには「未婚の女性」も分母に含まれています。たとえば地方から都市に出てきたばかりの未婚女性が多いほど、見かけの出生率は下がりやすくなります。また、同じ世帯数の夫婦がいたとしても、都市部で働く女性が30歳以降に出産を先送りするケースが増えると、20代の時点では出生率が低く見えるわけです。この点を踏まえると、「東京は住みづらいから出生率が低いのだ」と単純に結びつけるのは早計だという議論もあります。
本当に「のみこんで」しまうのか?
「ブラックホール」という言葉からは、なんでもかんでも取り込んでなくしてしまうようなイメージが湧きます。しかし現実には、「東京で子育てしない」「都市部で結婚しない」という選択をしているわけではなく、ライフステージが変わると都市近郊や他の地方都市へ転出していく事例も珍しくありません。たとえば東京圏で若いカップルが出会って結婚し、隣接する県に移り住むとか、勤務先の転勤に合わせて数年後に別の県や地方へ転出するということもあります。実際、一時的に都心で就職・生活していても、30歳を過ぎると近隣エリアに移るという傾向はデータで示唆されています。
また、地域別の実際の出生数を比較すると、必ずしも東京の出生数が激減しているわけではなく、この10年間(2010年から2020年)でみると都道府県別でそこまで極端な落ち込みになっていないとの指摘もあります。つまり「ブラックホール」というキャッチーな表現ほど、東京がすべてをのみこんでしまって破綻する──という状況とは限らないのです。
ブラックホール自治体のまとめ
ブラックホール自治体という表現は、あくまで「人が集まるが出生率が低い」という両面を示したレッテルにすぎません。その背景には
- 未婚女性が多い → 分母が増える → 合計特殊出生率が下がって見える
- ライフステージの移動 → 都市で働く期間が長くなり、晩婚化・晩産化が進む
- 郊外や地方にいくかどうか → 結婚後にそもそも都市部を離れるケースも存在
など、単純に「住みづらいから子が生まれない」というだけではない複合的要因があるわけです。
しかし、日本全体の視点でみると、20代〜30代前半の若い女性が都市へ吸い寄せられ(社会増)、その女性たちが子を産む時期が遅れれば、合計特殊出生率は低迷し、少子化対策上は難しさが増していきます。こうした点を含めて検討することが、今後の議論で欠かせないのです。
消滅可能性自治体とは?
消滅可能性自治体の定義
「消滅可能性自治体」とは、同じく民間有識者による会議(日本創成会議)が2014年に「ストップ少子化・地方元気戦略」(通称「増田レポート」)を出した際に注目を集めた言葉です。そこでは、20〜39歳の女性人口が2010年から30年後の2040年にかけて半分以下に減少する市区町村を「消滅可能性都市」と定義しました。2024年には人口戦略会議が最新のデータをもとにした再分析を公表し、再び話題になっています。つまり、この言葉は、今後若い女性が大幅に減ってしまう地域が、将来にわたって子どもが生まれなくなるおそれがある──という危機感を示すレッテルと言えます。
どうやって推定するの?
国立社会保障・人口問題研究所が作成している「地域別将来推計人口」を活用し、若い女性人口が30年後に50%以上減る自治体が該当とされます。さらに、該当する自治体の総数や都道府県別の数、該当割合(全自治体のうちどれくらいが該当するか)などが公表され、結果として地方部の市町村を中心に多数が「消滅の危機にある」と報道されました。
実際に「消滅」してしまうの?
「消滅可能性自治体」という言い方はとても刺激的で、「もうこの町は将来なくなる」と誤解されがちです。実際に「このままでは地域がなくなるんだ…」という不安を住民にもたらす面があり、各自治体から「一面的な指標で線引きするのは地域の努力に水を差す」という批判も出ました。
しかし、作成側は「このまま若い女性が減り続けると、その自治体が将来的に成り立たなくなるおそれが高い」という警鐘を鳴らす意図があったと説明しています。実際、出生数が少なくなると学校統廃合、医療・介護などのサービス低下、地域産業の後継者不足が進むリスクが高まります。いわゆる「人口維持のエンジン」がなくなってしまうからです。
一方で、あくまで推計は「現状の人口移動や出生率が続いたら」という仮定のもとで試算した結果なので、もし地域が積極的に子育て支援や企業誘致を進めて流入を増やし、出生率が上がるような施策をすれば、この推計は変わっていく可能性があります。このように、「消滅可能性都市」は「本当に消えてしまう」という意味ではなく「未来が危ういので早急に手を打たないとまずいですよ」というメッセージだと理解されるべきでしょう。
どの地域に多い? なぜ増える?
主に東北や北海道などの地方圏や、すでに高齢化率が高い小規模自治体が特に多いとされています。また、今回のレポートでは九州や沖縄などが比較的少ないとも言われています。この違いは、地域の結婚観や出生率、若年人口の流出度合い、それから外国籍住民の増加など多様な要因が絡み合って生じます。
さらに、前述の「ブラックホール自治体」と同様、地方同士でも若年人口の移動が起きており、より条件の良い中核都市に人が流れるなどの現象があります。これを放置してしまうと、小さな町村がどんどん人口を失い、やがて農地や山村が維持できなくなるかもしれません。
「消滅可能性自治体」への批判とこれから
「消滅可能性自治体」とレッテルを貼られた自治体からは、「地域住民に不安を与え、若い世代の流出を加速させる」といった懸念も出ました。しかしその一方で、「警鐘を鳴らしてくれたことで自治体が危機意識を強め、具体的な少子化対策や地域活性化政策に取り組むきっかけになった」という意見もあります。
現実に、増田レポート(2014年)の発表時に「消滅可能性都市」と名指しされたにもかかわらず、その後の取り組みによって若い世代が移住してきたり、出生数が回復したりして、今回「脱却した」と評価された例も報告されています。たとえば宮城県大衡村などは、企業誘致や子育て支援を強化し、実際に20〜39歳の女性人口が増加する成果を上げています。
最終的には、こうした「消滅」という言葉そのものが不安や反発を生む可能性があるものの、過疎が深刻化し高齢化が進む地域では、「あと数十年先を考えたときに、果たして若い人が残っているだろうか?」という根本的な課題を共有するきっかけともなっています。ゆえに、「消滅可能性」というラベリングをどう受け止め、どう反転させていくかが、今の地方創生の大きなテーマです。
今後への視点
ブラックホール自治体と消滅可能性自治体の接点
- ブラックホール自治体は「都市部に若者が集まるが出生率が低い」ため、長い目で見ると人口維持が困難という懸念があり、
- 消滅可能性自治体は「若年女性人口が急激に減ってしまう」ため、将来的に出生数が激減して自治体そのものが立ち行かなくなる可能性が高い。
異なる言葉ですが、どちらも「人口減少社会が進む中で、今のままだとその地域が将来立ち行かなくなるかもしれない」という危機感を示しています。
合計特殊出生率を読む際の注意
合計特殊出生率は便利な指標ですが、未婚女性を含むすべての15〜49歳女性人口を分母にするため、若い世代の移動や晩婚化の進展によって数値が大きく変動し、「低い=必ずしも子育て環境が劣悪」というわけではない点に注意が必要です。
人口減少は避けられない? それでも対策は重要
たしかに日本全体の人口は今後減っていく見通しですが、それをどこまで穏やかに進められるか、また子育て環境をどのように整備して若者を呼び込めるかによって、地域の将来は大きく変わります。「ブラックホール型自治体」も「消滅可能性自治体」も、すでに公表から時間がたち、新たなデータで再分析が行われるなど状況は絶えず変化しています。
大事なのは、一人ひとりが暮らしやすい環境を整えていくことです。都市と地方の対立ではなく、各自治体ごとの事情を踏まえながら、地域に合った施策や移住支援、働き方改革、子育て支援などを行い、それを国や地方の双方が支えていく。そうすることで、人口減少社会でも豊かで安心できる未来を形づくることが求められているのです。
「ブラックホール」という言葉からはネガティブな印象を受けやすいですが、それを鵜呑みにするだけでなく、実際のデータの見方や、それぞれの地域におけるライフステージの違いなどを踏まえて、冷静に理解することが必要になります。また、「消滅」とはいえ本当に市町村がなくなるわけではない場合も多く、むしろ危機感を共有して政策を考えるきっかけとする、という建設的な視点が求められているのです。