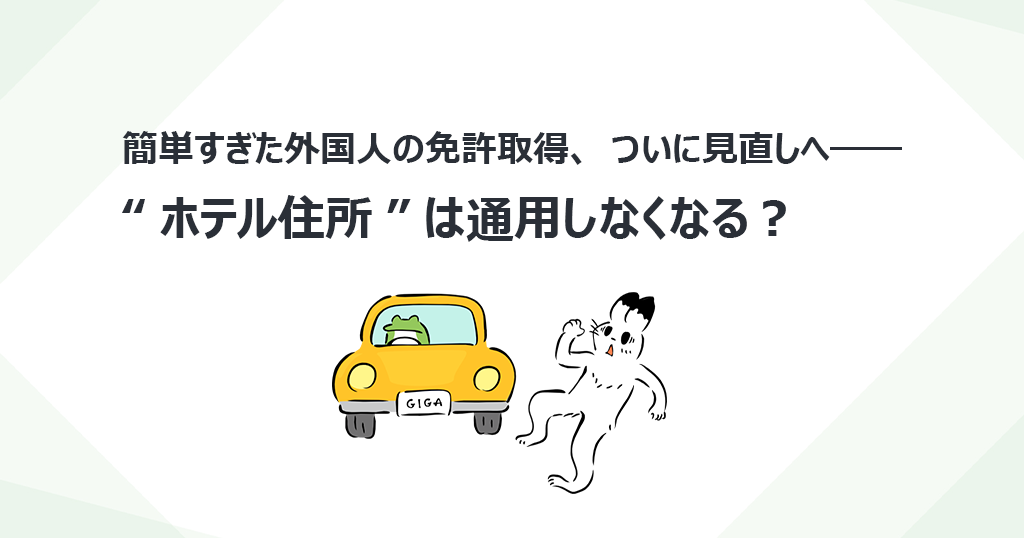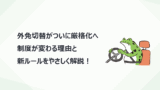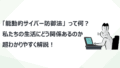先日、外国人の外免切替に関しての記事を公開しましたが、それ以降も連日のように外国人ドライバーの事故や外免切替、交通ルールに関しての報道が後を絶ちません。
また、外免切替に関しては河野太郎元外相が自身のXで「日本に住民票のない中国人が、来日して中国の運転免許証を日本の免許証に切り替えるのは今後認めないことを警察庁が明確にしました」と投稿し、外免切替制度の見直しに注目が集まりました。今回は、前回の記事を府前改めて解説していきます。
急増する外国人ドライバーとその現実
2020年代に入り、日本を訪れる外国人観光客は急激に増えました。円安やインバウンド政策の効果もあり、かつてないほど多くの外国人が日本の街を歩き、観光地を巡っています。そして、彼らの移動手段として今特に選ばれているのが「レンタカー」です。
観光地の中でも特に沖縄や北海道のように公共交通が限られている地域では、レンタカーが移動の要となっています。しかし、この利便性の裏で見逃せないのが、外国人ドライバーによる交通事故の増加です。警察庁のデータによれば、日本国籍以外の国際免許または外国免許を持つドライバーによる事故は、5年間で約3.5倍に急増しています。事故件数で見ると、2015年には68件だったのが、2019年には188件まで増加しました。
この背景にあるのが、「外免切替制度」という日本独自の免許取得方法です。本来、日本で車を運転するには教習所に通い、学科試験と実技試験に合格する必要があります。ところが、外国人であれば、母国の運転免許証を提示し、10問の簡単な○×試験に合格するだけで、日本の運転免許証に切り替えられるのです。しかも、住民票がなくても、滞在先のホテルを「住所」として記載すれば申請が通ってしまうのが現実でした。
この制度の甘さが、事故の温床になっていると指摘されています。
制度の「甘さ」が引き起こす現場の混乱
外免切替の問題点は一見、試験内容の簡略さだけにあると思われがちです。しかし、実際には「申請時の住所要件」こそが、もっとも深刻な問題を含んでいます。日本人が免許を取得する際には、住民票の提示が必要であり、行政機関が本人確認と居住実態を把握する仕組みが整っています。一方、短期滞在の外国人はホテルの宿泊証明書や、書面での「一時滞在証明書」を使って申請することが可能です。
その結果、事故を起こしても、運転者本人の所在がすぐに分からず、連絡がつかないケースが頻発しています。中には、事故後すぐに帰国し、罰金や損害賠償が未払いのまま放置されている事例もあります。日本の警察が外国語対応を迫られ、捜査や事故処理が滞る要因にもなっており、制度上の「抜け穴」が現場の混乱を引き起こしているのです。
このような現状に対して、2025年現在、警察庁はようやく制度の見直しに着手し始めました。外免切替時の住所確認に関しては、「住民票を原則とする方向で検討する」とし、短期滞在者のようにホテルの住所だけで手続きが完了する状態を是正しようとしています。さらに、これまで10問のみだった学科試験の内容を見直し、問題数の増加や出題難度の引き上げも検討対象とされています。
なぜ「制度見直し」が今必要なのか
制度見直しの必要性は、単に事故の多さにとどまりません。日本の運転免許証は国際的にも信頼度が高く、「日本で免許を取った」ということ自体が、海外での信頼材料になってきました。ところが、外免切替があまりに簡易であるがゆえに、「日本の免許は抜け道が多い」「旅行ついでに取れる」といった誤解が生まれ、悪用される事例も出てきています。
たとえば、中国や東南アジアの一部では、外免切替を前提とした「免許取得ツアー」が存在するとされており、観光ビザで短期滞在しつつ、日本で免許を取得し、そのまま帰国するという流れが実際に行われている可能性があります。こうした状況が続けば、日本の免許制度自体の信頼が国際的に失墜しかねません。
事故時の問題も深刻です。警察庁の調査では、外国人ドライバーによる右直事故の約8割が「信号交差点」で発生しており、その原因の多くが「安全確認不足」「前方不注意」によるものです。無信号交差点では、日本人よりも安全確認を怠る傾向が強く、そもそも現地の交通環境に不慣れなまま運転していることが事故につながっていると考えられます。
このような状況に鑑みて、制度の抜本的な見直しはもはや「いつか考えるべきこと」ではなく、「今すぐに取り組むべき緊急課題」なのです。
警察庁は現在、「外免切替の申請時に住民票の写しを必須にする」案を軸に検討を進めており、これが実現すれば、少なくとも短期滞在者が気軽に免許を取得することは難しくなります。また、学科試験においても、「日本の交通文化やマナー」をしっかり理解させるような設問に見直す必要があるでしょう。
国土交通省とレンタカー業界では、外国人向けのリーフレットやステッカーを配布し、危険運転を周囲に周知する取り組みも行われています。ETC2.0などの交通データを使って、外国人による急ブレーキが多発する箇所を特定し、ピクトグラムや多言語看板で注意喚起するという先進的な対策も始まっています。
それでも、制度や対策だけでは限界があります。私たち日本人一人ひとりが、「外国人が増える=リスクが増える」という偏見ではなく、「共に交通社会を支える参加者」としてどう受け入れていくのか。その上で、事故を防ぐために必要な「教育」「情報提供」「制度整備」を冷静に、かつ迅速に進めていく必要があるのです。
もし事故の相手が外国人だったら?
埼玉県三郷市で、登校中の小学生の列に外国人の運転する車が突っ込み、4人が負傷するという事件が報じられたのは、記憶に新しい出来事です。この事件では、加害者が事故直前に酒を飲んでいたとされ、しかもその場から逃走。後に中国籍の男性が「自分はぶつかったが、相手が大丈夫だと言ったので離れた」と説明し、世間に大きな衝撃を与えました。
このようなひき逃げ事件において特に問題となるのが、「加害者が外国人であることで、その後の補償が難しくなる」点です。実際、被害者が治療を受けた後、加害者が保険に入っていない、あるいは連絡が取れない状態だと、治療費や休業補償などが自己負担になる可能性があります。ひき逃げや無免許、飲酒運転といった悪質なケースであっても、「日本の法律に基づく賠償が実質的に機能しない」ことがあり得るのです。
事故直後、加害者が国外に出てしまえば、裁判も不可能に近くなります。例え損害賠償の判決が出たとしても、外国にいる相手に強制的に支払わせる法的手段は極めて限られているため、被害者は泣き寝入りせざるを得ない状況に追い込まれます。
そもそも保険に入っているのか?
日本では、自動車を運転する際には必ず「自賠責保険(強制保険)」に加入することが法律で義務づけられています。加えて、ほとんどの人は「任意保険」にも加入し、対人・対物の損害賠償に備えています。しかし、訪日外国人が借りるレンタカーでは、この仕組みが必ずしも徹底されていない場合があります。
たとえば、レンタカーを借りる際、契約書に「保険込み」と記載されていても、内容をよく読むと「対人賠償は無制限だが、免責金額が高い」など、被害者にとって不利な条件が隠れていることがあります。さらに、レンタカー店が法令違反すれすれのグレーな貸出をしているケースもあり、外国人ドライバーが保険未加入で事故を起こしたという事例も複数報告されています。
また、もっと悪質なパターンとして、「無免許で車を借りて事故を起こす」事案も存在します。群馬県では、無免許で不法滞在中の外国人に150台もの車を違法に貸し出していたという驚くべき事件もあり、事故を起こした運転手は逃走、警察が追跡中というケースも実際にありました。
被害者が直面する「保障されない現実」
加害者が外国人であることが、なぜここまで重大なリスクにつながるのでしょうか。それは、交通事故が起きた後の流れにおいて、「居場所の確定」「意思疎通」「支払い能力」という3つの要素が極めて重要になるからです。
まず、外国人観光客の多くは短期滞在のため、事故後に国外へ出てしまうことが容易です。そして、宿泊先がホテルである場合、事故処理や通知文書の送達がうまく機能しないこともあります。さらに、相手が無職・低所得層である場合、損害賠償金を支払える能力そのものがないケースもあります。
また、言葉の壁が障害になることで、被害者側が精神的にも法的にも不利な立場に置かれることが少なくありません。翻訳が必要で対応が遅れる、加害者が「理解していなかった」と主張する、証言が食い違う――こうした状況の中で、「日本人なら当然受けられる救済」が形骸化してしまう危険があるのです。
現実的な対策として必要なこと
こうしたリスクを踏まえると、いま私たちに必要なのは、事故の発生を「未然に防ぐ」だけでなく、事故が起きたときに「きちんと対応できる仕組み」を整えることです。
まず第一に、免許取得時の制度そのものにメスを入れる必要があります。警察庁が検討を進めているように、外免切替制度において住民票の写しを必須とすることで、「短期滞在者が事故後に行方不明になる」リスクはある程度抑えられます。
また、レンタカー業者に対しても、保険加入の確認や、運転者の身元確認を厳格に求める指導が必要です。事故時の連絡手段を確保するために、SNSアカウントや通訳サポートの体制も整備されるべきでしょう。
さらに、被害者救済のセーフティネットとして、「外国人運転者による事故に対応する公的基金制度」の創設も検討に値します。これは、無保険車による事故に備えるための既存制度(政府保障事業)の拡充として構想できるでしょう。
誰のための制度か? 問われるのは「公平性」
最後に、忘れてはならない視点があります。それは、「制度は誰のためにあるのか」という根本的な問いです。外免切替制度は、外国人を排除するための仕組みではなく、むしろ国際化する社会において必要な制度です。しかし、制度が正しく機能しなければ、守るべき人々――つまり、すべての交通参加者が不利益を被ることになります。
外国人観光客の歓迎と、交通社会の安全は、決して相反するものではありません。双方の理解と制度的裏付けによって、安全で公平な共生社会が成り立ちます。だからこそ、今こそ制度の見直しと、現場の実態に即した運用が求められているのです。
参考資料
交通事故分析レポート(交通事故総合分析センター)
訪日外国人観光客事故防止対策について(内閣府)