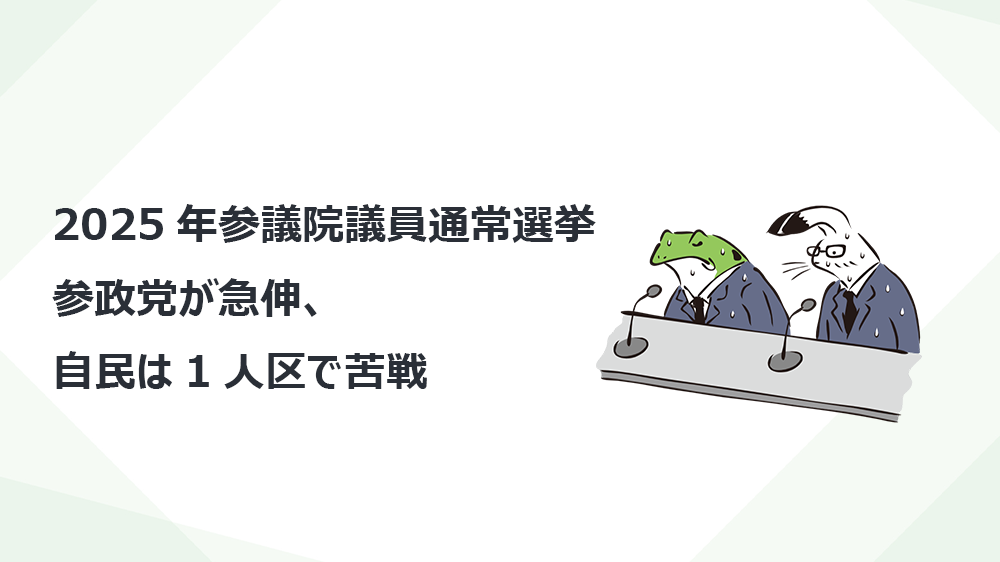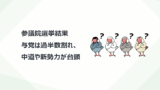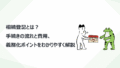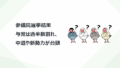2025年7月20日に投開票が行われた参議院議員通常選挙では、「物価高対策」「外交・安全保障」「政治不信と新勢力の台頭」の3つが大きな争点となった。自民・公明の与党は、改選議席の過半数確保が厳しい状況にあり、今後の政権運営にも影響を与える結果となる可能性が高い。
まず国民の関心が集まったのは、生活に直結する物価高への対応だ。ガソリン代や食料品、電気代などの高騰が続く中、政府の物価対策に対して「十分ではない」との声が広がっていた。特に地方では生活防衛を訴える候補が支持を集め、与党にとって逆風となった。
次に注目されたのは、外交・安全保障をめぐる姿勢だ。トランプ米政権との貿易交渉や、中国との関係、防衛費の増額などが争点化し、与野党で見解が分かれた。石破政権は「国際環境が不安定な中、安定した政権が必要」と訴えたが、有権者の間では「聞き飽きた説明だ」と冷めた見方も出ていた。
そして今選挙の大きな特徴は、政治不信と新勢力の台頭である。長年政権を担ってきた自民・公明に対する「変わらない」という不満が根強く、特に無党派層や若年層の間で新しい受け皿を求める動きが顕著となった。その象徴が、参政党の急伸である。SNSや動画サイトなどを通じて直接訴えるスタイルが、「政治は遠いもの」という感覚を持つ層に刺さった。
これらの争点が重なり合った結果、与党が掲げていた「改選過半数の維持」という目標は、達成が危ぶまれている。出口調査では、自民党の支持率は前回より大幅に減少し、公明党も議席を減らす見通しとなっている。新興勢力への票の流れは、従来の選挙構図を揺さぶりつつある。
今回の選挙結果は、今後の政権の正統性だけでなく、日本の政治構造全体に波紋を広げる可能性がある。選挙後には、与党内での責任論が再燃することも予想され、政界の再編成や野党勢力の動きにも注目が集まる。
石破首相、続投の意向を明言 「国家の責任に応える」
参議院選挙の投開票日となった7月20日夜、石破茂首相はNHKの開票速報番組に出演し、今回の選挙結果を受けた自身の進退について言及。「現状において比較第1党の議席数を頂戴している」と述べ、政権を維持する意向を明確に示した。
石破首相は番組内で「物価高への対応、外交・安全保障の強化、子育て支援など、多くの課題が山積している。こうした国家的課題に、引き続き責任を持って取り組まなければならない」と語り、選挙結果に関わらず政権継続が必要との認識を強調した。
ただし、今回の選挙では、与党である自民・公明が改選過半数を割り込む可能性が高まっており、石破首相の続投には党内外から異論も出ている。特に自民党内の一部保守派や若手議員からは、「過半数割れとなれば明確に責任を取るべき」との声もあり、選挙後の党内情勢は流動的となりそうだ。
今回の参院選では、石破政権が掲げてきた「実直な政治」「現場重視の政策」に対して、一定の評価があった一方で、「変化が見えにくい」「経済政策が物足りない」との批判も多かった。選挙終盤には物価高への対応や外交姿勢について、野党や新興政党からの追及も強まり、支持の伸び悩みにつながったとみられる。
石破首相が率いる内閣は、2023年秋に誕生して以降、着実な政権運営をアピールしてきたが、今回の参院選で与党が求めていた「国民からの信任」を明確に得られたとは言いがたい。続投を表明することで、まずは政権の安定を優先する構えだが、連立与党内での責任論や党内対立の火種は残ったままだ。
今後、石破首相は、選挙結果を踏まえた記者会見を行う見通し。続投の論拠や今後の政権運営の方向性について、より詳細な説明が求められることになる。選挙後の国会では、与野党から厳しい追及が予想され、石破政権にとって真価が問われる局面が続きそうだ。
自民党、1人区で苦戦鮮明に 参政党への票流れで構造変化も
2025年参議院選挙で自民党は、全国の選挙区で改選議席の確保に苦しんでいる。特に注目されるのが、1人区(改選数1の選挙区)での苦戦の広がりだ。伝統的に保守票が強く、自民が安定して勝ち越してきた地域でも、支持基盤の動揺が見られ、開票が進む中で野党候補や参政党に押される場面が相次いでいる。
朝日新聞が実施した出口調査によると、1人区全体での自民党支持率は30%。これは前回2022年の参院選で記録した49%から大きく落ち込む結果となった。代わって支持を伸ばしたのが、参政党(13%)と立憲民主党(14%)であり、特に無党派層の動きが自民党の失速に直結している。
無党派層の投票先では、参政党が22%、立憲も22%と並び、自民党は20%と下回った。政党支持が定まっていない層の中で、保守的な主張や情報発信の巧みさを武器に支持を集めた参政党が、自民の地盤を一部侵食する構図が鮮明になった。
また、注目すべきは自民党支持層のうち5%が参政党候補に投票していたというデータだ。前回の2%から微増とはいえ、従来は「固い」とされた自民の支持層にまで動揺が広がっていることを意味する。SNSを通じた訴求力や「新しい保守」としての存在感が、従来の支持層を引き寄せた格好だ。
こうした状況は、地方を中心とした「組織票だけでは勝てない」構造を映し出している。特に若年層や子育て世代では、「誰が言ったか」ではなく、「どう伝わったか」が重視されており、SNSや動画発信を駆使する政党とのギャップが課題として浮き彫りになった。
1人区は今回の選挙で全体の勝敗を左右する「要」とされており、自民党が多数を失えば、改選過半数の達成はさらに厳しくなる。こうした結果を受けて、選挙後には党内での総括や執行部への責任追及が避けられない情勢だ。
石破首相が続投の意向を表明しているが、与党内の力学は揺らぎ始めている。自民党にとって今回の選挙は、単なる勝敗を超えて、党の将来像や有権者との向き合い方を根本から問い直される局面となった。
公明党、重点区での総力戦実らず 連立の重圧に苦悩も
2025年の参議院選挙で、公明党は厳しい戦いを強いられています。今回の選挙では、改選前の14議席(選挙区7、比例区7)の維持を目指して、東京都新宿区にある党本部を中心に「総力戦」を展開しました。しかし、20日夜の開票速報が進むにつれ、議席減の見通しが強まっています。
公明党は今回、兵庫、福岡に加え、選挙期間中に神奈川を「超重点区」として指定。地方議員や支持母体から多くの応援部隊を投入し、選挙区での勝利を目指しました。6月の東京都議選での敗北を受け、危機感をもって組織を動かした形です。
当選確実の候補者には、斉藤鉄夫代表が笑顔で花をつける場面もありましたが、周囲の幹部の表情は硬く、全体の結果を受け止めきれていない様子がうかがえました。公明党は平成28年以降の参院選で13〜14議席を安定的に確保してきましたが、今回はそれすらも難しい状況です。
ある幹部は「自民党と同じだと思われている。四半世紀にわたる連立のツケが回ってきた」と厳しい口調で語りました。長年連立を組んできた自民党と政策の違いを打ち出しにくい中、有権者の間では「変わらない政党」とのイメージが定着しつつあります。
公明党の支持基盤である宗教団体との距離感も問われる中で、都市部の無党派層を中心に支持の広がりを欠いたことも、今回の苦戦につながっています。さらに、子育て支援や福祉政策での実績をアピールしても、物価高や経済不安といった国民の切迫した生活感には響きづらかった印象です。
党内では今後、選挙戦略の見直しとともに、連立与党としての立ち位置や存在意義を再定義する必要があるという声も出始めています。特に若年層の支持獲得や、SNSなどを活用した新しい訴求スタイルの欠如が課題として浮かび上がりました。
このまま議席を減らせば、連立政権全体の安定性にも影響を与える可能性があり、公明党にとっては次の衆院選や地方選にもつながる重要な岐路となりそうです。
参政党、ネット世代から支持拡大 比例区で急伸の勢い
今回の2025年参議院選挙で、最も注目を集めたのが参政党の躍進です。新興政党ながら、SNSや動画配信を駆使した情報発信を強みに、都市部を中心にネット世代の支持を急速に広げました。特に比例代表では、従来の野党勢力に割って入る勢いで、政党別の得票数で4位に浮上する可能性が出てきています。
朝日新聞と大阪大学の三浦麻子教授(社会心理学)が共同で行ったネット意識調査によると、5月以降、参政党を投票先に選んだ人の数は5倍以上に増加していることが明らかになりました。その伸びの背景には、主に国民民主党からの支持層の流入があると分析されています。
具体的には、今年2〜3月の時点では、国民民主党に投票すると答えていた人のうち、約13.7%が支持していたのに対し、7月18日にはその数字が10.1%に減少。代わって参政党の支持率が1.2%から7.4%へと急増しました。流入した層の半数以上は、国民民主からの転向と見られています。
参政党の支持者には、X(旧ツイッター)やYouTubeなどのSNSを通じて情報を得ている人が多く、「テレビや新聞を信用していない」「政府や専門家の言うことを疑っている」といった傾向が強いとされています。こうした価値観に訴えるメッセージが、既存政党に不信感を抱く層に広く刺さったとみられます。
また、比例区だけでなく選挙区でも、一定数の票を獲得しており、特に若年層や地方の無党派層からの支持が顕著です。朝日新聞の出口調査では、無党派層のうち22%が参政党に投票していたという結果も出ており、「新しい政治を求める声」の受け皿としての存在感を強めています。
こうした勢いは、自民党の伝統的な支持基盤にも食い込む形となっており、自民支持層の5%が参政党に投票していたことも明らかになりました。これは保守層の中でも変化を求める機運が高まっている証拠と言えそうです。
参政党はこれまで、地方選挙やネット世論で一定の存在感を示してきましたが、今回の参院選で初めて全国規模での「勢力」として認識される段階に達しました。今後の国政でどのような役割を果たしていくのか、注目が集まります。
国民民主党、期待先行から支持失速 参政党への票流出響く
2025年の参議院選挙において、国民民主党は一時、自民党に肉薄する支持を集める勢いを見せていましたが、終盤にかけて支持が伸び悩み、最終盤での失速が明らかになりました。特に比例区では、かつての支持層が参政党に流れたことが大きく影響したと見られています。
朝日新聞と大阪大学が共同で実施したネット意識調査によると、国民民主党に「投票するつもりだ」と回答していた人のおよそ2割が5月以降に参政党に支持を移したことが分かりました。この結果、国民民主党の支持率は、2〜3月時点の13.7%から、7月18日には10.1%まで低下。支持者の約3分の1が他党に流出していたことになります。
この背景には、5月以降に起きた党内の候補者公認をめぐる混乱があります。SNS上での批判が相次ぎ、党執行部の対応も後手に回ったことで、有権者の信頼が揺らぎました。6月には一部候補者の公認を見送る決定をしたものの、混乱の火消しには至らず、支持層の動揺が広がりました。
とくにネット世代や無党派層の有権者にとっては、対応の遅さや透明性の欠如が強く印象に残ったようです。同時期に参政党がSNSを通じて積極的に情報発信を行っていたこともあり、「変化を求める票」が国民民主から参政党へと移動した形です。
国民民主党は、2023年の衆院選では一定の議席増を果たし、「現実的な中道政党」として期待を集めました。特に雇用政策やエネルギー政策では明確な提案を打ち出し、政策論争でも存在感を発揮してきました。しかし今回は、それらの政策が有権者に十分に伝わらず、「無風」と評される選挙戦になってしまった側面もあります。
また、党を象徴するリーダーの不在や、メディアへの露出不足も支持拡大を妨げる一因となりました。有権者との接点を増やせなかったことが、結果として「分かりづらい政党」という印象につながった可能性も否定できません。
今回の結果を受けて、党内では今後の戦略や組織体制の見直しを求める声が高まると見られます。中道の受け皿としての役割を改めて見直すとともに、参政党のような新興勢力にどう対抗していくかが、次の選挙に向けた重要な課題となるでしょう。
立憲民主党、着実に議席増へ 1人区での健闘が浮上の要因に
2025年の参議院選挙において、立憲民主党は改選前議席を上回る見通しとなっており、野党第一党としての存在感を改めて示しました。とくに注目されたのは、改選数1の「1人区」での健闘です。保守地盤が厚いとされていた地方区で、自民党と接戦を繰り広げる選挙区が相次ぎ、複数の接戦区で勝利する可能性も出てきました。
朝日新聞が実施した出口調査によると、1人区での政党支持率は立憲民主党が**14%**となり、自民党(30%)に次ぐ支持を得ました。これに加え、無党派層の支持が重要な鍵を握るなかで、無党派層の22%が立憲候補に投票したというデータも出ており、浮動票の取り込みに成功したといえます。
立憲民主党は今回の選挙で、「生活の再建」「教育と子育ての充実」「格差是正」などを主な争点に掲げ、庶民目線での訴えを前面に打ち出しました。物価高に苦しむ有権者の声を拾い上げたことで、都市部だけでなく地方の選挙区でも徐々に浸透したとみられます。
また、SNSやオンライン演説を活用した情報発信も進化しており、従来は支持が伸びにくかった若年層からも一定の支持を得ています。自民党や公明党など、与党側に対する批判票の受け皿として機能したことも、今回の議席増の背景といえるでしょう。
選挙区では、野党共闘の枠組みが一部地域で復活したことも追い風となりました。過去に共闘路線が分裂した苦い経験を踏まえ、地域ごとに柔軟な候補者調整を行ったことが奏功したようです。野党同士の票の食い合いを回避し、自民候補との一騎打ち構造を作れた選挙区では、接戦の末に勝利する例も出始めています。
一方で、党全体としての「明確なビジョン不足」や、「政権交代の現実味に乏しい」といった指摘も根強く残っています。比例区では、参政党や維新の会など他の野党・新興勢力に押される場面もあり、勢力拡大にはもう一段の戦略が求められそうです。
今後は、今回の選挙結果をもとに、党内での体制強化や政策の打ち出し方を再検討し、次の衆議院選挙に向けてどう戦うかが問われます。枝野前代表をはじめとしたベテラン議員と、若手議員の融合が進むかどうかも注目される点です。
立憲民主党にとって今回の参院選は、政権交代への足がかりとはいかないまでも、「野党第一党」としての立場を再確認する選挙となりました。
維新・共産など他の野党勢も明暗分かれる 野党再編の兆しも
2025年の参議院選挙では、立憲民主党や参政党に注目が集まる一方で、その他の野党勢の動きにも大きな変化が見られました。とくに日本維新の会、共産党、れいわ新選組などは、それぞれ異なる立場から選挙戦に臨み、有権者の関心をどう引きつけるかが焦点となっていました。
まず、日本維新の会は、今回も大阪や関西圏を中心に地盤の強さを見せ、比例区・選挙区ともに一定の議席を確保する見通しです。物価高への独自の経済対策や行政改革への姿勢が都市部の有権者に浸透しつつあり、立憲民主党とは異なる“改革型野党”としての立ち位置を維持しています。ただし、全国的な広がりという点では依然として課題を抱えており、地方選挙での組織強化が次の課題となります。
共産党は、前回に比べるとやや後退傾向にあります。伝統的な支持層の高齢化に加え、立憲民主党との候補者調整が進まなかった地域では、票の食い合いが発生する場面も見られました。物価高や社会保障の問題では鋭い主張を続けましたが、若年層や無党派層への訴求力には限界があったようです。
れいわ新選組は、主に都市部やネット世代に一定の訴求を試みましたが、比例区で数議席を確保するにとどまる見込みです。障害者福祉や弱者支援などの訴えは共感を集めたものの、参政党や立憲との争いのなかで埋没する部分も見られました。代表の山本太郎氏による街頭演説やYouTubeでの発信は健在でしたが、組織力や候補者の知名度の面で伸び悩んだ印象です。
社会民主党は、今回も議席の維持が最大の課題でしたが、開票速報の段階では厳しい情勢が続いています。長年の固定支持層に支えられているものの、新規支持層の取り込みには苦戦しており、政党存続の危機を指摘する声も出ています。
今回の選挙全体を通して言えるのは、「自民対野党」という二項対立ではなく、「与党・既存野党・新興勢力」の三極化構造が明確になってきたことです。参政党や維新のように、既存の政治とは一線を画すスタンスを取る政党に票が流れたことで、野党内の勢力図にも大きな影響を与えました。
今後は、これらの野党がどのような立場で国会に臨むのか、政策や人材の再編を含めた新しい動きが起こるのかが注目されます。次の衆議院選挙に向けて、野党の再結集や連携の可能性が議論される展開も予想されます。