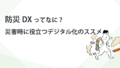改正育児・介護休業法とは?概要と背景
改正育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。この法律は、育児や介護をしながら働き続けることができるように、事業主が整えるべき制度や義務などを定めているものです。今回の改正は2024年5月に成立し、2025年4月1日および同年10月1日から段階的に施行されることになりました。
そもそもの背景には、日本社会の少子高齢化や労働人口の減少といった課題があります。育児や介護を理由として退職する人が多い状況を放置してしまうと、企業の労働力は失われ、本人やその家族にとっても経済的・精神的な負担が大きくなる可能性があります。こうした背景から、男女ともに仕事と家庭を両立できるよう支援する取り組みが、法律面や制度面でより強化されてきました。
令和3(2021)年にも改正育児・介護休業法が施行され、特に男性の育児休業取得促進が注目されました。このとき「産後パパ育休」などが制度化され、企業は育児休業の取得を推奨・促進する体制整備を進めています。しかし今回の2025年施行分では、「育児だけではなく介護にも焦点を当てた改正」が特徴となっており、さらに3歳以降の子を育てる家庭が利用できる措置を拡充する仕組みも導入される予定です。
改正の主なポイント
- 育児関係
3歳以降の子どもを育てる労働者に対して、多様で柔軟な働き方を可能にする制度を導入する義務を企業に課す(2025年10月施行)。また、子の看護休暇や残業免除の対象年齢を引き上げるなど、小学校入学前の子に関する両立支援を強化。 - 介護関係
介護休暇の取得対象者拡大に加え、企業には介護離職防止のための周知や相談体制整備などを義務づける内容が含まれている。特に、40歳になった従業員への情報提供など、「介護が始まる前の早期の対策」が意識されている点が新しい。 - 男性の育児休業取得状況公表義務の拡大
これまで従業員数1000人超の企業のみが対象だった公表義務の範囲が、300人超の企業にも適用される(2025年4月施行)。企業には自社サイトや厚生労働省の「両立支援のひろば」等での公表が求められる。
こうした改正によって、子育てや介護中であっても柔軟に働くことを目指し、退職や離職が防げる職場づくりを推進する狙いがあります。さらに、企業によっては就業規則の見直しや各種制度の拡充などが必要となるため、「単なる書類整備にとどまらず実務への落としこみ」が重要になってきます。
また、中学生にもわかりやすく言えば、この改正は「赤ちゃんのお世話だけでなく、小さい子どもや高齢の家族のお世話をしながらでも仕事が続けられるよう、国が応援してくれる仕組み」を強化したものと言えます。自分たちが大きくなっても働きやすい社会を作るために、とても大切な取り組みなのです。
今回の改正による施行時期は2025年4月1日と2025年10月1日の2段階に分かれているため、企業や労働者は段階的に内容を把握し準備を進める必要があります。まず2025年4月1日に施行される育児関連の改正点を詳しく見ていきましょう。
2025年4月施行の育児関連の改正点
2025年4月1日施行部分のうち、育児に関連する主な改正点としては以下があります。
- 子の看護休暇の対象範囲拡大・名称変更
- 改正前:小学校入学前の子ども(満6歳になる年度の始期まで)が対象
- 改正後:小学校3年生の3月末まで(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもが対象
- 休暇取得事由の追加:感染症による学級閉鎖や入園式・卒園式、入学式といった行事にも看護休暇を使えるよう拡充。
- 勤続6か月未満の労働者を除外できる仕組み廃止:短期間であっても看護休暇を取得可能に。
- 名称変更:「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」。
これにより、たとえば小学2年生の子どもの入学式や健康診断、学級閉鎖時などでも看護休暇を取得しやすくなるというわけです。
- 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
- 改正前:3歳未満の子を養育する労働者のみ、残業免除を請求可能。
- 改正後:小学校就学前の子ども(満6歳になる年度の始期まで)を養育する労働者にも適用。
これによって、保育園などを利用しながら働く家庭で、3歳以降も残業免除を選択できるようになるため、働きやすさが高まります。
- 短時間勤務制度(3歳未満)適用除外時の代替措置にテレワーク導入を追加
- 3歳未満の子を養育する労働者が短時間勤務を利用できない場合、事業主は代替措置を設ける必要があります。
- 今回の改正でその代替措置の選択肢に「テレワーク」が新設。
たとえば、航空機の客室乗務員など「短時間勤務が困難な業務」に従事する社員には、代わりに在宅勤務(テレワーク)の制度を整備することで育児をサポートしやすくなります。
- 育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(努力義務)
- 3歳未満の子を育てる労働者に対し、企業はテレワーク導入に努めるべきことが明文化。
- 努力義務であって強制ではないものの、「通勤時間を短縮し、子どもの世話と仕事を両立しやすくする」という狙い。
実際にテレワークを導入するときは、全員一律ではなく、一部職種・一部部署のみの導入も可能とされています。ただし従業員が活用しやすい仕組みにすることが望ましいでしょう。
- 育児休業取得状況の公表義務拡大
- 対象企業:従業員数1000人超 → 300人超に拡大
- 公表する内容は、主に「男性の育児休業取得率」または「男性の育児休業+育児目的休暇の取得率」。
- 公表方法は事業年度末からおおむね3か月以内に、インターネットなど一般の人が確認できる形で行う。
これにより、中堅規模の企業でも男性育児休業率を公表しなければならず、男性社員が育児休業を取りやすい環境づくりを進めるインセンティブとして働くことが期待されています。
就業規則の整備が必要
これらの変更点を踏まえると、子の看護休暇や残業免除、短時間勤務制度、テレワーク導入などに関する社内規定をアップデートしなければなりません。特に「勤続○か月以上でないと看護休暇は取れない」といった除外規定がある企業は、これを削除する対応が求められます。また、テレワークのガイドライン(対象部署や必要なセキュリティ対策など)を整備し、従業員に周知することもポイントです。
実務上の注意
- テレワークを導入する場合は、労働時間の把握やセキュリティルールの確立、コミュニケーションの方法等をしっかり決める必要があります。
- 男性の育児休業取得状況を公表するとなると、取得率計算のためのデータ収集やシステム整備が必要になります。加えて、単に数字を公表するだけでなく、「育休を取りやすい職場風土づくり」などの取組みを具体的に進めていかなければ、公表後に取得率が低いままだと企業イメージに影響が出る可能性もあります。
以上が、2025年4月施行の育児関連の改正概要です。次は、同じく2025年4月から施行される介護に関する改正点を見ていきましょう。
2025年4月施行の介護関連の改正点
育児だけでなく、仕事と介護を両立するための制度も大きく見直されます。日本は今後ますます高齢化が進むことから、多くの働く世代が家族の介護を担う可能性があります。そこで2025年4月施行分では、以下のような介護関係の改正が盛り込まれました。
- 介護休暇を取得できる労働者の範囲拡大
- 改正前:労使協定で「週の所定労働日数が2日以下」および「勤続6か月未満」の労働者を介護休暇の適用除外とできた。
- 改正後:勤続6か月未満の労働者は除外できなくなる。
- つまり、入社して間もない社員でも介護休暇を取得できるようになり、家族の介護が必要な場合に離職を防ぎやすくなる。
- 介護離職防止のための雇用環境整備(義務化)
介護休業や残業免除などの「介護両立支援制度」の申出がしやすいよう、以下のいずれか1つ以上を必ず実施しなければならない。- ①介護休業や介護両立支援制度等に関する研修の実施
- ②介護休業や介護両立支援制度等について相談窓口を設置
- ③自社の労働者の介護両立支援制度の取得・利用事例を収集し提供
- ④介護両立支援のための社内方針周知
これらによって、介護が必要な従業員が制度を知り、利用を申し出やすい環境を整えます。たとえば「研修」を行えば、管理職や同僚も介護との両立に理解を示しやすくなり、本人が介護休暇を遠慮しなくても済むようになるでしょう。
- 介護離職防止のための個別周知・意向確認(義務化)
- ケース1:従業員が「介護が必要になりそう」と申出たとき
事業主は、介護休業制度や各種介護両立支援制度の内容・申出先・介護休業給付金に関する情報を個別に周知し、その人が制度を使うかどうか意向を確認する。オンラインや対面、書面などで行ってよいが、「利用をためらわせる」ような誘導はNG。 - ケース2:40歳到達前後の時期に情報提供
介護は突然やってくるケースが多いため、前もって40歳前後(※介護保険の第2号被保険者となる節目)に情報を提供することが義務化。早い段階で介護に備えられるよう、社内制度・介護保険制度などを知らせる。
- ケース1:従業員が「介護が必要になりそう」と申出たとき
- 介護のためのテレワーク導入(努力義務)
- 改正後、介護を行う労働者がテレワークを選択できるよう企業は努力すべきと定められる。
- 業務の性質上、出社が必須なケースもあるが、可能な職種や部署があれば在宅勤務を推進し、通勤負担を減らすことで介護離職を防ぐ狙い。
これらの施策をまとめると、介護休暇を取得しやすくするだけでなく、実際に「仕事と介護を両立しやすい職場づくり」を行うことが企業に対して義務または努力義務として強化されている点が大きな特徴です。単純に「制度として存在している」だけで終わらず、労働者が気軽に相談・取得・利用できるように具体策を講じる必要があります。
企業側の実務ポイント
- 就業規則の改訂:介護休暇やテレワーク、相談窓口などの新設・整備に対応。
- 40歳を迎える社員への情報提供スケジュール:対象者を特定し、周知資料の準備。
- 研修や事例紹介の取り組み:特に管理職が介護の実態を理解しておくことは必須。
- テレワーク導入時の留意点:労働時間管理や評価の仕組みなど、育児と同様。
こうした介護分野の改正により、多くの社員が「介護のために会社を辞めざるを得ない」という状況を回避できるようになります。企業にとっては労働力の確保にもつながり、本人や家族にとっては生活の安定を得られるメリットがあるでしょう。
続いて、2025年10月1日に施行される育児関係の追加改正を見ていきます。
2025年10月施行の改正点(育児関係)
2025年10月からは、3歳以降の子どもを育てる労働者に向けた柔軟な働き方に関する措置が整備されるのが大きな特徴です。特に「3歳以降の子」は保育園から幼稚園、あるいは小学校へと移行する時期でもあり、それまでの短時間勤務制度ではなくフルタイム勤務で働きたいというニーズが高まる方も多いと考えられています。
柔軟な働き方を実現するための措置の導入(義務)
- 事業主は、小学校就学前(3歳以上~満6歳になる年度の始期まで)の子どもを養育する従業員に向けて、次の5つの選択肢のうち2つ以上を用意し、労働者が1つを選んで利用できるようにする。
- 始業時刻変更等(フレックスや時差出勤など、所定労働時間を短縮しない方法)
- テレワーク等(月10日以上・原則時間単位でも利用可能な形)
- 育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度:1日6時間など)
- 養育両立支援休暇(年10日以上・原則時間単位取得が可能)
- 保育施設の設置運営など(ベビーシッター補助など)
この仕組みを導入するにあたっては、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く必要があります。つまり企業は一方的に制度を決めるのではなく、現場や労働者の意見を反映しながら運用ルールを作ることが求められているわけです。
「柔軟な働き方を実現するための措置」の個別の周知・意向確認(義務)
- 子どもが3歳未満のうち(具体的には1歳11か月~2歳11か月のあいだ)に、事業主は個別面談や書面、メール等で「自社が用意している措置の内容」「申出先」「所定外労働の制限など他の制度」について周知し、利用する意向を確認しなければなりません。
- 労働者が実際に利用するかどうかを自由に決められるようにしつつ、事業主が「利用しなくていい」と促すような行為をしてはならない点に注意が必要です。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮(義務)
- 妊娠・出産の申出時、および子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は労働者の意向を聴取し配慮する義務が課される。
- 聴取する主な内容は、勤務時間や勤務地、育児休業・短時間勤務制度・残業免除など両立支援制度の利用期間、そして仕事と育児の両立に関わるその他の希望など。
- 希望に対して企業が100%応えなければならないわけではないが、「なぜ対応が難しいか」を誠実に説明するなど、できるだけ配慮する努力が求められる。
実際の運用イメージ
- たとえば子どもが2歳前後の社員に対して、上司や人事担当者が面談を行い、フレックスやテレワークなど複数の制度の説明をする。
- その際、従業員が「フルタイムで働きたいが、通勤ラッシュ時の送迎が大変なので時差出勤を希望したい」と言えば、それが可能になるよう社内規定を案内する。
- 定期的にフォローアップ面談をして、実際に制度がうまく機能しているか、困っていることはないかを確認する。
こうした形で、従業員一人ひとりの状況に合った働き方を選べるようにすることが狙いです。単純に「時短勤務か、フル勤務か」だけでなく、フレックスや在宅勤務、一定日数の休暇制度など、さまざまな組み合わせを用意しておくことで、働き方のバリエーションを増やしていきます。
これらが2025年10月施行の改正概要です。次のセクションでは、改正に対応するため企業が何をすべきか、また、施行後どのような展望が考えられるかを解説します。
企業が取るべき対応策と今後の展望
ここまで見てきた改正育児・介護休業法は、企業に対して単なる規定の新設だけでなく「運用面の充実」を強く求める内容が特徴的です。特に「周知義務」や「面談を通じた意向確認」など、より具体的なやり方が法律上明確化されているため、企業には丁寧な社内整備が必要となります。最後に、企業が取るべき主な対応策と今後の展望を整理してみましょう。
就業規則・社内規定の改訂
- 看護休暇や介護休暇、テレワーク制度などの条文を改める。
- 取得手続きや対象者の定義を法律の改正に合わせて変更し、社内で周知する。
- 特に除外規定(勤続6か月未満など)の取り扱いが変わる箇所に注意。
周知・意向確認のためのフロー構築
- 妊娠・出産時、子が3歳になる前、40歳に達する社員など、周知や面談を行うタイミングが具体的に決まっている。
- 人事部門や現場の管理者が連携し、**「誰が、いつ、どのような方法で周知・面談するか」**を明確化しておく。
- 書式を用意したり、オンライン面談用のマニュアルを整えたりするなど、実務的な準備が大切。
テレワーク導入支援・環境整備
- 育児や介護のためにテレワークを利用する場合、ネットワーク回線やセキュリティ面のほか、自宅の作業環境にも配慮が必要。
- チームコミュニケーションを円滑に行うため、オンライン会議ツールの使い方や勤務時間の管理方法を整備する。
- テレワークの利用が難しい職種向けには、時差出勤やフレックスなど別の措置を確保する。
介護離職防止のための研修・相談体制
- 介護が始まる前から「どんな制度があって、何を準備すべきか」を従業員が知ることが大切。
- 管理職向け研修や社内相談窓口の設置などにより、現場のサポート体制を整える。
- 介護による突発的な休暇や早退に備え、業務のバックアップやタスク共有方法も検討。
長期的な人材戦略への影響
- 育児休業や介護休業を充実させることは、企業にとってコスト面や運用面の負担が増えるように見えます。一方で、従業員が長期的に働き続けられることで採用コスト削減や定着率向上といったメリットを得られます。
- 男性の育休取得率公表も含め、ダイバーシティ推進企業としてのイメージアップをはかることで、人材確保にプラスになることも期待できます。
今後の展望
2025年改正に対応することで、育児や介護に対する企業のサポートが大幅に強化されます。その結果、「働きながら育児や介護をする」という選択肢がより一般的になり、女性だけでなく男性も含めて家庭に携わる時間を確保しやすくなるでしょう。また、高齢社会で要介護者が増えるなか、家族の介護でやむなく退職する人が減ることが見込まれます。
さらに、育児や介護の制度整備は、企業が生産性向上に向けて業務改善や働き方改革を進めるきっかけにもなります。テレワーク導入やジョブシェアなど、新しい働き方を取り入れていくことで、単に法律を守るだけでなく、企業としての成長戦略につなげる可能性もあるのです。
ここまで、改正育児・介護休業法の概要から施行時期別の内容と具体的な対応策まで、5つのセクションにわたって解説しました。
改正のポイントを一言でまとめると、「育児も介護も、『両立できる制度づくり』と実際に活用しやすい『運用の仕組み』を企業に求める」ということです。育児休業や介護休暇などが法令で定められるだけでなく、周知・面談・意向確認といった実務的なやり方まで詳細に規定されることで、職場全体で両立支援を当たり前にしていこうという流れが強まっています。
企業はこうした法律の動きに合わせて、就業規則の改訂や研修・周知策、テレワークなどの働き方改革を柔軟に進めることが必要です。結果的に、「従業員が辞めずに働き続ける」「職場の人材が多様化する」など、ポジティブな効果も期待できます。