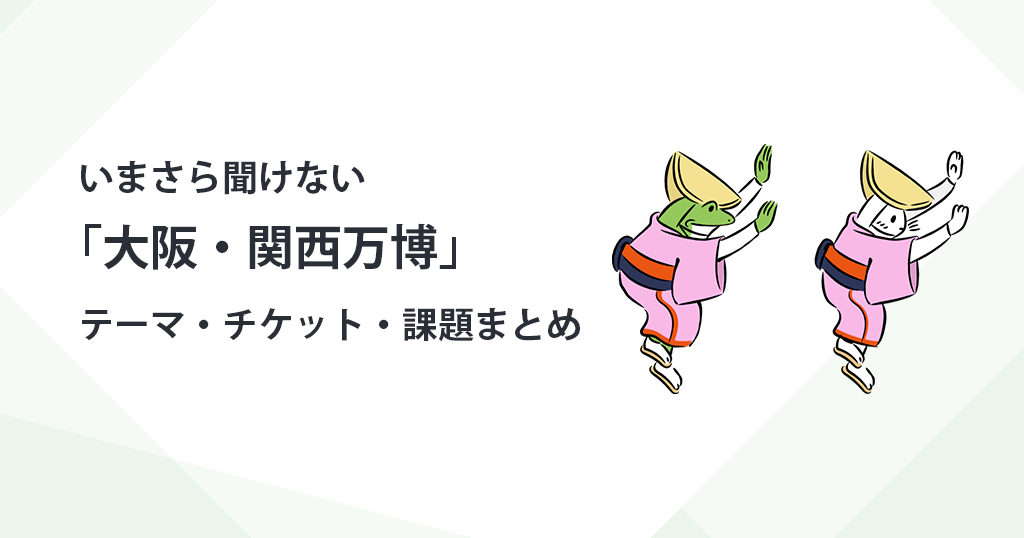2025年4月13日(日)~いよいよ開幕となる「大阪・関西万博」。日本政府が主催する一大国際イベントとして期待が高まる一方で、想定していた費用が大きく上振れ。ここにきてメタンガスの発生やパビリオンの建設・運営の遅れなど、無事に開幕出来るのか不安ではありますが、実際今回の万博ってどういう内容か皆さんご存じでしょうか?
今回は開幕までいよいよ4日となった「大阪・関西万博」についてまとめました。
大阪・関西万博の概要と歴史的背景
そもそも万博って?
「万博(ばんぱく)」という言葉を聞いたことはありますか? 正式には「国際博覧会」と呼ばれ、世界中の国や企業、団体が集まり、未来をテーマにした新しい技術や文化、社会課題の解決策などを紹介・交流する大規模な国際イベントです。5年に1度のペースで「登録博」という大規模な万博が行われており、2025年4月13日から10月13日までの約半年間、日本の大阪市此花区(このはなく)・夢洲(ゆめしま)という人工島で、「2025年日本国際博覧会(通称:大阪・関西万博)」が開催されます。
歴代の日本の万博と今回の意義
実は日本で万博が開かれるのは3度目。1回目は1970年の「大阪万博(日本万国博覧会)」、2回目は2005年の「愛・地球博(愛知万博)」でした。1970年の大阪万博では「太陽の塔」に代表される芸術や、当時の最先端技術(動く歩道など)が一気に披露され、約6400万人もの人が訪れたといわれています。2005年の愛知万博は、環境や持続可能性をテーマに掲げ、森や自然を大切にするパビリオンが注目されました。
そして2025年の大阪・関西万博が3回目となります。今回のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」(英語では “Designing Future Society for Our Lives”)です。私たちが生きる「いのち」と、それを取り巻くすべての環境や社会がより良くなるために何ができるか、技術や文化、国際協力などさまざまな形で提案・発信を行う場となっています。
テーマの背景
最近では、SDGs(持続可能な開発目標)が世界的に注目され、環境破壊や気候変動、高齢化、貧富の格差などさまざまな社会課題が浮き彫りになっています。こうした課題を解決するには国や企業だけでなく、多くの市民一人ひとりが当事者として意識することが大切です。
大阪・関西万博は「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」とも呼ばれ、会場では最新技術やアート、食文化、コミュニティづくりなど、多彩な分野のチャレンジを体験できます。いわば「みんなで実験しながら未来をつくる場」にしたい、という意図が込められているのです。
開催地・夢洲の位置づけ
万博の会場となる夢洲は、大阪市の湾岸部にある人工島。近隣には人気テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」や、商業エリアのベイサイドが広がります。将来的には、夢洲はカジノを含む統合型リゾート(IR)の建設が予定されていることもあり、大阪湾の新たな経済拠点としても期待されています。
会場のアクセスは、Osaka Metro中央線が夢洲駅まで延伸開業済みです。また、バスや船舶、場合によっては「空飛ぶクルマ」といった近未来モビリティも検討中。会期中は原則、公共交通機関での来場が推奨されています。
万博の「公式キャラクター」
赤と青の「細胞」と「水」が融合したようなビジュアルのキャラクター「ミャクミャク」。その名は、「受け継がれたものを脈々と未来につなげる」という意味が込められています。すでに公式グッズやコラボ商品も数多く販売され、「可愛い」「ちょっと不思議」と評判です。
こうして見ると、単なる展示イベントではなく、「未来に向けた実験」と「多彩な国際交流」が詰まったお祭りが大阪・関西万博と言えます。次章では、この万博の具体的な中身や目的、見どころについて詳しく紹介していきます。
万博の目的・見どころと注目のテーマ
万博の目的
大阪・関西万博は大きく分けて4つの目的を掲げています。
- 国際交流・国際協力の強化
世界約160の国・地域と9つの国際機関(2025年2月時点)が参加予定。各国の文化や技術を披露するパビリオンを通じて、新たなビジネスや観光交流、さらには平和構築に向けた国際連携が期待されています。 - 最先端技術・イノベーションの発信
「People’s Living Lab(未来社会の実験場)」コンセプトにふさわしく、ロボットやAI、自動運転、カーボンニュートラル関連技術などが集まり、来場者はそういった未来技術を体験・実験できる場となります。 - SDGs・社会課題の“自分ごと化”
環境・貧困・教育・健康などの課題を一部の専門家や行政だけでなく、幅広い市民が学び、考え、行動につなげるきっかけを作ります。万博会場の建築にも循環型社会の取り組み(ゴミを減らす、再生エネルギーの利用)が導入される予定です。 - 地域経済の活性化と観光振興
多くの外国人観光客が訪れることも見据え、大阪・関西エリアだけでなく全国へ旅行者の流れを広げたいという狙いがあります。実際、国の調査では外国人の来訪者数や旅行消費額はコロナ前の水準を上回っており、これを万博がさらに加速させることを期待しています。
見どころ1:シンボル「大屋根リング」
会場中央には、周囲約2kmにもおよぶ「大屋根リング」と呼ばれる巨大な木造建築が登場します。来場者がぐるりと歩ける通路にもなるため、会場全体を見渡せるビューポイントとして注目を浴びています。さらに雨風・日差しを防いで「心地よい空間」を作り、パビリオン間をスムーズに回れるように配慮されているのです。
見どころ2:個性豊かなパビリオン
各国や企業が独自のパビリオンを建設し、それぞれのテーマに沿った展示や体験型プログラムを提供します。たとえば、アメリカ館では先端技術や宇宙開発を背景にした展示が予定され、日本館では「循環型社会の実験」としてバイオガスやCO₂リサイクル技術を体験できるといった具合です。
さらに、民間企業や自治体が運営するパビリオンも見どころ。たとえば「電力館(可能性のタマゴたち)」では、核融合や無線給電などの未来エネルギーをゲーム感覚で学び、そこでのビジネスマッチングも期待できるといいます。
見どころ3:最先端のモビリティ体験とバーチャル空間
会場では、AIやIoTを駆使し、移動にかかるストレスを軽減するような乗り物(EVバス、空飛ぶクルマなど)を体験できる計画があります。また、会場に来られなくてもオンラインでパビリオンやイベントを体験できる「バーチャル万博」も展開し、世界中の人々が気軽に参加できることを目指しています。
見どころ4:豊富な食とエンターテイメント
世界各国の料理、そして大阪や関西の名物グルメも味わえるのが万博の魅力の一つです。また、水上ショーや音楽ライブなどのエンタメも予定されており、ただ見て回るだけでなく心躍る演出が盛りだくさん。コンサートやプロジェクションマッピングなど、夜間にも楽しめるコンテンツを盛り込むことで、1日では回りきれないほどの盛り上がりが期待されます。
万博は単に「国際色豊かなお祭り」というだけでなく、「私たちが抱える課題を解決するヒントや、新しい価値観に出会える場所」でもあるのです。次章では、そうした一方で顕在化しつつある「課題」や「懸念点」を掘り下げていきます。
大阪・関西万博が抱える主な課題と懸念点
課題1:アクセス・混雑の問題
万博は多くの来場者が見込まれる一方、主なアクセス手段がOsaka Metro中央線とバスなどに限られているため、混雑や待ち時間が大きな懸念点となっています。
実際、2025年4月の開幕を前に行われた「テストラン」でも、入場に1時間以上並んだり、手荷物検査に時間がかかるなど、混雑対策が課題として浮上しました。大会運営側(日本国際博覧会協会)は「並ばない万博」を目指していますが、ピーク時には1日20万人以上が訪れる想定のため、事前予約の徹底や公共交通機関の増便、来場時間帯の分散など、あらゆる工夫が必要になるでしょう。
課題2:メタンガスなど会場の安全・環境への配慮
夢洲は埋立地であることから、かつて埋め立てたゴミなどから発生するメタンガスの問題があります。報道によれば、2025年4月のテストラン中にも高濃度のメタンガスが検出され、一時的に爆発の危険性が指摘されました。協会は徹底した換気や測定体制の強化を行うと発表していますが、来場者の安心・安全を確保するためにも、ガスの常時監視や安全対策を開幕までに万全にする必要があります。
課題3:パビリオン建設・運営の遅れ
自前でパビリオンを建設する国が多い一方、新型コロナウイルス感染拡大や国際情勢などの影響もあり、建設が遅れる動きがみられます。実際、一部の海外パビリオンは建設費用や資材調達が想定より高騰し、出展を断念したり内容を縮小する例もあるといわれています。
このように、予算や建設工程の不確定要素が大きいのは万博全般にありがちな課題ですが、開催まであと1年あまりしかない中で、どこまで整備が間に合うかが注目されています。
課題4:熱中症や衛生面への対応
開催期間は4月から10月までの暑い時期をまたぐため、万博会場内の大屋根や屋内パビリオンであっても猛暑対策が必要です。特に多くの人が集まる状況下では、列に並ぶだけでも体力を消耗します。協会は冷房が効いた休憩所やウォータースタンドの設置などを計画していますが、熱中症リスクを念頭に、来場者自身も帽子や水分補給に注意しながら訪れることが重要です。
課題5:チケット販売・周知の不透明感
「会場の混雑対策」として導入される入場チケットの予約制度や、パビリオン入館のオンライン抽選など、事前に知っておかないとスムーズに入れない仕組みがあります。ネットやスマホに詳しくない層にはハードルが高いかもしれません。
また、チケットの種類が複雑(前売限定券、平日券、夜間券など)なため、分かりやすい周知やサポート体制が求められています。さらに大阪・関西万博の知名度は少しずつ上昇しているものの、「行きたいけどチケットの買い方や混雑が不安」という声も。運営としては、早期の情報提供と丁寧なサポートが重要でしょう。
課題6:持続的な国際交流につなげるには
国際博覧会協会(BIE)のねらいの一つは、「万博が終わったあとも、開催国や参加国との結びつきが強まっていること」。しかし過去の万博を見ると、閉幕と同時に関係が途切れてしまうケースも少なくありません。
今回の万博では、日本各地の自治体が外国企業や外国人コミュニティとの「国際交流プログラム」を実施しており、次章で解説するように、これを「万博後」の関係強化につなげることが大きなポイントとなっています。
各地域の取り組みと万博の今後の展望
地域が注目する「ビジネスマッチング」の機会
大阪・関西万博を単なるお祭りにとどめず、地域経済活性化のチャンスとして活用しようという動きが広がっています。内閣官房国際博覧会推進本部事務局「都道府県における大阪・関西万博に向けた取組について」によると、海外からのビジネスミッション団の派遣や、会場周辺での商談会や展示会が企画されているとのことです。
具体的には、海外の企業・自治体が自国のパビリオンを基点に日本企業との商談を行ったり、日本の中堅・中小企業がパビリオンや関連展示会で自社製品や技術をアピールする場が設けられる予定です。たとえば「J-GoodTech」というオンラインマッチングの仕組みを活用して、中小企業が海外企業から新たな販路や協業の可能性を探る、といった試みが挙げられています。
これにより、日本国内の地方自治体も地元の産業や観光資源をアピールし、海外の企業誘致につなげたい考えです。
各都道府県の「国際交流プログラム」
同PDFによれば、すでに全国62自治体(9府県・53市町村)が参加国との国際交流計画を登録しており、子ども同士の交流や芸術文化の発信など多角的な取り組みを進めています。たとえば北海道では写真文化を活用したカナダとの青少年交流、山形県村山市ではバラや新体操を軸にブルガリアとの交流、岐阜県では美濃焼を通じたフランスや中国との国際交流など、それぞれの地域特性に合わせた多様な事業が展開中です。
これらは「万博で国際交流を深める」だけでなく、万博閉幕後も継続する地域間連携や観光誘致を狙っています。つまり、大阪・関西万博が地方にとっても大きなチャンスになり得るというわけです。
日本博2.0や文化プログラムとの連動
一方で、文化的な面でも多彩な事業が計画されています。たとえば、「日本博2.0」という国の施策があり、伝統芸能や芸術、食文化をさらに磨き上げ、万博を通じて世界に発信しようとする取り組みが進行中です。地域の祭りや伝統文化と万博が連動することで、新たな観光客誘致や若い世代への文化継承が促進されると期待されています。
こどもたちの育成と地域社会への波及
政府は、令和6年度中に全国の小中高校200校程度を対象にした「万博出前授業」を計画しています。万博に出展する企業やNPOが、SDGsや環境問題、先端技術などについて授業を行い、子どもたちが社会課題を自分ごととして考える機会を提供します。また、多文化共生やグローバルコミュニケーションの視点も合わせて養う場として、万博に関連した特別授業が各地で展開される予定です。
大阪・関西万博が描く未来
総合的に見れば、大阪・関西万博は「未来社会を体験し、国際的な交流を深め、地域経済を活性化する大きな起爆剤」になる可能性を秘めています。課題は多いものの、国や自治体、企業、NPOなど多様な主体が連携し、開幕直前までさまざまな施策をアップデートし続けているのが現状です。
最後に、万博の開幕は2025年4月13日、閉幕は10月13日です。この約半年間にわたる「未来社会の実験場」で、私たちはどんな「いのちの輝き」と出会えるでしょうか。多くの課題を乗り越えながら、世界が一丸となって新しい価値を生み出すことを期待しつつ、大阪・関西万博の成功を見守りたいと思います。
ぜひ、ご自身の興味に合わせてさらに詳細を調べてみたり、実際に会場を訪れて体感してみたりしてみてください。未来につながる学びと出会いが、きっとそこにあるはずです。
参考資料
大阪・関西万博関連予算について(経済産業省)
都道府県における大阪・関西万博に向けた取組について(全国知事会)
大阪・関西万博公式HP