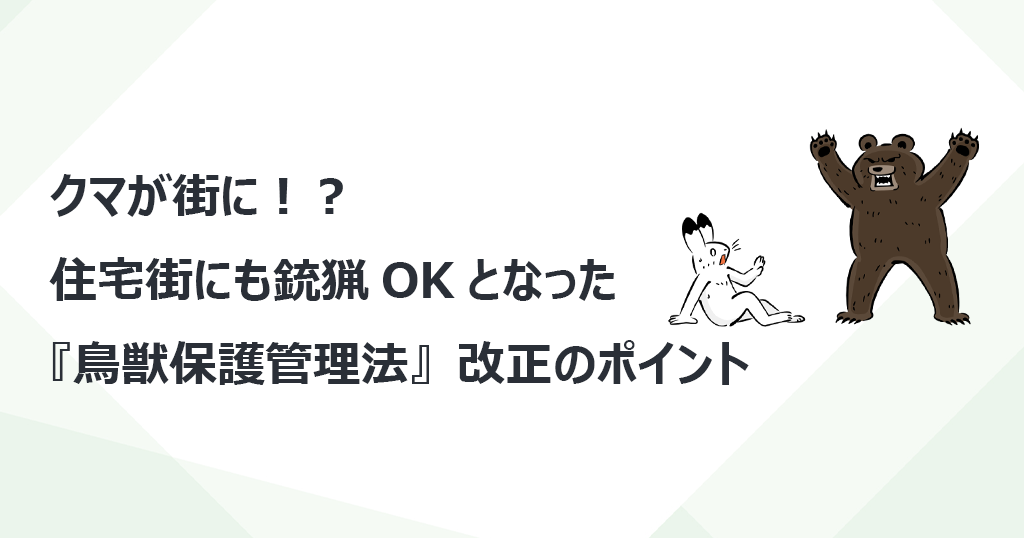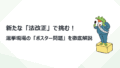2025年4月18日に改正された「鳥獣保護管理法」は、市街地にクマが相次いで出没する昨今の状況を踏まえ、私たちと野生動物との共存の在り方を改めて問いかける重要な契機となっています。今回は、改正の背景や主なポイントをわかりやすく解説します。
鳥獣保護管理法の基本概要
「鳥獣保護管理法」(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、日本の野生鳥獣(野生の鳥や哺乳類など)を保護する一方、個体数が増えすぎたり、市街地へ出没して人や農作物に被害を及ぼす場合には適切に管理するための法律です。もともとは「鳥獣保護法」という名前で、1896年(明治29年)の「狩猟法」から始まった長い歴史があります。大正・昭和期の改正を通じて、狩猟の対象として良い鳥獣の管理や狩猟許可の仕組みが確立され、1963年(昭和38年)からは「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」という名で運用されました。
その後、1971年に環境庁(現在の環境省)が設立されると、野生動物の保護や管理が林野庁から環境庁へ移管されます。しかし、戦後から現代にかけて人と野生動物との関係は大きく変化してきました。戦後は人口が増えて住宅地や農地が拡大し、一部の動物は生息域が減少して絶滅危惧種になったり、地域から姿を消したりするような時代がありました。ところが近年は少子高齢化や過疎化が進み、逆にシカやイノシシ、ツキノワグマといった大型の野生動物が増え、生息地を拡大する地域が見られるようになっています。そうした野生動物は農林水産業に被害を与えたり、市街地に出没したりして、人身事故・トラブルを引き起こすことが大きな課題となっているのです。
こうした状況の変化に対応するため、これまで何度も「鳥獣保護法」は改正が重ねられてきました。特に1999年以降、野生生物保護の専門家や環境NGOなどが声をあげ、「野生生物を単に“保護”するだけでなく、必要に応じて“管理”も行うべきだ」という議論が盛んになりました。例えば、シカやイノシシが増えすぎて農作物被害が深刻化しているなら、適切な捕獲(有害捕獲や狩猟など)で個体数を調整しなければならない、という考え方です。
一方で、クマのように生息数が少ない地域では保護を優先すべき、あるいはツキノワグマの中でも地域により数が急増している所と激減している所があるなど、状況は一様ではありません。こうした「保護と管理をバランスよく推進する」ことを法律の目的として明示したのが、2014年の改正です。このとき法律名称が「鳥獣保護管理法」に変わり、「鳥獣の保護及び管理」という言葉が法律名に入りました。
また、目的条文(第一条)には「生物多様性の確保」という表現も加わりました。これは国際条約である「生物多様性条約」に対応する国内法の一つとして、野生生物を保護するときに「種」だけでなく「生態系全体」のバランスにも配慮しよう、という意思を示した重要なポイントです。
まとめると、「鳥獣保護管理法」は明治から続く古い「狩猟法」がルーツですが、令和に至るまでの社会情勢や自然環境の変化に合わせて何度も改正を経てきました。近年は「保護」だけでなく「管理」にも重点を置き、野生生物と人間社会の共存をはかる法律として機能するよう整備が進められてきたのです。
保護から管理へ、歴代の改正と2014年までの動き
前章で触れたように、「鳥獣保護法」の考え方が大きく変化し始めたのは1999年の改正からです。当時、国会では鳥獣による農林業被害(有害鳥獣被害と呼ばれます)が深刻化していること、狩猟者が高齢化や減少によって捕獲体制が維持できなくなりつつあることなどが問題視されていました。さらに、大型哺乳類の増加によって人身事故が起こるリスクも高まっていたのです。
しかし、その一方で絶滅の危機に瀕している鳥獣も存在し、国際的にも希少な動物を保護しなければならないという要請が強まりました。結果、「保護と管理をうまく両立させるためには、まずは科学的な調査や計画が必要だ」として導入されたのが「特定鳥獣保護管理計画」です。
特定鳥獣保護管理計画とは?
- シカやイノシシ、ニホンザル、クマ(ヒグマ・ツキノワグマ)、カワウなど、個体数の増減が著しい種(特定鳥獣)を対象に、都道府県が計画的な保護・管理を行う仕組み。
- 個体数が増えすぎて被害が拡大している種は、捕獲(狩猟や有害捕獲)を活用しつつ生息数をコントロールする。
- 逆に減少が著しい種は保護を強化し、その生息域を広げるように働きかける。
この特定鳥獣保護管理計画が導入された背景には、「野生生物は自治体の境界線など意に介さず移動する」という事実があります。ある市町村で駆除されても隣の自治体では保護される、というバラバラな対応は、十分な効果を上げにくいのです。また、過疎化や高齢化が進む地方では、従来どおり“猟友会によるボランティア的な駆除”に頼るだけでは限界があるため、自治体レベルで計画を立て、予算を投入する仕組みが求められました。
ところが、この制度ができても当初はなかなか機能せず、被害は増える一方でした。最大の理由は、都道府県が計画を立てても「実行できるだけの予算や専門人材が確保しづらい」という点です。加えて、1999年改正時は「野生動物の管理」に法律全体が本腰を入れたわけではなく、「特定鳥獣保護管理計画」はまだ任意での策定に留まったため、都道府県によっては策定しないままのケースもありました。
この現実を踏まえ、2007年に「鳥獣被害防止特別措置法」(議員立法)が成立し、農林水産業被害を早急に抑え込むための制度強化が図られます。これは農林水産省が所管し、市町村が中心になって捕獲や防護柵などの被害対策を進める仕組みです。すると、環境省管轄の「鳥獣保護法」と農水省管轄の「鳥獣被害防止特別措置法」という二つの法律が並び立つ形となり、野生鳥獣対策はやや複雑化しました。
こうした流れの中で、2014年の改正により「保護管理」の考え方が法名にまで組み込まれ、「鳥獣保護管理法」という名称へ変更されます。これにより、狩猟の許可や捕獲のルールだけではなく、生態系全体を守りつつ被害を減らすために「保護」と「管理」の両方が法律の柱として明確化されたわけです。
しかしながら、実際には「管理」の要である捕獲事業の担い手不足や、地域住民の合意形成、予算確保の問題など課題は山積みでした。そこで2014年の改正では、狩猟を“事業化”して法人や認定された事業者が専門的に動けるようにする仕組みもつくられます。それでも現場からは、「専門的なスキルを持つ人材がまだ不足している」「自治体間の連携が不十分」といった意見が相次ぎました。
このように、2014年改正前後までの動向としては、野生鳥獣の保護と管理に本腰を入れ始め、制度も徐々に整いつつあったものの、実際の運用面では大きな課題が残り、それが次の段階(2025年改正)でより一層顕在化したといえます。
2025年の改正と「市街地でのクマ銃猟」の解禁
改正の背景
2025年4月18日、参議院本会議で「改正鳥獣保護管理法」が成立しました。大きな焦点となったのは、クマの市街地への出没が全国各地で相次いでいることです。環境省や警察庁の統計によると、ここ数年クマによる人身被害は増加傾向にあり、特に2023年度は被害者数が統計史上で最多を記録しました。クマは臆病な動物でもある一方、人里の食料やゴミをあさるうちに学習し、市街地を徘徊するケースが増えています。
これまでは、住宅地のように建物が密集している場所(「住居集合地域等」といいます)で銃を発砲することは、鳥獣保護管理法第38条などで厳しく制限されてきました。緊急事態で人の生命が危険にさらされている場合には、警察官が「警察官職務執行法」に基づいて発砲を命じる例外はあったものの、あくまでも“差し迫った危険がある”と明確に判断されなければ難しい対応でした。
ところが、実際にはクマが家の中や施設内に侵入して膠着状態となってしまい、「人命に直ちに危険が及ぶほどではないが、すぐに捕獲しないとさらなる被害リスクが高まる」という状況が起こり得ます。このようなケースで、自治体が迅速に判断してハンター(または銃の使用許可を持つ専門業者)を呼び、市街地でも銃を使った捕獲ができるようにする必要がある──これが今回の改正の大きな狙いです。
主な改正内容
- 危険鳥獣の定義
ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシなど、人間の生活圏に現れた際に大きな危害を及ぼすおそれがある鳥獣を「危険鳥獣」と定義し、政令で指定します。 - 市街地での銃猟解禁(緊急銃猟)
以下の4つの条件を満たせば、市町村が専門のハンターや職員に委託して、市街地でも銃猟を行うことが可能になります。- (1) クマなどが住宅地や公共交通機関の通る区域に侵入、または侵入するおそれが高い
- (2) 緊急に危害を防ぐ必要がある
- (3) 他の捕獲方法(わな・麻酔銃など)では的確かつ迅速に対処できない
- (4) 住民の避難などにより、弾が人や建物に当たるリスクを回避できる
- 安全確保と補償の仕組み
- 市町村は通行規制や避難指示を出し、一般住民の安全を守る
- 捕獲に伴う弾丸による物損(建物などの破損)が起きた場合は、市町村が補償する
- 専門家のリスト化
- 危険鳥獣の捕獲に対応できるハンターや銃所持者を自治体がリスト化し、秋などクマが増える時期までに体制を整備する予定
この改正によって市街地でのクマ駆除が“いつでも自由に行える”わけではなく、あくまで条件を厳格に満たした場合のみです。やみくもに銃猟を認めれば、誤射事故や弾丸被害のリスクが高まるため、自治体は通行止めや住民避難の手順などをきちんと整え、発砲できる捕獲者を厳選する必要があります。また、「銃猟以外で対応可能ならそちらを優先する」という建前も変わりません。
いずれにせよ、市街地でクマを「追い払う」だけで済むなら良いですが、どうしても確保が難しい場合には殺処分もやむを得ないとされ、地域社会における“捕獲のあり方”が問われる局面に突入したといえます。
今後の課題とまとめ―人と野生動物の共存をめざして
今後の課題
- 誤射や安全管理のリスク
市街地での銃猟を認めると、当然ながら誤射や流れ弾による被害が懸念されます。法改正では自治体による避難指示や通行制限、市町村の補償などが定められましたが、実際に現場でスムーズに周囲を封鎖し、確実に実施できるかは未知数です。また、ハンターが夜間に出動する可能性もあり、より一層のリスク対応が必要です。 - 担い手不足・人材育成
改正鳥獣保護管理法では、認定鳥獣捕獲等事業者という法人や専門家を活用できる仕組みがありますが、地域によっては人材不足が深刻です。特にクマのような大型猛獣に対処できる技術を持つ人は限られており、狩猟の高齢化も進んでいます。 - 根本的な対策―生息地管理やエサ源管理
銃でクマを捕獲するのはあくまで緊急手段であり、本質的にはクマが人里に降りてこないように山林の食糧不足を解消したり、人里におけるゴミや農作物へのアクセスを遮断したりすることが欠かせません。いわゆる「生息地管理」と「エサ源管理」の工夫がなければ、クマの生息数が減らないか、むしろ山に餌が少ないためにさらに人里へ出てくる、といった悪循環が続く恐れがあります。 - 市町村と都道府県・国の連携
今回の改正では、市町村が主体的に緊急銃猟を行うことが想定されました。その一方で財政的・人的リソースが十分ではない自治体も多く、都道府県や国がいかにサポートするかが重要になります。環境省はガイドラインを策定する予定ですが、単なるマニュアルだけでなく、費用負担や専門人材の派遣など実質的な援助が課題です。
まとめ
鳥獣保護管理法は、明治から続く狩猟制度をベースにしつつ、現代の課題「野生動物が増えすぎたり、市街地に出没して人の安全や農作物を脅かす」という問題に向き合い、かつ「希少な動物はしっかり保護し、生物多様性を守る」という二つの方向性を同時に達成しようとするものです。
2025年の改正で、市街地でのクマなどの銃猟が条件付きで可能になったのは、人命や生活への深刻な被害が発生しかねない現状に対処するためとはいえ、重大な転換点でもあります。自治体の判断でクマの捕獲を委託できることで、危機的状況に迅速に対応できるメリットがある半面、誤射や乱用を防ぐための厳格な手続きと専門知識、住民への周知が不可欠です。
最終的には、クマが山で生きられるような環境を整えたり、里への侵入経路やゴミの管理を徹底したりする長期的対策が重要といえます。安易に銃による捕獲に頼るだけでなく、地域住民・自治体・専門家が協力して「人と野生動物が共存できる環境」をつくり上げることが、今後の大きな目標です。森林の豊かさを守りながら、人身被害を防止するための仕組みづくりこそ、本当の“答え”といえるでしょう。