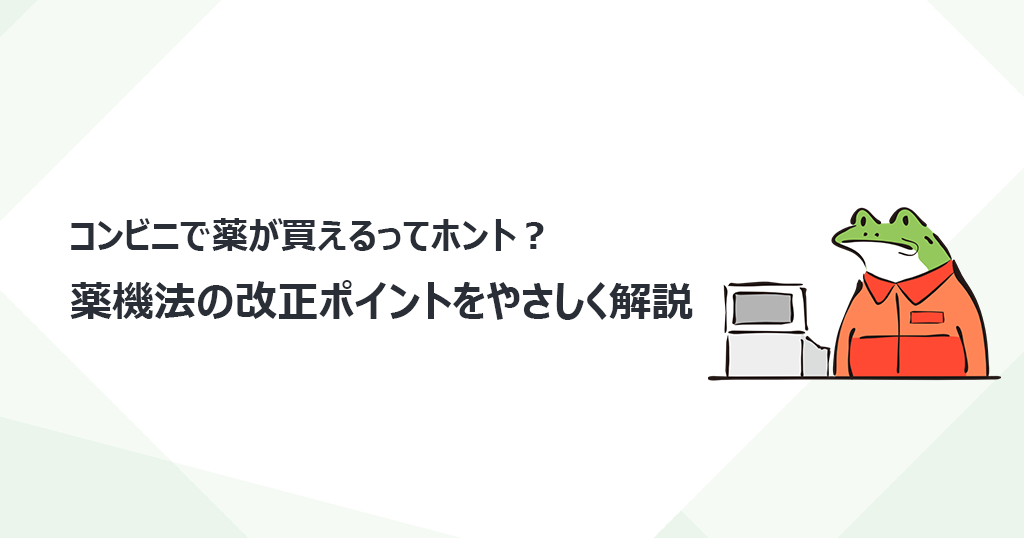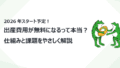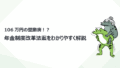薬の法律ってなに?
日本には、私たちが安心して薬を使えるように、薬や医療機器の品質や安全性を守るためのルールがあります。そのルールが「薬機法(やっきほう)」です。正式名称はとても長く、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。昔は「薬事法(やくじほう)」と呼ばれていましたが、2014年に今の名前に変わりました。
この法律は、薬や医療機器、化粧品、医薬部外品などがちゃんと作られて、ちゃんと使われるようにするために、とても大切な役割を持っています。
薬機法が改正された理由
2025年5月、薬機法が改正されました。なぜ改正が必要だったのでしょうか?理由は大きく分けて4つあります。
市販薬の使い方に問題があったから
最近、風邪薬や咳止め薬をたくさん飲んでしまう「オーバードーズ(過剰服薬)」という問題が特に若い人の間で増えています。正しく使えば体を助けてくれる薬ですが、間違った使い方をすると、逆に体に悪い影響を与えてしまいます。この問題を防ぐために、販売方法の見直しが必要になりました。
デジタル化が進んだから
今は、スマートフォンやパソコンを使ってお医者さんと話したり、薬について説明を受けたりできる時代です。だからこそ、遠隔(えんかく=離れた場所)で薬を売る新しい仕組みが必要になってきたのです。
薬が足りなくなる問題が増えているから
コロナ禍や工場のトラブルなどで、薬が足りなくなる「供給不足」という問題が起きています。病院や薬局で必要な薬が手に入らないと、大変なことになります。こうしたトラブルに対応するためのルールづくりが求められました。
創薬(新しい薬を開発すること)をもっと進めたいから
海外では使える新しい薬が、日本ではまだ使えないという「ドラッグ・ラグ」や、「開発すらされない」こともある「ドラッグ・ロス」が問題になっています。これらを解消して、もっと早く、もっとたくさん新しい薬を使えるようにしたいという背景がありました。
改正の決定と内容の流れ
政府は2025年2月に薬機法の改正案を閣議決定し、国会で審議を経て、2025年5月14日に参議院本会議で可決・成立しました。この改正では以下のような変化が起こります:
- 薬剤師がいないコンビニでも、条件を満たせば薬が買えるようになる
- 若い人への市販薬の販売が制限される
- 調剤(薬を用意する作業)の一部を外部に任せることができる
- 創薬スタートアップ企業への支援が強化される
- 国が薬不足のときに企業へ「増産してほしい」と要請できるようになる
薬機法改正のポイントをどう考えるか
この改正は、私たち一人ひとりの健康や安全に深く関係しています。たとえば、身近なコンビニで薬が買えるのは便利ですが、間違った使い方をすると命に関わることもあるため、「便利さ」と「安全性」をどう両立させるかが大きなテーマです。
また、遠隔で薬を販売できるようになると、過疎地や災害時などに役立ちますが、その管理体制やトラブル対応は今後の課題です。
国や企業だけでなく、私たち消費者一人ひとりが「薬を正しく使うこと」の大切さを理解しなければなりません。
薬機法改正で何が変わる?6つのポイン
2025年5月に改正された薬機法には、私たちの暮らしや薬の使い方に深く関わる重要な変化がいくつも盛り込まれています。ここでは、その中でも特に注目すべき6つのポイントについて、わかりやすく解説していきます。これらの変更はすぐにすべてが実施されるわけではなく、段階的に進められる予定ですが、今から理解しておくことが大切です。
コンビニでも薬が買えるようになる?
これまで、市販薬(風邪薬や胃腸薬など)を販売できるのは、薬剤師や登録販売者がいる薬局やドラッグストアに限られていました。しかし、今回の改正によって、薬剤師がその場にいなくても「オンラインで服薬指導(薬の説明)を受けること」を条件に、コンビニエンスストアや自動販売機などでも市販薬を買えるようになる道が開かれました。
ただし、これは安全面を確保したうえでの話です。実際には「薬剤師がオンラインで利用者と会話できる体制」が必要で、販売する店舗は当面、薬局と同じ都道府県内にある必要があります。すぐにすべてのコンビニで薬が買えるようになるわけではありませんが、過疎地や夜間などに薬を入手しやすくなる可能性があります。
若者への市販薬の販売に新たな制限が
若い世代、特に10代の間で、風邪薬や咳止め薬を意図的に大量に摂取する「オーバードーズ(OD)」の問題が深刻化しています。これを受けて、今後は「乱用の恐れのある医薬品」を20歳未満の人が購入する場合、原則として「1個まで」「小容量サイズ」に制限されるようになります。
さらに、購入時には薬剤師などから使用方法や注意点の説明を受けることが義務付けられ、必要に応じて氏名や年齢の確認も行われます。これにより、薬をむやみに買って悪用することを防ぐ仕組みが強化されるのです。
調剤業務の一部を外部に任せられるように
薬局では、薬剤師が処方箋に従って薬を準備し、患者さんに説明するという流れが基本です。しかし、薬剤師不足や業務の負担が増えている現状を受けて、「薬を取りそろえる作業(ピッキング)」や「包装、簡単な事務処理」など、直接患者に対応しない一部の業務については、外部の専門施設に委託できるようになります。
ただし、薬の内容説明や服薬指導など、専門性が高く、患者さんの安全に関わる作業は引き続き薬剤師が行う必要があります。これにより、薬剤師が本来の「人と向き合う」仕事に集中しやすくなると期待されています。
薬不足への対応がスピードアップ
コロナ禍や製造トラブルなどで、薬が一時的に手に入らなくなることが全国的に増えています。このような供給不足の状況に、国がもっと素早く対応できるように、薬機法が見直されました。
たとえば、今後は薬の製造会社に対して「供給不足が起きそうな場合はすぐに報告すること」が義務になります。また、国は必要に応じて「増産してください」と企業に要請できるようになります。さらに、ジェネリック医薬品(後発薬)を安定して供給するために、会社ごとに「供給体制を管理する責任者」の設置も義務化されます。
創薬スタートアップを国が応援
日本では、新しい薬の開発(創薬)に挑戦するスタートアップ企業が少なく、海外との「薬の承認の差(ドラッグ・ラグ)」や「日本では開発がされない(ドラッグ・ロス)」という問題が起きています。今回の改正では、このような課題に対応するために、国が「創薬支援基金」を創設することが盛り込まれました。
この基金は、研究設備の整備、薬の実用化までのサポート、申請手続きの支援などに使われる予定です。これにより、ベンチャー企業や大学発の研究機関でも、革新的な薬を開発しやすくなる環境が整えられていきます。
薬のオンライン販売と分類の見直し
要指導医薬品や第1類医薬品など、これまでは基本的に対面販売しか認められていなかった薬の一部でも、薬剤師の判断のもと「オンラインでの服薬指導」を受ければ購入できるようになる方向で制度が整備されます。
また、一般用医薬品の分類(第1類~第3類)については、大きく変更されることはないものの、「薬剤師や登録販売者がどう関与すべきか」を明確にし、必要な情報が利用者に届くようガイドラインがつくられます。薬をネットで買う人が増えている今、安全に使ってもらうためのルール整備が進んでいるのです。
便利さと安全性、その両立がこれからの課題
今回の薬機法改正は、「薬をもっと身近に、便利に使えるようにする」ことと、「薬の誤用や乱用から命を守る」ことの、両方を大事にした内容になっています。つまり、「利便性の向上」と「安全性の確保」のバランスをどうとるかが、これからの大きなテーマなのです。
私たち消費者も、薬を使うときには説明をしっかり聞いて、ルールを守って使うことが大切です。便利さだけに目を向けるのではなく、正しい知識と意識を持って薬と向き合う――それが、これからの時代に求められる姿勢なのかもしれません。
私たちにとっての意味と課題
薬機法が改正されたことで、私たちの日常にどのような影響があるのかを考えてみましょう。新しく始まる制度の多くは、一見とても便利に思えるかもしれません。しかし、その裏側にはいくつかの課題や注意点も潜んでいます。この章では、改正の「意味」と「これからの課題」を、ひとつひとつ丁寧に見ていきます。
便利になるけど、本当に安心?
改正された薬機法では、これまで薬局に行かないと買えなかった薬が、コンビニや自動販売機でも買えるようになる道が開かれました。さらに、薬剤師と直接話さなくても、スマートフォンやパソコンを通じて薬の説明を受けられるようになるのは、忙しい現代人にとってうれしい変化です。特に、夜中や休日に薬局が閉まっていても薬が買えるというのは、緊急時には大きな助けとなるでしょう。
しかし、その一方で「ちゃんと説明を聞かずに薬を使ってしまう人」が増える可能性もあります。薬には副作用があったり、飲み合わせに注意が必要だったりと、使い方を間違えると体に悪影響を与えることもあるからです。
たとえば、ある薬は「食後に1日3回飲んでください」と決まっていても、スマホの画面を流し見して誤解したまま服用してしまえば、効果が出なかったり、逆に体調を崩したりするかもしれません。便利さだけに目を向けるのではなく、「薬は正しく使うべきもの」という意識を社会全体で持つことが求められます。
若者を守る規制、だけど現場では…
市販薬の乱用が若者の間で広がっている問題に対して、改正薬機法では20歳未満への販売を厳しく制限するようになりました。これにより、風邪薬などを使って過剰摂取(オーバードーズ)をする人が減ることが期待されます。
しかし、実際の販売現場ではさまざまな工夫が必要です。たとえば、年齢確認のために身分証を見せてもらう必要がありますが、「個人情報を見せたくない」と感じるお客さんもいます。また、レジで「それ、1個までですよ」と声をかけることが、販売スタッフにとってはストレスになる場面もあるかもしれません。
つまり、制度の整備だけでなく、現場の人たちが無理なく実行できるような仕組みもあわせて整えていかなければなりません。
地方やへき地への期待と課題
今回の改正で、薬局がない地域でも薬を手に入れやすくなるように、オンラインでの服薬指導やコンビニでの薬の受け渡しが可能になります。特に離島や山間部のような「医療資源が少ない地域」では、大きな希望となる制度です。
しかし、その一方で、薬を管理する薬剤師や販売者の数が足りなかったり、通信インフラ(ネット回線)が整っていなかったりといった現実的な壁もあります。制度だけが先に進んでも、それを支える人や技術、環境が追いつかなければ、うまく運用できないのです。
また、遠く離れた場所から薬を管理するには、どうやって安全性を確保するのかという課題もあります。たとえば、倉庫に保管された薬が正しく温度管理されているか、期限切れになっていないかなど、これまでならその場にいる薬剤師が直接確認できたことが、遠隔では難しくなるケースもあるのです。
新しい薬が早く使える社会へ
今回の改正では、創薬スタートアップの支援が大きな目玉となっています。これは、新しい薬を生み出す小さな企業や研究チームを国が支援し、世界と遅れずに新薬を届けるための取り組みです。
これにより、いわゆる「ドラッグ・ラグ(海外では使えるのに、日本ではまだ承認されていない)」や「ドラッグ・ロス(そもそも開発されない)」といった問題が解決に近づくと期待されています。
ただし、創薬には長い時間と多額の資金が必要です。国の支援だけでなく、民間投資や大学などとの連携も大切になってきます。また、早く薬を承認するということは、それだけ「安全性を見極める時間が短くなる」というリスクもあります。スピードと安全性、その両立ができる制度運用が求められます。
情報の扱いとプライバシーの課題
オンラインで薬を買う、新しい薬を使う、供給状況をリアルタイムで国がチェックする――こうした新制度はすべて「デジタルデータ」が支えています。たとえば、電子処方箋のデータを活用して、薬の供給が足りているかどうかを国が監視できる仕組みも作られつつあります。
しかし、これには「個人の情報がどう扱われるのか」という懸念もあります。薬に関するデータは、いわばその人の体調や病歴にかかわるセンシティブな情報です。そのような情報が適切に管理されなければ、プライバシーが侵害されるおそれがあります。
便利な技術が進んでも、「人の情報は人が守る」という原則を忘れずに、制度の運用や企業の対応にも厳しい目が必要です。
社会全体で薬と向き合う姿勢が必要
改正薬機法は、私たち一人ひとりの生活をより快適で安全にする可能性を持っています。けれども、それは単なる制度の話ではなく、社会全体が「薬とは何か」「どう使うべきか」という価値観を共有することが求められているのです。
薬を「簡単に手に入る便利なもの」としてではなく、「正しく使えば命を守る大切なもの」として理解すること。そして、誰かが使い方を間違えそうなときには、そっと声をかけられるような、思いやりのある社会にしていくこと。そうした意識が、制度の効果を何倍にも高めてくれるのではないでしょうか。
これからの医療と薬のあり方
薬機法の改正は、単なるルールの見直しではなく、「医療のあり方」そのものを大きく変えていくきっかけになります。これからの日本社会は少子高齢化が進み、医療や福祉のかたちは今まで以上に多様化していきます。では、私たちはどのように薬と向き合い、どんな医療を目指していけばいいのでしょうか。この章では、改正薬機法がもたらす未来の姿と、そこに向けた私たちの役割について考えていきます。
医療が「届ける」ものから「支える」ものへ
かつて医療は、「病院に行って診てもらい、薬を受け取って帰る」という一方通行のサービスでした。ところが、社会の変化に伴い、「自宅で療養したい」「離島やへき地でも同じ医療を受けたい」「自分の健康は自分で守りたい」という声が高まっています。
今回の薬機法改正で、薬局に行かなくても薬が受け取れる仕組みや、薬剤師とオンラインでつながる制度が導入されるのは、まさにこうしたニーズへの答えです。つまり、医療は「患者が病院に行くもの」から、「医療のほうから患者に寄り添い、支えるもの」へと変わろうとしています。
特に高齢者や体が不自由な人にとって、薬を届けてもらえる、相談ができる、そして使い方まで教えてもらえる仕組みは、安心して暮らすうえで欠かせません。
「薬」は治療だけじゃない、生活の一部になる
これまで、薬といえば「病気になったら使うもの」というイメージが強かったかもしれません。しかし、これからの薬は「病気を防ぐ」「体調を整える」「生活の質(QOL)を保つ」といった目的でも使われるようになります。
たとえば、漢方薬や栄養補助のための医薬品など、使い方しだいでは日常の健康維持に役立つ薬もあります。また、今後はAI(人工知能)やビッグデータを活用して、一人ひとりの体質や生活習慣に合った薬の提案がされる時代も来るでしょう。
そうなると、「薬は医師の言う通りに飲むだけのもの」ではなく、「自分の体調を自分で把握して、必要なときに使う道具」のような存在になります。つまり、薬の使い方そのものが、より“自立的”で“パーソナル”なものへと変化していくのです。
医薬品の未来は「つながる」医療が鍵
これからの医療では、病院・薬局・家庭・地域がデジタルでつながる「連携型医療」がますます重要になります。薬機法の改正によって、電子処方箋やオンライン服薬指導が広まり、医師と薬剤師、患者がリアルタイムで情報を共有する時代が近づいています。
たとえば、患者の服薬歴がクラウド上で一元管理されれば、薬の重複処方や飲み合わせのミスが減り、より安全に薬を使えるようになります。また、薬剤師が患者のデータをもとに体調を把握し、生活面のアドバイスを行うことも可能になります。
これは、単なる「技術の進化」ではなく、人と人がより深くつながる医療のかたちです。薬剤師は「薬を渡す人」から「生活のアドバイザー」へと変わっていくかもしれません。
地域と医療の関係も再構築される
もうひとつ重要なのは、地域医療のあり方です。薬機法改正で注目されているのは、「地域連携薬局」や「健康サポート薬局」という、地域に根ざした薬局の役割です。これらはただ薬を出す場所ではなく、地域住民の健康を支える拠点としての役割を担います。
たとえば、地域の高齢者が相談できる場所として薬局を活用したり、生活習慣病の予防指導を受けたりすることが一般的になるでしょう。薬局が「健康の相談窓口」として機能すれば、病気になる前に防ぐ医療がもっと広がります。
また、災害時や感染症の流行など「非常時」にも、薬局が医療の最後の砦として機能するような制度設計が今後進められるでしょう。
「自己決定」の時代に必要な知識と責任
医療が個人に合わせて進化する時代において、私たち自身にも求められる力があります。それは、「正しい情報をもとに、自分の健康を判断する力」です。
薬を選ぶとき、処方箋に従って飲むとき、副作用に気づいたとき、そのすべての場面で「これは本当に自分に合っているか?」と考える姿勢が大切になります。
もちろん、その判断を支えてくれるのが医師や薬剤師です。しかし、「与えられた薬を黙って飲む」のではなく、「自分の生活にどう関わるのか」を意識して使うことで、医療の質はもっと高まります。
このように、改正薬機法が示した未来像は、「患者が主役になる医療」です。そのためには、学校教育や地域の学びの場などで、医薬品や健康に関するリテラシーを高めることが不可欠です。
未来の医療に向けて、いま私たちができること
これからの医療と薬のあり方は、国の制度だけでは完成しません。制度をどう活かすかは、私たち一人ひとりの意識と行動にかかっています。薬剤師や医師と信頼関係を築くこと。身の回りの人と健康について話すこと。正しい情報をもとに薬を選ぶこと。どれも小さなことですが、積み重なれば社会全体を支える大きな力になります。
そして何より、医療や薬の「使い手」として、自分自身の体と向き合いながら生活する姿勢が、これからの社会にとって大切な価値となるはずです。
まとめ
2025年に改正された薬機法は、私たちの暮らしに大きな影響を与える可能性をもつ、大切な法律の見直しです。本記事では、薬機法とは何か、どこがどう変わったのか、そしてそれが私たちの生活や社会にとってどんな意味をもつのかを、5章にわたってじっくりと見てきました。
この最終章では、あらためて「なぜこの改正が必要だったのか」「私たちはこれから何を考え、どう行動すればいいのか」を、わかりやすく、そして前向きな気持ちで振り返ってみましょう。
薬をめぐる社会のかたちは変わった
今回の法改正で最も大きな変化のひとつは、「薬がどこで、どうやって買えるか」という点でした。これまでは、薬局に行って薬剤師や販売員から説明を聞きながら買うのが当たり前でした。しかしこれからは、コンビニや自動販売機、さらにはオンラインでも薬が手に入るようになっていきます。
これは、仕事や育児で忙しい人や、薬局が近くにない地域の人にとって、大きな助けとなる可能性があります。さらに、AIやデジタル技術が進むことで、一人ひとりに合った薬の提案や健康管理も身近になっていくかもしれません。
しかしその一方で、薬を簡単に買えるようになるということは、「間違った使い方をしてしまうリスク」も高くなるということです。つまり、便利になる分、私たち一人ひとりが薬についての正しい知識や判断力を持つことが、これまで以上に重要になってくるのです。
法律は「守る」だけじゃない、「活かす」もの
法律というと、「してはいけないことを決めるもの」というイメージを持っている人もいるかもしれません。確かに、薬機法にも「これをしてはいけない」「これを守らないといけない」といったルールがたくさんあります。
でも本当は、法律は私たちの命や健康を守るための「道しるべ」であり、「安心して暮らすための仕組み」です。だからこそ、ルールをただ守るだけでなく、その意味を理解し、自分の生活にどう取り入れるかを考えることがとても大切なのです。
たとえば、薬局で薬を買うときに説明をしっかり聞いたり、気になることがあったら遠慮せずに質問したりすること。それは「ルールを守る行動」であると同時に、「法律を活かす行動」でもあります。
私たちが今できる、たった3つのこと
では、この記事を読んだ私たちが、今日からできることは何でしょうか。難しいことではなく、誰にでもできる小さな行動が、大きな変化につながっていきます。
まずひとつ目は、「薬についての正しい情報を持つこと」。インターネットにはたくさんの情報がありますが、中には間違った内容や誤解を招くものもあります。薬局や病院で配られるリーフレット、厚生労働省や薬剤師会などの公的なサイトを参考にするようにしましょう。
ふたつ目は、「自分の健康を自分で守ろうとすること」。体調が悪くなったとき、すぐに薬に頼るのではなく、まずは十分に休む、水分をとる、食事を整えるなど、基本的なケアを意識することも大切です。そして、どうしても薬が必要になったときは、正しく使えるように気をつけましょう。
最後の三つ目は、「身近な人と健康や薬について話すこと」。家族や友人と薬の使い方について共有したり、困っている人がいたら情報を伝えたりするだけでも、社会全体の医療リテラシーが高まっていきます。薬を正しく使う文化は、こうした一人ひとりの小さな会話から広がっていくのです。
未来の医療は、私たちがつくる
医療や法律は、専門家だけのものではありません。薬を使うのは誰か、医療を受けるのは誰か――それは、他でもない私たち一人ひとりです。
だからこそ、今回の薬機法改正をきっかけに、「もっと医療や薬に関心を持っていい」「自分の体と向き合っていい」と感じてくれる人が増えてくれたら、それこそが一番の成果だと思います。
これからの社会では、ただ「病気を治す医療」ではなく、「健康を支える医療」「誰も取り残さない医療」が求められていきます。その中心には、制度や技術だけでなく、「人と人とのつながり」や「学ぶ姿勢」があるのです。
参考資料
薬機法等制度改正に関するとりまとめ(厚生労働省)
テーマ④(少子高齢化やデジタル化の進展等に対応した薬局・医薬品販売制度の見直し)について(医薬品販売制度)(厚生労働省)