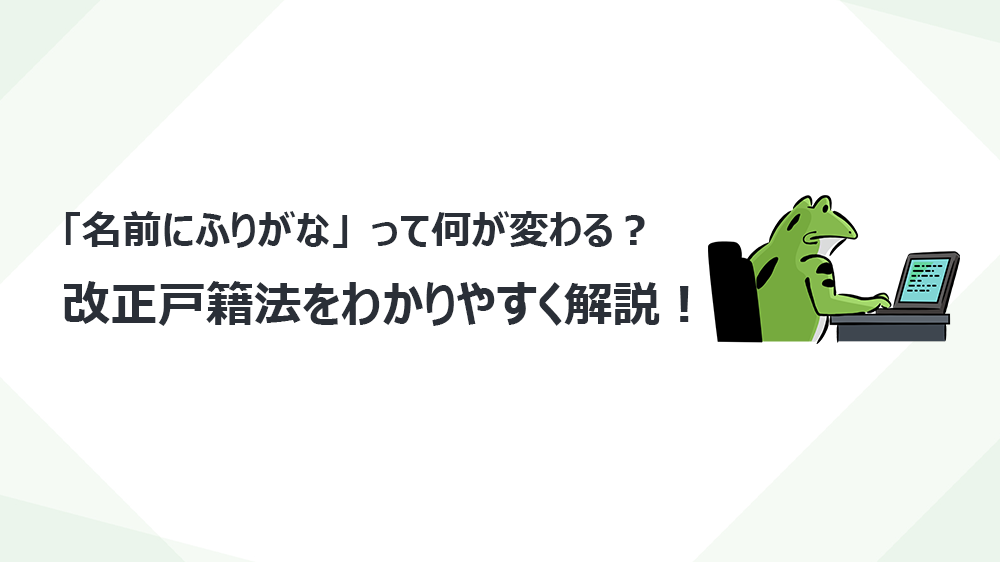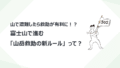2025年5月、戸籍に「ふりがな」を記載するルールがスタートしました。
これまでは名前の漢字だけが登録されていましたが、これからは“読み方”も正式に記録されます。
「ふりがなをつけるだけで、何が変わるの?」
そんな疑問に答えるために、この新ルールの意味や目的、私たちの生活にどう関わってくるのかを、わかりやすく解説します。
- 改正戸籍法とは何か?:名前に「ふりがな」がつく時代へ(第1章)
- 「ふりがなのルール」はどうなった?キラキラネームはどうなるの?
- ふりがなの届け出方法と手続きの流れを完全ガイド
- ステップ①:自分の戸籍にふりがなが登録されるってどういうこと?
- ステップ②:ふりがな確認はがきが届いたらやるべきこと
- ステップ③:ふりがなの届け出方法は3つある
- ステップ④:誰が届け出をするの?
- ステップ⑤:届け出用紙に何を書く?
- ステップ⑥:費用はかかる?罰則はある?
- ステップ⑦:もし後で間違いに気づいたら?
- 忘れてはいけない大切なこと
- たった1枚のはがきが、将来のトラブルを防ぐカギになる
- 名前に「ふりがな」があるだけで何が変わるの?
- 行政のデジタル化が加速する
- 本人確認がしやすくなる
- 不正利用やなりすましを防ぐ
- 未来の行政手続きは「ふりがな」でつながる
- 「ふりがな」で救われる人たちもいる
- 「名前を正しく呼ぶこと」は、社会の礼儀になる
- なぜ今?戸籍法が改正された理由とその背景を探る
- ふりがながあると何が便利?私たちの生活の中で役立つ具体的なシーン
- よくある質問とその答え(FAQ)――改正戸籍法をもっとわかりやすく
- 小さな変化が、大きな安心につながる
改正戸籍法とは何か?:名前に「ふりがな」がつく時代へ(第1章)
戸籍って何だろう?
まず、「戸籍(こせき)」という言葉は聞いたことがあるでしょうか。戸籍とは、私たち一人ひとりの「家族のつながり」や「名前」「生年月日」などを公的に記録した日本の制度です。例えば、どこで生まれて、誰の子どもで、どんな家族と一緒にいるのか、ということが戸籍には書かれています。
これまで、この戸籍には漢字で名前が書かれていても、「ふりがな(読み方)」は書かれていませんでした。たとえば「大翔」と書かれていても、「ひろと」「だいと」「たいしょう」など、いろいろな読み方があるため、正しく読むのは難しい場合があります。
なぜ改正するの?ふりがな追加の背景
2025年5月26日から、「改正戸籍法(かいせいこせきほう)」がスタートしました。この改正によって、すべての人の名前に「ふりがな」が戸籍に記載されることになります。
どうしてこんな改正が必要になったのでしょう?理由は主に3つあります。
- デジタル社会に対応するため
行政(市役所や法務局など)や銀行、病院、学校などでは、今や多くの情報がコンピューターで管理されています。漢字だけでは正しい読み方がわからず、データを扱うのに時間がかかっていました。ふりがながあることで、検索や確認がスムーズになります。 - 本人確認の精度を上げるため
名前の読み方が1つに決まっていないと、別人と間違えたり、なりすましに利用されたりする危険があります。ふりがなを決めておくことで、安全性も高まります。 - 不正を防ぐため
金融機関などでは、フリガナを使って口座を管理しています。ところが同じ漢字でも違うフリガナを使って複数の口座を作るなど、不正の原因になることがありました。ふりがなを統一することで、このような問題を防げるのです。
いつから?何をすればいいの?
改正戸籍法は2025年5月26日に施行されました。これから日本に住むすべての人に対して、市区町村から「確認はがき」が送られてきます。そのはがきには「あなたの名前はこう読むことにしますよ」という“ふりがな”が書いてあります。
ここでやるべきことはとても簡単です:
- そのはがきを確認して、ふりがなが間違っていないかを見る
- 間違っていた場合は1年以内(2026年5月25日まで)に届け出る
- 正しければ何もしなくてOK(自動的にそのフリガナが戸籍に記載されます)
フリガナの届け出、どうやる?
届け出の方法もいくつかあって、便利なやり方が選べます。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| マイナポータル | スマホやパソコンでオンライン申請可能 |
| 郵送 | 書類を郵送で提出できる |
| 市区町村の窓口 | 役所に直接行って手続き |
また、届け出には手数料はかかりません。つまり、お金を払う必要はありません。不審な請求には注意が必要です。
「ふりがなのルール」はどうなった?キラキラネームはどうなるの?
名前にルール?どういうこと?
「太郎」と書いて「ジョージ」と読む――そんな名前、あなたはどう思いますか?ちょっと変わってる、覚えやすい、でも読みにくい……いろんな意見があるでしょう。
実は今回の「改正戸籍法」で、こうした読み方に新しいルールが設けられました。それが、戸籍に記載される「ふりがな」に関する基準です。
どんなふりがながOK?NG?
法務省は、ふりがなについてこんなルールを発表しています:
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限る
つまり、「普通にこの漢字はこう読むよね」と誰もが納得できる読み方でないとダメ、ということです。
❌ NG(認められない例)
| 漢字 | フリガナ | なぜNG? |
|---|---|---|
| 太郎 | ジョージ | 意味や音が全く関係ない |
| 健 | ケンサマ | 尊称「さま」が不要・一般的でない |
| 高 | ヒクシ | 意味と逆(高=たかい/ヒクシ=ひくい) |
| 太郎 | ジロウ | 別の一般名と間違いやすく混乱の元 |
⭕ OK(認められる例)
| 漢字 | フリガナ | なぜOK? |
|---|---|---|
| 心愛 | ココア | 一部の読みを音として使っている(心=ここ、愛=あ) |
| 彩夢 | ユメ | 「彩」は読まないけど「置き字」として許される |
| 飛鳥 | アスカ | 熟字訓という例外的な読みが古くから認められている |
名前の自由って、なくなっちゃうの?
「名前にルールなんていやだ!」「個性がつぶされる」と思う人もいるかもしれません。でも、実はすでに使っている読み方は例外的に認められるのです。
もし現在、銀行の通帳やパスポート、学校の記録などで使っているふりがなが、法務省の定義する“一般的な読み方”に当てはまらなくても、次のようにすればOKです:
- 証明書を提出する(パスポート・預金通帳など)
- 長く使っていることを説明できる(例えば出生以来この読みで呼ばれているなど)
つまり、「今までもずっとこの読みで暮らしてきた」という証拠があれば、柔軟に対応してくれます。
赤ちゃんの命名はどうなる?
特に注目されているのが、これから生まれる赤ちゃんの名前です。出生届を出すときに名前にふりがなを添えて提出しますが、ここで“キラキラネーム”が審査の対象になります。
たとえば、
- 「太陽」と書いて「タカヤス」→OK(昔からある読み)
- 「太陽」と書いて「ルナ」→NG(関係ない意味)
市区町村の窓口で判断がつかない場合、法務局に確認されることもあります。これは、子どもが将来困らないようにするためです。
判断が難しいときは?
市区町村では、判断が難しい場合に以下のような資料の提出を求められることがあります。
- 辞書や図鑑のコピー
- 雑誌に載っている名前の例
- 親の説明文(どうしてこの読み方を選んだか)
つまり、ただの感覚ではなく、「その読み方に根拠があるか?」を重視するようになっているのです。
一度登録されたふりがな、変えられる?
ここがとても大事なポイントです。
ケース1:自分でふりがなを届け出た場合
→ 原則として、家庭裁判所の許可がないと変更できません。
なぜなら、自分の意志で届け出た以上、それを何度も変えると混乱の原因になるからです。
ケース2:届け出をしていない場合(市区町村が自動記載)
→ 一度に限り、届け出だけで変更が可能です。このときは家庭裁判所の許可は不要です。ただし、二度目以降は許可が必要になります。
改正で何が変わる?私たちの生活への影響
今回の戸籍法改正によって、「名前の読み方」が公的に登録されるようになりました。これにより:
- 行政手続きのスピードが上がる
- 読み間違いによるトラブルが減る
- 詐欺や不正利用の抑止になる
という多くのメリットがあります。
ふりがなの届け出方法と手続きの流れを完全ガイド
ステップ①:自分の戸籍にふりがなが登録されるってどういうこと?
2025年5月26日から、あなたの戸籍に「ふりがな」が正式に記載されるようになりました。でもこれは、自動的に記載されるのではなく、まずは市区町村から「ふりがな確認はがき」が届くのが第一歩です。
このはがきには、住民票などで使われている「名前の読み方」が書かれています。
- たとえば、「大翔」くんなら「ヒロト」か「タイショウ」など、実際に役所が把握している読み方が表示されます。
- この内容を見て、「あっている」「ちがっている」を判断します。
ここからが私たちの行動の番です。
ステップ②:ふりがな確認はがきが届いたらやるべきこと
はがきが届いたら、まずやることはたった一つ:
「名前のふりがなが正しいか確認する」
もし「まちがっている!」と思ったら、1年以内に届け出をしましょう。期限は2026年5月25日までです。
逆に、間違っていなければ、何もしなくてOK。1年後、自動的にそのフリガナが戸籍に登録されます。
ステップ③:ふりがなの届け出方法は3つある
ふりがなを届け出る方法は、あなたのライフスタイルに合わせて選べます。
| 方法 | 特徴 | 便利さ |
|---|---|---|
| ① マイナポータル(オンライン) | 自宅からスマホ・PCで完了。 | ★★★★★ |
| ② 郵送 | 本籍地の市区町村に郵送。 | ★★★★☆ |
| ③ 役所の窓口 | 直接相談しながら手続き。 | ★★★☆☆ |
マイナポータルって何?
マイナンバーカードを使ってログインできる、政府の便利なポータルサイトです。
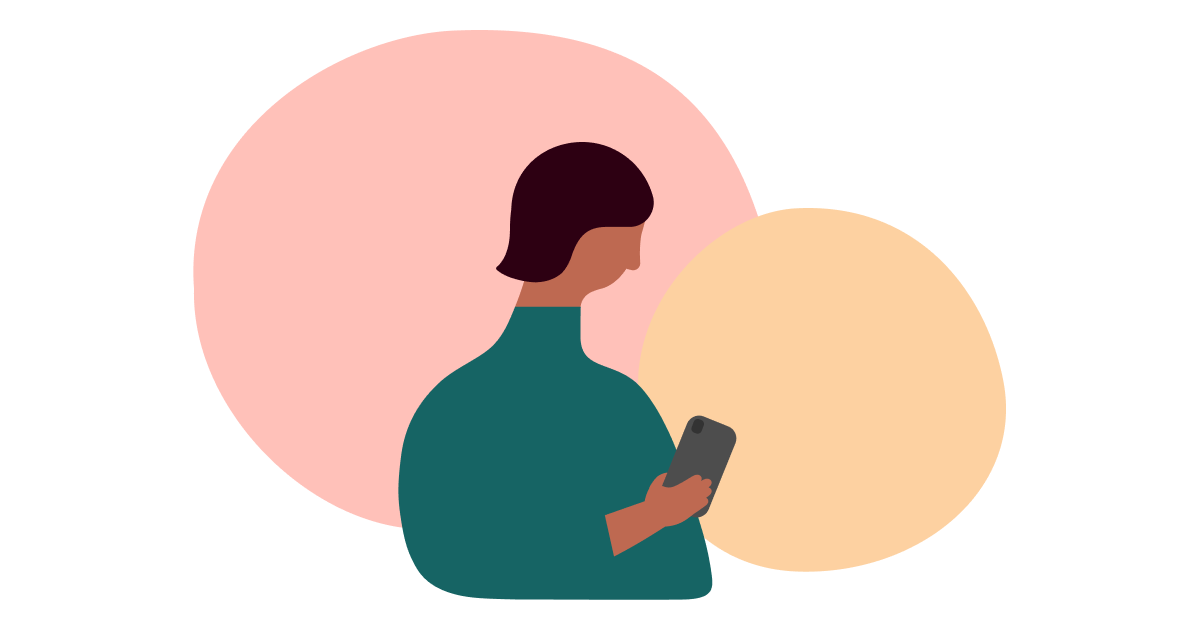
学校帰りや仕事終わりに時間を気にせず使えるので、とても便利です。
ステップ④:誰が届け出をするの?
名前の「ふりがな」を届け出る人は、苗字(氏)と名前(名)で違います。
| 内容 | 届出する人 |
|---|---|
| 苗字のフリガナ | 原則:戸籍の筆頭者(いちばん最初に名前が書かれている人) |
| 名前のフリガナ | 原則:本人自身 |
※子どもが未成年(18歳未満)の場合、親権者(保護者)が代わりに手続きできます。
ステップ⑤:届け出用紙に何を書く?
- 届け出る名前(氏・名)
- その「ふりがな」
- 本人の氏名・生年月日
- 戸籍の本籍(住民票などで確認できます)
もし「一般的ではない読み方(例:ジョージ)」を届け出たい場合は、それが日常的に使われていることを証明する書類が必要です:
- パスポート
- 銀行口座の通帳
- 学校の記録 など
ステップ⑥:費用はかかる?罰則はある?
かかりません!ゼロ円です!
今回の戸籍ふりがな登録に関して、届け出手続きに手数料はかかりません。これを悪用した「ふりがなの届け出に○○円必要です」といった詐欺には十分注意しましょう!
また、届け出をしなかったとしても罰則はありません。でも、そのままにしておくと間違った読み方が戸籍に記載されてしまう恐れがあります。
ステップ⑦:もし後で間違いに気づいたら?
状況によって、対応方法が変わります:
| 状況 | 変更方法 | 家庭裁判所の許可 |
|---|---|---|
| 自分でふりがなを届け出た場合 | 原則:裁判所の許可が必要 | 必要 |
| 届け出をしていなかった場合(自動記載) | 一度だけなら届け出でOK | 不要(一度だけ) |
※変更する場合は、市区町村に相談してみましょう。
忘れてはいけない大切なこと
戸籍にふりがなが登録されると、今後以下のような書類にも反映される予定です:
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 保険証、銀行口座などの公的手続き
つまり、「正式なあなたの名前の読み方」がいろんな場面で使われることになるのです。だからこそ、今のうちに正しいふりがなを確認しておくことが大切です。
たった1枚のはがきが、将来のトラブルを防ぐカギになる
今回の手続きはシンプルです。でもその効果はとても大きく、将来の本人確認や行政手続きのスムーズさに直結します。
- 「届いたはがき、確認しましたか?」
- 「ふりがな、合ってますか?」
- 「間違っていたら、1年以内に届け出ましたか?」
この3つを守るだけで、あなたの名前は安心して守られます。
名前に「ふりがな」があるだけで何が変わるの?
戸籍に「ふりがな」が記載される。これだけを聞くと、「そんなことで社会が変わるの?」と思う人も多いでしょう。
でも実は、この変化は日本の行政や社会の仕組みを根本から変えるきっかけになるのです。これからの日本社会が、もっと便利に、安全に、公平になるための大きな一歩と言えます。
行政のデジタル化が加速する
今までは…
戸籍にふりがながなかったため、役所のコンピューターで個人を検索するときに**「名前の読み方がわからない」**という問題がありました。
たとえば、「大翔」という名前だけでも「ひろと」「たいしょう」「だいすけ」など複数の読み方があります。コンピューターでは読み方が違うだけで「別人」と判断してしまうことも。
これからは…
戸籍に正式なふりがなが記載されることで、行政システムが正確に人を判別できるようになります。
たとえば:
- 年金や税金の記録がスムーズに統合される
- 災害時の避難者名簿が正確に作成される
- 就学・選挙・住民基本台帳の処理が高速・正確に
これにより、ミスや重複、誤送付なども防げます。
本人確認がしやすくなる
銀行口座を作る、パスポートを申請する、健康保険を使う……私たちの生活では「本人確認」が必要な場面がたくさんあります。
でも、名前の読み方がわからないと本人確認に時間がかかり、間違いも起きやすくなるのです。
改正でどう変わる?
- 住民票やマイナンバーカードにもふりがなが反映される
- コンビニでの住民票発行も、誤差なくできる
- 銀行や病院で名前の読み間違いが減る
つまり、私たちの「名前」がどこでも正しく使われるようになるのです。
不正利用やなりすましを防ぐ
これまで、ふりがなが公的に登録されていなかったため、同じ漢字の名前でも違うふりがなを使って複数の口座や契約を作ることができるケースがありました。
- 同じ「健太郎」さんでも、「けんたろう」「けんたろ」などと表記を変えることで別人になりすませる
- 悪用すれば、融資詐欺や身元偽装の原因にも
改正後は?
- 公的書類で使えるふりがなは「戸籍上の正式な読み」に統一
- 認証制度もこの読みをもとに管理される
- 不正目的でのフリガナ使い分けができなくなる
つまり、セキュリティが高まり、安心して生活できる社会に近づきます。
未来の行政手続きは「ふりがな」でつながる
政府は、デジタル社会の構築をめざして「デジタル庁」を中心にさまざまな取り組みを進めています。その中で、「人の情報の一貫性」が非常に大切だとされています。
名前という基本情報に「読み方」がつくだけで、行政の処理スピードや精度が飛躍的に向上します。
- 国税庁や年金機構、厚労省などの情報も連携しやすくなる
- 転居や転職、結婚後の各種手続きがスムーズに
- 海外での日本人登録でもふりがなが役立つ(ローマ字表記との一致)
「ふりがな」で救われる人たちもいる
名前の読み間違いは、見た目では分からないストレスを生むことがあります。
- 子どもの入学式で間違った名前を呼ばれる
- 病院で名前を言われても自分だと気づけない
- 郵便物の宛名の読み方が違って本人に届かない
戸籍にふりがながつくことで、こうした小さなトラブルや心の負担がなくなる可能性があります。
また、聴覚障害がある人や外国籍の方にとっても、ふりがながあれば音声や意味での理解がしやすくなります。
「名前を正しく呼ぶこと」は、社会の礼儀になる
ふりがなの登録は、単に「読み方を決める」というだけでなく、
「その人を正しく呼ぶことは、その人を尊重すること」
という意味をもっています。
これは、ダイバーシティ(多様性)の時代にふさわしい価値観ともいえるでしょう。
なぜ今?戸籍法が改正された理由とその背景を探る
そもそも戸籍法っていつからあるの?
戸籍制度の始まりは、なんと**飛鳥時代(7世紀)**までさかのぼります。当時は「庚午年籍(こうごねんじゃく)」と呼ばれるものが作られ、税や労働力の管理のために人々の名前と関係性を記録していました。
今の戸籍制度のもとになったのは、**明治時代の戸籍法(1872年:壬申戸籍)**です。そして、今私たちが使っている「戸籍法」は1947年(昭和22年)に制定されたもので、戦後の新しい日本の中で「家」ではなく「個人」を重視する制度へと切り替わりました。
けれども、70年以上が経った現在、社会は大きく変わりました。特にこの数年で、急速に**「デジタル化」や「グローバル化」**が進んだのです。
改正のきっかけは“行政のデジタル化”
今回の戸籍法改正の最大の目的は、ズバリ「行政のデジタル化」です。
政府は2021年、「デジタル庁」を設立し、「すべての人に優しいデジタル社会」を目指すと宣言しました。その一環で、以下のような課題が浮き彫りになりました:
- 名前が漢字だけでは検索できない(例:「大翔」の読み方がわからない)
- 人と人を区別するための正確なデータが必要
- 書類による手続きが面倒で時間がかかる
- 同姓同名や誤字によるトラブルが多い
これらの問題を解決するには、名前の「読み方」を国が公的に管理する仕組みが必要だったのです。
デジタル庁の計画とふりがな制度のリンク
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」には、戸籍制度も取り上げられており、特に次のような方針が示されています。
- 戸籍と住民票、マイナンバーの情報を統合管理
- オンライン申請の促進(例:婚姻届や引っ越し手続き)
- 正しいふりがなによる本人認証の効率化
- 海外在住者との連携(在外公館でも確認可能に)
つまり、戸籍にふりがなが入ることで、「人と人を正確に識別できるインフラ」が整うのです。
名前に「意味」と「読み」の両方が必要な時代に
これまでの戸籍には、漢字の名前があっても、「どのように読むか」はわかりませんでした。
たとえば:
- 「陽翔」→ひなた?ようしょう?はると?
- 「心愛」→ここあ?しんあい?みあ?
こうした名前の多様化(特にキラキラネームの流行)は、読み方を統一する必要性を高めました。しかも、これらの名前は学校、病院、役所などでも使われるため、公共機関同士で情報を共有する際に混乱の原因になっていたのです。
社会からの要望と議論も後押しに
今回の改正には、長年にわたる議論や社会の声も反映されています。
主な声
- 「子どもの名前が読めないと困る」
- 「同じ名前なのに違う読み方を使っている」
- 「災害時、名簿で名前が読めず支援が遅れた」
こうした現場の声が積み重なり、「戸籍にふりがなを入れよう」という動きが本格化したのです。
なぜ2025年5月26日だったの?
施行日が「2025年5月26日」になったのは、次のような準備が必要だったからです:
- 全国すべての市区町村でふりがなを管理するためのシステム整備
- 法務局・役所・外務省などの連携体制構築
- 一人ひとりに通知を送るための手続き整備
実際、2024年3月にも戸籍法の別の改正が行われており、行政手続きの簡素化や戸籍証明書のデジタル化も始まっています。この流れの「仕上げ」として、ふりがなの登録が制度化されたといえます。
法務省の姿勢:柔軟な運用と慎重な判断
改正にともない法務省は、「新しいふりがなに関するルール」だけでなく、以下のような柔軟な対応方針も示しました。
- 現に使っているふりがな(通帳・パスポート等で)を尊重
- 難読・異読名については「資料提出」による説明もOK
- 子どもの名付けについては社会常識とのバランスを重視
これにより、ルールはあるけど自由も守られるという絶妙なバランスが実現されています。
戸籍制度の「変わらない部分」と「変わる部分」
最後に、今回の改正で変わる部分と変わらない部分をまとめましょう。
| 項目 | 変わる? | 内容 |
|---|---|---|
| 戸籍にふりがな記載 | 変わる ✅ | すべての氏名にふりがなが入る |
| 名前の自由度 | 基本変わらない ✅ | ただし、読み方に基準が設けられる |
| 戸籍制度そのもの | 変わらない ❌ | 夫婦・親子関係などの基本構造はそのまま |
| 手続きの方法 | 変わる ✅ | マイナポータルなどオンライン活用 |
ふりがながあると何が便利?私たちの生活の中で役立つ具体的なシーン
「ふりがな」が戸籍に入ったからといって、何か変わるの?
「名前のふりがなが戸籍に書かれたからって、何が変わるの?」
そう思う人もいるかもしれません。でも、実はふりがなが入ることで、身近な暮らしの中でたくさんの「便利」や「安心」が増えるんです。
この章では、日常生活のいろんな場面で、ふりがながどう役立つかを例を交えて紹介していきます。
就職や進学の書類で名前を正しく読んでもらえる
たとえば、名前が「陽翔(はると)」という子どもが就職活動でエントリーシートを提出したとき、ふりがながなければ面接官は「ようしょう?たいよう?はると?」と迷ってしまうかもしれません。
でも、戸籍にふりがなが正式に登録されていれば、
- 学校の卒業証明書や
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
など、あらゆる書類に「はると」と書いてあれば、間違えられる心配がありません。
メリット
人前で自分の名前を読み間違えられることが減り、安心感につながります。
災害時の避難名簿や安否確認
地震や水害などの大きな災害が起きたとき、自治体や避難所は避難してきた人の名簿をつくります。そのとき、漢字だけの名前だと、読み方がわからず混乱することがあります。
- 同じ「優(ゆう)」という名前でも、「まさる」や「すぐる」と読む場合もある
- 音だけで名前を伝えると、漢字がわからない場合も
でも、ふりがな付きの戸籍があることで、
- 自治体の職員が正確に名簿をつくれる
- 被災者本人の身元確認もスムーズに
なります。
⇒ メリット
名前の混同や誤認が減り、命にかかわる場面でのトラブルを防ぐことができます。
外国で手続きするときに便利
日本人が海外に住んでいたり、働いていたりするケースも増えています。そうしたとき、現地の役所や銀行で書類に名前を書くと、「これはなんて読むの?」と聞かれることがよくあります。
将来的には、戸籍に記載されたふりがなをもとにして、
- マイナンバーカードにローマ字表記を追加する
- パスポートなどと統一される
といった運用が予定されています。
⇒ メリット
海外でも名前の読み方を統一して証明しやすくなるので、パスポート・銀行・入国管理などの手続きがスムーズになります。
高齢者の年金や福祉サービス
年金や介護保険などの手続きは、高齢者にとって難しく感じられるもの。でも、役所が本人確認をするとき、名前のふりがなが正式にわかっていれば、
- 書類の照合ミスが減る
- 電話や郵送のトラブルがなくなる
など、手続きが簡単になります。
特に「聞き取り」や「音声認識システム」で対応するケースが増えている中、ふりがながあることで、耳が遠くなった人にも正確な対応がしやすくなります。
婚姻届・出生届・転籍などの役所手続き
たとえば、赤ちゃんが生まれて出生届を出すときに「愛翔(まなと)」という名前をつけたとします。戸籍法改正後は、
- その「まなと」という読み方が一般的かどうかチェックされる
- 認められれば戸籍にふりがなも記載される
- 将来の書類にはすべて「まなと」と記載される
また、引っ越しや結婚で戸籍を移動するときにも、そのふりがなが自動で共有されるので、書類の不一致が起きにくくなります。
メリット
書類の手間が減る・届け出が簡単になる・不一致によるトラブルがなくなる。
病院での受付や薬の受け取り
病院で初診のとき、「〇〇さん~」と名前を呼ばれる場面がありますよね。ふりがななしの漢字だけでは、読み間違えられることがよくあります。
でも、マイナンバーカードと健康保険証が一体化することで、ふりがなが登録されていれば、病院の端末でも正確に名前を呼び出せます。
- 自分だと気づかないまま呼ばれていた
- 別の人の薬を間違って受け取ってしまった
そんなリスクが減ります。
ふりがなは「読み方」だけじゃない、“信頼”を生む仕組み
このように、戸籍にふりがながあるだけで、次のような場面で力を発揮します。
| シーン | 効果 |
|---|---|
| 学校・仕事 | 書類のミスを防ぐ |
| 災害時 | 正確な安否確認ができる |
| 海外 | ローマ字表記と一致する |
| 高齢者 | 年金・福祉手続きが楽に |
| 医療 | 名前の聞き違い防止 |
| 出生・婚姻届 | 早く正確に処理できる |
私たちが「名前を正しく呼ばれる」「書類に間違いなく書かれる」――
それは、個人を大切にする社会の基本です。
戸籍にふりがなが加わったことで、日本は“人を正しく識別し、正しく扱う”社会に一歩近づいたといえるでしょう。
よくある質問とその答え(FAQ)――改正戸籍法をもっとわかりやすく
Q1:なぜ今まで戸籍にふりがながなかったの?
A:制度ができた当時は、ふりがなを公的に登録する必要がなかったからです。
漢字の名前は日本では常識的に読めるものと考えられていましたが、最近では読みにくい名前が増えたこと、デジタル化が進んでコンピュータ処理が必要になったことなどが背景にあります。
Q2:ふりがなを間違って届け出てしまったら、直せますか?
A:はい、状況により変更できます。
- 自分で届け出た場合 → 原則、家庭裁判所の許可が必要
- 市区町村による自動記載の場合 → 一度だけなら届け出だけで修正可能
一度変更した後にもう一度変えたいときは、裁判所の許可が必要になります。
Q3:届け出を忘れたら、罰則はありますか?
A:ありません。
2026年5月25日までにふりがなを届け出なかったとしても罰則や罰金などはありません。ただし、その場合、市区町村が把握しているふりがなが自動的に戸籍に記載されてしまいます。
正しい読み方と違っていた場合は、あとから修正手続きをする必要があります。
Q4:戸籍に登録されたふりがなは、どこで使われるの?
A:さまざまな書類や手続きで活用されます。
以下のような公的書類に反映される予定です:
- 住民票
- マイナンバーカード
- 健康保険証(マイナ保険証)
- 年金・介護・福祉サービスの申請書
- 学校や就職の証明書類
また、銀行・病院・携帯電話契約など、本人確認が必要な場面でも使われるようになります。
Q5:ふりがなの届け出ってどうやってやるの?
A:3つの方法から選べます。
- マイナポータル(オンライン)
スマホやPCで、自宅にいながら手続き可能。 - 郵送
市区町村の役所に届書を送付。 - 窓口
直接、役所に行って相談・手続き。
それぞれの方法に応じて、本人確認書類や届書の準備が必要です。
Q6:手数料や費用はかかりますか?
A:かかりません。
戸籍にふりがなを届け出るために、お金は一切かかりません。
この点を悪用した詐欺には要注意です。
「お金を払えばふりがなを登録します」といった電話やメールには、絶対に応じないでください。
Q7:そもそも「ふりがな」って何の文字で書くの?
A:カタカナです。
戸籍に記載されるふりがなは、すべてカタカナ表記になります。
漢字やひらがな、ローマ字などでは記載されません。
Q8:外国籍の人や帰化した人も対象ですか?
A:はい、日本国籍を取得した時点で対象になります。
帰化や出生によって新たに戸籍が作られる場合、その時点でふりがなを届け出る必要があります。
在外公館(海外の日本大使館・領事館)でも相談できます。
Q9:名前の読み方に制限って、どこまで?
A:社会通念上「意味や音と全く関係ない読み」は認められません。
例として、以下のような読み方は原則NGとされています:
- 「太郎」→「ジョージ」
- 「高」→「ヒクシ」(意味が逆)
- 「健」→「ケンサマ」(尊称混入)
ただし、「心愛(ココア)」や「彩夢(ユメ)」のように一部の音を使っていれば認められるケースもあります。
Q10:この制度で私たちの暮らしはどう変わるの?
A:名前を正確に呼ばれ、正しく扱われる社会になります。
- 就職や進学で間違えられない
- 災害時の本人確認が正確に
- 行政サービスがスムーズに
- 病院や金融機関でのトラブル防止
この制度の本質は、「一人ひとりの名前を正しく尊重すること」です。
小さな変化が、大きな安心につながる
「ふりがな」の記載は、一見すると地味な変更です。
でも、その効果は確実に私たちの生活を変えます。
- デジタル社会の基盤として
- 名前の読み間違いを防ぐ安心として
- 自分の名前に誇りをもてる環境として
ふりがなは、「人を正しく認識する」という社会の基本的なルールに、新たな信頼と明快さを与えるものです。
戸籍法の改正は、これからの時代を支えるための第一歩なのです。
参考資料
マイナポータル
戸籍にフリガナが記載されます(法務省)
必ず確認しよう! 戸籍のフリガナ通知書(政府広報オンライン)