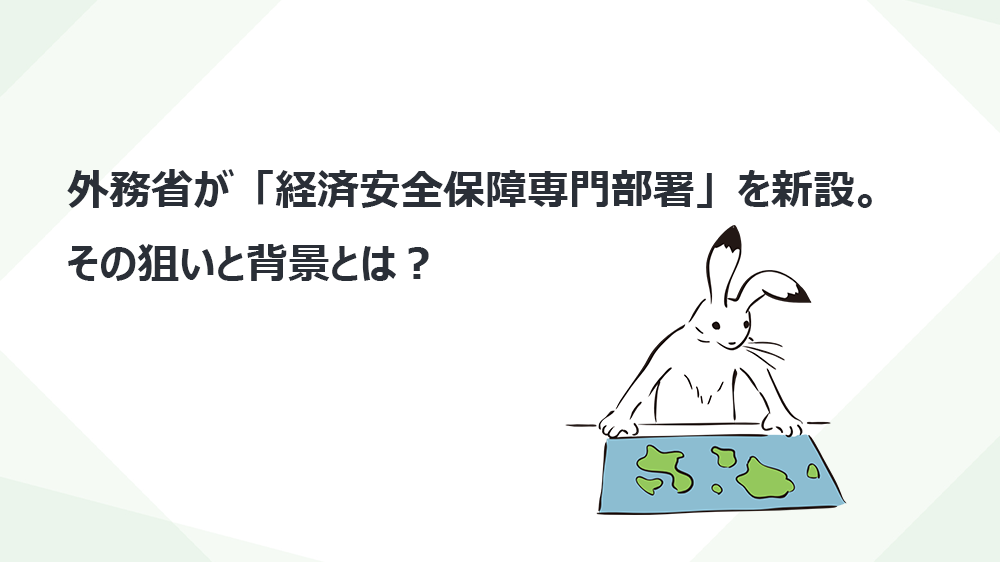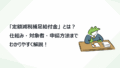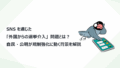経済の力が国家の安全保障に直結する時代。日本政府はその現実に対応するべく、外務省に「経済安全保障専門部署」を新設する方針を固めました。これまで経済産業省や内閣官房が担ってきた経済安保政策に、なぜ今、外務省が本格的に乗り出すのか――。その背景には、米中対立や先端技術の争奪戦といった国際情勢の急激な変化があります。本記事では、新部署の狙いと役割、そして日本の安全保障政策に与える影響について、わかりやすく解説します。
なぜ今「経済安保」なのか?
「経済安全保障」という言葉を耳にする機会が、近年急激に増えています。かつては安全保障というと、軍事や外交が主なテーマでした。しかし今や、経済の分野も国の安全と直結するようになっています。エネルギーの安定供給、先端技術の流出防止、サプライチェーン(供給網)の確保など、経済の動きが国家の安全に大きな影響を与える時代に入ったのです。
2022年には「経済安全保障推進法」が成立し、経済と安全保障を結びつけて国の政策を立案・実行する体制が整い始めました。この法律は、重要物資の供給確保や、先端技術の研究開発支援、重要インフラの監視などを通じて、外部からの経済的なリスクに備えることを目的としています。つまり、私たちの暮らしを支える“経済の基盤”を守るために、政府が本格的に動き出しているのです。
なぜ、こうした動きが急務となっているのでしょうか?最大の理由は、国際社会の構造変化です。特に米中対立の激化や、ロシアによるウクライナ侵攻など、地政学リスクが世界中で高まっており、経済の分断や技術覇権をめぐる争いが顕在化しています。日本も例外ではなく、外国との関係が経済的な形で揺さぶられる危険性が日増しに高まっています。
たとえば、ある国が半導体の製造装置を輸出制限すれば、日本の製造業全体が深刻なダメージを受けるかもしれません。逆に、日本の技術が他国に流出することで、安全保障上の脅威を生むリスクもあります。こうした経済と安全保障の複雑な関係性に対応するため、「経済安全保障」という新しい視点が必要とされているのです。
このような背景の中で、外務省が新たに「経済安全保障専門部署」を設けることを発表しました。これは単なる組織改編ではなく、日本の外交・安全保障政策において大きな転換点になる可能性を秘めています。
経済安保専門部署を新設
2025年7月29日、外務省は「経済安全保障」を専門に担当する新部署を設置する方針を発表しました。これは、現在の「経済安全保障室」を拡充し、局長級の幹部をトップに据えたより強力な体制へと格上げするものです。2025年度内にも本格始動するとされており、日本の外交政策における経済安全保障の優先順位が一段と高まったことを示しています。
この新設部署は、従来の「経済局」とは別組織として設けられます。経済局が貿易交渉や経済協定といった通常の経済外交を担当するのに対し、新部署は国家の安全保障という観点から経済問題に対処するのが特徴です。つまり、経済を「国益」と「脅威」の両面からとらえ、より戦略的に活用・管理していくための司令塔の役割を果たすことになります。
実際に新部署が取り組むとされる課題は多岐にわたります。たとえば、
- 先端技術の海外流出防止
- 対外投資や輸出管理の見直し
- 重要インフラ(通信・電力など)への外国資本の関与監視
- 経済制裁の実施と国際連携
といった領域が想定されています。これらはすでに内閣官房や経済産業省が対応している分野でもありますが、外交ルートを通じた国際協力や情報交換、外資規制に関する外国との交渉などは、外務省が主導すべき局面も多く、専門部署の新設はその体制強化の一環といえるでしょう。
また、外務省がこのタイミングで動いた背景には、国際社会の動きもあります。アメリカでは国家安全保障会議(NSC)内に経済安保の担当部署が設けられており、EUでも経済安全保障戦略が強化されています。日本もこうした各国の体制と連携を強める必要があり、そのためには外務省内に相応の窓口が不可欠だと判断されたのです。
加えて、サイバー攻撃や情報操作といった非軍事的な脅威が増加する中で、「外交×経済×安全保障」という複合的な視点を持つ組織が求められています。たとえば、ある国が企業買収を通じて日本の重要データにアクセスするような事態を未然に防ぐには、法的規制だけでなく、外交交渉や国際的な情報共有も不可欠です。そうした機能を果たすべく、外務省が経済安保に本格参入するのは自然な流れといえるでしょう。
今回の新部署設置は、日本の安全保障政策における「分野横断型アプローチ」の象徴ともいえます。これまでの縦割り的な行政構造では対応しきれなかったリスクに、より柔軟かつ迅速に対処することが期待されています。
なぜ外務省なのか? 経産省・内閣官房との役割分担
経済安全保障といえば、これまで主に「経済産業省」や「内閣官房」が中心的な役割を担ってきました。ではなぜ、今回新たに外務省が専門部署を設ける必要があったのでしょうか。そこには、経済安全保障というテーマの「性質の変化」と「外交の重要性」が深く関わっています。
まず経産省は、企業活動や産業政策を所管しており、経済安全保障推進法の設計・実施を主導してきました。たとえば、先端技術の研究開発支援や重要物資のサプライチェーンの強化など、企業や産業界との連携が求められる政策は、まさに経産省の得意分野です。
一方で内閣官房は、政府全体を束ねる司令塔的な役割を果たしています。国家安全保障局(NSS)内には経済班が設置され、戦略的な調整や政策全体の統括を行っています。つまり「全体の方向性を定めるのが内閣官房」、「具体策の設計・実行が経産省」という棲み分けがなされてきたわけです。
ここに、外務省が加わる意義は「外交ルートを活用した経済安保の実現」にあります。たとえば、半導体や通信機器といった戦略物資の取引や、対中・対露の輸出規制などでは、G7をはじめとする国際枠組みの中での協調が不可欠です。日本単独で動くのではなく、アメリカや欧州、アジア諸国との連携を図る上で、各国の外務当局とのパイプを持つ外務省の役割が大きくなってきているのです。
また、外国企業による日本企業の買収(外資規制)や、対外的な情報操作、サイバー攻撃への対処など、経済分野の脅威はますます「国際的・越境的」になっています。こうした課題は、日本国内だけで完結するものではなく、相手国との外交的なやり取りや情報共有が必要です。外務省には、各国大使館ネットワークや外交交渉のノウハウがあり、これを経済安全保障にも活用しようというのが今回の動きです。
さらに、外務省が経済安全保障に本格参入することで、国際交渉において“主導権を握るチャンス”も広がります。たとえば、米中の狭間で揺れるアジア諸国に対して、日本が技術協力やインフラ支援を通じて信頼を築くには、「経済」と「外交」を一体で考える戦略が欠かせません。新たな専門部署は、まさにそうした役割を担うために設けられたのです。
もちろん、今後の課題もあります。他省庁との「縄張り意識」が障害になる恐れがあり、縦割りの弊害をいかに乗り越えるかが鍵となるでしょう。しかし、経済安全保障の本質が複雑化している今、外務省がこの分野に本腰を入れることは、リスクに先回りする体制づくりとして大きな意義を持ちます。
米中対立・技術覇権争い
外務省が経済安全保障に本格参入する背景には、世界全体の緊張構造の変化があります。とりわけ注目すべきは「米中対立」と、それに伴う「技術覇権をめぐる争い」です。この対立は、単なる貿易摩擦ではなく、情報・軍事・経済を巻き込んだ“構造的な競争”へと発展しています。
近年、アメリカは国家安全保障の観点から、中国企業への規制を強化してきました。代表的なのが通信機器大手ファーウェイや半導体製造装置の分野です。輸出禁止措置や投資規制などを通じて、中国の先端技術の発展を封じ込めようとしています。これに対して中国は、自国の技術開発を加速させる「自立自強」路線を進め、国家主導で半導体・AI・量子技術などへの投資を拡大しています。
こうした動きは、世界中の国々に“選択”を迫っています。アメリカ側に立つのか、中国との関係を保つのか。特に日本のような先進技術を持ちつつも、対中経済依存度が高い国にとっては、慎重な対応が求められます。
日本政府も、この変化を受けて様々な対策を講じてきました。経済安全保障推進法の制定や、対内直接投資の審査強化、重要技術に関する官民共同の研究支援などがその一環です。そしていま、こうした国内政策を海外と連携して進める必要性が高まっていることから、外務省が新部署を設置するに至ったのです。
また、米中対立のほかにも、ウクライナ戦争によるエネルギー危機や、紅海の通商ルート不安定化、インド太平洋地域での地政学的緊張など、世界のあらゆる場面で経済と安全保障が結びつく現象が顕在化しています。従来のように「経済は経済、軍事は軍事」と分けて考えるのではなく、すべてがつながっているという前提で政策を設計する必要が出てきました。
技術覇権という観点でも、量子コンピューター・AI・宇宙開発・5G/6Gといった分野は、今後の国家間競争の鍵を握るとみられています。これらの分野では、軍事転用の可能性が高く、しかも一度でも技術が漏洩すれば取り返しがつかないリスクを伴います。そのため、どの国も「技術の囲い込み」と「国際的な枠組みづくり」の両方を急いでいるのです。
日本にとって重要なのは、こうした国際動向を的確に把握し、自国の産業・技術を守ると同時に、同盟国やパートナー国と信頼関係を築くことです。そのためには、外交の専門家である外務省が、経済安保の分野に乗り出すことが不可欠になっています。
今後の課題と展望
外務省が経済安全保障の専門部署を新設するという動きは、日本の安全保障体制にとって画期的な一歩ですが、同時にいくつかの課題も浮かび上がっています。経済と外交、さらには安全保障が交差する分野だからこそ、縦割り行政の限界や、情報共有の難しさ、民間との連携不足といった「構造的な壁」にどう向き合うかが問われることになります。
まず最大の課題は、他省庁との役割分担と連携のあり方です。すでに経済産業省や内閣官房が経済安全保障政策を進めている中で、外務省がどのように「自分たちの役割」を確立するかが重要になります。仮に各省がバラバラに動けば、国際交渉の場で一貫性を欠き、相手国との信頼関係を損なうおそれすらあります。したがって、組織間の横断的な調整機能や、定期的な情報共有の枠組みを構築することが急務です。
次に問われるのが、人材の育成と専門性の確保です。経済安全保障は、国際法、通商、技術、インテリジェンス(情報分析)など、非常に幅広い知識が求められる分野です。外務省の職員がこれまで担ってきた伝統的な外交業務とは異なり、サプライチェーンや先端技術に関する専門的な理解がなければ的確な判断ができません。そのため、専門人材の登用や、技術系省庁・民間企業との人材交流が鍵になります。
また、民間企業との関係構築も見逃せない課題です。経済安保の多くは「企業現場で起きる事象」です。たとえば、外国企業からの買収提案や、サイバー攻撃の兆候といった情報は、企業が最初に気づくケースが多いです。そうした情報を行政側とスムーズに共有し合えるような「信頼のインフラ」を築くことが、実効性ある政策につながります。民間への情報提供や助言、国際ルールの説明など、企業を支える立場としての役割も外務省に期待されます。
さらに視野を広げると、日本は今後、国際ルール作りの舞台でも主導権を発揮する必要があります。AI、量子技術、バイオなど、先端分野では国際的な合意形成が遅れており、ルールが不在のまま技術だけが進んでいます。こうした状況下で、民主主義国としての日本が透明性あるルール形成を主導すれば、国際的な信頼を高めることにもつながります。外務省の外交ネットワークや交渉力が試される場面です。
最後に、国民的な理解と関心の促進も忘れてはなりません。経済安全保障と聞くと、一般には「難しそう」「自分には関係ない」と思われがちですが、実際には生活や雇用、通信インフラ、医薬品の安定供給といった、私たちの身近な問題と密接につながっています。新しい体制が「国のため」だけでなく、「暮らしの安心」にもつながることを、わかりやすく伝える努力が今後求められます。
日本の経済安保政策はどう変わるのか
外務省が経済安全保障の専門部署を新設するというニュースは、一見すると省庁の組織改編のひとつに過ぎないように見えるかもしれません。しかし、その背後には日本が抱える国家的な課題と、急速に変化する国際情勢への強い危機感が透けて見えます。私たちはいま、経済の力が「武器」にも「脅威」にもなり得る時代に生きており、もはや安全保障を軍事だけで語ることはできません。
これまで日本の安全保障政策は、自衛隊の整備や日米安保体制の強化など、伝統的な防衛力を中心に構築されてきました。しかし近年では、半導体やレアアースの供給途絶、通信ネットワークの脆弱性、技術流出といった“経済由来のリスク”が急増しています。こうした問題は、外交交渉や国際協力なしには解決できないため、経済と外交、安全保障が交差する「経済安全保障」という視点が不可欠になったのです。
外務省がこの分野に本腰を入れることで、経済安全保障政策はより多層的かつ機動的になる可能性があります。外交ルートを通じてG7やQUADなどの多国間枠組みと連携し、信頼できるサプライチェーンを構築する。新興国と技術協力やインフラ支援を進め、日本の国際的な存在感を高める。さらには、AIや量子技術といった未来産業のルール作りでも、先進国として責任ある立場を果たす――そのすべてが、外務省新部署の今後の活躍にかかっています。
一方で、政策の実効性を高めるには、政治主導の明確なビジョンと省庁間の緊密な連携が必要です。さらに言えば、経済安保の要諦は「予防」にあります。すでに危機が表面化してからでは遅く、リスクを察知し未然に防ぐ体制づくりこそが、本質的な安全保障といえるでしょう。そのためには、外務省をはじめとした関係機関が、民間企業や学術機関とも連携しながら、“見えにくい脅威”を可視化する努力を続ける必要があります。
そして何より大切なのは、こうした取り組みが“私たちの暮らし”とつながっているという実感です。経済安全保障は決して専門家だけの話ではありません。電力や食料、通信、雇用といった日常の基盤を守るためにこそ、国は動いているのです。
外務省による新部署の設置は、その第一歩に過ぎません。これからの経済安全保障政策がどこへ向かうのか、私たち一人ひとりが関心を持ち続けることが、より強く、柔軟な国家づくりにつながっていくはずです。