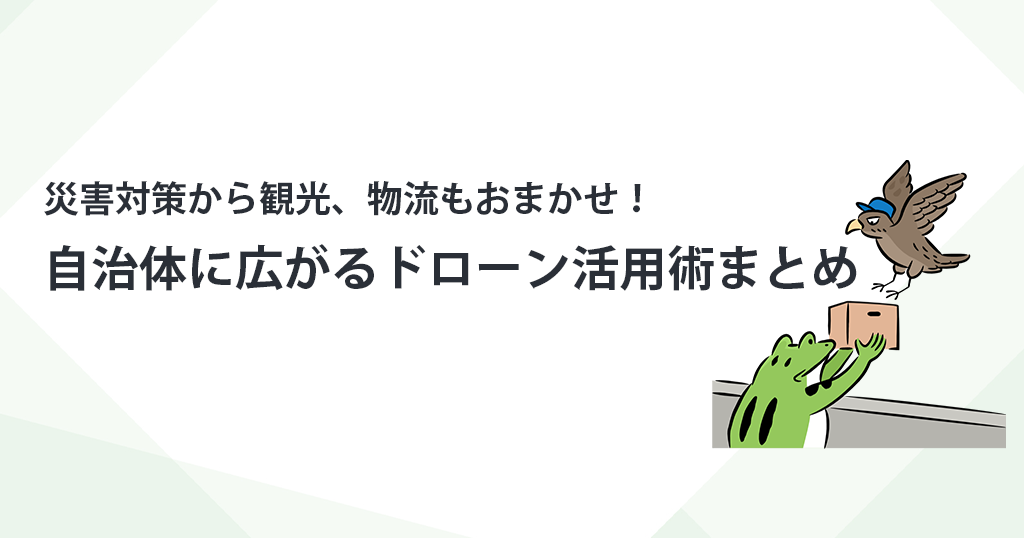ドローンは非常に多面的なツールであり、まさに地域課題や防災・減災に役立つ可能性が高いと言えます。各自治体が導入を進めている背景や課題、そして今後の展望などをまとめてみました。皆さんにも、身近な地域でのドローン活用にぜひ注目してみてください。
自治体とドローン活用の基礎知識
ドローンは、日本語で「無人航空機(むじんこうくうき)」と呼ばれ、遠隔操作や自動運航によって空を飛ぶ小型の航空機のことです。もともとは軍事目的で使われることが多かったのですが、近年では民間分野での利用が急速に広がっています。カメラを搭載した映像撮影から始まり、今では農薬散布や測量、災害現場の情報収集・救助など、多岐にわたる場面で活躍しています。
いま地方公共団体(市町村や県など)がドローンを導入したり、民間事業者と協力してサービスを展開したりする事例が増えています。特に広大な山間部や離島などがある地域では、高齢化・人口減少による人手不足や、道路整備が進んでいない場所が多く、「人が近づきにくい地域こそ素早く情報を集めて対応したい」というニーズがあります。そこで、軽くて小回りがきき、空から撮影・移動できるドローンが非常に役立つのです。
たとえば、以下のようなケースで自治体のドローン活用が注目されています。
- 災害対応・防災分野
大規模な台風や地震などで被害を受けた際、人命救助や被害状況の把握が必要になります。しかし、道路が寸断(すんだん)されて車両が入れないケースも少なくありません。そこで、ドローンを活用して上空から被災地の情報を収集する事例が多く見られます。 - 物流・物資輸送
山間部や離島などでは、高齢化や物流コストの増加が深刻です。郵便物や生活必需品(医薬品・食品など)をドローンで運搬する取り組みが進みつつあります。国土交通省や経済産業省などが主体的にガイドラインを作り、自治体と共同で実証実験を行う事例も増えています。 - インフラ点検・測量
橋梁(きょうりょう)やトンネルなどの土木インフラ、農地や森林の把握などにもドローンが役立っています。従来は人が目視や大がかりな機械を使って何日もかけて作業していた点検も、ドローンを使うことで上空から効率よくデータを取得しやすくなります。 - 観光振興・PR
観光地の魅力を伝えるために、ドローン空撮の美しい映像を使う自治体も増えています。また、「ドローンを飛ばせる観光地」としてツアーを企画し、ドローンファンの誘客を狙う事例もあります。
自治体がドローンを活用するには、航空法や電波法などの法律への対応が欠かせません。たとえば、人口密集地(DID地区)でドローンを飛ばすには国土交通大臣の許可・承認が必要です。また災害時には、消防・警察・自衛隊などの有人ヘリコプターが飛ぶ「緊急用務空域(きんきゅうようむくういき)」が設定される場合があり、ドローンとの空域調整が重要になります。一方で、自治体と企業・団体との間で「災害協定」を結び、非常時にドローンを活用する枠組みを決めておくことで、迅速に役割分担できる体制作りが進んでいます。
このように、ドローンの導入は自治体にとって大きなメリットをもたらす反面、操縦者の育成や機体の保有コスト、法規制への対応などクリアすべき課題も存在します。とはいえ、高性能化や価格の下落が進む今、各自治体がドローンを導入するハードルは年々下がっていると言えるでしょう。
災害時のドローン活用
近年、日本各地で大規模災害が多発しています。特に地震・台風・集中豪雨に伴う洪水や土砂崩れなどは、被災地の広範囲な道路寸断を引き起こし、現地での被害状況把握を困難にします。このようなときドローンは、迅速に上空から映像を取得して情報を集められる点で非常に強力なツールとなります。
たとえば2025年頃を目標にした国のロードマップでは、ドローンによる「レベル4飛行」(人口がいる地域の上空を補助者なしで目視外飛行)を実現するため、航空法の改正が進められてきました。これにより、災害発生直後に自治体や消防が「緊急用務空域」内で必要な手続き・調整を経てドローンを飛ばしやすくなる可能性があります。一方で、ヘリコプターなどの有人航空機との衝突リスクを避けるための空域調整や、現場での通信手段の確保などは大きな課題として残ります。
実際の災害では以下のような観点で、ドローンが大きく役立ちます。
- 被災現場の迅速な状況把握
人が立ち入れない場所や通行止めの道路沿いなどでも、ドローンを使えば上空から映像を撮影できます。これにより行方不明者の捜索や被災規模の早期評価が可能となります。
さらにドローンに赤外線カメラを搭載すれば、昼夜を問わず人や動物の体温を見分けて捜索することもできます。ただし雨天や強風下では飛行が不安定になるため、天候リスクにも配慮が必要です。 - 孤立集落などへの物資輸送
令和6年能登半島地震の事例では、道路の土砂崩れで車両が入れず徒歩でも危険なルートが残った地域に対し、ドローンで医薬品や生活必需品を運んだケースがありました。ペイロード(積載量)は比較的少ないものの、短距離かつ緊急性の高い物品を輸送するには効果的です。 - 被害認定調査の効率化
多くの住家が被災した場合、被災認定のために多数の職員や専門家が現地を回る必要がありましたが、ドローンによる撮影を活用すればリモートで認定調査の一部を行うことができます。たとえば自治体がドローンを保有していなくても、民間のドローン企業や専門団体と協定を結んでおけば、災害時にすぐに飛行チームを呼び寄せることが可能になります。 - 土砂災害現場の危険回避
土砂災害など二次災害のリスクが高い現場で、人員が近づくのは非常に危険です。そこで、ドローンによる上空監視や三次元地形計測を行うことで、地上での作業員の安全を確保しつつ、復旧計画に必要な情報を得られます。
実際に自治体レベルで導入が進む背景としては、「消防団へのドローン配備」「自治体が民間のパイロットと協力」「警察や自衛隊と合同訓練」などが挙げられます。消防庁や経済産業省なども支援策を講じており、導入に伴うコスト面での負担軽減や研修の機会提供が行われるケースがあります。
一方で、災害時のドローン活用には以下のような課題があります。
- 通信インフラの確保
電波が切れた場合に、操縦や映像伝送が中断される恐れがある。衛星通信などのバックアップやフェイルセーフ機能の確認が重要。 - 飛行ルールの理解
緊急時でも航空法の特例が適用される範囲や条件を把握し、事前に申請や協議をしておかなければならない。 - 操縦スキル
災害時は地形の変化や風が強いケースが多く、通常よりも高い操縦スキルが要求される。常日頃からの訓練が欠かせない。
それでも災害初動時の情報収集や物資輸送へのドローンの効果は大きく、今後ますます自治体への導入が広がると考えられています。
物流やインフラ点検・観光分野でのドローン活用
ドローンは災害対応だけでなく、平時においても自治体の抱えるさまざまな課題を解決するツールとして注目を浴びています。ここでは代表的な「物流」「インフラ点検」「観光」分野における活用事例を詳しく見ていきましょう。
物流分野での活用
日本全国で、人口減少や高齢化による人手不足が顕著になっています。特に離島や山間部などでは、宅配業者のトラックが走りにくい地形や長距離移動コストが課題です。そこでドローン配送の実験が複数の自治体で行われています。
- 中山間地域への買い物代行
石川県加賀市や小松市などでは、中山間地域の高齢者が日用品の買い物に苦労しているため、ドローンで医薬品や食料品を届ける取り組みを進めています。地上輸送とドローンを組み合わせる「ハイブリッド配送」を導入し、より効率的な物資輸送を実現しようとしています。 - 医薬品の緊急輸送
豪雪地帯や道路が災害などで遮断された地域に、必要な薬や医療品をドローンで運ぶ試みが各地で行われています。たとえばレベル3または4の飛行許可を取得することで、目視外飛行を行い、広範囲をカバーすることが期待されます。
こうした物流分野でのドローン活用は、国土交通省などが主導する実証実験でノウハウが蓄積されつつありますが、依然として規制面・安全面の課題は残っています。自治体としては、防災と合わせて「過疎地域の物流確保」という観点から導入メリットを考える例が増えているようです。
インフラ点検や測量での活用
自治体が管理する橋やトンネル、水道や下水管などのインフラは、経年劣化が進んでいます。ところが専門技術者や点検要員が不足し、従来のやり方では人手と時間が大幅にかかってしまうのが現状です。
- 橋梁の点検
ドローンに高性能カメラを搭載し、橋桁(きょうげ)の下面や支承(ししょう)部分など、人が足場を組まないと目視点検できなかった場所を短時間で撮影できます。加賀市や君津市などでは、職員がドローンで橋の損傷を確認したりAI技術で解析したりする事例も見られます。 - 河川やダムの調査
河川の堤防やダムの堆砂(たいしゃ)状況をドローンで空撮し、画像データを用いた三次元モデルを作成することで、土砂堆積量を正確に算出する取り組みが実施されています。防災や維持管理の計画に役立つほか、緊急時の判断材料としても有効です。
こうしたインフラ点検や測量にドローンを活用するメリットは、「大幅なコスト削減」「安全性の向上」「点検精度の向上」です。職員が危険な場所に立ち入るリスクを減らしつつ、広範囲を短時間でカバーできる点が評価されています。
観光振興・プロモーション
自治体が観光客誘致や地域ブランディングを狙う際にも、ドローンは大きな味方となります。具体的には以下のような事例があります。
- 空撮映像を活用した観光PR
迫力ある空撮映像を、テレビCMやSNSなどで発信して観光客を呼び込む事例です。山や海、城郭(じょうかく)などの名所を上空から見る映像は多くの人の興味を引きます。 - ドローン体験ツアー
豊かな自然が残る地域や離島などで「ドローン体験イベント」を開催し、ドローンを初めて操縦する人でも楽しめる仕組みを提供する試みもあります。自治体が民間企業と連携することで、地域経済の活性化や新しい観光商品につなげています。
さらに、ドローンレースやアート(ドローン・ライトショーなど)を観光コンテンツに取り入れる動きもあります。ただし、観光地は人が多く集まる場所でもあるため、安全確保や騒音対策、飛行規制への配慮が欠かせません。自治体が主体となって「飛行ルートや空域の指定」「事前の住民説明」などを行うことで、スムーズな運営を図っています。
導入に向けた課題と今後の展望
最後に、自治体がドローンを本格導入・活用する際の課題と、その先にある展望について整理します。
課題
- 法的・制度的ハードル
- 航空法では、150m以上の高さや人口密集地の上空飛行には国の許可・承認が必要。また、夜間や目視外飛行、物件投下など特別な飛行形態にも追加の許可申請が求められます。災害時の特例はあるものの、実際に災害が起きてから許可を取るのは現実的ではないため、自治体が平時から申請の準備やマニュアル化を進めておくことが重要です。
- また、住民のプライバシーや騒音への懸念など、自治体として地域住民と充分なコミュニケーションを図る必要があります。
- 操縦者の育成と人材不足
- ドローンを活用するには、操縦免許を持つ人材が不可欠です。特に災害や測量などは精度の高い操縦スキルが要求され、トラブル発生時のリカバリー能力も求められます。
- 自治体の職員だけでなく、消防団や地元企業、NPO法人などと連携して人材育成を進めるのが一般的です。
- コストと予算確保
- ドローンの機体価格やメンテナンス、通信費、システム導入費用などを総合的に見積もる必要があります。また、複数台の導入や高性能機の購入には相応の予算が求められます。
- 国や県の補助事業、または民間企業の協賛などを活用し、複数の財源を組み合わせるケースが多く見られます。
- 通信・運用体制の整備
- 災害時にこそドローンが活躍する場面が多いのに、同時に携帯電話やWi-Fiといった通信インフラが損傷を受ける可能性があります。衛星通信やフェイルセーフ機能を備えたシステムの導入が求められます。
- 複数のドローンが同時に飛ぶ場合の空域管理や衝突回避システムの導入も課題です。
今後の展望
- レベル4飛行の全面解禁と社会実装
- 2022年の航空法改正でレベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)が実現する方向にあります。これが本格的に運用されれば、自治体が小回りの効く形でドローンを使った物流や監視を行える可能性が飛躍的に高まります。
- 官民連携の促進
- 自治体だけでドローン導入・運用を進めるのは負担が大きい場合があります。そこで、「ドローンスクールを運営する民間企業」「ドローンを使った農薬散布サービス事業者」「映像撮影や測量に強いNPOや大学」といった様々なパートナーとの連携が鍵になります。特に災害協定の締結や平時の訓練は有効です。
- データの共有とAI解析
- ドローンが撮影・収集する膨大な映像や測量データを、AI(人工知能)や専用ソフトウェアで解析し、自治体の業務効率化をさらに進める取り組みが増加しています。道路や橋の点検で得られた画像をクラウド上でリアルタイムに共有し、専門家が遠隔地で解析する仕組みも登場しています。
- 世界的な事例との比較
- 海外では、災害時にドローンだけでなく配送ロボットとの連携による多拠点配送や、衛星との通信連携による常時接続など、より高度な活用が進んでいる地域があります。日本でもこうした事例を参考にしつつ、より広範囲・長距離の運航が可能になる技術開発が進められるでしょう。
今後の期待
ドローンは、地上車両や人が入りづらい場所で威力を発揮する非常に優れた手段です。自治体が率先して活用することで、災害対応をはじめ、物流、インフラ点検、観光など幅広い分野にメリットが及びます。今後は技術発展や制度整備により、コスト・安全面・操縦者不足などの課題が緩和されることが予想されます。そして実際に成果を上げている地域の成功事例が増えることで、他の自治体が導入を検討する動きもますます活発になるでしょう。
ただし、大きな成果をあげるためには単に機体を購入するだけでなく、事前の訓練や協定締結、運用マニュアルの整備、住民への理解促進が不可欠です。中学生の皆さんにとっても、将来働く職場として行政や消防・警察などでドローンを操縦する選択肢が出てくるかもしれません。そうしたときに、「ドローンは社会課題の解決や緊急時の救助に役立つテクノロジーなんだ」という視点を持っておくと、より広い将来像が描けるのではないでしょうか。