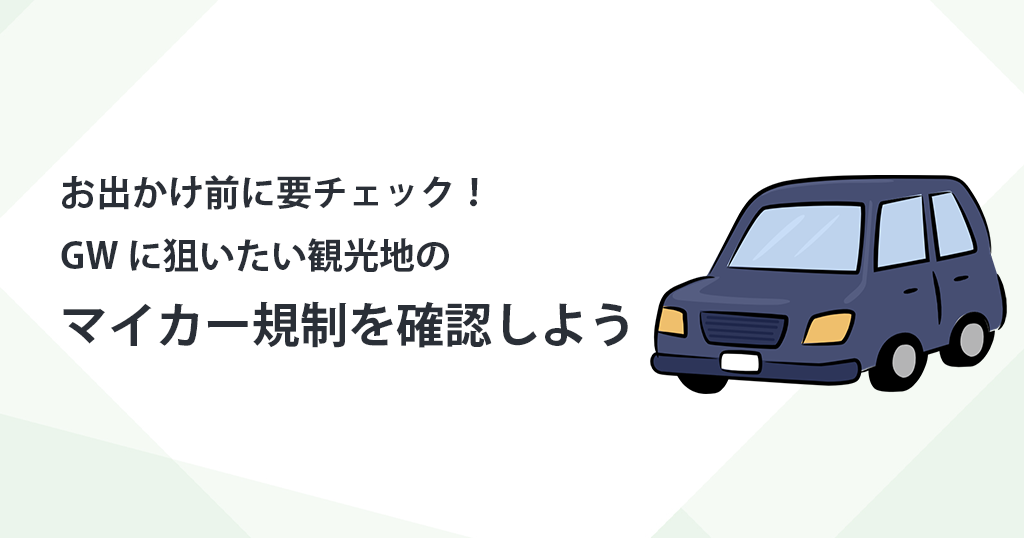今月末にはいよいよGW(ゴールデンウィーク)。普段いかない観光地に出かけることも多いかと思いますが、昨今のオーバーツーリズム(観光公害)や自然保護、渋滞緩和などの目的から、マイカー規制する観光地も増えてきました。今回はGW前に必ずチェックして楽しい休日をお過ごしください。
観光地におけるマイカー規制の背景と目的
観光地でのマイカー規制とは、一定のエリアや時間帯に自家用車の乗り入れを制限し、観光客や住民が公共交通機関やシャトルバス、タクシーなどを利用するよう促す取り組みです。なぜこのような規制が必要となっているのか、大きく以下のような理由が挙げられます。
- 交通渋滞の緩和
人気の観光地には多数の観光客が車で訪れるため、ピークシーズンや休日になると駐車場が満杯になったり、周辺道路で長時間の渋滞が発生したりします。例えば有名な桜の名所や紅葉スポットでは、道路脇への違法駐車も相次ぎ、緊急車両の通行にも支障をきたすことがあるほど深刻です。 - 自然環境・景観保護
車の排出ガスや騒音、路上駐車などは、豊かな自然を楽しむ観光地にとって大きな負担になります。山岳地帯や湖畔など、デリケートな生態系を抱えるエリアでは、排ガス・渋滞だけでなく、道幅の狭さや不適切な駐車による植生破壊などの問題が深刻化しがちです。そうした地域では「環境保全」が最優先となるため、マイカーの乗り入れを一定期間・一定区間で規制し、自然を守ろうという動きが古くから存在します。 - 安全確保と防災面
山間部の狭い道路、雪道・凍結した道路、急カーブが連続するような環境では、観光シーズンにマイカーが殺到すると立ち往生や接触事故が起きやすくなります。さらに有事(地震や豪雨など)における緊急車両が入れないという状況に陥るリスクもあるため、「人命を守る」観点からも規制が必要です。 - 観光体験の質向上
車両が多いと排気ガス・騒音が増えて街の雰囲気が損なわれたり、歩道が狭くて人と車が混在してしまったりと、観光自体の魅力が下がるという意見があります。そこで、観光客に対しては公共交通機関を利用させ、安心して散策を楽しめる空間を提供する、という施策が「観光の質」の向上にも繋がります。
銀山温泉における背景と事例
今回提示された情報の中には、山形県尾花沢市にある銀山温泉の事例がありました。ここでは、オーバーツーリズム対策として夕方から温泉街への立ち入りを予約制にし、自家用車は有料シャトルバスに乗り換えてもらう方式を一定期間試験導入しました。その結果、
- 滞在時間帯が分散され、混雑時のピークが和らいだ
- 雪道での立ち往生や違法駐車の件数が減少した
などの効果が確認されています。さらに、実施後のアンケートでは「混雑を解消することで旅行の満足度が上がる」という意見が95%にも及んだとのことです。これはマイカー規制が単に制限をかけるだけでなく、「快適に観光できる」というプラスのイメージへと繋がっている良い例といえます。
マイカー規制の歴史
日本でのマイカー規制の先駆けは、昭和50年代の上高地(長野県)といわれます。当時、自然環境保護の観点と渋滞対策から導入が開始され、その後は富士山、尾瀬、乗鞍岳など全国に広がっていきました。近年では山岳エリアのみならず、温泉地や市街地観光地でもピーク時に車両を規制し、シャトルバスや公共交通に置き換える「パーク&ライド方式」を実践する例が増えています。
こうした背景を踏まえると、マイカー規制はやや不便という側面もある一方で、観光客にも地元住民にもメリットが大きいことが分かります。しかし導入には、地元商店や宿泊施設、タクシー・バス業者などとの調整も不可欠です。次のセクションでは、具体的な事例や取り組み内容を詳しく見ていきましょう。
国内外の具体事例と導入の成果
国内事例:上高地の徹底したマイカー規制
長野県上高地は、自然景観保護のため早い時期からマイカーの通年規制を実施しています。上高地へアクセスする唯一の道路「県道上高地線」は釜トンネルより先がマイカー進入禁止となっており、手前の沢渡(さわんど)やあかんだな駐車場に車を止め、そこからシャトルバスやタクシーに乗り換える仕組みです。
- メリット
- 豊かな自然と静けさが守られ、「神域」的な雰囲気を保てる。
- 排ガスや交通渋滞、違法駐車などの問題が大幅に減少。
- 地域のブランド力が向上し、リピーターも多い。
- デメリット
- バス・タクシー費用や駐車場の負担がかかる。
- 予期せぬ天候変化などに対応しにくいという声も一部ある。
しかしながら、観光客にとっては「自然環境を守る取り組み」という理解が広がったことで、かえって「本物の自然を体感できる場所」として評判を高めているのが現状です。
富士山のマイカー規制
世界文化遺産にも登録されている富士山では、山梨県側の「富士スバルライン」と静岡県側の「富士山スカイライン」「ふじあざみライン」において、7月上旬〜8月末を中心にマイカー規制を行っています。特筆すべきは、環境配慮型の自動車(EV・FCV等)であれば規制中でも通行が可能という“優遇措置”が実施されている点です。これは「富士山の自然保護」と「脱炭素社会の推進」を同時に進める試みとして注目されています。
日光・奥日光エリア
栃木県の日光国立公園では、小田代原や千手ヶ浜へのマイカー進入を規制し、低公害バスを運行しています。周辺の繊細な山野草や湿原を守るために始められ、観光客からは「自然の音や景観をゆっくり楽しめる」と好評。さらに希少な動植物の生息環境を守りつつ、バスを利用することで渋滞を回避できるというメリットも生まれています。
国外事例にも学ぶ
海外でも、例えばカナダのバンフ国立公園やスイスのツェルマットなどでは、「中心部や自然公園への自家用車乗り入れ禁止」と公共交通・ケーブルカー・電気自動車などを組み合わせた観光地づくりを進めています。ツェルマットではガソリン車の乗り入れを基本的に禁止しており、駅前からは電動バスや電気タクシーのみが運行。町自体がEV導入のモデルケースになり、「自動車の排ガスのない快適な町」というイメージ作りに成功しています。
規制の成果
- 混雑解消による滞在時間の増加・観光消費拡大
規制により渋滞が減り、歩きやすい環境が整うと、訪問客が街や自然の中を散策しやすくなり、結果的に滞在時間が延びる傾向にあります。 - 自然環境への負荷軽減
排出ガス、騒音、植生破壊などの問題が軽減され、観光地の魅力が持続的に維持される。 - 安全性向上
狭い山道や急カーブの続くエリアでの事故や渋滞トラブルが減り、緊急車両の通行も確保される。
こうした先行事例から、観光地がマイカー規制を導入する大きな意義が見て取れます。ただし、住民生活や観光業者との調整、公共交通の確保など、導入時には十分な配慮が必要です。
導入時の課題と対策の工夫
地元住民・観光事業者との調整
観光地でマイカー規制を導入しようとすると、周辺の旅館や飲食店、土産物店などから「お客さんが来にくくなるのでは」「売上が減るのでは」と反対の声が挙がることがあります。たとえば白川郷(岐阜県)や吉野山(奈良県)などでは、地元の関係者から当初は大きな不安が示されました。しかし、次のような対策が功を奏しています。
- 代替交通手段の整備
シャトルバスを高頻度運行し、観光客がスムーズに回遊できるようにする。 - 駐車場の大規模整備
規制の起点付近に大規模な無料または格安の駐車場を整備し、そこからは公共交通で観光地へアクセス可能にする。 - 周遊バスや割引特典の導入
乗り換えた観光客に対して、地元飲食店やお土産店で使える割引クーポンを提供したり、周遊バス乗車とセットになったお得なプランを用意する。
こうした施策によって観光客が規制を前向きに受け止めるようになり、結果的に混雑が減少し、街中が歩きやすくなり、店をゆったりと見て回れるなどのメリットが生じています。
規制方法と段階的実施
マイカー規制には様々なやり方があります。一気に完全規制を実施すると混乱が生じるため、段階的な導入が効果的だといわれます。
- 特定のピーク時期・週末だけ規制
GWや紅葉シーズンなど、極端に混雑が集中する日だけ「試行規制」して住民や観光客の様子を把握する。 - 優遇措置や特例
EVやハイブリッド車など、環境負荷の低い車を規制対象外とするなど、段階的に“エコカー優遇”を導入する。 - 外部協力者の活用
警備会社やボランティアが誘導を行い、現場の混乱を防ぐ。事前予約制のシステムを使い、事前に案内メールやSMSで規制情報を通知する。
これらのステップを踏むことで、地域住民や事業者の不安を少しずつ取り除き、最終的に本格的なマイカー規制へ移行する事例が多いです。
インフラ整備・公共交通の充実
マイカー規制がうまく機能するためには、規制対象外となる「公共交通」の利便性を高める必要があります。特に地方の観光地は鉄道やバスの本数が少なく、車でなければアクセスできないといった環境の場所が少なくありません。
そこで、以下のような工夫が求められます。
- バス・タクシーの増便や低運賃化
ワンコインバスなどの導入を通して、低料金でも気軽に乗れる体制を作る。 - 周遊バス・循環バス
地域内の主要スポットを結ぶ周遊経路を頻繁に走り、乗り降り自由のフリー乗車券を発行することで移動のしやすさをアップ。 - 観光拠点での二次交通
レンタサイクル、E-Bike、電動キックボードなどを観光案内所で借りられるしくみを用意し、マイカー以外での移動をサポートする。
さらに、観光客だけでなく地元の方々にとっても便利な公共交通にする必要があるため、通勤・通学などの生活路線も合わせて整備し、「住民の生活の足」と「観光」の両方をカバーできるよう調整が欠かせません。
規制の効果測定と情報共有
マイカー規制を導入した場合、
- どのくらい交通量が減ったか
- 渋滞が解消されたか
- 排ガスの削減量はどう推移したか
などをデータとして記録・分析し、関係者や一般向けに発信することが大切です。たとえば、「マイカー規制による効果と影響」という資料から「マイカー規制によるCO₂が年間約22万トン削減できる」という試算結果も示されており、大きな環境効果が得られることをアピールすることで世論の理解が進みます。
今後の展望と結論
観光地の魅力を高める手段として
マイカー規制は「車で行きにくくなる」というマイナス要素に目を向けがちですが、逆にそれを上回るメリットが得られると評価される例が多く存在します。先述の銀山温泉や上高地のように、バスやタクシーでアクセスするからこそ得られる“特別感”や“静寂な風情”があります。宿泊して街歩きをしたり、バスの中でガイドの話を聞いて地域の歴史を知ったりと、むしろ旅の質が向上する面もあるのです。
サステナブルツーリズムの観点
近年のSDGs(持続可能な開発目標)の高まりもあり、観光地が次世代の観光客を惹きつけるには「環境負荷を下げる努力」が不可欠になりつつあります。マイカー規制はその最たる例ともいえる施策で、脱炭素型の交通システム(EVバス、燃料電池バスなど)の導入と合わせれば、一層高い評価を得られます。
地域の実情や自然環境を踏まえて、観光客が無理なく公共交通へシフトしつつ、新しい楽しみ方を提案することが持続可能な観光振興のカギとなっています。
地域社会の理解と協力
一方で、規制導入にあたっては地域住民や観光事業者、行政、交通事業者間の緊密な連携が必須です。地元商店は観光客が減るのではと心配しがちですが、規制と同時に周遊バスやパーク&バスライドをセットで導入し、乗り換え地点で特産品を紹介するなどの工夫を加えると、かえって地域経済が活性化することもあります。互いがメリットを得られる仕組み作りこそが重要です。
規制を“楽しさ”や“文化”として活かす
単純に「乗り入れ禁止」とするだけでなく、例えば「水陸両用バス」や「電動バス」「レトロ観光バス」などを運行し、その地域らしさを演出する企画が人気を呼んでいます。湯原温泉の「天丼号」(廃食用油のバイオディーゼル燃料を使った英国製タクシー)や門司港レトロ地区のトロッコ列車など、“移動そのものが観光コンテンツ”になれば、マイカーを手放してでも乗ってみたいという動機が自然に生まれます。
マイカー規制は課題解決と魅力アップの両立策
観光地におけるマイカー規制は、交通渋滞の緩和や自然環境保護、安全確保といった課題への解決策であると同時に、その土地ならではの魅力を高め、観光体験を質的に向上させる手段でもあります。地元の人々や旅行者が「規制されるから不便」というマイナス面ではなく「規制のおかげで自然や景観をしっかり楽しめる、混雑しないで安心安全に観光できる」というプラスの恩恵を実感できるよう、丁寧な合意形成と情報発信が欠かせません。
特に今回取り上げた銀山温泉では、雪道での車両トラブル低減や温泉街の混雑解消、予約制を導入することで人の流れを分散させるなど、実践的な成果が既に見られました。今後さらに、他の観光地も同様のモデルを参照しながら、地域住民と観光客双方にメリットをもたらすようなマイカー規制が広がっていくことが期待されます。
私たち観光客側も、現地への移動手段を車以外にシフトする楽しさや、環境に配慮した旅の仕方を模索することで、新たな価値に出会えるかもしれません。マイカー規制はあくまでも「制限」だけを目的とする施策ではなく、「持続可能な旅」と「地域の魅力発信」を両立させる可能性を秘めた取り組みと言えます。
マイカー規制は「不便になる」「車で来れない」という一面をどうしても感じがちですが、その代わりに得られる自然保護や混雑解消、観光の質向上のメリットは大きく、各地での取り組みを見ても十分に成功事例は蓄積されています。車以外の移動手段を楽しむことで、旅先の文化や歴史に触れられたり、地域の風景をよりゆっくり満喫できる醍醐味も生まれるでしょう。ぜひ今後も各地域での取り組みを注視しながら、持続可能で魅力的な観光地づくりに期待したいところです。
参考資料
域内交通に係る取り組み(国土交通省)
マイカー規制による効果と影響(環境省)