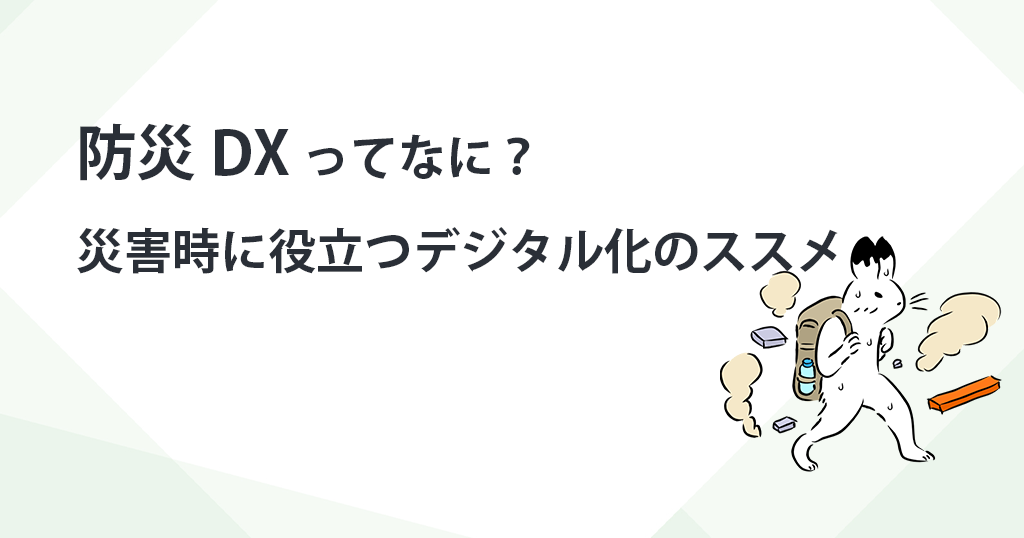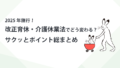”デジタル庁が取り組む「防災DX」~デジタルの力で、一人ひとりに的確な災害支援を~”という記事を読んだので、「防災DX」に関して調査してまとめてみました。

防災DXとは何か
防災DX(Disaster Prevention Digital Transformation)とは、「災害に備えたり、災害発生時に適切な対応を行ったりするために、デジタル技術を活用して社会や業務のあり方を大きく変革していくこと」を指します。DX(デジタルトランスフォーメーション)はもともと「デジタル技術を活用して、従来の仕組みや文化を刷新し、新たな価値を生み出すこと」を目的とする概念ですが、この視点を防災分野に応用したものが「防災DX」です。
具体的には、避難情報や被害状況の把握、被災者の支援制度の周知・運用など、災害対応にかかわるさまざまな場面でデジタル技術を取り入れ、業務を効率化したり、新しいサービスを生み出したりする取り組みを指します。たとえば、災害発生時の避難通知をスマートフォンアプリで一斉配信する、AI(人工知能)や人工衛星などを使って被害を予測する、マイナンバーカードを使って避難者の情報を正確に集約するといった手法が想定されます。
従来、災害対応の現場では、紙の書類に頼った受付や、自治体ごとに異なるフォーマットで被害状況をまとめるなど、情報の共有や処理に時間と手間がかかることが多く、迅速かつ効率的な対応の妨げとなっていました。また、近年は台風や豪雨などの気象災害が頻発し、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震などの大規模地震への懸念も高まっています。このような社会背景から、よりスピーディーで正確な情報伝達や避難支援が求められるようになり、防災DXが一気に注目を集めるようになりました。
さらに「防災のDX」は単なるシステム導入やクラウド化にとどまらず、「社会のあらゆる要素をデジタルによって最適化し、連携させる」ことを目指します。内閣府や総務省、デジタル庁などが取り組みを進めているほか、民間企業や大学、自治体、NPOなどとも協力しあい、新サービスやデータ連携の仕組みをつくっていく機運が高まっています。
たとえば、災害発生時に住民が自分の現在地情報や家族の安否を簡単に共有できるようにしたり、自治体同士で避難所の混雑情報を共有して広域避難をスムーズに行うなど、従来は個別に対応していた仕事を一元化する動きもあります。これによって、地域住民が「どのタイミングで、どこへ避難すればよいのか」を適切に判断しやすくなり、被害を最小限に抑えることが可能になります。
また、デジタル庁が中心となって官民一体で取り組んでいる「防災DX官民共創協議会」は、自治体・民間企業・学術機関など幅広い組織が参加し、サービスやシステムを「どう連携・標準化していくか」を検討しています。防災DXの目的は、あくまで「人の命を守る」こと。そのために技術やシステムを活用するのだ、という視点を常に持ちながら、社会全体でDXの恩恵を行き渡らせる必要があるのです。
防災DXが必要とされる背景と事例
防災DXの背景
日本では阪神淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)を経験し、地震・津波による大規模な被害の恐ろしさを痛感してきました。さらに、毎年のように発生する豪雨や台風などの気象災害も深刻化しています。また、近い将来に発生が予測される南海トラフ巨大地震や首都直下型地震では、全国的に大規模かつ同時多発的な被害が想定されており、被害を軽減するためには平時からの備えが欠かせません。
その一方で、国内では少子高齢化や人口減少が進行し、地方自治体の職員数や専門人材が限られている現状があります。大規模災害が発生した場合、自治体だけではとても対応しきれない業務が山積してしまう恐れがあるのです。こうした状況の中で、防災DXによる業務の効率化や連携強化が強く求められています。とくに、広範囲にわたる被災地では「自治体同士のデータ共有」「官民が連携する支援体制の構築」「国が保有する災害情報とのリアルタイムな連動」などが必須になるでしょう。
具体的な事例
- 災害リスク・避難情報の提供:SOCDA(ソクダ)
防災科学技術研究所と情報通信研究機構、株式会社ウェザーニューズなどが共同開発している「防災チャットボットSOCDA」は、LINE上で被災情報を投稿したり、自分に合った避難経路をAIが案内してくれる仕組みです。これにより、住民が迅速かつ的確に避難行動を取る手助けが期待できます。また、自治体側は住民から寄せられるリアルタイムの被害報告を把握でき、救助や物資配給の判断を素早く行うことができます。 - 被害状況の把握、通信の冗長化:Q-ANPI
人工衛星を活用する安否確認サービス「Q-ANPI」は、地上の通信インフラが破壊されても、衛星経由で安否情報をやり取りできる点が魅力です。避難者自身が携帯電話の番号をキーにして衛星に登録すれば、離れた家族や防災機関が安否や避難所の情報を取得することが可能になります。地上のネットワークが寸断されるリスクを補う「冗長化」は防災DXにおいて重要なテーマの一つです。 - 被災者支援制度のデジタル化
被災者向けの支援制度は多岐にわたりますが、紙ベースの申請や周知の不備により、せっかくの制度が活用されないケースもあります。そこで、アプリやオンライン手続きを導入し、被災者がスマホやタブレットから簡単に申請を行える仕組みを整備する動きがあります。申請の進捗や給付状況をオンラインで確認できることで、被災者の不安を軽減し、行政の処理スピードも上がります。 - 共助による避難所施設の確保:徳島県「シームレス民泊」
徳島県では、平常時は宿泊施設として営業している場所を、災害時には避難所として切り替える「シームレス民泊」という取り組みを進めています。デジタル技術を用いて避難所の混雑状況を把握し、優先的に保護が必要な高齢者や病気の方を安全な施設へスムーズに誘導できる体制を整備しています。これも、民間の宿泊事業者と自治体がデータを連携・共有することで実現する「防災DX」の好例といえます。 - 避難所運営支援システム(株式会社フォルテなどの取り組み)
避難所の受付業務をタブレットやQRコードを利用して効率化し、避難者の体調管理や物資配給管理をデジタルで一元化するシステムが開発・導入されています。たとえば株式会社フォルテが提案する「避難所運営支援システム」では、検温と同時にQRコード付きの整理券を発券し、避難者自身が必要情報を入力。これにより自治体職員は受付業務の負担を大幅に軽減でき、感染対策や避難者の健康管理もスムーズになります。
いずれの事例も、「災害による被害を減らし、一人ひとりが適切な支援を受けられるようにする」ことを共通の目的としています。デジタル化はゴールではなく、あくまでも手段です。しかし、必要な情報を誰でも簡単に共有できる仕組みづくりは、人命に直結する大きな意義があるといえるでしょう。
自治体による防災DXの取り組みと課題
自治体の取り組み事例
- 東京都のAI・ICT活用
東京都では、帰宅困難者オペレーションシステムの構築やドローンによる物資輸送・被害調査など、最先端技術を積極的に取り入れています。人口が集中する都市部では、災害時の混乱が大きくなるため、リアルタイムで正確な情報を収集し、市民へ伝達する手段が重要です。IoTを活用して水道管の漏水検知を行うなど、インフラ監視の効率化も進めています。 - 名古屋市の要支援者向け防災ヘルプサービス
名古屋市では、高齢者や障がい者といった要支援者がスムーズに避難できる体制づくりを目指し、防災アプリを取り入れた実証実験を実施しました。個別に策定した避難計画をアプリに登録し、発災時には支援者・自治体とリアルタイムで連携しながら避難訓練を行うという試みです。結果として、防災意識の向上や実運用に向けた課題整理が進みました。 - 長野県小谷村の一斉安否確認サービス
山間地域に集落が点在している長野県小谷村では、フィーチャーフォンや固定電話からも使える安否確認サービスを導入しました。着信時に自動音声ガイダンスが流れ、番号を押して回答するといったシンプルな仕組みです。高齢者が多い地域でも扱いやすく、平時にはクイズ形式で練習できるため、操作に慣れることができます。まさに「地域の実情に合わせた防災DX」の好例といえます。
防災DXを推進する上での課題
- システム連携・標準化の遅れ
自治体によって導入するシステムやツールがバラバラであり、連携が進んでいません。同じ被害情報でも市町村ごとにフォーマットが異なると、国や他自治体との情報共有がスムーズにできない原因になります。そこで、デジタル庁が進める「防災DXサービスマップ・サービスカタログ」や自治体向けのモデル仕様書整備などが注目されていますが、まだ実質的に標準化が十分進んでいないのが現状です。 - 人材不足とコスト問題
DXを推進するには、ITやデータ活用に詳しい人材が不可欠です。しかし自治体には、専門知識を持つ職員が限られており、外部の企業やNPOと連携しないと大規模システムを運用できない場合が多々あります。また、新しいシステム導入には初期費用や保守費用がかかり、自治体の予算を圧迫する問題もあります。国の補助金や広域連携など、財源や体制を工夫する必要があります。 - 停電・通信障害への備え
災害時には通信インフラが壊滅的に途絶える可能性があります。どれだけ高性能の防災アプリやオンラインシステムがあっても、通信できなければ意味がありません。そのため、人工衛星や多重化した通信網を確保する「冗長化」を進めたり、オフラインでも動作できるシステム設計が求められています。小型発電機や大容量バッテリーを備蓄するなど、物理的な対策と組み合わせることも重要です。 - 個人情報保護とプライバシー
避難者がオンラインで登録する情報には個人データが含まれるため、データの安全管理や不正アクセス対策が必須となります。とくに大規模災害時は混乱の中でセキュリティ対策が不十分になりがちです。防災DXの導入にあたっては、個人情報を取り扱うルールや責任分担を明確化し、「被災者保護」という目的のもと適切な運用を徹底することが求められます。
このように、自治体や地域の現場にはさまざまな事情や障壁があり、防災DXを一気に進めるにはまだ多くの課題が残っています。しかし、災害対応の現場で実際に導入・運用され、徐々に改善されていくシステムも増えています。今後は官民の垣根を越えた協力や、大規模災害の教訓を活かすことで、より使いやすく安全な防災DXが実現していくでしょう。
今後の展望
- 「防災DX官民共創協議会」のさらなる役割拡大
デジタル庁の呼びかけで誕生した「防災DX官民共創協議会」には、すでに多くの自治体や民間事業者、NPO、学術機関が参加しています。災害が起きた際、協議会の有志が被災地に入ってシステム構築やデータ連携を行ったり、「Suica」などのカードを活用して被災者情報を一元管理する事例も報告されています。今後は、こうした官民連携を制度面で支援する仕組みづくりが進められ、災害時に即応できる「防災版DMAT(医療チームをモデルにした情報支援チーム)」のような体制が整う可能性があります。
- 「防災DXサービスマップ」の継続的拡充
自治体が必要な防災システムやアプリをスムーズに検索・調達できるよう、デジタル庁が「防災DXサービスマップ」を公開しています。ここには200件以上のサービスが登録され、今後も増えていく見込みです。さらに、調達時の仕様を統一する「モデル仕様書」の整備が進み、導入手続きが簡略化されれば、自治体間の格差が縮まることが期待されます。 - 災害対応の高度化とデータ連携基盤の構築
平時からマイナンバーカードや自治体の住民情報を連携させ、災害時に即座に被災者の属性やニーズを把握できる仕組みづくりが進められています。たとえば「新総合防災情報システム」と、デジタル庁が検討している「データ連携基盤」を連動させれば、一人ひとりに必要な支援をスピーディーに提供できるようになるでしょう。また、備蓄品やボランティアのマッチングなどにも、データ連携は大きく寄与すると考えられます。 - 地域課題の解決と持続可能なビジネスモデル
防災DXには予算がかかりますが、単に一度きりのシステム導入に終わるのではなく、持続的に運用されるビジネスモデルの構築が必要です。たとえば、普段は住民サービスを行うチャットボットや観光アプリが、災害時に防災機能へ切り替わるといった「デュアルユース」の考え方が普及すれば、導入コストを抑えながら地域課題の解決に活かせます。
まとめ
防災DXは、技術やシステム導入だけでなく、社会全体や組織・業務フローを変革していく大きな試みです。避難情報の発信・共有、被災者の安否確認、支援制度の周知・活用、避難所や物資の運営管理など、防災にかかわるあらゆる業務を「デジタルによる連携」でつなぎ合わせることで、多くの人命を救い、被害の拡大を防ぐことができます。
他方、デジタル機器が動かなくなったときのリスクや、自治体・地域によって進捗状況に格差があるといった課題も無視できません。たとえば、令和6年能登半島地震の際は、デジタル庁や民間事業者などが現地に入り、避難所情報を一元化する支援を行いましたが、まったく同じアプローチがほかの地域で通用するとは限らないという面もあります。そのためには、各地域の実情に合わせながら「どのように連携すれば効果的か」を多様なプレーヤー同士で検討し、役割分担を決めておくことが大切です。
最終的に、防災DXがめざすのは「災害が起こっても、誰もが安心して助け合える社会の実現」といえるでしょう。個人や家庭での防災意識の向上が不可欠であることは変わりませんが、デジタル技術の力を使って早めに情報を共有し、必要な人へ支援を集中させる仕組みを平時から整えておくことが、未来の災害被害軽減に大きく役立つのです。官民の協働によって生まれるイノベーションをうまく活かしつつ、一歩ずつでも着実に前進することが求められています。