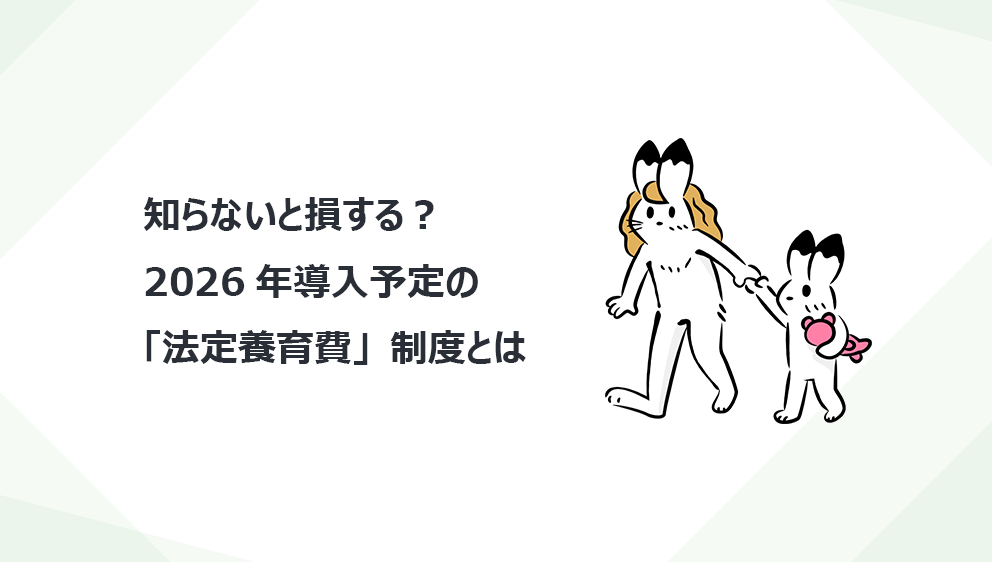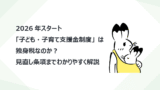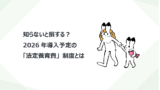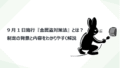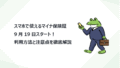離婚時に養育費の取り決めがなかった場合、それまで請求できなかった「養育費」が、2026年5月までに法改正され導入予定の「法定養育費」という制度により、一定額を請求できるようになります。これは子どもの最低限の生活を守るための新たなセーフティーネットとして注目されていますが、金額・期間・個別対応などにおいて課題や注意点も存在します。
背景と制度導入の目的
日本では離婚に伴い「養育費」を取り決めるケースが少なくありません。しかし現実には、取り決め自体が行われていなかったり、合意しても支払いが滞ったりするケースが後を絶ちません。厚生労働省の調査によると、母子家庭の約半数、父子家庭の7割近くが養育費に関する取り決めをしていない状況が報告されています。取り決めがなければ当然、子どもを育てるための経済的支援は受けられず、生活の質や教育機会に大きな影響が及びます。
こうした課題に対応するために新たに導入されるのが「法定養育費」制度です。これは、離婚時に養育費について合意がなかった場合でも、法律に基づいて一定額を請求できる仕組みです。従来のように「合意がなければゼロ」という状態を防ぎ、最低限の生活費を確保することを目的としています。
この制度は2024年5月に改正民法の一部として成立し、公布されました。施行は2年以内、つまり2026年5月までに予定されています。導入されれば、離婚後に生活が困窮しやすいひとり親家庭にとって、大きなセーフティーネットとなることが期待されています。
しかし一方で、この制度は「最低限の保障」にとどまる点や、教育費や医療費など実際の子育て費用を十分にカバーできない可能性が指摘されています。そのため「法定養育費だけで安心」と考えるのは危険であり、従来の協議や裁判での取り決めと併せて理解する必要があります。
「法定養育費」とは?
「法定養育費」とは、離婚の際に養育費の取り決めがなかった場合でも、法律に基づいて子どもの生活費を最低限保障するために支払いを請求できる新しい制度です。従来の制度では、養育費を受け取るためには、当事者同士の協議や調停・審判によって取り決めを行う必要がありました。そのため、合意が得られなかったり、相手が話し合いに応じなかったりすると、養育費を一切受け取れないケースが多く存在しました。
法定養育費制度は、この「取り決めがなければゼロ」という従来の仕組みを是正し、子どもが親の離婚によって経済的に過度な不利益を受けないようにすることを目的としています。
制度の仕組み
- 請求権の発生
離婚時に養育費の取り決めがなされていない場合、自動的に「法定養育費」を請求できる権利が発生します。請求できるのは子どもを実際に養育している親(監護親)です。 - 請求できる期間
請求は離婚した日までさかのぼって可能です。ただし、支払い義務は原則として子どもが18歳になるまでとされています。大学進学や専門学校など、その後の教育費までは対象外となるため注意が必要です。 - 金額の水準
支払う金額は、法務省令によって「子どもの最低限の生活を維持するために必要な標準的な費用」を基準に定められる予定です。現時点で具体的な額は確定していませんが、報道では 月額2万円程度 を目安とする方向が検討されていると伝えられています。
「最低限の保障」である点に注意
重要なのは、この法定養育費があくまで「最低限の生活保障」にとどまる点です。教育費、医療費、進学費用など、子どもにかかる実際の費用はそれ以上に大きくなることが一般的です。そのため、法定養育費があれば十分というわけではなく、できる限り当事者同士で協議し、調停や審判を通じて個別事情に応じた適正額を取り決めることが推奨されています。
この制度は「ゼロになってしまうリスクを防ぐ最低限の仕組み」と理解しておくことが重要です。
制度の成立スケジュールと施行予定
「法定養育費」制度は、2024年5月に成立した改正民法の一部として盛り込まれました。同年5月24日に公布され、公布から2年以内に施行されることが定められています。そのため、実際に制度がスタートするのは 2026年5月まで のいずれかの時期となる見込みです。具体的な施行日や詳細な制度設計は、今後の政令や法務省令で定められます。
制度導入までの流れ
- 2024年5月:改正民法成立・公布
国会で改正案が可決され、法定養育費制度が新設されました。 - 2025年〜2026年初頭:政令・省令の策定
実際の金額の基準や支払いの算定方式、請求手続きの詳細が法務省によって検討・公表される予定です。ここで「月額2万円程度」という試算が現実の制度として確定するかどうかが明らかになります。 - 2026年5月まで:施行開始
具体的な施行日は政令で定められます。施行日以降に成立した離婚については、自動的に法定養育費が適用されることになります。
遡及適用の範囲
注意すべき点として、この制度は 施行前に成立した離婚には適用されない ということです。つまり、制度が始まる前に離婚してしまった場合は、法定養育費を請求することはできません。あくまで施行日以降に新たに離婚したケースに限定されるため、導入後のタイミングを把握しておく必要があります。
今後の注目点
- 金額の確定:法務省が定める具体的な算定基準が社会的に大きな関心を集めています。最低額があまりに低いと、実効性に疑問が残る可能性があります。
- 周知の徹底:制度が始まっても、利用できることを知らなければ意味がありません。特に情報にアクセスしづらいひとり親家庭への周知が課題となります。
- 実務への影響:家庭裁判所での養育費調停の件数や、自治体によるひとり親支援との連動など、実際の運用にどう影響するかも注目されます。
支払いの対象・請求条件・期間
「法定養育費」は、単に“誰でも請求できる制度”ではありません。支払い義務者や請求できる人、対象となる子ども、そして請求できる期間が明確に定められています。ここでは、実際に制度を利用する際に重要となる条件を整理します。
支払い義務者
養育費を支払う義務を負うのは、離婚したもう一方の親です。たとえ親権を持たなくても、法律上の親子関係がある限り、生活費の一部を負担する責任があります。これは従来の養育費と同じ考え方で、子どもを育てる責任を両親が等しく負うという民法の原則に基づいています。
請求できる人
法定養育費を請求できるのは、子どもを実際に養育している親(監護親)です。親権者かどうかにかかわらず、子どもの日常生活を担っている人が対象となります。したがって、離婚後に父親が子どもを育てている場合は父親が請求者となり、母親に支払い義務が生じます。
対象となる子ども
請求の対象は、18歳未満の子どもです。改正民法では成年年齢が18歳に引き下げられているため、養育費の支払いも18歳到達時までが基本となります。
ただし、大学進学や専門学校に進むケースなど、現実的には18歳を超えても経済的に自立が難しい場面が多いのも事実です。そのため法定養育費はあくまで“最低限の保障”にとどまり、それ以上を求める場合は従来通り協議や裁判を通じて取り決める必要があります。
請求できる期間
- 開始時期:離婚成立の日にさかのぼって請求が可能です。つまり、離婚してから数か月後に請求しても、離婚時点に遡って養育費を受け取れる仕組みとなります。
- 終了時期:子どもが18歳に達するまで、または当事者間で新たに養育費を取り決めた時点で終了します。家庭裁判所の審判や調停で金額が確定すれば、そちらが優先されます。
注意点
- 法定養育費があるからといって、従来の養育費取り決めを省略してよいわけではありません。金額はあくまで最低限であり、教育や医療などの個別事情を反映できないためです。
- 制度が始まる前に離婚した場合には請求できません。施行日以降に成立した離婚に限られる点は押さえておく必要があります。
金額の算定とその限界
「法定養育費」の大きな関心事は、いくら支払われるのか という点です。制度の趣旨は「最低限の生活費を確保すること」であるため、金額は子どもの実際の養育費用全体をまかなう水準ではなく、あくまで下支えにとどまります。
金額の算定方法
法定養育費の金額は、法律の条文上「子の最低限度の生活を維持するために必要な標準的費用」とされています。具体的な額や計算方式は、今後 法務省令 によって定められる予定です。
現段階では確定していませんが、報道などでは 月額2万円程度 を基準とする方向性が検討されていると伝えられています。これは、食費や衣類、最低限の生活用品などに充てられる水準と考えられます。
金額の水準と現実とのギャップ
実際の子育てに必要な費用は、教育費や医療費、進学に伴う学費などを含めれば、はるかに大きな金額となります。文部科学省の統計によれば、子ども1人を高校卒業まで育てるには総額で 1,000万円以上 が必要とされており、月額2万円程度では到底足りません。
したがって、法定養育費はあくまで「最低限のセーフティーネット」と位置付けられており、十分な生活保障を提供するものではありません。実際の費用に応じた取り決めは、引き続き 協議・調停・審判 を通じて行う必要があります。
金額に関する課題
- 子どもの年齢や成長段階を考慮できない
実際には小学校・中学校・高校と進むにつれて費用は増加しますが、法定養育費は一律額となる見込みです。 - 地域差への対応不足
都市部と地方では生活費や教育費に大きな差がありますが、法定養育費ではその違いを反映できません。 - 「最低限額=十分」との誤解
制度が始まることで「法定養育費さえあればよい」と考えてしまうと、適正な養育費の確保が難しくなる恐れがあります。
実際の対応のポイント
- 法定養育費は「取り決めがなかった場合の最低ライン」と理解する
- 可能であれば、従来通り家庭裁判所の算定表をもとに協議し、実情に即した金額を取り決める
- 弁護士や専門家の助言を受けることで、子どもの将来を見据えたより現実的な養育費を確保できる
強制執行を容易にする「一般先取特権」
養育費の大きな課題のひとつに、「取り決めても支払われない」という問題があります。実際、養育費を取り決めていても、支払いが継続して行われている割合は約3割にとどまるという調査結果もあります。そこで「法定養育費」制度では、支払いを確実にするための仕組みとして 「一般先取特権」 が付与されることになりました。
一般先取特権とは?
一般先取特権とは、債権(お金を受け取る権利)の中でも 法律上、優先的に回収できる権利 のことです。
例えば、給与や預金口座などを差し押さえる場合、他の債権者よりも養育費の請求権が優先されるため、実際に回収できる可能性が高くなります。
これまでは養育費を回収するためには、家庭裁判所で調停や審判を経て「債務名義」(強制執行できる判決や公正証書)を取る必要がありました。しかし法定養育費については、こうした手続きを経ずに強制執行に移れる仕組みが整備されます。
期待される効果
- 未払いリスクの軽減
養育費の支払い拒否があった場合でも、スムーズに差し押さえが可能になります。 - 支払いの抑止効果
支払わないと即座に強制執行される仕組みが整うことで、支払い義務者に対して一定のプレッシャーが働きます。
制度上の限界
ただし、強制執行の制度が整ったからといって、必ず養育費が支払われるわけではありません。支払い義務者に そもそも資産や収入がない場合 は、差し押さえをしても回収できない可能性があります。また、フリーランスや個人事業主の場合、給与の差し押さえが難しいケースも想定されます。
利用者へのアドバイス
- 養育費が支払われない場合、早めに差し押さえなどの法的手続きを検討することが重要です。
- 弁護士や司法書士など専門家を通じて申立てを行えば、より確実に手続きを進められます。
- 法定養育費は「未払いを防ぐ仕組み」が整った点で従来よりも大きな前進といえますが、最終的には支払う側の収入状況が大きく影響することを理解しておく必要があります。
制度のメリットと課題・注意点
「法定養育費」制度は、子どもの生活を守るための新しい仕組みとして大きな意義を持ちます。しかし一方で、制度の性質や限界を正しく理解しておかないと「思ったほど役に立たない」と感じる可能性もあります。ここではメリットと課題・注意点を整理してみましょう。
制度のメリット
- 取り決めがなくても請求できる安心感
これまで離婚時に養育費を取り決めなかった場合はゼロになってしまいましたが、制度導入後は最低限の養育費を自動的に請求できるようになります。 - 強制執行の仕組みによる実効性向上
一般先取特権が付与されるため、未払いがあっても給与や預金の差し押さえがしやすくなり、実際に支払われる可能性が高まります。 - ひとり親家庭のセーフティーネット強化
経済的に不安定になりやすい離婚直後の生活を下支えし、子どもが極端な困窮状態に陥るのを防ぐ効果が期待されます。
制度の課題
- 金額の低さ
月2万円程度と見込まれる金額は、教育費や医療費を含む実際の養育費用には遠く及びません。これでは「最低限の保障」にしかならないのが現実です。 - 個別事情を反映できない
子どもの年齢や教育方針、地域の物価水準といった個別要素を考慮できず、一律の額しか請求できないため、不公平感が残る可能性があります。 - 誤解されやすい制度設計
「法定養育費があるから協議しなくてもよい」と考えてしまうと、子どもに必要な本来の金額を確保できなくなります。制度はあくまで補助的な役割にとどまります。 - 支払い能力の限界
強制執行が可能になっても、支払う親に十分な収入や資産がなければ現実的に回収は困難です。この点は法律の仕組みだけでは解決できません。
利用にあたっての注意点
- 法定養育費は「最低限の救済措置」であることを理解し、可能であれば調停や協議で適正額を決める努力を続けることが大切です。
- 制度開始後は広く周知されると見込まれますが、離婚前から制度の内容を理解しておくと、生活設計に役立ちます。
- 実際に利用する際には、専門家(弁護士、家庭裁判所の調停委員など)に相談し、自身のケースに合った対応を検討することが望ましいでしょう。
実際の対応:協議・裁判との併用の重要性
「法定養育費」は、離婚時に養育費を取り決めなかった場合でも最低限の額を確保できる仕組みです。しかし、繰り返し強調されている通り、この制度はあくまで「セーフティーネット」にすぎません。子どもの成長や進学、医療など、個別事情に応じた十分な金額を確保するためには、従来の協議や裁判手続きを並行して行うことが極めて重要です。
協議の重要性
離婚に際してまず取り組むべきは、当事者同士で養育費の金額や支払い方法を話し合い、合意書として残すことです。合意内容を公正証書にしておけば、支払いが滞った際に強制執行が可能となり、より実効性が高まります。法定養育費に頼るよりも、実際の生活費や教育費を反映した金額を設定できるため、子どもの将来を見据えた対応が可能です。
8-2. 家庭裁判所の活用
協議が難しい場合や合意に至らない場合は、家庭裁判所に「調停」や「審判」を申し立てることができます。家庭裁判所では、収入や子どもの人数などを基にした「養育費算定表」に沿って適正な金額が決定されます。これにより、法定養育費の一律額よりも現実に即した水準を確保できる可能性が高まります。
専門家への相談
- 弁護士:養育費請求の代理、合意書作成、裁判対応などトータルでサポート
- 司法書士:公正証書の作成支援や簡易裁判所での代理
- 行政書士・相談窓口:自治体のひとり親支援窓口での相談や情報提供
こうした専門家を活用することで、法定養育費に頼るだけでなく、実情に合わせたより確実な養育費の確保につながります。
法定養育費との併用のイメージ
- 離婚時に養育費を取り決めなかった場合 → 法定養育費を自動的に請求できる
- その後、生活費や教育費が不足する場合 → 調停や審判を利用して増額を求める
- 公正証書や裁判所の審判を得れば、強制執行もスムーズに可能
つまり法定養育費は「スタートライン」にすぎず、子どもの成長に応じた十分な支援を得るには従来の手続きを並行して行うことが不可欠です。
今後の見通しと展望
法定養育費制度は、2026年5月までに施行される予定ですが、現時点ではまだ制度の詳細が固まっていません。金額や手続きの具体像は法務省令や政令で定められるため、今後の動向を注視する必要があります。
金額基準の確定
最大の注目点は、具体的な支給額です。報道では「月2万円程度」という目安が示されていますが、これがそのまま制度に盛り込まれるかどうかは未定です。もし低額にとどまれば「制度はあるが実効性に乏しい」と批判される可能性があります。逆に、より実情に近い額に設定されれば、ひとり親家庭の安心感は大きく高まるでしょう。
制度の周知と利用促進
制度が導入されても、利用できることを知らなければ意味がありません。特に情報へのアクセスが限られるひとり親世帯に、どう周知し、手続きをわかりやすく案内するかが課題となります。自治体や家庭裁判所、弁護士会などが連携して広報・相談体制を整備することが不可欠です。
実務への影響
- 家庭裁判所の調停や審判が減少するのか、それとも「最低限の法定養育費では足りない」として申立てが増えるのか、制度運用の実態を見極める必要があります。
- 自治体が行う児童扶養手当や生活保護との関係も調整課題となります。法定養育費があることで、他の支援制度との「二重給付」や「控除扱い」がどうなるのか、利用者にとって重要な論点です。
長期的な課題と展望
- 教育費への対応:高校卒業後の大学進学や専門学校への進学費用をどう保障するかは今後の大きな課題です。
- 柔軟な制度設計:地域差や子どもの年齢による費用の違いをどこまで制度に反映できるかが問われます。
- 国民的な理解の深化:養育費の支払いは「離婚した夫婦間の問題」ではなく「社会全体で子どもを守る仕組み」の一環であるという認識が広がることが期待されます。
まとめ
「法定養育費」制度は、離婚時に養育費を取り決めなかった場合でも最低限の生活費を確保できるという点で、大きな前進です。しかし金額はあくまで「最低ライン」にすぎず、子どもの成長に必要な費用をすべて賄えるわけではありません。
したがって、法定養育費を「安心の保証」と考えるのではなく、「最後の安全網」と理解し、可能な限り協議や裁判を通じて実情に合った養育費を取り決めることが重要です。今後、制度の具体的内容が固まり、社会全体で周知・活用が進むことで、子どもの生活を守る仕組みがより強固になることが期待されます。