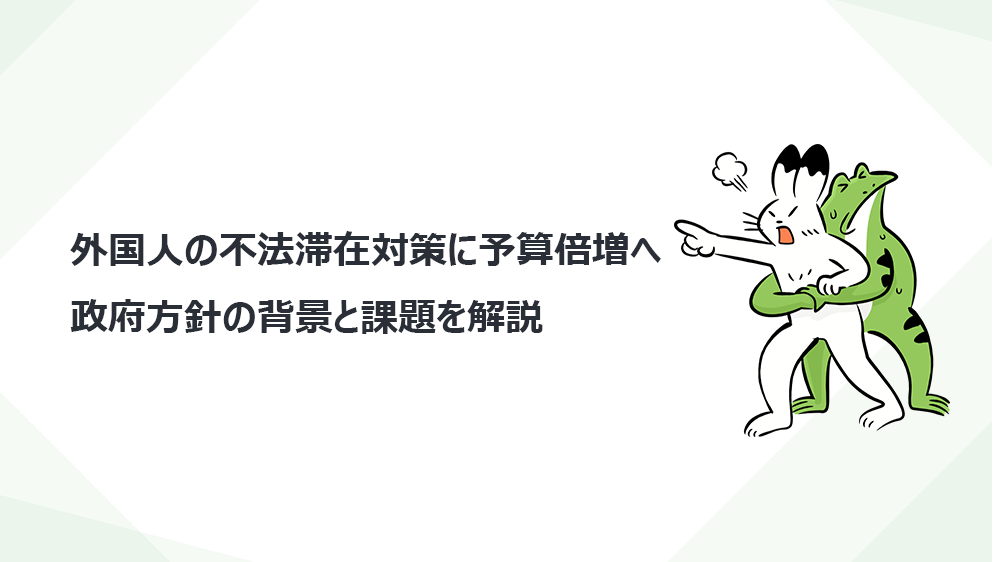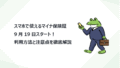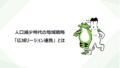政府は2026年度予算において、外国人の不法滞在や不法就労対策を強化するため、関連予算を倍増させる方針を固めました。出入国在留管理庁による摘発や監視体制の強化、地方自治体との連携支援が中心となる見通しです。本記事では、なぜ今「予算倍増」が必要とされるのか、その背景、具体的な対策、そして今後の課題をわかりやすく解説します。
政府が予算を倍増する背景
政府が外国人の不法滞在対策に関する予算を倍増させる方針を示した背景には、近年の社会状況の変化があります。特に注目されるのは、不法滞在や不法就労に関する数値の増加と、それが社会に及ぼす影響です。
まず、不法滞在者の数はコロナ禍以降、徐々に増加傾向にあります。国際的な人の移動が再び活発になる中、日本でも観光や留学を目的に入国した人が在留期限を超えて滞在するケースが目立っています。また、技能実習制度や留学生制度を利用して来日した外国人の一部が、在留資格を失っても日本に留まり、非正規で働き続ける事例も少なくありません。こうした事態は、表向きの統計には現れにくいものの、現場の労働市場や地域社会に影響を及ぼしています。
次に、不法就労が増えることで、労働市場に不公平が生じるという問題があります。正規のビザを持つ外国人や日本人労働者と比べて、不法就労者は低賃金・劣悪な環境で働かされることが多く、結果的に「安い労働力」として利用されやすい構造を生み出しています。これにより、国内の適正な雇用環境が損なわれ、法令を守っている企業との間で不均衡が生じかねません。
さらに、治安面への懸念も指摘されています。不法滞在や不法就労に関わるブローカーの存在や、外国人同士のトラブルが増えることで、地域社会の安心感が揺らぐ可能性があります。実際に、警察や自治体からは「取り締まりや情報共有の強化が不可欠だ」という声があがっています。
こうした状況を踏まえ、政府は出入国在留管理庁を中心に、監視や摘発体制を強化するための予算を大幅に拡充する必要があると判断しました。背景には単なる治安対策だけでなく、労働市場の公正性を守り、国民の安心を確保する狙いがあります。
具体的な対策内容
政府が予算を倍増して進めようとしているのは、単なる取り締まりの強化だけではありません。現場の執行力を高める施策から、ITを活用した管理体制の整備まで、多角的なアプローチが予定されています。主な内容を整理すると以下のようになります。
出入国在留管理庁の体制強化
最も大きな柱は、出入国在留管理庁(入管庁)の監視・摘発体制の拡充です。人員を増やすことで、不法滞在者の発見や不法就労ブローカーの摘発を迅速に行えるようにします。また、地方の入管施設や空港でのチェック体制を強化し、入国時点から不正を未然に防ぐ仕組みを整備する方針です。
不法就労への取り締まり強化
不法滞在者が働き口を得てしまう背景には、不正に雇用するブローカーや企業の存在があります。政府はこうした仲介業者の摘発や、雇用する側への罰則強化を検討しています。併せて、企業への監査体制を充実させることで「不法就労させる側」にも強い抑止効果を与えることが狙いです。
自治体や警察との連携
不法滞在の実態は地域ごとに異なります。そのため、政府は自治体や警察と協力し、地域レベルでの情報共有や取り締まりを強化する計画です。たとえば、住民登録や生活保護申請の場面で不法滞在の兆候があれば、速やかに入管庁と連携できるようにする仕組みが整備されます。
IT技術の活用
従来の紙ベースや人力でのチェックでは限界があるため、最新のITシステム導入も予算の使途に含まれています。顔認証やデータベース照合を利用して、在留カードの偽造や期限切れの見落としを防ぐほか、出入国履歴のデジタル管理によって迅速な確認を可能にします。
相談・支援体制の整備
一方で、不法滞在に至る外国人の多くは、制度や生活困窮の事情を抱えています。そのため、政府は一部の予算を、在留資格の更新相談や生活支援の窓口強化に充てる方向です。取り締まりと同時に支援を行うことで、外国人の権利侵害を防ぎながら対策を進める姿勢が示されています。
予算の規模と使い道
今回の対策で注目されるのは、政府が「予算倍増」という強いメッセージを打ち出した点です。前年度の関連予算と比較すると、その規模感や重点配分が見えてきます。
倍増の規模感
これまで外国人の不法滞在・不法就労対策に充てられていた予算は、主に出入国在留管理庁の運営費や監視システム導入費などに限定されていました。今回の予算案では、そのおよそ2倍にあたる数百億円規模へと拡大する方向が示されています。金額自体は国家予算全体から見れば小さいですが、特定分野での「倍増」は異例であり、政府の危機感の表れといえます。
主な使い道
増額された予算は以下のような分野に充てられる予定です。
- 人員増強
入管庁の職員を増やし、空港や主要都市におけるチェック体制を強化。監視や摘発に必要な人材育成のための研修費用も含まれます。 - 監視システムの導入
顔認証ゲートや在留カードのICチップ照合システムなど、最新技術を活用した監視・確認システムを全国に展開。偽造防止や不正利用の抑止を図ります。 - 自治体との連携支援
自治体が不法滞在の情報を把握した際、円滑に入管庁と共有できるようシステムを整備。そのための情報管理費や研修費用が計上されます。 - 企業監査の強化
不法就労を助長する企業への立ち入り調査や監査を行うための予算も拡充。監査官の増員や、調査に必要なデータベース整備も含まれます。 - 相談・支援体制
在留資格の更新を巡るトラブルや生活困窮に直面する外国人への相談窓口を強化。取り締まり一辺倒ではなく「予防的」な支援も想定されています。
予算配分の特徴
今回の予算の特徴は、摘発や監視だけでなく、「不法滞在を未然に防ぐ」施策や「外国人の生活を支える」支援策にも資金が振り向けられている点です。これは、単純に取り締まりを強化しても根本的な解決にはならないという認識が政府内で強まっていることを示しています。
期待される効果とメリット
予算を倍増して対策を強化することにより、政府はさまざまな効果を期待しています。治安や労働市場、国民生活への安心感など、多方面でのメリットが想定されます。
不法滞在者数の抑制
第一に期待されるのは、不法滞在者数の抑制です。これまで入管庁の人員不足やシステムの不十分さから、十分な摘発・対応が行えなかった地域もありました。人員増強や最新の監視システム導入により、滞在期限切れや偽造在留カードの使用といった不正を早期に発見できるようになると見込まれます。結果として、不法滞在の「温床」を減らす効果が期待されます。
不法就労の減少と労働市場の健全化
次に、不法就労の減少による労働市場の改善です。不法就労は低賃金労働を助長し、正規に働く労働者の賃金水準や雇用機会を圧迫する要因となります。企業監査の強化やブローカー摘発が進めば、不正に雇用される外国人が減少し、国内の労働環境がより公平で健全なものになると期待されます。
治安と地域社会の安心感
不法滞在や不法就労に関連して発生する犯罪やトラブルも少なくありません。摘発の強化と地域との連携が進めば、こうした事件の発生を未然に防ぎ、地域社会の治安維持につながります。住民の安心感を高めることは、外国人との共生を円滑に進めるうえでも不可欠です。
外国人への適正な支援
今回の予算では、支援策にも資金が充てられることが大きな特徴です。相談窓口の強化や生活支援の充実は、不法滞在に至る前に問題を解決できる可能性を広げます。外国人にとって「正規に滞在し続けるための選択肢」が増えることは、人権の保護にもつながります。
国際的信頼の確保
入国管理体制の強化は、日本が国際社会で信頼を得るためにも重要です。観光客や留学生を多く受け入れる一方で、不法滞在や不正労働に甘い姿勢を取れば、日本全体の評価が下がりかねません。厳格かつ適正な制度運用は、国際的な信用を高め、健全な外国人受け入れ政策の基盤を築くことになります。
課題と懸念点
予算を倍増することで不法滞在や不法就労対策が前進することは期待されますが、一方でいくつかの課題や懸念点も指摘されています。単純に「取り締まり強化=解決」にはならない点を整理してみましょう。
人権侵害リスク
不法滞在者への監視や摘発を強化すれば、過度な取り締まりによって外国人の人権が侵害される可能性があります。たとえば、正規に在留している外国人までもが「疑わしい」と見なされ、過剰にチェックされることがあれば、生活や就労に支障をきたします。人権保護と治安維持のバランスをどのように取るかが重要な課題です。
労働力不足への影響
日本はすでに深刻な人手不足に直面しています。特に建設、介護、農業、飲食といった業種では外国人労働者に大きく依存しているのが現状です。不法就労の排除が進むと、短期的には現場でさらに人手不足が悪化する可能性があります。企業にとっては法令遵守と人材確保を両立させる難しさが増すでしょう。
実効性への疑問
予算を増やしても、現場で十分に機能しなければ意味がありません。入管庁や自治体、警察の間で情報共有が遅れれば、対策は形骸化する恐れがあります。また、偽造在留カードや不法就労ブローカーの手口は巧妙化しており、新たな対策が追いつかない可能性も否定できません。
外国人との共生への影響
取り締まりが強まることで、外国人全体に「日本は厳しい国」という印象が広がる懸念もあります。観光や留学で訪れる人々にまで不安感を与えれば、日本の国際的な魅力が損なわれるリスクがあります。長期的には「共生社会」をどう築いていくかが重要なテーマとなるでしょう。
国際協力の必要性
不法滞在や不法就労は、日本国内だけで完結する問題ではありません。送り出し国や国際機関との連携が欠かせませんが、現時点では十分な仕組みが整っていない面もあります。国際的な協力体制がなければ、対策の効果は限定的になる恐れがあります。
まとめ
政府が外国人の不法滞在対策に関する予算を倍増させる方針を示したことは、日本が抱える課題への強い危機感を反映しています。背景には、不法滞在者や不法就労者の増加、労働市場の不公平、地域社会の治安不安といった複合的な問題があります。
今回の予算拡充は、単なる取り締まりの強化にとどまらず、
- 入管庁の人員増強
- ITを活用した監視システム導入
- 自治体や警察との連携
- 企業監査の徹底
- 外国人相談・支援窓口の充実
といった多面的な取り組みを支えるものです。これにより、不法滞在や不法就労の抑制、労働市場の健全化、治安の安定化といった効果が期待されます。
しかし一方で、人権侵害のリスクや労働力不足への影響、国際的な協力の不足といった課題も残ります。予算増額だけでは解決できない側面が多く、取り締まりと支援を両立させながら、長期的には「外国人との共生社会」をいかに築いていくかが問われています。
政府の施策が、国民の安心と公平な社会を守りつつ、外国人が適正に暮らし働ける社会の実現につながるかどうか。今回の予算倍増は、その試金石となる重要な一歩といえるでしょう。