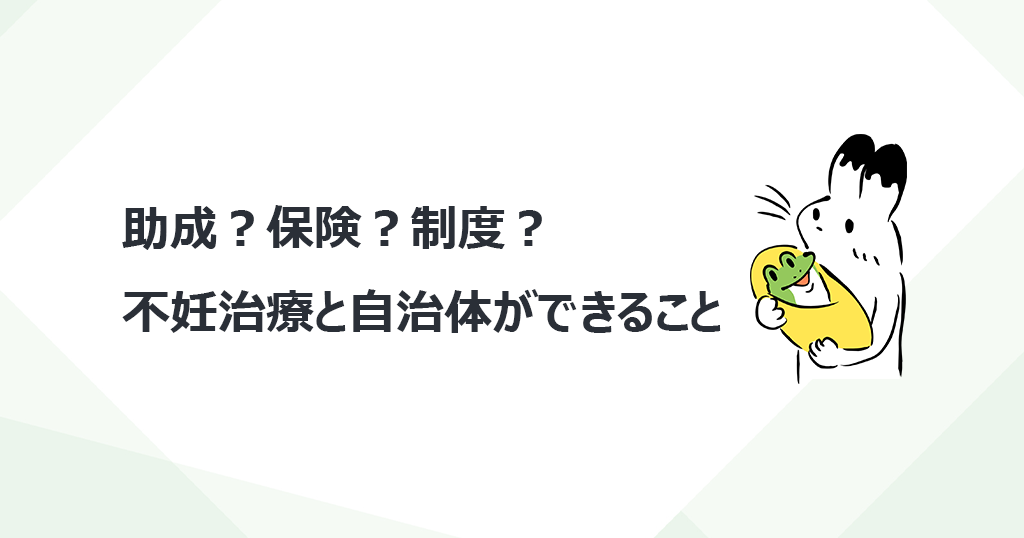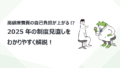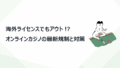妊活や不妊治療を考え始めたとき、まず気になるのがお金の話。2022年から体外受精などにも保険が使えるようになって、少しハードルは下がったけれど、それでも“すべてがカバーされる”わけじゃありません。
しかも、住んでいる自治体によって助成の内容がぜんぜん違うこともあるから、「調べれば調べるほどよくわからない…」と感じる人も少なくないはずです。
この記事では、そんな不妊治療にかかるお金の「いま」をわかりやすく整理します。
保険でどこまでカバーされるの? 自治体の助成ってどうなってるの? どんな制度をどうやって使えばいいの?
知っておくだけで“できること”が変わる、大切なお金の話をまとめました。
不妊治療にかかるお金のこと、保険や支援はどうなってる?
1割が体外受精児という現実
現代の日本では、体外受精で誕生する子どもが「9人に1人」と言われています。これは、出生数全体に占める割合が1割を超えており、もはや不妊治療は特殊な医療ではなく、社会全体の生殖における重要な選択肢の一つとなっていることを示しています。
不妊治療には、精液を子宮に注入する「人工授精」や、卵子と精子を体外で受精させたのちに子宮に戻す「体外受精」、より高度な「顕微授精」など複数の方法があります。そのいずれも、医学的・精神的・時間的に大きな負担が伴いますが、とりわけ大きな障壁となってきたのが「費用負担」でした。
保険適用のインパクトとその限界
2022年4月より、人工授精・体外受精・顕微授精などの生殖補助医療が公的医療保険の対象となりました。これにより、たとえば1回平均50万円とも言われる体外受精が、原則3割負担で15万円程度となり、家計に与えるインパクトは大きく改善しました。
しかし、保険適用には厳格な制限があります。
- 年齢制限:治療開始時に女性が43歳未満であること。
- 回数制限:40歳未満で最大6回、40〜42歳は最大3回まで。
このような制限があるため、「もう一度だけチャレンジしたい」「今度こそ妊娠するかもしれない」と思っても、保険対象外になり、1回数十万円の全額自己負担が必要になるケースも珍しくありません。
また、保険適用されない「先進医療」(例:タイムラプス培養、着床前診断、IMSIなど)は、費用負担が全額自己負担となるものの、効果を求めて併用する人も多く、結果として保険適用の恩恵を最大限に享受できない場合も多いのです。
自治体の助成制度:見えない「支え」のしくみ
ここで重要なのが、国の制度に「上乗せ」する形で行われている自治体の助成制度です。2024年末に読売新聞が90自治体を対象に行った調査では、全体の約7割にあたる62自治体が、以下のような支援を実施していました。
- 先進医療費に対する助成(41自治体)
- 保険適用後の自己負担分への助成(18自治体)
- 年齢・回数制限を超えて自己負担となった場合の助成(9自治体)。
例えば東京都では、体外受精や顕微授精と併用して実施された先進医療にかかる費用の7割(上限15万円)を助成しています。これは、1回20万円かかった場合に最大14万円が支給される仕組みであり、経済的な負担を大きく軽減する内容となっています。
ここまでの制度を見てわかることは、不妊治療への支援が「医療保険+自治体助成」の二層構造になっているということです。これは一方で「自治体間格差」を生む側面もありますが、逆にいえば、「住民に対する希望の提供」という側面も持ちます。
だからこそ、自治体が果たすべき役割は大きく、単なる金銭補助ではなく、
- 専門相談窓口の設置
- ピアカウンセリングの提供
- 職場と治療の両立支援
など、包括的なライフサポート政策として「不妊治療支援」を捉え直す必要があるのです。
なぜ今、“まち”が不妊治療を支えるの?
人口減少と少子化、その本質は「希望の断絶」
日本の出生数は、2023年に80万人を下回り、戦後最少を更新しました。これは単なる人口統計の問題ではなく、「子どもを持ちたい」と願う人たちが、経済的・社会的・心理的な障壁によってその希望を断念せざるを得ない状況を表しています。
不妊症を経験した夫婦はおよそ5.5組に1組とされ、それだけ多くの人々が子どもを持つという選択に挑んでいます。しかし、保険適用や助成制度が整備されたとはいえ、それでも「あと数十万円が用意できなかった」「仕事を休めず通院が継続できなかった」といった理由で治療を諦める人は後を絶ちません。
こうした状況が示すのは、少子化の直接原因は「子どもを持ちたくない」ことではなく、「子どもを持つための希望が現実化できない」ことなのです。つまり、少子化対策は、「希望の再構築」でなければならないのです。
自治体こそが「希望のインフラ」を担う主体
このような希望を支えるには、国の制度だけでは限界があります。そこにこそ自治体の出番があります。
まず、自治体には住民に最も近い立場として、ライフイベントの節目(婚姻、妊娠、出産、育児)に対して「切れ目のない支援」を届ける使命があります。たとえば、以下のような制度設計はその好例です。
- 東京都の例では、先進医療に対し最大15万円まで助成を行い、婚姻の有無に関わらず事実婚も対象とするなど柔軟な対応がなされています。
- 青森県では2024年度から全国初の「自己負担の実質無償化」に踏み切り、大きな注目を集めました。これは単なる助成ではなく、「不妊治療に前向きな社会的メッセージ」としての機能も果たしています。
自治体が独自にこうした支援策を展開することで、住民にとって「ここでなら生きていける」という安心感を創出できるのです。特に、若い世代が転居や移住を考える際、子育て・生殖支援の充実は無視できないファクターとなってきています。
「不妊治療と仕事」の両立支援が人口政策になる時代
さらに見逃せないのが、不妊治療の特性として、頻繁な通院と精神的な負荷が伴うという点です。これにより、多くの人が「働きながらの治療」に限界を感じ、退職や治療中断に追い込まれています。
厚生労働省の調査では、治療経験者の26.1%が「退職・雇用形態の変更・治療中断」を余儀なくされているとされています。この数値は、職場環境の整備が地域社会にとっても重要であることを示唆しています。
これを受けて、厚労省は「不妊治療と仕事の両立支援」を推進するために、企業向けのガイドラインや認定制度(例:くるみん「プラス」認定制度)を導入しました。加えて、企業が不妊治療のための特別休暇制度や柔軟な勤務制度を導入した場合には「助成金(最大60万円)」を支給する制度も存在します。
こうした取り組みに対して自治体が積極的に企業支援や情報提供を行うことで、「地域全体で治療と仕事を支える」という空気を作り出すことが可能です。
人口政策=「個人の希望の制度化」である
不妊治療に関する支援を、単なる「医療費助成」にとどめるのではなく、住民一人ひとりの「ライフプランの選択肢の保障」として捉え直すこと――これが自治体の役割であり、真の人口政策です。
未来の親たちは、「今この地域で家庭を築けるか」「生きやすいか」を敏感に感じ取り、住む場所を選びます。だからこそ、「不妊治療支援」はまさに地域のブランド構築そのものであり、人口戦略の最前線に位置づけられるべきなのです。
どこに住むかで変わる?自治体ごとのサポートのちがい
どこで治療するか、ではなく「どこでなら産めるか」が問われる時代
かつて医療政策において「地域差」はある程度容認されてきました。都市部と地方では財源や病床数、医師の数に違いがあり、制度運用の柔軟性が地方自治の魅力とされてきたからです。
しかし、こと不妊治療に関しては、その「自治体間格差」が当事者に深刻な現実を突きつけています。
たとえば、東京都渋谷区のように、先進医療の自己負担分や保険適用後の負担に対して手厚い助成を行う自治体がある一方で、まったく独自の支援策を用意していない市町村も存在します。この差は、単に金銭の多寡にとどまらず、「治療を継続するか断念するか」に直結する問題です。
ある人はこう語ります。
「あと数万円の助成があればもう1回チャレンジできた。隣の市に住んでいれば、その助成があった。」
これは個人の悲痛な叫びであると同時に、政策的には「住所によって人生の選択肢が変わる」現象を示すものです。
自治体ごとの支援格差の原因は「制度疲労」と「情報の非対称」
自治体間格差が生まれる背景には、主に以下の3つの要因があると考えられます。
- 財政基盤の違い
都市部では税収が多く、住民ニーズに即応した政策展開が可能ですが、地方や財政が逼迫している自治体では難しいのが現実です。 - 職員の専門性・熱量の差
不妊治療支援の制度設計や相談体制を構築するには、医療や福祉、ジェンダーに関する専門的知識が必要です。これを実務レベルで構築できる自治体は、まだ限られています。 - 情報の非対称性
住民が「どの自治体に、どんな支援があるのか」を正確に把握するのは容易ではありません。結果として、助成がある地域に住んでいても制度を利用し損ねてしまう人もいます。
このようなギャップが、現場では「自己責任」や「運の問題」として片づけられ、支援が届かないという事態を生んでいます。
解消の鍵は「横断型政策」と「デジタルによる可視化」
この格差を是正するために、以下のような施策が求められています。
1. 広域自治体による「最低支援水準」の設定
都道府県レベルでの統一的な支援基準の設定や、市町村への助成財源の補助を通じて、地域差を一定程度埋めることができます。東京都が行っているように、「市区町村とは別枠で東京都が独自助成を設ける」やり方は、その一例です。
2. 国による制度整備の「下支え」
厚生労働省は、不妊治療支援の一環として、自治体職員向けのガイドラインや研修事業を実施しています。また、ピアサポーター制度や職場の両立支援研修の全国展開も始まっています。
しかし、これを「任意」ではなく「努力義務」として強化することで、各自治体に「最低限の支援メニュー」を義務化することも検討されるべきでしょう。
3. 情報の可視化――全国版ポータルサイトの創設
国や民間と連携して、「不妊治療支援制度の全国マップ」を整備し、住民が自分の自治体にある制度を簡単に比較・確認できるようにするべきです。
具体的には、
- 助成内容(対象、金額、回数)
- 申請方法と受付期間
- 窓口担当課と連絡先
- 治療開始前のシミュレーション機能
などを盛り込んだユーザー目線の情報集約が重要です。
支援格差を「地域の競争力」に転換
繰り返しになりますが、自治体間で不妊治療支援に差がある現状は、「機会格差」であり、人生の質の格差でもあります。
しかし逆にいえば、これを逆手にとって「支援が手厚い自治体=魅力的なまち」としてブランド化することも可能です。青森県や京都市のように、自治体が先んじて支援を打ち出すことで、住民の満足度を高めるだけでなく、他地域からの移住・定住促進にもつながるのです。
政策において最も重要なのは、数字ではなく「人の選択肢を増やす」ことです。不妊治療支援の自治体間格差は、適切な仕組みづくりと情報発信によって、「格差」ではなく「先進性」として評価される未来へと転換できるのです。
安心して治療に向き合える“まち”をつくるには
支援とは「医療費の補填」だけではない
不妊治療支援と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは「費用助成」でしょう。確かに経済的支援は基盤の一つであり、不可欠な政策ですが、それだけでは「治療の継続」や「社会的孤立の回避」は困難です。
不妊治療は平均して数年単位の期間を要し、肉体的・精神的な消耗も大きい。「保険が利く」「お金が出る」だけではなく、「支えてくれる人がいる」「孤独じゃない」と感じられる環境づくりこそが、自治体に求められる次のステージなのです。
あるべき支援モデル①:3層構造の助成設計
1層目:ベースとしての医療保険適用制度
すでに述べた通り、公的医療保険により人工授精・体外受精・顕微授精の基本費用の3割負担化が実現しました。ただしこれは「最低限のセーフティネット」に過ぎません。
2層目:自治体による上乗せ助成
たとえば東京都のように、先進医療(保険適用外の高額オプション)に対し7割・上限15万円の助成を設けることで、「選択肢の幅」を保証します。
3層目:特別支援(低所得世帯・年齢回数制限越え対象者など)
年齢・回数制限に該当しないが医療的に妥当とされるケース、生活困窮世帯などには、例外的に独自審査型の特別助成を設ける柔軟性が必要です。実際、9自治体がこれに近い支援を行っています。
これにより、「費用により治療を断念しない」制度が完成するのです。
あるべき支援モデル②:相談・ピア支援体制の整備
不妊治療の当事者にとって、治療内容・通院スケジュール・副作用・メンタルケアなど、疑問や不安は尽きません。にもかかわらず、一般的な福祉窓口では専門的対応が困難です。
その解決策として以下の支援が有効です。
- 専門相談センターの設置(都道府県や中核市)
医師・助産師・看護師・心理士などが対応し、相談の入口として機能。 - ピアサポーター制度の活用
治療経験者が相談支援を行う制度。国は2021年度より育成研修も実施しており、これを地域に根付かせる体制づくりが求められます。 - LINEやチャットによる相談窓口
匿名性・即時性があるため、特に若年層の利用ハードルを下げる効果が期待されます。
相談体制を充実させることで、早期受診の促進・治療継続率の向上・メンタル不調の軽減といった効果が波及的に生まれます。
あるべき支援モデル③:啓発・教育の徹底
不妊治療に対する社会的な理解は、いまだ十分とは言えません。
- 「なぜすぐ子どもを作らないのか?」
- 「治療をしてまで産む必要があるのか?」
- 「仕事を休んでまで通院するのはわがままでは?」
こうした無理解・無関心・偏見が、当事者に精神的な二次被害をもたらします。
自治体が行うべきは以下のような啓発施策です。
- 地域広報誌やSNS、公共施設でのポスター掲示
- 学校教育での「生殖教育」の導入(高校・大学での授業等)
- 市民講座・フォーラムでの体験共有(ピア講演等)
さらに、治療を受ける住民だけでなく、職場(企業)への啓発も重要です。厚生労働省では「不妊治療と仕事の両立支援ガイドブック」や研修制度を用意しており、自治体が地元企業に対しこれらの活用を促すことで、支援の輪が拡大していきます。
あるべき支援モデル④:地域エコシステムの形成
ここまでの取り組みを一過性で終わらせないためには、「地域のエコシステム化」が必要です。
- 行政(子育て支援課・健康福祉部)
- 医療機関(産婦人科・生殖医療専門施設)
- 教育機関(中高・大学)
- 民間団体(当事者NPO、女性支援団体など)
- 地域企業(従業員支援策や福利厚生)
これらが連携し、情報共有・研修・協議会を定期的に行うことで、地域全体が「不妊治療を支える空気」をつくることができます。
その一例が、青森県が取り組んでいる「自治体・医療機関・地元企業の連携によるワンストップ支援体制」です。企業が従業員の通院に配慮し、医療機関は相談窓口を開設、自治体は費用支援を行う。この三位一体の体制こそが、持続可能な支援モデルの象徴です。
不妊治療は、人生をかけた挑戦です。その挑戦に行政が伴走することで、人々は初めて「自分の人生を自分で選べる」と実感できるのです。
自治体に求められるのは、「何人産ませるか」ではなく、「産みたい人が、安心して挑戦できる環境を整えること」です。制度、相談、啓発、連携。その全てを地域に根付かせることで、不妊治療支援は少子化対策以上の意味を持つ政策となります。
参考資料
不妊治療に関する取り組み(こども家庭庁)