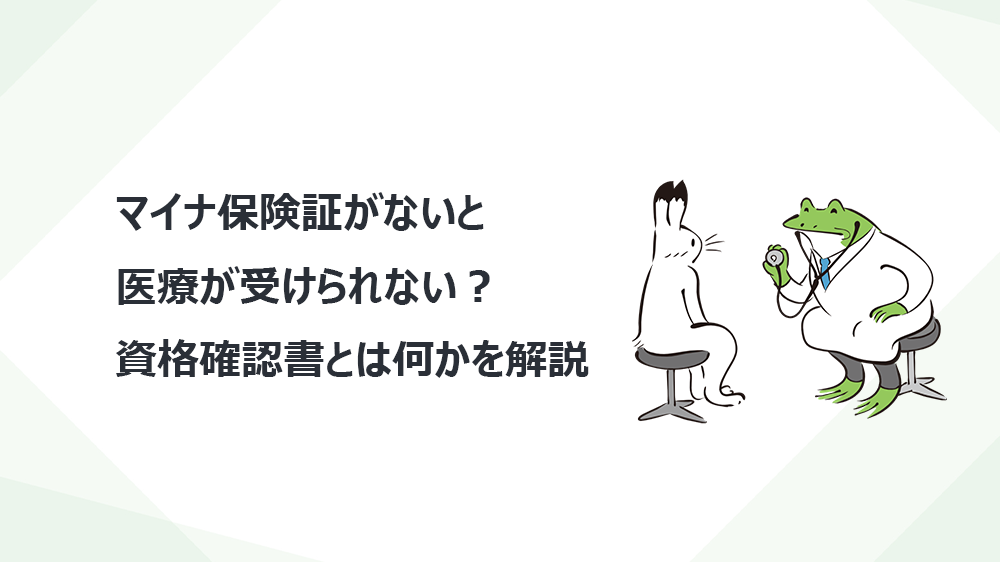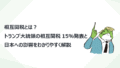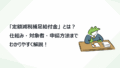2024年12月から、これまで使われてきた健康保険証が廃止され、原則として「マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)」が導入されます。
しかし「マイナンバーカードを持っていない」「健康保険証としての登録ができていない」といった理由で、不安を感じている人も少なくありません。
そんなときに備えて設けられているのが「資格確認書」という制度です。
この記事では、マイナ保険証が使えないときでも安心して医療を受けられるよう、「資格確認書とは何か」「誰が対象でどう使うのか」について、わかりやすく解説します。
マイナ保険証が話題の理由
2024年12月、私たちの医療制度に大きな変化が訪れます。これまで使われてきた紙の健康保険証が廃止され、「マイナンバーカード」を保険証として使う「マイナ保険証」へと一本化されるのです。
この動きは、政府のデジタル化政策の一環として進められており、医療機関でのスムーズな受診や、過去の薬剤情報・健診情報の共有など、利便性と安全性を高めることが目的とされています。しかし現実には、「マイナンバーカードをまだ作っていない」「保険証としての利用登録が済んでいない」という人も多く、制度への不安や疑問の声もあがっています。
特に高齢者や、デジタル機器の操作に慣れていない方、あるいは育児や介護などで忙しく手続きが後回しになっている家庭では、「マイナ保険証がないと病院にかかれなくなるのでは?」という切実な心配があるのも事実です。
そんなとき、私たちを支えてくれるのが「資格確認書」という制度です。これは、マイナ保険証を持っていない人でも医療を受けられるようにするための措置として、各保険者(協会けんぽ、市町村の国民健康保険、共済組合など)によって交付されるものです。
この資格確認書がどんな制度なのか、どんな人が使えるのか、どうすればもらえるのか――この記事ではその基本から活用方法までを丁寧に解説していきます。
資格確認書とは何か?
「資格確認書(しかくかくにんしょ)」とは、健康保険の資格を証明する書類のことです。2024年12月に紙の健康保険証が原則廃止されることに伴い、「マイナ保険証(マイナンバーカードを使った保険証)」を持っていない人が、医療機関を受診できなくなることがないように設けられた新しい制度です。
この資格確認書は、これまでの保険証と同様に、病院や薬局などの医療機関で提示することで、保険診療を受ける際に使うことができます。つまり、マイナ保険証をまだ持っていない人、あるいは手続きが完了していない人でも、この確認書さえあれば、これまでと同じように医療サービスを受けられるのです。
資格確認書は無料で交付されます。本人が加入している公的医療保険の「保険者」(たとえば、協会けんぽや市区町村など)から発行されるもので、申請が必要です。自動的に送られてくるものではない点に注意しましょう。
見た目はこれまでの健康保険証とは異なり、プラスチックのカードではなく、紙の様式になる場合が多いです。ただし、内容としては「その人が公的な健康保険に加入していること」を証明するものであり、医療費の自己負担割合(1割・3割など)も従来通り適用されます。
加えて、資格確認書には有効期限が設けられています。これはマイナ保険証が恒久的に使えるのに対して、資格確認書はあくまでも“つなぎ”の措置であるという位置づけであるためです。原則として1年間の有効期間となっており、その後も必要であれば更新の手続きが必要になります。
また、資格確認書は「オンライン資格確認」のシステムとは連携していないため、過去の診療情報や薬剤履歴などの共有機能はありません。つまり、医療の効率化や情報連携といったマイナ保険証の特長は使えないという制限もあります。
このように資格確認書は、マイナ保険証の取得や登録が間に合わない人に対する「セーフティネット」としての役割を担っているのです。
資格確認書が必要になる人とは?
健康保険証が廃止され、マイナ保険証への一本化が進められる中で、「資格確認書」は誰にでも必要になるわけではありません。では、どんな人が資格確認書を必要とするのでしょうか?主に以下のようなケースが該当します。
マイナンバーカードを持っていない人
もっとも多いのがこのケースです。マイナ保険証はマイナンバーカードと健康保険証の機能をひも付けることで利用できますが、そもそもマイナンバーカードを持っていない人はその登録すらできません。
現在も高齢者を中心に、マイナンバーカードの取得率は100%には至っておらず、「カードは作っていないが病院には行く必要がある」という人が少なくありません。こうした人にとって、資格確認書は非常に重要な受診手段となります。
マイナンバーカードを持っていても、健康保険証としての利用登録をしていない人
マイナンバーカードを取得していても、健康保険証として使うには「利用申込み(ひも付け)」を済ませておく必要があります。スマホやコンビニ端末を使った手続きが必要になるため、ITに不慣れな人はこの登録が完了していない場合があります。
この場合、カード自体を持っていても保険証としては使えないため、医療機関では資格確認書が必要になります。
一時的にマイナ保険証が使えない状態の人
カードの紛失や盗難、破損、あるいは申請中など、マイナ保険証を一時的に使えない場合も想定されます。とくにカードを再発行中の場合や、引っ越しや転職などで保険者が変わった直後は手続きが間に合わないことがあります。こうしたタイミングでも資格確認書があれば、必要な医療を受けることができます。
高齢者や子ども、障がいのある人など支援が必要な人
制度移行にともない、自治体や保険者は特別な配慮が必要な方々にも対応しています。高齢でマイナンバーカードの取得や利用が困難な方、介助が必要な障がい者、親が申請手続きを行っていない子どもなども、必要に応じて資格確認書の対象となります。
とくに介護施設などに入所している高齢者は、医療機関とのやり取りが頻繁になるため、施設の職員が代理申請するケースも考えられます。
どうすれば資格確認書をもらえるの?
資格確認書は、自動的に送られてくるものではありません。必要な人が自分で申請する必要があるという点が重要です。ここでは、申請方法や必要書類、注意点について詳しく解説します。
申請先は「加入している保険者」
資格確認書は、あなたが加入している医療保険の運営元、つまり「保険者」が交付します。保険者の種類によって申請先が異なりますので、自分がどこに加入しているかを確認することが第一歩です。
| 保険の種類 | 保険者(申請先) |
|---|---|
| 会社員など(全国健康保険協会) | 協会けんぽ 各都道府県支部 |
| 自営業・無職など | お住まいの市区町村(国民健康保険) |
| 公務員 | 共済組合 |
たとえば会社勤めの人で協会けんぽに加入している場合は、各都道府県支部に申請します。
自営業や無職の人は、市役所や区役所の国保窓口が対応窓口です。
申請方法と必要なもの
申請は基本的に「窓口」か「郵送」で行えます。一部の保険者ではオンライン申請に対応している場合もありますが、多くは紙の申請書が必要です。
主な必要書類
- 資格確認書交付申請書(保険者のウェブサイト等で入手可能)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 健康保険証(現在有効なものがあれば)
申請書は各保険者のサイトからダウンロードできます。たとえば協会けんぽの場合、専用の申請書式を印刷して記入・郵送する形となっています。
代理申請も可能
本人による申請が難しい場合、家族などによる代理申請も可能です。代理人が申請する場合は、以下のような書類が追加で求められます。
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(保険者が指定する様式)
施設に入所している高齢者や障がいのある方についても、家族や施設職員が代理で申請を行うことができます。
発行にかかる日数と受け取り方法
申請から実際に資格確認書が発行されるまでの期間は、保険者によって異なりますが、概ね1〜2週間程度と見込まれています。受け取り方法も、以下のようにいくつかあります。
- 窓口での受け取り
- 郵送での送付(郵送申請時はこちらが一般的)
- 特別な事情がある場合の個別対応(施設宛て送付など)
受診予定がある方は、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
資格確認書は、「いざというとき」の安心につながる重要な書類です。必要になりそうな場合は、慌てずスムーズに医療を受けられるよう、早めに準備しておきましょう。
有効期限と更新方法
資格確認書は、マイナ保険証の代替手段として発行される「暫定的な書類」です。そのため、通常の健康保険証とは異なり有効期限が設けられている点に注意が必要です。
有効期限は「原則1年間」
資格確認書の有効期間は、原則として交付日から1年間です。たとえば2025年1月10日に交付された場合、2026年1月9日まで利用できます。
ただし、被保険者の加入状況や保険者の判断によって、有効期間が短く設定されることもあります。特に転職・退職・転居などで保険者が変更になる可能性がある場合、短めの期限になるケースもあります。
また、資格確認書に記載されている有効期限を過ぎてしまうと、その書類は無効となり、医療機関で保険証として使うことができません。事前に期限を確認し、早めの更新を心がけることが大切です。
更新はどうやって行う?
資格確認書の有効期限が近づいてきたら、再び申請手続きを行うことで更新が可能です。更新といっても、手続きの内容は初回の交付とほとんど同じです。
更新時の流れ(例)
- 保険者の窓口やウェブサイトから申請書を入手
- 必要事項を記入し、本人確認書類とともに提出(郵送または窓口)
- 保険者が内容を確認し、新しい資格確認書を発行
- 郵送または窓口で受け取り
再申請にあたっての「受付開始時期」は保険者によって異なりますが、多くの場合、有効期限の1か月前から受付可能となっています。
紛失・破損した場合の対応
資格確認書を紛失したり破れてしまった場合も、再発行を申請することができます。この際も保険者への申請が必要となり、本人確認書類の提出が求められます。特に高齢の家族や子どもに持たせている場合は、保管場所の確認やコピーの保管も検討すると安心です。
マイナ保険証を取得・登録したらどうなる?
もし途中でマイナンバーカードを取得し、保険証としての利用登録が完了した場合には、資格確認書は不要になります。その時点でマイナ保険証が有効となり、以後はカードの提示で医療機関を受診できるようになります。
つまり、資格確認書は「マイナ保険証を取得するまでのつなぎ」としての役割を持っているのです。
有効期限がある以上、資格確認書は「もらって終わり」ではありません。期限管理と更新手続きまでを含めて、計画的に使っていくことが大切です。
資格確認書とマイナ保険証の違い
マイナ保険証と資格確認書は、どちらも「健康保険の資格を証明する」ための手段ですが、その性質や使い勝手にはいくつかの違いがあります。ここでは、両者をわかりやすく比較しながら、それぞれの特徴を整理してみましょう。
基本的な違いを表で確認
| 項目 | マイナ保険証 | 資格確認書 |
|---|---|---|
| 発行元 | 市区町村(マイナンバーカード) | 加入している保険者(協会けんぽ、市区町村など) |
| 取得方法 | マイナンバーカード取得+利用登録 | 保険者への申請 |
| 利用方法 | カードリーダーにかざすだけ | 医療機関窓口で紙を提示 |
| 有効期限 | マイナンバーカードの有効期限まで | 原則1年間(更新制) |
| オンライン資格確認 | 〇(医療機関と情報共有可) | △(限定的。対応しない施設も) |
| 健診・薬剤情報の連携 | 〇 | ×(データ連携不可) |
| 利用の手間 | 一度登録すれば簡単 | 毎年の申請・管理が必要 |
| 紛失時の影響 | 他の用途(本人確認等)にも影響大 | 資格確認用に限定される |
マイナ保険証のメリット・デメリット
マイナ保険証は、オンライン資格確認が可能で、医療機関での受診歴や薬剤情報、健診データを共有できるため、より質の高い医療が期待されます。また、カード1枚で本人確認と保険証の機能を兼ねられる点も利便性があります。
一方で、カードの取得や登録に手間がかかる、カードリーダーに不具合があると受付に時間がかかるといった現実的な課題も指摘されています。
資格確認書のメリット・デメリット
資格確認書は、マイナ保険証をまだ持っていない、または使えない人にとっての「医療アクセスの確保手段」として有効です。申請すれば無料で交付され、医療機関ではこれまでの保険証と同じように使うことができます。
ただし、オンライン資格確認や医療情報の共有には対応しておらず、有効期限の管理や毎年の更新が必要です。また、再発行にも一定の手間がかかります。
どちらが便利?選び方のポイント
原則として政府はマイナ保険証の利用を推進しており、今後も医療機関側の設備や制度はマイナ保険証に最適化されていく見込みです。そのため、マイナンバーカードの取得・登録が可能であれば、将来的にはマイナ保険証への移行が望ましいと言えます。
一方で、まだカードを取得していない、あるいは事情があって利用登録が難しいという人にとっては、資格確認書が確実で現実的な選択肢となります。特に高齢者や障がいのある方、申請手続きが難しい方には、資格確認書の活用が安心につながるでしょう。
それぞれの特徴を理解したうえで、自分や家族にとってどちらが適しているのかを考えておくことが大切です。
よくある質問(FAQ)
ここでは、資格確認書やマイナ保険証に関して多くの人が抱きがちな疑問にお答えします。
Q1. 資格確認書があれば、健康保険証と同じように病院を受診できますか?
はい、受診できます。
資格確認書は「その人が健康保険に加入していること」を証明する正式な書類です。窓口で提示すれば、健康保険証と同様に保険診療(3割負担など)を受けられます。自由診療になることもありませんので安心してください。
Q2. 資格確認書が手元に届くまでに病院に行きたいときはどうしたらいいですか?
申請中でまだ資格確認書が届いていない場合でも、受診は可能です。
この場合、医療機関の窓口で「保険証を申請中」であることを伝えましょう。後日、保険者に対して必要な手続きを行えば、自己負担分の差額(いったん10割負担していた場合)を返金してもらえる制度があります。
Q3. マイナ保険証の方が便利ですか?資格確認書ではだめ?
長期的にはマイナ保険証の方が便利です。
マイナ保険証を使えば、医療機関と過去の診療情報や薬の履歴などが共有されるため、より適切な医療が受けられるという利点があります。ただし、マイナ保険証の利用登録ができない、カードを紛失してしまったなどの場合には、資格確認書が確実な選択肢となります。
Q4. 高齢の親がマイナンバーカードを持っていません。代理で資格確認書を申請できますか?
はい、可能です。
代理人による申請は認められています。必要書類として、代理人の本人確認書類と委任状が求められるケースが多いです。自治体や保険者によって細かい要件が異なるため、事前に確認しましょう。
Q5. 資格確認書は、医療以外にも使えますか?
いいえ、医療用に限定されます。
資格確認書は、健康保険の資格を証明する目的でのみ使用されるもので、本人確認書類としての機能はありません。運転免許証やマイナンバーカードのように身分証明書としては使えないため注意してください。
Q6. 健康保険証が廃止されても、何もしなくても大丈夫?
何もしないと、保険診療が受けられなくなる可能性があります。
マイナ保険証の登録か、資格確認書の申請か、いずれかの対応が必要です。「まだマイナンバーカードを作っていない」「手続きが間に合わない」という場合は、早めに保険者に問い合わせて、資格確認書の準備を進めておきましょう。
このように、制度の変更にともない不安の声もありますが、正しく情報を知っていれば安心して対応できます。最後に、この記事の内容をまとめて確認しておきましょう。
参考資料
- 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)(厚生労働省)
- マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)(全国健康保険協会)