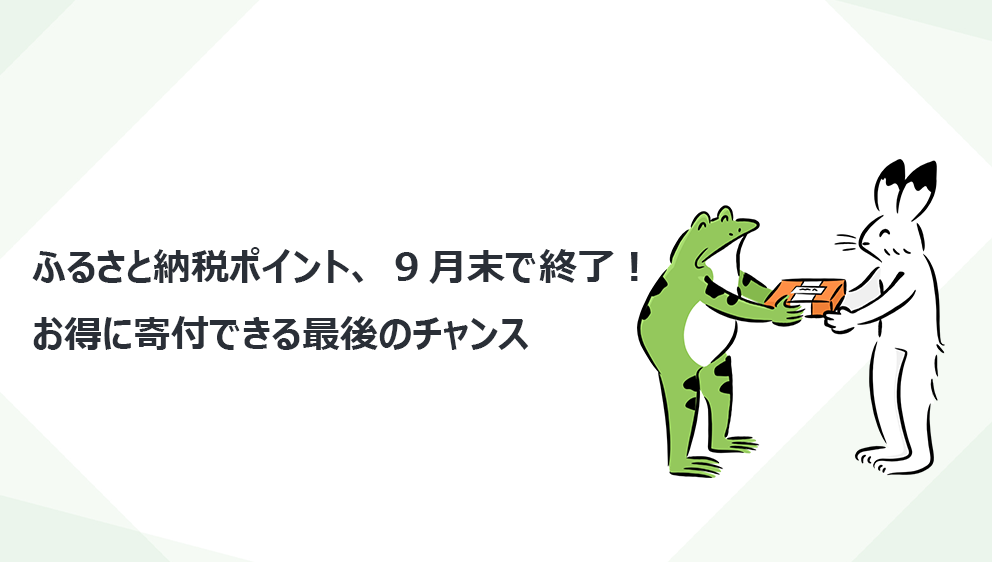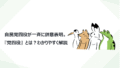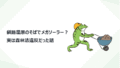ふるさと納税で人気を集めていた「ポイント制度」が、ついに2025年9月末で終了します。ポイントを貯めて好きなタイミングで返礼品を選べる“お得感”が魅力でしたが、この仕組みを利用できるのは今だけです。本記事では、ポイント廃止の背景や影響、そして終了前に寄付をしておくメリットをわかりやすく解説します。
ふるさと納税とポイント制度とは
ふるさと納税は、2008年にスタートした寄付制度です。仕組みはシンプルで、自分が応援したい自治体に寄付すると、その地域の特産品などを「返礼品」として受け取ることができ、さらに一定の手続きをすれば寄付額のうち2,000円を超える部分が住民税や所得税から控除されます。つまり、実質2,000円の自己負担で豪華な返礼品を楽しめるという制度として、全国的に人気を集めています。
当初は「地元の特産品を知ってほしい」「地域を応援してほしい」という狙いで始まった制度でしたが、年々返礼品競争が激しくなり、ブランド牛やカニ、家電など豪華な品が次々と登場しました。そのなかで生まれたのが「ポイント制度」です。
ポイント制度の仕組み
ふるさと納税のポイント制度とは、寄付をした際にすぐ返礼品を受け取るのではなく、寄付額に応じて「ポイント」を付与し、そのポイントを後日使って返礼品と交換できる仕組みです。
例えば、10,000円をある自治体に寄付すると、寄付者はその自治体のポイントを10,000ポイント分受け取ることができます。そして、そのポイントを使ってお米やお肉など複数の返礼品の中から好きな時期に選ぶことができる、というわけです。
この制度は、特に以下のようなメリットがありました。
- タイミングを選べる自由度
返礼品をすぐ受け取るのではなく、季節や生活の都合に合わせて後から申し込めるため、冷蔵庫がいっぱいの時期でも安心です。 - 複数回に分けて利用可能
一度の寄付で得たポイントを分けて使えるので、「今はお米、来月はお肉」といった形で楽しめます。 - 返礼品選びの幅が広がる
ポイントをまとめて高額な返礼品に充てたり、少額で手軽な品を選んだり、寄付者のライフスタイルに合わせやすい仕組みでした。
この“お得感”と“自由度”が、多くの寄付者に支持された大きな理由です。
ポイント制度が広がった背景
ふるさと納税市場は年々拡大し、2023年度には寄付額が9,654億円と過去最高を更新しました。その裏には、寄付者が「どれだけお得に返礼品を受け取れるか」を重視する傾向が強まったことがあります。
ポイント制度は、寄付を「すぐに返礼品が届く一回限りの取引」から「ポイントを貯めて自分の好きなときに使える長期的なお得サービス」へと変えるものでした。これは、ネットショッピングやクレジットカードのポイント還元に慣れた現代の消費者にとって、とても魅力的に映ったのです。
また、自治体側にとっても、ポイント制度は寄付を呼び込む強力な武器でした。返礼品をすぐに発送する必要がないため、在庫管理や発送業務の負担を軽減でき、寄付者との接点を長く保つこともできます。そのため、多くのポータルサイトや自治体が積極的にポイント制度を導入し、人気を集めてきました。
ふるさと納税の本来の目的とのずれ
しかし、一方でこの「ポイント制度」は制度本来の趣旨とのズレを生んでしまいました。ふるさと納税は「地域の応援」を目的としていますが、ポイント制度は「寄付者にとってどれだけお得か」という消費者目線に寄りすぎてしまったのです。
寄付者の多くは返礼品目当てで寄付先を選ぶようになり、自治体間で豪華さを競い合う“返礼品合戦”が激化しました。その結果、
- 地域資源を活かした本来の返礼品が埋もれてしまう
- 寄付金が一部の自治体に集中する
- 制度の健全性に疑問が生じる
といった課題が浮き彫りになったのです。
こうした流れの中で、総務省はふるさと納税制度の健全化に向けて規制を強めていきました。そしてついに「ポイント制度の廃止」という大きな決断に至ったのです。
ポイント廃止の背景
ふるさと納税におけるポイント制度は、寄付者にとって便利でお得な仕組みでした。しかし、この制度が広がるにつれて「本来の制度の目的から逸脱しているのではないか」という声が高まり、総務省はついに2025年9月末での廃止を決定しました。では、なぜ今、ポイント制度を廃止する必要があったのでしょうか。その背景を整理してみましょう。
過度な返礼品競争の激化
ふるさと納税は本来、「応援したい自治体に寄付をして地域を支援する」ことを目的に設計された制度です。しかし、ポイント制度は寄付者に「とにかくお得な返礼品を選ぶための仕組み」として利用されるケースが目立つようになりました。
例えば、ある自治体では寄付金額の50%相当のポイントを付与し、それを後日自由に返礼品と交換できるようにしていました。返礼品の還元率は原則3割以内と定められているにもかかわらず、ポイントに形を変えることで実質的に規制を回避していたのです。
このような「抜け道的」な仕組みは、一部の寄付者には歓迎されましたが、制度全体の公平性や健全性を損なう結果となりました。
制度本来の趣旨との乖離
ふるさと納税の原点は、「地方の財源を補い、地域振興につなげる」というものでした。ところが、ポイント制度では「後で返礼品を選べるから便利」「まとめて高額品をもらえるからお得」といった消費者視点が前面に出すぎてしまい、地域への応援という本来の趣旨が薄れてしまいました。
さらに、寄付金の一部は返礼品やポイント付与に充てられるため、自治体が実際に使える財源が減少するという問題もあります。これでは、地域の課題解決や住民サービスの向上に十分なお金を回せなくなってしまうのです。
寄付額の偏り
ポイント制度は、特に財政的に余裕がある都市部や人気の返礼品を扱う自治体に寄付を集中させる傾向を強めました。結果として、知名度の低い小規模自治体や特産品が限られている地域は寄付を集めにくくなり、地域間格差が拡大する懸念が高まりました。
ふるさと納税は「全国どの自治体にも寄付できる」というのが制度の魅力ですが、ポイント制度によって一部の自治体に過度に有利な状況が生まれていたのです。
総務省による制度の健全化方針
総務省は、ふるさと納税の急成長に伴って「制度が形骸化している」と危機感を強めていました。2019年には、返礼品の還元率を寄付額の3割以下とし、地場産品に限定する規制を導入しています。これは、制度が「お得なショッピング」のようになってしまうのを防ぐためでした。
しかし、ポイント制度はこれらの規制をすり抜ける存在として残ってしまいました。そのため、総務省は「寄付金の適正な活用」「地域資源の健全な発展」を重視し、2025年9月末でのポイント制度廃止を最終決定したのです。
タイミングとしての「2025年」
では、なぜ2025年9月末というタイミングだったのでしょうか。これは、自治体や寄付者に「制度変更への準備期間」を与えるためです。突然廃止してしまうと、寄付者が持っているポイントが失効するトラブルや、自治体の返礼品業者への対応が混乱するリスクがあります。
そのため、一定の猶予を設けた上で「9月末までに寄付すればポイント付与を受けられる」という形にし、円滑な移行を目指したと考えられます。
国民へのメッセージ
今回のポイント廃止は単なるルール変更ではなく、「ふるさと納税は地域応援の制度であり、消費者がお得さを追求する場ではない」という国からのメッセージでもあります。
もちろん、返礼品を楽しむこと自体は制度の魅力の一部です。しかし、「寄付はあくまで地域とのつながりを持つ行為」であることを強調し、本来の目的に立ち返ることが今回の決定に込められた狙いだといえるでしょう。
まとめ
ふるさと納税ポイント制度の廃止には、
- 過度な返礼品競争の是正
- 制度本来の趣旨への回帰
- 寄付額の偏り是正
- 総務省の健全化方針
といった複数の理由が重なっています。
この決定によって、ふるさと納税は「お得さ重視」から「地域とのつながり重視」へと大きく舵を切ろうとしています。
廃止のスケジュールと対象
ふるさと納税のポイント制度は、2025年9月末をもって廃止されることが決定しました。この日を境に、寄付者が新たにポイントを獲得することはできなくなります。すでにポイントを利用している人や、まだ残っているポイントをどう扱えばよいのか、不安を抱えている方も多いはずです。ここでは、具体的なスケジュールと対象範囲を整理し、読者が「いつまでに何をすべきか」を明確に理解できるように解説します。
廃止までのスケジュール
総務省の方針により、ふるさと納税ポイント制度は2025年9月30日をもって終了します。これは、9月末までに寄付をすればポイントを受け取れる一方で、10月以降は一切の新規付与が行われないことを意味します。
具体的な流れは以下のとおりです。
- 2025年9月30日まで
ポイント制度を導入している自治体に寄付した場合、従来どおりポイントが付与されます。 - 2025年10月1日以降
新規の寄付に対してポイントが付与されなくなり、寄付者はその場で返礼品を選ぶ通常の仕組みに一本化されます。
つまり、「今のうちに寄付をすれば最後にポイントを確保できる」ということになります。
廃止スケジュール
| 期間 | 寄付時の取り扱い | ポイント利用 |
|---|---|---|
| 〜2025年9月30日 | ポイント付与あり(従来通り) | 有効期限内で利用可能 |
| 2025年10月1日〜 | 新規ポイント付与なし | 保有分は期限まで利用可能(サイト・自治体により異なる) |
| 有効期限切れ後 | ポイント利用不可 | 自動失効 |
既存ポイントの扱い
最も気になるのは「すでに保有しているポイントはどうなるのか」という点でしょう。
総務省は廃止の発表にあわせて「既存のポイントは一定期間内に利用可能」としています。多くのポータルサイトや自治体は、寄付時に付与されたポイントは失効期限まで利用できると説明しています。
ただし、注意点もあります。
- ポータルサイトごとに有効期限が異なる
- 自治体によっては「廃止に伴い期限を早める」ケースもあり得る
- 期限内に交換しなければ自動的に失効してしまう
したがって、寄付者は「自分の持っているポイントの有効期限」を必ず確認しておく必要があります。
対象となる自治体やサイト
ポイント制度を導入しているのは一部の自治体と、その制度を提供するポータルサイトです。代表的なのは以下のようなケースです。
- 特定のポータルサイト(例:ふるなび、楽天ふるさと納税など)
ポイント制を利用できる仕組みを導入しており、寄付額に応じたポイント付与を行ってきました。 - ポイントを独自運用する自治体
自治体が自らの返礼品交換サイトを持ち、寄付金に応じた自治体オリジナルポイントを付与する方式を採用していました。
これらはいずれも、総務省の方針に従って9月末で終了となります。寄付者から見れば「どのサイトを使っても、ポイントの新規付与は受けられない」ということです。
廃止前にやっておくべきこと
9月末で終了となる以上、寄付者がやるべきことは明確です。
- 9月30日までに寄付を済ませる
今後ポイントを獲得することはできなくなるため、最後に活用するなら今がチャンスです。 - 既存ポイントの有効期限を確認する
サイトや自治体によって期限が違うため、自分が使える期間をきちんと把握しましょう。 - 返礼品交換を計画的に行う
ポイントは分割して利用できる場合が多いため、生活スタイルや季節に合わせて使い切る工夫が必要です。
廃止の影響範囲
今回の廃止は「ポイント付与」が対象であり、ふるさと納税制度全体が変わるわけではありません。つまり、以下の点は従来通りです。
- 返礼品そのものは今後も受け取れる
- 税控除の仕組み(ワンストップ特例や確定申告)は変わらない
- 自治体ごとの特色ある返礼品は引き続き利用できる
そのため、ふるさと納税が完全になくなるわけではなく、「ポイントという仕組みが廃止されるだけ」と理解するのが正しい捉え方です。
寄付者への影響
ふるさと納税のポイント制度が2025年9月末で終了することにより、最も直接的な影響を受けるのは寄付者です。これまで「お得さ」や「使い勝手の良さ」を理由にポイント制度を利用していた人は、制度廃止後に寄付スタイルを変える必要が出てきます。本章では、寄付者がどのような変化を感じるのか、メリットとデメリットを交えて整理していきます。
お得感の低下
まず、寄付者にとって大きな変化は「お得感の低下」です。
従来のポイント制度では、寄付額に応じて付与されたポイントを貯めておき、必要な時にまとめて利用することができました。たとえば、50,000円を寄付してポイントを獲得し、後から季節に合わせて高額な返礼品を選ぶといった使い方です。
しかし、ポイント制度がなくなると、寄付のタイミングでその都度返礼品を選ぶ必要があり、寄付者にとっては「自由度が狭まる」印象を受けるかもしれません。
返礼品選びの即時化
ポイント制度では「後で選ぶ」という猶予がありましたが、廃止後は寄付時に返礼品を決めなければならなくなります。
これにより、
- 「冷蔵庫がいっぱいだから後で…」という調整が効かない
- 「家族の予定に合わせて受け取りたい」といった柔軟性が失われる
といったデメリットが生じます。
一方で、即時化によって「寄付したのに返礼品を選び忘れてポイントを失効させてしまう」というリスクはなくなります。寄付と返礼品受け取りが一体化するため、ある意味ではシンプルでわかりやすい仕組みになるとも言えるでしょう。
寄付行動の変化
ポイント制度は、寄付者が「とりあえず寄付してポイントを確保し、後で使う」という行動を促していました。つまり、寄付の意思決定と返礼品選びを切り離すことができたのです。
制度廃止後は「寄付する=返礼品を決める」という一体型の行動に戻るため、寄付者はより慎重に寄付先を選ぶ必要があります。
結果として、
- 寄付の数が減り、一度の寄付額が増える
- 本当に欲しい返礼品がある自治体を選ぶ
- 応援したい地域やストーリーに共感して寄付する
といった寄付行動への変化が見込まれます。
税控除の仕組みは変わらない
ここで強調しておきたいのは、ポイント制度の廃止は「返礼品の受け取り方法」の変更にすぎず、税制優遇そのものには影響がないという点です。
ふるさと納税の最大の魅力は、寄付額から2,000円を差し引いた分が住民税や所得税から控除されるという仕組みです。この控除のルールは制度廃止後も全く変わりません。
したがって、「節税効果を得ながら地域を応援できる」という根本的なメリットは引き続き残ります。
「お得さ」から「つながり」へ
寄付者にとって最も大きな心理的変化は、制度の魅力が「お得さ」から「地域とのつながり」へとシフトする点です。
これまでは「ポイントを貯めて賢く返礼品をもらう」というスタイルが主流でしたが、廃止後は「自分が応援したい地域や魅力的な特産品を持つ自治体を選ぶ」という本来の姿に回帰します。
寄付者にとっては「お得さだけで選ぶ」ことが難しくなる代わりに、
- 自分や家族の好きな食材を扱っている自治体
- 応援したい被災地や地元にゆかりのある地域
- 環境保全や社会貢献に取り組む自治体
など、より「寄付の目的意識」を持った選び方が広がると考えられます。
廃止前に動くべき人
一方で、「どうしてもポイント制度の自由度を最後まで活用したい」という人は、2025年9月末までに駆け込みで寄付をしておくことが重要です。
特に以下のような人は、廃止前に動いた方がメリットがあります。
- まとめて寄付しておき、返礼品は少しずつ分けて受け取りたい人
- 冷蔵・冷凍庫のスペースが限られており、一度に返礼品を受け取れない人
- 高額寄付を予定しており、ポイントで後から柔軟に返礼品を選びたい人
こうした層にとっては、9月末までが「お得に寄付できる最後のチャンス」となります。
自治体への影響
ふるさと納税のポイント制度廃止は、寄付者だけでなく、寄付を集める自治体にも大きな影響を与えます。これまで「お得感」や「自由度の高さ」で寄付を集めてきた自治体は戦略を見直さざるを得ず、ふるさと納税をめぐる競争環境は大きく変化していくでしょう。本章では、自治体にとっての課題と今後の方向性を詳しく見ていきます。
寄付額の減少リスク
ポイント制度を導入していた自治体は、寄付額を集めやすい状況にありました。なぜなら、寄付者が「とりあえずポイントを確保しておこう」と寄付する心理を後押しできたからです。
しかし、制度が廃止されると「今すぐ欲しい返礼品がないから寄付を控える」といった寄付者が出てきます。結果として、短期的には寄付額が減少する自治体が出ることは避けられません。
特に、返礼品に強みがあるわけではなく、ポイント制度で集客してきた自治体ほど影響を受けやすいと考えられます。
地場産品の魅力発信が必須に
ポイント制度が廃止されることで、自治体は「自分たちの返礼品そのものの魅力」で勝負しなければならなくなります。
総務省は返礼品を「地場産品に限定」と定めています。つまり、自治体が寄付を集めるには、自地域の特産品や文化を最大限に活かした返礼品を提供する必要があるのです。
- 地元の農産物や加工品
- 伝統工芸品
- 宿泊券や体験型サービス
これらをどれだけ魅力的に発信できるかが、今後のふるさと納税競争を左右するポイントになります。
地域ブランディングの強化
これまでは「ポイントがあるから便利」という理由で選ばれていた自治体も、今後は地域そのもののブランド力が問われます。
たとえば、
- 「環境にやさしい農業に取り組んでいる」
- 「地域ぐるみで子育て支援をしている」
- 「観光と特産品を組み合わせた新しい魅力を発信している」
といったストーリーを持つ自治体は、寄付者から「応援したい」と思ってもらえる可能性が高まります。単なる返礼品競争から脱却し、地域の魅力を総合的に打ち出す「地域ブランディング」がこれまで以上に重要になるのです。
返礼品事業者への影響
ふるさと納税の返礼品は、地元の中小企業や農家、工芸事業者が担っています。ポイント制度を通じて安定的に受注していた事業者は、制度廃止後、注文の減少に直面する可能性があります。
これを避けるためには、自治体と事業者が協力して「より魅力的で差別化された返礼品」を開発することが求められます。例えば、単なる特産品の詰め合わせではなく、地域体験やSDGsに絡めた価値を提供するような取り組みがカギとなります。
自治体間競争の質的変化
これまでの自治体間競争は「いかに寄付者にお得感を感じさせるか」に偏っていました。しかし、ポイント制度が廃止されることで、その競争は「どれだけ地域の独自性を打ち出せるか」に移行します。
競争の軸が「価格・お得さ」から「価値・共感」へと変わることで、返礼品の内容やプロモーション戦略も大きく変わるでしょう。SNSや動画などを活用して「地域の魅力をストーリーで伝える」取り組みを進める自治体が増えると予想されます。
制度健全化による長期的メリット
短期的には寄付額の減少や調整コストが生じますが、長期的には制度の健全化が自治体にとってプラスに働く可能性があります。
- ポイント制度頼みの一時的な寄付から、地域を応援する継続的な寄付へ
- 地域の魅力発信が強化され、観光や移住促進にもつながる
- 地元事業者との連携が深まり、地域経済が持続的に成長できる
このように、制度廃止は自治体にとって「痛みを伴う改革」ですが、地域の本質的な力を高める契機となるのです。
今後のふるさと納税の方向性
ポイント制度の廃止は、ふるさと納税制度にとって大きな転換点です。これまで「お得さ」を武器に拡大してきた寄付市場は、今後「地域の魅力」や「共感」に基づく健全な成長へとシフトしていくことが期待されています。本章では、制度廃止後のふるさと納税がどのような方向に進んでいくのかを、返礼品のトレンドや寄付者の意識変化、自治体の取り組みという観点から整理します。
返礼品の多様化と「体験型」へのシフト
これまでの返礼品は「物(モノ)」が中心でした。お米や肉、魚介類といった食品、家電や日用品などが人気ランキングを占めてきました。しかし、今後注目されるのは「体験型」の返礼品です。
- 地元の宿泊券や温泉利用券
- 観光ツアーやアクティビティ体験
- 農業・漁業体験や工芸体験
- オンラインで楽しめる地域文化講座
こうした体験型返礼品は、単なるモノのやり取りを超えて「地域と寄付者のつながり」を感じられるものです。特に旅行需要の回復や地方創生の文脈とも相性が良く、今後拡大していくでしょう。
環境配慮・社会貢献型の返礼品
寄付者の意識変化として、環境や社会貢献への関心が高まっている点も見逃せません。ポイント制度廃止後は「お得さ」よりも「意義のある寄付」に重きを置く人が増えると予想されます。
例えば、
- 再生可能エネルギーを活用した製品
- プラスチック削減に貢献する商品
- 障がい者施設が生産した食品や工芸品
- 売上の一部が自然保護や子育て支援に回る返礼品
といった「買って応援、使って社会貢献できる返礼品」が注目されるでしょう。これにより、寄付者は地域とともに社会課題の解決に参加する意識を持ちやすくなります。
自治体間競争の新しい軸
ポイント制度がなくなることで、自治体間の競争は「還元率」から「独自性と価値」へと移ります。自治体は今後、次のような工夫で差別化を図る必要があります。
- ストーリー性のある返礼品
例:震災から復興した地域の特産品、伝統技術を守る工芸品 - 地域資源との組み合わせ
例:地元のワインと宿泊券をセットにする「観光体験パッケージ」 - ブランド化の推進
例:高品質な農産物を「地域ブランド」として全国に発信
このような施策は、一時的な寄付増だけでなく、長期的なファン作りにもつながります。
デジタル活用とプロモーションの強化
寄付者の多くはポータルサイトを通じてふるさと納税を利用しています。今後は、自治体がいかに効果的に情報発信を行えるかが寄付額を左右するでしょう。
- SNSの活用
InstagramやX(旧Twitter)で返礼品の魅力を発信 - 動画プロモーション
YouTubeやショート動画で地域のストーリーを伝える - データ分析によるターゲティング
過去の寄付者データを分析し、リピートを促す
こうしたデジタル活用は、単に返礼品を紹介するだけでなく、地域全体の魅力を発信するための重要な手段となります。
「応援消費」としての定着
ポイント制度がなくなった後、ふるさと納税は「応援消費」の形で定着していく可能性があります。応援消費とは、単なる経済的取引ではなく「その地域を支えたい」「その活動を応援したい」という気持ちで行う消費行動のことです。
- 地元にゆかりのある人が「ふるさとを支える」目的で寄付
- 災害被災地に「復興支援」の意味を込めて寄付
- 特定の政策や地域課題に共感して寄付
こうした「気持ちで選ぶ寄付」が増えることで、ふるさと納税は単なる節税対策ではなく「日本全国の地域を応援する仕組み」として本来の意義を取り戻すことになるでしょう。
長期的な展望
制度廃止後のふるさと納税には、以下のような長期的な展望が考えられます。
- 寄付者と自治体の関係が一過性から継続性へ
一度の返礼品で終わらず、リピートや定期的な寄付につながる - 地域経済への波及効果が拡大
特産品を軸に観光や移住促進へ発展 - 全国的な地域格差の是正
ポイント制度による「寄付の集中」がなくなることで、多様な地域に寄付が分散
このように、制度の健全化は自治体と寄付者の双方にとって「持続可能な関係」を築くきっかけとなります。
寄付者にとってのメリット・デメリット比較
| 項目 | ポイント制度あり | ポイント制度廃止後 |
|---|---|---|
| 自由度 | 後から返礼品を選べる、分割利用可能 | 寄付時に即決、分割不可 |
| お得感 | ポイントをまとめて高額品に使える | お得感は減少 |
| 管理の手間 | 期限管理や失効リスクあり | シンプルでわかりやすい |
| 税控除 | 変わらず利用可能 | 変わらず利用可能 |
参考資料
ふるさと納税の指定基準の見直し等(総務省)