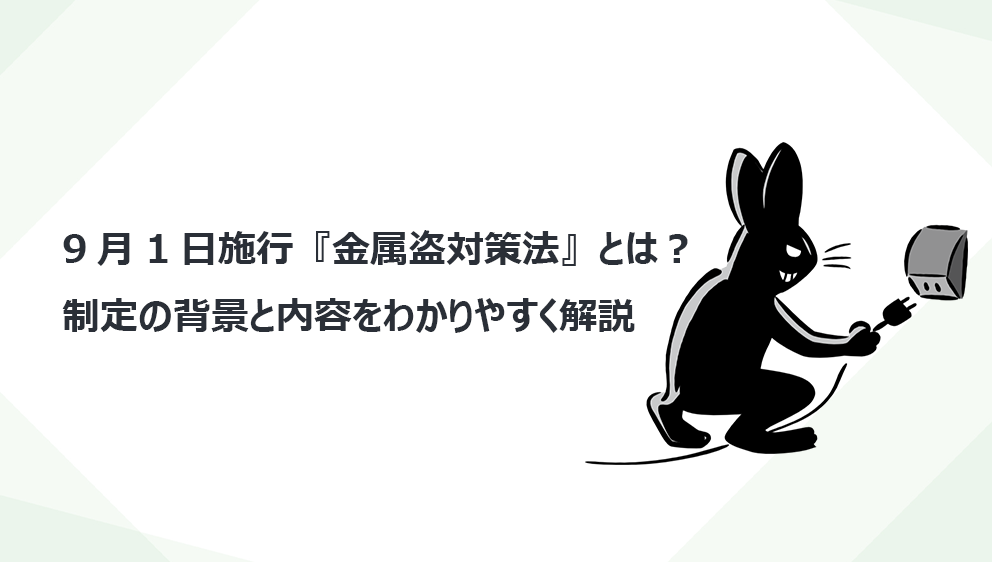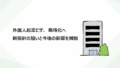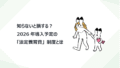電線や銅線、マンホールのふたなど、金属製品の盗難が全国で相次いでいます。こうした金属盗は、公共インフラや産業活動に深刻な影響を及ぼし、事故や停電といった二次被害につながるケースも少なくありません。こうした状況を受け、2025年9月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が施行されます。本記事では、この新しい法律が制定された経緯や具体的な内容、事業者や市民に求められる対応について、わかりやすく解説します。
金属盗難の現状と社会的影響
近年、日本各地で電線や銅線、マンホールのふたなど金属製品の盗難が相次いでいます。これらは一見すると身近な資材に過ぎないように思われますが、実際には社会生活や産業活動を支える重要なインフラ部品です。盗難が発生すると、修理費用や交換費用がかさむだけでなく、場合によっては人命に関わる重大な事故につながるおそれがあります。
代表的な被害例として挙げられるのが電線の盗難です。電力会社や鉄道会社が敷設する電線が切断・持ち去られると、広範囲の停電や列車の運行停止を招く可能性があります。実際に、電線の盗難によって地域全体が停電し、生活や経済活動に大きな支障をきたしたケースも報告されています。また、マンホールのふたが盗まれた場合、道路に大きな穴が残り、自動車や歩行者の重大事故を引き起こす危険性があります。さらに、エアコンの室外機や工事現場の資材が狙われるケースもあり、企業活動や公共事業に直接的な影響を及ぼしています。
こうした金属盗難が繰り返される背景には、銅やアルミなどの国際的な資源価格の高騰があります。盗難品が金属スクラップとして換金されることで、不正な利益を得られる構造が存在するのです。そのため、金属盗は単なる窃盗事件にとどまらず、資源の流通や治安にも悪影響を及ぼす深刻な問題と位置づけられています。
警察庁によれば、近年の金属盗被害は全国的に増加傾向にあり、自治体や業界団体からも強い危機感が示されてきました。被害に伴う修復コストは自治体の財政を圧迫し、結果的に住民サービスにも影響が及びかねません。また、復旧までの間に地域の安全が脅かされることを考えれば、金属盗難は社会全体の安心を揺るがす問題と言えるでしょう。
こうした背景を受けて、従来の窃盗罪や古物営業法による対応では限界があるとの認識が広まりました。その結果、新たに制定されたのが「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」、いわゆる「金属盗対策法」です。この法律によって、盗難品の流通経路を断ち、再犯を防止することが期待されています。
「金属盗対策法」制定の背景
金属盗難は、これまで「窃盗罪」として刑法で処罰されてきました。しかし、従来の仕組みだけでは被害を十分に防ぐことができませんでした。その理由のひとつは、盗まれた金属がすぐに「スクラップ」として市場に流通してしまい、証拠の追跡が困難になる点です。例えば、盗まれた電線や銅線は短く切断され、すぐに溶解されることもあるため、「これは盗品だ」と特定するのが非常に難しいのです。
この問題を受けて、警察庁や自治体、インフラ事業者から「抜本的な対策が必要だ」との声が強まっていました。とりわけ、公共インフラや鉄道、通信網に被害が及ぶと、市民生活全体に影響が出ることから、国会でも早期の対応が求められていました。
さらに、金属価格の国際的な高騰も背景にあります。銅やアルミといった金属資源は、国際市場で需要が増すと価格が跳ね上がり、不正取引の対象となりやすくなります。特に海外では「メタルシーフ(metal thief)」と呼ばれる犯罪が社会問題化しており、日本でも同様の被害が深刻化する可能性が高いと警鐘が鳴らされていました。
また、既存の「古物営業法」では、古物商に対して取引記録の保存や本人確認を求めていますが、金属スクラップは「古物」に含まれないケースが多く、規制が及ばないという抜け穴がありました。このため、盗品が堂々とリサイクル市場に流れ込んでしまい、犯罪を助長する構造になっていたのです。
こうした課題を受けて、政府は「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」を制定しました。狙いは大きく2つあります。
- 盗難品の流通経路を断つこと
→ 回収・処分の段階で厳格な規制を設け、盗品が市場に出回らないようにする。 - 業者に記録・確認義務を課すこと
→ 誰から、どのような金属を買い取ったのかを明確にし、不正取引を防止する。
この新法の施行によって、盗難の抑止力を高め、国民生活や社会インフラを守ることが期待されています。
法律の概要と対象となる「特定金属製物品」
2025年9月1日から施行される「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」は、盗まれた金属が不正に市場へ流れるのを防ぐことを目的としています。そのために、回収業者やリサイクル業者など、金属の取引に関わる事業者に新しいルールを課す点が大きな特徴です。
対象となる「特定金属製物品」とは
法律で規制の対象とされるのは、盗難が多く社会的影響が大きい金属製品です。具体的には以下のようなものが含まれます。
- 銅製の電線やケーブル
- アルミ製の電線やケーブル
- マンホールのふたや側溝のふた
- 鉄やステンレス製の公共インフラ部品
- その他、警察庁令で指定される金属製品
これらはいずれもインフラや公共の安全に直結するものであり、盗難が発生すると社会に甚大な影響を及ぼすため、特別に「盗難特定金属製物品」として規定されました。

新しい規制のポイント
法律の概要を整理すると、以下のような仕組みになります。
- 本人確認の徹底
金属を売却する人が事業者であっても個人であっても、買い取り時には身分証明書の提示など、本人確認が義務付けられます。 - 取引内容の記録保存
取引した日時、取引相手の氏名・住所、金属の種類や数量などを記録し、一定期間保存することが求められます。 - 報告義務
不審な取引があった場合や、盗難品と疑われる場合には、警察への報告が必要になります。 - 違反時の罰則
記録義務や本人確認を怠った事業者には、罰則が科される仕組みになっています。これにより、法の実効性を高める狙いがあります。
制度の特徴
従来の古物営業法では十分にカバーできなかった「スクラップ取引」を直接規制の対象にした点が、この法律の最大のポイントです。つまり、盗難が発生しても換金できなければ犯罪の動機は大幅に減少する、という抑止効果が期待されています。
事業者に求められる対応
「金属盗対策法」では、金属の回収や処分を行う事業者に対して、新たな義務が課されます。これは、盗まれた金属が市場に流入するのを防ぐ“最前線”としての役割を担うためです。スクラップ業者やリサイクル業者にとっては、従来の業務に加えて法的責任が強化されることになります。
主な義務内容
- 本人確認の義務
金属を売却に持ち込む人に対して、必ず本人確認を行わなければなりません。具体的には、運転免許証やマイナンバーカードなどの公的証明書の提示を受け、取引の相手が誰であるかを確実に把握する必要があります。法人からの持ち込みであっても、担当者の身元確認が求められます。 - 取引記録の作成・保存
金属の種類や数量、取引の日付、売却者の氏名・住所といった情報を詳細に記録し、一定期間保存することが義務付けられます。これにより、後に盗難品が判明した場合でも、追跡調査が可能になります。 - 不審取引の通報義務
取引の中で「通常ありえない量の持ち込み」や「説明がつかない由来の金属」など不審な点がある場合、警察への報告が必要です。これにより、早期に盗難事件の発覚・捜査につなげることができます。 - 登録・届出制度
金属の回収・処分を行う事業者は、都道府県公安委員会に登録または届出を行う必要があります。無届けでの営業は法令違反となり、行政処分や罰則の対象になります。
違反した場合の罰則
事業者が本人確認や記録保存の義務を怠った場合には、罰金刑などの罰則が科されます。これにより、業界全体に遵法意識を浸透させると同時に、違反業者の排除を通じて制度の実効性を確保する狙いがあります。
事業者が取るべき実務対応
- 新しい記録システムの導入(紙ベースからデジタル管理への移行も検討)
- 従業員への研修(本人確認の徹底や通報手順の習熟)
- 顧客への説明(新法施行後は「従来より手続きが増える」ことを丁寧に案内)
事業者にとっては負担が増える側面もありますが、その分「信頼される業者」として社会的評価を高めるチャンスでもあります。新法対応を的確に行うことで、安心・安全な資源循環の仕組みづくりに貢献できるでしょう。
市民にとっての影響と注意点
「金属盗対策法」は事業者向けの規制が中心ですが、市民にとっても無関係ではありません。家庭や地域から出る不要な金属を処分したいと考えたとき、新しいルールに基づいた手続きが必要になるからです。
不要な金属を売却する際の注意点
例えば、家庭で壊れたエアコンの室外機や古い電線をスクラップ業者に持ち込む場合、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示を求められます。これは、市民にとっては「少し手間が増える」ように感じられるかもしれませんが、盗難品の流通を防ぐために欠かせない仕組みです。
また、処分する金属の由来について質問を受ける場合があります。「どこで使っていたものか」「どのように入手したか」といった情報をきちんと説明できるようにしておくことが重要です。
安易な持ち込みのリスク
「近所で拾った金属を売る」といった安易な行動は、盗品処分に関与したと見なされるリスクがあります。意図せず法律違反に巻き込まれる可能性があるため、由来の不明な金属を持ち込まないことが市民に求められる基本的な姿勢です。
市民が協力できる防止策
金属盗難を防ぐためには、市民の協力も欠かせません。
- 公共施設や工事現場で不審者を見かけた場合は、速やかに通報する
- 自宅の金属製品(自転車・室外機・工具など)を施錠・固定する
- 地域での見守り活動に参加する
こうした日常的な取り組みが、金属盗難の抑止につながります。
市民にとってのメリット
一見すると「規制が厳しくなった」と思われがちですが、市民にとってのメリットもあります。金属盗難が減れば、停電や交通障害といった生活上のトラブルを避けられます。また、自治体や企業の修復コストが減ることで、間接的に公共サービスの安定にもつながります。
今後の課題と期待される効果
「金属盗対策法」は、盗難品の流通を断ち切ることで犯罪の抑止を図る画期的な法律です。しかし、施行後すぐにすべての問題が解決するわけではなく、いくつかの課題と改善の余地が残されています。
期待される効果
- 盗難の抑止力向上
売却時に本人確認や取引記録が必要になるため、「盗んでも換金できない」という状況を生み出し、犯行の動機を削ぐ効果が期待されます。 - 捜査の効率化
取引記録が残ることで、万が一盗難が発生しても「どこで処分されたのか」を追跡しやすくなります。これにより、犯人検挙率の向上につながります。 - インフラの保護
電線やマンホールといった公共インフラへの被害が減れば、停電や交通障害など二次被害のリスクを大幅に低減できます。市民生活の安定に直結する効果です。
残された課題
- 事業者の負担増
記録や本人確認など新たな事務作業が発生するため、特に中小のスクラップ業者にとっては業務負担が大きくなります。デジタル化やシステム導入の支援が求められるでしょう。 - 法規制の徹底度
法律の実効性は「どれだけ厳格に運用されるか」にかかっています。現場で本人確認が形骸化してしまえば、抜け道が残り、抑止効果は限定的になります。警察や行政による監督体制の強化が課題です。 - 国際的な転売ルート
国内での処分が難しくなると、海外に持ち出して不正に転売するケースも懸念されます。輸出入規制や国際的な連携も必要です。 - 市民の理解と協力
「面倒だから」と本人確認を嫌がる市民が一定数いることも予想されます。法の趣旨を広く周知し、理解と協力を得ることが不可欠です。
今後の展望
今後は、法律の施行状況を見ながら、実際の運用に即した改善が進められると考えられます。たとえば、取引記録のデジタル化を進めて効率的な管理を可能にすることや、地域ごとの被害状況に応じた重点対策を講じることが想定されます。
さらに、国際的な金属盗難の流通網に対応するため、周辺国との情報共有や規制強化も求められるでしょう。
まとめ
金属盗難は、単なる窃盗事件にとどまらず、公共インフラの安全や市民生活の安定を脅かす深刻な社会問題です。電線やマンホールのふたといった身近な金属製品が狙われることで、停電や交通障害など二次的な被害が発生し、自治体や企業にも大きな負担を与えてきました。
こうした状況を受けて、2025年9月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が施行されます。この法律では、銅線やマンホールのふたなど特定の金属製品を対象に、買い取り時の本人確認や取引記録の保存を義務付けることで、盗難品が市場に流通するのを防ぎます。事業者にとっては新たな業務負担が増える一方、透明性の高い取引が進むことで「信頼される業界づくり」にもつながります。
市民にとっても、不要な金属を売却する際には身分証の提示や由来の説明が必要になるなど影響がありますが、それは結果的に生活の安全を守るための仕組みです。不審者の通報や日常的な防犯意識の向上など、市民が協力できることも少なくありません。
法律施行によって、金属盗難は抑止され、捜査もしやすくなります。しかし、事業者の負担や国際的な不正流通といった課題も残されているため、今後の運用と改善が重要です。
「盗んでも換金できない」という社会を実現することが、この法律の最大の目的です。市民・事業者・行政が一体となって取り組むことで、安心して暮らせる社会の実現に大きく近づくでしょう。
参考情報
金属盗対策(警察庁)