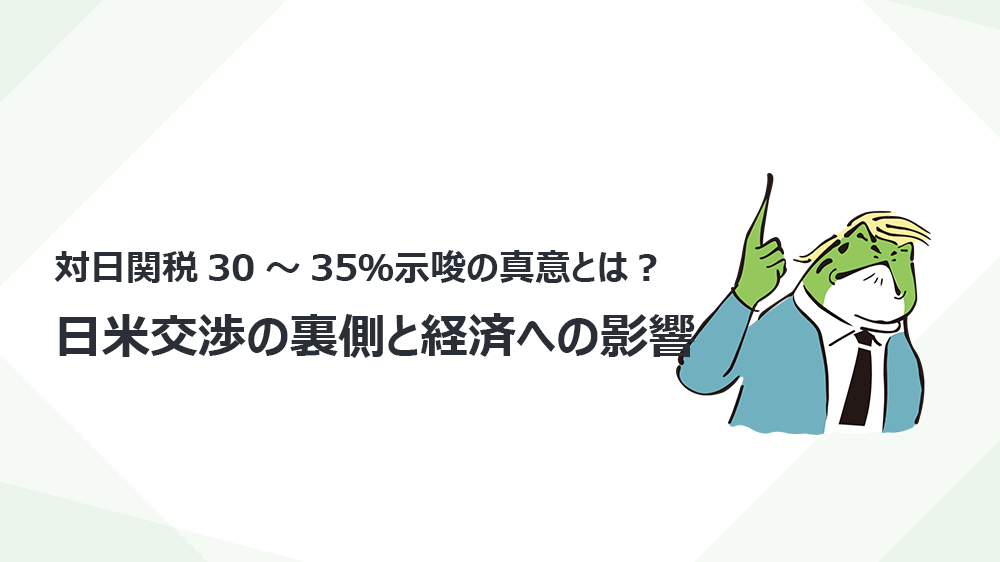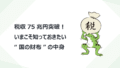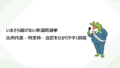アメリカのトランプ大統領が日本に対して「30〜35%の関税を課す可能性がある」と発言し、日米通商交渉に緊張が走っています。自動車やコメといった重要品目をめぐる強硬姿勢に、日本政府はどう対応しているのか。7月9日に迫る「関税一時停止」の期限、繰り返される“押し掛け外交”、経済界の反応、株価への影響──関税発言の真意と、その裏側にある駆け引きをわかりやすく解説します。
関税30~35%に言及
2025年7月1日、アメリカのトランプ大統領が再び日本に対する強い発言を行いました。大統領専用機「エアフォースワン」の機内で記者団の取材に応じ、日本との貿易交渉について「合意できるかどうか疑わしい」と述べ、なんと日本に30%から35%の関税を課す可能性があると明言したのです。この発言は、日本政府や経済界、そしてメディアに大きな波紋を広げています。
そもそも「関税」とは、外国から輸入される商品に対してかける税金のことです。たとえば、アメリカで作られた自動車を日本に持ってくるとき、日本政府が税金をかけることがあります。逆に、日本の車をアメリカで売る場合には、アメリカ政府が税金をかけることもあります。この税金が高くなればなるほど、商品は値上がりし、売れにくくなってしまいます。つまり、関税は貿易を調整するための「壁」のような役割を果たしているのです。
今回のトランプ氏の発言が注目された理由は、その数字の大きさです。現在、日本に対してアメリカが課している関税は、基本的には一律10%です。しかし、これには「相互関税」と呼ばれる追加措置があり、それを含めると最大で24%になります。それでもまだ現在は「一時停止」されている状態で、実際には10%でとどまっているのです。
ところが、トランプ大統領は「日本は非常に不公平な貿易をしている」として、「30%か35%、もしくは我々が決めた数字」に引き上げる可能性を示したのです。この発言が出たのは、「相互関税」の一時停止期限である7月9日が迫っている、まさにタイミングが重なった時期でした。
では、トランプ氏はなぜこのような発言をしたのでしょうか。その背景には、アメリカが日本との貿易で「損をしている」と感じていることがあります。とくに、大統領が何度も名指ししたのが「コメ」と「自動車」です。トランプ氏は「日本はアメリカのコメを受け入れていない」「アメリカの自動車も買わない」として、日本側の姿勢に強い不満を抱いています。
実際、トランプ氏は次のような言葉を残しています。「日本は非常に手ごわい。日本との合意は難しい。彼らは甘やかされてきた」。このような言い方には、日本がこれまで優遇されていたという不満と、それを正したいという強い意志がにじみ出ています。
ここで重要なのは、今回の発言が「交渉カード」として使われている可能性もあるという点です。つまり、あえて大きな数字を示すことで、日本側にプレッシャーをかけて、より有利な条件を引き出そうとしているわけです。これはビジネス交渉や国際政治ではよくある手法で、「脅しておいて、少しマシな条件を提示する」という流れに持ち込む狙いがあるともいえます。
しかし、このような高圧的な姿勢は、日本側にとっても大きな問題です。とくに、自動車産業は日本経済の柱の一つです。もし、アメリカが本当に30%や35%といった関税をかければ、日本の自動車メーカーはアメリカ市場での価格競争力を一気に失うことになります。それだけでなく、日本経済全体への影響も大きく、株式市場ではトランプ氏の発言直後に日経平均株価が500円以上下がるという事態も起こりました。
このような状況の中、日本政府は冷静に対応する姿勢を見せています。青木官房副長官は「トランプ大統領の発言は承知しているが、個々の発言にコメントすることは差し控えたい」と述べつつ、「日米双方の利益になる合意を目指し、誠実に協議を続けていく」と発言しました。
また、日本商工会議所の小林会頭も「トランプ大統領の一言一言に過敏に反応してはいけない」と語り、冷静な姿勢を求めています。「今までも、彼の発言がそのまま実現したとは限らない」との指摘には、これまでの経験から来る慎重さがにじみ出ています。
一方で、日本製鉄の橋本会長は「アメリカは製造業、特に自動車に焦点を当てすぎている」と指摘しました。これは、アメリカ側が自動車だけに注目しすぎて、交渉全体のバランスを欠いているという批判とも受け取れます。橋本会長はまた、トランプ政権の「製造業復活」の方針には理解を示し、日本としても協力していく姿勢を見せました。
まとめると、今回のトランプ大統領の発言は、関税引き上げという「爆弾カード」を使って日本にプレッシャーをかけるものであり、実際に発動されるかどうかはまだ不明です。しかし、その影響はすでに経済や政治に現れており、日本政府や企業は今後の交渉の行方に大きな関心を寄せています。
関税の仕組みと「相互関税」問題の背景
トランプ大統領が示唆した「30%〜35%の関税」という数字は、驚くほど高いものです。ですが、そもそも関税とはどういうしくみで決められていて、なぜ「相互関税」などという言葉が出てくるのでしょうか?この章では、ニュースだけではなかなか見えてこない「背景」をわかりやすく解説していきます。
関税ってそもそも何?
関税とは、外国から商品が入ってくるときにかけられる税金のことです。たとえばアメリカから日本にオレンジが届くと、税関で「じゃあこのオレンジには〇〇円の税金が必要です」といった具合にお金が取られます。その分、商品は高くなります。逆に、日本からアメリカに車を送ったときも、アメリカ側が関税をかければ、現地での値段は高くなります。
このように関税には大きく2つの役割があります。
- 国内産業を守る:安い外国製品に対して税金をかけることで、国内の農家や工場を守る。
- 交渉のカードになる:他国との貿易で「言うことを聞かないなら関税を上げるぞ」と交渉に使える。
トランプ大統領がまさにこの「交渉カード」として関税を使おうとしているのが、今回の問題の根本にあります。
「基本関税」と「上乗せ関税」
今回、ニュースでは「現在10%、上乗せすると24%」という数字がよく出てきます。これはどういうことなのでしょうか?
図で整理してみましょう。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 基本関税(10%) | アメリカが日本に一律でかけている通常の関税。今も有効。 |
| 上乗せ関税(+14%) | トランプ政権が2025年4月に発表。現在は90日間の一時停止中。 |
| 合計(最大24%) | 上乗せが解除された場合の関税の最大値。 |
この「上乗せ関税」が、7月9日まで一時的に止められている状態です。トランプ大統領はこの一時停止を延長しないと宣言しました。つまり、もし本当に延長されなければ、10%だった関税が一気に24%に跳ね上がることになります。これは、自動車などの輸出品にとって非常に大きな痛手です。
そして、ここで出てくるのが「相互関税(reciprocal tariff)」というキーワードです。
相互関税とは何か?
相互関税というのは、簡単に言うと「相手の国がうちの商品に〇%の関税をかけているなら、こっちも同じだけかけてやる!」という考え方です。
たとえば、もし日本がアメリカの牛肉に20%の関税をかけているなら、アメリカも日本の牛肉に20%の関税をかけ返す、というイメージです。これが「対等・公平な貿易」だというのが、トランプ政権の主張です。
トランプ大統領は、長年アメリカが日本やヨーロッパなどに「甘すぎた」と考えています。たとえば、日本ではアメリカの自動車がほとんど売れていませんが、それは税金や規制があるからだと主張し、その不公平を関税で調整しようとしています。
しかし、この「相互主義」には問題もあります。
- 各国の事情(産業保護、食料安全保障)が無視される
- WTO(世界貿易機関)のルールに違反する可能性がある
- 報復関税合戦になって、世界的な貿易戦争になる恐れがある
つまり、トランプ氏の関税戦略は、正義のように見えて実は国際社会ではかなり強引な手法とされています。
なぜ今「7月9日」がカギになるのか?
では、なぜ今回、7月9日という日付がここまで注目されているのでしょうか。
それは、2025年4月にアメリカ政府が発表した「上乗せ関税」が、90日間だけ一時停止されるという措置を取ったからです。そして、その90日目が7月9日です。この日までに日本とアメリカが「関税を上げないための合意」にたどり着かなければ、関税は自動的に最大24%に戻ってしまうことになります。
さらに、トランプ大統領は7月1日の発言で「もう猶予は考えていない」「日本との合意はできないかもしれない」とまで言い切っています。これは、日本に対して「早く譲歩しろ」という強烈な圧力です。
もし本当に24%になり、さらに30〜35%まで関税が上がれば、自動車や電機などの日本の主力産業は大打撃を受けることになります。
日本はどう対応しているのか?
このようなトランプ氏の姿勢に対して、日本政府は慎重に、しかし冷静に対応しています。
青木官房副長官は記者会見で、「アメリカ側の発言についてはコメントを控える」としつつも、「真摯かつ誠実に協議を進める」と語りました。あくまで感情的に反応せず、交渉のテーブルに立ち続ける姿勢を見せています。
また、商工会議所や経済団体も「過敏に反応すべきでない」と冷静な対応を呼びかけています。一方で、企業への影響が大きくなった場合には、国として中小企業への支援を最大限行うと表明しており、事態を静観しつつも備えを進めているのが現状です。
赤沢大臣の「押し掛け外交」と成果の乏しさ
今回の関税問題において、日本政府はアメリカと何もせずに黙っていたわけではありません。むしろ、日本はこの数カ月、必死にアメリカとの交渉を続けてきました。その中心にいるのが、赤沢亮正(あかざわ・りょうせい)経済再生担当大臣です。
彼は、関税引き上げを回避するために、今年4月からアメリカを7回も訪れ、現地の高官たちと交渉を重ねてきました。このような頻繁な訪問と交渉姿勢は、メディアから「押し掛け外交」と呼ばれています。
なぜ「押し掛け」なのか?
通常、外交交渉というのは、事前に相手国と日時を調整し、正式な形で会談を行うのが基本です。しかし赤沢大臣の場合、アメリカへ出発する時点ではまだ交渉相手と日程が決まっていないことが多く、飛び込みに近い形で現地入りしています。
赤沢氏自身も「押し掛け外交」であることを認めており、「羽田を出るときは会談の予定はないが、現地に着けば必ず相手には会えている。だから成功率100%です」と記者団に語っています。このような柔軟かつ粘り強い姿勢は評価される一方で、事前に約束が取れていない交渉には限界があるのも事実です。
7回の訪米、その成果は?
赤沢大臣は、6月末にもアメリカ・ワシントンを訪れ、通算7回目となる交渉を行いました。今回も、アメリカのラトニック商務長官などと対面および電話で複数回協議を行いましたが、期待されていたベッセント財務長官との会談は実現しませんでした。
しかも、協議の結果として発表されたのは「事務レベルでの継続的な協議を確認した」という、いわば“確認にとどまった”程度の内容です。これでは、7月9日の関税引き上げ回避に向けた「成果」とは言えず、むしろ交渉は行き詰まりを見せているという印象が強まっています。
トランプ氏の態度が急変?
4月に初めて赤沢大臣が渡米した際には、トランプ大統領本人が赤沢氏と写真撮影に応じ、「日米交渉は大きな進展があった」とSNSに投稿するなど、関係は順調に見えました。実際、このときは「早期の合意もあるのでは?」という見方が広がりました。
しかし2回目以降、交渉は次第に停滞。赤沢氏は毎回、「前進」「進展」「さらに進展」など前向きな表現を使って成果をアピールしてきましたが、肝心の関税問題については実質的な解決策が見えてきません。そうしている間に、トランプ氏の発言はどんどん強硬になっていったのです。
「日本は米国産のコメも車も買わない。そんな不公平な時代は終わった」
「30%か35%の関税を課す書簡を日本に送る」
こうした発言が相次いだことで、日本政府は再び厳しい交渉の局面に立たされることになりました。
なぜ成果が見えないのか?
交渉が進まない理由は複数ありますが、主に次のような点が挙げられます。
- アメリカ側が「譲歩しない姿勢」を貫いている
ベッセント財務長官は「不公平な取引は受け入れないようトランプ大統領に言われている」と発言しており、譲歩する余地が小さい状況です。 - 日本側の「守りの交渉」が強い
日本はコメや自動車といった重要産業を守ることを最優先しているため、アメリカが求める「市場開放」には簡単に応じられない構造的な問題があります。 - 国内政治の影響もある
日本はまもなく参議院選挙を控えており、農業団体などの票田を抱える政府としては、大きな譲歩は避けたいという政治的事情もあります。
交渉失敗は政権への打撃?
このまま交渉が不調に終わり、関税が実際に30〜35%へ引き上げられれば、日本経済への影響は大きく、与党政権にとっても大きなダメージとなります。とくに今回の交渉は「経済安全保障」と「対米関係」の象徴として注目されており、単なる貿易問題ではありません。
政策シンクタンク「アジア・グループ」の西村凜太郎氏は、「日本はアメリカの期待と、国内世論(譲歩しすぎるなという声)の板挟みになっている」と指摘しています。この言葉は、まさに今の赤沢大臣と石破政権の置かれている立場をよく表しています。
日本側の反応と各界の温度差
トランプ大統領が日本に対して30~35%の関税を課す可能性を示唆したことで、日本国内には大きな波紋が広がっています。しかし、政府や経済界、そして一部の専門家たちの反応を見てみると、その温度差が目立ちます。この章では、日本側がどう反応しているのか、それぞれの立場からの考え方を整理してみましょう。
政府:冷静さを強調、「真摯に協議を続ける」
日本政府は、アメリカ側の強硬な発言に対して、あくまで冷静な対応をとっています。青木一彦官房副長官は記者会見で「トランプ大統領の発言は承知している」としつつも、「一つ一つの発言にコメントすることは差し控える」と述べ、落ち着いた姿勢を示しました。
ただし、そのまま放置するわけではありません。「日米双方の利益となる合意を目指し、誠実に交渉を続けていく」という基本方針は堅持しており、交渉継続の意思ははっきり示しています。
このような姿勢は、過剰に反応してアメリカに「焦っている」と思われないための戦略とも言えるでしょう。外交の場では、冷静な対応が信頼を生むこともあるのです。
経済団体:過敏に反応しすぎるな
経済界の代表的な団体である「日本商工会議所」も、政府と同様に冷静な対応を求めています。小林健(こばやし・たけし)会頭は、7月2日の記者会見で次のように語りました。
「トランプ大統領のひと言ひと言に過敏に反応しても仕方がない。過去を見ても、彼の発言がそのまま実現したわけではない。過敏になれば相手の思うつぼだ。冷静に対応すべきだ」
この発言からもわかるように、経済界は「発言の真意」を見極めつつ、冷静な判断を心がけているのです。ただし、「冷静=何もしない」ではありません。
同じ会見で小林会頭はこうも述べています。
「関税が高くなれば企業への影響は当然大きい。中小企業が困るような結果になれば、政府と連携して最大限の支援を行う」
つまり、「今はまだ反応しすぎない。でも、実際に影響が出てきたらすぐに動く」という姿勢です。
産業界:不満と不安が入り混じる
一方、実際にアメリカとの貿易に大きく関わっている企業のトップたちは、より現実的な不安を抱いています。
たとえば、日本製鉄の橋本英二(はしもと・えいじ)会長は、トランプ大統領の発言を受けてこう語っています。
「アメリカ政府は製造業、特に自動車に重点を置きすぎている。焦点が偏っているのではないか」
橋本会長は、日本製鉄がアメリカの大手鉄鋼メーカー「USスチール」を買収したことにも触れ、「製造業の連携はアメリカの国益にもなる」と述べました。つまり、日本企業によるアメリカへの投資も含めて、もっと広い視野で交渉を見てほしいというメッセージです。
これは、産業界として「単なる関税の話」で終わらせたくない、という願いが込められています。
一部の専門家:日本の戦略に疑問の声も
さらに、政策の専門家たちの中には、日本側の交渉スタンスに疑問を投げかける声も出ています。
政策研究大学院大学の川崎研一教授は、トランプ氏の「コメの関税は700%」という発言について「事実ではない」としたうえで、日本政府がそれにいちいち屈しない姿勢を見せていることは評価できると述べました。
一方で、日本政府がよく使う「対米投資」や「フレンドリーな戦略」に対しては、「どこまで効果があるのか疑わしい」として、根拠の薄い戦略に頼りすぎていないかを指摘しています。
このように、専門家の間でも「冷静さは必要だが、戦略は再点検すべき」という声が上がっているのです。
政治的な影響は?
忘れてはならないのが、日本ではまもなく参議院選挙が行われるというタイミングです。つまり、関税交渉の結果が政権支持率にも大きな影響を与えかねません。
とくに農業団体や自動車業界など、強い業界団体からの支持を受けている政治家にとって、今回の関税問題は非常にデリケートです。譲歩すれば「国益を売った」と批判される可能性があり、強く出すぎれば交渉が決裂しかねない。まさに「板挟み」の状態にあるといえます。
また、トランプ氏はインドとの通商合意に関しては「楽観的」な見方を示しており、日本との比較としてますます立場が悪くなることも懸念されています。
こうしたさまざまな反応を見てわかるように、政府・経済界・産業界・専門家で温度差があるのは事実です。ただし、共通しているのは「冷静に対処すべき」「影響があれば動く」という姿勢です。問題は、この「冷静さ」がどこまで有効に働くか、そして7月9日までに具体的な成果が得られるかという点にかかっています。
経済と政治への影響:株価・世論・参院選
トランプ大統領による関税引き上げの示唆は、単なる外交交渉の一幕では終わりませんでした。その影響は、経済や株式市場、そして日本の政界にまで広がっています。「30~35%関税」という発言が、どのようにして日本経済と政治に動揺をもたらしているのかを詳しく見ていきます。
日経平均、一時500円超の下落
トランプ大統領が7月1日に「関税引き上げ」を言及した直後、日本の株式市場は敏感に反応しました。7月2日午前の東京株式市場では、日経平均株価が一時500円を超える下落を記録。これは、投資家たちがトランプ発言を「本気」と捉え、日本の輸出産業に悪影響が出ることを恐れたからです。
特に売りが集中したのは、以下のような「輸出依存度の高い」業種でした。
- 自動車(トヨタ、ホンダ、日産など)
- 電機(ソニー、パナソニック、シャープなど)
- 機械(コマツ、日立建機など)
これらの企業は、アメリカ市場が大きな販売先となっており、関税が引き上げられれば「価格競争力」を一気に失います。たとえば、今まで300万円で売れていた日本車が、関税によって390万円になってしまえば、アメリカの消費者は買い控える可能性が高くなります。
その結果、売上が落ち込み、業績が悪化するという「連鎖反応」が起こると考えられたのです。
為替市場も反応:円高進行
加えて、外国為替市場でも円が買われる動きが強まりました。トランプ発言の直後、円はドルに対して堅調に推移し、他の主要通貨に対しても強い動きを見せました。
一般に、政治や経済に不安があると「安全資産」とされる円が買われる傾向があります。今回は「日米関係の先行きが不透明になった」ことがその引き金となりました。
ただし、円高が進むと輸出企業にはマイナスの影響が出ます。円の価値が上がるということは、同じ100ドルの商品を売っても、日本円に換算したときの金額が減ってしまうからです。
中小企業・地方経済にも影響の波
大企業だけでなく、地方の中小企業もこの問題の影響を受ける可能性があります。
たとえば、地元で部品を製造し、大手自動車メーカーに納入している企業があるとします。もしその自動車がアメリカで売れなくなれば、大手メーカーは生産量を減らすかもしれません。その結果、中小企業への発注も減り、売上が落ち込むことになります。
こうした「下請けの下請け」まで連鎖的に影響が及ぶのが、関税問題の怖さです。特に自動車関連の部品や金型産業が集積している東海地方や九州の中小企業には、懸念が広がっています。
政権への影響:参院選を前に揺れる判断
もうひとつ見逃せないのが、政治への影響です。日本では、7月20日に参議院選挙の投票が予定されています。石破政権にとって、このタイミングで「外交交渉に失敗し、経済が混乱した」と見られることは、大きなリスクです。
有権者は経済状況に敏感です。たとえば、物価が上がったり、企業が倒産したり、ボーナスが減ったりすれば、政府に対する不満が高まり、選挙で「お灸を据える」動きが出てきます。
とくに、農業団体や地方の中小企業を支持基盤とする与党議員たちは、「日本がアメリカに譲歩しすぎて、国益を損なっているのでは」と懸念する声を強めています。そのため、石破政権は「経済を守りつつ、外交で妥協しすぎない」という難しいバランスを迫られています。
世論の反応:SNSでは不満と不安
SNSやニュースコメント欄でも、多くの国民が今回の関税問題に関心を寄せています。「またトランプに振り回されるのか」「日本政府はちゃんと交渉できているのか」「アメリカにばかり配慮していないか」など、不安や怒りの声も少なくありません。
一方で、「過剰に反応するべきではない」「トランプの発言は交渉術だ」と冷静な意見も一定数あります。
世論が二極化している中で、政府の対応ひとつで政権支持率が大きく変動する可能性もあるため、慎重な舵取りが求められているのです。
このように、関税引き上げの問題は、日本経済に直撃するだけでなく、政治や世論、企業活動にまで幅広い影響を与えています。いまや単なる「外交交渉」ではなく、国家の命運を左右する局面に差し掛かっているのです。
日米貿易協定の内容と関税措置の関係
ここまで、トランプ大統領の発言や関税の仕組み、日本政府の対応や経済的影響などを見てきました。では、そもそも日本とアメリカは「貿易協定」を結んでいるのに、なぜまた関税問題が起きているのでしょうか?この章では、2019年に結ばれた「日米貿易協定」と現在の関税問題の関係についてわかりやすく説明します。
そもそも「日米貿易協定」とは?
2017年にアメリカがTPP(環太平洋パートナーシップ協定)から離脱したことで、日本との貿易ルールが宙ぶらりんになってしまいました。そこで、2019年に日本とアメリカは新たな2国間の貿易ルールとして「日米貿易協定(US-Japan Trade Agreement)」を結びました。
この協定は、いわば“TPPの代わり”としてスタートしたもので、内容は以下のようなものでした。
| 分野 | 日本の譲歩 | アメリカの譲歩 |
|---|---|---|
| 農産品 | 牛肉や豚肉、チーズなどの関税を段階的に引き下げる | 特になし |
| 工業製品 | 現状維持(関税なし) | 工業製品の一部で関税を撤廃 |
| 自動車関税 | 将来の協議課題として継続 | 維持(2.5%関税)だが「追加関税は避ける」と明記 |
ここで注目すべきは、「自動車」の扱いです。日本は自動車分野で大きな譲歩をしておらず、アメリカは現状の2.5%の関税を維持しながら、「今後の交渉課題」として継続するという形にとどまりました。
つまり、当時の交渉では「とりあえず今は関税を上げないけれど、これから話し合いを続けよう」という“先送り”の内容だったのです。
なぜ今また問題になっているのか?
今回の関税問題は、この「先送りされた宿題」が再び表に出てきた形です。トランプ大統領は「日米貿易は不公平だ」として、自動車・農産品分野での譲歩が足りないと感じているのです。
とくに、以下の2点が今回の強硬発言の根拠になっていると考えられます。
- 日本がアメリカのコメを受け入れない(輸入しない)
- 日本車がアメリカ市場で強く、米国製の車が日本で売れない
トランプ氏にとっては、2019年の協定が「片方にだけ得な内容」だったように見えるのでしょう。そのため、「もう一度交渉して、公平な形にしよう。できないなら関税を上げるぞ」と迫っているのです。
トランプ氏は本当に協定を破るのか?
通常、国際的な貿易協定には「約束は守ろうね」というルール(=信頼性)が存在します。国家間の約束を一方的に破れば、「あの国は信用できない」と見なされ、他の国との関係も悪くなりかねません。
しかし、トランプ大統領は過去にもこうした「協定見直し」や「一方的な関税発動」をたびたび行ってきました。たとえば、
- カナダやメキシコとのNAFTAを見直し(USMCAに)
- 中国に対して数千億ドル規模の関税を発動
- 欧州にも鉄鋼・アルミ関税をかける
このような実績から見ても、「約束を破る可能性はゼロではない」というのが、国際社会の現実的な見方です。
日米貿易協定は今どうなっている?
実は、2019年の協定は「物品貿易」が中心で、「デジタル経済」や「サービス貿易」などはほとんど扱われていません。つまり、現在の日米経済の実態に対して、やや“古くなっている”とも言えるのです。
日本としては、「すでに十分に譲歩した」「これ以上の関税引き下げは難しい」という立場ですが、アメリカ側は「まだ不十分」と見ています。こうして、「どこまで譲るか」「どこで踏みとどまるか」という綱引きが続いているのです。
協定は守るべきか、見直すべきか
この問題には2つの見方があります。
A. 協定は守るべき(日本側の主張)
- 国家間の約束を破れば国際的信用を失う
- 一方的に関税を上げるのはWTO(世界貿易機関)違反の可能性も
- 日本はすでに農業などで譲歩しており、これ以上の譲歩は国益を損なう
B. 協定は見直すべき(アメリカ側の主張)
- アメリカの農業・自動車産業はまだ不利な条件に置かれている
- 公平な貿易には「結果としての平等」も必要
- 協定が古くなっているので、今の経済実態に合わせて再交渉すべき
どちらにも一理ありますが、重要なのは「一方的に決める」のではなく、交渉でバランスをとることです。そのため、日本政府は一貫して「誠実に協議を続ける」としており、協定を守りながらも、実情に応じた対応を探っている最中です。