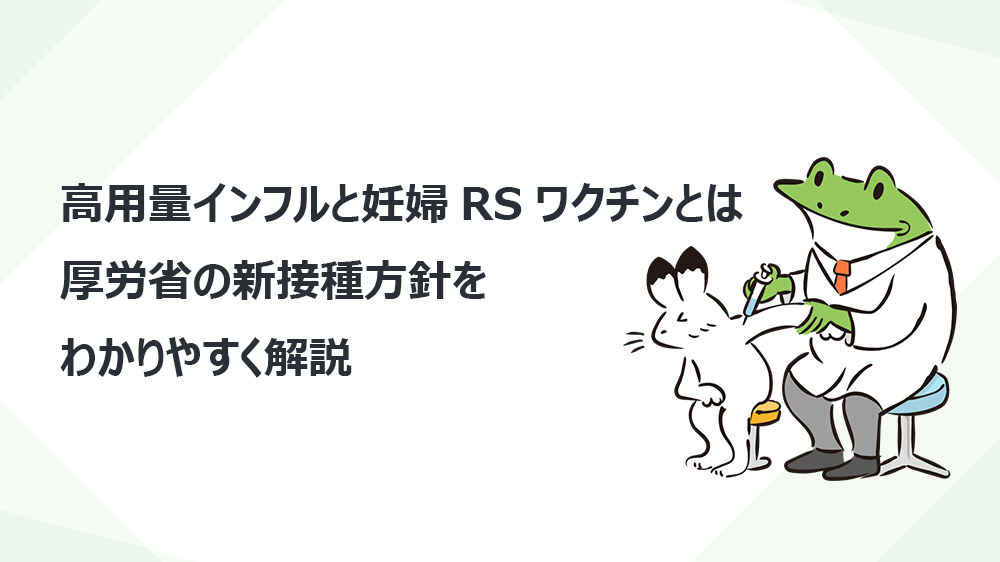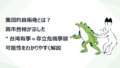厚生労働省は2024年10月に開催された専門部会において、高齢者向けの「高用量インフルエンザワクチン」と、妊婦を対象とした「RSウイルスワクチン」の2つについて技術的な評価をまとめました。これらはいずれも、今後の日本の予防接種制度の見直しに大きく関わる重要なテーマです。
インフルエンザは高齢者が感染すると重症化や入院に至るリスクが高く、社会全体の医療負担も大きくなるため、より効果的な予防策の確立が求められてきました。一方、RSウイルスは乳児の呼吸器感染症として知られ、とくに1歳未満では入院が必要になるほど重症化するケースが多く、公衆衛生上の課題となっています。妊婦にワクチンを接種することで、胎児に抗体を移行させ、生まれる直後から赤ちゃんを守る「母子免疫」という考え方が注目されています。
今回の専門部会で示された評価は、これら2つの疾患への予防手段を制度としてどのように取り入れていくかを決めるための基盤となるものです。ニュースでは、とくに「妊婦向けRSウイルスワクチンが2026年4月にも定期接種化される可能性」が大きく報じられ、社会的な関心が高まっています。
本記事では、厚労省の審議資料をもとに、両ワクチンが評価された背景や期待される効果、安全性、今後の導入スケジュールなどをわかりやすく整理して解説していきます。
高用量インフルエンザワクチンとは
高用量インフルエンザワクチンは、これまで日本で使用されてきた標準量ワクチンの4倍の抗原量を含むワクチンで、より強い免疫応答を誘導するよう設計されています。厚労省の専門部会がまとめた資料でも、高齢者の重症化を抑えるための有力な選択肢として注目されており、その効果や安全性について詳細な評価が示されています。
まず理解しておきたいのは、インフルエンザが高齢者にとって非常に負担の大きい疾患であるという点です。高齢になるほど免疫機能が低下し、感染後に肺炎や心不全などの合併症を引き起こしやすくなります。その結果、入院リスクや死亡率が大きく上昇するため、より強力な予防策の確立が長年の課題となってきました。
その課題に応える形で登場したのが高用量インフルエンザワクチンです。専門部会のまとめによると、このワクチンは標準量よりも高い免疫原性を示し、発症予防効果や入院予防効果のいずれにおいても標準量を上回る結果が確認されています。特に興味深い点として、年齢が高くなるほど相対的な有効性が高まるという報告が示されており、80代以上などの超高齢層での導入効果がより期待されると評価されています。
一方、安全性についても慎重な検証が行われました。高用量であることから局所反応(注射部位の痛みや腫れ)や筋肉痛、発熱といった全身症状が出る頻度は標準量よりやや高くなりますが、多くは軽度から中等度で短期間で消失するものであり、重篤な有害事象の頻度は標準量と同程度と整理されています。「重大な懸念は認められない」という評価は、定期接種として導入するうえで非常に重要なポイントです。
費用対効果も大きな焦点でした。仮に1回の接種価格を5,000円程度とした場合、65歳以上全体を対象にしても費用対効果は良好とされています。ただし、より効率的な導入を検討した場合、75歳以上を優先するケースが最も費用対効果に優れるという分析も示されています。このため、今後の制度検討では、対象年齢の設定をどうするかが重要な論点となります。
専門部会のまとめでは、技術的な評価は一定の結論に達しているものの、接種対象年齢や自治体での運用、ワクチンの安定供給、国内生産体制の維持など、制度として導入する際の実務的な課題については今後も審議が必要であるとされています。高齢化が進む中で、高用量インフルエンザワクチンは重症化予防の強化策として大きな役割を果たす可能性があり、今後の検討に注目が集まります。
妊婦向けRSウイルスワクチンとは
RSウイルスは乳児の呼吸器感染症として広く知られ、とくに生後1歳未満では重症化しやすい特徴があります。日本でも毎年多くの乳児が入院し、医療負荷が高まる時期が続いてきました。厚労省の専門部会がまとめた資料でも、1歳未満の乳児における疾病負荷が非常に高いことが明確に示されています。
こうした背景のもと、近年注目されているのが「母子免疫ワクチン」という考え方です。これは、妊婦がワクチンを接種することで体内に産生された抗体を胎盤を通じて胎児に移行させ、生後すぐの赤ちゃんを感染から守るという仕組みです。RSウイルスのように、生後早期から重症化リスクが高いウイルスに対しては、非常に理にかなった予防手段といえます。
専門部会の資料では、妊娠28週から36週の間に接種することで最も高い有効性が期待できると整理されています。これは、胎盤を通じた抗体移行が活発になる時期と、ワクチン接種によって母体内の抗体価が上昇するタイミングが最も合致しやすいためです。実際、海外の研究でもこの時期の接種が乳児の重症化予防に最も効果的であるとの報告が多く見られます。
安全性については、妊婦という対象特性から慎重な評価が行われました。専門部会のまとめによると、接種部位の痛みや軽度の筋肉痛などはみられるものの、早産や低出生体重児の発生率は対照群と同等で、重大な安全性の懸念は認められていません。ただし、臨床試験で妊娠高血圧症候群のリスクがわずかに高まる傾向が示されたため、日本で導入する際には、リアルワールドデータを継続的にモニタリングする必要があるとされています。
費用対効果も検討されており、母子免疫ワクチンの導入は非接種と比べて良好な費用対効果が期待できる結果となっています。これは、乳児の入院率の高さを考えると、医療費や社会的負担を抑える効果が大きいことを意味します。
専門部会が示した最も重要なポイントの一つは、母子免疫ワクチンを定期接種として導入することが妥当だと結論づけた点です。ニュースでは「2026年4月にも妊婦の定期接種が始まる可能性」と報じられており、今回の技術的評価が制度化に向けた基礎資料となっています。
また、再接種(複数回の妊娠で再び接種する場合)については、妊婦を対象とした臨床的な有効性データが現時点で十分ではないものの、健康成人では抗体価がしっかり上昇しているため、制度設計の中で慎重に取り扱うべき課題とされています。今後もデータ収集が進むことで、より明確な接種指針が示される可能性があります。
このように、妊婦向けRSウイルスワクチンは乳児の重症化を防ぐための重要な予防手段として、定期接種化に向けた議論が大きく前進しています。出生直後の赤ちゃんを守る「生まれる前のワクチン接種」という新しい発想は、今後日本の予防接種制度の大きな柱となることが期待されています。
乳児への抗体製剤との違い
RSウイルス感染症への予防策として、妊婦へのワクチン接種と並んで検討されているのが、乳児に直接投与する「抗体製剤」です。これは赤ちゃん自身に防御抗体を与える方法で、すでに海外で広く使用され、日本でも一部の高リスク児では導入が進んでいます。厚労省の専門部会資料(PDF2)でも、抗体製剤の有効性や安全性が詳細に整理されており、母子免疫ワクチンとの比較が重要な論点となっています。
まず有効性については、抗体製剤は乳児に対して非常に高い予防効果を示すことが確認されています。生後すぐから免疫が十分に働くため、日常生活での感染リスクが高い乳児には有効な手段となります。また、安全性も高く、重大な副反応は報告されていません。こうした点を踏まえると、乳児自身の防御力を直接高めるという意味で、抗体製剤は確かな有効性を持つ予防手段だといえます。
一方で課題となるのが費用対効果です。専門部会の分析では、抗体製剤を定期接種として広く導入した場合、
費用対効果が一般的に重視される基準値(500~600万円/QALY)を大きく上回るという結果が示されています。
これは、高い予防効果を持ちながらも、製剤価格が高額であることが要因となっており、定期接種化を判断するうえで慎重な姿勢が求められる部分です。
この点で、妊婦向けRSウイルスワクチンによる「母子免疫」は、費用対効果が良好と評価されているため、より効率的に幅広い乳児を守る手段として期待されています。妊婦への1回の接種で、生まれる赤ちゃん全体を守ることができるため、制度全体の負荷も軽減しやすいという強みがあります。
ただし、抗体製剤が不要になるわけではありません。RSウイルスは地域や年度によって流行時期が異なるため、母子免疫だけではカバーしきれないケースが生じることが予想されます。とくに、早生まれの乳児や、母子免疫ワクチンの接種時期に母親が妊娠していなかった場合などには、抗体製剤による補完が重要になります。専門部会資料でも、流行期の定義や接種適期の見極めについて、引き続き検討が必要であるとされています。
また、日本特有の課題として、流行期の変動の大きさが挙げられます。新型コロナウイルスの流行以降、RSウイルスの流行時期が前倒しになったり大幅に遅れたりと、従来の季節パターンが崩れています。こうした状況では、乳児にどのタイミングで抗体製剤を投与するべきなのか、地域ごとに柔軟な判断が求められる可能性があります。
総合すると、母子免疫ワクチンと抗体製剤はどちらか一方ではなく、状況に応じて併用し得る二つの手段として位置付けられます。費用対効果の観点では母子免疫が優れていますが、乳児の個別状況や地域の流行状況によっては抗体製剤が重要な役割を果たします。制度化にあたっては、両者の特性を生かした柔軟な仕組みづくりが不可欠だといえます。
2026年度以降の導入スケジュールと今後の見通し
厚生労働省がまとめた技術的評価や各種報道を踏まえると、妊婦向けRSウイルスワクチンと高用量インフルエンザワクチンは、それぞれ異なるタイミングで制度導入が進む見通しです。特にRSウイルスワクチンについては、時期が具体化しつつあり、一般の妊婦や医療機関にとっても関心が高まっています。
まず、最も進展が明確なのは妊婦向けRSウイルスワクチンです。ニュース報道では、厚労省が2026年4月にも定期接種として導入する方向で調整していると伝えられています。これは、専門部会の資料(PDF2)で、妊娠28週〜36週で接種することが妥当であり、乳児の重症化予防に高い効果が期待できるという評価が固まったことが背景にあります。
また、海外における実績や安全性データが蓄積されてきたことも、日本での導入を後押ししています。定期接種化されれば、妊婦が公費負担で接種できるようになり、社会全体として予防可能な入院や重症化を大幅に減らす効果が期待されます。
一方、高用量インフルエンザワクチンについては、技術的な評価は十分に整理されたものの、制度導入のタイミングはまだ明確ではありません。高齢者の重症化予防に有効であることは示されているものの、定期接種として導入する場合には、いくつかの重要な課題が残されています。たとえば、対象年齢をどう設定するのか、65歳以上全員なのか、それとも費用対効果が最も高いとされる75歳以上に限定するのかといった議論があります。また、ワクチン供給量の確保、自治体の運用体制、国内生産ラインの維持など、実務面での調整も必要です。
専門部会のまとめでも、「ワクチンの安定供給」「自治体や医療機関での運用」「制度上の観点」を踏まえ、引き続き議論を行うことが妥当とされています。これらの条件が整い次第、定期接種への追加が本格的に検討される見込みです。そのため、開始時期としては2026年度以降が目安となるものの、RSウイルスワクチンよりは後になる可能性があります。
いずれのワクチンも、日本の予防接種制度をアップデートする上で重要な役割を担うものです。妊婦向けRSウイルスワクチンは導入が目前となり、出生直後の乳児を守る体制が大きく変わろうとしています。一方で高用量インフルエンザワクチンは、超高齢社会において高齢者の重症化を抑制するための重要な政策として期待されており、今後の審議と制度設計が注目されます。
高齢者と乳児の重症化を防ぐため、日本の予防接種制度が大きく前進します
高用量インフルエンザワクチンと妊婦向けRSウイルスワクチンはいずれも、これまでの日本の予防接種制度には存在しなかった新しいアプローチであり、重症化リスクの高い世代をより確実に守るための重要な一歩となります。今回の厚生労働省の技術的評価によって、その有効性、安全性、そして費用対効果のいずれも科学的根拠に基づいて整理されたことで、制度化に向けた議論が大きく進みました。
まず、高用量インフルエンザワクチンは、高齢者、とくに75歳以上の層で高い相対効果が期待されることが明らかになりました。標準量ワクチンよりも強い免疫応答が得られるため、入院や死亡リスクを減らす可能性が高く、超高齢社会において非常に重要な意味を持つワクチンです。導入に向けては、対象年齢の設定、自治体での運用、供給体制の安定化など実務的な課題がありますが、日本の高齢者医療を支える大きな柱になることが期待されています。
一方、妊婦向けRSウイルスワクチンは、乳児を生まれる前から守る「母子免疫」という新しい発想を取り入れる点で非常に特長的です。妊娠28〜36週に接種することで、出生直後の赤ちゃんを最も危険な時期から守ることができ、社会全体の医療負担軽減にもつながります。臨床試験で一部懸念が指摘された妊娠高血圧症候群については継続的なモニタリングが必要ですが、総合的には定期接種として導入することが妥当と判断されています。2026年4月に導入される可能性が高いこともあり、現場では早期の情報提供が重要になります。
また、乳児向けの抗体製剤という別の選択肢も存在し、母子免疫ワクチンと併用・補完していくことで、さまざまな家庭状況や地域の流行状況に柔軟に対応できる体制が構築されていくと考えられます。RSウイルスの流行時期が地域で異なるという日本固有の課題に対しても、複数の予防手段があることは大きな安心材料です。
全体として、今回の厚労省の方針は、高齢者と乳児という最も感染症の影響を受けやすい二つの世代を守るため、科学的根拠に基づいた予防策を整備するものです。2026年度は、日本の予防接種制度にとって大きな転換点になる可能性があり、今後の制度設計や導入準備に注目が集まります。制度が正式にスタートすれば、予防可能な入院や重症化を大幅に減らし、安心して暮らせる社会の実現に一歩近づくことが期待されます。
参考資料
高用量インフルエンザワクチンについての議論のまとめ(厚生労働省)