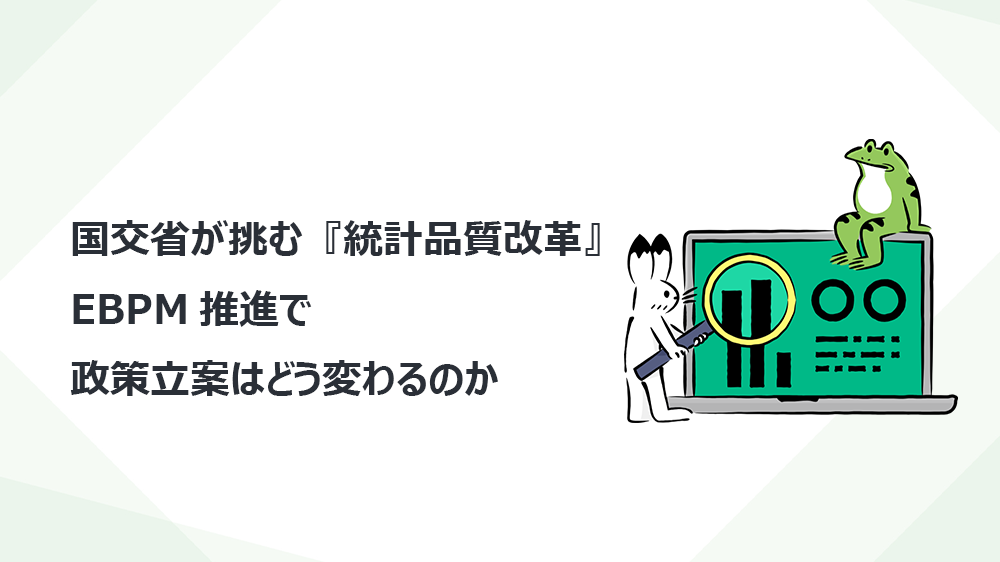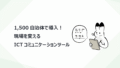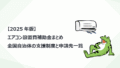政策の信頼性や実効性を高めるには、客観的なデータに基づいた判断が欠かせません。こうした「エビデンスに基づく政策立案(EBPM)」の必要性が高まる中、国土交通省は統計の品質改革に向けた取り組みを加速させています。従来の統計は精度や収集方法に課題があり、政策効果を正しく検証するうえで限界が指摘されてきました。国交省が進める統計改革は、データの信頼性を高め、より実効的な政策づくりを支える基盤整備にあたるものです。本記事では、その背景や具体的な取り組み、自治体や社会に与える影響について解説します。
EBPMとは何か?
EBPMとは Evidence-Based Policy Making(エビデンスに基づく政策立案) の略称です。直訳すると「証拠に基づいた政策づくり」となり、科学的なデータや客観的な調査結果を根拠に、政策を立案・評価・改善していくアプローチを指します。
これまで日本の政策は、政治的判断や過去の慣例、あるいは官僚や有識者の経験則に基づいて決定されることが多くありました。しかし、社会課題が複雑化・多様化する中で、こうした従来型のアプローチでは限界が見えるようになっています。特に少子高齢化や災害対策、都市インフラの老朽化など、国や自治体が直面する問題は「勘や経験」だけでは対応できません。
EBPMが注目される背景
- 少子高齢化と人口減少
限られた財源の中で効果的に施策を打つためには、データに基づく「投資効果の高い施策選択」が不可欠です。 - 災害や感染症など不確実性の増大
災害発生時の被害想定や避難計画は、統計やシミュレーションに裏付けられた判断でなければ実効性が担保できません。 - 説明責任の強化
政府や自治体は住民に対して「なぜその施策が必要なのか」を説明する必要があります。データに基づく根拠を示すことで、住民の納得感や政策への信頼性が高まります。
海外におけるEBPMの先行事例
- イギリス
1990年代以降、「What Works Network」という機関を設立し、教育・福祉・犯罪対策などの政策効果を科学的に検証しながら改善を行ってきました。 - OECD諸国
各国でEBPM推進が共通課題となっており、統計の整備や政策効果の評価手法が進化しています。
これに比べ、日本では「統計データの品質問題」や「人材不足」などにより、十分にEBPMが浸透しているとは言えません。そのため国交省をはじめとした中央省庁が「統計改革」を通じてEBPMの実践基盤を整えようとしているのです。
統計の品質が政策に与える影響
政策立案における「統計」は、いわば政策の“設計図”のようなものです。信頼できるデータがあれば、課題を正確に把握し、効果的な施策を打つことができます。しかし、もし統計の品質が低ければ、誤った前提のもとで政策が作られ、期待した成果を上げられないばかりか、かえって社会に負担を与えるリスクも生まれます。
統計不備がもたらすリスク
日本でも、統計の不備が大きな問題となった事例があります。代表的なのが 「毎月勤労統計調査の不正問題」 です。この調査は雇用・賃金・労働時間の動向を把握する基幹統計ですが、調査手法の誤りにより、雇用保険や労災保険の給付額に誤差が生じ、数百万人規模の国民に影響を及ぼしました。この問題は、統計の信頼性が損なわれると、政策や制度運営そのものが揺らぐことを示した典型例です。
また、災害対策や都市インフラ整備においても、統計の精度は極めて重要です。
- 避難計画の策定における人口分布データが誤っていた場合、十分な避難所を確保できず、住民の安全に直結するリスクが生まれる。
- 道路や橋梁の老朽化対策で交通量データが不正確であれば、投資の優先順位を誤り、限られた財源を効率的に活用できない。
統計品質の低下は単なる「数字の問題」ではなく、住民の生活や安全、ひいては行政への信頼そのものに影響を与えるのです。
信頼できる統計がもたらす効果
一方で、高品質な統計は政策を強力に支えます。
- 政策効果の検証が可能になる:施策の前後でデータを比較することで、効果があったかどうかを定量的に把握できる。
- 予算配分の正確性が高まる:需要や課題の規模を数値で把握できれば、限られた資源を効率的に配分できる。
- 住民への説明責任を果たせる:データを根拠に「この政策はこうした成果を生みました」と説明でき、納得感が高まる。
このように、統計の品質は「政策の質」を左右する基盤であり、国交省が取り組む統計改革の核心もここにあります。
国交省が進める「統計品質改革」とは
国土交通省は2025年、「統計品質改善会議」を立ち上げ、政策立案の基盤となる統計の信頼性向上に本腰を入れ始めました。この背景には、行政全体でのEBPM推進に向けた動きと、過去の統計不備による国民の不信感が重なっています。国交省が扱うデータは、人口動態から交通量、住宅・土地情報、防災関連まで幅広く、社会基盤整備や都市計画に直結するものです。そのため、統計の精度を高めることは「住民の暮らしを守る政策づくり」に不可欠といえます。
統計改革の主なポイント
1. 調査手法の見直し
従来の紙ベース調査や限られたサンプルに依存する方式から、ICTを活用したデジタル調査へと移行します。オンライン回答やビッグデータの活用によって、調査範囲の拡大とコスト削減を両立させる狙いがあります。
2. データ品質の保証
「精度がどれだけ高いか」だけでなく、「どのように収集・処理されたか」というプロセスの透明化が重視されています。統計の作成段階から検証体制を強化し、第三者によるチェックを取り入れることで、恣意的な操作や誤りを防ぐ仕組みを整えています。
3. 公開と透明性の強化
国交省は、統計データの公開プロセスを改善し、利用者がデータの根拠や背景を把握できる仕組みを進めています。これにより、自治体や研究者、市民も信頼性のあるデータを政策立案や研究に活用できるようになります。
4. 新技術の導入
AIによるデータ解析や、交通センサー・衛星データなどの新しい情報源を統計に組み込む取り組みも進んでいます。これにより、従来では把握が難しかったリアルタイム性の高いデータが政策判断に活かせるようになります。
国交省が目指すもの
これらの改革によって、国交省は「政策の精度を高めるための土台づくり」を進めています。つまり、単なる数字の改善ではなく、データの信頼性そのものを担保し、住民や自治体にとって「安心して使える統計」を提供することがゴールです。
自治体・現場への影響
国交省の統計品質改革は、中央省庁レベルの話にとどまらず、地方自治体の現場に直接的な影響を及ぼす取り組みです。自治体が実際に政策を立案・実行する際、国が提供する統計は大きな拠り所となるため、その精度が上がることは実務の質の向上につながります。
インフラ整備計画の精度向上
道路や橋梁、水道などの社会インフラは、老朽化対策や新規整備に際して「どの地域で需要が高いか」「将来的な利用見込みはどうか」といった予測が欠かせません。統計品質が高まれば、自治体はより合理的に投資の優先順位を判断でき、限られた予算を効率的に使えるようになります。
防災計画の実効性強化
防災分野では、人口動態や土地利用データの精度が避難所の配置や避難経路の設計に直結します。これまで地域ごとの詳細データが不十分で「机上の計画」にとどまるケースもありましたが、統計改革により現実に即したデータが提供されれば、住民の安全性をより高められます。
自治体が使えるデータの拡充
国交省の統計はオープンデータ化も進められており、自治体は自らの施策に合わせて自由に分析できるようになります。たとえば、都市再開発を検討する自治体が、最新の人口動態や交通量データを基に将来シナリオをシミュレーションする、といった活用が可能になります。
フィードバックループの形成
国が統計を整備し、自治体がそれを使って政策を実施し、その結果を再び国にフィードバックするという「循環」が生まれます。このループが機能すれば、国と地方が一体となってEBPMを実践する体制が整い、政策の質を継続的に高めていくことができます。
統計品質改革は、自治体にとって「政策づくりの道具箱が精度の高い工具で揃えられる」ようなものです。現場レベルの意思決定が変わり、住民サービスの向上に直結する可能性を持っています。
EBPM推進の課題と展望
統計品質改革によってEBPMの基盤が整いつつありますが、現場への浸透と定着にはまだ多くの課題が残っています。ここでは主な課題と、それを踏まえた展望を見ていきます。
主な課題
1. データ整備にかかるコスト
統計の精度を高めるためには、調査対象の拡大やデジタル化が必要ですが、その分コストや人員の確保が求められます。特に地方自治体にとっては、予算や専門人材の不足が導入のネックになりやすいと指摘されています。
2. 統計リテラシーの不足
高品質な統計が整備されても、それを活用する職員にデータ分析や活用スキルがなければ意味を持ちません。現状では、統計データを政策立案に活かせる人材は限られており、リテラシー教育や専門職育成が不可欠です。
3. データの相互連携の難しさ
国交省だけでなく、厚生労働省・総務省など各省庁が独自に統計を持っています。これらを横断的に連携させる仕組みが未整備のため、統計の「サイロ化(縦割り化)」が課題となっています。
今後の展望
1. 行政データの統合・オープン化
統計改革の先には、国・自治体が持つデータを一元的に管理し、住民や民間企業も活用できるようにする動きが想定されます。これにより、行政内外でのイノベーションが促進される可能性があります。
2. AI・ビッグデータの本格活用
AIによる解析や衛星データ、スマートシティで収集されるセンサー情報など、従来の調査では得られなかったリアルタイム性の高いデータが政策判断に活かされていくでしょう。
3. 住民への説明責任の強化
統計を根拠に施策を示せば、住民に対して「なぜこの政策を選んだのか」を明確に説明できます。これは行政への信頼回復にもつながり、民主主義の健全性を高める重要な一歩となります。
EBPMの推進は、単なる行政の効率化ではなく、「根拠に基づいた政策判断を通じて、住民の生活をより良くする」ことを目的としています。そのためには、統計の品質向上だけでなく、データを活用できる人材育成や省庁間の連携、住民への説明責任を果たす仕組みづくりが不可欠です。
まとめ
国交省が進める「統計品質改革」は、一見すると専門的で地味な取り組みに見えるかもしれません。しかし、統計の信頼性は政策の正確性や効果を左右する“根幹”です。データが誤っていれば、政策判断も誤り、住民生活に直接的な影響を与える恐れがあります。逆に、精度の高い統計があれば、行政は課題を正確に把握し、限られた資源を有効に使い、住民にとって実効性のある政策を実現できます。
国交省が掲げるEBPM(Evidence-Based Policy Making)は、「勘や慣例に頼る行政」から「証拠に基づく行政」への転換を意味します。これは政策の質を高めるだけでなく、住民に対して「なぜこの政策を行うのか」を明確に説明できる土台をつくり、行政への信頼性を高める重要な役割を担っています。
統計の品質改革は、国の政策だけでなく、自治体の現場にも直接的なメリットをもたらします。インフラ整備、防災計画、都市再生といった分野で、これまで以上に精度の高い意思決定が可能となり、住民サービスの質向上へとつながるでしょう。
今後は、AIやビッグデータの活用、省庁間のデータ連携、統計リテラシーを備えた人材の育成など、さらなる課題への対応が必要です。しかし、それらを乗り越えた先にこそ「持続可能で信頼される行政」の姿があるといえます。
国交省の挑戦は、日本全体の行政改革の大きな試金石となるでしょう。