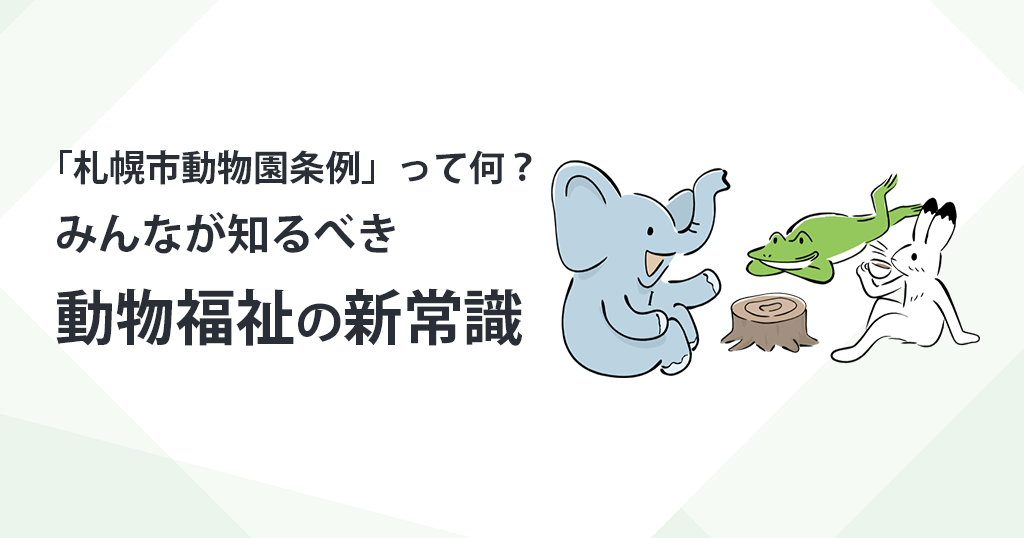条例が生まれた背景と社会的意義
札幌市が「動物園条例」を制定した背景には、大きく分けると以下のような社会的・歴史的流れがあります。
- 生物多様性の急速な損失
近年、世界中で多くの野生動物や植物が絶滅の危機に瀕しており、「生物多様性の保全」が地球規模の課題になっています。これを受け、各国や自治体が法律や条例を用いて、野生動物の保護や環境保全に取り組む機運が高まってきました。 - 動物園の役割変化
かつて動物園は「珍しい動物を見て楽しむ娯楽施設」の要素が強く、単に動物を収集し展示するだけの時代がありました。しかし今では、生物多様性保全・野生動物の繁殖研究・教育普及など“保全”と“教育”に重きを置く方向へと大きく転換しています。世界動物園水族館協会(WAZA)や各国の先進的な動物園でも、種の保存と動物福祉がとても大切だという認識が広がっています。 - 「動物福祉」という概念の浸透
「動物福祉(アニマルウェルフェア)」は家畜の飼養管理に端を発する考え方でしたが、野生動物を飼育するうえでも不可欠な要素として世界的に広がりました。飼育動物が痛みや苦しみを減らし、なるべく本来の行動を発揮できるようにする――そうした“科学的根拠に基づく飼育管理”が重要視されるようになっています。日本でも、2015年の円山動物園におけるマレーグマ事故などが契機となり、飼育動物の取り扱いについて見直しが進みました。 - 円山動物園における事故と市民の意識変化
札幌市では、2015年に円山動物園で起きたマレーグマの死亡事故が大きな転換点でした。事故の原因は飼育管理や組織体制の不備に起因するとされ、行政や市民からは「動物への配慮」や「園としての責任体制」の不十分さが批判されました。
これを深く反省し、「ビジョン2050」という長期的方針を策定するとともに、“動物福祉”と“種の保存”を根幹に置く運営を目指すようになりました。 - 法的根拠の必要性
日本には、動物園に関する総合的な法律が存在しません(動物園の運営目的や実施事業を包括的に定める法律がない)。そのため、飼育動物の取り扱いは「動物愛護管理法」で登録・届出の規定があるものの、“野生動物を保全するための具体的な枠組み”までは網羅されていません。
また、欧米では「動物園を営業するには、野生動物保護や動物福祉向上に取り組む条件を満たす必要がある」等の厳しい法制度を整備している国もあります。そうした世界の動きに遅れをとらないため、札幌市としては独自の条例で動物園の運営に必要な基準・理念を打ち立てることになりました。 - 条例が生み出す新たな役割
札幌市の「動物園条例」は単にルールを課すだけでなく、市民や事業者と動物園が協働しながら「動物福祉を確保しつつ生物多様性を守る」という共通目標を実現する仕掛けを作ろうとしています。さらに、条例に基づく「認定動物園」という仕組みを通じ、事業者や市民からの寄附や協力を得やすくなるような優遇措置や広報支援を行います。
条例制定の経緯と「動物福祉」の重要性
2015年のマレーグマ事故とその後の改革
- マレーグマ死亡事故の概要
円山動物園で、若いオスと高齢のメスを同居させ繁殖を試みたところ、闘争が激化して死亡事故が起きました。当時は飼育管理上のリスク評価が十分でなく、繁殖計画の進め方も明確ではありませんでした。 - 事故が突きつけた課題
(1)飼育動物の健康状態を正しく把握し組織として管理する体制の不備、(2)繁殖による種の保存という“動物園の社会的役割”を果たすには施設や獣医療の充実が不可欠だったこと、(3)人間の判断で動物を同居させる難しさ――などが露呈しました。
円山動物園が掲げた「ビジョン2050」
- 長期的視点へシフト
上記の事故をふまえ、円山動物園は「ビジョン2050」という長期的な基本方針を策定し、「動物福祉の充実」「生物多様性の保全」「環境教育や調査研究」を重視する姿勢を打ち出しました。 - “レクリエーション”から“リ・クリエーション”へ
かつての「動物園=見世物」という旧来の認識を改め、「学びの場」「再創造の場」としての役割を強化する意識が強まっています。
「動物福祉(アニマルウェルフェア)」とは
- 5つの自由からの発展
動物福祉はもともとイギリスで家畜の飼育環境改善のために提唱された概念ですが、近年は野生動物を飼育する動物園においても科学的な評価や管理が欠かせないとされています。
具体的には、「苦痛やストレスを与えない」「動物本来の行動を発揮できる環境を整備する」など、飼育動物の視点に立つアプローチが求められます。 - 円山動物園での取り組み
事故をきっかけに、飼育体制や獣医療体制、職員研修などを強化。さらには「動物福祉規程」を整備し、定期的な見直しと改善を組織的に行うようになっています。
指定管理や法的根拠との絡み
- 国内法の不備
日本では「動物園の運営」を包括的に定める法律がなく、かつ動物園の営業や飼育の在り方を直接規制する法律も現状ありません(「動物愛護管理法」で最低限の登録制度はある)。
そのため各自治体・各動物園が独自で運営方針をつくる一方、「生物多様性の保全」や「動物福祉」に本腰を入れるには法的根拠が弱いという課題がありました。 - 条例による担保
札幌市では、円山動物園の取り組みが継続・強化されるよう、そして他の民営動物園・水族館にもこの考え方を広げるために、「札幌市動物園条例」を成立させました。
この条例によって動物園が「保全」「教育」「研究」「リ・クリエーション」といった社会的役割をしっかり担える仕組みを作り出す狙いが明確になります。
動物園への認定制度と市民参加
- 認定動物園制度
条例では、「動物園が生物多様性保全や動物福祉の確保にしっかり取り組む」ことを要件として、「札幌市認定動物園」として認定する仕組みを設けています。
認定された園は、市からの情報提供や助成金・広報支援を受けられるメリットがあり、市民や企業からの寄附や協力も得やすくなる仕組みです。 - 寄附文化の醸成
動物園の活動に資金面で協力したいと考える人々の支援を受けとめる「動物園応援基金」も条例で位置づけられました。これにより基金を積み立て、必要に応じて保全活動に活用するサイクルを作ります。
以上のように、「条例が生まれた経緯」の裏には、円山動物園の事故を通じて生じた反省や、動物園全体の社会的役割の変化が大きく関与しています。「動物福祉」という観点が深く浸透したことが、条例制定の大きな意義と言えるでしょう。
札幌市動物園条例の構成とポイント
札幌市動物園条例の条文は前文を含め、大きく7つの章から構成されます。ここでは各章の概要をかみ砕いて紹介します。
前文
- 条例の目的や背景
条例の前文では、現代の動物園がどんな役割を担ってきたかを振り返りつつ、「絶滅の危機にある野生動物の保全」「動物福祉への世界的な関心の高まり」などを理由に、本条例を制定する必然性を示しています。
さらに、円山動物園で起こった事故の反省から「今後は良好な動物福祉を確保しながら生物多様性を保全していく」という強い決意が述べられています。
第1章 総則(目的、定義、基本理念、市民や事業者の責務)
- 第1条:目的
- 「野生動物の保全を通じて、現在および将来世代のために生物多様性を守る」と言及
- 単に“飼う・見せる”ではなく、“保全活動を行う”施設としての動物園の立場を明確化
- 第2条:定義
- 「野生動物」「動物園」「動物福祉」「生息域内保全」「生息域外保全」「累代飼育」などの言葉を法律レベルで明文化
- 特に「野生動物」は“家畜化されていない動物”と明確に定義しており、保全の対象がはっきりする
- 第3条:基本理念
- 飼育動物の動物福祉を確保しつつ野生動物の保全を推進する
- 豊かな人間性と感性を育む学びの機会を提供し、市民や事業者と協働する姿勢を重視
- 第4~6条:市、市民、事業者の責務
- 市は、動物園における生物多様性保全を支えるために施策を策定・実行する責任を負う
- 市民や事業者も「動物園の活動への理解と協力」「生物多様性のための行動」を求められる
第2章 動物園(保全活動、動物福祉の確保、活動情報の公表)
- 保全活動
(1)動物収集、(2)調査研究、(3)生態を伝える展示、(4)保全意識を醸成する教育、(5)生息域外保全のための累代飼育、(6)関係機関との情報交換――これら6点を行うよう定めています。 - 動物福祉の確保
最新の科学的知見に基づき、その種や個体に適した飼育環境を整える義務があると明言。さらに動物福祉規程を定め、定期的に評価・見直しを行うことを求めています。 - 活動情報の公表
飼育や研究の成果、改善の取り組みなどを社会へ公開することで、協力や寄附などを得やすくし、市民の意見を取り入れることが期待されます。
第3章 認定動物園
- 札幌市認定動物園制度
市は、この条例に適合する動物園(円山動物園を除く)を「認定動物園」として認定できます。認定要件を満たさないと認定は取り消される仕組み。 - 認定動物園への支援
市は野生動物の保全活動における情報提供、助言、広報、助成などを行い、取り組む園が増えるよう促す方針です。
第4章 円山動物園
- 運営方針・実施計画
円山動物園は市営なので、この条例に沿った総合的かつ計画的な運営方針をつくり、それに基づく中期計画を定期的に見直すよう規定。 - 良好な動物福祉の確保
市民動物園会議による評価、動物福祉規程の制定・改正時の意見聴取などを行う。職員が組織として動物福祉を守ることを明記。 - 円山動物園動物福祉の日
7月25日を「動物福祉の日」として、過去の事故を忘れずに教訓とし、市民にも広く啓発。 - 動物展示および教育活動の原則
野生動物に直接触れる体験や、擬人化する演出を行わない方針を示し、本来の生態を保つ形で見せることを求めている。
第5章 動物園応援基金
- 寄附文化の醸成と基金
動物園が保全活動を続けるには資金が不可欠。条例では「動物園応援基金」を設け、市民や事業者が寄附しやすくすることで活動を後押しする仕組みを整えています。
認定動物園の保全活動に対する助成も、この基金によって行われます。
第6章 市民動物園会議
- 市長の諮問機関
「動物園の施策や円山動物園の運営について、専門的かつ客観的な意見を述べる場」として市民動物園会議が置かれます。
また、認定動物園の審査や動物福祉の評価なども行うため、専門家や市民代表が加わり、必要に応じて部会を設置して検討します。
第7章 雑則・附則
- 施行期日や関連条例の改正
公布の日から一部施行し、認定動物園制度や基金に関する条文は1年以内に施行するなどの経過措置が定められました。
今回問題となっている部分――「かわいそう」「触れ合い」「擬人化」の是非
ニュース記事などを読むと、この条例に対して「動物園で飼うのはかわいそう」「そもそも動物園はいらないのでは?」という意見も見受けられます。一方で「動物と触れ合う体験ができなくなるのは寂しい」「擬人化的なイベントも子供にとっては良い影響があるのでは?」といった声もあります。こうした論点を整理します。
「動物園で動物を飼うなんてかわいそう」問題
- 動物福祉を重視しつつ野生動物の保全に貢献
条例では「動物福祉」と「保全」の両立を目指しており、飼育される動物が苦しむ環境ではあってはいけない、という原則を明示しています。
しかし、「動物を見世物として閉じ込めるのは根本的にかわいそう」と感じる人も少なくありません。ここでの考え方としては「動物園が生存可能な繁殖群を維持することで、将来的に絶滅を防ぎ、生息域内保全をサポートする」という公益上の意義が重視されています。
「ふれあい体験はダメなのか?」問題
- 野生動物と直接触れるリスク
特に**円山動物園では「原則として触れない」**という姿勢が条例に盛り込まれました。これは、動物側のストレスや安全面(動物にとっても人間にとっても)を踏まえたものです。
例えば、野生動物を触っても大丈夫だと来園者が勘違いすると、自然界のクマやキツネなどを安易に手なづけようとして事件になる恐れがあります。動物園のふれあいが「人と動物の誤った距離感」を助長する危険性を認識する必要があります。 - 例外措置
ただし本当に教育効果が大きく、かつ動物福祉を損なわないと市民動物園会議が判断した場合は、例外的に認める仕組みがあります(条例第14条ただし書き)。
ここに言う「教育効果」とは「野生動物の保全や生息環境への理解が深まり、行動を促せるか」といった高いハードルが設定されており、単なるエサやりショーや記念撮影とは一線を画します。
擬人化への賛否
- 人間の言葉をしゃべらせたり、衣装を着せたりする表現
条例では「動物に人間っぽい行動をとらせる」「動物に吹き出しをつけてしゃべらせる」といった擬人化を禁止する方向が示されています。
これは動物をキャラクター化することで、「動物本来の生態への理解」を歪めてしまう恐れがあるとされるためです。 - 教育や広報とのバランス
一方で、広報やグッズ展開ではキャラクター化した動物がよく使われます。条例はここを完全否定しているわけではなく、「実際の飼育動物を用いた展示や教育のシーンで、人の姿や行動を強要しない」という原則を定めていると理解できます。
今回の騒動と広がる認識
- ABEMA Primeなどでも議論
「動物園って必要?」「かわいそうじゃないか?」という問いは、SNSやメディアでたびたび取り上げられています。北海道の円山動物園が主体となった条例制定は全国でも珍しく、動物愛護団体からも注目されています。 - “誰のための動物園か”再考
従来は「市民のレクリエーション」であった時代から、「保全・研究・教育のための施設」に役割が変化する中で、動物園のあり方や演出方法が問われる事態になっています。
問題の核心
- 動物を保全するために、飼育繁殖が要る
一部の希少種は野生の生息地そのものが破壊されていて、もはや動物園などの飼育繁殖に頼らなければ絶滅を免れない種も存在します。その繁殖や研究を進めて将来的に生息地へ戻す――そうした生息域外保全を担うことが動物園の大きな役割です。
しかし、その前提として動物園は本当に動物の命を大切にしているのかという市民からの目が厳しくなっています。条例で動物福祉を重視し、定期評価や見直しを義務付けたのはまさにこの疑問に応えるためです。
今後の在り方――条例の先に目指すもの
札幌市動物園条例は、動物園を「ただの見世物」から「野生動物の保護・研究・教育を行う公共性の高い施設」へシフトさせるための法的枠組みとして大きな意義を持ちます。しかし、条例を作っただけでは課題が一気に解決するわけではありません。ここでは、条例の先にある将来像や今後の課題を考えます。
動物園同士の連携と情報共有
- 国内外の連携強化
一つの動物園だけで完結できる保全活動は限られます。繁殖のための血統管理や研究データの交換は、全国・海外の動物園や大学・研究機関と連携する必要があります。
例えば希少種のオランウータンやアジアゾウの繁殖には、遺伝的多様性を守るための複数施設の協力が欠かせません。条例をきっかけに、札幌市主導でネットワークづくりを進めることが期待されます。
認定動物園のレベル向上
- ステップアップ方式
条例では「さっぽろの動物園ステップアップ制度」として、段階的に動物園の取り組みを評価し支援する仕組みが考案されています。
認定要件を満たす園は認定を受け、さらに高度な取り組みを行う園は「優良認定動物園」という形で差別化するなど、動物園同士が向上を競い合う効果が出る可能性があります。
動物福祉規程の充実と評価
- 世界の流れに追随
アメリカのAZAやヨーロッパのEAZAなど海外の動物園水族館協会が示す「アニマルウェルビーイング」「アニマルウェルフェア」の考え方では、飼育空間の広さや環境だけでなく、動物が退屈していないか、社会的・心理的な要求も含めて考えます。
札幌市でも獣医学や行動学の専門家を招き、科学的に評価し、円山動物園や認定動物園の取り組みを検証・改善し続ける仕組みが必要でしょう。
市民参加の拡大
- 観察と意見交換
「市民動物園会議」は、市民委員を加え、保全や福祉の実態を評価する役割を担っていますが、多くの市民の声をどのように吸い上げるかも課題です。オンラインでのアンケートや説明会開催など、条例を身近にする工夫が求められます。 - 寄附やボランティア
条例に基づく「動物園応援基金」は、寄附文化の醸成を狙っています。今後は、ふるさと納税の仕組みを応用したり、寄附に応じて動物の保全活動を定期報告するなど、寄附者が応援し続けられるようなフィードバック体制がポイントになるでしょう。
生息域内保全への発展
- 野生復帰を意識した飼育
条例文にも「生息域外保全は生息域内保全を補完するために行う」という国際的な考え方が反映されています。動物園での繁殖や研究結果が、そのまま野生での保護活動につながる仕組みを確立することが大切です。
例えば、シマフクロウの野生復帰への取り組みを拡大し、専門研究機関や森林管理機関と協同するなど、動物園が保全の核となる道が考えられます。
課題の残る部分
- 他自治体や国の法整備
札幌市だけが先進的な条例を作っても、他自治体に動物園がある限り、全国規模の整合性が取れなければ限界があります。将来的には、このモデルをもとに全国的な動物園法の検討が進む可能性があります。 - 費用負担と収益確保
動物福祉や保全研究には手間や費用がかかり、施設改修や獣医療体制の充実も簡単ではありません。「どうやって財源を確保するか」が大きな課題です。市民・企業からの支援を受ける仕組みづくりにおいては、情報公開や成果の見せ方がカギになります。
条例によって基本的な枠組みは生まれましたが、制度をどう実践し発展させるかが今後の焦点といえます。
他地域・海外の事例との比較と連携
札幌市の動物園条例は国内初の包括的な条例とされています。では、他地域や海外ではどんな取り組みがあるのでしょうか。ここではいくつか紹介し、比較してみます。
他自治体の動物園関連条例
- 国内での条例例は少ない
北海道以外では、動物の愛護や管理に特化した条例(動物愛護条例)を設けている自治体はあるものの、「動物園」に焦点を当てた包括的な条例は非常に少ないのが実情です。
札幌市の試みは全国的に見ても先駆的です。今後、他都市が同様の条例を作るか注目されます。
海外の動物園とその法制度
- EUの例
ヨーロッパでは「EU動物園指令(EU Zoo Directive)」という法規制があり、動物園に対し「保全に貢献すること」「教育を行うこと」などを義務付けています。動物園は各国の中央政府や地方自治体から許可を得る際に、保全計画や飼育環境を明確に示す必要があります。 - 米国の例
アメリカではAZA(米国動物園水族館協会)が厳しい基準を設けており、会員として認められる(いわゆる「認定」される)には飼育環境や繁殖計画、動物福祉の管理などをハイレベルで維持する必要があります。
認定・登録制度の運用
- WAZA(世界動物園水族館協会)
WAZAは保全文化の創出や持続可能性戦略を掲げ、各国の動物園が世界的な協力体制を築くよう促しています。日本動物園水族館協会(JAZA)もWAZAの方針に準じたガイドラインを策定していますが、罰則などはなく、あくまで任意協力にとどまっていました。 - 札幌市の条例による独自認定
先述の第3章で規定された「認定動物園制度」は、国内版AZA認定のように機能する可能性を秘めています。特に助成金や基金などのサポート体制が明文化された点が特徴で、運用次第で大きな成果が期待されます。
国際的な役割分担
- 種別担当園制
世界的に希少な種の繁殖は、1つの動物園だけで抱え込むのは難しく、国際的な種管理プログラムに沿って役割分担されることが多いです。
例:ある動物園が「ホッキョクグマ」の繁殖計画を担い、別の動物園が「スマトラトラ」の血統管理を担うなど。 - 情報共有の迅速化
円山動物園や他の認定動物園が、海外の保全団体や大学と情報交換をスムーズに行えるようにするため、条例で「連携」を推進しています。そこには言語の壁や書類手続きがある程度クリアされるよう、自治体が橋渡しをする役割が期待されます。
連携による効果
- 飼育・繁殖ノウハウの共有
海外でうまくいった飼育方法や治療方法、遺伝管理ツールを学び、取り入れることで「希少な動物の死亡や近親交配を防ぐ」成果が上がる。 - 研究成果の相乗効果
動物の行動や食性のデータを世界規模で集約し、野外保全(生息域内保全)とシームレスにつなげる動きが広がる。札幌市条例は、その一部を地域自治体レベルで担おうとする先駆けとなっています。
今後の展望
- 他都市と連携し全国規模へ
条例自体が市の範囲に限られるため、全国的に拡張するには法改正や他自治体とのネットワーク形成が必要。 - 観光との兼ね合い
動物園は観光資源でもあるため、海外観光客にアピールする際、保全や福祉の充実ぶりを強調できると札幌市のイメージアップにつながるという期待もあります。
総じて、「海外に倣って動物園を厳しく規制するだけ」ではなく、「連携や支援を通じて質を上げるアプローチ」が札幌市の条例には見られます。これによって、国内でも動物園のあり方が大きく変わる可能性があるでしょう。
条例の本質を活かすために
最後に、ここまで見てきた「札幌市動物園条例」の要点と、今後さらに条例の本質を活かすための提言をまとめます。
条例の要点
- 生物多様性の保全
動物園は「野生動物を安全に飼育・繁殖するだけ」ではなく、最終的には野生に返すことも視野に入れた生息域外保全の場となる。また自然界(生息域内保全)を補完することが目的とされる。 - 動物福祉の確保
飼育下にある動物であっても、無理なショーや演出をさせるのではなく「本来の行動を尊重し、痛み・ストレスを減らす」管理を徹底する。定期的に評価・改善を行う。 - 市民や事業者との協働
複雑な保全や研究には多額の費用・専門知識・市民の理解が不可欠。条例で基金の仕組みなどを定め、寄附文化の醸成や市民参加の機会を広げる意図がある。 - 専門家の評価・助言
市民動物園会議が設置され、専門家が動物福祉規程の妥当性や認定動物園の基準適合をチェックする。透明性を高める狙いがある。
条例施行後の成果と課題
- 成果
- 円山動物園の飼育環境改善や動物福祉規程の整備が進み、「動物福祉の日」を設けるなど意識向上が図られた。
- 認定制度を新設し、他の民営動物園や水族館も保全活動に取り組むインセンティブが生まれつつある。
- 課題
- 動物園の運営には費用がかかり、基金だけでは十分ではない可能性がある。今後は企業スポンサーやクラウドファンディング等、さらなる資金調達策も検討が必要。
- 「ふれあい体験」や「擬人化イベント」に慣れた市民とのコミュニケーションの取り方。条例の趣旨を十分に説明し、不必要な軋轢を減らす努力が重要。
今後への提言
- 動物園の公共的価値を市民に伝える
「動物園=かわいそう」という否定論への対策として、動物園が種の保存や環境教育で果たしている役割を可視化し、市民の理解を得る必要がある。SNSやイベントで、科学的かつ分かりやすい情報発信を継続してほしい。 - 動物福祉の評価システムの充実
動物福祉規程に沿って定期的に評価するといっても、その項目や基準は多様で専門的な検討が不可欠。専門家だけでなく、市民やNPOがモニタリングできる仕組みがあるとさらに透明性が増す。 - 全国的な法整備へのステップ
札幌市だけでは限界がある面も大きい。今後は他の大都市や国レベルの法整備を促すきっかけになってほしい。たとえばEUのように「動物園が教育・研究・保全に責任を負う」枠組みを全国化することで、動物福祉や保全への意識がさらに高まるだろう。 - 国際的連携の強化
絶滅危惧種の遺伝管理や繁殖研究では、国際機関や海外の専門家との協力が欠かせない。札幌市動物園条例が一つのモデルケースとなって、世界的に認められる動物園づくりを進めることで、札幌市のみならず日本全国の動物園レベルの底上げが期待できる。
まとめ
- 条例はゴールではなくスタート
新たなルールを設けただけでは課題は解決しない。条例を活かし、市民・事業者・研究機関が協力し、動物福祉向上や生物多様性保全を現実に進める必要がある。 - 動物園の未来像
今後は、動物が苦しまず、むしろ生き生きと暮らせる環境を整えつつ、学びや研究を深める場としてさらに進化する動物園が期待される。市や市民がそれを温かく見守り、資金や知恵をサポートし合う文化が根付けば、日本の動物園も国際水準に達するだろう。
札幌市動物園条例は、いわば「動物を大切にしながら保全を推進するための社会的契約」。この条例の理念を共有し、実践し続けることで、私たちは「野生動物と人間が共生できる未来」へ着実に歩んでいくことができるでしょう。
以上が、「札幌市 動物園条例」をめぐる詳解と今後の見通しです。
この条例が単なる「市の規則」にとどまらず、「動物園が果たすべき社会的責任」を示す道しるべになり、世界的にも注目される取り組みへと発展していくことを期待したいですね。