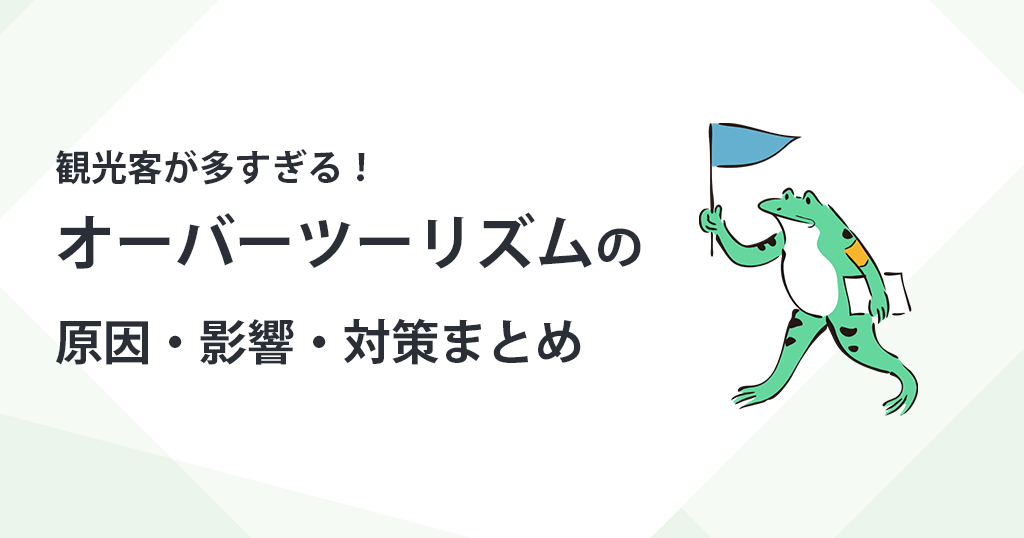オーバーツーリズムという言葉は、近年よく耳にするようになりました。もともとは2016年頃にアメリカの旅行系メディア「Skift(スキフト)」が初めて使ったとされる用語で、日本語では「観光公害」と呼ばれることもあります。今回は、オーバーツーリズムとは具体的に何を指すのか、海外や各自治体の事例をもとに解説していきます。
オーバーツーリズムとは何か
オーバーツーリズムは、一言でいえば「ある観光地に過剰に観光客が集中し、地元住民の生活や自然環境、文化財などに深刻な悪影響をもたらす状態」のことです。観光客が増えること自体は地方経済の活性化や雇用創出、国際交流の促進など、多くのメリットをもたらします。しかし、その規模があまりにも大きくなり、地域や環境が受け止めきれないほどになると問題が生じてしまうのです。
たとえば、道路や公共交通機関の混雑、ゴミのポイ捨て、夜間の騒音などは、観光客が集中する地域でよく見られるトラブルです。特に海外からの観光客が増えるインバウンド時代には、言語の壁や文化の違いからマナー意識が浸透しにくいといった課題も表面化しやすくなります。さらに、自然保護地区でのルール違反、私有地への無断立ち入り、大きなスーツケースを持って狭い路地を歩きまわるなど、住民にとっては日常生活が脅かされる事態にもつながります。
このような状況が続くと、住民は「もう観光客はうんざりだ」と強く反発し始めるかもしれません。実際、海外の有名観光地では反観光デモが行われたり、観光客の入場を制限したり、宿泊税を導入したりする例が増えています。日本においても、外国人観光客が増加傾向にある都市や人気の観光地で、徐々にオーバーツーリズムの問題が顕在化してきました。
日本政府は「2030年までに訪日外国人旅行者数を6000万人にする」という目標を掲げています。もちろん、観光客はビジネスチャンスをもたらし、旅館やホテル、飲食店、お土産店などさまざまな産業が潤う効果も大きいでしょう。しかし、「住民がもともと暮らしてきた街をどう守るか」「観光客と地域が共存する方法をどう創出するか」という点をしっかり検討しなければ、メリットよりもデメリットのほうが大きくなりかねません。
さらに、オーバーツーリズムが深刻化すると、観光客自身も混雑やマナー違反に悩まされ、旅先で満足感を得られなくなります。混雑で写真を撮るのがひと苦労、道が渋滞して予定通りに観光ができない、公共交通機関がぎゅうぎゅう詰めで移動が辛い……こうしたストレスが高まり、結局はリピーターが減少してしまう可能性もあるでしょう。
日本では、コロナ禍からの回復とともに急激に外国人旅行者が戻り、各地でインバウンドの恩恵を期待する声が高まっています。一方、タクシーやホテルなどの供給が追いつかずに「観光客を十分に捌ききれない」「混雑で住民の負担が増えている」などの悲鳴も聞こえはじめました。政府はこうした問題に対応するため、2024年度補正予算に「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」を計上し、地域を支援する姿勢を示しています。
では、日本各地で実際どのような事例が起きているのか、また世界の観光先進国ではどのような取り組みがおこなわれているのか。次章から具体例を交え、詳しく見ていきましょう。
国内自治体における具体的な事例
オーバーツーリズムの問題は、国内でどのように表れているのでしょうか。ここでは、特に深刻な状況が報告されている自治体や観光地の事例を取り上げ、住民が抱える悩みや行政の対策について解説します。
京都市:歴史ある街が抱える混雑
京都市は日本屈指の観光都市で、清水寺や金閣寺、伏見稲荷大社など世界的に知られた名所が集中しています。一方で、市バスや京都駅周辺のタクシー乗り場は観光シーズンになると大混雑。通勤や通学、買い物といった地元住民の日常移動がままならない事態が起きています。さらには、有名な花街の祇園付近での芸舞妓の無断撮影や、私有地への立ち入りなどマナー違反が相次ぎ、地域住民が大きなストレスを感じるケースが増加しました。
こうした状況を受け、京都市は観光客の分散と混雑緩和を目指して、「地下鉄や別ルートへの誘導」「手ぶら観光(荷物を駅や宿へ送るサービス)の促進」「タクシー乗り場の混雑対策」といった複数の取り組みを打ち出しています。さらに、宿泊税を導入し、その税収を地域住民との共生を図るための施策に活用している点も注目すべき動きです。
参考資料
京都観光を取り巻く情勢を踏まえた今後の方向性について(国土交通省)
神奈川県鎌倉市:アニメの聖地と観光公害
歴史と海の街として人気の鎌倉市は、近年ではアニメの舞台となった踏切の周辺が“インスタ映え”を求める観光客に占拠される問題が話題になりました。路上駐車やゴミの増加、踏切付近での写真撮影による交通妨害など、地域住民や交通安全を脅かすトラブルが頻発。一部の住民は「踏切周辺が観光客の写真スポットと化して生活が落ち着かない」と苦言を呈しています。
対策として、鎌倉市は混雑する時期やエリアを可視化して別ルートへの誘導を促すシステムを活用するほか、SNSを通じたマナー啓発を積極的に進めています。また、観光客向けの混雑マップを公開し、ピーク時を避けた時間帯の訪問を促すなど、局所的な集中を緩和しようと努力を続けています。
北海道美瑛町:景観を守る戦い
美瑛町の有名な丘や農地の風景は、観光ポスターやSNSで広く知られるようになりました。しかし、美しい景観を求めるあまり、大勢の観光客が私有地である農地に無断で立ち入ったり、車を勝手に道路脇へ停めたりするケースが相次ぎました。地元の農家は生活道路や農道が塞がれ、生産活動に支障が出ているばかりか、畑の作物を踏まれてしまうという被害も報告しています。
町や地元団体は看板を増やしたり、マナー啓発のパンフレットを多言語で作成したりして注意を呼びかけています。しかし、SNSで一度「絶景スポット」として拡散されると、想定以上の観光客が訪れて混乱を招くため、根本的な仕組みづくりが欠かせません。最近では、観光DXの導入による予約制ツアーの整備や、公式の展望スポットの明確化といった手段に力を入れています。
参考資料
美瑛町でオーバーツーリズム対策を推進します!(北海道開発局)
沖縄・西表島:入域管理と自然保護
世界自然遺産にも登録された西表島では、エコツーリズム推進法や自然公園法によって一定の入域規制やガイド同行が義務化されています。これらは、観光客が一気に押し寄せることで生態系が破壊されるのを防ぐ狙いがあります。一方で、完全な観光客排除ではなく、観光を通じて自然の価値を体感してもらう取り組みも同時に進められており、「自然保護と観光収益の両立」がキーワードとなっています。
参考資料
西表島の一部フィールドにおける利用人数制限(特定自然観光資源)の開始について(竹富町)
課題と今後の展開
これらの事例に共通するのは、「多様なマナー違反」「交通の混雑」「地域住民の生活を圧迫するほどの観光客集中」という点です。自治体や観光協会は、看板やパンフレットによるルール周知だけでなく、時間帯や季節ごとの分散化、入場・入域の制限といった実質的な人数調整にも乗り出しています。次章では、世界各地のオーバーツーリズムに対する取り組みも交えながら、具体的な解決策を考えていきましょう。
世界各国のオーバーツーリズム対策と国内の新たな取り組み
オーバーツーリズムは日本だけの問題ではなく、世界各地の有名観光地でも大きな課題となっています。ヨーロッパでは、イタリアのベネチアやスペインのバルセロナなどが反観光デモや行政による観光客抑制策のニュースで取り上げられてきました。ここでは海外の事例と、日本国内の新しい取り組みを紹介します。
ベネチア(イタリア):入域料と大型船の規制
水の都として知られるベネチアは、一日に何万人もの観光客が押し寄せるため、狭い路地や水路に深刻な混雑を起こしています。大型クルーズ船が入港するたびに、一気に数千人規模の観光客が街にあふれ、騒音や汚染、歴史的建造物へのダメージなどが顕著でした。これに対し、市当局は「入域料」(日帰りでも支払いが必要)を徴収し、その収益を環境保護やインフラ整備に使う仕組みづくりを進めています。また、環境への負担が大きい大型船の航行を制限する方向で動き出しており、持続可能な観光を守る試みが注目されています。
参考資料
伊ベネチア、観光客から入市料徴収 オーバーツーリズム対策で世界初(ロイター通信)
バルセロナ(スペイン):宿泊施設の新設制限
バルセロナでは、観光客による家賃の高騰や、街の中心部がホテルや民泊施設ばかりになり、住民が住みにくくなるという問題が起きました。さらに、夜間の騒音やゴミ問題など、住民の不満が高まり、ついには「ツーリスト、帰れ」といった激しいデモが発生しました。市政府はそれを受けて、中心部における新たなホテル建設を禁止し、すでにある宿泊施設の営業許可を厳しくチェックするなどの規制を打ち出しています。
参考資料
オーバーツーリズムでバルセロナが悲鳴 地元民ら反発デモ、観光客に水鉄砲も(朝日新聞Globe+)
ハワイ・マウイ島:自然保護のための予約制
ハワイ・マウイ島では、自然景観を守りながら観光資源を持続させるため、一部の国立公園や保護地域を予約制にしています。朝・昼・夕方といった時間帯に区切り、同時間帯に入れる観光客数を制限することで、一極集中を緩和。結果として、自然の回復が進むだけでなく、観光客自身も混雑を避けて快適に観光できるというメリットを生み出しています。
日本国内の新たな動き:2024年度補正予算と「対策パッケージ」
日本政府も、増え続ける外国人観光客を見据え「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」を取りまとめました。具体的には、観光客を過度に集めない工夫や、地方部への誘客促進、そして地域住民との協働による観光振興などが3本柱として掲げられています。これには、交通インフラの整備支援や、混雑スポットの可視化、多言語対応のマナー啓発、エコツーリズムの推進などが含まれ、2024年度の補正予算案に関連費用が計上されました。
参考資料
オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ(首相官邸)
デジタル技術を使った混雑緩和
近年ではデジタル技術が急速に進歩しており、観光地の混雑状況をリアルタイムで配信したり、事前予約による分散化を図るシステムが注目を集めています。たとえば、北海道の美瑛町や神奈川県の鎌倉市では、混雑度を可視化して観光客に周辺エリアへの誘導を促すアプリやウェブサービスを導入しました。また、手ぶら観光を促進することで、公共交通機関や道路の混雑を幾分か和らげる取り組みも進んでいます。
観光客にもメリットがある取り組み
ここで重要なのは、規制をかけるだけではなく、「観光客にとってもメリットがある」仕組みをつくることです。例えば、事前予約や混雑状況の可視化によって待ち時間を減らすことができれば、観光客はよりストレスなく目的地を楽しめます。また、オフシーズンや時間帯をずらす旅行が推奨されれば、宿泊費や交通費が比較的安くなるなどの利点も考えられます。
このように、世界中で様々な対策が試されているなか、「観光産業の利益」と「地域住民の生活・環境保全」をどのように調和させていくのかが大きな課題です。次章では、こうした国や自治体、そして事業者の取り組みが今後どのように展開していくのか、まとめと今後の展望を解説します。
まとめと今後の展望
オーバーツーリズムは、観光客が増えることによる経済効果と、地域が受け止めきれない負担が衝突することで生じる複雑な問題です。観光産業の成長は、地方創生や雇用拡大、文化交流の拡大につながる一方で、交通の混雑やゴミ・騒音問題、自然破壊、住民の生活圏侵害といった深刻なデメリットを引き起こします。とくに中学生のみなさんにも身近な例として、夏休みなどに旅行へ行った際、人気観光地で大混雑を経験したり、バスや電車に乗れず困ったことがある人もいるかもしれません。それこそが「オーバーツーリズム」によって生じる代表的な困りごとなのです。
観光客と地域の「適正バランス」
解決策としては、まず「観光客を無理に増やしすぎない」ことが重要です。国や自治体は、観光PRで人を呼び込むだけでなく、年間を通して何人ぐらいまでなら安心して観光できるのかを検討し、必要に応じて観光税や入域制限、あるいは事前予約システムを導入するなど、管理の仕組みを整備する必要があります。
さらに、人気の観光スポットだけに人が集中しないように、周辺地域への誘導や、オフシーズンや朝晩の時間帯に分散を促す工夫も欠かせません。これは「静かに落ち着いて観光を楽しみたい」という人にも大きなメリットになります。混雑を避けたい観光客にとっても、バラついた旅行スタイルはストレスを減らし、満足度を高める効果があるのです。
地域住民との協働
地域住民との連携は、持続可能な観光を実現するうえで欠かせません。自治体が一方的に規制を導入するだけでなく、住民が「自分たちの町を守りながら観光客を受け入れるにはどうしたらよいか」を考える場を設けることが大切です。たとえば、住民の協力によるガイドツアーや文化体験ワークショップなどを新しく用意すれば、観光客に深い学びや感動を与えると同時に、住民も自分たちの地域資源を再発見することにつながります。
デジタル技術とアフターコロナ
コロナ禍で一時的に落ち込んだ観光客数が急速に回復する「リベンジ消費」の波によって、再びオーバーツーリズムのリスクが浮上しています。こうした動きに対応するためにも、デジタル技術の活用は有効です。混雑状況をリアルタイムで提示するアプリや、複数言語に対応したチャットボットでマナーやルールを案内するシステムなどがあれば、観光客も事前の計画を立てやすくなるでしょう。入場制限やチケット予約システムをオンライン化することで、行列や密集を緩和できる可能性もあります。
今後の展望:地域活性化と調和の取れた観光
日本政府は引き続き外国人観光客の呼び込みを推進しており、観光業界にとっては大きなビジネスチャンスであることに変わりはありません。しかし、数字上の目標だけに囚われると、住民の生活や地域の自然・文化が破壊される危険性が高まります。そうならないためには、観光客の数や動き方を管理できる仕組みをつくるとともに、地域住民が「観光客を歓迎する気持ち」を持続できる環境を整備する必要があります。
加えて、従来型の「有名スポットを巡る」だけの観光ではなく、長期滞在型や体験型、地域の人と交流するサステナブルなツーリズムが注目を集めています。たとえば、農業体験や伝統文化の参加型イベントなどを拡充することで、観光客はその土地の魅力を深く知り、地域経済にも資金が循環する相乗効果が期待できます。結果として、住民にとっても観光産業は「自分たちの暮らしを支える誇り」となり、観光客にとっては「また訪れたい場所」へと発展していくのです。
結びに
オーバーツーリズムは、現代の観光業が抱える大きな課題です。しかし、観光地や自治体、住民が協力し合い、適切な政策と工夫を重ねることで、観光客と地域住民の双方にメリットのある持続可能な観光を実現できます。「ただ数を追うだけではなく、どのように受け入れるか」をしっかり考えながら、日本国内・海外のさまざまな取り組みを参考にして、より良い観光地づくりを進めていきましょう。中学生のみなさんにも、ぜひ地元や旅先の魅力を守りつつ楽しむ観光のあり方を知ってもらい、次世代のアイデアへとつなげていただければと思います。
観光客数をただ増やすだけでなく、地域住民の生活や観光の持続可能性を守りながら、世界中の人々に日本の魅力を伝えていくためにも、オーバーツーリズムへの理解と対策が一層求められています。