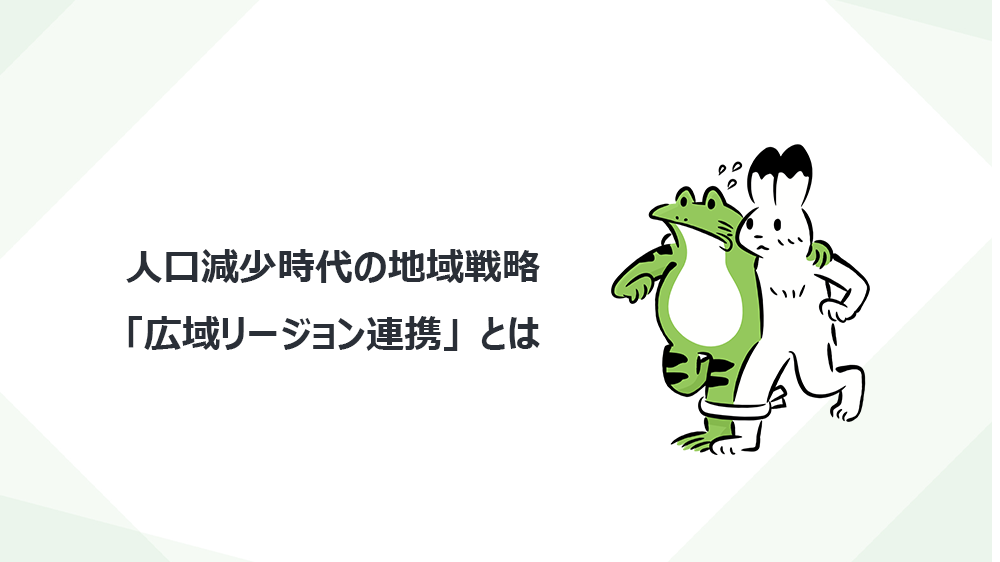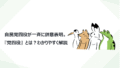人口減少や地域経済の縮小が進む中、従来の市町村や都道府県単位では解決できない課題が増えています。こうした中で注目されるのが、行政区域を超えて複数の自治体・企業・大学・研究機関が連携し、広域的に産業振興や観光、交通などの課題に取り組む「広域リージョン連携」です。
広域リージョン連携とは?
近年、日本社会は急速な人口減少と少子高齢化という大きな転換点を迎えています。総務省の資料によれば、今後数十年にわたり全国的に労働人口が減少し、地方圏では特に産業や雇用の維持が難しくなることが見込まれています。地域における成長力を保つためには、「しごと」を安定的に生み出し続ける仕組みが欠かせません。しかし、単一の市町村や一つの都道府県だけでは、現代の複雑で広域的な課題に十分に対応することは難しくなっています。
たとえば産業振興を考えると、企業活動は行政区域の境界に縛られません。部品調達から製造、販売までのサプライチェーンは複数の地域にまたがるのが当たり前であり、一つの自治体だけで産業クラスターを完結させるのは非現実的です。観光に目を向けても同様です。観光客は「県境」を意識せず移動し、広域に存在する観光資源を組み合わせて楽しむ傾向が強まっています。交通や物流の整備についても、地域をまたぐネットワークが不可欠です。こうした実態を踏まえると、行政の枠組みごとに分断された施策では、期待される効果を十分に発揮できない場面が多いのです。
この課題を克服するために導入された仕組みが「広域リージョン連携」です。これは、従来の自治体単位の取り組みを超えて、複数の都道府県や市町村が連携し、さらに企業、経済団体、大学、研究機関などの多様な主体と協力して進める包括的な枠組みを指します。重要なのは、行政だけが動くのではなく、地域経済や社会を支える幅広いプレイヤーが一体となることです。いわば「行政区域を超えた共創プラットフォーム」であり、そこから相乗効果を生み出していくことが狙いとされています。
広域リージョン連携が重視される背景には、いくつかの重要な視点があります。
第一に、規模の経済です。人口減少社会においては、一つひとつの自治体の「市場」は縮小し、従来のように地元だけで産業や観光を支えるのは困難です。しかし、複数の地域が連携することで、需要や人材を補い合い、より大きな規模で事業を展開できるようになります。たとえば農産物の輸出拡大を目指す場合、単独の産地では量が足りなくても、複数地域がまとまることで安定供給が可能になります。
第二に、多様性と専門性の確保です。どの地域にも独自の強みがありますが、それを単独で完結させるには限界があります。工業に強い地域と観光に強い地域、大学や研究機関を持つ地域など、それぞれの特徴を組み合わせることで、新しい付加価値やイノベーションを生み出せる可能性が高まります。例えば、観光資源に恵まれたエリアと、先端技術に強い大学があるエリアが連携すれば、デジタル技術を活用した新しい観光サービスを創出できるかもしれません。
第三に、広域課題への対応力です。交通網の整備、物流の効率化、災害対応、環境問題などは、一つの自治体だけでは取り組みに限界があります。特にMaaS(Mobility as a Service)のような次世代交通システムは、複数の交通手段を束ねる仕組みであるため、自治体の境界を超えて取り組まなければ成立しません。広域リージョン連携は、こうした「地域横断的な課題」に対応するための不可欠な基盤ともいえます。
また、この制度は単なる協議の場ではなく、具体的なプロジェクトを持続的に実行することを重視している点も特徴的です。過去にも都道府県間の協議会や経済団体による意見交換は存在しましたが、それだけでは成果が限定的でした。広域リージョン連携では、「宣言」と「ビジョン」を通じて共通の目標を掲げ、実際に分野横断的なプロジェクトを進めていくことが求められています。つまり、理念だけでなく実行力を伴った取り組みへと進化させる狙いがあるのです。
さらに重要なのは、この取り組みが中長期的な視点を持っていることです。短期的な補助金や単発イベントではなく、地域の未来像を描き、10年後・20年後の持続可能な成長を見据えてプロジェクトを設計していくことが求められます。そのため、自治体や企業にとっても「長期的なパートナーシップ」を築く機会となり、従来の縦割り的な施策からの脱却が期待されています。
基本的な考え方
広域リージョン連携の根本にあるのは、「一つの自治体だけでは解決できない課題を、複数の地域と多様な主体が協力して取り組む」という考え方です。人口減少が進む中で、地域の経済や社会の持続可能性を確保するには、より広い視点で戦略を立てなければなりません。そのための仕組みとして、国は「広域リージョン」という概念を提示しました。
多様な主体が参加する「広域リージョン」
まず押さえておきたいのは、「広域リージョン」とは単なる自治体連合ではないという点です。従来、広域連携といえば都道府県同士の協議や、市町村の一部事務組合のような枠組みをイメージすることが多かったでしょう。しかし広域リージョンは、それよりもはるかに広く、多様な主体が参画することを前提としています。
具体的には、地方公共団体だけでなく、経済団体、企業、大学、研究機関などが加わり、共通の目標に向かって協力します。このように行政・産業界・学術界が一体となることで、各プレイヤーの強みを活かした取り組みが可能となります。たとえば、自治体は制度設計や公共インフラを担い、企業は事業実行力や投資力を発揮し、大学や研究機関は科学的知見や人材育成を支援する、という役割分担が考えられます。
特に重要なのは、リージョン構成団体には必ず「地方公共団体」と「経済団体」が含まれることが義務づけられている点です。行政の意思決定と経済界の実行力の両方を取り入れなければ、実効性のある広域連携は成り立たないからです。さらに複数の都道府県にまたがることも条件となっており、単なる「県内の連携」ではなく、真に広域的なスケールでの取り組みを意図していることが分かります。
「宣言」と「ビジョン」による枠組み
広域リージョン連携を進める際の柱となるのが、「広域リージョン連携宣言」と「広域リージョン連携ビジョン」です。
連携宣言は、複数の団体が「このリージョンとしてどんな未来を目指すのか」を公表する文書です。そこにはリージョンの名称や区域、参画団体の一覧、そしておおまかに取り組むべき分野が盛り込まれます。言い換えれば、これは広域リージョンとしての「意思表示」であり、各主体の合意形成を社会に示す役割を持ちます。
一方、連携ビジョンは、宣言をさらに具体化した「実行計画」にあたります。中長期的な将来像を描き、その実現のためのロードマップや、具体的なプロジェクト内容を明記するものです。単なる理念にとどまらず、どの主体がどのような役割を担い、どんな成果を目指すのかを明確にすることで、実効性を担保します。ビジョンは状況に応じて修正・更新される仕組みも備えており、時代の変化に対応できる柔軟性を持っています。
この二段構えにより、「理念と実行」の両立が図られているのが広域リージョン連携の特徴です。
相乗効果と分野横断的な取り組み
広域リージョン連携の大きな意義は、参加主体がそれぞれの強みを持ち寄り、相乗効果を発揮できる点にあります。例えば以下のような連携が考えられます。
- 産業分野:大学の研究成果を企業が事業化し、自治体が規制緩和や補助金で後押しする。
- 観光分野:隣接する地域同士が観光ルートをつなぎ、広域的なブランドを確立する。
- 交通分野:鉄道会社・バス事業者・自治体が協力し、MaaSを導入して住民や観光客の移動をスムーズにする。
これらの取り組みは、一つの自治体や組織だけでは実現が難しいものです。しかし、広域リージョンという枠組みを通じて結びつくことで、全体としての価値が高まり、結果として地域の持続可能性が強化されます。
さらに、分野横断的な取り組みを推進できるのも広域リージョン連携の特徴です。産業・観光・交通はそれぞれ独立しているように見えますが、実際には密接に関連しています。例えば観光を振興するには交通インフラが不可欠であり、観光需要が高まれば地域産業への波及効果も期待できます。単独分野ではなく横断的に施策を展開することが、広域リージョン連携の本質といえるでしょう。
中長期的な共通ビジョンの重要性
広域リージョン連携が従来の取り組みと異なるのは、短期的な事業連携にとどまらず、中長期的な共通ビジョンを描くことに重点を置いている点です。単発のイベントや短期間の補助金事業では、持続的な地域の成長は難しいという反省が背景にあります。
そのため、広域リージョン連携では「5年程度のプロジェクト期間」を基本としつつ、さらにその先の10年、20年を見据えた将来像を共有することが求められています。この共通ビジョンがあることで、参画団体は一過性の協力関係に終わらず、長期的なパートナーシップを築くことが可能になります。
広域リージョン連携宣言
広域リージョン連携を進める際の第一歩となるのが「広域リージョン連携宣言」です。これは、参画する自治体や経済団体、企業、大学などの多様な主体が共同で作成し、公表する文書であり、広域リージョン全体としての意思を明確に示すものです。言い換えれば、連携の「憲章」や「旗印」にあたります。
宣言の内容
連携宣言書には、必ず以下の項目が記載されます。
- リージョンの名称と区域
どの範囲を「広域リージョン」と呼ぶのかを明確にする。複数の都道府県にまたがることが条件であり、単なる県内連携ではなく広域的なスケール感が求められます。 - 参画する団体の名称
地方公共団体だけでなく、必ず経済団体を含めることが必須とされています。その上で企業や大学、研究機関なども加わり、多様な構成となります。 - 目指すべき姿(将来像)
広域リージョンがどんな未来を実現したいのかを理念として掲げます。これが後に策定する「連携ビジョン」の基盤となります。 - 想定する取り組み分野
おおむね産業振興・観光・交通の3分野が想定されており、地域の持続可能性やイノベーション創出につながることが重視されます。
想定される取り組み分野
宣言で例示されている分野には、以下のようなものがあります。
- 産業振興:産業クラスターの形成、スタートアップ支援、農林水産物の輸出促進など
- 観光:文化・スポーツを含む地域資源を活用した観光振興
- 交通:MaaS(複数の交通手段を統合し、検索・予約・決済を一括化するサービス)の推進
いずれも単一の自治体では効果が限定されがちな分野ですが、広域で取り組むことでスケールメリットや波及効果が期待できます。
宣言の意義
この宣言は単なる形式的な文書ではなく、以下の点で重要な意味を持ちます。
- 合意形成の証明
多様な主体が「共通の方向性を持つ」ことを内外に示す効果があります。 - ビジョン策定の前提
連携ビジョンを策定する際の土台となり、プロジェクトの方向性を揃える役割を果たします。 - 国との連携の基礎
宣言が公表されることで総務省に送付され、国の助言や支援の対象となります。
また、参画団体の増減や情勢の変化に応じて、宣言は変更・廃止も可能です。これにより、柔軟に枠組みを更新できる仕組みとなっています。
広域リージョン連携宣言は、広域連携を「理念から実行へ」進める最初のステップです。多様な主体が共通の旗印を掲げることで、単なる寄り合い的な協議体から、実効性のあるプロジェクトを進めるための基盤が整うのです。
広域リージョン連携ビジョン
「広域リージョン連携宣言」が旗印を掲げる段階だとすれば、「広域リージョン連携ビジョン」はその旗印をどのように現実化していくのかを示す「実行計画」の位置づけにあたります。宣言が理念を共有するための文書であるのに対し、ビジョンは中長期的な将来像を描き、具体的なプロジェクトをどのように展開するのかを体系的にまとめたものです。
ビジョンに記載する内容
広域リージョン連携ビジョンには、以下のような要素が盛り込まれることが定められています。
- 目指すべき姿(中長期的な将来像)
広域リージョンがどのような地域像を実現したいのかを明確にします。例えば「観光と先端産業が融合した国際的な地域拠点」や「脱炭素社会のモデルとなる広域圏」など、将来のビジョンを具体的に示すことが求められます。 - ロードマップ
その将来像を実現するための道筋を整理します。複数のプロジェクトをどう連携させ、どの順序で進めるのか、目標やスケジュールを含めた全体像を提示することが重要です。 - 具体的なプロジェクト内容
- プロジェクトの名称
- 実施主体(自治体、企業、大学など複数の団体)
- 関連する国の計画との位置づけ(国土形成計画、北海道・沖縄振興計画など)
- 役割分担や実施体制
- 事業費(必要な予算、年度ごとの見込み)
- 広域で取り組むことによる効果(単独で実施する場合との違い)
- 実施期間(おおむね5年以内)
これにより、理念と実務をつなぐ橋渡しが行われます。
多様な主体による実行体制
プロジェクトの実施主体は、必ず複数かつ多様な団体で構成される必要があります。自治体だけ、企業だけといった偏った構成は認められず、行政・産業・学術の連携が不可欠です。また、必要に応じてリージョン外の主体を加えることも可能であり、柔軟な組織設計が想定されています。これにより、より実効性のある推進体制が整えられます。
ビジョンの検証と更新
広域リージョン連携ビジョンは一度作れば終わりではありません。社会経済の情勢は常に変化するため、ビジョンに基づくプロジェクトの進捗や効果を適時に検証し、必要があれば改定を行うことが求められます。軽微な変更であれば迅速に、重大な変更の場合は構成団体間の協議を経て修正を行う仕組みとなっています。こうした柔軟性によって、ビジョンが「絵に描いた餅」で終わらず、持続的な実行力を持つよう設計されています。
ビジョンの意義
この仕組みの意義は大きく分けて三つあります。
- 中長期的な方向性を示す
広域リージョン全体が共通の未来像を共有することで、取り組みが一過性ではなく持続的なものとなります。 - プロジェクトの実効性を高める
誰が何を担い、どんな効果を出すのかを明確にすることで、実行力が担保されます。 - 国の支援との接点をつくる
ビジョンは総務省に送付され、関係府省との調整や支援策の対象となる基礎資料となります。
国による支援策
広域リージョン連携は、自治体や企業など地域の多様な主体が自発的に協力して進める取り組みですが、その実効性を高めるためには国の後押しが不可欠です。総務省を中心に、関係府省が連携して多角的な支援を行う仕組みが整えられています。
総務省の役割
まず総務省は、広域リージョン連携を推進する「ハブ」としての役割を担います。
- 助言・調整:広域リージョン連携宣言や連携ビジョンの策定段階で、事前相談があれば助言を行い、関係府省との連絡調整も担います。
- 情報提供:策定されたビジョンに基づくプロジェクトに対して、利用可能な支援策や補助金情報を分かりやすく提供します。
- 要望対応:リージョンから新たな支援ニーズが出れば、関係府省に検討依頼を行い、制度改善や支援拡充につなげます。
このように総務省は、現場と国の施策をつなぐ「調整役」として機能します。
具体的な支援の柱
国の支援は大きく三つの柱で構成されています。
- 新しい地方経済・生活環境創生交付金の活用
連携ビジョンに基づくプロジェクトのうち、交付金の目的に合致するものについて支援が行われます。地域経済や生活環境を改善する事業であれば、広域的なプロジェクトにも適用される可能性があります。 - 関係府省の補助事業の活用
各省庁が所管する補助事業と連携する形で支援を受けられる点が大きな特徴です。例えば、- 経済産業省:中小企業の成長投資支援、スタートアップ支援、研究開発助成
- 国土交通省:MaaS推進、社会資本整備交付金、物流脱炭素化事業
- 文部科学省:半導体人材育成拠点形成、大学を中心とした共創プログラム
- 農林水産省:輸出産地モデル形成、フードテック支援
- 環境省:脱炭素型循環経済システム構築、気候変動適応地域づくり
などがあり、分野横断的に多様な事業を組み合わせることが可能です(PDF別紙の補助事業一覧参照、p.8)。
- 規制緩和等の検討
広域的なプロジェクトを進める際に既存の規制が障害となる場合、地方分権改革の仕組みを通じて規制緩和が検討されます。たとえば、ドローン配送や次世代交通システムの導入には新しい制度設計が必要となる場面が想定されます。
支援策の意義
これらの支援策には三つの大きな意義があります。
- 資金面での安心感
広域プロジェクトはスケールが大きいため、自治体や民間だけで賄うのは困難です。交付金や補助事業の活用は資金調達を容易にし、挑戦を後押しします。 - 分野横断的な取り組みの実現
産業、観光、交通、環境、人材育成など複数の分野にまたがる事業を、省庁の縦割りを超えて進めやすくなります。 - 制度的な柔軟性の確保
規制緩和を含む制度的な支援により、従来の仕組みでは難しかった事業にも挑戦できる環境が整います。
国の支援は単なる補助金提供にとどまらず、助言・制度調整・規制緩和まで含めた包括的なものです。広域リージョン連携の成功には、地域の主体性と国の後押しをどう組み合わせるかが重要となります。自治体と民間が主体的にビジョンを描き、国が制度面・資金面で支える。この役割分担こそが、人口減少時代における持続可能な地域戦略の中核といえるでしょう。
期待される効果と今後の展望
広域リージョン連携は、単なる行政の枠組みを超え、自治体・企業・大学・研究機関など多様な主体が一体となって進める地域戦略です。この仕組みがもたらす効果は多方面に及びます。ここでは主な効果と、今後の展望について整理してみましょう。
経済活性化と産業クラスター形成
まず大きな効果が期待されるのは、地域経済の活性化です。複数の地域が力を合わせることで、単独では難しかった規模の大きな産業クラスターを形成できるようになります。特にスタートアップ支援や農林水産物の輸出促進などは、供給力・販路開拓力を広域で補完し合うことで相乗効果を発揮します。これにより、雇用の創出や若者の定着にもつながる可能性があります。
観光の広域展開とブランド化
観光分野でも広域連携の強みが活きます。県境を超えた観光ルートの整備や、複数地域の資源を組み合わせた観光商品の開発は、一つの自治体だけでは難しい取り組みです。広域的に観光資源をつなげることで、長期滞在型の観光やインバウンド需要に対応しやすくなり、地域全体としての「ブランド力」を高めることができます。文化やスポーツを観光に結びつける動きも、広域スケールだからこそ可能になります。
交通・物流インフラの最適化
交通分野では、MaaS(Mobility as a Service)の導入が注目されています。鉄道、バス、フェリー、タクシーなどを統合し、検索や予約、決済を一括で行える仕組みは、自治体の境界を超えて初めて効果を発揮します。さらに物流の効率化や脱炭素化、ドローン配送拠点の整備なども広域で取り組むテーマです。これにより、移動や物流の利便性が高まり、住民の生活の質の向上にもつながります。
人材育成とイノベーション
広域リージョン連携の特徴は、大学や研究機関が積極的に参画する点にもあります。これにより、高度専門人材の育成や研究開発の成果を地域で活用する仕組みが整います。たとえば、半導体や環境技術の人材育成拠点を広域で形成することで、企業の需要に応えつつ、新たな産業分野を切り拓くことが可能になります。産学官が一体となった取り組みは、イノベーションの創出に直結します。
持続可能な地域づくりへの貢献
環境やエネルギーの分野でも、広域連携は重要です。脱炭素型の社会システムや循環型経済の構築は、単一の自治体だけではスケール不足ですが、広域で資源や技術を共有すれば大きな成果を上げられます。加えて、気候変動適応や生物多様性保全といったテーマも広域的な視点で取り組むことで、持続可能な地域づくりに貢献できるでしょう。
今後の課題と展望
もっとも、広域リージョン連携には課題も存在します。一つは、多様な主体の合意形成の難しさです。自治体、企業、大学、住民など、利害の異なる主体が同じ方向を向くには、強いリーダーシップと丁寧な調整が不可欠です。二つ目は、プロジェクトの持続性です。単発の補助金事業に依存してしまうと、制度が終わった途端に取り組みも止まってしまうリスクがあります。長期的なビジョンに基づいた仕組みづくりが求められます。
今後の展望としては、広域リージョン連携が全国各地で展開され、それぞれの地域が独自の強みを活かしながら競い合い、学び合う「広域連携のエコシステム」が形成されることが期待されます。成功事例が積み重なれば、他地域への波及効果も大きく、結果として日本全体の地方創生につながる可能性があります。
参考資料
広域リージョン連携推進要綱(総務省)