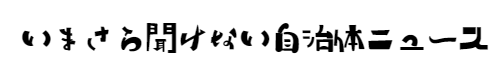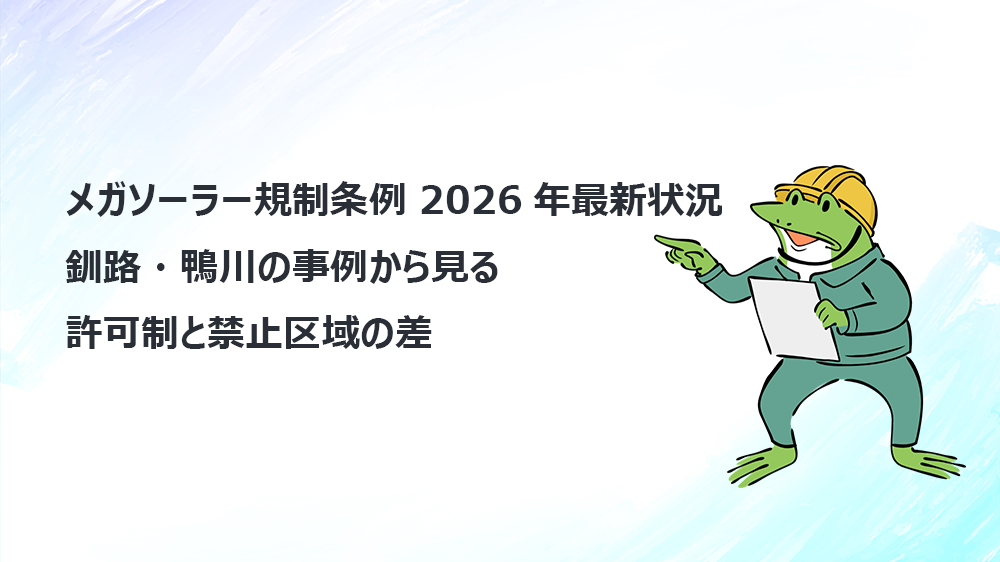「脱炭素」の旗印の下、全国の山林で急速に広がった大規模太陽光発電(メガソーラー)。しかし、2026年現在、その風景は劇的な転換期を迎えています。
かつては国の「再生可能エネルギー最優先」の方針を背景に、地方自治体の反対を押し切る形で強引に進められるケースも目立ちましたが、今や状況は一変しました。2025年から2026年にかけて、釧路市(北海道)や鴨川市(千葉県)といった象徴的な地域で、「自治体による規制」が国や事業者の計画を事実上ストップさせる事態が相次いでいます。
特に注目すべきは、単なる「反対運動」にとどまらない、条例による「許可制」の厳格化と「禁止区域(ゾーニング)」の設定です。2026年1月に本格施行された釧路市の条例や、鴨川市で起きたFIT認定失効という事態は、今後の国内再エネ事業のあり方を根本から変える可能性を秘めています。
釧路湿原の危機と「ノーモア・メガソーラー宣言」の実効性
メガソーラー規制の最前線として今、全国の自治体から熱い視線を浴びているのが北海道釧路市です。
釧路湿原という世界に誇る生態系を抱えながら、その周辺部では「国立公園の外側」という法の隙間を突いた大規模開発が相次いできました。これに対し、釧路市は2025年6月に全国で2例目となる「ノーモア・メガソーラー宣言」を公表。さらに2026年1月、より強力な法的拘束力を持つ新条例(釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例)を本格施行させました。
「特定保全種」を守るための厳しい不許可基準
釧路市の規制が画期的なのは、単なる景観保護にとどまらず、具体的な「生物種」を軸に許可判断を下す点にあります。条例では、以下の5種を「特定保全種」に指定しています。
- タンチョウ、オジロワシ、チュウヒ、オオジシギ、キタサンショウウオ
これらの希少生物の生息可能性が高いエリア(市街化調整区域等)は「特別保全区域」に設定され、事業者には専門家による生息調査と保全計画の作成が義務付けられました。もし野生生物の生息に重大な影響を及ぼす恐れがあると判断されれば、市は設置を「不許可」にすることができます。
条例施行後の「新規届出ゼロ」が物語る抑止力
特筆すべきは、2026年1月の本格施行以降の動きです。最新の報道(2026年1月時点)によれば、条例の適用が始まった昨年10月以降、市内での新規建設計画の届け出は一件もありません。
かつては「ガイドライン(お願い)」ベースでの協力要請しかできなかった自治体が、条例によって「義務」を課し、不許可というカードを手にしたことで、安易な開発計画を門前払いする強力な抑止力が働いていると言えます。
釧路モデルが示す「許可制」の限界と可能性
しかし、課題も残っています。この条例が適用されるのはあくまで「施行後」の案件であり、それ以前に着工・認定された既設のメガソーラーを遡って排除することはできません。
釧路の事例が示したのは、「一度壊れた自然は戻らないが、これ以上の破壊は自治体の意思(条例)で食い止められる」という希望です。この成功体験は、同様の希少種を抱える全国の自治体にとって、強力な実務マニュアルとなっています。
千葉・鴨川の教訓――「命」に関わる崩落リスクとFIT認定失効の衝撃
「生態系」を主眼に置いた釧路に対し、千葉県鴨川市のメガソーラー計画は、住民の「命の安全」を巡る戦いでした。そして2026年1月9日、この計画に終止符を打つ決定的なニュースが飛び込みました。資源エネルギー庁が、同事業者の「FIT(固定価格買取制度)認定」の失効を確認したのです。
「崩落の恐怖」が動かした行政の壁
鴨川市の先達山(せんだつやま)周辺で計画されていたこの事業は、土砂災害警戒区域を含む急傾斜地での開発を伴うものでした。
- 背景: 2021年の静岡県熱海市での土石流災害以降、山林開発への住民の不安はピークに達していました。
- 行政の姿勢: 鴨川市長や千葉県知事は、事業者が提出した防災対策の不備を鋭く指摘。「課題が解決されない限り、着工は認めない」という強い姿勢を貫きました。
「認定失効」という致命的な決着
今回の認定失効は、単なる工事の中断ではなく、事業の「経済的死」を意味します。
- 失効の理由: 認定から一定期間内に運転を開始できない、あるいは事業計画に不備がある場合、FIT認定は失効します。
- インパクト: 市場価格より高い価格で売電できる権利を失ったことで、莫大な開発コストを回収する見込みが消滅。事業の継続は事実上、不可能となりました。
改正盛土規制法が「追い風」に
2025年から本格運用が始まった「改正盛土規制法」も大きな役割を果たしました。かつては林地開発許可さえ得てしまえば自治体は介入しにくかったのですが、現在は「安全が担保されない盛り土」に対して自治体が非常に強い停止命令権を持てるようになっています。
鴨川の事例は、自治体が「安全」という絶対的な大義名分を掲げ、国や県と連携してデータの不備を突き続けることで、最終的に事業そのものの収益性を枯渇させて白紙化できることを証明しました。
徹底比較――「許可制」と「禁止区域(ゾーニング)」は何が違うのか?
釧路や鴨川の事例を受け、現在多くの自治体が条例制定を急いでいますが、その手法は大きく「許可制の厳格化」と「禁止区域(ゾーニング)の設定」の2パターンに分かれます。
どちらの手法を採るかによって、事業者へのインパクトや法的なリスクが異なります。
許可制の厳格化(釧路モデル)
「条件が整えば設置できるが、そのハードルを極限まで上げる」手法です。
- 仕組み: 「住民説明会の開催」「専門家による生態系調査」「防災計画の詳細提出」などを許可の必須条件とします。
- メリット: 完全に拒絶するわけではないため、事業者からの「営業の自由を阻害している」という法的訴訟リスクを抑えやすい。
- デメリット: 事業者が条件をすべてクリアした場合、最終的に不許可にするのが難しい。実務上の「持久戦」になりやすく、自治体側のチェック体制にも高い専門性が求められます。
禁止区域の設定(ゾーニング・鴨川等の教訓)
「この場所には絶対に建てさせない」とあらかじめエリアを指定する手法です。
- 仕組み: 土砂災害警戒区域、重要景観地、災害危険箇所などを条例で「設置禁止区域」に指定します。
- メリット: 入口でシャットアウトできるため、不毛な交渉や紛争を未然に防げます。事業者は最初からその土地での開発を断念するため、最も抑止力が高い。
- デメリット: 「禁止」という強い制限をかけるため、客観的・科学的な根拠(ハザードマップや景観条例との整合性)が不可欠です。
比較表:自治体が選ぶべき規制のカタチ
| 項目 | 許可制(実務・ハードル型) | 禁止区域(ゾーニング型) |
| 主な目的 | 調和・合意形成の強制 | 災害防止・環境の絶対保護 |
| 事業者への影響 | 開発コストと時間の増大 | 開発そのものの断念 |
| 自治体の負担 | 継続的な審査・監視が必要 | 指定時の科学的根拠の策定が必要 |
| 適した場所 | 市街地近郊、耕作放棄地など | 山林、急傾斜地、国立公園周辺 |
結論:2026年のトレンドは「ハイブリッド型」
最新の条例の傾向として、「急傾斜地などは絶対禁止」としつつ、「それ以外は厳しい許可制」にするハイブリッド型が主流となっています。
特に2025年施行の改正盛土規制法により、自治体は「盛り土」を理由にした禁止区域の設定が法的にやりやすくなりました。これにより、鴨川のように「認定失効」まで追い込むための法的な足場が固まったと言えます。
【2026年版】自治体が手にした「新・三種の神器」
釧路や鴨川の事例を受け、現在多くの自治体が条例に盛り込んでいる強力な規制策は、大きく分けて3つの柱に集約されます。これらは単なる「マナー」ではなく、違反すれば氏名の公表や過料、さらには事業継続を困難にさせる「実効性のある武器」として機能しています。
「同意書」の義務化――周辺住民への拒否権付与
かつては「説明会の開催」だけで免罪符となっていたケースが目立ちましたが、最新の条例では「周辺住民および自治会による同意書の提出」を許可の必須条件とする例が急増しています。
- 実務のポイント: 単に「説明した」という事実だけでなく、地域の代表者が納得し、署名捺印した書類がない限り、市町村長が許可を出さない仕組みです。
- 狙い: 事業者に対して、地域貢献策や景観対策を「住民が納得するレベル」まで引き上げさせる強力な交渉カードとなります。
独自基準の「廃棄費用積立」と「保証金」
国(資源エネルギー庁)も2022年から廃棄費用の外部積立を義務化していますが、多くの自治体は「国の基準では不十分」と考えています。
- 上乗せ規制: 国の積立が「売電期間の後半10年間」から始まるのに対し、自治体条例では「着工前」または「運転開始直後」からの全額積立を求めるケースがあります。
- 原状回復の担保: 倒産や夜逃げに備え、自治体が指定する口座に「撤去保証金」を供託させることで、将来の「負の遺産化」を徹底的に防ぎます。
改正省エネ法・再エネ特措法との連動(罰則の適用)
2026年度から本格稼働する国の規制と、自治体の条例が「連携」し始めている点も重要です。
- 報告義務と罰則: 工場や店舗の屋根への設置目標が「努力義務」から「報告義務」へ格差化される中、自治体は報告に虚偽があった場合に「氏名の公表」や「50万円以下の罰金」といった社会的・経済的制裁を科す仕組みを整えています。
- 行政指導の強化: 条例違反を放置した場合、経産省へ報告し、「FIT/FIP認定の取り消し」を直接働きかけるスキームが確立されつつあります。
実務者が注目する「地域共生」の新たな定義
これらの「三種の神器」を盛り込むことで、自治体は「国が認定したから止められない」という受動的な立場から、「地域のルールに従わない者は参入させない」という主体的な立場へと移行しました。
これにより、これまでの「開発の自由」と「環境保全」の力関係は、2026年を境に完全に逆転したといっても過言ではありません。
政府の「GX推進」と地方の「ブレーキ」――ネジレが生む2026年以降の展望
ここまで見てきたように、2026年のメガソーラーを取り巻く環境は、国の「脱炭素推進(攻め)」と、自治体の「地域保護(守り)」が真っ向から衝突する、激しい「ネジレ」の中にあります。
選挙公約に見る「再エネ」の温度差
2月8日に投開票を控えた衆院選において、各党の公約には「再エネの主力電源化」や「GX(グリーントランスフォーメーション)の加速」という言葉が並びます。しかし、釧路や鴨川で起きたような「現場の対立」にどう向き合うかという具体策については、党によって大きな温度差があります。
- 与党: 原発再稼働とセットでの再エネ推進を掲げつつ、2026年中に電気事業法を改正し、第3者機関による「安全審査」を義務付けるなど、ようやく重い腰を上げ始めました。
- 野党: 「地産地消」「地域共生」をキーワードに、地方自治体の規制権限をより明確に法律で裏付けるべきだとする主張が目立ちます。特に、維新や立憲は、地方の拒否権を尊重する姿勢を強めています。
「山」から「屋根」へ。ルールは変わった
この記事の結論として、事業者が直面している現実は明白です。 もはや、「国(経産省)が認めたから、地方(自治体・住民)は口を出すな」という理屈は、2026年の日本では通用しなくなりました。
今後は、山林を切り拓く大規模開発は、自治体条例による「禁止区域」や「厳しい許可制」の壁に阻まれ、コスト・リスクともに増大し続けるでしょう。一方で、2026年4月から本格化する「屋根置きパネル」の設置目標義務化に見られるように、「既にある人工物(屋根・駐車場)の活用」へと投資の主戦場が移っていくのは確実です。
自治体ニュースとしての視点
私たち市民や自治体担当者にとって重要なのは、自らの町の条例が「釧路モデル(生態系)」や「鴨川モデル(災害防止)」のように、最新の法的武器を備えているかをチェックすることです。
2月8日の選挙結果を受けて、国のエネルギー政策がどう微調整されるのか。そして、それを受けて自治体条例がさらにどう進化するのか。本サイトでは引き続き、政府と地方行政の「ネジレ」の最前線を追っていきます。