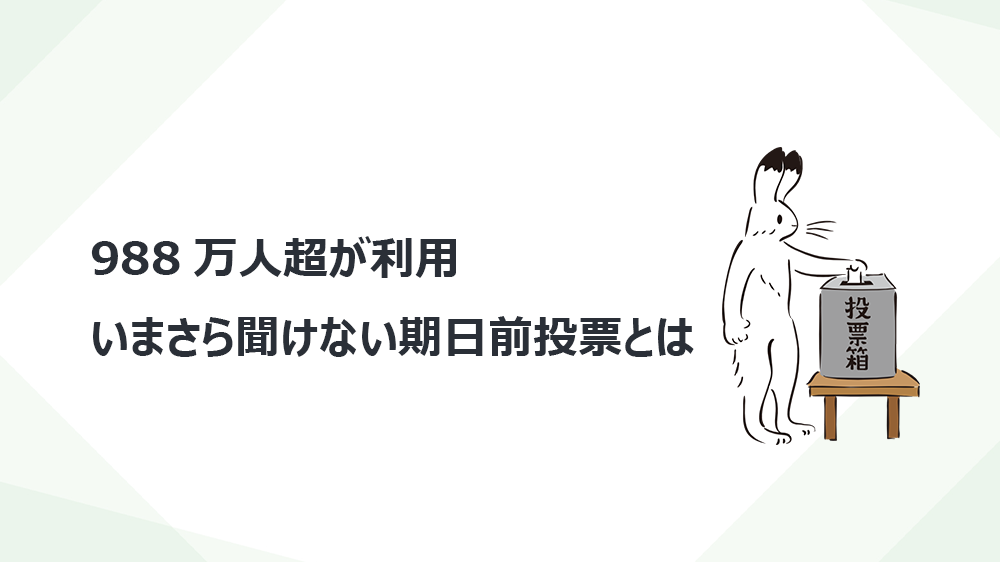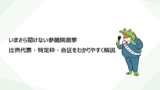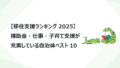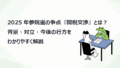期日前投票を利用する人が、いまや全国で988万人超にのぼっています。選挙といえば「当日行くもの」と思っていた方も、この数字を見て驚いたのではないでしょうか?
実は、仕事や旅行、体調の都合などで当日に投票できない人のために用意されている「期日前投票」は、今や選挙のスタンダードとも言える存在です。
でも、「どうやってやるの?」「何を持って行けばいいの?」と疑問を持ったまま、なんとなく利用してこなかった人も多いはず。
この記事では、期日前投票の基本から手順、注意点まで、いまさら聞けないポイントをやさしく丁寧に解説します。
期日前投票ってなに?
選挙には、原則として「投票日」が決められています。たとえば「7月15日(日)」のように、1日だけが正式な投票日になります。ふつうはその日に、自分の住んでいる地域の投票所に行って投票するのが基本です。
しかし、すべての人がその日に投票に行けるわけではありません。たとえば、その日は仕事があってどうしても行けない人や、旅行や出張で地元にいない人、あるいは病気や出産などで体調が万全でない人もいます。そうした人たちのために用意されているのが「期日前投票(きじつまえとうひょう)」という制度です。
「期日前」という言葉のとおり、正式な投票日の“前の日”に、あらかじめ投票を済ませてしまう仕組みです。つまり、「投票日には行けないけど、事前に時間をつくって投票したい」という人が、もっと気軽に、もっと柔軟に投票できるようにするための制度なんです。
この制度が生まれる前、つまり昔の選挙では、投票日に投票に行けない場合は「不在者投票」という別の手続きが必要でした。でもそれは、手続きがちょっと面倒だったり、特定の理由がないとできなかったりして、使いにくいという声もありました。
そこで2003年の公職選挙法の改正によって、「期日前投票制度」がスタートしました。この制度は、理由を問わず「投票日に行けない予定の人」なら誰でも利用できるという、よりシンプルで使いやすい制度です。実は今、選挙のたびにこの制度を利用する人がどんどん増えていて、全体の3人に1人以上が期日前投票を使っていると言われています。
ここで、少し具体的な例をあげてみましょう。
たとえば、ある高校生の兄が社会人1年目で働いているとします。投票日は日曜日だけれど、その日はシフト勤務でどうしても仕事を休めない。でも、選挙には行きたい。そんなとき、彼は仕事の前後や休日に「期日前投票所」に行けば、正式な投票日より前にちゃんと投票をすませることができます。これなら、自分の意思をきちんと選挙に反映できるわけです。
また、大学生で遠方に住んでいる人が、ちょうど選挙期間中に地元に帰省していたとします。地元を離れる前に期日前投票をすれば、地元の投票権を使い切ることができます。このように、期日前投票はライフスタイルが多様な現代社会にとても合った制度なんです。
さらに、選挙当日は投票所が混みあったり、天気が悪かったりして、思ったように動けないこともあります。そういう不確定な要素を避けるために、早めに投票しておくという人も多くなっています。とくにコロナ禍のときは「密を避けたいから」という理由で期日前投票を選ぶ人が増えました。
そしてもう一つ、大事なポイントは「誰でも使える」ということです。「期日前投票=特別な理由がある人だけ」というイメージを持っている人もいるかもしれませんが、実はそうではありません。投票日に投票できない予定なら、ちょっとした理由でも構わないのです。たとえば、「部活の大会があるかもしれない」とか「家族で出かける予定がある」といった理由でも、十分利用できます。
もちろん、制度を使うにはルールがあります。実際に期日前投票をするときは、「宣誓書」という書類に「投票日に行けない予定の理由」を書く必要があります。ただし、その内容は自己申告でOKですし、「旅行」「仕事」「冠婚葬祭」など、大まかな項目から選ぶ形式なので、あまり難しく考える必要はありません。
こうした背景から、期日前投票は今ではごく普通に使われている投票方法となりました。選挙管理委員会も「もっと便利に、もっと多くの人に選挙に参加してもらう」ことを目指して、この制度を広めています。選挙を「行ける人だけのイベント」にしないための工夫となります。
次の選挙では、「その日は忙しいから行けないかも」と思ったら、ぜひこの制度を思い出して、活用してみてください。
どうして期日前に投票できるの?その目的とメリット
「選挙の投票って、本来は投票日にするんじゃないの?」
そう思った人もいるかもしれません。たしかに昔は、投票日に行けない人は「不在者投票」というちょっと手間のかかる制度を使うしかありませんでした。でも今は、もっと気軽に、もっと多くの人が投票できるようにと考えられたのが「期日前投票」という制度です。
このセクションでは、「なぜわざわざ期日前に投票できるようにしたのか」という制度の目的と、実際に使うことのメリットを詳しく見ていきましょう。
期日前投票が生まれた背景
そもそも期日前投票という仕組みが始まったのは、2003年のことです。それ以前にも「不在者投票」という方法で投票日以外の投票ができましたが、これは「病気」「出張」「旅行」など、ある程度しっかりとした理由がないと使えず、しかも手続きも複雑でした。
たとえば、「出張の予定があります」と証明するために書類を提出したり、別の投票所に行って紙に記入したりと、ちょっと大変だったんですね。
そのため、制度はあっても利用する人は少なく、「投票に行きたくても行けない人」が多くいました。とくに働き世代や子育て中の人たちの間では「時間が合わないから行けない」という声が多く、結果として投票率の低下が課題になっていました。
そこで、もっと多くの人が投票しやすいようにと作られたのが「期日前投票制度」です。理由の証明はいらず、簡単な宣誓書を記入するだけで投票できるようになったことで、一気に使いやすくなりました。
期日前投票の目的は「投票しやすくすること」
制度がある理由は「多くの人に投票してもらいたいから」。
民主主義の国では、国民の声を政治に反映させることがとても大事です。でも、投票日が決まっていて、しかもその日にしか投票できないとなると、さまざまな事情で行けない人が出てきてしまいます。
たとえば、
- 仕事が入っている
- 家族の世話で外出できない
- 地元を離れている
- スポーツ大会がある
- 災害や大雨の予報が出ている
こういった理由がある人たちに「その日は行けません」とあきらめてもらうのではなく、「じゃあ前もって投票しておきましょう」と言えるようになったのが、期日前投票の大きな意義です。
実際に増えている利用者数
期日前投票を使う人は年々増えています。総務省のデータによれば、国政選挙では全体の3〜4割の人が期日前投票を利用していることもあるほどです。
とくに若い世代や働く世代での利用が目立っており、「平日は忙しくて時間がとれない」「日曜に家族で出かける予定がある」といった理由で、前倒しで投票する人が増えています。
また、大きな選挙になると、各地のショッピングモールや駅ビルなどにも臨時の投票所が設置されることがあります。これは、「生活動線の中に投票所をつくる」というアイデアで、よりアクセスしやすくする工夫です。
期日前投票のメリット
ここからは、実際に私たちにとってどんな良いことがあるのか、期日前投票のメリットをいくつか紹介していきます。
1. 自分の都合で投票できる
もっとも大きなメリットは「自分の予定に合わせて投票できる」ことです。投票日は1日しかありませんが、期日前投票は公示日の翌日から前日まで、数日間にわたって利用できます。仕事や学校、イベントなどの予定とぶつかっても、自分の空いている日に済ませておけば安心です。
2. 混雑を避けられる
選挙当日は、特に朝や夕方に投票所が混雑しがちです。でも期日前投票なら、時間帯や日にちを選べるので、比較的すいている時間に行くことができます。感染症が心配な時期や、体調に不安がある人にも安心です。
3. 災害や天気の影響を避けられる
近年では、大雨や台風、地震などの自然災害が選挙当日に重なるケースもあります。そうなると投票所への移動が難しくなったり、安全面での不安が出たりします。期日前投票を利用すれば、そういったリスクも避けることができます。
4. 気持ちが新しいうちに投票できる
選挙前にニュースや候補者の演説を聞いて「この人にしよう」と思ったタイミングですぐに投票できるのもメリットの一つです。投票日まで日があると、気が変わったり忙しくなって忘れてしまうこともありますが、期日前なら思い立ったその日に行動に移せます。
5. 家族や友人と予定を合わせやすい
「家族で一緒に投票に行きたいけど、投票日に全員の予定が合わない」という場合にも、期日前投票は便利です。たとえば、週末に家族で投票に行って、そのあとにランチを楽しむ、というような使い方もできます。
投票率アップのカギにも
こうしたメリットが多くの人に広まり、結果として「投票率の向上」にもつながっています。選挙に参加する人が増えれば、その分だけ民意が正しく政治に反映されやすくなります。
とくに若い世代の投票率は他の年代と比べて低くなりがちですが、期日前投票を活用することで、「投票に行きたいけど行けない」というギャップを埋めることができます。たとえば、大学のキャンパス内に投票所が設けられたケースもあり、学生が講義の合間に投票できるよう工夫されているのです。
このように、期日前投票は「投票しにくさ」を減らすためのとても重要な制度です。選挙のあるとき、「その日は無理かも」と思っても、あきらめる必要はありません。むしろ、自分の生活スタイルに合わせて投票する手段があるというのは、現代らしい柔軟でスマートな方法だといえるでしょう。
いつからいつまで?期日前投票の期間
期日前投票は「投票日に行けない人のための仕組み」とお伝えしました。では実際に、いつから期日前投票ができるのでしょうか? そして、いつまでなら間に合うのでしょうか?
期日前投票の期間や時間帯、どこで確認できるかなどをくわしく紹介していきます。
公示(告示)の翌日から投票日の前日まで
期日前投票は、選挙の種類によって若干違いがありますが、基本的なルールは共通しています。
- 国政選挙(衆議院選挙や参議院選挙)では「公示日」の翌日から
- 地方選挙(知事選挙や市議会議員選挙など)では「告示日」の翌日から
つまり、選挙が始まる日(公示日または告示日)の翌日から、投票日の前日までが期日前投票の期間になります。投票日は基本的に「日曜日」とされているため、期日前投票の最終日はその前の土曜日です。
例:衆議院選挙の場合
たとえば、衆議院議員選挙が「7月15日(日)」に行われるとします。この場合のスケジュールは次のようになります。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 7月3日(水) | 公示日(選挙開始) |
| 7月4日(木) | 期日前投票スタート |
| 7月13日(土) | 期日前投票最終日 |
| 7月14日(日) | 本来の投票日(当日) |
このように、期日前投票の期間は「投票日の約10日前から前日まで」というのが一般的です。選挙によって日数は多少変わりますが、だいたい1週間から10日間のあいだに投票ができると思っておくといいでしょう。
投票時間は?朝から夜までやってるの?
次に、1日のうちで「何時から何時まで」投票できるかという点ですが、これは各自治体の選挙管理委員会が決めています。全国一律ではないので、住んでいる地域によって少し差があります。
ただし、よくある時間帯は以下の通りです。
- 午前8時30分から午後8時まで
- 午前9時から午後6時まで
中には、商業施設の中にある投票所では「午前10時から午後8時」といったケースもあります。
また、一部の地域では「日によって時間が変わる」こともありますので、正確な情報は「入場券(ハガキ)」や自治体の公式ホームページで確認するのがベストです。
どこで確認すればいい?
「この選挙の期日前投票、いつからできるの?」と思ったら、次のような方法で確認できます。
- 投票所入場券(ハガキ)をチェックする
選挙が近づくと、自宅に郵送されてくる「投票所入場券」。その中に、あなたが行くべき投票所や期日前投票の場所・日時が書かれています。 - 市区町村のホームページを見る
たとえば「○○市 期日前投票 〇年 選挙」と検索すれば、スケジュールと場所、時間などの情報がすぐに出てきます。 - 選挙管理委員会に問い合わせる
役所にある「選挙管理委員会」に電話をすれば、ていねいに教えてくれます。疑問があったときは気軽に問い合わせてみましょう。
早めの投票が安心
期日前投票の期間中は、日によって混雑具合が異なります。とくに最終日(土曜日)は、投票所がとても混むことがよくあります。多くの人が「明日はもう投票できないから」と、駆け込みで来るためです。
そのため、できれば「早めに」投票しておくのが安心です。とくに平日の午前中や午後の早い時間帯は比較的すいていることが多いです。
また、思わぬ用事や体調不良で行けなくなることも考えて、予定に余裕をもって行動しておくとよいでしょう。
休みの日に行きたいけど、期日前って平日だけ?
よくある誤解の一つが「期日前投票は平日しかできない」というものです。これは間違いです。実は、期日前投票は土曜日も日曜日も利用できます。
もちろん、投票日の「当日(日曜日)」は期日前投票は終了していて、通常の投票しかできませんが、その前の土日にはほとんどの自治体で開いています。
そのため、「平日は学校や仕事で無理だけど、週末なら時間がある」という人も安心して利用できます。
複数の投票所から選べる場合も
自治体によっては、期日前投票所が「市役所だけ」ではないこともあります。たとえば、
- 駅前のビル
- ショッピングモール
- 公民館
- 出張所
など、複数の場所に設置されることもあります。こうした場所では、投票所入場券に記載された以外の投票所でも投票できるケースがあるので、「通勤途中に寄る」「買い物のついでに立ち寄る」など、生活スタイルに合った方法で選ぶことができます。
まとめ
期日前投票は、「投票日の前日まで」に済ませられる、とても便利な制度です。
おもなポイントをまとめると次の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 投票できる期間 | 公示(告示)日の翌日〜投票日前日まで |
| よくある投票時間 | 8:30〜20:00 など(自治体により異なる) |
| 開いている曜日 | 平日・土日どちらもOK(最終日は混雑注意) |
| 確認方法 | 投票所入場券、市区町村HP、選挙管理委員会など |
選挙は、私たちが自分の声を社会に届けるチャンスです。「その日は無理かも」と思っても、期日前投票があれば、自分の都合に合わせてちゃんと意思表示ができます。
次のセクションでは、「どこでできるの?期日前投票所の場所」についてくわしく紹介していきます。どんな場所に投票所があるのか、駅前やショッピングモールにもあるって本当?といった疑問にもお答えします。
どこでできるの?期日前投票所の場所
期日前投票は「投票日の前日まで」なら何日かの間に済ませられるとお伝えしました。では、実際に「どこで投票すればいいのか?」という疑問に今回は答えていきます。
期日前投票は、住んでいる地域の「選挙管理委員会」が指定した場所で行います。これは、通常の投票所(投票日に行く場所)とは別の場所であることが多いので、注意が必要です。「あれ? いつもの小学校じゃないの?」ということがあるんです。
一番多いのは「市役所・区役所」などの庁舎
もっとも基本的で多くの人が利用する場所は、自分の住んでいる地域の「市役所」や「区役所」です。役所の中やその近くに、特設の期日前投票所が用意されています。
たとえば、東京都内であれば「○○区役所1階 特設会場」といった具合です。普段は手続きをする場所が、選挙のときだけ投票会場になるというイメージですね。
このような役所内の期日前投票所は、平日も土日も開いていることが多く、朝から夕方までしっかり対応してくれます。場所もわかりやすく、案内のスタッフもいるので、はじめての人でも安心です。
意外な場所にもある?ショッピングモール・駅前施設など
最近では、期日前投票所の「アクセスの良さ」や「立ち寄りやすさ」を考えて、役所以外の場所にも設置されるケースが増えています。
たとえば、次のような場所でも期日前投票ができることがあります。
- 駅に近いビルの会議室
- 商業施設(ショッピングモール、デパートなど)
- 大型スーパーの一角
- 公民館、地域センター
- 体育館や文化ホール
- 出張所(市民サービスセンターなど)
これらの場所は「サテライト会場」とも呼ばれることがあり、平日でも学校帰りや仕事帰りに立ち寄れるような位置に設けられているのが特徴です。
たとえば、「○○ショッピングセンター2階 特設会場」など、買い物ついでにふらっと立ち寄れる場所に投票所が設けられると、「せっかくここまで来たし投票していこうかな」と思える人が増えるのです。
こうした取り組みは、若い人や子育て中の世代、外出のついでに済ませたい人たちにとって、とても助かる制度となっています。
投票所は自分で選べるの?
「じゃあ、自分の家から一番近い投票所に行っていいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
原則として、自分が住民票を登録している自治体の期日前投票所であれば、どこでも利用できることが多いです。たとえば「○○市」に住んでいる人は、○○市内に設けられたどの期日前投票所でも投票できます。ただし、細かいルールは自治体によって異なるので、事前に確認することが大切です。
また、「選挙区が分かれている」ような自治体では、行ける場所が限られていることもあります。「入場券(ハガキ)」や市役所のサイトを見て、事前にチェックしておきましょう。
自分が行ける投票所を調べるには?
ここで、期日前投票所の場所や開いている時間を調べる方法を紹介します。
投票所入場券(ハガキ)を確認する
選挙が近づくと自宅に届く「投票所入場券」には、あなたが利用できる投票所の情報が記載されています。期日前投票所の場所や期間、時間帯もこのハガキに詳しく書いてあるので、まずはここをチェックしましょう。
自治体の公式ホームページをチェック
「○○市 期日前投票」と検索すれば、あなたの住んでいる市区町村の選挙ページにすぐたどり着けます。会場の地図やバリアフリー情報まで載っていることもあるのでとても便利です。
役所に電話で聞く
もしわからなければ、市区町村の「選挙管理委員会」に電話をすれば、丁寧に教えてくれます。はじめて選挙に行くという人でも、不安なく投票できるようにサポートしてもらえますよ。
期日前投票所には案内スタッフが常駐
はじめての場所で投票するのは少し緊張するかもしれませんが、期日前投票所には案内スタッフがいて、流れをサポートしてくれます。
「どこに並べばいいか」
「宣誓書ってどこに書くの?」
「ペンはどれ使えばいい?」
こうした疑問も、すぐに教えてもらえます。とくに若い人や高齢の方には、丁寧にサポートしてくれるので、安心して利用できます。
地域によって違う会場の工夫
一部の自治体では、独自の工夫をして期日前投票をもっと身近にしようとしています。
たとえば、
- 大学のキャンパス内に投票所を設けて、学生が授業の合間に投票できるようにしたり
- イベント会場の一角に設置して、来場者がそのまま投票できるようにしたり
- ドライブスルー形式の投票所を試験的に設けた事例もあります
こうした工夫は、「もっと投票しやすくしたい」「もっと投票率を上げたい」という思いから生まれているのです。
自分の生活に合った場所を選ぼう
期日前投票は、住んでいる地域の中で「複数の場所から選べることがある」というのが大きな特徴です。
役所だけでなく、駅前やショッピングセンター、公共施設にも投票所が設置されている場合があります。
| 投票所の例 | 特徴 |
|---|---|
| 市役所・区役所 | 一番オーソドックス。案内もしっかり |
| 商業施設・駅ビル | アクセスがよく、立ち寄りやすい |
| 公民館・出張所 | 地域密着でわかりやすい |
| 大学・イベント会場など | 特定層向けの工夫(学生・来場者など) |
生活の動線に合わせて、行きやすい場所を選べば、無理なく投票ができます。次の選挙では、自分にとって便利な投票所を選んで、ぜひ期日前投票を活用してみてください。
何を持っていけばいい?必要なもの
「期日前投票に行きたいけど、何を持って行けばいいの?」
はじめて選挙に行く人にとって、この疑問はとても自然なものです。選挙ってちょっと緊張するし、持ち物に不備があると投票できないのでは…と不安になりますよね。
でも大丈夫。期日前投票に必要な持ち物は、基本的にとてもシンプルです。このセクションでは、必ず持って行きたいもの、あれば便利なもの、忘れても大丈夫なことなどを、ひとつずつ丁寧に解説します。
基本の持ち物:投票所入場券(ハガキ)
まず、投票に行くときに「必ず持っていきたいもの」として挙げられるのが、「投票所入場券(とうひょうしょ にゅうじょうけん)」です。
これは、選挙の少し前にあなたの家に郵送されてくるハガキで、次のような情報が書かれています。
- あなたの名前・住所・生年月日
- 投票できる選挙の種類
- あなたが行くべき投票所の場所
- 投票できる日時(期日前投票・当日両方)
- 問い合わせ先の電話番号
この入場券は、いわば「あなたが有権者であること」を示す招待状のようなものです。これがあると、投票所での本人確認がとてもスムーズに行えます。
ハガキを持って行けば、選挙人名簿と照合して、すぐに受付が完了し、投票手続きに入ることができます。
もし入場券を忘れたら?なくても投票できるの?
ここがとても大事なポイントです。
実は、投票所入場券を忘れてしまっても、期日前投票はできます!
入場券がなくても、選挙人名簿にあなたの名前が登録されていれば、本人確認ができれば問題ありません。本人確認として使えるものは、たとえば以下のようなものです。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- 学生証(生年月日や住所の記載があるもの)
- パスポート など
本人確認の方法は自治体によって異なる部分もありますが、入場券を忘れたからといって「投票できない!」ということはありません。安心してください。
宣誓書の記入が必要
期日前投票をするときには、「なぜ投票日に行けないのか?」という理由を記入する「宣誓書(せんせいしょ)」という書類を提出する必要があります。
これはちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実際にはとてもシンプルな紙で、受付で用意されています。たいていは以下のような理由の選択肢からチェックする形式です。
- 仕事や学業があるため
- 冠婚葬祭(結婚式やお葬式など)があるため
- 旅行やレジャーの予定があるため
- 出産や病気、介護などの事情があるため
- 天候の悪化が予想されるため
- その他
これらの選択肢から該当するものを選んで、署名すればOKです。理由の内容を細かく書く必要はありませんし、証明書のようなものも必要ありません。
なお、宣誓書は事前に自宅で記入して持参することも可能です。各自治体のホームページからダウンロードできる場合がありますので、「混雑を避けたい」「時短したい」という方は活用してみるのもおすすめです。
その他、持っていると便利なもの
ここでは、絶対に必要ではないけれど、持って行くと便利なものをいくつか紹介します。
印鑑(いらないことがほとんど)
昔は必要だったこともありますが、現在の選挙では原則として印鑑は不要です。ただし、まれに必要となる地域があるかもしれませんので、心配な場合は持って行ってもよいでしょう。
メモや下書き(投票先を忘れないために)
投票所では「誰に投票するか」を紙に書く必要があります。でも、名前をうっかり忘れてしまったり、字があいまいだったりすると困りますよね。
そこで、「投票する候補者の名前をメモして持参する」という方法もあります。もちろん、投票所の中で見ながら書くことはできませんが、事前に見直しておくのはOKです。正確な名前を覚えておくための工夫です。
マスク(感染対策として)
現在ではマスクの着用が義務ではない場合も多いですが、人が集まる場所なので、体調に不安があるときや高齢者と接する機会が多い人は、マスクを着けていくと安心です。
忘れ物が心配な人へ:チェックリストで確認しよう
最後に、期日前投票に行く前に確認したいチェックリストを用意しました。出発前にぜひ見ておいてください。
| 持ち物 | 持った? |
|---|---|
| 投票所入場券(ハガキ) | |
| 本人確認書類(免許証など) | |
| 宣誓書(事前記入する場合) | |
| 投票先のメモ(必要なら) | |
| マスク(必要に応じて) |
期日前投票に必要な持ち物はとても少なく、基本は「入場券だけ」でOKです。
それがなくても、本人確認ができれば投票はできますし、宣誓書もその場で書けるので、あまり心配しすぎなくて大丈夫です。
選挙はあなたの声を社会に届ける大切な機会です。少しの準備をしておけば、安心して期日前投票に臨むことができます。次の選挙では、ぜひ一歩を踏み出してみましょう。
当日の流れをステップで紹介
「期日前投票に行きたいけど、何をすればいいのかわからない」
そんな不安を感じる人は少なくありません。とくに、はじめて選挙に行く人にとっては、投票所での流れや作法がわからず、ドキドキするするかと思います。
ここでは、当日のステップをわかりやすく段階ごとに紹介していきます。これを読めば、スムーズに投票できるようになりますよ。
ステップ①:受付に並ぶ
まずは、期日前投票所に行って、入口付近にある「受付」に並びましょう。
入口には「期日前投票所」「受付」などの案内板が出ていて、スタッフが立っているので迷うことはありません。ほとんどの場合、選挙ポスターや案内パネルも目立つところに掲示されているので、はじめて行く場所でも大丈夫です。
並んでいるときに、投票所入場券(ハガキ)を用意しておくとスムーズです。忘れてしまった人も、スタッフに「ハガキを忘れました」と伝えれば対応してもらえます。
ステップ②:宣誓書を記入する
期日前投票を行うときは、「なぜ投票日に行けないのか?」という理由を簡単に記入する「宣誓書(せんせいしょ)」が必要です。
受付の近くにテーブルや記入台が用意されていて、そこに「宣誓書」が置かれています。用意されたペンを使って、氏名・住所・生年月日と、行けない理由にチェックをつけるだけでOKです。難しい内容を書く必要はありません。
※事前に自治体のサイトからダウンロードして自宅で記入して持参することも可能です(必須ではありません)。
【よくある理由の選択肢】
- 仕事や学業のため
- 冠婚葬祭のため
- 旅行・レジャーの予定があるため
- 出産・病気・介護のため
- 天候の悪化が予想されるため
書き終わったら、その宣誓書と入場券を一緒に提出します。
ステップ③:本人確認と選挙人名簿の照合
次は、本人確認のステップです。受付で係の人が、提出された入場券または本人確認書類をもとに、選挙人名簿と照合します。
この作業は、あなたがその地域の選挙権を持っている人かどうかを確認するために行われます。
身分証を提示したり、生年月日を聞かれたりする場合がありますが、特に難しい手続きはありません。
照合が終わると、「投票用紙交付所」に案内されます。
ステップ④:投票用紙を受け取る
次に進むと、投票用紙をもらうコーナーに案内されます。選挙の種類によって、1枚または複数枚の投票用紙が手渡されます。
たとえば、国政選挙(衆議院・参議院)では次のような紙があります。
- 候補者名を書く紙(選挙区)
- 政党名を書く紙(比例代表)
- 裁判官の信任投票(国民審査がある場合)
自治体の選挙(市長選・市議選など)でも、同様に立候補者の名前を書くための紙が渡されます。
用紙は名前の書き間違いを防ぐため、選挙ごとに色が違ったり、文字の説明が書かれていたりするので、混乱しにくくなっています。
ステップ⑤:記載台で名前を記入する
投票用紙を受け取ったら、すぐ近くにある「記載台(きさいだい)」という机に向かいます。ここで、自分が投票したい候補者や政党の名前を、ペンで投票用紙に記入します。
記載台には、記入例が掲示されていたり、誤字を防ぐ工夫がされていたりするので安心です。
注意点としては、次のようなことが挙げられます。
- 候補者名はフルネームで書くのが確実(例:たなか たろう)
- 他人と相談しながら書いてはいけない
- 候補者の名前を正確に書かないと無効票になることがある
- 落書きやシールを貼ったりすると無効になる
記載を終えたら、投票用紙を持って投票箱の前へ移動します。
ステップ⑥:投票箱に用紙を入れる
最後に、記入した投票用紙を、それぞれの投票箱に自分で入れます。選挙区・比例代表・国民審査など、種類ごとに投票箱が分かれていることが多いので、スタッフの案内に従って正しい箱に入れましょう。
ここでようやく、あなたの一票が正式にカウントされることになります。
投票用紙をすべて投票箱に入れたら、期日前投票は完了です。所要時間は、混雑していなければ5分〜10分程度で終わることも多いです。
こんなときどうする?
Q:途中で書き間違えたら?
→ 大丈夫です。スタッフに申し出れば、用紙を交換してくれます(※回数制限があります)。
Q:候補者の名前を忘れた!
→ 記載台ではスマホを見たり、メモを見たりできません。投票所に来る前に候補者の名前をしっかり覚えておきましょう。
Q:体が不自由で字が書けない…
→ 代理投票や補助投票といった制度があります。スタッフに申し出れば、サポートしてもらえますので安心してください。
期日前投票の流れは、意外とシンプルでやさしいものです。
以下にステップを簡単にまとめます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 受付に並ぶ |
| ② | 宣誓書を記入する |
| ③ | 本人確認を受ける |
| ④ | 投票用紙を受け取る |
| ⑤ | 記載台で名前を記入する |
| ⑥ | 投票箱に入れて終了 |
この流れさえつかんでおけば、はじめての投票でも自信をもって臨めます。「自分の声を届ける」大切な一歩として、ぜひ経験してみてください。