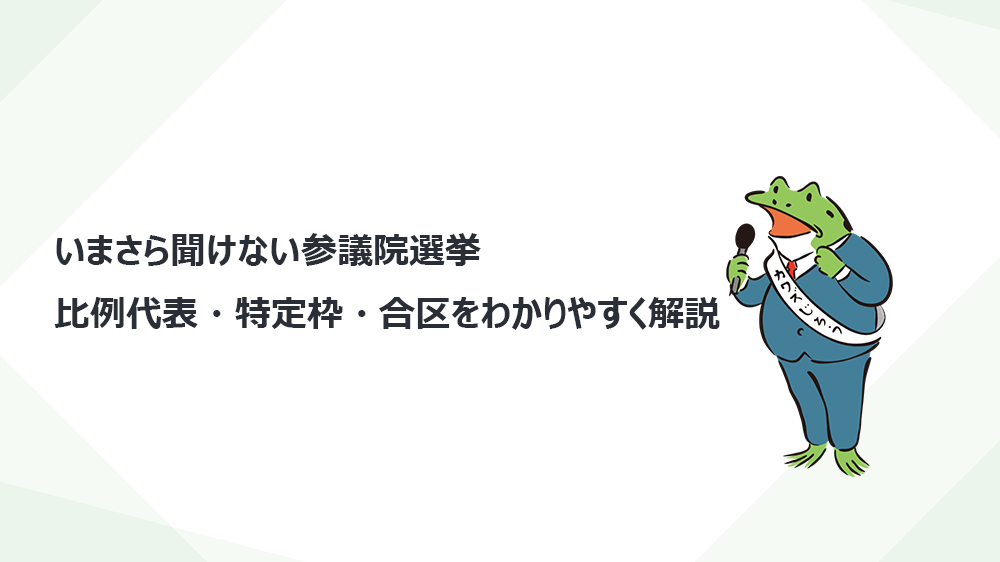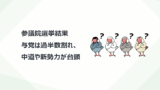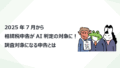「比例代表ってなに?」「特定枠ってなんのため?」「合区っていつからあったの?」
選挙のたびに聞こえてくるこの言葉たち。なんとなく耳にしているけど、実はちゃんと説明できない……そんな方はきっと多いはずです。
この記事では、いまさら聞けない参院選挙のキホンを、選挙制度に詳しくない方にもわかるように、やさしく丁寧に解説します。
衆議院との違いから、比例代表制の仕組み、話題の「特定枠」、そして複雑な「合区」問題まで、これ1本でスッキリ理解できる内容になっています。
政治や選挙がちょっと身近に感じられるようになる。そんな“入り口”として、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「参議院選挙」って何?
参議院選挙とは、日本の国会を構成する「参議院」の議員を選ぶための選挙です。国会には「衆議院」と「参議院」の二つがあります。つまり、私たちが普段ニュースで聞く「国会」とは、この二つの議院を合わせたものです。
参議院は「第二院」と呼ばれることもあり、政治における“ブレーキ”のような役割を担っています。法律を作ったり、予算を決めたりする中で、衆議院だけで決まってしまうのを防ぎ、もう一度慎重に議論し直す機会を持たせてくれるのです。
選挙は3年ごとに、全議員の半数(124人)を選びます。任期は6年で、解散はありません。これにより、政治が急激に変わりすぎないように調整することができます。
なぜ「参院選」が注目されるのか?
「選挙」と聞くと、どうしても「衆議院選挙」のほうが話題になることが多いかもしれません。なぜなら、衆議院は内閣の不信任決議ができたり、解散総選挙があったりと、ダイナミックに政権を左右する力が強いからです。
しかし、近年では参議院選挙も非常に注目されています。理由は主に以下の3つです。
(1)国会の「ねじれ現象」が起きるかどうか
衆議院では多数を占める与党が、参議院では少数になってしまう――こうした状況を「ねじれ国会」と言います。ねじれると、法律や予算がスムーズに決まらなくなり、政権運営が難しくなることもあります。つまり、参議院選挙の結果は政治の安定やスピードに大きな影響を与えるのです。
(2)選挙制度の見直しが相次いでいる
参院選では近年、「合区」や「特定枠」といった新しいルールが導入されています。これらは、選挙の公正さや地域の代表性を保つための制度ですが、やや複雑です。制度が変わるたびに、私たちも仕組みを理解し直す必要があります。
(3)私たちの生活に直結する政策が争点になる
年金、医療、教育、子育て、災害対策など、生活に関わるさまざまな政策が参院選での争点になります。「誰が政治を動かすか」だけでなく、「どんな社会をつくるか」に関わる選挙なのです。
若者にこそ知ってほしい「一票の重み」
「自分が投票しても変わらない」と感じてしまうかもしれません。でも実は、一票の重みは地域や選挙区によっても異なります。例えば、人口の少ない地方では一票の影響が大きくなりやすく、逆に都市部では多くの票が必要になることも。
また、若い世代の投票率が低いと、政治家はどうしても「票をくれる高齢層」に向けた政策を打ち出しがちになります。若者が選挙に参加することは、自分たちの未来に関わる社会を形作ることにつながるのです。
参議院と衆議院の違いとは?
日本の政治を動かしている「国会」は、衆議院と参議院という二つの議院からできています。この仕組みは、政治を一つの方向に偏らせすぎないよう、バランスを取るために設けられています。
でも、具体的に何が違うのか? どうしてわざわざ二つも必要なのか?ここでは、その疑問をひとつずつ解き明かしていきましょう。
衆議院と参議院の基本的な違い
まずは以下の表で、両者の違いをざっくり比較してみましょう。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 定数(議員数) | 465人(小選挙区289・比例代表176) | 248人(選挙区148・比例代表100) |
| 任期 | 4年(ただし、解散あり) | 6年(解散なし。3年ごとに半数改選) |
| 選出方法 | 小選挙区制+比例代表制 | 選挙区制+比例代表制 |
| 解散の有無 | あり(首相の判断などで解散できる) | なし(任期満了まで議員の地位継続) |
| 主な権限 | 内閣不信任決議、予算・法律の優越 | 衆議院との再審議など |
| 政治への影響力 | 強い(政権選択に直結) | 比較的穏やか(政策の熟慮・監視) |
こうして見ると、衆議院の方が「ダイナミックで政治の中心的役割を担っている」ことがわかります。それに対して、参議院は「安定性と慎重な審議」を重視する存在です。
衆議院の特徴:国政の主役、でも不安定
衆議院は、「政権を決める選挙(政権選択選挙)」といわれるように、内閣(総理大臣を含む政府の中心)を直接左右する力を持っています。
衆議院で多数派を占めた政党が、そのまま内閣を作るのが日本の仕組み。だから、政党間の力関係によって「政権交代」が起こるのも衆議院選挙の大きな特徴です。
ただし、衆議院には「解散」があるため、任期4年を全うできるとは限りません。実際、多くの総選挙は解散によって行われています。その分、政治が大きく動きやすい=不安定な側面もあります。
参議院の特徴:政治のブレーキ役、安定重視
一方で参議院は、政権を直接変える力は持っていません。内閣不信任案も出せず、解散もないため、「じっくりと議論する場」「衆議院のチェック機関」としての役割が強調されます。
6年の任期があり、しかも3年ごとに半分だけ改選されるため、選挙で一気に議席が大きく入れ替わることがありません。つまり、政権交代の波を受けにくく、政治の「安定性」を保つ役割を担っているのです。
このように、参議院は慎重な議論と多様な意見の尊重を目的としており、衆議院で通った法案を一度立ち止まって検証する“セカンドチェック”の場として機能しています。
衆議院と参議院が同じ法案について「賛成・反対」で意見が割れたら、どうなるのでしょうか?このときに登場するのが「衆議院の優越」というルールです。
これは、以下のような場合に最終的に衆議院の決定が優先されるというものです:
- 内閣総理大臣の指名
- 予算の決定
- 条約の承認
- 法律案の再議決(衆院で3分の2以上が再可決した場合)
つまり、最終的な「決断の場」として、衆議院に強い権限が与えられているのです。
こうした違いを見て「じゃあ、衆議院だけでいいのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、それは危険な発想です。
仮に一つの議院しかなければ、民意の一部だけに偏った政治が進んでしまう恐れがあります。そこで参議院のような「熟議の場」「少数意見も吸い上げる場所」があることで、バランスの取れた政治が実現しやすくなるのです。
さらに、参議院には女性やマイノリティ、高齢者、若者など、多様な立場の人々が参政するための入り口としての意味もあります。
参議院選挙の仕組み
参議院選挙では、私たち有権者が2つの票を投じることをご存じでしょうか?
- ひとつは「選挙区」の候補者に投票するもの
- もうひとつは「比例代表」の候補者または政党に投票するもの
この「2票制」が参議院選挙の基本です。それぞれの票がどんな意味を持ち、どのように議員が選ばれていくのかを、わかりやすく解説していきます。
選挙区
「選挙区」とは、全国をいくつかの地域に分けて、その地域ごとに代表者(議員)を選ぶ仕組みです。
選挙区は主に都道府県単位で構成されています。たとえば東京都は大都市なので6議席、山梨県のような小規模な県では1議席というように、人口や地域性に応じて議席数が割り当てられています。
- 東京都:6人を選出(2025年時点)
- 北海道:3人
- 鳥取・島根:合区で2県合わせて1人 ←これが「合区」、次章で詳解
有権者はどう投票するの?
選挙区では、自分の住んでいる地域の候補者の名前を1人だけ書いて投票します。立候補者は、政党に所属している人もいれば、無所属の人もいます。選挙戦はその地域ごとで繰り広げられます。
当選はどう決まる?
候補者ごとの「得票数」で争われ、得票の多い順に定められた人数が当選します。これは「多数代表制」という方式で、単純な数の勝負です。
比例代表:全国単位で政党に投票
もうひとつの票は「比例代表」です。これは日本全国をひとつの大きな選挙区(全国区)とみなして、政党ごとに議席を分け合う仕組みです。
投票用紙には何を書く?
有権者は、以下のどちらかを記入できます。
- 政党名(例:自由民主党、立憲民主党、日本維新の会など)
- 候補者個人の名前(ただし、その人が比例代表に名簿登録されていることが条件)
候補者の名前を書いた票は、その人に加点されるだけでなく、その政党の得票数にも加算されます(これを「個人票」「政党票」とも呼びます)。つまり、応援したい人がいれば、その人の名前を書くことで個人と政党の両方を応援することができます。
当選はどう決まる?
- まず、政党ごとの得票率に応じて「何議席取れるか」が決まります。
- 次に、政党内で多くの票を集めた順に、議席が割り当てられます。
例:
- A党が比例代表で1000万票を得て20議席を獲得
- A党内で一番票を得た候補者から順に20人が当選
つまり、「政党の人気」+「個人の人気」=当選への道という形です。
選挙区と比例代表、どっちが大事?
どちらも大切ですが、比例代表の方が「国全体の方向性」を示す指標になりやすいです。たとえば、東京などの大都市では選挙区だけでも大きな影響がありますが、比例代表なら地方に住む人の1票も全国に平等に反映される仕組みになっているため、公平性が高いといわれています。
また、比例代表は無名でも有能な人材が当選するチャンスがある制度でもあります。地域のしがらみにとらわれず、政策一本で勝負できる候補者が支持されることも多くあります。
2つの投票、使い方が違う
| 投票の種類 | 投票先 | 決まり方 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 選挙区 | 候補者の名前 | 地域内で得票順 | 地域代表、地元密着型 |
| 比例代表 | 政党名 or 候補者名 | 全国区で得票順 | 政策型、政党支持が反映される |
比例代表と「特定枠」制度とは?
参議院選挙では「比例代表制」が採用されており、私たちは政党名や候補者名を書いて投票します。前章で触れたように、政党の得票数に応じて議席が配分され、候補者は党内の得票順で当選が決まります。
しかしこの仕組みに、2019年から導入された「特定枠(とくていわく)」という新しい制度が加わったことで、一部の候補者は“順位をつけずとも優先的に当選できる”という仕組みが生まれました。
この章では、特定枠とは何か、どのように使われるのか、どんな背景から導入されたのかをわかりやすく解説します。
特定枠とは?かんたんに言うと…
特定枠とは、比例代表に立候補する候補者のうち、あらかじめ政党が「この人を優先して当選させる」と決めておける仕組みのことです。
通常の比例代表では、政党の得票数に応じて「誰が一番票を集めたか」で当選者が決まりますが、特定枠が使われた候補者は、得票数にかかわらず、政党が獲得した議席数のうち、優先的に当選します。
順位付き比例代表+特定枠
比例代表の候補者は、次のように区分されます:
- 特定枠候補者(順位あり)
- 「1位」「2位」などの順番が、政党によってあらかじめ決められている
- 得票数に関係なく、政党が取った議席の中から優先的に当選
- 非特定枠候補者(順位なし)
- 有権者から得た「個人名の票」で順位が決まり、それに応じて当落が決まる
たとえば…
ある政党が比例代表で5議席を獲得したとします。
この政党が「特定枠1人・通常候補4人」としていた場合、
- 特定枠の1人は、無条件で1議席目に当選
- 残る4議席を、通常候補の中から得票順で割り振る
このように、特定枠の候補者は「選挙での人気(得票)」に関係なく当選できる仕組みになっているのです。
特定枠を使うと、個人名投票ができない?
はい、ここが大きなポイントです。
特定枠に指定された候補者には、有権者が個人名で投票することができません。
投票用紙にその人の名前を書いても、それは無効票となってしまいます。これは、「すでに順位が確定しているため、得票数による順位争いに関係しないから」という理由です。
つまり、有権者の意思で順位を上げることも下げることもできず、党の判断でその人が自動的に当選する仕組みといえます。
なぜ特定枠が導入されたの?
この制度の背景には、合区問題があります。つまり、「選挙区の統合(合区)によって、地方の声が国政に届きにくくなっている」という問題です。
たとえば、鳥取県と島根県、徳島県と高知県は、人口減少により一つの選挙区(合区)として統合され、議席が1つだけになりました。その結果、片方の県の候補者は立候補しにくくなってしまい、「地域代表が失われる」という不満が出ていたのです。
そこで考えられたのが「比例代表の中で優先的に当選させる=特定枠」という制度。これにより、合区で立候補できなかった地域の候補者も、比例代表を通じて国会に送り込むことが可能になったのです。
特定枠のメリット・デメリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | ・地域代表性の確保(特に合区対策) ・社会的弱者・マイノリティ支援にも活用できる可能性 |
| デメリット | ・有権者が個人を選ぶ権利を持てない ・政党の「公認権」が強くなりすぎる懸念 |
たとえば、障がい者や難病患者、困難な状況にある社会的立場の人たちが議会に参加しやすくなるよう、特定枠を活用する政党も出てきています。これは多様な意見を国会に届ける新しい方法ともいえるでしょう。
一方で、党の都合で「この人を当選させたい」と決めてしまう危険性もあり、透明性や公正性の担保が求められています。
比例代表+特定枠=選び方の多様化
比例代表制度に「特定枠」という選択肢が加わったことで、政党はより戦略的に候補者を擁立できるようになりました。そして、有権者としての私たちも、単なる人気投票ではない、“政治に多様性を取り入れる”選び方が可能になってきているのです。
合区ってなに?なぜ問題になっているの?
「合区(ごうく)」という言葉、ニュースなどで聞いたことがあるかもしれません。でも、「どんな制度?」「なぜ導入されたの?」「なぜ問題視されているの?」と聞かれると、答えるのはなかなか難しいですよね。
この章では、参議院選挙における「合区」制度について、その背景と仕組み、そして今も続く課題や議論をわかりやすく説明します。
合区とは?
合区とは、「選挙区の合併」を意味する言葉です。
参議院選挙では原則として都道府県単位で選挙区が設定されていますが、人口の少ない県が“1つの選挙区”として認められなくなったため、2つの県を1つにまとめたというのが合区の正体です。
つまり、「鳥取県と島根県で1議席」「徳島県と高知県で1議席」というように、2県で1人の代表者しか選べない選挙区が誕生したのです。
なぜ合区が導入されたの?
背景にあるのは、「1票の格差」という問題です。
1票の格差とは?
簡単に言うと、「人口が少ない県の有権者1人の票の重みが、人口の多い県の人よりも何倍も大きくなる」ことです。たとえば、東京都では100万人が1人を選ぶのに対し、鳥取県では20万人で1人を選ぶようなケースがあると、地方の票が“重すぎる”=不公平だとされます。
このような格差は憲法の「法の下の平等」に反する可能性があるとされ、最高裁からもたびたび「違憲状態」との指摘を受けてきました。
そのため、2015年の公職選挙法改正で、人口の少ない県同士を合区し、格差を縮める措置として導入されたのです。
現在の合区対象はどこ?
2025年時点で、以下の2つの合区があります。
| 合区された選挙区 | 議席数 | 対象都道府県 |
|---|---|---|
| 鳥取・島根合区 | 1 | 鳥取県+島根県 |
| 徳島・高知合区 | 1 | 徳島県+高知県 |
このように、2つの県でたった1人しか国会議員を選べない状態になっているのです。
合区の何が問題なのか?
一見、「票の価値を平等にするための制度」であり、理にかなっているように見えます。しかし、合区には多くの批判や課題が存在します。代表的な問題点は以下の通りです。
(1)地域代表の消失
合区により、どちらか一方の県からしか議員が選ばれないケースが多くなります。すると、もう一方の県の声が国政に届きにくくなり、「地域代表を失った」という不満が生まれます。
例:鳥取県の候補者が当選 → 島根県民から「我々の代表はいない」と不満
(2)立候補のハードルが上がる
2県をまたいで活動するため、候補者は広い地域を回らなければなりません。これは資金的・体力的な負担が大きく、特に無所属や新人にとっては立候補が難しいという壁になります。
(3)地元密着型政治の後退
合区によって県ごとの事情に応じた政策提案がしづらくなり、“地域に根差した政治”が実現しにくくなるとの声もあります。
(4)地方と都市部の格差感の増大
「人口の多い都市ばかりが優遇される」「地方の声が無視される」という感覚が強まると、地方と中央の政治的な距離感や不信感が拡大する危険性もあります。
合区への対策は?特定枠の登場
前章で述べた「特定枠」は、まさにこの合区問題への対策として生まれた仕組みです。
たとえば、合区で立候補できなくなった県の候補者を比例代表の「特定枠」に登録し、優先的に当選させることで、地域代表の復活を図っています。
ただし、「特定枠=比例代表」という形は、選挙区制とは異なり、地域の直接的な代表性という観点では限界もあります。
「合区解消」はできるのか?
政治家や地方自治体からは、「合区をやめて、再び都道府県単位の選挙区に戻すべきだ」という声も上がっています。
一方で、人口減少の流れは続いており、1票の格差を縮めるには他の方法(議員数の調整やブロック制導入など)も検討されているところです。
合区は“格差是正”と“地域代表”のジレンマ
合区は「票の平等」という憲法の原則に基づいた改革でありながら、地方の声を国政から遠ざけてしまうという矛盾を抱えています。
この課題にどう向き合い、制度を進化させていくのか――それはまさに「民主主義のかたち」を私たち自身が考えていくべきテーマなのです。
参院選の争点や注目ポイントはここ!
選挙に行こうと思っても、「どこに注目すればいいのかわからない」「誰を選べばいいのかわからない」と感じてしまう人は多いはずです。特に参議院選挙は「政権選択選挙」ではないため、争点がぼんやりしやすいという印象を持たれがちです。
しかし実際には、私たちの暮らしや未来に関わる重要な政策が数多く争点になっているのです。この章では、過去の参院選で注目された争点や、私たちが見るべきポイントを整理していきます。
政党や候補者が争う「争点」って何?
「争点」とは、選挙のときに政党や候補者が主張の違いを示すテーマのことです。これを見比べることで、「自分の考えと合っている政党・人はどこか」を判断する手がかりになります。
争点は選挙のたびに少しずつ変わりますが、共通してよく取り上げられる主なテーマには以下のようなものがあります。
経済政策と物価対策
- 物価上昇(インフレ)への対応
- 賃上げと中小企業支援
- 消費税率の見直し
ここ数年、食料品やエネルギーなどの物価上昇が家計を直撃しています。各政党は「物価に負けない給料の仕組み」「消費税減税の是非」などをめぐって、異なる立場を示しています。
社会保障と少子化対策
- 年金制度の維持と見直し
- 医療や介護への予算配分
- 出産・育児支援の強化(児童手当、無償化など)
高齢化が進む日本では、社会保障費が膨らむ一方で、少子化に歯止めがかからない状況が続いています。政党によっては「育児にかかる費用の全額国負担」や「年金受給年齢の見直し」など、インパクトのある政策を掲げていることもあります。
憲法改正と安全保障
- 憲法9条の改正の是非
- 自衛隊の明記
- 台湾有事・北朝鮮ミサイル問題への対応
近年、安全保障への関心が急速に高まっています。特に憲法改正については、改憲に前向きな政党と慎重な政党とでスタンスがはっきり分かれているため、選挙の中でも激しい議論が交わされるテーマです。
エネルギー政策と気候変動
- 原発の再稼働・廃止
- 再生可能エネルギー(太陽光・風力など)の導入拡大
- カーボンニュートラルへの対応
「再エネか?原発か?」という問いは、エネルギーの安定供給と環境負荷の両面から非常に重要なテーマです。特に若い世代の間では「持続可能性」や「地球温暖化対策」への関心が高まっており、各政党のスタンスが注目されています。
教育・労働・ジェンダー平等
- 高等教育の無償化
- 非正規雇用の待遇改善
- 選択的夫婦別姓、LGBTQ+の権利保護
教育格差の是正や、働き方改革、ジェンダー平等の実現は、未来に直結する問題です。「すべての人が自分らしく生きられる社会」をめざす政策には、特に若年層の関心が集まっています。
若者が注目すべき3つの視点
選挙というと「政治のプロがやるもの」と感じがちですが、むしろ政治は“日常生活のルール作り”そのもの。若い世代こそ、次のポイントに注目して投票を考えてみてください。
「自分の生活」に関係あるか?
たとえば…
- 学費が下がる?
- バイト代が増える?
- 通勤・通学の交通費は?地方の移動手段は?
「将来の社会」に関わるか?
たとえば…
- 子育て支援や教育環境
- 気候変動や災害対策
- 働く環境の変化(フリーランスや副業の法整備)
「声を届けられる政治家」か?
- SNSや街頭で意見を発信しているか?
- 議会で発言しているか?
- 政治に無関心ではないか?
争点から「自分の一票の意味」を見つけよう
参院選は、政権交代こそ起きませんが、法律をつくる人たちを選ぶ大切な機会です。そして、その法律は、私たちの日常や将来の選択に大きく関わってきます。
だからこそ、「なんとなくで投票する」のではなく、自分が大事にしたいテーマに注目しながら政党や候補者を選ぶことがとても重要です。
よくある疑問Q&Aで理解を深めよう
「選挙に行きたい気持ちはあるけど、手続きや仕組みがちょっと不安……」
「比例代表って政党名でいいんだっけ?名前でもいいの?」
そんな疑問を抱いている人は、決して少なくありません。ここでは、参院選にまつわる“よくある疑問”をQ&A形式でスッキリ解決していきます。
- Qどうして参議院選挙では「2票」あるの?
- A
参院選では2つの目的で議員を選ぶからです。
- 1票目:自分の住んでいる地域(選挙区)から選ぶ
- 2票目:全国を1つの区として、政党または候補者を選ぶ(比例代表)
つまり、「地域代表」+「政策・政党の支持」という2つの観点から選べる仕組みです。
- Q比例代表って、政党名と人名どちらでもいいの?
- A
どちらでも有効です。
- 政党名を書くと → その政党の得票になります。
- 候補者の名前を書くと → その候補者+所属政党の得票になります。
個人名を書いても、その票は政党の票としてカウントされるので、安心して応援したい候補の名前を書いてOKです。
- Q無所属の人は比例代表に立候補できるの?
- A
できません。
比例代表は政党単位で立候補者を登録するため、政党に所属していない「無所属」の人は、比例には立候補できません。
無所属候補は、選挙区からの出馬に限られます。
- Q特定枠の候補者にも名前を書いて投票できるの?
- A
できません。
特定枠に入っている候補者は、名簿順位が固定されているため、個人名での投票が無効になります。
投票したい場合は、その候補者が所属する政党名を書くことで、その人が当選する可能性を支えることはできます。
- Q投票に行けない日はどうすればいいの?
- A
期日前投票を活用しましょう。
投票日(通常、日曜日)に行けない場合でも、公示日の翌日から投票日前日まで、役所などで投票できます。
必要なのは:
- 投票所入場券(なくてもOK)
- 印鑑や身分証は不要(選挙人名簿に登録されていれば投票可)
- 「仕事・旅行・体調不良・学業・冠婚葬祭」など理由は形式的でOK
- Q引っ越したばかりでも投票できるの?
- A
引っ越し前の自治体で、条件を満たせば可能です。
原則として、選挙人名簿に登録されている市区町村で投票します(通常、住民票を移してから3カ月以上たった人が対象)。
引っ越し直後の方は、
- 旧住所での不在者投票
- 期日前投票
- 郵便投票(特定条件下)
などが使えるケースもあるので、自治体選管に早めに確認を。
- Q選挙に行かないと何か罰則があるの?
- A
罰則はありません。でも、代わりに決めてくれる人は“必ず”います。
日本では選挙は「権利」であり、義務ではありません(義務投票制ではない)。
ただし、投票しなかったからといって空白のままにはならず、他の誰かの票によって政治が決まるという事実は覚えておきましょう。
- Q誰に投票するか迷ったらどうすればいい?
- A
まずは「何を大事にしたいか」を考えてから、候補者・政党を比べてみましょう。
便利な方法として:
- 各政党の公約比較サイト
- 選挙公報(各家庭に配布/選管サイトで閲覧可)
- SNSや動画で候補者の人柄や主張を見る
など、調べやすく・比べやすい環境が整ってきています。
「誰に投票するか分からない」=「投票しない」ではなく、「分からないからこそ調べてみる」ことが大切です。
わからないことは調べてOK!選挙は誰でも参加できる
参院選は「専門知識がある人だけのもの」ではありません。
仕組みを知れば知るほど、自分にとっての意味が見えてくるのが選挙です。
わからないことがあったら、選挙管理委員会のサイトや候補者のSNS、政党の公式発表などを活用して、正確な情報をつかみに行きましょう。
参議院選挙は、衆議院選挙とは異なる「安定と熟議の場」でありながら、私たちの生活に密接に関わる重要な選挙です。
「知らないから行かない」から、「知ったから行ってみたい」へ。
この特集記事が、あなたにとって「一票を考える」きっかけになれば幸いです。