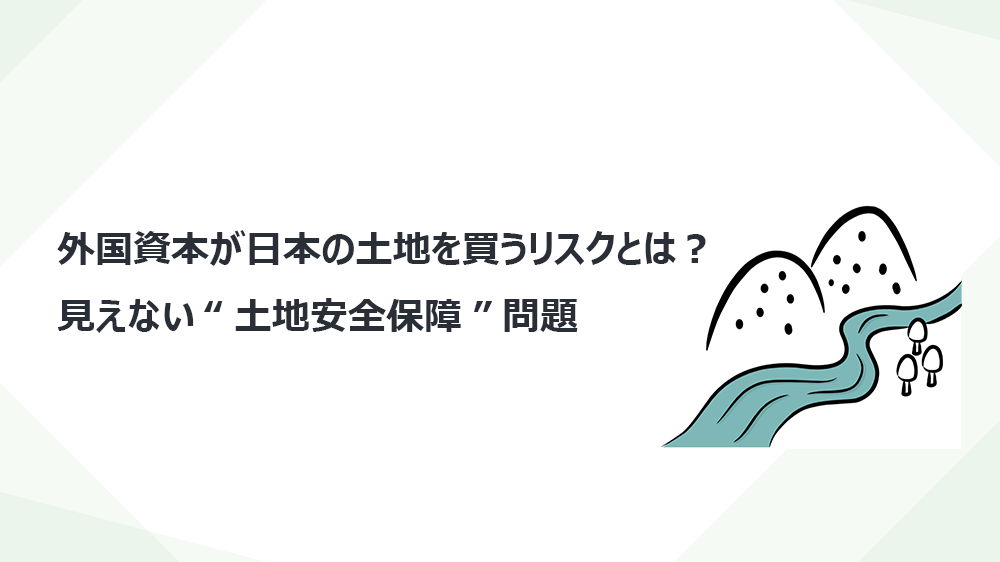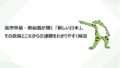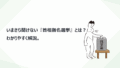静かに進む“土地の安全保障”というテーマ
近年、「外国の企業や投資家が日本の土地を購入している」というニュースを耳にすることが増えました。観光地やリゾート地などでは経済効果が期待される一方、防衛施設の周辺や水源地、国境離島などでは「安全保障上のリスクではないか」と不安視する声も出ています。いずれも合法的な取引ですが、土地は一度所有権が移れば長期間固定化されやすく、地域やインフラへの影響が大きいため、慎重な議論が求められています。
こうした問題の背景にあるのが「土地の安全保障」という考え方です。安全保障というと軍事や外交の印象がありますが、土地は水やエネルギー、通信など国民生活の土台に直結します。防衛施設の周辺や資源のある土地が、目的の見えにくい形で取得されることは、今後の国の安全や自治体の管理にも影響しかねません。
問題を複雑にしているのは、所有構造の“見えにくさ”です。登記上は日本法人でも、実際の出資者が外国にいるケースもあり、誰が最終的に支配しているのか分かりにくいことがあります。再エネ開発や観光事業を名目に取得された土地が転売を繰り返すうちに、実態が不透明になることも珍しくありません。土地は動かせない資産だからこそ、所有者が変われば地域の将来に長期的な影響を及ぼします。
もちろん、外国資本の流入にはプラス面もあります。老朽施設の再生や地域投資の拡大など、経済的な効果は少なくありません。重要なのは「どこで、どの目的で、どのように」土地が使われるかを見極めること。開かれた経済と国の安全をどう両立するかが、今後の課題です。
今回は、そうした疑問に答える形で、制度の仕組み、リスクが集中する土地の特徴、国の対応策(重要土地利用規制法)を順に解説します。
なぜ外国人でも日本の土地を買えるのか
まず押さえておきたいのは、日本では外国人でも自由に土地を購入できるという点です。これは「日本人と同じように土地を所有できる」という意味で、特別な許可や制限はほとんどありません。実はこのルールは、戦後の憲法や法律の仕組みに深く関係しています。
日本国憲法では、国民の財産権が保障されています。そして、土地基本法や民法などの関連法にも「土地取引は自由」という考え方が貫かれています。つまり、日本は“誰が土地を持っているかよりも、どう使うか”を重視する制度になっているのです。そのため、外国人や外国企業も、個人名義や法人名義で土地・建物を購入できます。もちろん登記も可能で、固定資産税などの税金も日本人と同じように支払います。
ただし、土地を「持つこと」と「住むこと」は別の話です。たとえば、外国人が土地や住宅を購入しても、長期間その場所に住むには在留資格(ビザ)が必要になります。また、住宅ローンを組む場合は、外国人に対して審査が厳しくなる傾向があります。これは、万が一の帰国や在留期限切れなどのリスクを銀行が考慮しているためです。
このように、日本の制度は「購入」には開かれていますが、「居住・融資」には一定のハードルがあるといえます。逆にいえば、資金力さえあれば、在留資格のない海外企業でも日本の土地を取得できるということでもあります。
一方で、諸外国では外国人による土地取得に制限を設ける国が少なくありません。
たとえばオーストラリアでは、外国人が住宅を購入する際には政府機関の承認が必要です。農地など広い土地の場合は、外国投資審査委員会(FIRB)のチェックが入ります。カナダでは、住宅価格高騰への懸念から、一部地域で外国人による住宅購入を一時的に禁止したこともありました。韓国でも、防衛施設や国境付近などでは外国人の購入に届け出が義務付けられています。
このように比較すると、日本の制度は非常にオープンで、「土地取引の自由」を最優先にしている国だとわかります。これは経済成長期に「外資の流入=投資促進」として歓迎されてきた流れでもあります。
しかし、時代が進み、安全保障やエネルギー、環境保全といった国の基盤に関わる土地の重要性が増す中で、「自由すぎる制度が逆にリスクになっていないか」という問いが浮かび上がってきました。
土地は動かせない資産です。一度買われてしまえば、国が簡単に取り戻すことはできません。
この点で、外国人の土地取得は“法律上は自由”であっても、“安全保障上は注意が必要”という考えが広がりつつあります。
外国資本が狙う土地とは?
外国資本が日本の土地を購入する動きには、いくつかの傾向があります。
単なる“投資目的”にとどまらず、自然環境や立地条件、さらには地政学的な位置づけが関係しているケースも多いのが特徴です。ここでは、具体的にどのような土地が注目され、なぜリスクが指摘されているのかを見ていきましょう。
北海道――水と自然をめぐる静かな買収
最も知られているのが、北海道での土地買収です。
広大な土地と豊かな水源を持つ北海道は、外国資本にとって魅力的な投資対象です。特に近年は、中国やシンガポールなどの企業が、観光開発やリゾート事業の名目で土地を取得する例が増えています。
問題視されているのは、水源地や農地の近くの土地が含まれている点です。
もし水源を囲い込むような形で所有された場合、将来的に水資源の利用や保全に支障をきたす可能性があると懸念されています。
北海道庁の調査でも、外国資本による森林買収が一定の割合で進んでおり、「資源管理の観点からも実態把握が急務」との指摘があります。
沖縄――米軍基地周辺と観光地の二重構造
もう一つ注目されているのが沖縄県です。
沖縄は観光地として人気が高く、海外資本のホテル開発やリゾート投資が活発です。一方で、防衛施設が多く存在し、地政学的にも重要な位置にあります。
米軍基地や自衛隊施設の周辺で、外国人や外国企業が土地を取得しているケースも確認されており、「基地の監視や情報収集に悪用されるおそれがあるのでは」と懸念する声もあります。
現時点で違法な取引ではありませんが、“どの国の資本が、どの場所を所有しているのか”を国として正確に把握できていないことが問題の根本にあります。
国境離島・長崎・対馬――海の国境線を守る土地
日本海に浮かぶ対馬(長崎県)や、隠岐諸島、石垣島など国境に近い島々も、外国資本の土地取得が話題になってきました。
これらの島は韓国や中国からの距離が近く、観光や物流の拠点として注目される一方、防衛上の重要拠点でもあります。
一部の土地では、外国資本が観光施設を建設したり、港湾周辺の土地を取得したりする例があり、万が一の際に安全保障上のリスクになりかねないとの指摘もあります。
離島は人口が少なく、土地売買の情報が表に出にくいため、実際にどの程度進んでいるかを把握すること自体が難しいという課題もあります。
再生可能エネルギー・山林――「環境投資」の裏側
最近では、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー事業を名目にした土地取得も目立ちます。
自然エネルギーの普及は歓迎されるべき流れですが、実際には山林を大規模に切り開いたり、発電所周辺の土地を買い占めたりする事例もあります。
こうした土地の中には、所有者の国籍や最終的な出資元が不明確なケースもあり、地元自治体が管理に苦慮することも。
「環境への配慮」を掲げながら、実際には収益目的や転売狙いで土地を押さえる動きもあるといわれています。
所有の“見えにくさ”が最大のリスク
これらの事例に共通するのは、誰が最終的な所有者なのかが見えにくいということです。
土地の登記簿には法人名義が記載されますが、その背後にある資本がどの国のものかまでは分かりません。
ペーパーカンパニーを経由して所有されている場合もあり、実際の出資者をたどるのは難しいのが現実です。
こうした「不透明な所有構造」が積み重なると、国として土地の利用をコントロールすることが難しくなります。
地元にとっては単なる投資取引でも、国家レベルで見ると、安全保障や資源管理の観点から見えないリスクを抱えているのです。
国が動いた「重要土地利用規制法」とは
外国資本による土地取得が増えるなかで、「このままでは国家の安全に関わる」との懸念が強まりました。
こうした背景から、2021年に成立したのが「重要土地等調査法」(一般的には「重要土地利用規制法」)です。
これは、防衛施設や原子力発電所、国境離島など安全保障上、特に重要な施設の周辺土地について、
国が利用実態を調査・監視できるようにするための新しい法律です。
目的:土地の「所有者」ではなく「利用目的」を監視
この法律のポイントは、誰が土地を持っているかよりも、どう使っているかに注目している点です。
たとえば、基地や原発の周囲1キロ以内の土地で、
通信施設や見張り台など「安全保障上の支障を生むおそれがある行為」が行われた場合、
政府が調査・勧告できる仕組みになっています。
国が直接「購入を禁止」するわけではありません。
しかし、土地の利用状況を調べ、必要に応じて制限や勧告を行うことで、
事実上の“監視網”を整えることを目的としています。
指定区域:全国で段階的に拡大
法律の対象となるのは、「重要施設」や「国境離島」の周辺。
このエリアは、政府によって注視区域または特別注視区域に指定されます。
| 区分 | 対象となる場所 | 規制内容 |
|---|---|---|
| 注視区域 | 防衛施設・原発・空港・港湾などの周辺 | 利用状況の調査、必要に応じて勧告 |
| 特別注視区域 | 特に安全保障上の懸念がある地域 | 取引前の事前届出・監視の強化 |
たとえば、防衛省の自衛隊基地、原子力発電所、米軍関連施設などが対象となっており、
2022年以降、段階的に区域指定が進んでいます。
また、国境離島の中でも外国との往来が多い場所は、より厳しく監視される仕組みになっています。
調査・勧告・罰則の流れ
法律では、国が土地や建物の利用目的を調査できるようになっています。
もし調査の結果、「安全保障上の支障がある」と判断された場合、
内閣総理大臣が勧告を行い、それに従わなかった場合は罰則(最大2年以下の懲役または罰金)が科される可能性があります。
ただし、この勧告や罰則はあくまで“最終手段”であり、
現状では多くのケースが「調査」や「情報提供」の段階にとどまっています。
限界と課題
制度として一歩前進したとはいえ、課題も多く指摘されています。
まず、区域の指定がまだ限定的で、全国の重要地域すべてをカバーしているわけではありません。
また、登記簿上は日本法人でも、実際には外国資本が出資しているケースがあるため、
「本当の所有者(最終的な支配者)」を把握するのは容易ではありません。
さらに、地方自治体や不動産業界の協力体制も十分とはいえません。
地方では、土地取引の情報が限られており、
現場レベルで国が把握するには時間がかかるという問題もあります。
安全保障とプライバシーのあいだで
一方で、この法律には「国による監視が行き過ぎではないか」という懸念もあります。
土地の所有者や利用状況を国が調べる以上、個人情報や企業活動の自由とのバランスも問われます。
「どこまで監視を強めるべきか」「経済活動の妨げにならないか」という議論は、今も続いています。
この法律は、外国資本の土地買収を直接禁止するものではありません。
しかし、「重要な土地の利用状況を政府が把握し、必要な場合に介入できる」という枠組みを整えた点で、
日本が初めて“土地の安全保障”に本格的に踏み込んだ象徴的な一歩といえるでしょう。
それでも防げない“抜け道”と新たな懸念
重要土地利用規制法の施行によって、政府はようやく土地の利用状況を把握する仕組みを整えました。
しかし現実には、この法律だけではすべてのリスクを防ぎきれないというのが実情です。
制度の隙間を縫うように、いくつもの“抜け道”が存在しているのです。
名義を変えた「実質的支配」
最もよくあるのが、日本法人を経由した実質的な外国資本の支配です。
登記簿上の所有者は日本の会社でも、その会社の株主が外国企業だったり、
最終的に海外の個人が支配していたりするケースは珍しくありません。
こうなると、法律上は「日本法人による所有」と見なされ、
外国資本として監視の対象に入りにくくなります。
つまり、“誰の土地か”ではなく“どの国の意思が働いているか”が見えない状態になるのです。
この構造的な不透明さこそ、土地の安全保障における最大の課題といえます。
取引情報の分断と自治体の限界
もう一つの問題は、土地取引の情報がバラバラに管理されていることです。
登記情報は法務局、固定資産税の情報は自治体、不動産売買の実務は民間業者がそれぞれ扱っています。
このため、国が全国的な視点で「どこにどんな土地が売買されているのか」をリアルタイムで把握するのは困難です。
特に地方自治体では、外国資本による取引を把握する人員も予算も足りず、
現場では「噂で知る」「新聞で知る」といったケースもあります。
国の監視体制が整っても、地域レベルでの目が追いつかないという現実的な問題が残っています。
不動産業者にも難しい判断
不動産会社にとって、取引の相手が外国資本であっても、
法的に問題がなければ契約を拒む理由はありません。
むしろ商業取引としては歓迎されることもあります。
そのため、「安全保障上の懸念があるかもしれない土地取引」を
民間企業の判断に委ねるのは現実的ではないという声もあります。
実際、不動産業界でも「合法的な取引を止めることは難しい」という意見が多く、
行政がきちんとリスクを把握・共有しなければならないという認識が広がっています。
情報の“後追い”になっている現状
現行の仕組みでは、土地が購入された後になって初めて調査が始まるケースが多いのも課題です。
たとえば、防衛施設や水源地周辺の土地が買われてから「どんな企業か調べてみたら外国資本だった」と分かる。
つまり、事前にチェックする仕組みが弱いのです。
一方、オーストラリアやカナダなどでは、外国人が土地を買う前に政府への申請や承認が必要な場合があります。
こうした制度を「安全保障と投資の両立」として見習うべきだという声も増えています。
不透明な所有の連鎖が生むリスク
土地取引は転売が容易です。ある企業が買った土地が、数年後には別の企業に渡り、
さらにその裏にまた別の資本がある――というケースも少なくありません。
この“所有の連鎖”をたどるのは非常に難しく、
結果として「誰が最終的に支配しているのか」が分からないまま土地が利用されることになります。
特に再生可能エネルギー関連の開発やリゾート開発では、
複数の企業が関わるため資本関係が複雑化しやすく、
国や自治体の調査が追いつかない状況が生まれています。
法律だけでは守りきれない“現場の安全保障”
このように、法律が整備されても、運用と現場の体制が追いつかないというギャップが存在します。
土地は一度所有者が変わると、売買を遡って無効にすることは非常に難しいため、
本来は「買われる前に気づく」仕組みが求められます。
つまり、法律だけでリスクを防ぐのではなく、
自治体・不動産業界・地域住民が情報を共有し、
“おかしな土地取引”を早期に察知できるネットワークづくりが重要です。
さらに強化を求める声
外国資本による土地取得をめぐる問題は、すでに国会でも大きな関心事となっています。
「重要土地利用規制法」が施行された後も、実際には監視や情報共有が追いつかず、
「これで本当に十分なのか」という疑問が、与野党を問わず多くの議員から上がっています。
水源地・防衛施設周辺での懸念が続出
2024年の国会質疑では、特に水源地や防衛施設周辺の土地取得が繰り返し取り上げられました。
水源地の買収については、自治体や民間の調査で「すでに外国資本が所有している可能性がある」
という報告が出ており、国としての把握が追いついていない実態が指摘されています。
また、防衛施設の近くの土地が観光や再エネ事業の名目で購入されている例もあり、
議員からは「安全保障に関わる施設の周辺こそ、購入時点でチェックできる体制が必要だ」との声が上がりました。
運用で対応」では限界も
政府側は、
「重要土地利用規制法に基づき、注視区域の指定を拡大していく」
「必要に応じて関係機関と連携し、適切に対応する」
といった答弁を繰り返しています。
しかし現状では、指定区域の拡大には時間がかかっており、
実際に監視できる範囲は全国のごく一部にとどまっています。
議員からは「法律を作っただけで満足してはいけない」「現場の運用を支える人員と情報体制が必要」との指摘が相次ぎました。
一部の専門家は、「事後的な調査では遅い。購入の段階で審査する仕組みを検討すべき」と提言しています。
登記情報の透明化と“実質支配者”の特定
国会で特に注目されているのが、「誰が最終的に土地を支配しているのか」という点です。
現在、登記簿には所有者の法人名や代表者名しか記載されませんが、
背後にいる投資家や親会社の国籍までは明らかにならない仕組みです。
このため、外国資本が日本法人を経由して土地を取得しても、
「外国資本による所有」としては表に見えません。
議員の間では、「登記制度を見直して、最終的な実質支配者(UBO=Ultimate Beneficial Owner)を
明確にする仕組みが必要ではないか」という意見が広がっています。
政府もすでに企業登記の透明化を進めており、
今後は土地取引においても「誰が背後にいるのか」を把握する制度が求められています。
自治体・不動産業界との情報連携
もう一つの論点が、現場レベルの情報共有です。
土地の売買情報は国だけでなく、自治体や不動産業者が最前線で扱っています。
そのため、地方自治体や業界団体との連携が不可欠です。
国会では、「国が持つ監視情報を地方にも共有するべき」「地域側からの通報制度を整えるべき」など、
双方向の情報ネットワーク構築を求める意見も出されました。
すでに一部の自治体では、外国資本の土地取得を独自にモニタリングする動きも始まっています。
事後監視から「事前チェック」へ
こうした議論の流れを受け、政府内では「事前審査制度」の導入も検討されています。
土地が売買される前の段階で、購入者の国籍や資本関係を確認できれば、
問題のある取引を未然に防ぐことが可能になります。
ただし、これを実現するには個人情報保護や経済活動の自由との調整が必要で、
慎重な議論が続いています。
法律を“生かす”ための次の一手
国会でのやりとりを見ても分かるように、
重要土地利用規制法はあくまで「スタートライン」にすぎません。
制度を機能させるには、
- 監視区域の拡大
- 登記情報の透明化
- 自治体・業界との連携強化
といった“運用面の強化”が欠かせません。
政府も2025年度以降、これらの仕組みを段階的に整備する方針を示していますが、
現場でどこまで機能するかはこれからの課題です。
経済開放と安全保障のはざま
外国資本による土地の取得をめぐる議論は、突き詰めると「経済の自由をどこまで認めるか」というテーマに行き着きます。
土地取引の自由は、経済成長や国際交流を支えてきた日本の基本原則でもあります。
しかし同時に、それが国の安全や地域の持続性とぶつかる瞬間も確実に増えています。
経済の自由がもたらす恩恵
まず、外国資本の流入には明確なメリットがあります。
たとえば、地方の観光地では、海外投資によって老朽化したホテルや商業施設が再生し、地域経済が活性化する例も少なくありません。
また、外資による不動産投資が市場を動かすことで、地価の上昇やインフラ整備が進むこともあります。
政府としても、外資の受け入れは「経済の国際化」や「地域の再生」に欠かせない要素として歓迎してきました。
つまり、外国資本による土地取得は「悪」ではなく、適切に管理されれば経済を支える力にもなるのです。
しかし、土地は“動かない資産”
一方で、土地は株式や通貨と違い、動かすことができない資産です。
そのため、誰が所有しているか、どのように利用しているかが、その地域や国の将来に直接影響します。
水源地が外国資本の手に渡れば、水の管理や供給に関わる懸念が生じますし、
防衛施設の周辺であれば、監視や情報収集の拠点として悪用されるおそれもあります。
また、土地は世代を超えて引き継がれる性質を持つため、
「今は問題がなくても、将来どう使われるか分からない」という長期的リスクをはらんでいます。
見えにくい支配構造が生む不安
外国資本の土地取得が問題視される背景には、単なる国籍の違いではなく、
所有構造の不透明さがあります。
表面上は日本の企業が所有していても、背後の資金源が外国にある場合、
国としては誰がその土地を実際に支配しているのか判断しづらいのです。
こうした“見えない支配”が進むと、
土地利用の透明性が損なわれ、結果的に行政が地域計画を立てにくくなります。
特にインフラや防災拠点など、公共性の高い土地においては、
所有者の不明確さが地域全体のリスクにつながります。
「自由」と「安全」は両立できるのか
では、経済の自由と安全保障は相反するものなのでしょうか。
実はそうとは限りません。
両者を両立させるための仕組みづくりが世界的にも進んでおり、
日本でも今後、次のような方向性が鍵になると考えられています。
- 土地取引の透明化
所有者や出資構造を明らかにし、「誰がどこを持っているのか」を国が把握できるようにする。 - リスクの高い地域での事前審査
防衛施設や水源地の近くなど、戦略的に重要なエリアでは購入前に申請・確認を行う。 - 地域と行政の情報連携
国・自治体・不動産業界が連携し、土地取引の異変を早期に察知する仕組みをつくる。
こうした施策が整えば、「経済の自由を保ちつつ、安全も守る」バランスが見えてきます。
土地は“国のインフラ”という意識を
最終的に大切なのは、土地を単なる不動産や投資対象としてではなく、
国の基盤インフラの一部として考える姿勢です。
水、エネルギー、交通、情報といったすべての要素が土地の上に成り立っています。
つまり、土地の安全はそのまま「暮らしの安全」でもあるのです。
外国資本を完全に排除することは現実的ではありません。
むしろ、日本としてどんなルールで受け入れ、どこで線を引くのかを明確にすることが重要です。
この線引きこそが、経済開放と安全保障を両立させるための第一歩といえるでしょう。
今後の課題と展望
外国資本による土地取得をめぐる問題は、いまも進行中です。
国は「重要土地利用規制法」で一定の枠組みを整えましたが、それだけで十分とはいえません。
土地は一度売却されると国が簡単に介入できないため、事後対応では遅いという指摘が根強くあります。
これからの課題は、「自由な経済活動」と「安全保障」の両立を、どう制度として形にしていくかです。
① 情報の透明化と“実質支配者”の特定
まず必要なのが、土地所有の「見える化」です。
現行の登記制度では、土地の名義人は分かっても、その背後にいる最終的な出資者や支配者(いわゆるUBO=Ultimate Beneficial Owner)までは把握できません。
これでは、外国資本が日本法人を経由して土地を買う場合、その実態を掴むのが難しくなります。
今後は、法人登記だけでなく土地登記にもUBO情報を紐づける仕組みが検討される可能性があります。
欧米の一部ではすでに、企業の最終支配者を登録・公開する制度が始まっており、日本でも議論が進みつつあります。
「誰が本当に土地を所有しているのか」を国と自治体が正確に把握できるようになることが、最初の一歩です。
② 自治体と業界の連携による早期発見
次に求められるのは、地域レベルでの情報共有と監視体制の強化です。
土地取引の最前線にいるのは不動産業者や自治体の職員です。
彼らが「どんな企業が買っているのか」「どんな用途で利用されるのか」を把握できれば、
国が調査を始める前に異変に気づくことができます。
たとえば、不動産業界団体が外国資本の取引情報を共有し、
自治体が重要地域の動きを定期的に国へ報告するような仕組みがあれば、
“見えないリスク”を早期にキャッチできるようになります。
こうした地道な情報ネットワークの構築が、制度を実効性あるものに変えていくカギとなります。
③ 事前チェック制度の導入
現行制度の最大の弱点は、事後的な調査にとどまっていることです。
重要な土地がすでに外国資本の手に渡った後に調べても、取り戻すことは容易ではありません。
そのため、「購入前に審査・届け出を行う制度」を検討すべきだという声が強まっています。
オーストラリアや韓国のように、政府の許可を必要とする仕組みを導入すれば、
安全保障上のリスクを事前に防ぐことが可能になります。
ただし、日本では経済活動の自由を重んじるため、過度な規制が企業活動を萎縮させる懸念もあります。
そのため、“全国一律ではなく、リスクの高い地域に限定して運用する”といった柔軟な制度設計が現実的です。
④ 経済の自由とのバランスをどう取るか
土地規制を強化するほど、外国投資の意欲が下がるのではという懸念もあります。
特に地方では、外資によるリゾート開発やホテル再建が地域経済の支えになっているケースも多く、
単純に「外国資本=リスク」とは言い切れません。
大切なのは、「制限する」ことではなく「信頼できる形で受け入れる」こと。
取引の透明性を高め、誰が何の目的で土地を利用しているのかを明らかにすれば、
安全保障と経済発展の両立は十分に可能です。
⑤ 国民への情報開示と意識の共有
最後に欠かせないのが、国民一人ひとりがこの問題を“自分ごと”として理解することです。
外国資本の土地取得というと、遠いニュースのように感じるかもしれませんが、
水源地や再エネ開発、観光地の開発など、実際には私たちの生活に直結しています。
土地は国の資産であると同時に、地域の暮らしを支える基盤です。
国がどんな土地を重要視し、どう守ろうとしているのか――
その情報を国民が知ることで、社会全体の監視力と透明性が高まります。
日本の土地制度は長らく「経済の自由」を優先してきました。
しかし今後は、「安全保障の観点からの土地管理」が欠かせない時代に入ります。
完全な規制ではなく、信頼と透明性に基づく“開かれた安全保障”こそ、これからの日本に必要な姿勢といえるでしょう。
参考資料
外国人による土地の所有に関する質問主意書(衆議院)