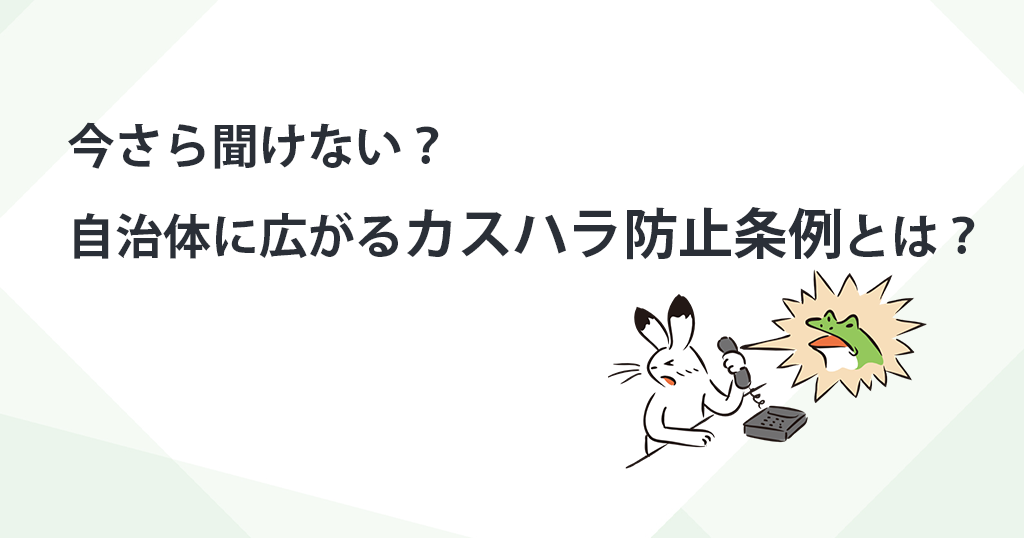徳島県内の11市町がフルネームの名札を廃止したりと、全国の自治体で広がるカスタマーハラスメント対策。東京都や三重県、北海道ではすでに「カスタマーハラスメント防止条例」が成立しており、政府は2025年3月11日に、顧客による従業員への著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策を企業に義務付けることを柱とした労働施策総合推進法など関連法の改正案を閣議決定し、企業に対応義務付けをする方針。
今回はそんな「カスハラ」に関してまとめてみました。
自治体で深刻化するカスハラとは
カスハラとは「カスタマーハラスメント」の略称です。民間企業などに対する過度なクレームや理不尽な要求を総称する言葉として広まりましたが、近年は官公庁や地方自治体の窓口でも、同様の行き過ぎた要求や暴言、暴力などが増え、「自治体のカスハラ」として社会問題化しています。
中学生のみなさんにとっては、役所や市役所は住民票を取ったり学校給食費の手続をしたりと、あまり普段意識しない場所かもしれません。しかし、地域の住民が毎日のようにやってくるこういった「公的な窓口」こそ、カスハラが起きやすい場でもあるのです。
なぜ自治体でカスハラが深刻化しているのか
通常、住民は行政サービスを受ける際に役所へ出向き、住民票や税、生活保護、福祉サービスなど、さまざまな手続や相談を行います。その場で不満や要望がある場合、正当なクレームや意見として、職員がきちんと対応するのは当然のことです。ところが、社会通念を大きく超えた迷惑行為――たとえば暴言を吐く、土下座を強要する、窓口に居座って業務を妨害する、SNSに個人名を晒(さら)すなど――が発生すると、それは「カスハラ」にあたります。
さらに、自治体は公共性をもつ組織であるがゆえに、民間企業のように簡単に「出入り禁止」や「契約解除」をしづらい面があります。憲法や地方公務員法でも「全体の奉仕者」としての責務が規定されているため、住民の求めるサービスを拒みにくいという特質を持っています。そのため、一部の悪質な住民が「公務員は断れないだろう」と見込んで行き過ぎた要求を繰り返す、という実態が見え始めています。
実際に増えているカスハラの事例
令和2年に厚生労働省が行った全国調査によると、公務員の約46%が過去3年間に何らかのカスハラを受けている、との報告もあり、窓口や電話対応の場面での精神的負担が深刻化していることがわかります。ここでいうカスハラの例としては、「長時間の居座り」「侮辱的な暴言」「名札や個人情報のSNS拡散」「土下座の強要」などが挙げられます。こうした行為は職員の尊厳を傷つけるだけでなく、ほかの住民サービスにも悪影響を及ぼす重大な問題です。
一部の自治体では住民だけでなく、周辺住民や利用者の家族からも、「担当者をクビにしろ」「金銭を払え」「自宅に来い」といった正当性を欠く要求が増えているという報道もありました。民間企業と違い、誰でも利用できる公共の窓口だからこそ、「やりすぎを止める仕組み」がなければ職員が一方的に被害を受けてしまうのです。
こうした自治体のカスハラに対して、総務省や厚生労働省などの中央省庁も対策を呼びかけていますが、自治体ごとに取り組みのばらつきがあるという課題もあります。そこで、まずは「自治体カスハラ問題の全体像」を理解することが、この先の防止策や条例制定の経緯を読み解くうえで重要です。
参考資料
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(厚生労働省)
自治体が抱えるカスハラ問題の背景と現状
公務現場ならではの「公共性」と「住民の権利」のはざま
民間企業が顧客対応をする際、最終的には「顧客との契約解除」や「取引停止」といった手段を講じるケースがあります。しかし自治体の場合、住民票の発行や福祉関連の申請など、公的サービスを拒否することは非常に難しいのが実情です。住民の権利を守る観点から、正当な意見であればしっかり受け止める必要がありますが、その正当性を逸脱しているかどうかの判断は簡単ではありません。
カスハラが深刻化する自治体ほど、職員の退職意向やメンタル面の不調が増えるというデータもあります。役所の職員が心身を壊して辞めてしまったり、住民対応が怖くて異動を望んだりするケースが増えると、地域にとって大切な行政サービスの維持まで危ぶまれます。人口減少で公務員のなり手が足りない地方部にとって、カスハラ問題の放置は「住民サービスの質を低下させる要因」とも言えるわけです。
具体的に増えた事例:名札フルネーム問題やSNS拡散
最近、多くの自治体で「職員の名札をフルネームから苗字のみの表記に変更する」動きが広がっています。これは、暴言や脅迫を受けた職員が個人情報を特定されることを防ぐためであり、そのきっかけはSNSでの誹謗中傷、ストーカー行為などが相次いだからとされています。
たとえば徳島県では、県内11市町が職員の名札表記を「苗字のみ」に変更し、7市町で録音機能付きの電話を導入していることが伝えられています。まさに、カスハラを「録音する」「個人情報を隠す」という組織的な対応が、新たな防止策として注目されているわけです。
加えて「道の駅」や観光関連の公務的サービスでも、高圧的なクレームや暴力・脅迫まがいの要求が後を絶たないため、対策として窓口のカメラ録画や警備強化を行うケースもあります。公務員だけでなく、委託先の職員や臨時雇用スタッフにも同様の被害が及ぶことから、自治体全体で対策を講じる必要が高まっています。
カスハラの背景にある社会変化
近年、オンラインやSNSでの意見発信が一般化する一方、人と人のコミュニケーションが希薄になり、「意見をすぐに相手にぶつけてしまう」風潮も指摘されています。行政も電話や窓口だけでなく、メールやSNSを使った広聴活動を行うようになりました。しかし、その結果として「SNSで一方的に攻撃する」「職員の実名や顔写真をネット上に晒(さら)す」などの新手のカスハラも増えています。
総じて、「住民の正当な声を受け止めつつ、理不尽な要求を毅然と拒む」両立の難しさが自治体カスハラ問題を深刻化させています。こうした背景を踏まえ、自治体では条例化や防止策の検討が急務になっているのです。
条例制定や具体策が進む自治体の事例
東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例
全国初となる都道府県レベルのカスハラ防止条例として、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、令和7年4月から施行されます。この条例は、都民に対して「カスハラの禁止」を明確に示し、事業者に「カスハラ防止のためのマニュアル策定など必要な措置」を求める内容が含まれています。
ただし、東京の条例に刑事罰など強制力はなく、あくまでも「指針(ガイドライン)をまとめ、事業者などが適切な防止措置に努める」ことを促す形です。それでも、「公のルール」として都がカスハラにNOを示した意義は大きいと言えます。自治体の窓口業務を含む事業者の多くが、この条例をもとにマニュアルを整備し始めています。
三重県桑名市のカスタマーハラスメント防止条例
また、三重県桑名市も独自の「カスタマーハラスメント防止条例」を成立させました。桑名市の条例は住民に向けて「不当な言動はやめましょう」と呼びかけると同時に、市が「対応にかかった人件費などを損害として請求」できる仕組みを示唆しています。こちらも具体的な制裁が目的というよりは、「明らかに度を越した迷惑行為があった場合の手段を確保する」狙いが強いとされています。
北海道カスタマーハラスメント防止条例
北海道でも議会で可決され、令和7年4月1日から「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が施行される予定となっています。道民一人ひとりがカスハラの防止に取り組むこと、道が相談窓口の整備や事業者支援を行うこと、そして事業者は従業者をカスハラから守るための対策を講じること――これらが柱になっています。条例内で、道と市町村、事業者、労働者団体などが情報共有をするため「カスタマーハラスメント対策推進協議会」を設置するのも特徴です。
いずれの地域でも、住民が公務員に対して行う不当な言動を抑止するために何らかの条文化・ルール化を進めています。特に東京や北海道の例は、広域自治体としての施策が市町村ごとにバラつきがある取り組みを補完する意味合いを持ち、「全道的・全都的な支援体制づくり」「相談窓口の周知」などが期待されています。
その他の取り組み事例
- 徳島県内の市町村:名札表記の変更、録音機能付き電話導入など。
- 愛媛県伊方町:条例を制定し、名札表記を苗字のみに変更したうえ、防犯カメラ設置など物理的対策を強化。
- 福岡県のいくつかの自治体:通話録音の活用や「カスハラ抑止ポスター」掲示など。
これらの取り組みからわかるように、どの自治体も「住民の正当な声は尊重しながら、迷惑行為や不当要求は明確に対処する」という二軸で動いています。ただし、条例や内部マニュアルにも罰則がなく、どこまで強く抑止できるかは課題が残されています。
自治体ならではの難しさ
「全体の奉仕者」という性格
地方公務員法では「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する」と明記されています。これは、公務員が特定の個人や集団のためだけではなく、社会全体の幸福や利益のために職務を遂行するという理念です。しかし、これが逆手に取られて「公務員だからどんな要求でも聞く義務がある」という誤解を招きやすいのも事実です。
たとえば生活保護の窓口で、「サービスが気に入らないから土下座しろ」「お前のせいで生活が苦しいんだ」などと極端な攻撃を受ける事例も報告されています。公務員としては住民の生活困窮を把握し救済する使命があるのは確かですが、度を越した暴言や恐喝は到底受け入れられません。この「行政サービスを断りにくい」特性と「一部住民の理不尽な要求」がぶつかり合う構造こそが自治体カスハラを根深い問題にしているのです。
住民の正当な権利とのバランス
さらに、住民には正当な権利として「情報公開請求」や「意見書提出」などが認められています。こうした行使自体を妨げるわけにはいきません。カスハラ対策としては「過度な長時間拘束には応じない」「侮辱的な言葉をやめるよう求める」というルールを設けることが考えられますが、その一方で「単なる苦情・要望の段階で一方的に締め出してしまうのは問題」という声もあります。
多くの自治体では内部マニュアルのなかで「どこまでが正当なクレームで、どこからがカスハラか」という判断基準を細かく設定し、かつ住民への説明責任を果たす仕組みを構築しています。たとえば対応時間の目安を30分や1時間に設定し、それを超える場合は「組織としての回答はお示ししたので、これ以上の対応はできません」と打ち切る手順を定めるケースもあります。ただし、社会福祉や税など住民の生活を左右する分野では慎重な運用が求められるため、他部署や管理職とも連携するなど、より大規模な協力体制が重要です。
防止対策と職員のメンタルヘルス
カスハラによって心身の不調を訴える職員が増えると、職場環境が悪化し、離職者が出るリスクも高まります。特に地方部で若年公務員が減るなか、「お客様(住民)のために尽くしたい」という意欲で就職しても、いざ実際に迷惑行為にさらされ、助けてもらえないとなればモチベーションが一気に下がるでしょう。メンタルヘルスの視点から、カスハラ被害を受けた職員をケアする相談窓口や外部カウンセラーとの連携が不可欠とされています。
ここで、道内(北海道)や全国の一部自治体が「複数人対応」「録音・録画の実施」「上司や関係部署へのすみやかな報告」を義務づけたマニュアルを導入していることが注目されています。職員が迷惑行為を一人で抱え込まない仕組みこそが、公務現場でのカスハラを抑止するカギといえるでしょう。
各自治体のカスハラ防止条例・取組の詳細
北海道カスタマーハラスメント防止条例
「北海道カスタマーハラスメント防止条例」は令和6年11月に成立し、令和7年4月から施行される予定です。この条例には次のような特徴があります。
- カスハラの定義:顧客等による社会通念上不相当な言動・要求をカスハラとして明確化
- 事業者の責務:就業者(公務員を含む)をカスハラから守るため、必要な防止措置(マニュアル作成、相談体制整備など)を講じるよう努める
- 道の役割:都道府県単位で相談窓口の設置、事業者・市町村との連携を強化し、対策を総合的に推進
- 推進協議会:道、市町村、事業者、その他関係者で情報共有し、連携を図るための場を設置
この北海道の条例は、東京に続き、都道府県レベルとしては2例目の大規模な試みといわれています。特に協議会を設置して各主体を結びつけることで、地域全体でのカスハラ対策を進める点が注目されています。
三重県桑名市の条例
桑名市の「カスタマーハラスメント防止条例」も自治体独自の特徴があります。自治体内部でマニュアルを整備するだけでなく、悪質な迷惑行為には損害賠償を求める姿勢を示唆し、制裁措置を盛り込んでいます。いわゆる「抑止力」としての役割が期待されていますが、どの程度実効性があるか、また他の市町村でも同様の動きが出てくるかは今後の注目点です。
東京都カスタマーハラスメント防止条例
東京都の条例は、全国初の「カスハラ禁止」を明文化し、事業者に対して「カスハラ防止マニュアルを作成するよう努めること」を呼びかけています。公務員や公共サービスの従事者も「就業者」に含まれると解釈されるため、都道府県全体でカスハラを無くす方針を打ち出しました。
施行後は、都内の市区町村でも独自の取り組みが一層進むと見込まれています。たとえば受付電話の録音、窓口での監視カメラ活用、名札の変更、時間超過時の対応ルール化など、それぞれの自治体が創意工夫をこらしているところです。
名札変更や録音機能付き電話の全国的普及
名札をフルネームから姓のみの表記にしている自治体は、全国的にみるとかなり増えています。市役所や町役場だけでなく、県庁や警察、消防など幅広い公務現場で導入されています。電話録音に関しても、時間外や休日の緊急連絡を装ってカスハラ行為を行うケースが多いことから、通話内容を記録することで抑止するとともに、万が一迷惑行為があった場合の証拠を確保できるメリットがあります。
これらの施策は、一見すると「住民と職員との壁」を作るようにも見えますが、職員の安全が守られることで、真面目な住民の要望により適切かつ安心して対応できる――というポジティブな効果も期待されています。
住民も職員も守るために
ここまで自治体でのカスハラ問題について、その背景や条例、そして具体的な事例を見てきました。
- カスハラとは何か
そもそも正当な意見や要求を伝えることは悪いことではありません。行政サービスをより良くする貴重な声となるはずです。しかし、「暴力的な言葉や態度」「土下座の強要」「不当に長時間拘束する行為」「SNSで個人情報を拡散して脅す」などは社会通念を逸脱しており、それがカスハラです。 - なぜ自治体で問題になるのか
自治体は誰でも利用できる公共サービスの場であり、職員が住民の要求を簡単には拒めない特徴があります。そのため一部の住民が「公務員なら何でも我慢して対応してくれるはず」と考え、迷惑行為をエスカレートさせるケースがあるのです。これは公務員の心身をむしばみ、サービス品質を下げ、地域全体に悪影響を及ぼします。 - 全国で進む条例化や対策の取り組み
東京都、三重県桑名市、北海道などで「カスタマーハラスメント防止条例」が相次いで成立し、住民に向けてカスハラ禁止を明示しています。あわせて、自治体職員を守るための体制づくり(名札表記変更や録音機能付き電話、複数人対応など)が全国的に広がっています。 - 住民を守るためにも必要な対策
一見すると「職員ばかりが守られるのでは」という印象を受けるかもしれませんが、職員が疲弊して離職が増えれば、地域の住民サービスが手薄になる可能性が高まります。つまり、カスハラ対策は回り回って住民を守ることにもつながるのです。 - これからの課題と展望
条例には強制的な罰則がなく、実効性を確保する手立てが十分でないとの指摘もあります。正当なクレームと迷惑行為の線引きが難しいという課題も残ります。それでも「法令や条例でカスハラがダメだと示す」ことが社会的な牽引力となり、自治体が組織的に職員を守る姿勢を示すことで、着実に風向きは変わり始めています。住民も「行き過ぎた要求は、かえってサービスの質を下げる」ことを理解し、思いやりを持ったコミュニケーションを心がけることが大切です。
まとめ
自治体におけるカスハラ問題は、単に一部のクレーマー対策というだけでなく、「公的サービスを支える公務員・職員の尊厳と健康」「地域住民の正当な権利」「安定した行政運営」という三つの要素を同時に守る戦いでもあります。だからこそ全国各地で条例化やマニュアル整備が進み、名札表記の見直しや録音機能付き電話が導入されているのです。
大切なのは、住民も公務員も「相手を尊重すること」。将来役所で働いたり、あるいは住民として役所に意見を伝える機会が増えたりします。そのとき「お互いを思いやる姿勢」があれば、社会全体がより良くなるはずです。
私たちが今できるのは、「まずカスハラがどれだけ深刻かを知り、行き過ぎた行為に気づいたら声をあげる」こと。そして「職員を孤立させず、組織や地域全体で支える仕組みを応援すること」です。これがカスハラのない自治体を作り上げ、地域の暮らしをより豊かにしていく答えといえます。
自治体ごとの独自性や住民の多様な事情にも配慮しつつ、条例整備やマニュアル策定、名札・録音電話の導入など、社会全体でカスハラを抑止する動きが広がっています。住民と公務員がお互いに対等な存在として尊重し合い、正当な意見を取り入れながら理不尽な要求は毅然と拒む――そのバランスを保つために、多くの自治体がいま真剣に取り組んでいるのです。