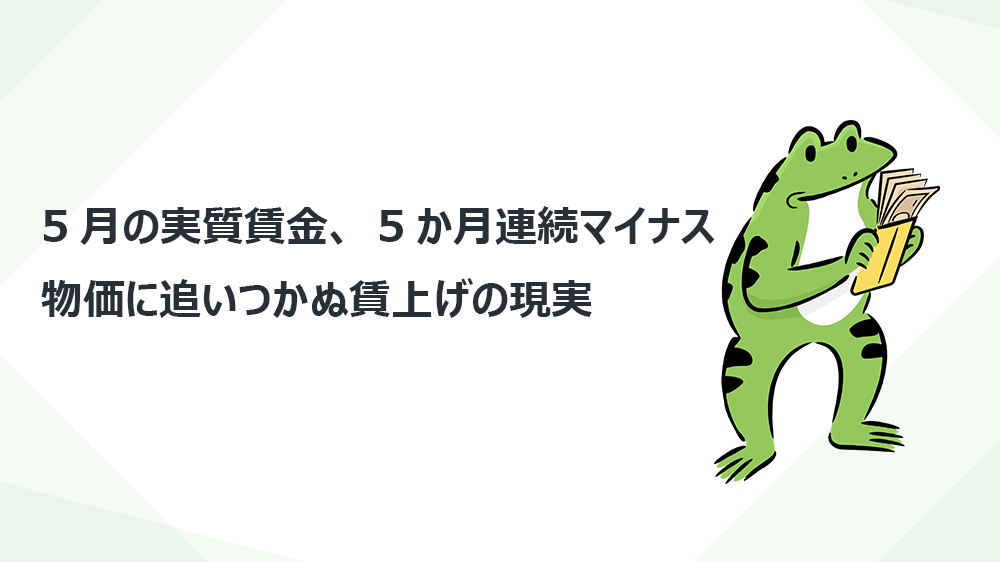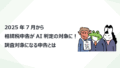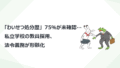5か月連続マイナスの衝撃
2025年7月7日に厚生労働省から発表された最新の統計によると、2025年5月の実質賃金は、前年の同じ月と比べて2.9%減少しました。実質賃金というのは、給料の金額から物価の上昇分を差し引いて、私たちが実際にどれくらいの買い物ができるかという「お金の価値」を表した数字です。
この実質賃金がマイナスになるということは、給料が上がっても、物価の上昇の方がもっと速く進んでいるということ。つまり、「お金は増えているけれど、買えるものは減っている」という現実が続いていることになります。そして、こうした実質賃金のマイナスは、なんと5か月連続で起きています。これはとても深刻な状況です。
このニュースは、働く人たちにとって無視できない内容です。見た目には給料が増えているように見えても、生活の中で感じる「暮らしにくさ」はむしろ増しているからです。たとえば、スーパーで買い物をしていて「この間まで100円だった卵が120円に上がってる」「外食が高くなってきた」と感じることはありませんか? それがまさに、給料が上がっても実質的に生活が苦しくなるという「実質賃金の減少」の正体です。
今回の実質賃金の減少幅(2.9%)は、2023年9月以来の大きさです。つまり、1年8か月ぶりにこれほど深刻な下がり方をしたということになります。しかもこれは、単なる月ごとの「一時的な変動」ではなく、5か月も続いていることから、物価高と賃金上昇のバランスが崩れている構造的な問題だと見られています。
では、なぜ給料が上がっているのに、実質賃金が下がってしまうのでしょうか? その背景には、「名目賃金」と「物価上昇率」のギャップがあります。名目賃金というのは、実際に支払われた給料の金額そのもののことです。2025年5月の名目賃金(1人当たりの平均現金給与総額)は30万141円で、前年同月比で1.0%増加しました。これだけ見ると、給料はちゃんと増えているように見えます。
しかし、その一方で5月の消費者物価指数(CPI)、つまり物の値段の平均は4.0%も上昇していたのです。給料の伸び率が1%なのに、物の値段が4%も上がっているのでは、生活はどんどん厳しくなっていきます。これが、実質賃金が下がる仕組みです。
特に、今回の物価上昇は食料品を中心に深刻です。たとえばコメは、前年同月と比べてなんと101.7%上昇。つまり価格がほぼ2倍になったということです。おにぎりは19.2%上昇、外食のすしも6.3%上昇と、日常の食事が明らかに高くなっているのがわかります。これは一部のぜいたく品ではなく、私たちの日常生活に欠かせないものが高騰しているということを意味します。
さらに、この物価高の影響をもっと強く受けているのが、家計に余裕のない世帯や一人暮らしの若年層、高齢者世帯などです。特に食費の割合が大きい家庭では、実質賃金のマイナスがそのまま家計への打撃となり、貯金を切り崩したり、外食や娯楽を減らしたりと、生活スタイルにまで影響を与えています。
ニュースの中でも紹介されているように、政府や企業はここ数年、春の労使交渉(春闘)などを通じて賃上げを進めてきました。たとえば2025年の春闘では、平均で5.25%の賃上げが実現しています。これは34年ぶりの高い水準だといわれています。しかしそれでも、物価上昇のスピードには追いつけていないのが現状なのです。
つまり、「給料は上がっているのに生活は楽にならない」という、いわば「逆転現象」が起きているということ。これは数字だけ見ていてもわからない「暮らしの実感」の部分で、多くの人が不満や不安を感じている背景です。
名目賃金は上昇、だが中身は異なる
今回の統計で発表された数字を見ると、2025年5月の「名目賃金」は前年同月比で1.0%増加しました。名目賃金とは、物価の影響を考えず、そのままの金額で見たお給料のことです。数字だけを見れば、働く人のお給料が41か月連続で増えていることになります。
でも実際には「給料が増えている感じがしない」と思っている人も多いでしょう。それは、名目賃金の中身をよく見ると、「増えている部分」と「減っている部分」に差があるからです。
名目賃金の内訳(2025年5月)
| 項目 | 金額(平均) | 前年同月比の増減 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 総額(全体) | 30万141円 | +1.0% | 41か月連続でプラス |
| 所定内給与(基本給など) | 26万8177円 | +2.1% | 43か月連続でプラス、春闘賃上げを反映 |
| 特別給与(ボーナスなど) | 不明(構成割合で推定) | -18.7% | 5月はボーナス支給が少なく大幅減少 |
この表からもわかるように、名目賃金のうち「所定内給与(基本給など)」はしっかり上がっている一方で、「特別給与(ボーナスなど)」が大きく減っているのです。
特別給与は、企業の業績や支給時期によって大きく変動するため、毎月のデータで見ると前年比で大きく動く傾向があります。たとえば5月のように、ボーナスの支給が少ない月では、少しの違いでも大きなマイナスとして現れます。
ポイント整理:なぜ名目賃金が「伸び悩み」に見えるのか?
- 基本給(所定内給与)は上がっている
→ 春闘(労働組合と会社の話し合い)によるベースアップの影響。平均+2.1%と好調。 - ボーナス(特別給与)が大幅に減っている
→ 5月は支給する企業が少なく、前年より金額が下がって統計上は-18.7%の大幅減。 - 結果として総額の伸びはわずか+1.0%
→ プラスではあるが、ボーナス減の影響で全体の伸びが小さくなった。
実際、厚生労働省の担当者も次のように説明しています。
「この時期にボーナスを支給している企業が少ないため、金額の少しの違いでも前年比で見ると大きく振れてしまう。名目賃金全体の動きは一時的なものと見ている。」
このように、給料の一部だけを見て「増えている」「減っている」と判断するのは早計です。実態を見るには“内訳”を確認することが大事なのです。
名目賃金の「増加」と言える理由はあるか?
実はポジティブな面もあります。それは、所定内給与(基本給)が安定して増えていることです。これは「企業が従業員の給料を毎月しっかり上げている」という証拠でもあります。
とくに一般労働者(正社員など)に限ると、所定内給与は前年同月比で+2.5%の増加となっており、春闘での賃上げが数字に反映されてきたといえます。
しかし、この名目賃金の「中身の変化」には注意が必要です。
- ボーナスの減少により生活費が足りない
→ ボーナスに頼っていた人ほど生活に影響が出る可能性があります。 - 中小企業への賃上げの波及が遅れている
→ 大企業は賃上げできても、中小は人件費の増加に耐えきれないことも。 - 所定内給与だけでは生活費の高騰に追いつかない
→ 食料・電気代・ガス代などの物価が一気に上がっている現状では、基本給2%の増加では間に合わない家庭も多い。
今後のカギは?
名目賃金の見かけの増加ではなく、安定して支給される基本給の上昇がポイントです。そして、企業全体にそれが広く浸透することが重要です。
| 目指すべき方向 | 内容 |
|---|---|
| 基本給の安定的な上昇 | 一時的なボーナスに頼らず、毎月の給与水準を底上げする |
| 中小企業への支援強化 | 賃上げをしても倒産しないよう、国の支援策が必要 |
| 生活コストの抑制 | 物価高騰を抑える政策と併せて、実質賃金の改善を図る |
物価高が実質賃金を圧迫
実質賃金が5か月連続でマイナスとなった最大の理由は、「物価の上昇」にあります。物価が上がると、たとえお給料の金額が増えていても、実際に買えるモノやサービスの量が減ってしまいます。これは、私たちが日々の生活の中で「最近、なんか高いなあ」と感じている感覚と一致しています。
2025年5月の消費者物価指数(CPI)は、前年同月と比べて4.0%上昇しました。消費者物価指数とは、日常生活でよく買う品物やサービスの価格がどれくらい変化したかを示すものです。政府が調査し、その平均値をまとめて「物価の上がり下がり」を数字で表したものです。
この4.0%という数字は、実はかなり高い水準です。たとえば、日本銀行が目標にしているインフレ率は「2%程度」。それを大きく上回る4%台が、すでに6か月連続で続いています。つまり、日本の物価は今、想定よりもかなり速いペースで上がり続けているということです。
では、どのようなものが、私たちの生活に直接的な負担を与えているのでしょうか? その代表例が「食料品」です。
中でもとくに目立ったのが、「コメ」の価格です。2025年5月の統計によると、コメの価格は前年同月と比べてなんと101.7%上昇しています。これは「価格がほぼ2倍になった」ということで、異例の事態です。
さらに、おにぎりは19.2%上昇、外食のすしは6.3%上昇と、私たちが日々よく食べているものの価格が軒並み上がっています。もともと価格が安定していた日本の食卓が、今は「高くて手が出しにくい」という状況になってきています。
なぜ、ここまで食料品の価格が上がってしまっているのでしょうか?
背景には、いくつかの要因があります。
1つ目は、世界的な農産物の価格上昇です。気候変動によって世界各地で干ばつや大雨が起き、作物の収穫量が減少しています。とくに日本はコメ以外の多くの食材を海外から輸入しているため、世界の価格の影響を強く受けます。
2つ目は、円安の影響です。2025年は円の価値がドルなどの外貨に対して下がっており、輸入する際に以前より多くの円が必要になっています。その結果、海外から入ってくる食品の値段が上がってしまうのです。
3つ目は、エネルギー価格の高騰です。電気代やガス代、ガソリン代が上がると、農業や物流にかかるコストも一緒に上がります。農作物の栽培、食品の加工、スーパーへの輸送など、あらゆる過程でエネルギーを使うため、これが最終的な商品価格に反映されてしまいます。
こうした複数の要因が重なって、私たちの生活に直結する「食料」が一気に高くなり、家計にのしかかっているのです。
実は、食料品だけではなく、電気代や日用品の価格も上昇しています。たとえば、トイレットペーパーや洗剤、調味料など「なくては困るもの」ほど値上がりしている傾向にあります。しかも、値段は上がっても中身の量が減る「実質的な値上げ」も広がっており、生活者の負担感はさらに大きくなっています。
その一方で、給料は思ったほど増えていません。とくに、生活の中で支出割合が高い低所得層や一人暮らしの若者、高齢者にとっては、物価の上昇は「直撃」になります。毎月の給料が入っても、家賃や光熱費、食費を払ったらほとんど残らない。そんな声が多く聞かれています。
政府は、春闘での賃上げや最低賃金の引き上げを通じて「物価に負けない賃金上昇」を目指しています。しかし、実際には「賃金の伸び」よりも「物価の伸び」がずっと速いため、その差が「実質賃金のマイナス」という形で現れているのです。
厚生労働省も今回の発表で「物価の高止まりによって実質賃金がマイナスとなっている」と認めており、「今後も春闘効果の波及を注視する」とコメントしています。つまり、企業の賃上げがもっと広く行き渡れば、いずれ実質賃金もプラスに転じる可能性がある、という期待も残されています。
ただし、それにはいくつかの条件があります。たとえば、物価の上昇がいったん落ち着くこと。エネルギー価格や円安が安定しない限り、食品や生活必需品の価格がすぐに下がるとは考えにくいのが現実です。
また、ボーナスや特別手当だけでなく、毎月の基本給を安定的に上げていくことが重要になります。そうでなければ、「一時的に賃上げがあったけど、結局生活は変わらなかった」という声が増えてしまうでしょう。
春闘効果と限界:持続できるか?
ここ数年、政府と経済界は「賃上げによる景気回復」を目指して、春闘(春季労使交渉)を強く後押ししてきました。特に2024年、2025年は、歴史的な物価高への対応として、かつてない規模の賃上げが話題となりました。2025年の春闘では、主要企業の平均賃上げ率が5.25%となり、これは34年ぶりの高水準です。数字だけを見れば、順調に給料は上がっているように見えます。
では、なぜこれだけの賃上げが行われても、実質賃金は依然としてマイナスなのでしょうか? その理由を整理すると、以下の3つに分けることができます。
実質賃金が上がらない主な理由
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| ① 物価上昇のスピードが速すぎる | 食料やエネルギーなどの価格が急上昇し、給料の上昇が追いつかない |
| ② ボーナスの減少 | 5月はボーナス支給が少なく、名目賃金の伸びが抑えられた |
| ③ 中小企業への波及が遅れている | 春闘で賃上げがあっても、大企業中心で中小企業は対応が追いついていない |
この中でも特に注目すべきなのは、中小企業の「賃上げの息切れ感」です。大手企業では、業績が回復している企業も多く、従業員への還元として賃上げが可能ですが、中小企業は人手不足や原材料費の高騰など、複数のコストに直面しています。
日本経済新聞の報道によると、企業規模30人以上の事業所では、4月に+2.4%だった名目賃金の伸びが、5月には+0.3%にまで縮小しています。これは、ボーナスの減少だけでなく、「継続的な賃上げが難しい現実」を映しているともいえます。
春闘効果が「持続しにくい」背景
- 固定費としての負担
所定内給与(基本給)は、一度上げると簡単には戻せません。企業にとっては大きな固定費の増加となるため、慎重にならざるを得ません。 - 物価が予測しにくい
エネルギーや原材料の価格が急に変動する中で、「来年の利益がどれくらい見込めるか」が読みにくく、長期的な賃上げ計画が立てにくくなっています。 - 人手不足の影響
若年層の労働人口が減っており、雇用競争が激しくなっています。人手を確保するために賃金を上げる必要はある一方で、企業体力が持たないケースもあります。
このように、春闘による賃上げ効果は、一定の成果を上げているものの、それがすぐに全体の実質賃金をプラスに転じさせるには時間がかかるというのが現実です。厚生労働省も、「基本給(所定内給与)は堅調に増加しているが、実質賃金の下がり幅が大きくなったのは、物価の高騰やボーナスの減少が影響した」と述べています。
また、専門家の分析もこの点に注目しています。第一生命経済研究所の首席エコノミスト・永浜利広氏は、次のようにコメントしています。
「名目賃金の前年比を見ると、5人以上の事業所で+2.0%から+1.0%に急減速している。これはボーナス減の影響が大きい。一方で所定内給与は+2.5%と高く、春闘効果は見られるが、インフレが続く限り実質賃金の安定プラスは難しい。」
これはつまり、今の日本では「一時的なボーナスや手当」だけではなく、基本給の安定した引き上げが求められているということです。
とはいえ、こうした構造的な課題を解決するには、民間企業の努力だけでなく、政府の政策的支援も必要です。たとえば、中小企業への補助金制度や、地域間格差の是正策などが必要とされているのです。
| 課題 | 今後の注目点 |
|---|---|
| 賃上げの持続性 | 一時的な昇給に終わらず、継続的にベースアップできるか |
| 中小企業支援の強化 | 春闘の効果を広く波及させるためにどんな支援ができるか |
| インフレ対策 | 原材料価格・エネルギー価格の高止まりをどう抑えるか |
| 労働分配率の改善 | 利益のうち、どれだけを従業員に還元するかの考え方の見直し |
厚労省・専門家の見解と今後の注目点
5月の実質賃金が5か月連続でマイナスとなった今回の発表を受けて、厚生労働省や経済の専門家たちからも、さまざまな見解や分析が示されています。問題の本質が「賃金が伸びない」のではなく、「物価の伸びが早すぎる」ことにあるため、今後の政策や経済動向に注目が集まっています。
まず厚生労働省は、今回の統計について次のようにコメントしています。
「所定内給与(基本給)は堅調に増加しており、賃上げの流れは継続している。ただし、物価の高騰や賞与(ボーナス)の変動が、実質賃金の押し下げにつながったと考えられる。6月はボーナスを支給する企業も多いため、その動向を注視したい。」
この発言からわかるのは、現在の「実質賃金のマイナス」は一時的な要因も含んでおり、今後のボーナスや秋の経済指標で改善する可能性があるという点です。実際に夏のボーナスが多く支給される6月・7月は、名目賃金の伸びが一時的に回復する可能性があります。
一方、経済の専門家たちは、もう少し厳しい視点から現状を見ています。
経済専門家の見解(例:永浜利広氏)
第一生命経済研究所の首席エコノミスト・永浜利広氏は、以下のように分析しています。
「賃上げは一部で進んでいるが、物価の上昇がその効果を打ち消している。とくにエネルギーと食料の価格が高止まりしており、この状況が続く限り、実質賃金の安定的なプラスは期待しにくい。」
これはつまり、「給料を増やすだけでは足りない。物価の安定が同時に必要だ」ということです。今は給料も物価も同時に上がっていますが、そのスピードに差があるために、実質的な生活は苦しくなっているわけです。
また永浜氏は、大企業と中小企業の格差についても言及しています。
「賃上げの恩恵は、従業員30人以上の大企業ではある程度見られるが、中小企業ではほとんど効果が出ていない。経済の“二極化”が進んでいる。」
これが意味するのは、政府や大企業だけが頑張っても、社会全体の実質賃金を改善するのは難しいということです。中小企業にも春闘の効果が届き、そこで働く人たちの生活も安定することが、実質賃金の改善には不可欠です。
今後の課題と政策対応の方向性
今後、実質賃金を安定してプラスにするためには、以下のような複数の対策が必要とされています。
| 対応策 | 説明 |
|---|---|
| 物価対策の強化 | エネルギーや食料品価格の高騰を抑えるための補助金や関税見直しなど |
| 中小企業支援 | 賃上げに取り組む中小企業への助成金や税制優遇の強化 |
| 労働市場の改革 | 働き方改革や非正規雇用から正社員化への流れを促進 |
| 再分配政策 | 給与だけでなく、減税や社会保障で家計への負担を軽減 |
| 生産性向上への支援 | 中小企業が高付加価値化できるように設備投資やIT導入への支援を行う |
とくに注目されているのが「物価対策」です。たとえば、2025年現在の日本では、電気・ガス代やガソリン代に対する補助金政策が段階的に見直されつつありますが、物価高の影響が続く限りは、生活必需品への直接的な支援策が必要だという声も強まっています。
また、中小企業に対しては「賃上げをしても経営が苦しくならないようにする」支援策が求められています。たとえば、政府は「賃上げ促進税制」などを導入して、給料を上げた企業の法人税を軽くする取り組みを進めていますが、これが本当に現場の中小企業に届いているかは、今後の調査と改善が必要です。
市民の暮らしに直結する「実質賃金」
ここまで見てきたように、実質賃金というのは、単に「経済の数字」ではなく、私たちが実際に感じる暮らしやすさ・豊かさと直結しています。名目賃金が上がっても、食費・光熱費・家賃などがどんどん上がっていれば、家計は苦しくなってしまいます。
給料が上がったのに、生活が楽にならない。
働いても働いても、貯金ができない。
そんな声が聞こえてくるのは、実質賃金がマイナスのときに必ず現れる現象です。
だからこそ、ニュースで実質賃金がマイナスかプラスかを報じることは、「国民の暮らしの体温計」を示すことと同じなのです。
まとめ
2025年5月、実質賃金は5か月連続でマイナスとなり、その幅は2.9%と大きくなりました。名目賃金が上がっていても、物価の上昇には追いつけていない。中小企業や非正規雇用者にとって、その影響は特に深刻です。
しかし一方で、春闘を中心とした賃上げの動きや、政府の支援策も少しずつ成果を見せ始めています。今後は、「物価が落ち着くか」「基本給の上昇が広がるか」「中小企業が賃上げできる体力を持てるか」といった点に注目が集まります。
次に実質賃金がプラスに転じるのはいつなのか。数字の裏にある「暮らしの実感」を大切にしながら、私たち一人ひとりが社会の動きを見守っていくことが必要です。